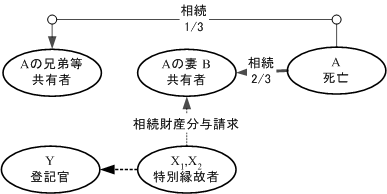
本件土地は,Aの妻B(持分3分の2)とAの兄弟姉妹(代襲相続人を含む)28名,合計29名の共有となる。
2004年6月22日
名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂
相続は,人(被相続人)の死亡によって開始する。そして,相続が開始すると,被相続人の財産に帰属した一切の権利義務が相続人に承継されるとされている。しかし,被相続人が死亡した場合に,すべての権利義務について相続が開始するわけではない。
それでは,相続はどのような考え方に基づいて財産の承継を認めたり,認めなかったりしているのであろうか。「相続が開始して初めて問い直される,家族の構成員と財産の帰属」という切り口から,相続法の基本的な考え方を理解しようというのが,今回の講義の目的である。
遺言の制度を認めることによって,人は遺言により,生前だけでなく,その死後にも自己の財産を自由に処分できることになる(遺言自由の原則)。ただし,近代的なスローガンとしての「遺言自由の原則」には,使い方次第で,「家」制度を復活させることもできるという,以下のような弊害も存在する。
「家」制度の下では,家の財産を戸主がほぼ独占し,家督相続制度(家督相続人は男性の長子が優先する)の下で,戸主のみに家の財産を承継させた民法旧規定(明治31年民法)。現行民法は,「家」制度の中核をなしていた家督相続を廃止して,共同相続人の均等相続(平等相続の原則)を実現したはずであった。
しかし,現実には,遺言自由主義の隆盛によって,相続人間の平等は,瀕死の状態にあるというのが現実である。「家」制度の復活を思わせる,すべての財産を長男に相続させるという試みは,これまでにも,相続放棄の利用,遺産分割協議の利用などによってなされてきた。しかし,最近では,公証人よって考案され,法務省の登記実務に支えられ,最終的には,最高裁判決(最二判平3・4・19民集45巻4号477頁)によって追認された「相続させる」遺言という方法によって,相続放棄も遺産分割協議も必要とすることなく,即座に,被相続人の財産を長男だけに相続させるという方法が実務で定着しつつあるからである。
契約自由の下で,情報力,交渉力に劣る消費者に多くの被害が生じたため,契約自由の原則も万能ではなく,一定の制限の下で,契約の自由が認めれれている現代において,「遺言自由」の名の下に,死者の判断によって,遺産分割協議という手続保障がなされないまま,生きている共同相続人が,相続廃除の要件がないにもかかわらず,「相続させる遺言」により,長男以外の共同相続人が,相続権を否定されるというのは,奇異というほかはない。
相続は,人(被相続人)の死亡によって開始する(民法822条)。そして,相続が開始すると,被相続人の財産に帰属した一切の権利義務が相続人に承継されるとされている(民法896条本文)。しかし,被相続人が死亡した場合に,すべての権利義務について相続が開始するわけではない。
| 被相続人の権利義務の分類 | 被相続人の財産の具体例 | 承継関係 | ||
|---|---|---|---|---|
| 「相続人の財産に属した一切の権利義務」 (896条) |
相続開始時に被相続人に属していた財産 (996条,997条の「相続財産」) |
共同相続の対象外 | 一身専属の権利義務(896条但書) | 相続人に承継されない |
| 祭祀財産(897条) | 祭祀承継者が承継 | |||
| 死亡退職金債権 (最一判昭55・11・27民集34巻6号815頁) |
受給権者が承継 (特別受益とみる説がある) |
|||
| 共同相続の対象となる権利義務 (898条の「相続財産」) |
(−)非相続人への遺贈 | 受遺者が承継 | ||
| (−)相続人への遺贈 | 受遺者が承継 | |||
| 土地建物,現金,預金等 | 相続人が相続によって承継 | |||
| 相続債権 | ||||
| (−)相続債務 | ||||
| 相続開始後に被相続人に帰属する財産 | 生命侵害による損害賠償債権 | |||
| (−)死亡時に発生する損害賠償債務 | ||||
たとえば,被相続人の一身に専属するしたものは,相続人には承継されない(民法896条但書)。たとえば,以下のような法律上の地位や権利義務は相続されない。
また,祖先祭祀のための財産,例えば,系譜,祭具,墳墓については,相続とは別の規範によって承継が行われる。すなわち,以下の基準に従って決定される祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する(民法897条)。
被相続人の遺体・遺骨について,最高裁(最三判平元・7・18家月41巻10号128頁)は,民法897条を準用することによって,「遺骨の所有者は,慣習に従つて祭祀を主宰すべき者に帰属した」として,祭祀を主宰すべき者への遺骨の引渡しを命じた原審の結論を維持する判決を下している。
これに関連して,臓器の移植に関する法律6条(臓器の摘出)は,本人の書面による意思表示のほか,脳死判定を行うことにつき「家族」の承諾を,また,臓器摘出につき「遺族」の承諾をそれぞれ要求している。遺体等の帰属に関する重要な問題であるので,臓器の提出の承諾に関する「遺族」,「家族」の範囲について,「『臓器の移植に関する法律』の適用に関する指針(ガイドライン)」(1997年10月8日)を見ておこう。
相続人には,以下のタイプのものがある。
ただし,被相続人の財産を承継するはずの相続人でも,相続秩序を侵害する重大な非行をした相続人は,相続欠格により,法律上当然に相続権が剥奪されるし(民法891条),重大な非行ではなくても,被相続人に対する虐待・侮辱がある場合には,相続人の廃除といって,被相続人の意思に基づいて相続人の資格を剥奪する制度が認められている(民法892条以下)。
反対に,共同相続人の一人が死亡したときに,その共同相続人には相続人がなく,その共同相続人に特別縁故者がいる場合には,その特別縁故者は,他の共同相続人に優先して,共有持分について財産分与をうけることができるとされている(家族法判例百選〔第6版〕第53事件(最二判平元・11・24民集43巻10号1220頁))。
相続人の不存在の場合には,最終的には遺産は国家に帰属する(959条)。しかし,それに至るまでに,以下の手続が踏まれる。
| 相続欠格(民法891条) | 廃除(民法892〜895条) | |
|---|---|---|
| 事由 | (1)殺害 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知つて,これを告発せず,又は告訴しなかつた者。但し,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは,この限りでない。 (2)遺言に関する不正(二重の故意) 三 詐欺又は強迫によつて,被相続人が相続に関する遺言をし,これを取り消し,又はこれを変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によつて,被相続人に相続に関する遺言をさせ,これを取り消させ,又はこれを変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者 |
(1)虐待又は重大な侮辱 遺留分を有する推定相続人が,被相続人に対して虐待をし,若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき,又は (2)著しい非行 推定相続人にその他の著しい非行があつたとき
|
| 手続 | 手続は不要。 欠格事由があるときは,自動的に相続人でなくなる。 |
被相続人は,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 審判(家審9条1項乙9号);調停(家審17条) |
| 効果 | 相続人資格を失う。遺留分権者でもなくなる。 受遺能力(遺贈を受ける能力)も失う(965条)。 |
相続人資格を失う。遺留分権者でもなくなる。 ただし,受遺能力は残る。 |
| 宥恕 | 規定なし。贈与によって事実上宥恕の目的を達することができる。 | 被相続人は,何時でも,推定相続人の廃除の取消を家庭裁判所に請求することができる。 |
なお,推定相続人の廃除の問題点については,補遺で詳しく論じる。
以下は,新約聖書の中の一節であり,賃金の平等に関する問題を扱っているが,相続分の平等を考察する上でも,示唆に富んでいると思われる。以下の文章を読んで,次の問に答えなさい。
| 「ぶどう園の労働者のたとえ」
MAT20:01 「天の国は次のようにたとえられる。ある家の主人が,ぶどう園で働く労働者を雇うために,夜明けに出かけていった。 MAT20:02 主人は,一日につき1デナリオンの約束で,労働者をぶどう園に送った。 MAT20:03 また,9時ごろ行ってみると,何もしないで広場に立っている人々がいたので,MAT20:04 『あなたたちもぶどう園に行きなさい。ふさわしい賃金を払ってやろう』と言った。 MAT20:05 それで,その人たちは出かけて行った。主人は,12時ごろと3時ごろにまた出て行き,同じようにした。MAT20:06 5時ごろにも行ってみると,他の人々が立っていたので,『なぜ,何もしないで一日中ここに立っているのか』と尋ねると, MAT20:07 彼らは,『だれも雇ってくれないのです』と言った。MAT20:08 夕方になってぶどう園の主人は監督に,『労働者たちを呼んで,最後に来た者から始めて,最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさい』と言った。 MAT20:09 そこで,5時ごろ雇われた人たちが来て,1デナリオンずつ受け取った。 MAT20:10 最初に雇われた人たちが来て,もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし,彼らも1デナリオンずつであった。MAT20:11 それで,受け取ると,主人に不平を言った。 MAT20:12 『最後に来たこの連中は,1時間しか働きませんでした。まる一日,暑い中を辛抱して働いた私たちと,この連中とを同じ扱いにするとは』 MAT20:13 主人はその人に答えた。『友よ,あなたに不当なことはしていない。あなたとわたしと1デナリオンの約束をしたではないか。MAT20:14 自分の分を受け取って帰りなさい。わたくしはこの最後の者にも,あなたと同じように支払ってやりたいのだ。 MAT20:15 自分のものを自分のしたいようにしては,いけないのか。それとも,わたくしの気前のよさをねたむのか。』 MAT20:16 このように,後にいる者が先になり,先にいる者が後になる。」 |
問1 このたとえの労働者を被相続の子と考えてみよう。そして,最初の来た労働者を第1子,次に来た人を第2子,その次に来た人を第3子というように考えてみよう。第1子の方が,第2子よりも被相続人に貢献できる可能性が高いのに,相続分が均等なのは,なぜなのであろうか。
問2 このたとえの労働者を一日の過程で捉えるのではなく,ぶどうの栽培,収穫,ぶどう酒の醸造,ぶどう酒の保存という長いスパンで考え,以下のような物語の中で考えてみると,貢献の度合いは,どのように変化するか。
被相続人甲は,ぶどう農園を経営する父母αβの第1子として生まれた。その後に生まれた兄弟姉妹a,bとともに,ぶどうの栽培,ぶどう酒の醸造の仕事を手伝ってきたが,甲が18歳のときに,父αの土地の一部をローンで購入して独立し,乙と結婚し,子A,Bをもうけた。ぶどう酒の醸造の際には,甲の兄弟a,bも時々手伝いに来てくれたが,主として,乙と子A,Bが作業を行って財産を形成してきた。その後,子A,Bは甲乙のもとを離れ,独立したため,ぶどう園の経営は,すべて,甲乙二人で行い,土地のローンも両親に完済したた。甲が死亡した場合に,甲の相続財産は,誰に,かつ,どのように分配されるか。
問3 以上の物語において,被相続人の生前の意思が,相続分の割合を決定すると考えた場合,この被相続人の意思を推測してみなさい。
問4 家族法判例百選〔第6版〕第50事件(最三判平9・1・28民集51巻1号184頁)を読んで,以下の点を検討しなさい。
問5 家族法判例百選〔第6版〕第51事件(東京高判平4・12・11判時1448号130頁)を読んで,以下の点を検討しなさい。
問6 相続人の欠格と廃除に関する解釈について,共通点または特色を挙げ,その理由を考えなさい。
問7 家族法判例百選〔第6版〕第52事件(東京高判昭62・10・8家月40巻3号45頁)を読んで,以下の点を検討しなさい。
問8 家族法判例百選〔第6版〕第53事件(最二判平元・11・24民集43巻10号1220頁)を読んで,以下の点を検討しなさい。
| 人物関係図 | 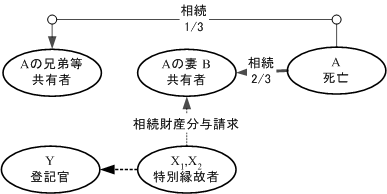 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | 事実 | 争点 | |||
| 原告 | 被告 | 裁判所 | |||||
| 本件土地は,A所有の土地であった。 | |||||||
| 1980 | 昭和55 | 12 | 19 | A死亡。 本件土地は,Aの妻B(持分3分の2)とAの兄弟姉妹(代襲相続人を含む)28名,合計29名の共有となる。 |
|||
| 1981 | 昭和57 | 07 | 28 | Aの妻B死亡。 | Bに相続人がいない場合に,Bの持分権は他の共有者に帰属するのか。 | ||
| X1,X2夫婦が,民法958条の3に基づき,Bの特別縁故者として大阪家庭裁判所岸和田支部へ相続財産分与の申立て。 | Bに相続人がいない場合に,Bの持分権は特別受益者に分与されるのか。 | ||||||
| 1986 | 昭和61 | 04 | 28 | 大阪家庭裁判所岸和田支部は,本件土地のBの持分の各2分の1をX1,X2に分与する旨の審判を行う。 | |||
| 07 | 22 | X1,X2は,大阪法務局佐野出張所登記官Yに対して,審判を原因とする本件土地のBの持分の全部移転登記手続を申請した。 | |||||
| 08 | 05 | Yは,不動産登記法49条2号に基づき,事件が登記すべきものでないとの理由でこれを却下する旨の決定をした。 | 民法255条優先説に基づく決定だが適切か。 | ||||
| X1,X2は,YがなしたBの持分全部移転登記申請を却下する旨の決定につき,この取消をもとめて訴えを提起した。 | |||||||
| 1987 | 昭和62 | 07 | 28 | 第1審(大阪地裁)判決:X1,X2の請求を認容(控訴) | 民法958条の3優先説 | ||
| 12 | 22 | 第2審(大阪高裁)判決:第1審判決を取り消し,X1,X2の請求を棄却。 | 民法255条優先説 | ||||
| 1989 | 平成01 | 11 | 24 | 最高裁判決(破棄自判):X1,X2の請求を認容。 | 民法958条の3優先説 | ||
問9 家族法判例百選〔第6版〕第54事件(最一判平11・1・21民集53巻1号128頁)を読んで,以下の点を検討しなさい。
問10 相続財産の種類について,以下の観点から分類し,その理由を検討しなさい。
廃除の制度(民法892条以下)は,推定相続人のいわゆる親不孝(虐待,重大な侮辱,その他の著しい非行)を理由に,被相続人が,自分の意思で,推定相続人の相続人資格を,遺留分減殺請求権を含めて剥奪するという過酷な制度である。この制度の問題点は,規定上は,被相続人の側にもあるかもしれない非難すべき事情を考慮することなく,推定相続人の親不孝のみを理由に,推定相続人の相続資格を剥奪できる点にある。
確かに,廃除の最終的な判断は,家庭裁判所に委ねられており,かつ,以下のように,被相続人にも非があり,そのことが推定相続人の非行を誘発するようになった場合には,廃除権は,常に生じるものではないとの判例法理が形成されている(大判大15・6・2評論16巻民44頁)。
父ニシテ其ノ子ヲ待ツニ 其ノ道ヲ以テセス 因テ以テ 子ノ非行ヲ誘発スルニ至リタル場合ニ於テハ 廃除権ハ常ニ必スシモ之ヲ生スルコトナシ 蓋若爾ラサレハ 己ノ失ヲ省ス専ラ他ノ非ヲ責ムルニ急ナルノ嫌アリ 事ノ当ニ許ス可カラサルモノニ属スルハ云フヲ俟タサレハナリ
原判決ノ確定スルトコロニ依レハ 上告人カ被上告人ニ対シ尠カラサル失態ヲ演シタルコトハ甚タ明白ナルト共ニ 被控訴人(被上告人)ハ控訴人(上告人)ノ弟英三及長輝ヲ愛シ 前ニ控訴人ニ子無カリシ際 長輝ヲ以テ控訴人ノ継嗣タラシメンコトヲ欲シタルモ 同人之ニ従ハサリシコトアリ 遂ニ其ノ間不和ト為リ 控訴人ハ自暴自棄酒ニ沈溺スルニ至リタル事実アルコトモ亦甚明白ナリ
然ラハ則 上告人ノ失行ハ 被上告人ニ於テ其諸子ノ内少弟ヲ偏愛シテ長兄ヲ疎却シタルコトニ生スルモノ尠カラサルノ消息ハ之ヲ窺フニ難カラス 事情ノ如何ニ因リテハ 本件廃除権ハ或ハ存セサルヤモ亦知ル可ラス 夫人事上ノ事件ニ在リテハ斯ル機微ノ関係ハ特ニ意ヲ加ヘテ之ヲ審査考覈スルコトヲ要ス 人事訴訟ニ於テ裁判所ヲシテ当事者ノ提出セサル事実ヲ斟酌シ申立テサル証拠調ヲ為スヲ得セシムル所以蓋之カ為ニ外ナラス 原裁判所カ「斯ノ如キ事情ハ叙上相続人廃除ノ原因ヲ阻却スルニ足ラサルカ故ニ」云々ト称シテ輙ク被上告人ノ本訴ヲ是認シタルハ 廃除権ノ発生ニ関スル法律ノ解釈ヲ誤リタルカ 爾ラサレハ事実ノ審理ヲ尽ササルカ 孰ニセヨ原判決ハ違法ニシテ 本件上告ハ其ノ理由アリ
しかし,最近においても,以下に示すように,被相続人側の問題点を無視して,推定相続人の廃除を認める決定(東京高決平4・12・11判時1448号130頁)が下されているのを見ると,一部の裁判官の頭の中には,理由のいかんを問わず,親不孝は制裁を伴ってもやむをえないという,儒教思想の影響が残っているのではないかとの危惧の念を消し去ることができない。
しかしながら,この決定によって取り消された第1審(審判)においては,以下のような,被相続人の側の非が認定されている。それにもかかわらず,第2審決定では,そのような被相続人側の問題点が完全に無視されている。また,第1審では,被相続人は,推定相続人の「著しい非行」のみを問題にしていたのであるが,第1審で,それが認められず,被相続人にも非がある場合には「著しい非行」では廃除ができないと知ると,第2審になって,はじめて,もう一つの廃除事由である「虐待や重大な侮辱」に当たる事実を持ち出して,廃除を正当化しようとした。そして,第2審の裁判官は,被相続人側の非が問題となりにくい「虐待や重大な侮辱」を認定することによって,非のある非相続人側の主張を認めて,推定相続人の廃除を認めている。
これまでの判決を検討してみても,推定相続人の廃除の制度は,家督相続の時代にあっては,被相続人の意にそぐわない,いわゆる親不孝な推定家督相続人の相続権を排除するために利用されてきた。たとえば,家業である農業を嫌う家督相続人(長女)について,婿養子が決まったために,廃除を狙った事例(大判大11・7・25民集1巻478頁),推定家督相続人よりも,偏愛する末子を家督相続人としようとしたがうまくいかなかったために,推定家督相続人を廃除しようとした事例(大判大15・6・2評論16巻民44頁)などがある。
大審院は,以上の例のように,被相続人にも非があり,そのことが推定相続人の非行を誘発するようになった場合には,廃除権は,常に生じるものではないとの判例法理を形成したきた。しかし,家督相続を廃止し,遺産相続のみになった現行法においても,廃除の制度は,被相続人の主観で,親孝行な子と親不孝な子とを区別し,親不孝な子に対して制裁を与える手段として利用されている。
いまだに,親孝行を美徳と信じ,以下の記述(ルース・ベネディクト,長谷川松治訳『菊と刀−日本文化の型』社会思想社(1972)117頁以下)に見られるように,理由もなく,その徳目を子に押し付けようとする親が多いわが国においては,被相続人の意思だけで,本来均等であるべき相続人の地位を不平等にするばかりでなく,遺言によっても奪えないとされている子の遺留分権をも剥奪する廃除の制度の運用は,慎重であるべきであると思われる。
何世紀もの久しい間にわたって「恩を忘れない」ということが日本人の習性の中で最高の地位を占めてきた…恩が,親たちを子供に対してあのように権力のある枢要な地位に置いているあの有名な,東洋の孝行の基礎である。それは子供が親に対して負っており,返済に努力する負債として言い表されている(117頁)。
日本では,孝行は,たとえそれが親の不徳や不正を見て見ぬふりをすることを意味する場合においても,履行せねばらならない義務となった。それは天皇に対する義務と衝突する場合にだけ廃棄することができるのであって,親が尊敬に値しない人間であるとか,自分の幸福をそこなうとかいう理由で棄て去ることは絶対にできなかった(140頁)。