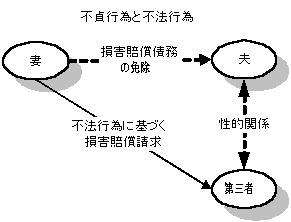 |
法学教室2001.1-No.244 特集・新世紀の法とコンピュータ
-連帯債務に関する相互保証理論モデルを例として-
2000年12月2日
名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂
コンピュータ科学の進展を考慮して,21世紀の民法学を展望するというのが筆者に課せられたテーマである。また,このテーマを論じるに当たっては,できるだけ最近の具体的な事例・判例を取り上げてわかりやすく論じるというのが編集者からの要請である。
そこで,本稿では,民法の中で最も判例の多い不法行為の分野から1つの最高裁判決(最一判平6・11・24判時1514号82頁)を選択して,その判決で扱われた問題を,コンピュータを活用して検討し直してみることにする。ここで選択する判決は,「とりたてて根拠があるとは限らない」いわゆる不真正連帯債務のドグマをほとんど唯一の理由として下された最悪の判決の一つであり,21世紀には,このような判決を書く法曹は育ってほしくないというのが筆者の率直な感想である。
本稿では,なぜ,このような判決(具体的な解決としても妥当性を欠き,ほとんど根拠のないドグマを振りかざすだけで論理的にも破綻した判決)が民法学者から総攻撃を受けずに済まされているのか,コンピュータを利用することで,どこまで,この判決を批判し,このような問題に対して新たな展望を切り開くことができるのかを検討してみることにしよう。
このような実例を通じて,厳密な検証を経ていない「ドグマの体系」から,社会科学の一つとして民法学を再生させるという試みに次の世代を担う学生諸君を誘おうというのが本稿の目的である。
妻Xと夫Aとの婚姻関係を継続中,第三者であるY女が夫Aと不貞行為に及び,そのため右婚姻関係が破綻するに至ったとして,妻Xは,Y女に対し,不法行為に基づく慰謝料300万円とこれに対する遅延損害金の支払を請求して訴えを提起した。
第一審は,Xの請求を全部認容した。これに対して,控訴審は,本件不法行為に基づく慰謝料は300万円が相当であると判断したものの,Yが原審において主張した債務免除の抗弁を一部認め,YがXに支払うべき慰謝料は150万円が相当であるとし,一審判決を変更して,Yに対し,150万円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた。
控訴審の判決理由は以下の通りである。
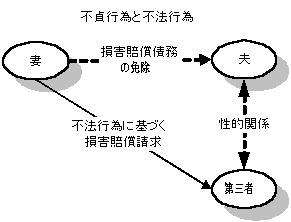 |
これに対して最高裁は,以下のように判断して,原審の判決を破棄した。
「しかしながら,原審の(1)の判断は是認することができるが,(2)のうち,本件調停による債務の免除が被上告人の利益のためにもその効力を生ずるとした判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。
民法719条所定の共同不法行為(者)が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないものと解するのが相当である(最高裁昭和43年(オ)第431号同48年2月16日第二小法廷判決・民集27巻1号99頁参照)。
原審の確定した事実関係によれば,XとAとの間においては,平成元年6月27日本件調停が成立し,その条項において,両名間の子の親権者をXとし,AのXに対する養育費の支払,財産の分与などが約されたほか,本件条項が定められたものであるところ,右各条項からは,XがYに対しても前記免除の効力を及ぼす意思であったことは何らうかがわれないのみならず,記録によれば,Xは本件調停成立後4箇月を経過しない間の平成元年10月24日にYに対して本件訴訟を提起したことが明らかである。右事実関係の下では,Xは,本件調停において,本件不法行為に基づく損害賠償債務のうちAの債務のみを免除したにすぎず,Yに対する関係では,後日その全額の賠償を請求する意思であったものというべきであり,本件調停による債務の免除は,Yに対してその債務を免除する意思を含むものではないから,Yに対する関係では何らの効力を有しないものというべきである。
そうすると,右と異なる見解に立ってXの請求を一部棄却した原判決は,共同不法行為者に対する債務の免除の効力に関する法理の解釈適用を誤ったものであり,この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。この趣旨をいう論旨は理由があり,原判決中X敗訴部分は破棄を免れない。そして,以上に判示したところによれば,Xの本件損害賠償請求はすべて理由があることになり,これと結論を同じくする第一審判決は正当であるから,右部分に対する控訴は理由がなくこれを棄却すべきものである。」
本稿のメインテーマである「浮気をした配偶者の債務を免除しておきながら,その浮気相手には,全額の損害賠償債務を負担させることが許されるかどうか」という問題を論じる前に,そもそも,「浮気をした配偶者の相手方に対して,他方の配偶者が不法行為に基づいて損害賠償を請求できるかどうか」を検討することにする。配偶者の一方が浮気(不貞行為)をした場合に,他方の配偶者または子は,不貞行為の相手方に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できるかどうかについて,裁判所の見解は,変化してきている。裁判所の見解がどのように変化してきているかを,判例データベース(例えば,新日本法規出版の「判例MASTER」など)を利用して検索してみることにしよう。
最高裁は,当初は,夫婦の一方の配偶者と性的関係を持った第三者は,故意または過失がある限り,配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,また,それが男の場合であれ([1]最二判昭41・4・1裁集民83号17頁),女の場合であれ([2]最二判昭54・3・30民集33巻2号303頁),それぞれ,他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し,その精神上の苦痛を慰謝すべき義務を負うとしていた。
しかし,昭和54年の[2]最高裁判決は,妻及び未成年の子のある夫が第三者(女)と性的関係を持ち,妻子のもとを去って第三者(女)と同棲するに至った結果,未成年の子が日常生活において父親から愛情を注がれ,その監護,教育を受けることができなくなったとしても,第三者(女)の行為は,特段の事情のない限り,未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと判示している。反対意見はあるものの,最高裁は,親の浮気について,子はとやかくいう立場にないことを明言したことになる。
同日の最高裁の別の判決([3] 最二判昭54・3・30家月31巻8号35頁)も,先の判決の場合と夫と妻の立場が逆転した事例について,夫及び未成年の子のある妻と性的関係を持った第三者(男)が夫や子のもとを去った妻と同棲するに至った結果,その子が日常生活において母親から愛情を注がれ,その監護,教育を受けることができなくなったとしても,その第三者(男)が害意をもって母親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り,第三者(男)の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと判断しており,ここでも,親の浮気について,子はとやかくいう立場にないという立場が保持されている。
その後,平成8年には,最高裁は,すでに婚姻関係が破綻している場合([4] 最三判平8・3・26民集50巻4号993頁),および,妻が第三者に「夫と離婚するつもりである」と話していた場合([5] 最三判平8・6・18家月48巻12号39頁)においてではあるが,配偶者の一方と第三者が性的関係を持った場合において,第三者は,他方の配偶者に対して不法行為責任を負わないと判示するに至っている。
コンピュータを利用して収集した最高裁の判決を原告・被告の組み合わせに着目して分類し,表にまとめると以下のようになる。
| 損害賠償請求の当事者 | 不法行為 の成立 |
判決 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原告 | 被告 | ||||
| 夫の家族 | 夫 | 第三者(男) | 肯定 | [1] 最二判昭41・4・1裁集民83号17頁 | 妻と第三者との不貞行為によって婚姻関係が破綻 |
| 妻 | 第三者(女) | 肯定 | [2] 最二判昭54・3・30民集33巻2号303頁 | 夫と第三者との不貞行為によって婚姻関係が破綻 | |
| 夫の子 | 否定 | ||||
| 妻の子 | 第三者(男) | 否定 | [3] 最二判昭54・3・30家月31巻8号35 | 妻と第三者との不貞行為によって婚姻関係が破綻 | |
| 妻 | 第三者(女) | 否定 | [4] 最三判平8・3・26民集50巻4号993頁 | 不貞行為の当時,夫婦関係がすでに破綻していた | |
| 妻 | 第三者(女) | 否定 | [5] 最三判平8・6・18家月48巻12号39頁 | 妻が第三者に「夫と離婚するつもりである」と話していた | |
上記の最高裁の判例の動きにさらに一歩を進めて,婚姻関係が破壊されているかどうかにかかわらず,配偶者の一方が浮気をしたとしても,他方の配偶者は,浮気の相手方に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することはできないのではないのか,すなわち,浮気は夫婦間の債務不履行にはなっても,不法行為にはならないのではないかというのが筆者の仮説である。
確かに,夫婦の一方が第三者と性的関係を結んだ場合,それが,夫婦の約束に違反するという意味で債務不履行を構成し,それが,不貞行為として離婚原因となることはいうまでもない。しかし,夫婦の一方が,第三者と関係を持ったとしても,第三者が害意をもって婚姻関係を破壊しようとしていた等の特段の事情のない限り,不法行為とはならないように思われる。
夫婦は,お互いに独立の対等な人格であり,物権のように一方が他方を支配するという関係にはない。したがって,配偶者の一方は,相手方に対して,第三者と性的関係を結んでほしくないと要求することはできるが,配偶者以外の者を好きになるなとか,配偶者以外の者と性的関係を結んではいけないと命令できる関係にはない。すなわち,配偶者が約束を破ったとしても,それは,夫婦間の問題であって,一種の債務不履行として,損害賠償や離婚原因となるに過ぎないと考えるからである。
夫婦の一方が第三者と性的関係を持つことが直ちに不法行為に該当すると考えるのは,性的関係を持つことができるのは夫婦間だけであり,夫婦以外の者が性的関係を持つことは好ましいことではないという考え方の名残に過ぎないのではないだろうか。夫婦間以外の性的関係を不法行為だと考えることは,一見道徳的のように見えるが,それは,美人局を正当化し,婚外子差別を生み出す温床ともなっており,道徳的にも決して誉められた考え方ではない。
夫婦以外の者が性的関係を持つべきでないという考え方は,個人の道徳のレベルの問題として議論する価値はあるが,他人を拘束するものとして一般化することはできないと思われる。例えば,配偶者以外の第三者と性的関係を持つ人々,すなわち,浮気をする人々が全体の半数を超えるというデータがあれば,それを不法行為と考えること自体に疑問をもつべきであろう。
そこで,インターネットを利用して,夫婦,または,ステディな関係となったパートナーがどのくらいの割合で浮気をしているのかを調査した資料を検索してみよう。検索エンジン(例えば,インフォシーク(http://www.infoseek.co.jp)など)を駆使すると,2000年4月に『月刊現代』が行なった調査(年齢的に結婚・出産が可能な全世代の男女とし,有効回答総数は,男性が1,291人(平均年齢37.3歳),女性が1,977人(同29.3歳)で,合計3268人(4月10日現在の集計)という大規模な調査)を検索することができる(http://kodansha.cplaza.ne.jp/mgendai/)。
パートナーのいる男性回答者のうち,有効回答のあった人数は669人で,その61.7パーセントに相当する413人が浮気の経験が「ある」と回答している。そして,経験した相手の平均人数は,4.6人であるという。一方,パートナーのいる女性で,パートナー以外の男性と浮気をした経験のある女性は,有効回答総数1574人中428人で27.2パーセント,経験した相手の人数は平均2.2人である。
| 浮気(カジュアルセックス)経験 |
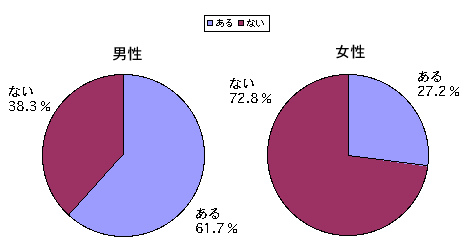 |
| Web版月刊現代2000年7月号より http://kodansha.cplaza.ne.jp/mgendai/2007/2007_6.html |
男性の61.7パーセント,女性の27.2パーセントが浮気の経験を持つというデータを前にした場合,現在においては,浮気は犯罪とか不法行為ではなく,あまり誉められない行為(契約違反)ではあるが,普通に行なわれており,以下のような効用もある事象であると考えざるをえないであろう。
| 浮気で得られたものは何か(複数回答・回答の多かった上位5項目) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Web版月刊現代2000年7月号より | |||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットでの検索結果によると,このほかにも,日本人の性行動・性意識に関する調査としては,1984年に共同通信社が発表した「現代社会と性に関する調査」(サンプル数:男女合わせて2200人),女性誌『モア』が1980年と1987年に行った大規模な読者アンケート「モア・リポート」(サンプル数:5,000人を超える女性),1999年に厚生省が公表した「日本人のHIV/AIDS関連知識、性行動、性意識についての全国調査」(サンプル数:3,562人)等があることがわかる。これらの調査によると,人間は結婚の前後を問わず,複数の人と性的関係を持つことが異常ではなく,むしろ,多数であること,この傾向は,強められることはあっても,弱められそうにはないこともわかる。
このように見てくると,厳格な一夫一婦制は,あくまで建前であって,配偶者の浮気の問題は,配偶者間で処理すべき問題であり,浮気の相手方を不法行為者として非難することは当たっていないように思われる。将来的には,配偶者間でも,相手に配慮しつつも,浮気の権利が認められるようになる可能性すら否定できないであろう。
不貞行為(浮気)は配偶者の間で解決すべき問題であり,配偶者が不貞行為の相手方に対して,不法行為に基づいて損害賠償を請求することは認められるべきではなく,少なくとも,制限されるべきであるということが明らかになったように思われる。そうだとすると,配偶者の責任を免除しながら,不貞行為の相手方から,不法行為に基づいて慰謝料全額を請求するということも制限すべきであるということになる。
最初に紹介した平成6年の最高裁判決(最一判平6・11・24判時1514号82頁)が,事案の解決としても妥当ではないと述べたのは,この判決が,前記のような考え方に逆行しているからである。
平成6年の最高裁判決は,不貞行為をした配偶者とその相手方とは共同不法行為者に該当するとした。この点が問題であるが,その点を無視したとしても,この判決には以下のような問題点がある。すなわち,共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,民法の条文では,連帯債務とされており,連帯債務の場合であれば,民法437条が適用される。したがって,配偶者に対して全額免除を行なえば,負担部分の範囲で,浮気の相手方にもその効力が生じるため,損害賠償請求は半額に減額されるはずである。ところが,本判決では,これを連帯債務ではない不真正連帯債務であると解釈し,不貞行為をした配偶者に対する免除の効力は,不貞行為の相手方には及ばないとして,相手方は全額の損害賠償責任を負うとした。
確かに,わが国の通説・判例は,連帯債務は主観的な共同関係がある場合であって,一人の連帯債務者に生じた弁済以外の事由である更改・相殺・免除・混同・消滅時効という事由は他の連帯債務者に影響を与える。これに反して,主観的な共同関係がない場合には,一人の連帯債務者に生じた弁済以外の事由が他の連帯債務者に影響を与えないようにするのが,債権者の保護の観点からも有益であるとして,そのような場合を不真正連帯債務と呼んでいる。
しかし,不真正連帯債務の考え方は,そもそも,連帯債務者間の求償権を否定するために提唱された見解であったが,現在の通説・判例は,不真正連帯債務においても,連帯債務者間の求償権を認めるとするに至っている(最二判昭63・7・1民集42巻6号451頁)。そうだとすると,連帯債務者間の求償権を認めつつ,不真正連帯債務者の一人に生じた弁済以外の事由が他の債務者に影響を与えないとすることの正当性が問われることになる。例えば,不真正連帯債務の場合には,免除の絶対効は認められないと主張してみたところで,全額支払を余儀なくされた一人の債務者が,免除を受けた債務者への求償が認められるのであれば,免除を受けた債務者は,さらに,不当利得に基づいて,債権者からその求償分の返還を受けることができる(求償の循環)ため,絶対的効力を認めたのと結果は異ならなくなってしまう。
いずれにせよ,本件の場合には,夫AとY女とが連帯債務者であるとすれば,妻XがAに対して債務を全額免除した以上,XがYに対して全額請求しようとしても,Aの負担部分の範囲でYの連帯債務も減額され,全額請求はできないことになる。また,AとYとは,不真正連帯債務者であるとして,絶対的効力を否定し,Yに対して全額請求できることにしたところで,求償の循環によって,結局は,Yから全額の賠償を受けることはできないのであるから,平成6年の最高裁判決は不可解というほかない。この原因は,最高裁の連帯債務の性質に対する無理解に起因すると思われる。
そこで,連帯債務と免除との関係について,さらに詳しく見ていくことにしよう。
通説を代表する我妻栄『新訂債権総論(民法講義Ⅳ)』岩波書店(1954)401頁によれば,連帯債務は,以下のように定義されている。
連帯債務とは,数人の債務者が,同一の給付について,各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し,しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務である。
しかし,この定義は,「各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担する」としているところに「ごまかし」があり,以下のような破綻をきたしている。
このような論理的な破綻が明らかな定義が,何の反論も受けずに,通説として幾世代にもわたって保持されてきたこと自体が,法律学の悲劇である。つまり,他の社会科学者から,法律学とは,権威主義的カルト集団の学問と揶揄されていても,当人たちは,全くそれに気づかないのである。
この点に関しては,最近出版された太田勝造『法律(社会科学の理論とモデル)』東大出版会(2000)Ⅴ-Ⅵ頁)が,以下のように述べて,社会科学としての法律学の無価値性に言及している。
そこで,ここでは,社会科学の方法論に従い,連帯債務を科学的に分析し,通説の地位を占めつづけているが論理的に破綻している従来の考え方に代わる理論(相互保証理論)の正しさを検証することにしよう。
連帯債務の性質として一般に認識されている点を以下に列挙する。連帯債務の理論モデルは,これらの性質をすべて矛盾なく説明できるものであることが必要であり,かつ,そのモデルにしたがって推論を行なうと,条文に従って解決したのと同様の結果が生じるものでなければならない。
連帯債務に関する通説の定義や解説では,連帯債務の多数性・独立性と,一人の債務者が負担部分を超えて支払ったときに,他の債務者がそれに影響されること,すなわち,連帯債務の従属性とを矛盾なく説明することができないことは,すでに述べた通りである。
以下では,連帯債務における多数性・独立性と,一人の債務者の一定の行為によって他の債務者が影響を受けるという連帯債務の従属性とを矛盾なく説明できるモデルを提示することにする。そして,そのモデルに従ってシミュレーションを行なうと,連帯債務の規定にしたがった解釈と同じ結論を導くことができる上に,通説よりも,より分かりやすく説明することができることを示そうと思う。
連帯債務における債務の複数性と目的の単一性とを同時に説明し得るモデルとして,固有の債務と連帯保証との組み合わせという相互保証理論モデルを提示する。
この相互保証理論というのは,以下の図のように,連帯債務のモデルを,各債務者が負担する債務(負担部分)の上に,他の債務者の負担部分を連帯して保証する連帯保証(連帯部分)が乗っているものとして理解しようとするものである(山中康雄「連帯債務の本質」『私法学の諸問題』有斐閣(1955)所収,浜上則雄「連帯債務の本質と免除」法学セミナー1972年8月号),於保不二雄『債権総論(新版)有斐閣(1972)234頁参照)。
例えば,XからY1,Y2,Y3がそれぞれ,600万円,400万円,200万円を借り受けて,連帯して弁済することを約した場合,Y1,Y2,Y3は,以下のように,各自の負担部分のほか,他の債務者を相互に連帯保証するという負担を負うことになる。
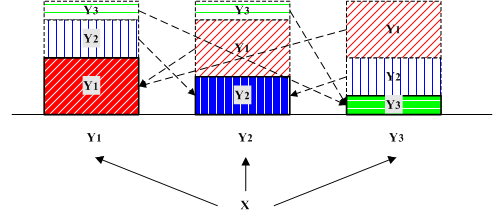 |
| 図1 相互保証理論モデルによる連帯債務の構造 |
相互保証理論モデルは,連帯債務を通常の債務(負担部分)と連帯保証(連帯部分)との結合と考える理論(相互保証理論)に基づいたモデルであり,連帯債務に関する規定は,すべて,弁済の規定と保証の規定から導くことができるという野心的な試みを実現するために,そのモデルでシミュレーションを行なう場合の適用法理は,債務の消滅に関する理論及び保証の理論に限定する。
相互保証理論モデルに基づくシミュレーションに用いられる法理のうち,当面利用されるのは,具体的には以下の4つの法理のみである。
ここで,連帯債務者の一人であるY1が,連帯債務の全額である1,200万円をXに弁済した場合に,相互保証理論モデルでは,他の債務者の債務がどのように変化するのかを見てみることにしよう。
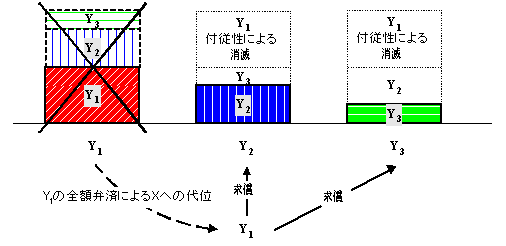 |
| 図2 連帯債務者の一人による弁済が連帯債務に及ぼす影響 |
従来の学説では,一人の債務者が連帯債務の全額を弁済すると,なぜ,独立の債務であるはずの他の債務も消滅するのか,また,なぜ,他の債務者に対して求償権を取得できるのかが十分に説明できなかった。
しかし,相互保証理論モデルによれば,一人の債務者が連帯債務の全額を支払うことには,第1に,自らの固有の債務(負担部分)を支払うこと,第2に,他の債務者の債務を連帯保証人として弁済すること,という性質の異なる2つの行為が含まれていることが明らかとなる。
そして,第1の行為によって,他の債務者が負担していた連帯部分が付従性によって消滅すること,第2の行為によって,他の債務者の負担部分も付従性によって消滅し,それと同時に,他の債務者に対する求償権とそれを担保するための債権者への代位が発生するメカニズムを説明することができることが明らかになったと思われる。
相互保証理論モデルの特色は,連帯債務を固有の債務としての負担部分と連帯保証としての連帯部分とに分解して再構成した点にある。従来の通説が説明できなかった連帯債務の独立性と従属性という矛盾する性質を,このモデルは,負担部分が債務の独立性を,連帯部分が付従性によって従属性をそれぞれ説明することによって,矛盾なく整合的に説明することが可能となったのである。
次のような単純な例について,通説と相互保証理論に基づく説明を対比してみよう。
Xに対してY1,Y2,Y3がそれぞれ,600万円,400万円,200万円を借り受け,各自がXに対して1,200万円の連帯債務を負担する場合に,XがY1の債務を全額免除したとしよう。その場合,Xは,Y2,Y3に対して,いくらの請求ができるか。
我妻栄『新訂債権総論(民法講義Ⅳ)』岩波書店(1954)416頁の記述を,上記の例にアレンジして提示すると,以下のようになる。
債権者が連帯債務者の一人に対してその債務を免除したときは,民法437条により,その債務者の負担部分について,他の債務者も債務を免れる。Xに対してY1,Y2,Y3がそれぞれ,600万円,400万円,200万円を借り受け,各自がXに対して1,200万円の連帯債務を負担する場合に,XがY1の債務を免除するときは,Y2もY3もY1の負担部分600万円について債務を免れる。その結果,Y2,Y3が600万円の連帯債務を負担することになる。
この規定(民法437条)は,当事者間の法律関係を簡易に決済しようとする-転償(求償の循環)を避ける-と説かれる。このような規定がなければ,XはY2,Y3からなお,1,200万円を請求し,弁済者は,Y1に600万円求償し,Y1はこれをXから不当利得として償還させることになるからである。そして,この規定は,債権の効力を弱めるものとして批判されている。
通説が,連帯債務者の一人が弁済した場合と異なり,連帯債務者の一人が免除された場合に,他の連帯債務者に対して絶対的効力が及ぶことに批判的なのは,以下の理由に基づいている。
弁済の場合は,連帯債務の目的が実現されるため絶対的効力が及んでも,連帯債務の独立性とは矛盾しないが,免除の場合は,連帯債務の目的が実現されているわけではないので,他の債務者に対しても絶対的な効力が及ぶのは,連帯債務の独立性と矛盾するばかりでなく,連帯債務の効力を弱めることになるので,なるべく認めるべきではない。
債権者Xが連帯債務者の一人Y1に対してその債務を全額を免除したときは,Y1の固有の債務(負担部分)である600万円が消滅するので,Y1の債務について連帯保証していたY2,Y3の連帯部分が,それぞれ,600万円の範囲で付従性によって消滅する。したがって,Y1の連帯債務は消滅し,Y2の連帯債務は,600万円(負担部分400万円,連帯部分200万円)となり,Y3の連帯債務も600万円(負担部分200万円,連帯部分400万円)となる。
このように考えると,民法437条は,連帯債務の本質から必然的に導かれる当然の規定であり,転償(求償の循環)を避けるために,やむなく規定された不合理な規定ではないことがわかる。
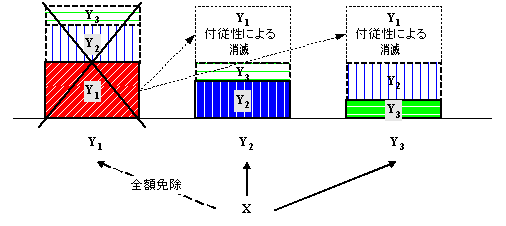 |
| 図3 連帯債務者の一人に対する免除が他の連帯債務者に及ぼす影響 |
連帯債務者の一人によって連帯債務の全額が弁済された場合と連帯債務者の一人が全額を免除された場合の相違は,以下の点にある。
通説による免除の絶対効の説明が煮え切らないものであるのに対して,相互保証理論に基づく説明は簡潔であり,しかも,民法437条の条文の意味が鮮明となることが明らかとなった。
通説が,民法437条の規定があるにもかかわらず,この条文を含めて,弁済以外の事由に絶対的効力を認めることに批判的な理由は,以下の点にあると思われる。
しかし,連帯債務者の一人に生じた事由が弁済以外の場合でも,連帯債務者の一人の負担部分が消滅すれば,その債務について連帯していた他の債務者の債務に影響が生じるのは,当然のことであるといわなければならない。連帯債務における「連帯」とは,先に述べたように,個別に債務を負った債務者が,さらに債務の弁済を確実にするために,債権者との契約により,または,法律の規定(例えば民法719条)によって相互に連帯保証しあう関係に入ることにほかならない。したがって,主たる債務が消滅すれば,連帯保証は付従性によって当然に消滅する。これは,連帯債務者の間に主観的な共同関係があるかないかとは無関係である。
通説の致命的な欠点は,一人の債務者に生じた弁済以外の事由について他の債務者が影響を受けるのは,債務者間に主観的な共同関係がある場合に限り,そのような関係がない場合には,影響が及ばないとしている点にある。しかし,連帯債務における共同関係とは,相互保証の関係であり,主観的な共同関係の有無には関係なく,すべての連帯債務が相互保証関係にあることを認識すべきである。
これまでに述べた相互保証理論に関して,平井宜雄『債権総論』〔第2版〕弘文堂(1994)329-330頁は,以下のような評価をしている。
(相互保証)説は,きわめて明快であり,連帯債務を対人担保の側面において理解しようとする本章の立場の理論的根拠となるものではあるけれども,負担部分を基礎とした効果を生じる場合以外の場合(435条,438条)についての説明に窮する。こう考えると,連帯債務の性質を一義的に定め,そこから連帯債務の要件・効果を導くための前提を論理的・演繹的に導き出すことは困難である。
しかし,平井の批判は以下に述べるように,的を射ていないと思われる。相互保証理論は,立法者の趣旨を十分に発揮できる優れたモデルであって,すべての答えが一義的決定されるという硬直的なモデルではない。更改や混同を弁済と同様に扱うか,弁済以外の免除と同じように扱うべきかは,立法者・解釈者の意思に従うのであって,相互保証理論モデルは,それらの意思に応じて働きを変えることが可能なのである。
債権者と連帯債務者の一人との間に生じた事由については,先に弁済の絶対効の説明の個所で述べたように,それが債権を満足させて消滅させるものか,債権を満足させずに消滅させるものかを判断しなければならない。そして,それが,債権全体を満足させるものである場合には,一人の債務者の負担部分の消滅に留まらず,連帯債務全体の消滅(厳密には,求償権の発生と代位)をもたらす。これに反して,債権を満足させずに終了させる場合には,その債務者の負担部分のみが消滅し,他の債務者は,連帯債務の付従性を通じて影響を享受できるのである。このような結論は,まさに,相互保証理論によってのみ容易に説明することができるといわなければならない。
平井(債権総論330頁)は,「連帯債務の性質を一義的に定め,そこから連帯債務の要件・効果を導くための前提を論理的・演繹的に導き出すことは困難である。」と述べている。しかし,連帯債務の要件と効果を導くための仮説モデルを設計し,モデルにしたがったシミュレーションを行ないながら,そのモデルによってすべての効果が説明できるようにモデルの修正・発展を行なうことは重要な研究課題となりうる。従来の通説が,連帯債務の性質を導く理論を構築できなかったからといって,連帯債務の要件・効果を論理的・演繹的に導き得るモデルの構築を否定することは正当とはいえないであろう。
科学とは,まさに,このような仮説を構築し,それを公表することを通じて,他人による検証・反証に曝すことを可能にする作業に他ならないからである。
われわれは,「法律学とは,とりたてて根拠があるとは限らないようなドグマ(教義)の「体系」に他ならない」との批判(太田・法律(社会科学の理論とモデル)Ⅴ-Ⅵ頁)を率直に受け入れ,民法学においても,様々な分野において,これまでの学問の発展の歴史と社会の現状とを考慮しつつ,困難な問題をよりよく解決するための仮説を構築し,自ら検証してその理論を発展させるばかりでなく,外部からの厳しい反証に曝すために,それらの理論を公表し続けることが必要である。
根拠のないドグマ(教義)を廃し,大陸法の考え方だけでなく,英米法の考え方を思い切って取り入れつつ,それらのルール間の矛盾を最小限に押さえた,緩やかなルールの体系を構築することこそが,21世紀の人々に課せられた民法学の課題であろう。
本稿で取り上げた「不真正連帯債務に関しては,一人の債務者に生じた弁済以外の事由は他の債務者に影響を与えない」というドグマに対する批判とその方法は,民法学を社会科学へと変えていくためのささやかな試みに過ぎない。
インターネットに繋がったパソコンからは,世界中の様々な調査資料,統計資料を利用できる。これらの資料を利用したシミュレーション実験は,法律学における仮説の構築,検証・反証に大きな貢献をすることであろう。さらに,インターネットを通じて公表された新しい仮説については,双方向の批判を通じた反証に耐えぬいた新たな理論の構築が期待できる。インターネットによって提供される情報は,近年,量的のみならず質的にも著しく向上している。今後は,このような良質な環境を法律学の研究・教育にいかに利用すべきかという問題も大きな研究課題となるであろう。