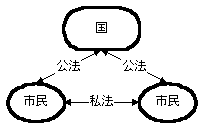
作成:1998年06月26日
追加:1998年07月05日
改訂:2001年06月15日
名古屋大学大学院法学研究科教授 加賀山 茂
本稿は,名古屋大学の新入生を対象とする法政基礎講座Ⅲ(実定法入門)において,「民法の学び方」という講義を行ったときのレジュメである。
主要な部分は,私の教科書『民法体系1(総則・物権)』信山社(1996年)からの引用であるが,注の部分は省略している。詳しい説明は,私の教科書を参照していただきたい。ただし,「II. 民法をマスターするとはどういうことか」以下の部分は,この教科書には記述がないため,新しく書き加えたものである。
本稿の内容は,民法の学び方を,以下の3点に分けて解説している。つまり,第1に,対象を知り(民法とはどのような法律か),第2に,マスターするための目標を設定し(民事事件の法的解決),第3に,方法論を知って実践する(民法をマスターするにはどうすればよいか)という構成をとっている。
学生諸君が,本稿を読み,対象である相手を知り,自分なり目標を定め,さまざまな方法を駆使して,着実に民法を学習されることを希望する。初めての人には,分からないところがあると思うが,気にせずに読み進めてほしい。学習を進めた後に,もう一度読み直せば,理解は自ずと深まるであろう。
法律は,国家と市民との関係を規律する公法(憲法,刑法,刑事訴訟法,民事訴訟法など)と,市民の間の権利義務関係を規律する私法(民法,商法など)とに大別される。
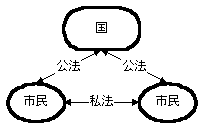
もっとも,現代においては,社会関係の複雑化に対応して,労働立法,社会福祉立法に代表される社会法や独占禁止法を中心とする経済法によって規制される法分野が増大している。これらの法律は,公法としての性質と私法としての性質を併せ持っており(公・私混合法),公法と私法との境界線は,あいまいなものとなってきている。
公法のうち,憲法は,公法としての性格の外に,すべての法律の根本法(lex fundamentalis)としての性格をも有している。例えば,民法における財産権の内容は,憲法29条2項の「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める」という規定を受けて立法されている。
私法のうち,民法は,市民生活,例えば,家族関係や相隣関係,毎日の買い物で利用されている売買契約,借金の返済に関する消費貸借契約,交通事故の示談など,身近な法律関係について規定しており,私法の基本法と呼ばれている。
さらには,資本主義の根幹をなす金銭担保(保証,抵当等)に関しては,それに該当する規定が商法にはほとんど存在しないため,民法およびその特別法が基本から応用までをカバーしており,この点では,民法は,企業取引の基本法としての性格をも有している。
したがって,市民生活に関する法律問題を解決するためばかりでなく,企業法務における複雑な法律問題を解決するためにも,民法を理解していることが不可欠の素養とされている。
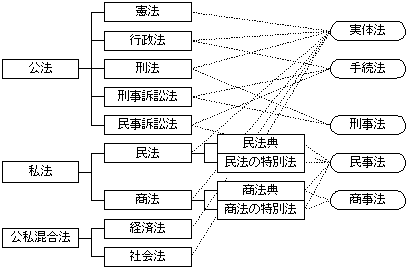
私法の基本法とされる民法の特色の1つは,国と私人という「縦」の関係を規律する公法とは異なり,自由平等を前提とする私人と私人との間の「横」の関係を規律する点にある。
したがって,原則として,「縦」の考え方が通用しない国際関係については,公法の考え方よりも,民法の基本的な考え方である「契約」,「不法行為」,「法人」の考え方の方がよりよく妥当するという逆説的な現象が生じる。例えば,国際公法は,条約,国際慣習法,国際組織法から構成されるが,これらは,それぞれ,民法の「契約」,「慣習」,「法人」の考え方がその基礎となっている。
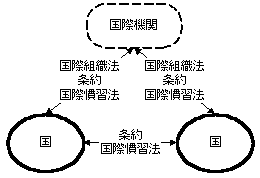
したがって,民法を学ぶということは,単に,日常生活の法律問題や企業取引に関する法律問題を解決するということに留まらない。むしろ,憲法を頂点とする国内法を超える次元の問題である国際関係を考える上で,欠くことのできない知識を修得することにもつながるのである。
以上のことは,公法と私法との関係において,国を国際機関へ,市民を国へと置き換えてみれば,よく理解できるであろう。
民法は,先に述べたように,国内法としては,根本法である憲法の制約の中でのみ効力を有し,憲法の精神に従った解釈を行うべきである。しかし,自由・平等な権利主体の間の権利義務関係を規律するという民法の基本的な考え方は,国家主権の枠を超えた国際関係を明らかにする上で,他のいかなる法律よりも重要な役割を果たす可能性を秘めているのである。
民法は,すでに述べたように,市民の間の権利関係を規律する私法に属しており,私法の一般法としての性質を有する。民法と商法とが,私法の代表的存在であり,民法は市民生活の一般法,商法は商事に関する民法の特別法として位置づけられている。
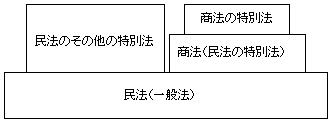
一般法と特別法という二本立てを行う理由は,立法の効率化のためである。例えば,市民生活一般に通用する一般法としての民法を作成しておけば,商取引とか商人間でのみ通用する特別のルールについては,一般法と異なる点だけを取り上げ,商法という特別法を作成することによってスムーズな法の適用を実現することができる。なぜなら,特別法である商法に規定がある場合には,一般法である民法は適用されず(特別法は一般法に優先する),特別法である商法に規定がない場合に一般法である民法が適用される(一般法は特別法を補充する)からである。同様にして,事業者(商人を含む)と消費者との間の消費者取引については,消費者保護という観点から,一般法である民法や特別法である商法とは異なる点だけを拾い出して,消費者保護の特別法を作成することも可能である。
このように,一般法と特別法の二本立てにしておくと,一般法を改正することなく,特別法を改正するだけで,新たな事態に対応した実質的な一般法の改正を容易に行うことができるうえ,「取引の安全の保護」と「消費者の保護」というような一見矛盾するようにみえる解決策についても,分野を限定した別個の特別法を作成することによって両立させることが可能となる。
もっとも,立法者の利益と,法律を学ぶ者の利益とは必ずしも一致しない。一般法と特別法の二本立ては,すでに述べたように立法者にとっては好都合であるが,これを学ぶ者にとっては,1つの事実関係について,多くの法律を参照しなければならないという不便を強いることになる。例えば,商事に関する法律問題を解決しようと思えば,民法の規定だけを学習したのでは不十分である。かといって,商法の規定だけを学習したのでは,これもまた不十分である。というのは,商事に関する法律問題を解決する場合にも,商法を補充する一般法としての民法の規定を学習し,必ず参照しなければならないからである。同様にして,割賦販売に関する事件を解決しようと思えば,商法,および,その特別法である割賦販売法の規定だけでなく,関連する民法の規定を必ず参照しなければならない。
民法は市民の権利と義務を規定しており,どのような事実があると,どのような権利・義務が生じるかを規定している。 実体法と訴訟法の役割分担を論理学における三段論法を例にとって考えてみよう。
三段論法においては,例えば,大前提として,「人間は死ぬ(すべての人間は,必ず死ぬものである)」というルールがあり,小前提として,「ソクラテスは,人間である」という事実が与えられると,結論として「ソクラテスは死ぬ」という命題が,論理必然的に導き出される。
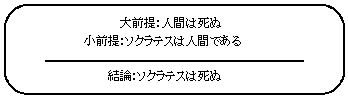
以上のような,論理学における三段論法に即して説明すると,「実体法」とは,大前提としてのルール(「要件」と「効果」との結びつきのルール)を宣言するとともに,どのような事実がいかなる「要件」に該当するかという小前提の解釈ルールを宣言するものである。
これに対して,「訴訟法」とは,実体法のルールを前提にしつつ,小前提となるべき事実を明らかにする手続きを定め,さらに,結論としての判決・決定を導き出す手続きを定めるものである。
(1)裁判規範としての実体法の存在,(2)事実認定と要件への当てはめ,(3)実体法の事実への適用としての判決の言い渡し,という3つの過程を,論理学における三段論法になぞらえて,「判決三段論法」ということがある。判決三段論法を民法709条の適用を例にして図式化すると以下のようになる。
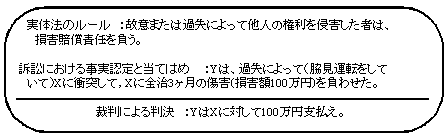
民事訴訟法は,民事紛争が生じた場合の紛争解決のための手続きを定めている。この手続きのうち,実体法である民法との関係で最も重要な問題と思われるのは,実体法の定める要件をどちらが証明しなければならないかという事実認定の基本ルールである。
一般的に,実体法上の要件について,その要件に該当する事実を原告と被告のうちのどちらが証明しなければならないかという証明責任の分配法則は,個々の要件ごとに,どちらに証明責任を負わせるのが衡平かという考慮によって決定される。しかし,ここでは,初心者のために,大まかではあるが,わかりやすい「慣性の法則」ともいうべき秩序維持のための現状肯定原則を紹介しておくことにしよう。
ここでいう証明責任における「慣性の法則」とは,静止した状態は証明がない限り永久に静止し続け,いったん変更した状況は証明がない限り永久に変更されたままとなるという原則である(この考え方は,占有状態の保護原則と呼ばれることもある)。
この原則を使うと,以下に述べる,権利根拠事由,権利消滅事由に関する証明責任の分配も容易に説明できる。というのは,何もない状態から契約が成立したことを主張するためには,契約が成立するための要件事実が証明されなければならないし,いったん成立が証明されると契約は惰性で存在し続けると考えられるので,契約上の権利の消滅を主張する者は,消滅を根拠づける事実を証明しなければならないということになるからである。
訴訟においては,権利を主張する者は,原則として,その権利の主張(請求)を根拠づける要件(権利根拠事由)を主張し,証明しなければならない。
例えば,貸金請求訴訟の場合,原告は,被告にお金を貸したこと(被告が借りた金を返すという約束をして金銭を受け取ったこと)を借用証等に基づいて証明しなければならない(民法587条)。証拠が不十分であれば,そんなお金は借りていないとの被告の「否認」が効を奏することになる。
これとは反対に,すでに発生した権利が実は無効であるとか,権利が消滅したとか主張する者は,成立した権利の無効要件(いわゆる権利障害事由)や消滅を根拠づける要件(権利消滅事由)を主張し,証明しなければならない。
例えば,先の例で,原告がお金を貸したことを証明したときは,被告の方で,契約が錯誤で無効であるとか,免除をしてもらったとか,時効で消滅しているとか,借金はすでに返済している等の事実(「抗弁」事実)を証明しなければならなくなる。つまり,相手の攻撃に対して防御する場合,自らが証明責任を負わない事実について反撃する場合である「否認」は比較的楽であるが,自らが証明責任を負う事実について反撃する「抗弁」は楽ではないということになる。
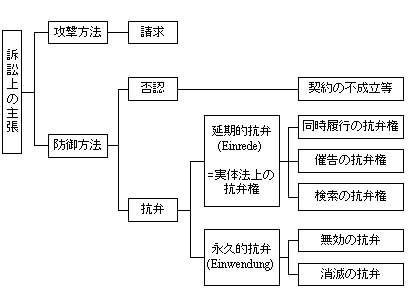
このように考えると,紛争解決手続きは,民法の要件事実を証明して法律効果の発生を主張する原告と,それを争う被告との攻防戦と見立てることができる。民事訴訟法も,原告と被告の主張方法を「攻撃または防御の方法」(Angriffs- und Verteidigungsmittel)」と呼んでいる(民事訴訟法137条,139条)。
原告は訴訟の開始に際して,要件事実に基づいて法律効果の発生を主張するが,この原告の主張のことを請求(Anspruch)といい,これが訴訟の対象としての訴訟物(Streitgegenstand)となる。これに対して,被告は「否認」と「抗弁」によって,請求の存在を争うのであるが,訴訟法上の「抗弁」には,請求権を無効としたり,消滅させる永久的抗弁(Einwendung)と,一時的に権利の行使を妨げる延期的抗弁すなわち実体法上の抗弁権(Einrede)とが含まれている。
1853年にペリー(Perry)が浦賀へ上陸したのを契機として,日本は,1858年に日米修好通商条約を締結した。その後,列強諸国(蘭,露,英,仏)との間で,次々と同様の通商条約を結んだが,それらは,日本の関税自主権を否定し,かつ,相手国の治外法権と最恵国待遇を承認するものであり,日本にとって,かなり不利な条約であった。
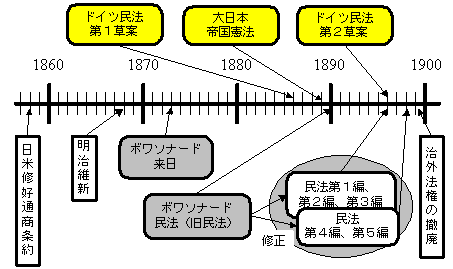
日本国民も,治外法権を含む屈辱的な不平等条約の撤廃を強く望んでおり,不平等条約の改正は,徳川幕府を承継した明治政府の最大の課題となった。 しかし,治外法権の撤廃を求める条約改正にとって最大の障害となったのは,その当時,日本には,市民の基本的な権利義務を規定した民法すら存在しないという事実であった。
そこで,不平等条約の撤廃を求めるには,市民生活の基本的な法律関係を規定するものとしての民法を制定することが不可欠であることが一般の理解を得るようになった。
 当時の国際社会において,ドイツはいまだに統一されておらず,列強の中で,体系的な民法典を有する国は,1804年に制定されたフランス民法典(ナポレオン法典)を持つフランスのみであった。
当時の国際社会において,ドイツはいまだに統一されておらず,列強の中で,体系的な民法典を有する国は,1804年に制定されたフランス民法典(ナポレオン法典)を持つフランスのみであった。
その他の列強の中でも,アメリカ,イギリスは,もちろん,すぐれた民法を持っていたが,それは,成文法ではなく,個別的な判例の集積としてのコモン・ローのシステムであり,それをそのまま輸入することはほとんど不可能であった。
そこで,明治政府は,フランス民法典を日本に取り入れることを決意し,フランス民法典を翻訳して日本民法とすることを真剣に検討した。しかし,「権利」という言葉すら存在しない当時の状況においては,翻訳すら困難を極めた。
試行錯誤の上,明治政府は,翻訳を含め,わが国独自で民法を作成することを断念し,フランス人の手を借りてわが国の民法を作成することにした。そして,パリ大学の教授就任を前にした民法学者ボワソナード(G. Boissonade)を口説き落とし,莫大な費用でわが国に招聘して,民法の作成を依頼することになったのである。
1873年に来日したボワソナードは,数年で民法典を起草するつもりであったが,一国の民法典を起草することは,それほど簡単なことではなかった。しかも,最初の7年は,政府の法律顧問の仕事と刑法典(治罪法典)の起草に忙殺され,民法典の起草が開始されたのは,1879年のことであり,民法典の起草が完成するのは,その10年後のことであった。
民法典の起草については,ボワソナードはその全体について起草し,決定稿とする権限をもっていた。事実,民法典のほとんどの部分はボワソナード自身が起草を行った。しかし,第1編(人事編)と第3編第2部(家督相続等)については,日本の風俗習慣,特に,武家の慣習を重視すべきとの理由で,ボワソナード自身は,直接に起草することはせず,日本人によって草案が作成された。そして,その草案を日本人の起草委員とボワソナードとが討議したうえで,ボワソナードが正稿にするという作業を行った。
その間,ドイツでは,プロイセンを中心に国家統一が進められ,民法典の起草作業が開始された。そして,1889年に発布されたわが国の明治憲法は,1871年に普仏戦争でフランスを破ったプロイセンの憲法を範としており,このころから急速にドイツ法の影響力が強まっていった。フランス民法を模範とすべき理由は決定的なものとはいえなくなってきたのである。
ボワソナードの起草した旧民法は,1890年,帝国議会を通過して公布され,1893年から施行されることになっていた。
ところが,封建的な家族制度を重んじる保守層から,民法は進歩的・個人主義的に過ぎるという理由で,施行延期の声が上がる(法典論争)。そして,延期派の穂積八束の論文「民法出デテ忠孝亡ブ」が世論を盛り上げ,ついに,旧民法は施行されないまま廃案へと追い込まれてしまう。
フランス民法の影響を強く受けたボワソナードの旧民法が廃止され,後に述べるように,それに代わって成立した明治民法が,ドイツ民法草案にならってパンデクテン(Pandekten)方式を採用したことから,わが国では,現行民法は,フランス民法から決別し,内容的にもドイツ民法を継受したものと考えている人が多いように思われる。
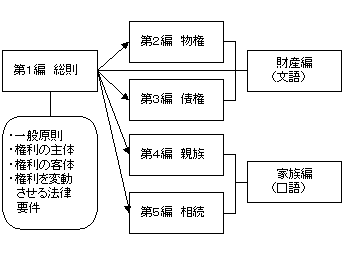
しかし,現行民法の個々の条文を詳細に検討すると,民法典は,パンデクテン方式の中に,かなりフランス法の考え方を残していることに気づく。不動産物権変動の対抗要件主義に代表される「対抗不能」の理論はその典型例であり,ドイツ法にはないフランス法の成果が巧みに取り入れられている。
つまり,日本の民法典の立法者は,その法典編纂方式をドイツ民法に依拠しながらも,個々の条文の内容やその基礎にある法原理については,ドイツ民法だけではなく,フランス法やその他の国の法律の原理を取り入れている。フランス民法にはなく,ドイツ法に特有の「法律行為」の理論,「法人」論,「不当利得」の理論についても,ボワソナードの創見による,ドイツ法とは異なる規定がかなり取り入れられている。
さらに,法典編纂の編別についても,ドイツ民法の編成方式に近いのは,最初の総則だけであり,物権になると,ドイツ法の編成方式とはかなり離れていく。そして,担保物権については,ボワソナードの債権担保編の規定を尊重し,ドイツ法にはない留置権,先取特権が大胆に取り入れられている。また,債権についても,詳細に検討すると,債権の効力等のように,必ずしも,ドイツ民法の編別には従っていないことが明らかとなる。
注目すべきは,法典論争のきっかけとなった親族法,相続法の規定である。特に,封建的な家制度および家督相続に関する旧民法の規定は,ボワソナードではなく,日本人の委員によって起草されたものであること,これらの家制度,家督相続に関する明治民法の規定は,ドイツ民法には参考にすべき規定が存在しないため,明らかに旧民法の編別がそのまま受け入れられているという点に留意すべきである。つまり,法典論争の中心とされた戸主権を中心に構成された家制度・家督相続制度については,旧民法と明治民法に本質的な相違はないのである。そうだとすると,法典論争とは,いったい何だったのかという疑問が生じてくる。
この点を踏まえて,法典論争は,自由主義的進歩的法思想と国家主義的保守主義的法思想とのイデオロギー対立というよりは,当時存在していた自然法学的「仏法学派」と歴史法学的「英法学派」の一面感情的で,他面功利的な学派の対立に由来するものであったとする見解が主張されている。
この見解によれば,これらの学派の対立を助長し,大論争に発展させた原因は,条約改正に関連する政治的立場の対立,すなわち,一方において,国権の確立のためには条約の改正が必要であり,その条約の改正のためには付帯条件として法典の編纂が必要であるとする政府当事者および断行派の人たちの考え方と,他方において,条約改正の手段として法典の編纂を約束することは主権の侵害であり,内政干渉を誘致するものであるという延期派の考え方の対立であったというのである。このように考えると,単に,断行派が自由主義的であり,延期派が封建的であったとはいえないし,家制度の内容が旧民法と明治民法とで大同小異だったとしても論争としては成り立ちえたということになろう。
法典論争をどのように位置づけるかについては,現在でも定説をみていない。しかし,わが国の民法典の成立に決定的な役割を果たしたにもかかわらず,正当な評価を与えられることなく失意のうちにフランスに帰らざるをえなかったボワソナードの業績に報いるためにも,法典論争について正確な歴史的評価に努めることは,わが国の民法を学ぶ者に課せられた重要課題の1つであると思われる。
話を元に戻そう。法典論争によって,旧民法が廃止されたため,日本民法は,日本人の手によって作成し直されることになる。
 すなわち,1892年,旧民法延期派の穂積陳重(1855-1926),富井政章(1858-1936),旧民法断行派の梅謙次郎(1860-1910)の3人が新たな民法の起草委員に選ばれ,ドイツ民法第1草案を含め,当時の世界中の民法を斟酌しつつ,ボワソナードの旧民法を修正するという方法で,新しい民法が起草されることになった。
すなわち,1892年,旧民法延期派の穂積陳重(1855-1926),富井政章(1858-1936),旧民法断行派の梅謙次郎(1860-1910)の3人が新たな民法の起草委員に選ばれ,ドイツ民法第1草案を含め,当時の世界中の民法を斟酌しつつ,ボワソナードの旧民法を修正するという方法で,新しい民法が起草されることになった。
旧民法の土台があったため,わずか4年後の1896年には,民法第1編,第2編,第3編(財産編)が公布され,1898年には第4編,第5編(家族編)が公布され,新しい民法全体がその年に,同時に施行されることになる(明治民法)。
懸案の治外法権の撤廃が実現するのは,民法典の施行の翌年の1899年であり,関税自主権の完全回復を含めた不平等条約の改正が実現するのは,1911年のことであった。
民法のうち,財産法は,見かけは,文語カタカナ書きでのままではあるが,戦後の民法改正(男女平等の解釈原則の追加と妻の無能力の規定の削除)によって男女平等を実現した。しかし,家族法は,見かけは口語ひらがな書きにもかかわらず,封建的な「家」制度を温存し,合理的な根拠もなく男女不平等の規定を残してきた。
戦後50年を経て,1996年1月に,法制審議会民法部会は,婚姻適齢の男女不平等の撤廃(民法731条),婚姻に際して配偶者の一方に氏の変更を義務づけてきた夫婦同氏義務(民法750条)の廃止,女に不当に長い期間の再婚禁止(待婚期間)を義務づけていた規定(民法733条)の改正,および,非嫡出子の相続分の差別の撤廃(民法900条4号)を骨子とする「民法の一部を改正する法律案要綱案」をまとめあげた。
しかし,この要綱案は,保守勢力の強い反対を受け,結局,政府は,法案を国会に提出することすらできなかった。しかも,男女平等と自己決定の自由をスローガンとした改正要綱案さえも,女にのみ一定期間の再婚禁止(待婚期間)を義務づけるという男女不平等を温存していた。したがって,家族法の分野では,今なお,ものごとを権利の側面から考えることが特に強調されなければならない。
何かをマスターしようと思えば,目標をはっきりと設定し,その目標を達成した状況を心に思い浮かべることが重要であるといわれている。
それでは,民法をマスターする場合に,その目標をどのように設定すべきであろうか。さしあたっては,教科書が理解できるようになる,試験で優をとる,司法試験の予想問題が解けるようになる等の身近な目標を設定することも悪くはない。
しかし,民法をマスターすることの究極の目標は,ある事件に遭遇した場合に,その事件を民事的に解決する能力を身につけることである。これは,ある事件が法廷に持ち出された場合に,どのような判決が下される可能性があるかを的確に予測できる能力といってもよいであろう。
民法をマスターするということは,ある事件が与えられた場合に,その事件を民法に基づいて解決することができる能力を養うことである。
ある事件が与えられた場合に,その事件を民法に基づいて解決するためには,2つの方法がある。ひとつは,適用すべき民法の条文を探し出し,その条文に基づいて解決するというものであり,もうひとつは,事実から出発して,似た先例を探し出し,その先例と同じように解決するというものである。
前者は,大陸法的アプローチ,後者は,英米法的アプローチである。わが国は,大陸法国に属しており,事件を法律の条文に基づいて解決するというやり方が採用されている。しかし,現実には,先例,特に,最高裁判所の判例は,条文と同じように,もしくは,条文以上に重視されている。
従来は,判例は,条文の解釈を補うものとされ,あくまで,条文の補助的なものとみなされてきた。判例を事実から切り離して,あたかも条文の解釈命題としてのみ理解するという傾向にそれが現れている。しかし,判例は,単なる条文の解釈を補うという機能だけでなく,条文が予想しなかった新しい問題に対して,一見,条文に反する解決に見えても,実は,同じ事例は同じように解決するという方法で正義を実現する,英米法的な機能をも果たしている。
大陸法的アプローチと英米法的アプローチというふたつのやり方は,それぞれ,独自の哲学に基づいて運用されているのであり,都合のよいところだけ取り入れようとすると,かえって,その長所を殺してしまうおそれがある。むしろ,両者の本質的な相違を理解し,それぞれの方法をきちんとマスターした後に,それらの長所を生かした解決方法を学ぶという努力が必要であろう。
大陸法においては,事件を条文の形で表された法律によって解決するというアプローチをとる。つまり,先に述べた,判決三段論法という論理的なアプローチである。英米法が,事件を,似た事件において下された先例から導かれた法理に基づいて解決するというアプローチをとるのと対照的である。
大陸法のアプローチは,要件と効果の組み合わせからなる条文を大前提とし,ある事件の事実関係がそれらの条文のうちどの条文の要件に該当するかを検討し,最も適切な要件に事実を当てはめてみて,その要件が充足されるならば,その法律効果を主張する当事者の主張を認める判決を下し,もしも,要件に該当しないならば,当事者の主張を否定する判決を下すというものである。
判決文を読むと,事件に適用する条文はわかったものとして扱われ,認定された事実が適用されるべき条文の要件を該当するかどうかが検討されている。しかし,実際の裁判においては,ある事件をどの条文に基づいて判決すべきかが大問題となる。適用条文が異なれば,結論は異なるからである。
事件に適用されるべき条文を明らかにするためには,まず,条文の要件が,どのような事実に該当するのかを事前に明らかにしておく必要がある。そのような検討が十分になされ,どのような事実がどの条文のどの要件に該当するのかが明確になっていて初めて,要件にしたがった事実認定,条文への当てはめが可能となるのである。
そこで,ここでは,大陸法的アプローチの前提となる条文の要件効果分析,適用条文の発見のプロセス,さらには,適用条文の要件に事実をあてはめた結果の妥当性の検討と類推解釈の意味について順を追って説明することにする。
条文の要件がどのような事実を想定しており,どのような事実までカバーしているのかを明らかにすることが,条文を事件に適用するための前提となる。
この作業を行なうためには,法律の起草者の考え方がまず参照されなければならない。起草者の考え方は,議会の委員会の議事録,議会の議事録,起草委員がまとめた立法理由書,法律解説書等で知ることができる。
起草者の考え方を知ることによって,条文の要件がどのような事実を想定していたかは理解できる。しかし,社会の変化によって,その条文の要件をどのような事実にまで拡張して,または,ある事実だけに限定して解釈すべきかは,困難な問題である。
そのような作業を専門に行なっているのが,法律学者であり,論文,教科書,注釈書によって,条文がどのような事実をカバーしているかを明らかにする努力を続けている。
学者は,みずからの問題意識に応じて,さまざまな条文を取り上げ,その条文が関係する従来の判例を丹念に調査し,外国法の状況も押さえた上で,条文の解釈の限界を明らかにし,将来予測される事実について適用の可否を検討している。このような数々の著作のおかげで,事件を担当する弁護士,裁判官は,ある事実について,どの条文を適用することが可能であるかを,事前に知ることができるのである。
もちろん,社会の進展に応じて,これまで予想もしなかったような事実が発生する。その場合,どの注釈書,論文にも出てこないような事実をどの条文によって解決すべきかは,最終的には,裁判官の判断に委ねられている。裁判官が判断を下すと,それは,さっそく,論文,判例評釈に取り上げられる。そこで一応の評価が下されると,注釈書の改定の際に,新しい解釈として採用されることになる。
法律の条文は,典型的な事実を想定して起草され,解釈を通じて,要件がカバーすべき事実群が一応確定される。しかし,社会の進展に伴って予想を越える事実が発生した場合には,裁判官は,これまでの解釈を踏まえた上で,適切と思われる要件を探し出し,その要件にしたがって事実を構成し,判決を下す。その判断は,学者の評価を経て,注釈書において,要件がカバーする新たな事実群として取り込まれる。このような繰り返しによって,法律要件と事実との関係が明らかとなっていくのである。
法律家は,法律の条文の中にある要件がどのような事実をカバーしているかという解釈問題に通暁している。これを前提として,ある事件が発生した場合に,その事実関係を調べながら,それらの事実が,どの法律のどの要件に該当するかを決定する作業を行なう。
この作業は,見かけ上は,事実→法律要件→法律効果,というように一定方向にしかも一直線に進むように見えるが,実は,ある程度事実が明らかになってくると,法律家には,結論としての望ましい法律効果が見えてきて,→その法律効果を導く別の条文→その条文の要件→事実,というように,逆向きの推論が開始される。
特に弁護士の場合には,依頼者が望む法律効果が決まっており,それにうまく乗るような条文を見つけて,その要件に該当する事実のみを選んで主張することになる。他方の当事者の弁護士は,相手方の持ち出す条文に則り,要件に該当する事実はないことを主張することもあるが,反対の結論を導くことのできる別の条文を見つけて,その要件に該当するような事実のみを主張することもありうる。
例えば,自衛隊員が敷地内で交通事故で死亡したため,被害者の遺族が国を相手取って損害賠償訴訟を提起した有名な事件において,原告(被害者の遺族)が訴えを提起したのは,事故発生からすでに3年を経過した後であったため,原告側は,損害賠償の根拠を3年で時効にかかる不法行為ではなく,信義則から生じる安全配慮義務,すなわち,10年間時効にかからない債務不履行であると主張した。これに対して,被告は,この問題は交通事故の問題であり,原告の請求は不法行為に基づくもので,3年の時効によって消滅していると主張した。
裁判所は,結局,原告の主張を入れて,安全配慮義務の存在を認めて原告を勝訴させたのであるが(最三判昭50・2・25民集29巻2号143頁),裁判所の判断は,結論が先にあったことは明らかである。裁判所は,原告を救済するために,信義則上の安全配慮義務という,学説が発展させた法理を用いて,本来なら適用すべき不法行為の条文を適用せず,信義則という一般条項を介することによって,あえて,時効期間の長い債務不履行の条文を適用したのである。
このように,適用すべき条文は,決して,要件効果分析という法解釈によって一義的に決定されるものではなく,事実→要件→効果,という方向と,効果→要件→事実という逆の方向からも検討が進められ,妥当な解決を導くものとして,最適の条文が「発見される」ものなのである。
大陸法の特色である法律の条文に基づく紛争の解決は,その前提として,あらゆる事実に対してそれを解決するに適する条文が存在するということを前提としている。
確かに,自然科学の分野においては,たとえば天体の運行,たとえば,日食の時期,彗星の出現の時期等は,ニュートンの万有引力の法則を適用することによってすべて予測することができるかもしれない。
しかし,社会現象に関しては,そのような一般法則はいまだに発見されていないし,生じうるすべての事実を事前に予測して,適用されるべきルールをあらかじめ制定することはとうてい不可能である。したがって,新しい社会現象が生じた場合には,従来の法律を適用したのでは,具体的な妥当性を確保できない事態が生じうる。
大陸法の特色である法律の条文に基づく紛争の解決という方法は,この点で,論理的な破綻を生じてしまう。
紛争解決のためのルールは,すでに存在しており,「法の欠缺」はないというのが,いわゆる概念法学の立場であるが,神ならぬ人間が,すべてのことを事前に予測しうると考えること自体が不遜であり,そのような強弁は今日では通用しないであろう。
新しい社会現象が生じた場合に,必ずしも適切な条文が存在しないことを認めつつ,かつ,大陸法の考え方を維持するためには,実定法の解釈という名の下に,新たなルールを創造する権限を,司法機関に過ぎない裁判所に与える必要がある。
一つは,本来適用すべき条文があるにもかかわらず,それとは異なる結論を導きうる他のルールの適用を認める類推解釈であり,もう一つは,まったく新しい解釈を導くことを許す,一般条項の適用である。
厳密には要件に該当しない事実に対して,その要件と似ている要件を介在させることによって,適用したいルールを適用してしまうことである。結果的には,本来なら適用されるべき法律の適用を廃して,結果の異なる別の法律の適用を導くことになる点で,新たな立法をしたのと同様の効果を生じる。
たとえば,契約当事者A,Bのうち,登記を有するBから不動産を買いうけた善意の第三者Cを保護したいが,登記は,まだBに残っているという場合を考えてみよう。登記を有しないCは,民法177条によったのでは,保護することができない。また,たとえCが登記を有していても,それが,真実の登記でない場合は,やはり,Cを保護できない。
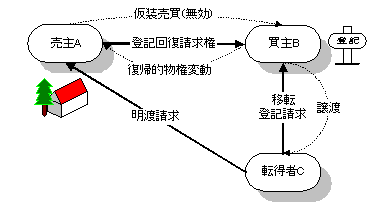
このような場合でも,民法94条2項が適用されれば,善意の第三者Cは保護されるのだが,当事者A,B間には,要件としての「通謀」がないとしよう。
この場合に,当事者の一方が勝手にした意思表示であっても,相手方当事者がそれを認容して利用していたときは,通謀があるのと同様に,民法94条2項が類推されるとしたり(最三判昭45・9・22民集24巻10号1424頁),さらには,当事者の一方が勝手にした意思表示であり,かつ,それを明示的に認容したり,利用したこともないが,長期間にわたって,黙認していたときには,通謀があるのと同様に,民法94条2項が類推されるとする(最一判昭48・6・28民集27巻6号724頁)のが,類推解釈の典型例である。
この場合,単に要件が大幅に拡大解釈されただけのようにも考えられるが,このような場合には,本来ならば,民法177条が適用され,登記を有しない第三者Cは,真の権利者であるAに対抗できないはずであるのに,あえて,民法177条を適用せず,民法94条を適用するところに,通常の解釈を超えた類推解釈の意味がある。なぜなら,民法177条が認めていない登記の公信力が,民法94条の類推解釈を通じて,一部実現されたことになるからである。
本来なら適用されるべき法律があるにもかかわらず,一般条項,たとえば,信義誠実の原則を利用して,新たな解釈ルールを作り出し,別の結果を導き出すことが可能である。
たとえば,自衛隊員の敷地内での交通事故について,本来なら民法724条が適用されて,3年の消滅時効にかかるべきところを,国には,自衛隊員の安全について配慮する信義則上の義務があり,国はそれを怠ったのであるから,債務不履行があり,10年の消滅時効が適用される(最三判昭50・2・25民集29巻2号143頁)として,被害者を救済するというのがその典型例である。
契約交渉に関しては,当事者は自由に交渉することができ,合意に達しなかったからといって責任を負わないのが原則である。しかし,当事者との合意に到達しない意思を有しながらも交渉を開始したり,継続した場合のように,交渉を不誠実に行って契約締結しなかった当事者は,契約締結段階における信義則上の注意義務に違反しており,損害賠償責任を負う(最三判昭59・9・18判時1137号51頁)というのも,一般条項を利用して,契約準備段階の過失責任という新たな法理を導いた典型例ということができよう。
英米法の場合,大陸法とは異なり,民法の条文は存在しない。民法は判例法として存在するだけである。
判例は,事実から出発し,その事実を法的に解決するための法理を創造する。判決によって生み出された法理は,すべての事例に一般的に通用するのではなく,それと同じ事実が生じたときにのみ適用されるに過ぎない。
事実が違えば,他の先例の法理,または,新しい法理が適用される。たとえば,馬車の欠陥によって乗客が怪我をしたときに適用された法理が,自動車の欠陥によって乗客が怪我をしたときにも同じように適用されるとは限らないのである。
ある事件が生じた場合,英米法では,その事件の事実を分析し,その事件と似た事実に関して出された判決を検索することが必要である。似た事件は似たように,違う事件は違うように判決することが正義にかなうと考えられているからである。
似た事件は似たように判決することを先例拘束の原理(doctrine of precedent)といい,違う事件は違うように判決することを区別(distinguish)のルールという。
英米法では,条文のルールではなく,事実の解決として判決の理由で示された法理(ratio decidendi)が先例として拘束力を有する。
これが英米法における先例拘束の原理であり,ある判決でとられた法の準則は,将来の同種事件において,原則として従われるべきであるということになる。
なお,判決理由の中で述べられた法理でも,その事件における重要な事実に関する部分以外のものは,傍論(obita dictum)であって,拘束力を有しない。判例法は,あくまで,特定の事実に関する法的判断なのであって,事実を抜きにしたまま抽象的な法理を展開しうる大陸法とは根本的に異なる点に注意を要する。
ある事件を解決するために似た判例を検索しても似た判例がない場合には,裁判所は,その事件を解決するための新しい法理を創造することができる。
ある事件を解決するために一見似た事例がある場合でも,その事例に関する先例を適用すると妥当な結論が導けないという場合にも,その先例と当該事件との事実関係との間には,「重要な事実」(material fact)に差異があると判断できれば,新たな法理を創造できる。
上に述べた区別(distinguish)の法理があるために,英米法は,先例拘束の原理を維持しつつ,柔軟な解決を行うことが可能となっているのである。
第1に,大陸法においては,法律は,条文の形で表現される。法典と呼ばれる法律の場合には,体系的な整合性をも有しており,ルールの全体を理解するのが比較的容易である(全体像の把握の容易さ)。
第2に,大陸法の中心を占めるルールとしての法律については,その条文は有限であり,かつ,ルールは全て事前に示されているので,自分の行動が,ルールに違反するかどうか,あらかじめ知ることができる。その意味で,法的安定性が確保される(法的安定性の確保)。
第1に,大陸法においては,事実を認定する場合にも,判決の大前提となるルールの要件に即して,事実を見ることになるため,前提となる要件に引きずられて,事実を歪めて認定する傾向が生じる。適用すべき法律の条文を誤った場合には,その傾向は顕著であり,具体的妥当性を確保するために,無理な事実認定が行われることが少なくない(ルールにあわせて事実をゆがめて認定する傾向がある)。
第2に,大陸法においては,事件の性質から特定の条文を適用するのがもっとも素直であるという場合,結論は,判決三段論法によって,必然的に導き出される。しかし,その結論は,具体的な妥当性という観点からは,問題がある場合が少なからず生じる(理論的だが具体的な妥当性に疑問のある結論が導かれることがある)。
たとえば,欠陥自動車によって購入者に事故が生じた場合,従来の民法の過失責任のルールを適用すると,購入者は,メーカーの過失を証明することが困難であり,民法709条を適用すると,過失の立証が不十分ということで敗訴する可能性が高い。
民法は,危険物である土地の工作物の場合には,民法709条の特別法である民法717条によって,土地の工作物の所有者に対して,無過失責任を負わせている。しかし,自動車については,そのような責任を認めていない。民法が制定・施行された1898年当時,日本には,まだ,ガソリン自動車は存在しなかった。
 |
| 朝日新聞1969年6月1日 この新聞報道を契機に, わが国でも,製造物責任が 議論されるようになった。 |
もしも,民法が制定されていた当時,すでに,自動車が実用化され,交通事故等も起こっていたとしたら,民法の立法者は,民法717条の土地工作物責任と並んで,欠陥商品に関しても,メーカーの無過失責任を認める条文を起草していたかもしれない。
しかし,現実には,欠陥商品に関するメーカーの製造物責任が条文で認められるのは,1994年に成立し,1995年から施行された製造物責任法が最初であり,わが国で製造物責任が議論され始めた1969年から四半世紀を経た後のことであった。それまでは,動産の欠陥については,被害者がメーカーの過失を証明しない限り,被害者が救済されることは困難であった。
製造物責任法が制定される以前においても,地方裁判所や高等裁判所のレベルでは,欠陥プロパンガス・ボンベについて民法717条を適用したり,食品・薬品について民法709条の解釈を通じて過失の証明責任を転換したりする試みが続けられたが,わが国の最高裁判所は,条文の根拠なしに法律上の推定を行うことは,解釈の範囲を超えるとして,地裁・高裁レベルでの柔軟な解釈を否定している(最二判平元・12・8民集43巻11号1259頁参照)。
後に述べるように,英米法の場合には,事実から出発し,事実の相違に応じて法理を異にすることが許されている。たとえば,馬車には過失責任法理,自動車には厳格責任法理というように,主要な事実が異なれば,適用する法理を使い分けることが制度として認められている。これに対して,大陸法のシステムの場合には,すべての事件を抽象的な条文に基づいて,一律に判断しなければならないため,メーカーに対して無過失責任を認めるためには,新しい立法が成立するまで待たなければならなかった。
大陸法諸国でメーカーの無過失責任が一般に認められるようになるのは,1985年に製造物責任に関するEC指令が採択されてからであり,1963年にアメリカでメーカーの無過失責任(厳格責任)が認められてから20年が経過していた。わが国で無過失の製造物責任が認められるまでには,さらに10年が必要だったのである。
大陸法的アプローチの第3の短所は,体系的に作られた条文の一部を変更すると,それにあわせて,さまざまな条文を変更しなければならなくなるという点である(新しい事実に対応するために常に体系の修復が必要)。
民法のような重要な法律を改正する場合には,その波及効果は計り知れない。新しい判例が形成される場合にも,その影響は,さまざまな法律の解釈の変更を促し,その都度,体系の修復を行う必要に迫られることになる。
新しい判例の登場とともに,本来は,それに合わせて条文自体を変更するのが望ましいのであるが,わが国においては,立法者は,民法のような基本的な法律の改正には消極的であり,条文の通常の意味と,判例によって新しく付け加えられた意味との間に大きな隔たりが生じても,条文の文言は昔のままに放置されていることが多い。そうなると,制定法によって現在のルールを明確に表明しうるという大陸法の利点は,大きく後退することになってしまう。なぜなら,わが国においては,制定法主義を採用しながら,その後の判例の準則等を通じて条文の意味が変質してしまっており,条文の意味を知ろうと思えば,結局,多くの判例を読んでみなければわからないという状況が発生しているからである。
英米法における先例拘束の原理は,似た事例については,同じように判決すべしという考え方に基づいている。したがって,似ていない事例については,裁判官は,新しい法理を創造しうる。これが,英米法的アプローチの第1の長所である。
似た事例について先例が存在する場合であっても,裁判官が,その先例に拘束されるのを避けたいと考える場合には,先例となる事件にさかのぼって仔細に事件を検討し,当該事件と先例となる事件の間にある事実の相違を指摘し,両者を区別することによって先例法の束縛から免れ,新たな法理を展開することができる。
大陸法においては,ルールは立法者によって示され,裁判官は,そのルールを事件に適用して法的解決を示すという形式をとる。したがって,適用すべきルールが明白である場合には,その結果が妥当とはいえない場合であっても,そのルールを適用せざるをえない。これに対して,英米法の場合は,裁判官は,事件の具体的妥当性を確保できる法理を発見することが課題となる。
まずは,似た事件に関する先例を検索し,同じ法理を適用してみる。しかし,その法理が具体的妥当性を確保できない場合には,次に,具体的な妥当性を導きうる他の法理を探し出す。そして,その法理が適用された事例の事実を分析し,その先例の方が,当該事件により似ていると判断することによって,具体的な妥当性を確保することも可能である。
さらには,具体的妥当性を確保するに足るような先例が存在しない場合には,似た事例はなく,先例はないとして,具体的妥当性を確保できると思われる新たな法理を創造することもできる。
英米法的アプローチの第2の長所は,形成されるルールが常に,特定の事実を前提としていることである。前提となる事実が異なれば,ルールも異なりうる。したがって,似たような事実関係について,法理を変更すべき場合においても,事実関係が異なるという理由をつけることができれば,異なる法理を適用しても矛盾ではない。
大陸法の場合においては,法律の制定者が予想しない問題が生じ,かつ,従来の法律では,具体的な妥当性が確保できないという場合には,法律を変更しなければならず,しかも,その場合,他の法律に影響が及ぶ場合には,それらの法律もすべて変更する必要が生じる。
しかし,英米法の場合には,判例が変更されたように見えても,事実関係が異なるとして,その矛盾を解消することができるため,判例は,常に,追加すれば済む。これは,データベースの蓄積という立場からは,非常に優れた特色であるといえる。どんな昔の判例でも,使える法理は,すべて先例として引用することができるからである。
英米法的アプローチにも,もちろん,短所が存在する。第1に,英米法の場合,全体像を把握することが困難である。具体的妥当性を確保することと,ルールの単純性・体系性とは両立しない。具体的妥当性に重きを置く英米法は,ルールが常に事実に結びついているだけに複雑であり,単純なルールとして表現することは困難である。したがって,ルールの全体像を理解することは困難である。
第2に,判例法の法理は,常に事実関係と結びついており,事実関係が異なる場合には,違う法理が適用される可能性がある。したがって,ある事件と似た事件について判決があるからといって,その判決が当該事件に適用されるという可能性は必ずしも高くない。つまり,法的安定性は,それほど高くないということになる。
 |
| 司法研修風景 発行・木村達也法律事務所 (1991年)31頁による |
わが国においては,司法試験に合格して司法修習生となった人たちは,司法研修所に入り,法曹教育の一環として,民事訴訟に関して「要件事実教育」と呼ばれる特別の訓練を受ける。それまで,民法等の実定法の条文について,その意味を教科書や注釈書に基づいて理解してきたに過ぎない法曹の卵たちは,ここで,もっと実践的な教育,すなわち,民事裁判においては,何が重要な事実であり,その事実,すなわち,「要件事実」は,原告,被告のうち,どちらが主張・立証しなければならないのかという観点から,訴状の書き方,答弁書の書き方,判決の書き方等について,実例に基づいた徹底した教育を受けることになる。
この要件事実教育については,即戦力となる人材を養成しているとして高い評価がなされる一方で,概念法学的な「形式論理の機械的操作を習得させる平板な技術的教育に過ぎないとして非難されてもきた」(三井哲夫『法律要件分類説の修正及び醇化に関する若干の具体的事例に就いて』法曹会(1984年)1頁)。要件事実教育に対する批判のポイントは,要件事実教育は,実定法のルールが完全であることを前提にしており,その完全無欠とされる法律要件の観点から,すべての事実を分類し,その分類に基づいて,事実を機械的に認定するという方法論であって,法律の柔軟な解釈を阻害する傾向が強く,具体的妥当性を確保できないというものである。
ある事件が裁判所に持ち込まれた場合に,その事件を法律に基づいて解決するためには,その事件に含まれるさまざまな事実の中から,重要な事実は何かということを的確に判断する確固とした法的視点が必要となる。その視点を法律の条文の要件とするのが要件事実教育の教育方針であるといえよう。しかし,重要な事実は何かを判断する法的視点としては,法律の条文のほかにも,先例の重要な事実を手がかりにするという方法も存在する。
従来の大学教育が,事実関係を無視した条文の解釈を偏重してきた弊害を克服するため,以下においては,事実を重視し,ある事実が与えられた場合にどの法律を適用すべきかを考える能力を伸ばすという本来の実定法学教育のあり方を模索する。その際,事実を重視する点では共通するが,わが国の司法研修所が行ってきた事実を見る視点を法律の条文だけに限定するという弊害を克服するため,先例で用いられた重要な事実の判断基準を事実を見る視点として採用するという英米法的なものの考え方を重視することが大切である。この点を踏まえて,大陸法の利点と英米法の利点をともに生かす方法を呈示することにしよう。
従来は,判例は,条文の解釈原理として扱われ,適用された条文にしたがって分類がなされてきたため,似た事実に対して判例を検索しようとしても,事実から判例を検索することはほとんど不可能であった。
しかし,最近の判例データベースの発達により,事実のキーワードからも判例の検索ができるようになった。たとえば,CD-ROMによる判例検索システムの「判例MASTER」においても,「判例体系」においても,欠陥自動車に関する判例とか,いじめ事件に関する判決というように,必ずしも適用される条文にこだわらない検索が可能となっている。
したがって,ある事件について法的な解決を模索する場合,このようなデータベースを利用して,その事件の事実関係に関連するキーワードを使って,関連する判例を検索し,事案が似ていると思われる判決をいくつか集めてみるのがよい。
この段階では,いかなる条文が適用されるべきかどうかという観点は抜きにして,問題となっている事件の事実関係に関連の深い判決を検索してみるのがよい。
問題となっている事件の事実関係に似ている判決が検索された場合には,その判決によって採用された論理を使って,当該事件に関する第1の解決案を予測してみるのがよい。
そこで得られた解決案は,以下に行う条文に基づく解決案とは無関係に,一応の解決案として,心に留めておくべきである。
キーワードによる判例検索によっても,問題となる事件と似た判決が検索できた場合であっても,似た判例が検索できないない場合も,次の段階として,その事件の事実関係に適用されるべき条文を検索する。
この場合は,その事件の事実に当てはまりそうな条文の要件,当事者が求めている効果の両面から,条文を検索し,適用の可能性のある条文はすべてチェックすべきである。事実は無限であるが,条文の数は限られているのであるから,ここでの検索は,すべてを尽くすよう努力すべきである。
適用すべき条文の候補が見つかったら,それぞれの条文に事実を当てはめて,法的結論を導いてみる。どの条文を使っても結論が同一になる場合は,問題がないが,どの条文を使うかで,結論が異なる場合には,どの条文を適用すべきかを検討しなければならない。
条文の間に,一般法と特別法との関係がある場合には,特別法が優先される。しかし,特別法と一般法との関係は,条文の体裁だけから一律に決めるということはできないので,一般法であっても,事案の解決に適するものであれば,適用の余地を残しておくべきである。
例えば,条文の体裁だけを根拠に,債権総論の民法415条は,債権各論の民法709条の一般法であるから,民法415条よりも,民法709条を優先的に適用すべきであるといった形式的な議論は,差し控えたほうがよい。契約という特別関係のない一般的な問題に適用される民法709条の不法行為責任の方が,特別の契約関係を前提としている民法415条の契約責任の方が特別法に該当するという考え方も可能だからである。
問題となる事件に適用されるべき条文のすべてについて,事実を当てはめて結論を導いてみても,具体的な妥当性が得られない場合には,本来,具体的なルールの陰に隠れている一般条項を適用して,具体的なルールの適用による結果の不都合を回避したり,具体的な事実に適した新しい解釈原則を引き出すという方法も試みるべきである。
ただし,一般条項を適用しようとする場合には,本来適用されるべき条文が,時間の流れによって機能不全に陥っているか,事案の特殊性によって,本来適用すべき条文では,妥当な解決を導くことができないということをはっきりと認識しておくべきである。一般条項の濫用にならないよう,適用には慎重でなければならない。
このような注意が必要ではあるが,一般条項は,時代の変化によって,個々の具体的な条文が不具合を生じている場合に,その条文の適用を実質的に廃止し,新しい解釈原則を打ち立てる機能を果たすものとして,よく用いられてきた。
体系的な条文構造をもつ大陸法の場合,具体的妥当性を確保するためには,明確なルールの他に,一見あいまいで,頼りなく見える一般条項を持つことが不可欠である。そして,このような一般条項の働きを通じて,体系を保持しつつ,英米法の場合と同じように,具体的妥当性をも確保することが可能となるのである。
最期に,問題となる事例の事実関係に似た判例の法理による結論,個々の条文を適用して得られる結論,一般条項の適用による結論を全て検討し,その事案の解決にもっとも適していると思われる結論を選択する。
その後,その結論を正当化する条文のルールを再選択し,その条文に基づいて事案の事実関係を整理し,判決三段論法にのるように,説得力のある解決案を作成する。
個々の条文の間に抵触が生じ,事実関係に最も適した条文よりも,事実関係にとは少し離れるが,妥当な結論を導きうる条文がある場合には,その条文を類推適用するのが説得力を高める。その条文では,どうしても,妥当な結論を導くことができない場合は,一般条項を適用して,新しい解釈原則を創造すべきである。
民法をマスターしようと思えば,まず,次の道具をそろえなければならない。外国語の学習に,辞書,適切な教材,豊富な文例が必要なのと同様である。六法,教科書,判例集,法律辞書は,必携である。
専門用語の意味を知るためには,辞書が有効である。法律を学ぼうとする者は,自分のレベルにあった法律用語辞典を1冊は用意すべきである。筆者が利用している法律用語辞典は以下のとおりであり,後の2つは,CD-ROM版があってコンピュータ上で利用できる。
法律の条文は有限であるが,世の中に生起する事件の事実の組み合わせは無限である。無限の事実を前にして,その事実に適用されるべき法律を有限の候補の中から的確に選び出す能力というのは,理論ではなく,それをマスターした指導者による訓練を通じてのみ習得される。
大学における実定法学教育は,以下の順序を踏んで,事実がわかると,その事実に適用されるべき法律を探し出すことができる能力を養成しようと努力している。
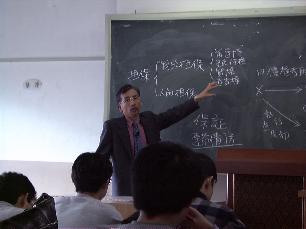 大学における実定法学教育のうち,講義は,主として,法律の条文の意味,すなわち,条文はどのような事実について適用されるかをマスターすることをねらって行われる。
大学における実定法学教育のうち,講義は,主として,法律の条文の意味,すなわち,条文はどのような事実について適用されるかをマスターすることをねらって行われる。
講義は,全体像を捕らえること,全体の中の各部分がどれだけの重要性をもっているかを知るために有益である。
これまでは,大学の講義は,教授が専門とするところだけを詳しく解説というスタイルも存在したが,現在では,講義計画に従って,全体をもれなく説明し,かつ,重要な部分については,かなり丁寧に講義をするという方法がとられるようになってきている。
講義によって民法全体をカバーしようとすると,おのずと,講義の進度は過密にならざるをえない。したがって,講義のスケジュールにあわせて,該当部分をあらかじめ予習し,わからないところをチェックしてから講義に臨むようにすると早い講義にもついていくことができるし,得られる効果も大きい。
一見,退屈に思われる講義でも,講義の進路にあわせて,教科書で予習をし,練習問題を解いてみて,分からない箇所を明確にしておくと,自学自習とは比べ物にならない成果を得ることができるであろう。
大学のゼミナール(演習)は,講義の場合とは反対に,判決に登場する事実を素材として,その事実にはどのような条文が適用されるべきかを検討することに重点が置かれる。
ゼミに参加して,初めて,法律解釈の楽しさを体験する人が多いのは,条文の意味を知るだけならば,独学でもなんとかなるが,反対に,ある事実にどの条文を適用すべきかを知るためには,適切な指導者の下で,訓練を積むことが不可欠であるからであり,そのような訓練は,小人数のゼミナールでしか実現できないことを示している。
ゼミで判例研究を行う場合には,ある事件の事実関係を把握することから出発して,その事実関係を適切に解決することのできる条文は何かを探し当てるという観点から考察を行うことに主眼を置くべきである。
 判例を条文の解釈命題として理解し,単に条文を補足するものだという意識で,事実をおろそかにしたまま判例を読んでいたのでは,ゼミナールに参加する意味がない。ゼミナールに参加するときは,第1に,取り上げられる事件の事実関係を直接判例集に当たって十分に把握することが必要である。そして,第2に,その事件に適用されるべき条文はどのようなものがあるか,それらの条文のうち,当該事件をもっとも適切に解決できる条文はどれかを検討することが必要である。そのような課題をこなす上で,判決は,最高の教材であるであると考え,自分が裁判官だったらどのような判決を下すだろうかという意気込みで読みこなすという努力が必要である。
判例を条文の解釈命題として理解し,単に条文を補足するものだという意識で,事実をおろそかにしたまま判例を読んでいたのでは,ゼミナールに参加する意味がない。ゼミナールに参加するときは,第1に,取り上げられる事件の事実関係を直接判例集に当たって十分に把握することが必要である。そして,第2に,その事件に適用されるべき条文はどのようなものがあるか,それらの条文のうち,当該事件をもっとも適切に解決できる条文はどれかを検討することが必要である。そのような課題をこなす上で,判決は,最高の教材であるであると考え,自分が裁判官だったらどのような判決を下すだろうかという意気込みで読みこなすという努力が必要である。
そして,ある判決の法理を導き出す場合には,後に述べるように,問題となった事実関係を考慮して法理を導き出すようにすべきである。前提となる事実関係を無視して,条文のような命題を抽象的に引き出すことには慎重であらねばならない。
法律学は,平等と衡平の考え方に基づいて,他人を説得する学問である。感情ではなく,論理的に人を説得するには,考え方をしっかりと組み立てる必要がある(もっとも,説得の段階で,感情のこもった言葉が必要であることを否定するものではないが,論理に裏付けられた感情の吐露と感情剥き出しの議論とは,結果が異なると思われる)。
ものごとを論理的に考えるには,思ったことを文章にしてみるのがよい。文章にしてみると,論理が客観化され,論理の間違い,論理の飛躍がよくわかる。
論理に基づいて客観的に話すことができる人というのは,はじめからそれができるのではなく,日記,手紙,論文等,表現手段はいろいろであるが,いずれにせよ,事前にそのことを文章にしていることが多い。教壇で,とうとうと論理を述べる教授は,そのテーマについて,深く掘り下げた論文を書いているからこそ,何も見ずに,立派な講義が可能なのである。
感情ではなく,客観的な根拠に基づいて説得するためには,入念な準備が必要なのであり,みずからの考えを,文章にしてみて,客観的な立場で点検できるようにしておくのがよい。そのためには,普段から,ゼミの報告レジュメだけでなく,テーマを決めて小論文を書く習慣を身につける努力をすることが大切である。
これまで述べた方法を実践すると,民法の学力は間違いなしに向上する。しかし,それだけでは,ある点でその成長も限界に達する。本当の学力を身につけたければ,やはり,人格を円満に保ち,その人にはいろいろな情報を与えてあげたいと人から慕われるようにならなければ,上達は望めない。
いい論文を書いても,それに対する批判を許さない態度をとれば,誰も,助言をしてくれなくなる。文章を書くのは,自分の考えを客観化し,人から批判を受けるためである。どんなささいな批判でも,ありがたく,快く,応答し,わかりにくい個所を改め,間違いを改める努力をしなければ,文章を書く意味は半減する。
他人の論文を読むのは大変である。読んでくれただけでもありがたいことであり,それについて批判してくれることはもっとありがたいことである。批判を快く受け入れ,その意見に耳を傾け,自分の文章をよりよくする努力を重ねる人のみが,学習者の前に立ちはだかる高くて厚い学問の壁を越えることができるのである。
ところで,法律の基礎とか,「法の精神」とかいわれるものは,教えてもらって習得できるようなものではない。一方では,法律の個々の条文から始めて,条文全体の意味を体系的に理解するとともに,他方では,事例から始めて,どのような事例に,どの条文が適用されるべきかを学ぶ過程で,自ら発見するものである。
法律の意味を理解するためには,教科書,注釈書を丹念に読むと同時に,体系的な理解を深めるために,講義を聴講するのが有効である。また,特定の事例について,どの条文が適用されるべきかが適切に判断できるようになるためには,志を同じくするものが,励ましあい,よい指導者のアドバイスを受けながら,判例研究をするのが有効である。
「学問に王道なし」といわれるが,法律学についても同様である。地道な事例研究とそれを通じたルールの再発見へと至るしか,法律をマスターする道はないのである。