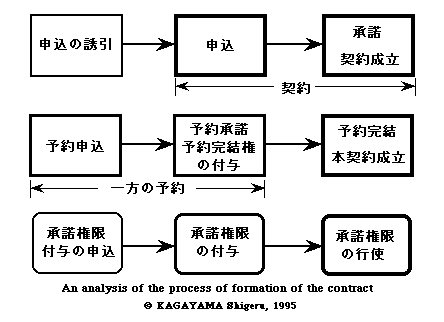
1996年12月5日
名古屋大学法学部教授 加賀山 茂
契約の成立は、「申込の意思表示」と「承諾の意思表示」によって成立する。従来の考え方によれば、申込の意思表示と承諾の意思表示を等質のものとし、申込と承諾の性質を捨象した「意思表示の合致」によって契約が成立すると言い換えることを許してきた。
しかし、現実には、申込の意思表示と承諾の意思表示は等質なものではなく、承諾をする者のみが、契約締結のキャスティング・ボートを握っている。
このような契約締結のキャスティング・ボートという観点から見ると、「予約する」ことと、「申込の誘引に基づいて申込をする」こととは、従来の考え方によれば、全く異なるもののように思われてきたが、実態は同じである。
申込の誘引から契約締結に至るプロセスと、予約から本契約の締結に至るプロセスを統一的に説明するためには、申込を「契約締結権限の付与」と位置付け、承諾を「契約締結権限の行使」と考えることが有効であることを論証する。
法律時報68巻10号(1996)76-80頁に掲載されたものに参考文献等を加筆したもの
「予約」の実質的な意味は、契約交渉において、当事者の一方(予約権者)が、契約締結に関してキャスティング・ボート(casting
vote)を持つという点にある。
もっとも、その点に関する限りでは、本契約においても、被申込者(承諾者)は、契約成立に関するキャスティング・ボートを握っている。英米法において、申込が「承諾権限(power
of acceptance)」の付与行為と考えられているのは、この理由に基づく。
両者の相違点は、予約の場合、権利主体である予約権者が、予約および本契約の締結に向けて、積極的に行動できるのに対して、承諾の場合には、承諾権者としての被申込者は、あくまで消極的な立場にあり、申込をしてもらわない限り、何の権限も生じないという点にある。
そこで、被申込者が積極的に行動しつつ、かつ、キャスティング・ボートを握れる仕組として、「申込の誘引(invitation
to make offers)」という概念が登場する。
申込の誘引をする者は、相手方に申込をするように誘導し、自らは、被申込者に納まることによって、キャスティング・ボートを維持しうる。
このように、契約締結のキャスティング・ボートという観点から見ると、「予約する」ことと、「申込の誘引に基づいて申込をする」こととは、実態は同じであり、「申込の誘引」という用語は、不特定多数を対象とするというイメージが強いため、事業者が主体となる場合に多く用いられ、消費者が主体となる場合には、「予約」という用語が多く用いられるという、用語法の問題に還元できるのではないだろうか。
ここでは、「予約する」ことと「申込の誘引によって申込をする」こととは、同じ概念の異なる用語法であるとの仮設を立て、それを検証することにする。
契約の一般的なイメージは、対等な契約当事者が、例えば、「売りましょう」「買いましょう」という意思表示の合致をみることによって成立するものとして描かれている。
ここにおいては、契約の成立要件に関して「『売りましょう』『買いましょう』」と「『買いましょう』『売りましょう』」との間に存在する申込と承諾の順序の区別は意識されていない。
つまり、契約の成立は、申込に対する承諾の発生というよりは、より観念的な意思表示の合致という概念で捕えられている。その点で、契約の一般的なイメージとしては、申込と承諾の間に等質性と相互性(reciprocity)が保持されているといえよう。
しかしながら、現実においては、申込と承諾は等価ではない。申込をする者と承諾をする者とでは、決定的な違いがあり、承諾をする者が有利な立場に立っている。なぜなら、申込に対して承諾をする方がキャスティング・ボートを持っているからである。
高額商品の消費者取引において、事業者が、自分の側からは決して申し込まず、消費者側から申し込ませて、信用調査の後に事業者の方から承諾をするという方式をとるのは、事業者が、申込と承諾の非相互性を熟知しているからである。
弱くみえる女性が、結婚において女性優位を保ちうる秘密の一つは、男性に申し込ませて、女性が承諾するという、スタート時点での女性優位の伝統にあるのかもしれない。
契約締結交渉において、当事者の関心事の一つは、契約締結のキャスティング・ボートをどちらが握るかであろう。
相手方が契約の申込をしてくれて、自らが承諾をできるのであれば、問題はない。しかし、現実の取引社会においては、申込をしてくれるまで気長にじっと待っているというわけにはいかない。
例えば、事業者は、顧客に対して受け身の立場に立っていたのでは、業績を伸ばすことはできない。つまり、事業者は、顧客の申込を辛抱強く待ち、承諾の側に回るという戦略をとることはできない。
そうかといって、顧客に対してうっかり申込をしてしまうと、信用のない顧客と取引をしなければならなくなるなど、危険が大きくなる。
そこで、事業者は、不特定多数の顧客に対して申込の誘引をして、多くの顧客に申込をさせ、その上で、優良な顧客を選別するという戦略をとることになる。
このような、積極的なアプローチと最終的な承諾者の立場を両立させるための戦略が「申込の誘引」にほかならない。
したがって、不特定多数の顧客に対する広告媒体を持ち、申込の誘引を積極的にするめることのできる事業者にとって「予約」なる概念は無用である。
予約の現代的意義は、予約をすることによって、本来、申込者の立場にある者が、予約完結権を取得することによって、立場を逆転させ、本契約の承諾者と同様にキャスティング・ボートを握ることにある。
不特定多数に対して申込の誘引をするという、広告媒体を持たない一般消費者が、能動的に行動し、かつ、承諾者と同様のキャスティング・ボートを握ろうと思えば、予約をするほかないであろう。
ところで、来栖三郎『契約法』(1974年)有斐閣22頁以下によれば、現代における予約の機能は以下のように限定されたものとなっているという。
本稿でも、来栖説に従い、予約とは、特に断わらない限り、一方の予約を意味するものとする。
本契約の締結を強制しうる約諾としての『売買の予約』という観念は、契約が要物契約としてのみ認められた時期から、契約方式自由の原則が認められ、売買も諾成契約として両当事者の合意のみによって有効に成立すると認められるに至る転換期の一産物だと思われる。
しかし、契約方式自由の原則が確立し、端的に売買を諾成契約と認めるようになると、売買の本体は両当事者の意思の合致にあり、目的物の譲渡と代金の支払に先立つ売ろう買おうという約諾こそ売買の予約でなく売買そのもので、目的物の譲渡と代金の支払は単なるその履行にすぎなくなる。そして、その上に、もう一つ売ろう買おうといいう約諾は、もはや存在しない。従って、売買を諾成契約と認めるなら売買の予約なる制度を必要としないのである。
ただ、諾成契約としての売買に予約が必要とすれば、それは当事者の一方のみが本契約締結の権利をもち、他の一方が本契約締結の義務を負う場合である。そしてその場合に当事者の一方が売買契約の締結を請求し、他の一方が応諾の意思表示をするか応諾の意思表示に代わる判決があってはじめて売買契約が成立するとするのは、売買のような諾成契約については無用の手数に過ぎないので、予約権利者たる一方が売買を完結せんとする意思を表示したときは、さらに予約義務者としての他の一方の意思表示を俟たずに売買契約が成立するものとするのが自然であろう。かくて売買が諾成契約となると予約は当事者の一方に完結権を与え、その完結権の行使によって本契約を成立しめうるものとしての意義をもつようになるのである。これが民法556条にいわゆる売買の一方の予約である。
予約は、婚姻予約に代表されるように、契約成立前の当事者の不当な行為を、予約における債務不履行と根拠づけることによって損害賠償を導き出す手段として使われてきた。
しかし、この機能は、契約締結上の過失理論等の、契約交渉段階の責任を予約理論を借りることなく追及できる法理が発達するに連れて、弱まってきている。
ただし、申込の誘引と申込の代替機能の他に、予約は、仮登記の原因となることが認められている。
この機能は、再売買の予約、代物弁済の予約などとして、実務に定着している。
このように考えると、予約は、申込の誘引による申込の代替機能、および、担保権の創設に不可欠の仮登記原因を創設する機能等の役割をもっており、この機能が申込によって代替される可能性がないい以上、予約が現代的役割を終えることはないと思われる。
「予約」と「申込の誘引による申込の受理」は同一現象の異なる見方であり、その実態は、承諾権限の付与手続に過ぎない。
このことを図示すると以下のようになる。
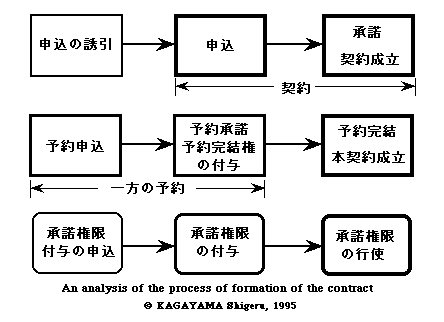
わが国の通説は、売買一方の予約をもって停止条件つき売買として把握してきた。つまり、売買の一方の予約というのは、実は真の意味での予約ではなく、予約完結権の行使を停止条件とする売買本契約であり、したがって、予約の時点で売買契約は成立するが、未だその効力を生ぜず、予約完結権の行使により条件が成熟してはじめて売買は完全に効力を生ずると考えている(柚木馨・生熊長幸「売買の予約」柚木馨・高木多喜男『新版注釈民法(14)債権(5)贈与・売買・交換』有斐閣(1993年)154頁。)。
しかし、一方の予約は、上の図からも明らかなように、本契約における申込の段階にとどまるものであって、予約の段階では、本契約は成立していない。もしも、「一方の予約をもって、停止条件つき売買が成立している」というのであれば、「申込もって、相手方の承諾を停止条件とする売買契約が成立している」ということも認めなければならなくなってしまう。
これまでの考察を通じて、「申込の誘引」と「予約の申し入れ」とは同一レベルにあること、そして、「申込」と「予約完結権の付与」とは同一レベルにあること、さらに、「承諾」と「予約完結権の行使」とは同一レベルにあることが明らかとなった。
申込は「権限の付与」であり、承諾は「権限の行使」であるという考え方は、実は、英米法においては伝統的な考え方である。
英米法においては、コービン教授によって、申込とは、「一方当事者の行為で、相手方に対して契約とよばれる権利義務関係を創設する法的権能(legal
power)を与えるものをいう」(樋口範雄『アメリカ契約法』弘文堂(1994年)110頁。)と定義され、承諾とは、「申込によって与えられた権能を被申込者が行使し、それによって契約とよばれる法律関係を創設する被申込者の自発的行為をいう」(樋口『アメリカ契約法』119頁)と定義されている。
申込と承諾に関する以上の定義は、申込と承諾の本質的な差異を正確に把握している点、および、「申込の誘引と申込」と「予約」のメカニズムを承諾権限の付与という一つの観点によって統一的に説明できる点で、契約を等質的な意思表示の合致によって説明しようとする従来のわが国の説よりも実際の取引実態に適合していると思われる。
英米法の考え方をどのように評価するかについては、さまざまな議論が予想されるが、いずれにせよ、申込を「契約締結権限の付与」、承諾を「契約締結権限の行使」と位置付けることにより、申込の誘引から契約に至るプロセスと、一方の予約から本契約に至るプロセスを、統一的に説明することが可能になることは疑いがない。
ホテルの予約については、それが予約であるのか、本契約であるのかについて争いがある。
通説は、日常用語としては「予約」という用語が用いられているが、法律的には「本契約」に他ならないとする(小川幸士「予約の機能としては、どのような場合が考えられ、何を問題とす
べきか」『講座 現代契約と現代債権の展望(5)−契約の一般 的課題』(1990)84頁は、ホテルの予約は、「説明するまでもなく『本契約』である」と断定している。)。
これに対して、須永説(須永醇「ホテル・旅館宿泊契約」『契約法大系VI』有斐閣(1963年)195頁)は、ホテルの予約は、文字どおりの予約であるとし、この予約を客は自由に破棄できるが、ホテルは客の予約完結権に応じなければならない予約だから、当事者の一方の予約であるととしている。
従来の説は、通説が一方の予約を停止条件つき本契約であると解していることに影響されたためか、予約と本契約との区別の判断基準を明確にしないままに議論をしており、議論が噛み合っていないように思われる。
ここでは、ホテル客とホテルのいずれが、契約締結のキャスティング・ボートを握っているかという観点から、ホテル客の申込とホテルの承諾が、予約の申込と承諾なのか、本契約の申込の誘引とサービス提供の申込なのか、それとも、本契約の申込と承諾なのかを論じたいと思う。
ホテルを予約する場合に、消費者は、自らがキャスティング・ボートを持っていると考えて行動していると思われる。少なくとも筆者はそう考えて行動している。
筆者は、出張で東京に行くことが多い。したがって頻繁にホテルの予約を行っている。最近では、東京のホテルの利用者が多く、特に週末にかかる場合には、よほど前に予約をしておかないと行きつけのホテルを予約することが困難になっている。そこで、いきおい、何件ものホテルに予約を入れて、空室を確認し、その中で、最も安くて設備とサービスの良いところを選ぶようにしている。
このように考えると、ホテルの予約については、拘束を受けるのは、ホテル側のみであり、消費者は団体客等の特別の場合を除いて、拘束を受けていない。
したがって、ホテルの予約は、本契約の申込ではなく、予約の申込か、本契約の申込の誘引かのいずれかであると考えなければならない。
ホテルの予約は、本質的には、本契約の申込の誘引と同じことであるが、「ホテルの予約」を「ホテル宿泊契約の申込の誘引」といわないのは、一般消費者は、不特定多数に対する申し入れをするための媒体をもたず各個撃破的に契約交渉をするという、伝統的な契約技術を使うより方法がないからである。
事業者は、自らが契約締結交渉のキャスティング・ボートを握るために約款を作成する。したがって、その約款には、自らにとって都合の良い契約形態が選択されるのは自然の成り行きである。
したがって、事業者が、約款において、相手方に申込をさせ、自らは承諾者の立場に立つことを宣言するのは当然のことといえよう。
実際のホテル宿泊標準約款によれば、契約しようとする者は、一定の事項について申し出をしなければならず、宿泊契約は、「当ホテル(館)が前条の申込みを承諾したときに成立する」と規定している。したがって、顧客によるキャンセルは、予約のキャンセルではなく、本契約の解除であり、前日の解除の場合は、基本宿泊料の20%、当日の解除の場合は80%、解除なしの不泊の場合は、100%の違約金を申し受けることが規定されている(甲斐道太郎・清水誠他編『消費者取引六法』(1991年)786頁)。
従来の学説は、このようなホテルや旅館の約款や資料を基に契約の構成をしてきたために、ホテルの予約は「予約ではなく、本契約である」と主張する向きが多いように思われる。
しかしながら、この考え方は、事業者の方から、積極的に契約交渉を行う、団体目当ての契約には妥当するが、一般消費者の側から積極的に契約のアプローチをする場合の法律構成としては、消費者の立場を無視しており、妥当ではないと思われる。
現実には、ホテルの標準契約約款が厳格に適用されることはなく、一般客が前日にキャンセルをしたからといって、20%の違約金をとるという慣行はないように思われる。筆者は、当日のキャンセルの場合には、常に違約金の支払の必要性を確認するのであるが、これまで、80%の違約金はおろか、違約金が必要だと応えたホテルに行き当たったことがない。
ホテル宿泊契約標準約款においても、「当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします」と規定しており、実際のところは、一般客については、特別の事情のない限り、違約金なしにキャンセルを自由に認めるというのが、ホテル宿泊契約に関する慣行として定着しているように思われる。
したがって、ホテルの予約は、文字どおりホテル宿泊契約の予約であり、ホテルのレセプションにおける顧客の予約完結権の行使によって本契約が成立すると考える方が実態に即している。
このように考えると、これまで、「予約といわれているものも、よく調べて見ると、本契約である」といわれてきたものについても、約款や事業者の言い分のみを調査するのではなく、消費者の言い分や苦情処理の実態を詳しく分析して見ると、「本契約といわれてきたものが、実は文字どおり予約であった」という場合が、ホテルの予約以外に発見できるかもしれない。
学生の就職活動における採用内定が、労働契約の締結なのか、採用内定契約(見習社員契約)という無名契約の締結であるかについて争いがある。また、ここで問題となるその交渉経過の法律構成については、以下の2つの考え方が対立している。
第1は、社員公募を見習社員契約の「申込みの誘引」、これに対する受験申込みは契約の「申込」、受験者に対する書面による採用通知は申込みに対する「承諾」とみる見解であつて、これらの一連の行為により、契約の効力発生の日を将来の確定日とする見習社員契約が締結されるとするものである(大阪高判昭48・10・29判時722号25頁)。
第2は、採用通知による契約の申込みと応募者の承諾により、健康診断の結果に異常があることを解除条件とする始期付見習社員契約が成立するとするものである(大阪地判昭46・8・16判時643号9頁)。
この見解は、採用通知を承諾ではなく、申込としている点で、第1の見解と異なる。
しかし、採用通知を申込としている点に多少無理があるので、法律構成を少し変更して、応募者による受験申込を労働契約の「予約の申込」、受験者に対する採用通知を「労働契約の予約に対する承諾」、応募者の採用通知後の諸行為を「予約完結権の行使」とみると、応募者の採用通知後の諸行為により、健康診断の結果に異常があることを解除条件とする始期付見習社員契約が成立したという同一の結果を導くことができる。
問題は、申込の誘引説のように、採用試験の受験申込みを契約の「申込」と考えることが可能かどうかである。
受験者は、受験の放棄を始めとする応募の撤回の自由を有し、それ自体に何らの拘束力をも課していない(大阪地判昭46・8・16判時643号9頁、11頁)ことを考えるならば、受験申込は、労働契約の予約の申込と考える方が妥当であると思われる。
契約の成立は、「申込の意思表示」と「承諾の意思表示」によって成立する。従来の考え方によれば、申込の意思表示と承諾の意思表示を等質のものとし、申込と承諾の性質を捨象した「意思表示の合致」によって契約が成立すると言い換えることを許してきた。しかし、現実には、申込の意思表示と承諾の意思表示は等質なものではなく、承諾をする者のみが、契約締結のキャスティング・ボートを握っている。
このような契約締結のキャスティング・ボートという観点から見ると、「予約する」ことと、「申込の誘引に基づいて申込をする」こととは、従来の考え方によれば、全く異なるもののように思われてきたが、実態は同じである。
従来の通説は、一方の予約を、予約完結権の行使を停止条件とする本契約の締結であると説明してきたが、予約は、申込の誘引による申込の段階にとどまるものであって、本契約ではありえない。一方の予約をもって停止条件つき本契約の締結というのであれば、申込によって、承諾を停止条件とする契約が成立しているとまでいわなければならないであろう。
「予約」と「申込の誘引による申込」という等価な問題について、実態が同じにもかかわらず、用語法が区別されている要因としては、「申込の誘引」は不特定多数を対象とするために広告媒体を持つ事業者によく用いられ、そのような媒体を持たない消費者が主体となる場合には「予約」が多く用いられるからであることを論証した。
さらに、申込の誘引から契約締結に至るプロセスと、予約から本契約の締結に至るプロセスを統一的に説明するためには、申込を「契約締結権限の付与」と位置付け、承諾を「契約締結権限の行使」と考えることが有効であることを論証した。
予約は、諾成契約の発展にともなって役割の低下を来しているが、申込の誘引という方法を利用できない消費者にとって、また、仮登記を利用する取引実務にとっては不可欠の存在であり、予約の本質的な機能としては、「申込の誘引による申込」の代替機能を果たすものに過ぎないとしても、現代的役割を失っているわけではない。したがって、予約と申込の誘引は実務的には併存しつつ発展していくものと思われる。
国連動産売買条約 第14条【申込の要件−申込の誘引との区別】
(1) 一または複数の特定のものに向けられた契約締結の申入れは、その内容が十分に確定しており、かつ、承諾があった場合には拘束されるとの申し込み者の意思が示されている時は、申込とする。申入れは、商品を示し、かつ、明示または黙示によりその数量および代金を定めまたはこれを決定する条項を含む場合には、内容が十分に確定しているものとする。
(2) 一または複数の特定の者に向けられたもの以外の申入れは、申込の単なる誘引とみなす。但し、申入れをした者が反対の意思を明確に示している場合は、この限りでない。
国連動産売買条約 第55条【代金決定条項を欠く場合の代金額の解釈】
契約が有効に締結されているが、代金が、明示もしくは黙示によっても定めるための条項を欠いている場合は、別段の事情がない限り、当事者は、契約締結当時に当該取引と対比しうる状況の下で売買されていた同種商品につき一般に請求されていた価格に、暗黙の言及をしているものとみなす。