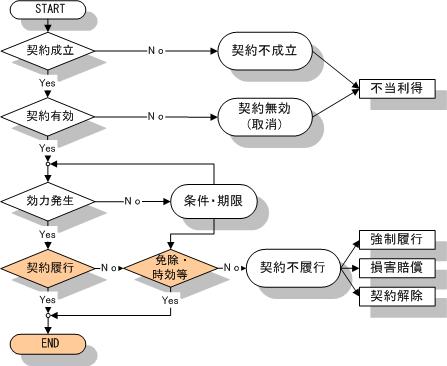 |
[契約法講義の目次]へ
作成:2006年9月18日
明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂
この講義では,債権の目的が達成されないまま債務が消滅するものとして,債権者の意思によって債務者が免責される免除と,一定期間の無催告状態の継続によって債務が消滅するという消滅時効の制度について概観する。
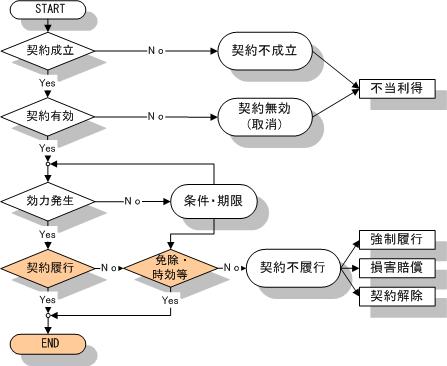 |
債権者が,債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させることを免除という(民法519条)。債務の免除は,債権の放棄と同じである。免除は,債権総則で規定されている免除以外の債権の消滅原因である弁済,相殺,更改とは異なり,対価又は代償を得ることなく債務を消滅させる点に特色がある。
わが国の民法においては,免除は単独行為として規定されているので,債務者の意思を問わずに債権者が自由にすることができる。しかし,多くの立法例は,免除を契約として規定し(フランス民法1285条,1287条,ドイツ民法397条,スイス債務法115条など),義務者の意思に反して債権を放棄することはできないとしている。わが国の民法においても,免除によって第三者を害することは許されないと解さなければならない(大判大11・11・24民集1巻738頁)。例えば,賃借地上の建物につき抵当権をもつ者があれば,借地人が賃借権を放棄しても抵当権者に対抗できないとされている(民法398条の類推:上記大判大11・11・24民集1巻738頁,大判大14・7・18新聞2463号14頁参照)。
第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)
地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は,その権利を放棄しても,これをもって抵当権者に対抗することができない。
大判大11・11・24民集1巻738頁(家屋取払並損害賠償請求事件)
借地上の建物に対し抵当権を設定した借地権者が借地権を放棄しても,その放棄は建物抵当権者及び建物競落人に対抗しえない。
大判大14・7・18新聞2463号14頁(家屋取除請求事件)
借地人が借地上に建設した建物に抵当権を設定した後土地所有者と合意し土地の賃貸借契約を解除しても,賃貸借の終了をもつて抵当権者に対抗することができない。
時効とは,一定の事実状態が一定期間継続した場合に,それが真実の権利状態と一致するか否かを問わずに,その事実状態に即した権利関係が発生したもの,または,消滅したものとする制度である。時効には,権利行使の外形である占有・準占有を一定期間継続することによって所有権・その他の財産権を取得する取得時効と,権利不行使の状態が一定期間継続することによって債権その他の財産権が消滅するとされる消滅時効とがある。
本書では,契約に焦点を当てて問題を論じているため,契約上の債務の消滅と関連する消滅時効については取り上げるが,所有権を中心とした取得時効の問題については取り上げない。もっとも,わが国の民法典は,取得時効と消滅時効とは,同じ時効という名の下に民法総則の第7章において統一的に取り扱っており,2つの時効制度に共通の問題として,時効の遡及効,援用・放棄,時効の中断・停止をまとめて規定していることは,世界の法制と比較しても特色を有している。したがって,本書でも,2つの時効制度に共通する問題である時効の遡及効,援用・放棄,時効の中断・停止については,これを取り上げることにする。
時効は,一見すると,泥棒を含めて所有者でない者が所有権を取得したり,債務を踏み倒した者を含めて未だ弁済していない者が債務を免れることを認めたりという,法律のイメージとはかけ離れた不道徳な制度に見える。そこで,時効はいかなる存在理由をもつのかが大いに議論されてきた。時効制度の存在理由としては,以下の3つの理由が挙げられてきた。
表19-1 時効制度の存在理由
| 時効を援用する側 (権利保護的側面) |
長期間続いた事実関係に対する信頼保護の要請 | 取得時効 | 長期の自主占有状態から生じる本権への連動の期待 |
| 消滅時効 | 長期の無催告状態による,債務は免除されたものとの期待 | ||
| 証明困難の救済 | 取得時効 | 所有権の証明(悪魔の証明)は困難 | |
| 消滅時効 | 弁済の証明のため,領収書を一生保管することは困難 | ||
| 時効を援用される側 (権利喪失的側面) |
権利の上に眠る者を保護せず | 取得時効 | - |
| 消滅時効 | 長期の債権不行使は,相手方に免除等の信頼を付与する |
時効の完成による債権の消滅は,債務者が証明しなければならない。証明の方法は,返還された債権証書や弁済の証明書としての領収書(受取証書)によることが多く,民法も弁済者に受取証書の交付請求権(民法486条),債権証書返還請求権(民法487条)を認めている。
弁済の証明責任は弁済者にあるため,受取証書(領収書)がないと,弁済者は再度弁済を余儀なくされるおそれがある。したがって,弁済者は,消滅時効の制度がないと,領収書を死ぬまで,また,死んでからも,相続人はそれを永久に保管しなければならないことになってしまう(梅・民法要義1(1986)311頁)。反対から言うと,消滅時効の制度は,領収書の保管限度を画するものとしての意味をもっている。つまり,真の弁済者は,消滅時効制度の下でのみ,消滅時効を経過した債権について,安心して領収書を破棄できるのである。この場合においても,副作用として,弁済もしないのに債務を免れる者が出てくるのは避けられない。したがって,この場合も,取得時効の場合と同様,明白な証拠がある等の特段の事情がある場合には,時効利益の援用が信義則に反するとして認めないことも必要となろう(最三判昭51・5・25民集30巻4号554頁(民法判例百選I[第4版]2事件)参照)。
また,債務の弁済の請求がないままに長期間を経過すると,債務者は,弁済が免除されたのかという期待が大きくなる。証明の窮乏から弁済者を保護すると同時に,長年にわたる権利の不行使の結果として生じる債務者の債務免除の期待に応えるのが消滅時効の制度の存在理由である。取得時効の場合と同様,
民法は,一方で,一定の事実状態が一定期間継続して時効が完成すると所有権等を「取得する」(民法162条),または,債権等は「消滅する」(167条など)とするが,他方で,時効が完成しても当事者がこれを援用しないと裁判所は「これによって裁判をすることができない」と規定している(民法145条)。
この規定に関して,学説では,(A) 時効の完成によって確定的に権利の得喪が生じるのか(確定効果説),それとも,(B) 当事者の意思表示(援用,放棄)をまって,確定的に効果が生じるのか(不確定効果説)という2つの説が対立している。
不確定効果説の中では,(a) 時効の完成によって権利の得喪という効果が一応生じるが,時効の援用がないこと,または,時効の放棄がなされたことによって,時効の効果は生じなかったことになるとする説(解除条件説),(b) 時効の完成によって権利の得喪という効果は確定的には生じず,援用があったときに効果が確定的に生じ,時効の利益の放棄によって効果は生じないことに確定するとする説(停止条件説)が対立している。
停止条件説,解除条件説といっても,援用によって時効の効力は,その起算日に遡る(民法144条)のであり,また,時効の利益の放棄によって,時効の効力は初めに遡って効力を失う。民法が,停止条件,解除条件について,条件成就のときから効力を発生させたり,効力を失わせたりしている(民法127条)のとは異なる。そもそも,効力が遡る場合には,停止条件も解除条件もその効果は全く等しくなるのであって,停止条件説と解除条件説の学説の対立は,無意味である。問題は,むしろ,時効の効力がなぜ遡るのかを考えることが重要である。20年間の自主占有によって所有権を取得するという場合に,所有権の取得がなぜ,20年間の自主占有の継続の後ではなく,占有の開始の時点にまで遡るのか,10年間の債権の不行使によって債権が時効消滅するのに,なぜ,10年前に遡って債権が消滅するのかという問題を考えることが,重要である。
時効制度の本来の趣旨が,真の権利者を証明窮乏から保護することにあるということを考慮するならば,時効の効力が起算日に遡るという意味も,容易に理解できる。なぜなら,時効制度の本質を年月の経過による証明窮乏から真の権利者を保護するもの,すなわち,訴訟法における自由心証主義を一部変更するものとしての法定証拠の問題である。そうだとすると,この法定証拠は,権利変動の証拠ではなく,権利存否の証拠であるから,時効期間の経過後にはじめて権利を取得するのではなく,はじめから権利者であったということになるということが理解できる(余力のある者は,民法696条(和解の効力)と比較してみるとよい)。したがって,時効制度は,当事者の援用・放棄をまって,真の権利者の権利を正当化したり,または,権利のない者には権利を与え,もしくは,債務のある者には債務を免れさせたりするために,起算日に遡ってその効力が認められている特別の制度(旧民法では,時効は,権利の存否に関する法定証拠,すなわち,証拠法の問題として位置づけられていた)であると理解すべきであろう。
「債権」は,10年の消滅時効にかかり(民法167条1項),債権を除いた「所有権以外の財産権」は20年の消滅時効にかかる(民法167条2項)。これらの権利は,権利を行使しない(権利不行使)の状態が一定期間継続することにより消滅するとされる(民法167条)。
なお,民法は実体権である債権が時効によって消滅すると規定しているのであるが,時効によって消滅するのは,実体権が訴訟上現状変更的に主張される場合の現象形態である請求権であって,実体権たる債権そのものではないと解する説もある。さらには,時効は当事者が援用しなければ効力を生じないことをもって,債権そのものは消滅せず,当事者に債務の履行を拒絶できる抗弁権が発生するに過ぎないと考える説も存在する。
消滅時効は,権利を行使することができる時から進行する(民法166条1項)。「権利を行使することができる」とは,権利行使について,弁済期の未到来・停止条件の未成就などの法律上の障害がないことを意味する(最三判平6・2・22民集48巻2号441頁(民法判例百選I[第4版](1996年)46事件))。もっとも,債権について同時履行の抗弁権が付着している場合のように,債権者の行為(反対債務の履行等)によって除去できるものであるときには時効期間は進行するとされている。
普通の債権の消滅時効期間は,10年である(民法167条)。この原則は,民法または他の法令による特則がある場合を除き,すべての債権に適用される(重要な特則として,商行為により生じた債権の時効期間を5年とする商法522条がある)。
終身年金債権・扶養料債権のような,定期に一定の金銭その他の代替物の給付を求めることができる定期金債権(毎期に定期給付を請求する支分債権ではなく,支分債権を生ぜしめる基本債権)については,第1回の(支分権の)弁済期から20年,最後の弁済期から10年で時効が完成する(民法168条1項前段・後段)。
賃料債権・扶養料債権など,基本権である定期金債権から生ずる支分債権(いわゆる定期給付債権)のうち,支払の定期が1年以内のものは,5年で消滅時効が完成する(民法169条。ただし民法174条1項を参照)。
(i) 医師,助産師又は薬剤師の診療,助産又は調剤に関する債権,(ii) 工事の設計,施工又は監理を業とする者の工事に関する債権(起算点は工事終了の時),(iii) 弁護士・弁護士法人又は公証人が職務に関して受け取った書類に関する責任(起算点は前者について事件終了,後者について職務の執行の時)は,3年で時効が完成する(民法170,171条)。
(i) 弁護士・弁護士法人又は公証人の職務に関する債権(起算点は事件終了の時),(ii)生産者,卸売商人および小売商人が売却した産物および商品の代価債権,(iii) 自己の技能を用い,注文を受けて,物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権,(iv) 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育,衣食又は寄宿の代価について有する債権は,2年で時効が完成する(民法172,173条)。
(i) 月またはこれより短い期間をもって定めた使用人の給料債権,(ii) 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権,(iii) 運送賃債権,(iv) 旅館,料理店,飲食店,貸席又は娯楽場の宿泊料,飲食料,席料,入場料,消費物の代価又は立替金に係る債権,(v) 動産の損料,すなわち,短期の賃貸借に基づく賃料債権は,1年で時効が完成する(民法174条)。
ところで,実体法と訴訟法とを架橋するものとして,要件事実の考え方,および,要件事実教育の重要性が強調されている。要件事実教育とは,おおむね,以下のような教育をいう。
時効制度は,実体法と訴訟法とを架橋する制度でもあるので,この時効制度について,要件事実教育がどのような考え方をしているかを見てみることは非常に有用である。そして,消滅時効に関する要件事実教育の教科書等を見てみると,立証責任の分配法則にとらわれるあまり,実体法の要件を捻じ曲げるという,要件事実教育の負の部分が集約的に表現されていることがわかる。つまり,消滅時効に関する要件事実の考え方を検討してみるだけで,実体法の要件を再構成するという要件事実教育の意図が見事に破綻していることが明らかとなる。要件事実教育は,法科大学院の教育方法に取り入れるべきであるというのが,通説の考え方であるが,消滅時効に関する要件事実の理論(要件事実論)を検討するならば,要件事実論は,法科大学院の教育方法として採用することのできない,壮大な誤謬の体系であることを簡単に示すことができる。したがって,その点を少し詳しく見てみることにしよう。
立証責任は,本来は,実体法の要件に該当する事実について,さまざまな政策的な考慮に基づいて,原告と被告とに証明の負担を分配することによって明確となる問題である。ここで問題としている民法167条1項の消滅時効についていえば,「債権の10年間の不行使」が実体法の法律要件であり,「債権の消滅」が法律効果である。法律要件の内部の①債権の不行使,②10年間の経過という2つの法律要件要素のうち,第1の法律要件要素である「債権の不行使」については,否定的命題を証明するのは困難である等の理由から,原告に立証責任を負わせるのではなく,その「反対事実」である「債権の行使」の事実(債権の行使を主な内容とする民法147条に定められた時効の中断事由)について被告に立証責任が負わされている。そして,第2の法律要件要素である「10年間が経過していること」は,原則どおり,原告に立証責任が負わされている。
要件事実教育においては,このような素直な考え方はできない。要件事実論のバイブルともいえる司法研修所編集『民事訴訟における要件事実』第1巻(1985)9頁を見てみよう。
消滅時効については,民法147条以下に規定するような債権の行使が消滅時効の効果の発生障害の要件事実(時効の中断事由)であり,時効期間中の債権の不行使は時効消滅の要件事実とはならない。
それでは,要件事実論は,なぜ上記のような民法167条1項の条文の文言からかけ離れるような突飛な解釈をしなければならなくなっているのか。それは,要件事実論が前提としている要件事実はすべて原告が証明すべきであるという大前提があって,これをくつがえすことができないからである。しかし,債権の不行使ではなく,債権の行使に該当する中断事由について被告に立証責任を負わせるという結論を維持しなければならないとすると,民法167条1項の条文を無視して,「消滅時効の要件事実は,10年間の経過のみであり,債権の不行使については,時効の中断事由という抗弁である」とするほかないのである。しかし,そうすると,今度は理論の破綻が待ち構えている。なぜなら,債権の行使の反対事実である時効の中断事由を抗弁だというと,抗弁とは,原告の主張する債権の不行使とは別の事実でなければならないという本来の抗弁の定義との間に矛盾を生じることになるからである。
抗弁とは,民事訴訟において,原告の請求を排斥するため,被告が原告の権利主張・事実主張を単に否定・否認するのではなく,自らが証明責任を負う事実による別個の事項を主張すること。
時効が完成するためには,時効の基礎となる一定の事実状態が一定期間継続することを必要とするが,民法は,時効の進行中に裁判上の請求がなされるなど右の事実状態と相容れない一定の事由が発生した場合に,それまで経過した期間をご破算としている。これを時効の中断(取得時効について定められている一定状態(占有)の継続の中断,すなわち,自然中断との対比で,「法定中断」)という。
表19-2 時効の中断の要件
| 時効の中断事由 | 根拠条文 | |
|---|---|---|
| 請求 | 裁判上の請求 | 民法149条 |
| 支払命令の申立て | 民法150条 | |
| 和解のためにする呼出・任意出頭 | 民法151条 | |
| 破産手続参加 | 民法152条 | |
| 催告 | 民法153条 | |
| 差押え・仮差押え・仮処分 | 民法154条,民法155条 | |
| 承認 | 民法156条 | |
債権等の一定の権利について不行使の状態が一定期間継続することにより,その権利が消滅するというのが消滅時効の趣旨である。したがって,一定の期間の間に権利の行使があれば,時効が完成しないのは,当然である。
裁判上の請求,すなわち訴えを提起することは,時効の中断事由となる。中断の効力が生ずるのは,訴えを提起した時である(民事訴訟法235条)。もっとも,訴えが不適法として却下されたり,当事者により取り下げられたりした場合には中断の効力は生じない(民法149条)。
なお,裁判上の請求によって時効中断の効力が生じるのは,訴訟物(訴訟の対象)となった範囲に限られると解されているため,一部請求の場合には,残部については,時効中断の効果は及ばないとするのが判例の考え方である(最二判昭34・2・20民集13巻2号209頁(民法判例百選I[第4版](1996年)44事件))。
民事訴訟法430条以下に規定されている督促手続きによって,金銭その他の代替物または有価証券の一定数量の給付請求につき,債権者が支払命令を申し立てると,時効は中断する。中断の効力は,債務者に対する支払命令の送達があれば,申請の時に遡って生ずるというのが判例である。もっとも,支払命令送達の日から2週間以内に異議の申立てがなく仮執行宣言の申立てができるようになったにもかかわらず,債権者が法定の期間内に仮執行の申立てをなさないために支払命令が効力を失うと,時効中断の効力は生じなかったものとみなされる(民法150条)。
民事上の争いにおいて,普通裁判籍所在地の簡易裁判所に和解の申立てがなされ,当事者が呼び出され,和解が成立すると,和解の申立ての日に時効の中断が生ずる。しかし,相手方が出頭せず,あるいは和解が調わない場合には,1ヵ月以内に訴えを提起しなければ,中断の効力は生じない(民法151条)。当事者が和解のために任意出頭する場合にも和解が成立すれば,出頭の日に遡って中断の効力が生ずるものとしている。また,調停の申立ても同様に扱われている。
破産債権者が,裁判所の定める期間内に破産の配当に加入するための債権の届出(破産法228条)を行うと,この時に時効中断の効力が生ずる。ただし,債権者がこれを取り消し,あるいは請求が却下された場合には,中断効は生じない(民法152条)。破産宣告の申立て,民事訴訟法によると配当要求なども同様に解されている。
権利者が時効利益を受けるべき相手方に対してなす催告すなわち裁判外の請求(催告には特別の方式はないが,内容・配達証明郵便でなされることが多い)も時効の中断事由とされている。
しかし,6ヵ月以内に裁判上の請求・差押えといった他の強力な中断事由となる手続きをとることによって中断の効力が生ずるとされているのであるから(民法153条),催告は,いわば正規の中断方法をとるまで6ヵ月,時間かせぎをするという機能を果たす暫定的な中断事由ということができる。催告による時効の中断効は,催告が相手方に到達した時に生ずる。催告の中断効は1回限りのものである。
訴えが提起されたが取り下げられもしくは却下された場合,あるいは裁判上の請求に準ずるとはみられない場合などについて,権利の主張が継続する間,催告の効力すなわち暫定的な中断効を認めてよいのではないかとされている(いわゆる裁判上の催告)。この場合には,6ヵ月の延長期間は(最初の権利主張があった時ではなくて),権利主張の最終の時点,すなわち,取下げ・却下があった時あるいは当該訴訟の終結の時から起算されると解されている(最一判昭45・9・10民集24巻10号1389頁,最大判昭38・10・30民集17巻9号1252など)。
時効は,権利の現実的実行行為である差押え・仮差押え・仮処分によっても中断する(民法147条2号)。差押えとは,確定判決その他の債務名義(民事執行法22条)に基づいてなされる強制執行手続きの第一段階で執行機関が執行の目的物について執行債務者の処分権を制限する行為であって,執行官の占有,執行裁判所の差押命令・競売開始決定などによっておこなわれる(民事執行法122条1項・143・145条1項ほか)。担保権の実行としての競売も差押えに準じて中断効が認められる。
仮差押え・仮処分は,権利者が債務名義を得ていない段階で,強制執行もしくは権利の実現が不能もしくは著しく困難になるおそれがある場合に,これを保全するための手続きである(民事保全法20・23条)。差押え・仮差押え・仮処分が中断効を生ずるのは申立ての時であると解される。
差押え・仮差押え・仮処分は,権利者の請求によりあるいは法律の定めに従わなかったことにより取り消されたときは,時効中断の効力は生じないものとされる(民法154条)。また,これらは,物上保証人に対して差押えがなされた場合のように,義務者以外の第三者に対してなされたときは,権利者が義務者にこれを通知した後でなければ時効中断の効力は生じないものとされる(民法155条)。
時効は,時効の利益を受けるべき者が時効によって権利を失うことになる者に対してその権利の存在を認める旨を表示する観念の通知,すなわち承認によっても中断する。 承認には特別の方式を必要としない。具体的には,支払延期の懇請,債務の一部弁済(債務全部についての承認となる),利息の支払(元本債務についての承認となる),担保の提供などが承認とみられる。
承認をするには,時効利益を受ける者が相手方の権利につき処分の能力・権限のあることを必要としない(民法156条)。したがって,被保佐人でも保佐人の同意なく承認できる。しかし,管理の能力・権限は必要とするから,未成年者が承認をなすには,法定代理人の同意を要すると解されている。
時効の中断事由が生ずると,その効果として,時効の完成は阻止され,それまで経過してきた期間は無意味となる。
時効中断の効果は,原則として,当事者とその承継人(包括承継人,特定承継人)との間においてだけ生ずる(民法148条)。これを,時効中断の効力の相対的効力と呼ぶ。したがって,たとえば2人が共有する土地につきある者が占有している場合に,共有者の1人が占有者に対して時効中断の措置をとっても,他の共有者にはその効力は及ばない(民法284条2項参照。ただし民法292条はその例外を定めている)。
この相対的効力の例外としては,連帯債務における請求の絶対効(民法434条),主たる債務者に対する時効中断の保証人に対する効力(民法457条)がある。なお,取得時効についての自然中断(占有の中断)は,その性質上,すべての人に対してその効力が及ぶ。
いったん中断効が生じても,時効の基礎となる占有・準占有あるいは権利不行使の状態があらためて生じ,または,継続すると,中断事由の終了時からあらためて時効が進行することとなる(民法157条1項)。
すなわち,裁判上の請求は裁判確定の時(民法157条2項),支払命令・和解の申立てなどは確定判決と同一の効力が生じた時,破産手続き参加は破産手続き終了の時,催告はその後補強的にとられた中断事由の終了の時,差押え等はその手続き終了の時(例えば,抵当権の実行の場合は競落代金受領の時,金銭債権に対する差押えの場合は転付命令の時),承認はそれが相手方に到達した時から,新たに時効が進行することとなり,所定の時効期間が経過すると時効が完成することとなる。
時効の完成間際に,天災・事変など時効の中断を著しく困難にする一定の事由が発生したり,そのような事由が存在したりするときは,時効によって不利益を被る者の保護のために,その事由の消滅後,一定期間が経過するまで時効の完成を猶予する(それまで経過した期間をご破算とするのではない)ことを認めている。これを時効の停止という。
時効は,当事者が援用しないと裁判所はこれによって裁判をすることができないものとされている。そこで,なぜ援用が必要とされているのか,援用することができるのはいかなる者かが問題となる。
時効には,当事者の援用が必要であるとしておくと,そのような衡平でない事態を当事者の自発的な判断で回避することが可能であるし,裁判所としても,そのような場合に時効を援用することは信義則に反して許されないとすることが,一般の権利・義務の関係の場合よりも容易になる(最三判昭51・5・25民集30巻4号554頁(民法判例百選I[第4版](1996年)2事件))。つまり,時効に援用が必要とされる理由は,裁判所が,特別の場合に,時効の援用を信義則に照らして許されないとする余地を残しておく点に存すると思われる。
民法145条は,時効の援用をなしうる者(いわゆる時効の援用権者)について,「当事者」としか規定していない。そこで,その範囲をどう定式化するか,個々の場合について具体的にどう考えたらよいのかが問題となる。
まず,判例は,「当事者」を「時効により直接に利益を受ける者」,すなわち取得時効により権利を取得しまたは消滅時効により権利の制限または義務を免れる者およびその承継人に限定してきた(直接受益者説(大判明43・1・25民録16輯22頁など))。具体的には,消滅時効にかかった債務についての連帯保証人,保証人などは当初より援用権者であるとされてきたが,反対に,抵当不動産の第三取得者,再売買の予約完結権の仮登記のある不動産の所有権を取得した者(大判昭9・5・2民集13巻670頁),物上保証人,表見相続人から相続財産を譲り受けた者(相続回復請求権の消滅時効),詐害行為の受益者などは,「間接に利益を受けるべき者」に過ぎないとして,時効の援用をなしうる者とは認められなかった。その理由は,時効によって直接利益を受ける者(例えば債務者)が時効を援用しないのに,時効によって間接に利益を受けるに過ぎない者(例えば物上保証人)に時効の援用が認められるならば,債権者は主たる債権を有しているにもかかわらず,従たる抵当権を失うというような不都合が生じるからであるとされてきた。
これに対し学説では,かつては判例を支持する説が有力であったが,最近では,むしろ「当事者」の範囲についての判例のような制限は狭過ぎると批判し,これを拡大すべきであるとしている。すなわち,「時効によって直接権利を取得し義務を免れる者のほか,この権利・義務に基づいて権利を取得し義務を免れる者(我妻栄『新訂民法総則』岩波書店(1965年)446頁)」は,時効の援用をなしうる者であるとしている。
こうした学説の影響を受けて,最近の判例は,「直接利益を受ける者」という従来の定式は維持しながらも,かつてに比べ「当事者」の範囲を拡大する傾向を示すようになっている。
具体的には,他人の債務のために自己所有物を譲渡担保に供した者(最二判昭42・10・27民集21巻8号2110頁),他人の債務のために自己所有の不動産に抵当権を設定した者(物上保証人)(最二判昭42・10・27民集21巻8号2110頁,最一判昭43・9・26民集22巻9号2002頁),抵当不動産の第三取得者(最二判昭48・12・14民集27巻11号1586頁),仮登記担保権付の不動産の第三取得者(最三判昭60・11・26民集39巻7号1701頁),売買予約に基づく仮登記のある不動産に関する予約完結権の消滅時効につき抵当権者(最三判平2・6・5民集44巻4号599頁)および第三取得者(最一判平4・3・19民集46巻3号222頁(民法判例百選I[第4版](1996年)42事件))を時効の援用権者として認めている。
ただし,判例による「直接の利益を受ける者」の解釈の範囲の拡大にも限度があり,最近の判例においても,後順位抵当権者に対しては,時効の援用権を認めていない(最一判平11・11・9民集53巻7号1190頁)。
もっとも,時効援用権の代位行使(民法423条)を認める判例もある(最一判昭43・9・26民集22巻9号2002頁(反対意見がある))。このため,後順位抵当権者による時効の援用権を制限したところで,後順位抵当権者が債権者として債務者の時効援用権を代位行使できるとすれば,そのような制限は,余り意味がないともいえよう。
なお,消滅時効の場合とは反対に,取得時効の援用については,判例は援用権者の範囲を制限する傾向にあり,係争土地を時効取得すべき者またはその承継人から右土地上の建物を賃借している者は,取得時効の援用をすることができないとしている(最三判昭44・7・15民集23巻8号1520頁)。
時効の利益は,あらかじめ放棄することはできない。事前の放棄を認めると,とくに消滅時効の場合に債権者が取引上の有利な立場を利用して債務者に放棄をさせるという不合理な結果を生ずるおそれがあるからである。
したがって,時効が完成した後における放棄は許される(民法146条の反対解釈)。時効完成後に債務者が任意に債務を弁済するというのがその典型例である。
これに対して,債務者が時効の完成を知らずに債務の承認や一部弁済をした場合には,債務者に時効利益を放棄するという意思が欠けている。しかし,すでに時効の存在理由の箇所で示したように,消滅時効の制度が,長期の無催告状態から生じる債務は免除されたとの債務者の期待の保護(信頼の保護)にあることを考慮するならば,時効完成の事実を知らずに,債務承認や一部弁済がなされた場合には,もはや,改めて時効を援用することはできないと解すべきであろう(時効援用利益の喪失)(最大判昭41・4・20民集20巻4号702頁(民法判例百選I[第4版](1996年)43事件))。
一定の財産権について一定の事実状態(権利不行使の事実状態)が一定期間継続することにより時効が完成し,かつ当事者が援用すると,時効の効果として,実体上の権利の消滅がはじめに遡って生ずることとなる。
時効の効力はその起算日に遡る(民法144条)。時効の効果を現実に主張することができるのは,いうまでもなく時効が完成した後においてであるが,時効による「権利の得喪」は起算日に遡って生じていたものと扱われるのである。
時効とよく似た制度に除斥期間(délai préfixe, Ausschlussfrist)という制度がある。
例えば,占有の訴えの提起期間(1年以内:民法201条),建築差止めの訴えの提起期間(1年以内:民法234条),売主の担保責任の期間(1年以内:民法564条,566条),請負人の担保責任の期間(1年以内:民法637条,638条2項,5年以内・10年以内:638条1項),婚姻の取消期間(3ヶ月以内:民法745条2項,746条,747条2項),離婚による財産分与に関する協議に代わる処分請求の期間(2年以内:民法768条2項),嫡出否認の訴えの提訴期間(1年以内:民法777条),認知の訴えの提訴期間(3年以内:民法787条),縁組の取消期間(6ヶ月以内:民法804条,806条,807条,808条),相続の承認・放棄の期間(3ヶ月以内:民法915条,924条)等,立法者が一定の権利について,その行使を迅速に行うことを特に望んで期間制限を課したものがこれに該当する。
これらの期間は,特に権利行使の迅速性が要請される権利の行使期間に限定されており,その期間は,1年以内のものが圧倒的に多く,最高で10年となっている。
このように,時効期間とは別に,訴えや責任追及の期間があらかじめ法律によって定められている場合について,立法者は,これらを予定期間(délai préfixe)と呼んでいた。権利行使に期間が予めフィックスされているという意味である(フランス民事訴訟法典122条は,現在でも,délai préfixeという用語法を用いている)。
この予定期間(除斥期間)については,民法の立法者は,以下のように述べて,予定期間(除斥期間)には,時効の中断,停止の規定は適用されないと考えていた。
「時効の規定を適用すべき場合には,殊に時効なる文字を用い,その他の場合は,予定期間(délai préfixe)と称して,これに時効の中断停止等の規定を適用せざるを妥当なりとす。」(広中俊雄『民法修正案(前三編)の理由書』有斐閣(1987)193頁。読みやすくするため,送りがなは筆者がひらがなに改めた。)
民法の起草委員の1人である梅謙次郎もその教科書において,「時効は之を予定期間(délai préfixe)と混ずべからず。…本法に於いては,時効は明かに其時効なることを示し他の法定期間は皆予定期間にして之に時効の規定を適用すべからず」と述べていた(梅謙次郎『民法要義・巻之一(総則編)』有斐閣(1896)312頁。送りがなは筆者がひらがなに改めた)。
除斥期間は,一定の権利行使について,法的安定性を確保するために,権利行使の期間を予め一定期間に定めたものであり,権利行使期間を延長することとなる時効の中断,停止の規定は適用されない。
民法の定める権利の期間制限が消滅時効と除斥期間(予定期間)のいずれかであるかを定める基準は,立法理由に従って,「時効ニ因リテ」という明文があるかどうかに求められていた。判例も,原則として,この基準に従っているといわれてきた。
しかし,その後,学説では,権利の性質と規定の趣旨によって実質的に判断すべきことが主張されるに至り,現在では,立法者が時効期間であると規定している場合においても,特に,ひとつの権利について長期と短期の期間制限が定められている場合(民法126条,724条)については,短期の期間制限は消滅時効であるが,長期の期間制限は除斥期間と解すべきであるという硬直的な区別の基準が有力に主張され,最高裁もこれに追随している(最一判平元・12・21民集43巻12号2209頁)。
しかし,この考え方は,権利の行使期間を不当に制限するものであって賛成できない。旧民法は,権利の期間制限につき,明文のないものは時効として扱うとしていた(旧民法証拠編92条)。確かに,現行民法はこの立場を逆転して,原則は除斥期間(予定期間)とするのであるが,時効期間とするという明文の規定がある権利については,時効中断・中止による権利行使の延長を認め,権利者の権利行使を特に保護しているのである。
したがって,民法が明文の規定で権利行使の期間延長を認めているものを,期間が2つ定めている場合には,長期の期間は除斥期間と解すべきであるという説は,立法趣旨に反するばかりか,権利行使を不当に制限するものであって賛成できない。民法126条,民法724条の20年の期間は十分に長いとも考えられるかもしれないが,ドイツの債務法改正においても,不法行為の30年の時効期間は保持されていることも考慮すべきであろう(ドイツ民法199条2項)。いずれにせよ,民法の立法者が明文で規定した20年の時効期間を除斥期間として実質的に短縮する理由はないと考える。
問題1 取得時効の存在理由を説明し,「権利の上に眠る者は保護せず」という考え方が通用するかどうか検討しなさい。
問題2 消滅時効の存在理由を説明し,「権利の上に眠る者は保護せず」という考え方が通用するかどうか検討しなさい。
問題3 「民法においては,たとえ泥棒でも,堂々と20年間占有を続ければその物の所有権を取得する(民法162条1項)と規定しているのであるから,刑法と異なり,民法は,泥棒の味方をしている。」という考え方を批判しなさい。
問題4 時効の効力が生じるためには援用が必要であることの意味を時効の援用に信義則が適用されるべきかどうかという問題と関連させて説明しなさい。
新司法試験プレテスト問題〔第6問〕
| AはBに対し,1,000万円を貸し付けた。その際,B所有の甲土地に抵当権を設定するとともに,Cがその債務を保証し,D所有の乙土地にも抵当権が設定された。甲土地はその後Eに売り渡され,乙土地にはDのFに対する債務のため次順位の抵当権が設定された。また,BはAからの借入れ後,Gからも500万円を借り受けた。BのAに対する債務が弁済期から10年を経過したとき,判例の趣旨に照らし,Bを除き,この債務の消滅時効を援用できるのはだれか。(解答欄は,[№6]) 1.C及びD 2.C,D及びE 3.C,D及びF 4.C,D,E及びF 5.C,D,E,F及びG |
〔解説〕
第145条(時効の援用)
時効は,当事者が援用しなければ,裁判所がこれによって裁判をすることができない。
大判大4・7・13民録21輯1387頁
民法145条にいわゆる当事者とは,主たる債務が時効によつて消滅した場合の保証人を包含するのであり,保証人は主債務の時効を援用することができる。
最二判昭42・10・27民集21巻8号2110頁 (大審院の判例の「時効により直接の利益を受ける者」の用語を受け継ぎつつ,その意味内容を変更した)
時効は当事者でなければこれを援用しえないことは,民法145条の規定により明らかであるが,右規定の趣旨は,消滅時効についていえば,時効を援用しうる者を権利の時効消滅により直接利益を受ける者に限定したものと解されるところ,他人の債務のために自己の所有物件につき質権または抵当権を設定したいわゆる物上保証人も被担保債権の消滅によつて直接利益を受ける者というを妨げないから,同条にいう当事者にあたるものと解するのが相当であり,これを見解を異にする大審院判例(明治43年1月25日大審院判決・民録16輯22頁)は変更すべきものである。
最一判昭43・9・26民集22巻9号2002頁
他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は,右債務の消滅時効を援用することができる。
最二判昭48・12・14民集27巻11号1586頁
抵当不動産の譲渡を受けた第三者は,抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
抵当権が設定され,かつその登記の存する不動産の譲渡を受けた第三者は,当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから,抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であり,これと見解を異にする大審院明治42年(オ)第379号同43年1月25日判決・民録16輯1巻22頁の判例は変更すべきものである。
最一判平11・11・9民集53巻7号1190頁
後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない。
先順位抵当権の被担保債権が消滅すると,後順位抵当権者の抵当権の順位が上昇し,これによって被担保債権に対する配当額が増加することがあり得るが,この配当額の増加に対する期待は,抵当権の順位の上昇によってもたらされる反射的な利益にすぎないというべきである。そうすると,後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく,先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないものと解するのが相当である。
ただし,代位行使は認められるという抜け道が残されている。
最一判昭43・9・26民集22巻9号2002頁
債権者は,自己の債権を保全するに必要な限度で,債務者に代位して,他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。(反対意見がある。)
判例は,民法145条の時効援用権者である「当事者」を制限的に解釈し,時効の援用によって直接の利益を受ける者に該当するとしている。そして,大審院は,「直接の利益を受ける者」には,物上保証人も第三取得者も含まれないとしていた。
しかし,最高裁は,大審院時代の判例を変更し,「直接の利益を受ける者」という用語を維持したまま,その内容を変更し,物上保証人も,抵当不動産の第三取得者,詐害行為の受益者も「直接の利益を受ける者」に含まれるとした。しかし,判例による消滅時効の援用権者の制限緩和もここまで。後順位抵当権者や債権者は,援用権者に含まれないという。
しかし,「直接の利益を受ける者」か「間接の(反射的な)利益を受ける者」という基準は,援用権者の範囲を確定するには,不明確である。最高裁自身が,大審院の用語法を使いつつ,内容を完全に変えてしまったのであるから,基準としては,ほとんど使い物にならないというのが実態であろう。
そこで,学生としては,最高裁の基準をすべてうまく説明できる新たなキーワードが必要となる。後順位抵当権者による時効援用を否定した最一判平11・11・9民集53巻7号1190頁の判例解説を読むと,そのような新しいキーワードの手がかりが得られると思われるので,各人でよく考えてみよう。
筆者は,「債務者,保証人,物上保証人のように,消滅時効の援用によって,自らの負担(債務,責任を含む)を免れる地位にある者をいう」という定義を考えている。参考になれば幸いである。
2006年度新司法試験問題・短答式〔第21問〕
続いて,次の問題を検討してみよう。
|
消滅時効に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものを2個選びなさい。(2006年度新司法試験問題・短答式問題〔第21問〕) 1. AのBに対する売買代金債権について時効期間が経過した後,Bが当該代金債務を承認した場合であっても,その債務を被担保債権とする抵当権を設定した物上保証人Cは,その債務について消滅時効を援用することができる。 2. AのBに対する債権について,連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときは,時効中断の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。 3. 商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて,債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは,当該債権の時効期間は10年となる。 4. 時効の完成後に,そのことに気付かないで債務を弁済した債務者は,債権者に対して,弁済金を不当利得として返還請求することができる。 5. AがBから土地を買い受け,所有権移転登記をしないまま20年が経過してから,AがBに対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合,Bは,その登記請求権の消滅時効を援用することができる。 |
消滅時効は,権利を行使することができる時,例えば債権では弁済期が到来した時から起算し(民法166条),一般の債権では10年(民法167条1項),商事の債権で5年(商法522条)である。定期給付の債権は5年(民法169条)とされているほか,種々の債権につき3年から1年の短期の時効期間が定められている(短期消滅時効)。債権又は所有権以外の財産権の消滅時効期間は20年である(民法167条2項)。なお,10年以下の時効期間の定められている権利も,その存在を認める確定判決があったときはその時効期間は10年になる(民法174条の2)。
1. AのBに対する売買代金債権について時効期間が経過した後,Bが当該代金債務を承認した場合であっても,その債務を被担保債権とする抵当権を設定した物上保証人Cは,その債務について消滅時効を援用することができる。
第1に,物上保証人は,時効消滅によって「直接利益を受ける者」に該当するとして消滅時効の援用をすることができる。
最一判昭43・9・26民集22巻9号2002頁
消滅時効を援用しうる者は,権利の時効消滅によって直接利益を受ける者に限られるが,他人の債務のために自己の所有物件につき抵当権を設定したいわゆる物上保証人もまた被担保債権の消滅によつて直接利益を受ける者というを妨げないから,民法145条にいう当事者として右物件によつて担保された他人の債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのを相当と〔する〕(当裁判所昭和39年(オ)第523号,第524号,同42年10月27日第二小法廷判決,民集21巻8号2110頁参照)
また,金銭債権の債権者は,その債務者が,他の債権者に対して負担する債務,または前記のように他人の債務のために物上保証人となつている場合にその被担保債権について,その消滅時効を援用しうる地位にあるのにこれを援用しないときは,債務者の資力が自己の債権の弁済を受けるについて十分でない事情にあるかぎり,その債権を保全するに必要な限度で,民法423条1項本文の規定により,債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することが許されるものと解するのが相当である。
第2に,時効完成後の債務者による債務承認は,時効利益の放棄と考えられている。そして,時効利益の放棄は,相対的であり,放棄を援用した者のみが援用権を失うとされている(大判大5・12・25民録22輯2494頁)。したがって,この選択肢は正しい。
大判大5・12・25民録22輯2494頁
時効の利益の放棄は放棄者その承継人以外の者に対しては効力を生じない(主債務者のした時効利益の放棄は,保証人に対してその効力を生じない)。
だだし,時効完成前の債務者による債務承認は,時効の中断事由にあたり,この場合には,物上保証人が,債務者による債務承認によって生じた時効中断の効力を否定することはできないとされている。
最二判平7・3・10判時1525号59頁
他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人が,債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは,担保権の付従性に抵触し,民法396条(抵当権の消滅時効)の趣旨にも反し,許されないものと解するのが相当である。
したがって,時効完成前の債務承認の効果(時効中断)と時効完成後の債務承認の効果(時効利益の放棄)との微妙な違いに注意が必要である。なお,時効中断の効力の範囲については,次の問題で触れる。
2. AのBに対する債権について,連帯保証人Cが時効期間の経過前にAに対して承認したときは,時効中断の効力は主債務者Bに対しても及ぶ。
時効中断の効力は,原則として,当事者およびその承継人にのみ及ぶ(民法148条)。
第148条(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
前条の規定による時効の中断は,その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ,その効力を有する。
例外的に,連帯債務者の1人に対する履行の請求は,他の連帯債務者に対しても,その効力が及ぶため(民法434条),債務者に対する時効中断の効力は,他の連帯債務者にも及ぶことになる。また,民法458条により,連帯保証人について生じた事由については,連帯債務の絶対効(民法434条~440条)の規定が準用されている。
しかし,連帯保証人による主債務の承認には,これらの絶対的効力の規定が準用されないため,時効中断の効力は,主債務者には及ばない。したがって,この選択肢は誤りである。
もっとも,債務承認ではないが,連帯債務者に対する請求による時効中断に関しては,時効中断の効力は,主たる債務者にも及ぶとした判例があるので,注意を要する。
最二判昭48・9・7判時718号48頁
手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において,連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは,手形債務についても消滅時効が中断すると解すべきである。けだし,連帯保証人に対する請求は,主たる債務者に対してもその効力を生ずる(民法458条,434条)から,連帯保証人に対する裁判上の請求は主たる債務につき消滅時効中断の効力を生ずるが,この理は,主たる債務が手形債務であるからといつて別異に解すべき理由がないからである(大審院昭和5年(オ)第1811号同6年1月29日法律新聞3230号15頁参照)。
3. 商行為によって生じた債権で履行遅滞になったものについて,債務者が分割弁済をする旨の民事調停が成立したときは,当該債権の時効期間は10年となる。
10年以下の時効期間の定められている権利も,その存在を認める確定判決(裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものを含む)があったときはその時効期間は10年になる。
商法 第522条(商事消滅時効)
商行為によって生じた債権は,この法律に別段の定めがある場合を除き,5年間行使しないときは,時効によって消滅する。ただし,他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは,その定めるところによる。
第174条の2(判決で確定した権利の消滅時効)
①確定判決によって確定した権利については,10年より短い時効期間の定めがあるものであっても,その時効期間は,10年とする。裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても,同様とする。
②前項の規定は,確定の時に弁済期の到来していない債権については,適用しない。
4. 時効の完成後に,そのことに気付かないで債務を弁済した債務者は,債権者に対して,弁済金を不当利得として返還請求することができる。
消滅時効にかかった債務は自然債務といわれる。自然債務とは,債務者が任意に履行すれば有効な弁済となり,債務者は給付したものを不当利得として債権者から取り戻すことはできないが,債権者のほうから裁判所に訴えて履行を求めることができない債務のことである。
5. AがBから土地を買い受け,所有権移転登記をしないまま20年が経過してから,AがBに対して所有権に基づき移転登記手続を請求した場合,Bは,その登記請求権の消滅時効を援用することができる。
登記請求権は,その発生原因に応じて物権的請求権としての性質を有する場合(所有権に基づく登記請求権,実体的な権利関係と登記簿上の権利関係とが一致しないとき,登記簿上の権利関係を実体的な権利関係に一致させるために発生する登記請求権)と債権的請求権としての性質を有するにすぎない場合(売買契約に基づく登記請求権)とがある。
債権的請求権としての性質を有する登記請求権は消滅時効にかかるが,物権的請求権の性質を有する登記請求権は,消滅時効にかからない。
最二判昭51・11・5判時842号75頁
不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は,右譲渡によって生じた所有権の移転を第三者に対抗することができるものとするため,これに附随するものであるから,所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかかるものではないと解すべきである。
消滅時効に関しては,援用権者,消滅時効にかかる権利とかからない権利との区別,短期消滅時効が確定判決を受けた場合の変化,時効の起算点等が重要な論点となる。これらの点について,表を作成してまとめておくとよい。
消滅時効の主要な論点をカバーしており,かつ,条文の知識だけでなく,判例の知識の正確さをもチェックすることのできる良い問題である。
[契約法講義の目次]へ