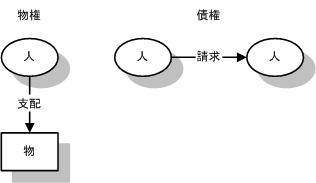 |
| *図1 物権と債権との区別 |
[民法目次]へ
作成:2010年9月25日
明治学院大学法科大学院教授 加賀山 茂
本書の特色
担保法(多数当事者の債権・債務および担保物権法)が好きな学生はほとんどいない。担保法を喜んで教えることのできる先生はもっと少ない。誰もが認めざるをえないこのような不幸な事態はなぜ生じたのか。このような現状を克服するにはどのような方法があるのか。これが,学問としての担保法学が抱える最大の課題である。
従来の担保法の学説は,この原因を担保法の「技術的性格」に求めてきた。すなわち,「担保制度は技術的性格が強く,学生諸君には比較的理解が困難な領域である」([高木・担保物権(1984)初版はしがき],[道垣内・担保物権(2004)初版はしがき],[髙橋・担保物権(2007)はしがき]など)というものである。
しかし,「技術的性格が強ければ理解が困難だ」というのは,技術的な学問に対する冒涜であろう。担保法の理解が困難な原因を突き詰めていくと,その原因は,むしろ,担保法の学説が未熟な状態にあり(学問の領域確定基準さえ確立されていない),体系的な理論を欠いている(例外ばかりで,原則は破壊されている)ことにあることがわかる。その結果,学生たちは,原則からは導けない数多くの例外を暗記するほかなく,「暗記に頼るほかない学問」という意味で,担保法は「技術的な性格が強い」学問領域であるとされているに過ぎない。
そこで,このような現状を打破するため,筆者は,担保法の理解を困難にしている従来の学説からひとまず決別し,1989年から担保法の新しい学問体系を構築する作業に着手した。そして,2002年に,担保物権とは,物権ではなく,「債権に付された優先弁済権」に過ぎないこと,したがって,「債権以外に別個の担保物権が存在するわけではない」ことを論証する論文(潮見佳男編『民法学の軌跡と展望』日本評論社(2002)291-324頁)を公表し,2009年には,『現代民法・債権担保法』(信山社)によって,通説とは全く異なる新しい担保法の理論体系を構築することができた。
この担保法の体系[加賀山・担保法(2009)]においては,担保法をすべての債権に備わっている掴取力(強制履行力)の強化として再定義するところから始めている。そして,担保法のすべてを「債権の掴取力の強化」の展開過程として説明している。すなわち,第1に,債権の掴取力の「量的強化」として人的担保(保証と連帯債務)を位置づけ,第2に,債権の掴取力の「質的強化」として物的担保(事実上または法律上の優先弁済権)を位置づけている。
この新しい担保法の体系の特色は,「債権の掴取力の強化」という1つの概念(公理)から始まって,誰もが疑うことのできない変形規則(推論規則)によって,担保法に共通する「付従性」等の定理を導き出し,それら定理を使って,担保法に関するすべての条文のルール,および,条文に内在する原理を導き出すというものである。この体系は,いわゆる公理的体系であるから,公理に反する例外は存在しない。このため,従来の学説においてその理解を困難にしてきたいわゆる「技術的性格」からも完全に解放されている。したがって,この体系に沿って学習を行えば,担保法の理解が従来よりはずっと容易になるはずである。
しかし,この新しい体系[加賀山・担保法(2009)]は,あくまでも学問体系として構築されたものであり,試行錯誤のプロセスと詳細な論証が記述されているため,学生がこの体系を短時間で理解するには,別な意味での困難を伴うことが予想される。そこで,筆者は,1つの概念から例外のない推論規則によって担保法のすべてのルールを導き出すことのできるという新しい体系に基づきつつも,短時間で担保法のすべてをマスターできるための教科書として本書の執筆に取り掛かることにした。このような意図で作成された本書は,以下の3つの特色を有している。
第1に,担保法全体を「債権の掴取力の強化」という1つの概念で捉え,それを,債権の掴取力の量的強化(人的担保)と債権の掴取力の質的強化(物的担保)という2つの方向で展開することによって担保法の体系化を実現している。このため,これまで別々に論じられていた保証・連帯債務と担保物権(物的担保)を連続的に理解することができる。また,従来,物的担保の特質とされてきた「直接取立権」,「追及効」,「事実上または法律上の優先弁済権」のすべてが,物権法ではなく,債権法の内部(債権者代位権,詐害行為取消権,同時履行の抗弁権,相殺)に存在していることを論証し,そのことを通じて,担保法の総論を創設している。このため,担保法のすべての内容が,債権法の法理だけを使って例外なく説明されており,担保法の全体を容易に理解できるようになっている。もっとも,資格試験をめざしている学生にとっては,通説の理解も必要である。このことを考慮して,本書の考え方と通説とが異なっている点については,最初に,基本的な考え方の違いについて対照表によって詳しく説明している。さらに,随所で,両者の違いを説明し,混乱が生じないように配慮している。
第2に,担保法の理解にとって判例の理解が重要であることを考慮して,重要判例(民法判例百選Ⅰ・Ⅱ〔第6版〕の判例)の事実関係・法律関係をすべて図解して,判例の理解を容易にするという工夫を行っている。この図解と解説によって,従来の通説では説明が困難とされてきた,さまざまな判例の法理がわかりやすく説明されている。もっとも,判例の中には,理論的な混乱に陥ったり,事案の具体的解決としても問題があるものが存在したりするのであって,判例の考え方がすべて正しいとはいえない。本書においては,担保法の新しい体系の観点から最高裁の判断を厳しく批判している箇所も数多く存在するが,筆者としては,そのような批判を通じて読者の判例に対する理解がより深まることを期待している。
第3に,学習の成果を確認するため,学習到達度チェックを単元ごとに配置している。もちろん,体系的な本書の記述を読むだけでも,学習の成果が大いに上がることが期待できる。しかし,本というものは,読んでいる途中はわかった気になったとしても,その後で試験を受けてみると,本当には理解していないことがわかるということが多いものである。そこで,本書では,単元ごとに,学習の到達度を確認する3段階の項目(☆は基礎レベル,☆☆は標準レベル,☆☆☆は研究者レベル)を置き,読者の学習の効果がどの程度上がっているかを常時チェックできるように工夫をしている。読者は,本書の単元を読み終わるごとに,学習の到達度をチェックして,自分の理解度を確認するとよい。そういった地道な努力を重ねることによって,読者は,レベルに応じた学習到達目標を完全にマスターできるようになると思われる。
本書は,2007年に出版した『契約法講義』に続く,筆者の「講義シリーズ」の2冊目の教科書である。柴田英輔氏の企画・編集の下,前回に引き続き,深川裕佳氏(東洋大学法学部講師)に構成等の内容を含めた原稿校正をお願いし,短期間で完成にこぎつけることができた。また,明治学院大学法科大学院での担保法の講義の受講生である原口暁美氏から,原稿段階で多くの誤りを指摘していただいた。紙面を借りてお礼を申しあげる次第である。
筆者としては,担保法の教科書として,最もわかりやすく,かつ,最もレベルの高いものとなることめざして執筆を行ったつもりである。しかし,担保法の体系書である『現代民法・債権担保法』信山社(2009)の完成後,講義の合間を利用して急いで作成したため,なお未熟な点が残っているものと思われる。この点については,読者のご批判を得て,改善の努力を続けていきたいと考えている。
2010年9月 明治学院大学高輪校舎の研究室にて
加賀山 茂
目次
担保法の目的は,債務の履行の確保である。債務が任意に履行されないときには,債権者は,債務者の総財産に対して強制執行を行い,そこから債権の回収をすることになる。このように,債権に備えられた強制執行をすることができるという効力を債権の掴取力という。この掴取力は,債務者の財産に対する「潜在的な換価・処分権」であるため,債権(人と人との関係)と物権(人と物との関係)とが交錯することになる。
債権の効力としての掴取力は,債権者平等の原則によって制限されているため,債務者に他の債権者が存在する場合には,債権者は債権の回収によって完全な満足を得ることができない。そこで,債権者としては,債務の履行を確保するため,債権の掴取力をさらに強化するための制度を必要とする。
ここでは,債権の掴取力を強化する方法は,2つの方向に向かうことを理解する。1つは,債務者の総財産以外の財産からも債権の回収を計ること(掴取力の量的拡大)であり,これが人的担保(保証と連帯債務)である。もう1つは,債務者の総財産,または,特定の財産について,他の債権者に先立って弁済を受けること(掴取力の質的拡大)であり,これが物的担保(事実上の優先弁済権と法律上の優先弁済権)である。
本書は,担保法の体系[加賀山・担保法(2009)]に基づくわが国で最初の担保法の教科書である。本書は,第1編の担保法総論と第2編の担保法各論(人的担保,物的担保)とで構成されている。
第1編の担保法総論は,担保法の本質が何であり,それが,どのようなメカニズムによって実現されているのかを明らかにするものであり,人的担保(広義の保証)と物的担保(いわゆる担保部権)とを架橋する理論を提供している。人的担保と物的担保を架橋する「担保法総論」を有する教科書はこれまでに例がなく,これが本書の特色となっている(*表1)。
| 編 | 章 | 節 |
|---|---|---|
| 第1編 担保法総論 | 第1章 担保法序説 | 第1節 本書の構成 |
| 第2節 担保法総論の構造 | ||
| 第3節 物権と債権の分離と交錯 | ||
| 第4節 債権の掴取力の強化(担保法の本質) | ||
| 第5節 担保法の歴史(旧民法と現行民法との対比) | ||
| 第6節 担保法の体系 | ||
| 第7節 担保法における従来の学説の問題点 | ||
| 第2章 担保法を実現するメカニズム | 第1節 債権者代位権(直接取立権の実現) | |
| 第2節 詐害行為取消権(追及効の実現) | ||
| 第3節 同時履行の抗弁権(事実上の優先弁済権の実現) | ||
| 第4節 相殺(法律上の優先弁済権の実現) |
担保法総論の第1章(担保法の本質と体系)では,担保法の本質が,債権の掴取力の強化,すなわち,債権の掴取力の量的強化(人的担保)と債権の掴取力の質的強化(物的担保)であることを明らかにするとともに,それに基づいた担保法の新しい体系を創設している。
担保法総論の第2章(担保法を実現するメカニズム)では,担保法の本質である債権の掴取力の量的・質的強化を実現する手段が,すべて,債権法の内部に存在していることを明らかにする。すなわち,債権の直接取立権は,債権者代位権[民法423条]・直接訴権[民法613条,自賠法16条など]によって実現されていること,債権の追及効は,詐害行為取消権[民法424条~426条]によって実現されていること,債権の優先弁済権は,同時履行の抗弁権[民法533条],相殺[民法505条~512条]によって実現されていることを示し,担保法全体を債権法によって説明することが可能であることを明らかにしている。
担保法とは,債権の保全と取立てを確実にするための法制度である。民法は,債務が任意に履行されない場合に,債権者に債務者の財産に対して強制執行ができるという救済手段を与えている[民法414条]。このことは,債権者が債務者の責任財産に対して潜在的な支配力を有していることを意味する。このため,債権者の債務者の財産に対する潜在的な支配力は,債権の「掴取力」と呼ばれている。
しかし,債権の掴取力は債務者の資力が十分でない場合には,他の債権者との競合にさらされる。このことは債権者平等の原則といわれている。このため,債権の掴取力は債権の回収という点で,実効性に欠ける面があることは否めない。そこで,民法は2つの方向で,債権の掴取力を強化する手段を債権者に与えている。
第1は,債権者が把握できる責任財産を債務者だけでなく保証人の責任財産にも拡大することによって債権の掴取力を量的に強化するものである。これを人的担保という。人的担保には,保証[民法446条~465条の5]と連帯債務[民法432条~445条]が含まれる。
債務のない責任である「保証」ばかりでなく,債務としての「連帯債務」が人的担保に含まれるはなぜであろうか。その理由は,連帯債務とは,単なる債務ではなく,本来の債務と保証(連帯保証)とが結合したものだからである(相互保証理論)。すなわち,保証と連帯債務とは,連帯保証を通じて連続している。なぜなら,負担部分ゼロの連帯債務が,すなわち,連帯保証だからである。
第2は,債権者平等の原則の例外として,特定の債権者に他の債権者に先立って弁済を受ける権利(優先弁済権)を与えることによって,債権の掴取力を質的に強化するものである。これを物的担保という。
物的担保には,民法に規定されている典型担保としての留置権[民法295条~302条],先取特権[民法303条~341条],質権[民法342条~368条],抵当権[民法369条~398条の22]のほか,学説・判例によって認められている非典型担保としての仮登記担保,譲渡担保,所有権留保が含まれる。
このようにして,担保法が掴取力の量的強化(人的担保)と質的強化(物的担保)であることが明らかになると,次に,それがどのような方法によって実現されているかを探求することが重要な課題となる。
従来の考え方では,人的担保は債権法に属するのに対して,物的担保は物権法に属するという理由で,両者を統一的に考察することが困難であった。本書では,それらを債権の掴取力の量的・質的強化であると位置づけているため,それらを統一的に考察することが容易となる。
その結果,人的担保と物的担保に共通する掴取力の強化方法(直接取立権,追及効,優先弁済権)が債権法内部に存在することを発見することが可能となり,そのことを通じて,人的担保と物的担保とを統合するわが国で最初の担保法の体系(債権の掴取力の強化)を創設することができたのである(担保法革命2009)。
| 担保の分類 | 民法の根拠条文 | ||||
| 債権担保法 | 総論 | 直接取立権 | 債権者代位権 | 民法423条 | |
| 直接訴権 | 民法314条,613条(自賠法16条) | ||||
| 追及権 | 詐害行為取消権 | 民法424-426条 | |||
| 優先弁済権 | 同時履行の抗弁権 | 民法533条,546条1項,571条,576条-578条,634条2項,692条 | |||
| 相殺権 | 民法511条,468条2項 | ||||
| 各論 | 人的担保 | 保証 | 民法446-465条の5 | ||
| 連帯債務 | 民法432-445条 | ||||
| 物的担保 | 典型担保 | 留置権 | 民法295-302条,194条,475条,476条 | ||
| 先取特権 | 民法303-341条,511条 | ||||
| 質権 | 民法342-368条 | ||||
| 抵当権 | 民法369-398条の22 | ||||
| 非典型担保 | 仮登記担保 | 民法482条(仮登記担保契約に関する法律) | |||
| 譲渡担保 | なし(学説・判例)←立法の必要性大 | ||||
| 所有権留保 | 民法128-130条(割賦販売法7条など) | ||||
上記の*表2は,*第4節で説明する*表6を簡略にしたものであり,担保法の体系の意義と解説は,次の*第3節で行う。
担保とは,債権の保全と取立てを確実にするための法制度であるが,その内容を知るためには,まず,物権の世界と債権の世界の違いとその交錯について理解を深めておく必要がある。
債権と区別される物権とは,ある人が物(有体物)に対して,排他的な支配権(使用・収益権または換価・処分権)を有するという関係にあること(*図1の左部分)をいう。物権(本権)は,使用・収益権,換価・処分権を有するかどうかによって,以下のように分類されている。
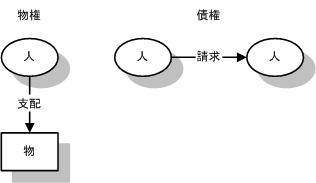 |
| *図1 物権と債権との区別 |
これに対して,債権とは,ある人(債権者)が他の人(債務者)に対してあることをすること(作為)またはあることをしないこと(不作為),すなわち,給付を請求することができる関係があること(*図1の右部分)をいう。
債権の定義については,上記の定義にさらに給付保持力を追加するのが最近の有力説[奥田・債権総論(1992)3頁]の考え方である。すなわち,債権とは,「特定人(債権者)が特定の義務者(債務者)をして一定の行為(給付)をなさしめ,その行為(給付)のもたらす結果ないし利益を当該債務者に対する関係において適法に保持しうる権利」であるとされている。しかし,いずれの説によっても,債権に掴取力があるということ,すなわち,債務者が債務を任意に履行しない場合には,債権者は,一定の要件の下で,裁判所に「強制履行」を請求することができる[民法414条]という点では異論はない。
債権の種類は様々な観点から分類されているが,債権の発生原因にしたがって分類すると以下の通りである。
物権と債権とは,上記のように一応区別され,独自の世界を展開する。しかし,これら2つの世界は,債務者が債務を任意に履行しない場合に交錯することになる(*図2)。なぜなら,債務者が任意に債務を履行しない場合には,債務者の財産(有体物,無体物を含む)に対して強制執行を行う権利(掴取力)を有する[民法414条]からである。
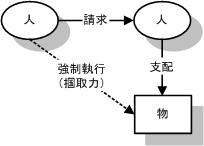 |
| *図2 物権と債権との交錯 (債権の掴取力) |
民法414条に規定された債権の強制履行力のことを債権の掴取力と呼ぶ。この掴取力(債権における債務者の財産に対する換価・処分権)が,排他的支配権としての物権の世界と,平等な関係としての債権の世界を交錯させている。なお,法律辞書([有斐閣・法律学小辞典(2004)])によれば,掴取力の定義が以下のようになされている。
当初からの金銭債権だけでなく,それ以外の債権も不履行の場合には損害賠償債権に転化することにより,究極的には債務者の一般財産(責任財産)に対する強制執行によって終局的満足を受けることになる。これを実体法的にみれば,債権は債務者の一般財産への潜在的支配力を有しており,それが執行を通じて実現されるものとみることができる。債務者財産に対するこのような抽象的・潜在的支配力を掴取力と呼んでいる。
掴取力の実現は,民法414条およびそれに対応する民事執行法の規定にしたがって実現される。債務の種類に応じた掴取力(強制履行)の態様については,以下の*表3のようにまとめることができる。
| 債務の種類 | 民法 | 民事執行法☆☆☆ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作為債務 | 引渡債務 | 金銭債務 | 402条~405条 | 民法414条1項 (直接強制) |
43条~167条 (強制執行) |
167条の15 (間接強制) |
|
| 物の引渡債務 | 特定物の引渡債務 | 400条 | 168条~170条 (強制執行) |
||||
| 種類物の引渡債務 | 401条 | - | |||||
| 行為債務(引渡以外の作為債務) | 414条2項 (代替執行,法律行為の強制履行) |
171条(代替執行) 167条の15・16(間接強制) 172条~173条(間接強制) 174条(意思表示に代わる裁判) |
|||||
| 不作為債務 | 414条3項 (差止請求権を含む) |
171条 | |||||
もっとも,債権の掴取力(換価・処分権)は,以下の2つの制約を伴っている。
第1の制約は,債権の相対性に由来する原則であり,債権者が掴取力を獲得するのは,債務者が債務を任意に履行しない場合に限られる。債務者が債務を履行するならば,債権者は債務者の財産に対して掴取力を及ぼすことはできない。ただし,掴取力も,実際の効力は債務不履行の時点からであるにしても,万一の場合に発動できるように債権にはじめから備わった効力として存在している。これは,条件付権利が,権利として尊重されている[民法128条~130条]のと同じである。
第2の制約は,債権の掴取力は債権者平等の原則に服するということである(*図3)。債権の掴取力は,民事執行法の手続きを介して,債務者の責任財産に対する換価・処分権として機能するが,この掴取力は,債権の相対性により,排他的な効力ではなく,すべての債権者が平等な立場で行使できるものである。
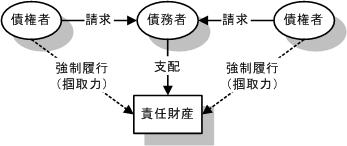 |
| *図3 債権の掴取力の制限 (債権者平等の原則) |
ここでいう責任財産とは,強制執行の対象物として,ある請求の実現の用に供される財産(物または権利)のことをいう。金銭債権の強制執行に即していえば,責任財産とは,債務者に属する執行可能な(法律上の差押禁止財産や一身専属的な権利を除く)総財産のことである。総財産は日々入れ替わり,その総額も刻々と変化しており,有体物を目的物とする物権の対象にはなりえず,債権譲渡など,債権の目的物となりうるだけであるというのが,現行民法の立法者の考え方である。
債権の掴取力が債権者平等の原則に服することについて,民法には直接の規定がない。ところが,旧民法には,債権者平等の原則とその例外に関する明文の規定があった[旧民法債権担保編1条]。その規定の内容は以下の通りである
旧民法 債権担保編(明治23年法律第28号)
第1条 ①債務者の総財産は,動産と不動産と現在のものと将来のものとを問はず,其債権者の共同の担保なり。但,法律の規定又は人の処分にて差押を禁じたる物は此限に在らず。
②債務者の財産が総ての義務を弁済するに足らざる場合に於ては,其価額は,債権の目的,原因,体様の如何と日附の前後とに拘はらず,其債権額の割合に応じて之を各債権者に分与す。但,其債権者の間に優先の正当なる原因あるときは此限に在らず。
③財産の差押,売却及び其代価の順序配当又は共分配当の方式は,民事訴訟法を以て之を規定す。
このように,旧民法においては,債権者の平等原則に服する人的担保と,債権者平等の例外に属する物的担保とが,債権担保編という1つの編に,統一的な形で規定されていた。したがって,旧民法においては,債権者平等の原則とその例外としての優先弁済権とを,債権担保という共通の土俵の下で考察することが容易であった。
それにもかかわらず,現行民法が,担保法に見られるこれらの共通性をあえて分断し,人的担保を債権編に,物的担保を物権編へと再編したことは,不幸なことであった。しかし,現行民法の立法理由([民法理由書(1987)],[梅・要義巻二(1896)]など)を読んでみると,ボワソナードが起草した債権担保編の条文自体は,文言等についての多少の修正は受けつつも,内容は変更されずに現行民法の中に取り込まれているというものが意外と多いことがわかる。したがって,ボワソナードの立法の精神に立ち返って,現行民法の立法の問題点を再検討することも不可能ではない。
むしろ,物的担保(担保物権)を,債権における掴取力が債権者平等の原則の枠を超え,債権が優先弁済権を獲得したものとして理解することは,旧民法の起草者であるボワソナードの精神に立ち返るばかりでなく,フランス民法典における担保法の改正(2006年)の動向にも適合するものといえよう。なぜなら,2006年の担保法の改正によって,フランス民法もまた,従来の考え方を改め,人的担保と物的担保を,共通の「担保」として,同一の編に取り込んで,統一的な規定を行うこととしたからである。
担保という用語は,債権の履行を確実にするという意味であり,通常は,保証と同じ意味で用いられる。売買契約における瑕疵「担保」[民法570条]という用語も,黙示の品質「保証」の意味で用いられている。また,民事訴訟において裁判所によって「担保の提供」を命じられる場合([民事訴訟法75条以下],また[民事執行法15条]参照)にも,その担保の提供には,「保証人を立てる」ことが含まれている([民事訴訟規則29条],また[民事執行規則10条]参照)。
担保と保証とを区別する場合には,担保を最も広い意味で用い,広義の担保の中に,人的担保としての保証と物的担保としての優先弁済権とを対立させて位置づけるという方法がとられている。そして,人的担保としての保証と区別される物的担保は,被担保債権の履行が確実でない場合には,牽連する義務の履行を拒絶することができることによって事実上の優先弁済権を確保するもの(履行拒絶の抗弁権)と,法律上の優先弁済権(他の債権者に先立って弁済を受ける権利)を有するものとがある。
担保という用語が最初に出てくる民法の条文は民法29条(不在者の財産管理人の担保提供および報酬)である。この条文で規定されている裁判所への担保提供義務[民法29条]に関しては,民事訴訟法においても,担保提供義務(立担保)の規定が用意されている。例えば,裁判所が原告に訴訟費用の担保を立てるべきことを命ずる場合において,被告は「原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる」[民事訴訟法75条4項]とされている。この規定を実体法的に分析すると,原告敗訴の場合に,訴訟費用を確実に原告に負担させるために,法が物的担保の一つとしての「拒絶の抗弁権」を被告に与えたものと考えることができる。また,原告が敗訴した場合に,被告は,「供託した金銭又は有価証券について,他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する」[民事訴訟法77条]と規定されているが,このことは,被告に物的担保の一つとしての法律上の優先弁済権を認めたものと考えることができる。
このように,担保という用語は,法律の分野によって,さまざまな意味で用いられているが,「債権の担保」という場合には,債権の履行と回収を確実にする制度という意味で用いられている。本書でも,担保とは,債権担保の意味,すなわち,債権の掴取力の強化の意味で用いることにする。
債権の掴取力は,先に述べたように,債務者の資力が十分でない場合には他の債権者との競合にさらされるために,債権の回収という点で実効性に欠ける面があることは否めない。そこで,民法は,2つの方向で,債権の掴取力を強化する手段を債権者に与えている。1つは,責任財産の個数を増やすことである。これを人的担保(債権の掴取力の量的強化)という。もう1つは,責任財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利を取得することである。これを物的担保(債権の掴取力の質的強化)という。
| 担保の分類 | 性質・内容 | 対象・目的物 | 民法の根拠条文 | |
| 人的担保 (掴取力の量的強化) |
保証 | 債務者に代わって債務の弁済をする責任 | 責任財産 | 民法446-465条の5 |
| 連帯債務 | 債務と保証(連帯保証)との結合 | 民法432-445条 | ||
| 物的担保 (掴取力の質的強化) |
留置権 | 引渡拒絶の抗弁権(事実上の優先弁済権) | 動産,不動産 | 民法295-302条, 194条,475条,476条 |
| 先取特権 | 法律上の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法303-341条,511条 | |
| 質権 | 留置的効力を利用した約定の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法342-368条 | |
| 抵当権 | 追及効を伴う約定の優先弁済権 | 不動産,財産権 | 民法369-398条の22 | |
人的担保には保証と連帯債務とが含まれるが,連帯債務は通常の債務と,保証との結合であり,連帯債務の箇所で詳しく説明するので,ここでは,とりあえず保証について説明する。
また,物的担保には,民法に規定のない非典型担保(譲渡担保,仮登記担保)が含まれるが,これも,非典型担保の箇所で詳しく説明するので,ここでは,民法に規定された4つの物的担保について説明する。
債権は,通常の場合には,債務者の責任財産に対してしか掴取力を及ぼすことができない。しかし,人的担保(広義の保証:狭義の保証と連帯債務とを含む)を設定すると,債権者は,債務者以外の保証人の責任財産に対しても,掴取力を及ぼすことができる。
この意味で,人的担保(広義の保証)とは,責任財産の個数を増やすことを通じて債権の掴取力を量的に強化するものであるといえる。すなわち,人的担保とは,債務者の責任財産だけでは債権の満足を得られない場合に備えて,資力のある人との間で保証契約を締結して,その人を債務者の保証人としておき,その人の責任財産からも債権の回収ができるようにする制度である。
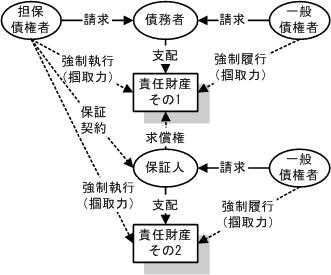 |
| *図4 掴取力の量的強化としての保証 (人的担保) |
保証の制度は,債務者に信用を増加させるために有用な制度ではある。しかし,一方で債権者にとって都合のよい制度は,他方で責任を負担する保証人に過酷な責任を強いるおそれがある。そこで,民法は,いったんは債務者の債務を肩代りして弁済をすべき責任を負う保証人が,債務者に対して確実に求償ができるように[民法459条以下],求償権の範囲で,「債権者が有していた一切の権利を行使することができる」という,弁済による代位の規定[民法500条,501条]を用意している。それだけでなく,過酷な責任から保証人を免責するために,債権者に保証人に対する担保保存義務(広い意味での安全配慮義務)を課し,債権者がそれに違反した場合には,保証人が免責されるという保証人保護の規定を置いている[民法504条]。
その結果として,保証人の責任は,債権者に支払った額の全額を債務者に求償することを通じて完全に免責される。すなわち,保証人は,求償を通じて債務を負担しない状態に回復される。したがって,民法自体が「保証債務」という用語を用いているにもかかわらず,保証人の責任は,物上保証人[民法351条]の場合と同じく,「債務」ではなく「責任」である。すなわち,「保証債務」とは,実は,求償のできない本来の「債務」ではなく,求償を通じて債務を免責されるのであるから,「債務のない責任」に過ぎないと考えるべきである。
もっとも,通説([我妻・債権総論(1954)449頁],[於保・債権総論(1972)253頁],[奥田・債権総論(1992)380頁],[平井・債権総論(1994)303頁],[内田・民法Ⅲ(2005)338頁]など)は,保証を債務と考え,保証人は第三者ではなく,債務者と同じ地位に立つ者と考えている。
しかし,保証人が債権者に債務を支払った場合に,保証人が債務者に全額求償できるのは,保証人は債務者ではないからである。債務者の債務を他人である保証人が肩代りして弁済する[民法474条]からこそ,保証人は全額を債務者に求償できるのであって,保証人が最終的な負担を負う者という意味での債務者であるならば,求償はできないはずである。
そればかりでなく,保証を債務と考える通説の考え方は,民法448条が規定する「保証債務の付従性」によって,以下のように破綻するに至る。すなわち,通説は,「保証債務」を主たる債務とは別個・独立の債務であると定義しつつも,「保証債務」が主たる債務に従属するということを認めざるを得ない([我妻・債権総論(1954)450頁],[於保・債権総論(1972)254頁],[内田・民法Ⅲ(2005)338頁])。しかし,「主たる債務とは独立の債務」のはずが,「主たる債務に従属する」というのは,明らかな自己矛盾であり,理論自体が破綻している。この矛盾を解消するためには,根本にさかのぼって保証理論を再構築する必要がある。
本書の立場は,保証は債務ではなく,唯一存在する「主たる債務」について保証人が肩代りの責任を負うというものであるから,「独立の債務が従属する」という矛盾を,以下のように,完全に回避できる。
民法448条の保証の付従性とは,実は,「主たる債務」が消滅すれば,その債務を肩代りするという「保証人の責任」も当然に消滅するということを意味する。すなわち,「保証の付従性」とは,「主たる債務」の外に,「保証債務」という別の債務が存在するわけではないこと,そして,保証とは,債務ではなく,「主たる債務」を担保するための保証人の「責任」であることを証明するものにほかならない。
なお,人的担保に含まれる連帯債務は,本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)との結合であるため,連帯債務者の1人に生じた負担部分の消滅は,必然的に他の連帯債務者の保証部分に影響を及ぼすのであり[民法434条~439条],連帯債務においても,保証部分については付従性が妥当する。この点,通説は,連帯債務は債務であって保証ではないので,付従性の問題は生じない(例えば,[平井・債権総論(1994)327頁],[内田・民法Ⅲ(2005)372頁])としているが,これが誤りであることは,*第4章第3節(連帯債務)の箇所で詳しく論じる。
以上の議論を踏まえると,以下のような本書の立場(加賀山説)は,保証の性質について,矛盾のない理論を提供していると思われる。
民法448条は,保証人の責任が主たる債務に付従することを明らかにしている。この「保証の付従性」という法理は,保証理論の中核をなすものであり,学説においても争いがない。したがって,これを保証に関する原理として尊重することが許されよう。
民法448条の「保証の付従性」を前提とするならば,「保証債務」という民法の用語法自体が誤りであるということになる。このように,現行民法は,編別,タイトル,条文見出しには不用意な分類や用語法の誤りが多く見られるが,個々の条文の内容には間違いが少ないという特色を有している。現行民法のこのような特色は,典型的にはいわゆる担保物権の定義条文に見られるが,民法446条にもその特色が現れている。すなわち,タイトルの第4款「保証債務」という用語法は誤用である。しかし,そのタイトルに続く民法446条の具体的な内容は,「保証人は主たる債務者の債務の履行をする責任を負う」としており,保証が本来の債務でないことを正しく表現している。
左の図を見ながら,保証の最初の条文(冒頭条文)の民法446条1項をじっくり眺めてみよう。
第446条(保証人の責任等)
①保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う。保証人は,債務を負うのではなく,他人(債務者)の債務を肩代りして履行する責任を負うに過ぎないことが,条文に明確な形で書かれていることに気づくであろう。したがって,保証に関する本書の立場は,以下のようにまとめることができる。
*図5 債務のない責任としての保証の構造
保証とは,債権者・債務者間に存在する「主たる債務」について,債務者の支払い能力(信用)を強化(担保)するために,債務者がその債務を履行しないときは,保証人が債務者に代わって「主たる債務」を履行するという保証人の「責任」を意味する。したがって,保証は,終局的な責任を負うという意味での「債務」ではなく,債務者への求償が可能な「債務のない責任」である。
このように考えると,保証ばかりでなく,物上保証([民法351条],[民法372条]参照)も,ともに,「債務のない責任」であることが明らかとなる。もっとも,物上保証人が,担保となった特定の財産についてのみ責任を負う(有限責任)のに対して,保証人は,債務額の範囲で,一般財産を引き当てにする責任(無限責任)を負担する点で,物上保証と保証との間には責任の重さという点で大きな違いがあることに留意しなければならない。
ところで,債権の掴取力の量的拡大という点では,後に述べる詐害行為取消権も,債務者から逸失した責任財産について,受益者,転得者へと追及できる権利であり,広い意味での掴取力の強化である。この場合,追及を受ける受益者,転得者は,あたかも,物上保証人であるかのように,前主の責任を肩代りする有限責任を負うことになる。ただし,詐害行為取消権の場合には,責任を追及される人が受益者または転得者の2人に限定される。この点が,責任財産を何人にでも拡大できる保証とは異なっている。
債権者が債権の回収を確実にするための1つの方法は,すでに述べたように,責任財産の個数を増やすことである(人的担保)。もう1つの方法は,責任財産から他の債権者に先立って弁済を受ける権利(優先弁済権)を取得することである。これを物的担保という。
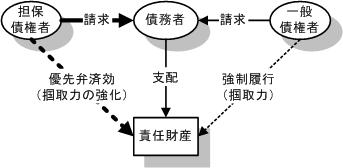 |
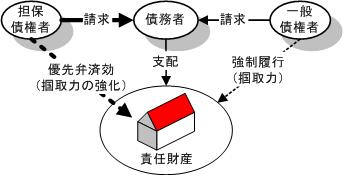 |
| *図6 一般先取特権における優先弁済権 | *図7 質権・抵当権における優先弁済権 |
| 掴取力の質的強化としての優先弁済権(物的担保) | |
債権と物的担保との相違は,前記の*図3と上記の*図6,*図7との比較を通じて説明するのがもっとも簡明である。
第1に,すべての債権は,債務者が任意に履行しないときは,債務者の財産に対して債務名義を必要とする強制執行を通じて,債務者の財産を換価・処分する効力(掴取力)を有する。しかし,目的物を換価・処分した代金の中から,債権者は他の債権者と平等の割合(按分比例)で配当を受けるに過ぎない(債権者平等の原則)。
第2に,これに対して,物的担保は,債権(被担保債権)があることを前提にするが,債務者の責任財産に対して(一般先取特権の場合には責任財産すべてに対して,その他の物的担保については特定の目的物に対して),債務名義を必要としない(担保権の存在を証明する法定文書が必要となるに過ぎない)担保権の実行手続きを通じて,債務者の財産を換価・処分することができる。その上,目的物の換価・処分した代金の中から,他の債権者に先立って弁済を受ける権利(優先弁済権)を有する。
債権と物的担保との間における上記の違いを決定的と考えるのが通説の考え方である。これに対して,本書の立場は,この違いは,相対的な違いに過ぎず,むしろ,債権の掴取力という点では,債権も物的担保も共通しており,両者は,債権者平等原則に基づく按分比例か,それとも優先弁済が可能か,という違いがあるに過ぎないと考えている。
従来の学説が物的担保を物権であると考えてきたのは,物的担保が物権編に編入されているという理由だけでなく,物的担保の対世的な機能(直接取立権,追及効,優先弁済効)が,相対的な債権では説明がつかないと考えられてきたからである。
しかし,わが国の民法は,ドイツ民法とは異なり,債権の内部において,対世的な機能を有する権利(債権者代位権,詐害行為取消権等)を有している(ドイツ民法はこれらの制度を有していない)。したがって,これらの権利,および,同時履行の抗弁権の対外的効力,相殺の担保的機能を再構成することにより,物的担保のすべての機能を債権法の世界の中で矛盾なく説明することが可能となる。
| 担保の手段 | 性質・内容 | 対象・目的物 | 民法の根拠条文 | ||
| 直接取立権 | 債権者代位権 | 第三債務者に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法423条 | |
| 直接訴権 | 第三債務者に排他的に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法314条,613条 (自賠法16条) |
||
| 追及権 | 詐害行為取消権 | 受益者,転得者の財産に追及できる権利 | 第三者の責任財産 | 民法424-426条 | |
| 優先弁済権 | 同時履行の抗弁権 | 履行拒絶による事実上の優先弁済権 | 対立する債権・債務 | 民法533条 | |
| 相殺権 | 牽連性ある債権に対する即時・優先回収権 (法律上の優先弁済権) |
受働債権 | 民法511条,468条2項 | ||
債権の掴取力は,債権の相対性に基づき,債務者の責任財産に及ぶが,債務者の財産のうち,債務者の第三債務者に対する債権については,債権の相対性の原則に従い,債権者が直接に第三債務者に対して支払いを求めることはできない。債権者が債務者の債権に対して換価・処分権を行使するためには,まず,債務者に対して債務無名義を取得し,その債務名義に基づいて,債務者の債権を差押え,差押えの効力として第三債務者に対して取立てを行うのが本筋であると考えられてきた[民事執行法143条以下]。
しかし,わが国の民法は,それにとどまらず,債権執行の制度が発達していなかったフランスにおいて実体法の制度として発展した債権者代位権(action oblique[民法423条]),および,直接訴権(action directe[民法613条,自賠法16条])の制度を取り入れている。この2つの制度によって,わが国の民法においては,債権者は,債務者に対する債務名義を必要とせず,裁判上および裁判外で,第三債務者に対して直接の取立権を行使することが可能となっている。
さらに,債権者を害することを知りながら重要な責任財産を債務者が第三者に譲渡した場合には,債権者は,悪意の第三者に移転した財産に対して追及できる権利として詐害行為取消権(action paulienne)の制度を取り入れている[民法424条~426条]。
債権者が第三者に対して直接に取立を行うことは,物権とされてきた債権質に特有の現象と考えられてきたし,債権者が第三者の財産に対して直接に強制執行を求めることは,物権としての抵当権に特有の現象と考えられてきた。しかし,上記の債権者代位権,直接訴権は,債権質と同様に,債権者に第三債務者に対して直接の取立権を認めるものであり,詐害行為取消権は,抵当権と同様に,第三者に追及効を認めるものである。
このように考えると,これまで,物権である担保物権だけに可能とされてきた直接取立権も,また,物権にだけ認められると考えられてきた追及効も,債権の掴取力の強化としてすでに存在していることがわかる。そして,このことは,物的担保を債権法の制度として再構築が可能であることが可能であることを示唆しているといえよう。
本書を読み進めていくと,そのほかにも,物的担保に特有の機能として考えられてきた優先弁済権(他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと([民法303条],[民法342条],[民法369条]))が,実は,債権法の内部にすでに存在していることが明らかとなる。留置権の効力は,事実上の優先弁済権であることは,疑いがない。しかし,その効力を導き出しているのは,履行拒絶の抗弁権であり,それは,すでに,同時履行の抗弁権においてその道具立てが用意されている。さらに,法律上の優先弁済権についても,実は,相殺の効力の中の相殺の担保的機能といわれているものは,債権法の内部において,すでに,法律上の優先弁済権を実現しているのである。
同時履行の抗弁権も,留置権も,相殺も,2つの債権の間に牽連性が認められる場合には,一方の債権だけを実現すると不当な結果が生じるという抗弁(悪意の抗弁(exceptio doli))に由来している。すなわち,事実上の優先弁済権(同時履行の抗弁権~留置権)も,法律上の優先弁済権(相殺~物的担保)も,牽連する2つの債権は運命共同体のように同時に履行されるべきであり,この関係は,第三者の介入によっても害されるべきでない(牽連性の第三者対抗力)というメカニズムによって実現されているのである。
このように,担保法の本質と考えられる掴取力の量的強化(人的担保),掴取力の質的強化(物的担保)の実現手段は,すべて,債権法の内部において用意されているのである。
以下の項目について,学習目標が到達されているかどうかをチェックしてみよう。まず,本文を見ずに,六法と自分の頭だけを頼りに,答えを必ずノートに書いてみること。その上で,本文を読み直して,答えが正しいかどうかチェックしてみよう。本文を読んだときはわかったつもりでも,実際に自分の頭で考え,それを書いてみようとすると,答えが書けるほどには理解していないことがわかるはずである。もしも,前提知識が十分でないために,本文を読んでも答えることができない場合には,巻末の用語辞典等の法律辞書や民法判例百選ⅠⅡ等の参考書を利用するとよい。
物権と債権の交錯について
債権の掴取力の強化について
債権担保法という概念とその成文法化は,実は,120年も前に制定された旧民法の債権担保編によって実現されていた。そこでは,人的担保(保証,連帯債務)と物的担保(留置権,先取特権,質権,抵当権)が統一的に規定されていた。旧民法が施行されないまま廃止され,それに代わって制定された現行民法は,ドイツ流のパンデクテン方式を採用したため,人的担保が債権編へ,物的担保が物権編へと分断されることになった。このため,両者は次第に別々の制度として考えられるようになった。しかし,人的担保と物的担保とは,付従性という共通の性質を有しており,物上保証という制度によって密接に関連している。フランス民法典が,2006年の民法改正によって,担保編を創設し,それまでばらばらに規定されていた人的担保と物的担保とを統合したことは,旧民法の考え方がいかに優れていたかを実証することになった。
ここでは,フランス民法典の担保法の改正を契機として,フランス民法典の改正を先取りした旧民法とドイツ民法に近いと考えられてきた現行民法とを比較することを通じて,現行民法の担保法部分は,ドイツ民法やフランス民法とも異なり,ボワソナードが起草した旧民法の債権担保編の規定をわずかな修正を加えただけで成立したものであることを明らかにするとともに,人的担保と物的担保とを統一的に把握することによって,担保法の体系を再構成できることを明らかにする。
わが国の担保法を考える上で,現行民法の成立過程を振り返ってみると,いくつかの重要な点を発見することができる。とくに,わが国の担保法の母法ともなっているフランス民法典における最近の改正(2006年の担保法改正)は,担保法の体系をどのように構築すべきかという点で参考になる。
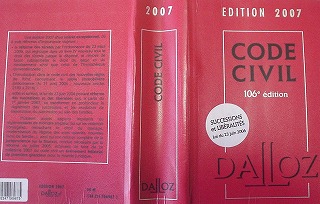 |
フランス民法典〔2007年版〕Dalloz社の表紙 裏表紙に,2006年担保法改正(人的担保と物的担保の統一) ①2006年3月23日のオルドナンスによる担保法の改革。 |
| *図8 Dalloz社のフランス民法典2007年版 |
2006年のフランス民法典の改正(2006年3月23日のオルドナンス)により,それまで,別々に規定されていた人的担保(Des sûretés personnelles)と物的担保(Des sûretés réelles)が1つの編(フランス民法典第4編:担保編(Livre IV: Des sûretés))にまとめられることになった(詳しくは,平野裕之「2006年フランス担保法改正の概要/改正経緯及び不動産担保以外の主要改正事項」ジュリスト1335号(2007)36頁以下,片山直也「2006年フランス担保法改正の概要/不動産担保に関する改正について」ジュリスト1335号(2007)49頁以下を参照のこと)。
わが国の旧民法は,ボワソナードによって起草された(1890年)。旧民法☆は,わが国最初の民法典であり,現行民法の土台となった法典である。2006年のフランス民法改正よりも120年も前に,旧民法では,すでに,人的担保と物的担保を債権担保編として1箇所に規定していた。
旧民法の編成:人事編/財産編/財産取得編/債権担保編/証拠編/
 |
ボワソナードが起草した旧民法の債権担保編の構成☆☆☆は,以下の通りであり,ドイツ民法とは全く異なる上,当時のフランス民法の編成とも異なっていた(むしろ,2006年の担保法改正によって実現された現行のフランス民法典編成とほぼ同じである)。
このように,旧民法には,フランス民法に規定がなかった留置権,および,ドイツ民法に規定がない先取特権が規定されていた(現行民法も,留置権,先取特権を明文で規定しており,現行民法は,構成こそ異なるものの,旧民法の考え方を引き継いでいる)。 |
| *図9 旧民法を起草した 近代私法の父ボワソナード |
旧民法は,1893(明治26)年から施行されることになっていたが,その施行をめぐって法典論争が起こり,断行派(フランス法派)と延期派(イギリス法派等)とが争った結果,延期派の勝利に帰し,旧民法は,一度も施行されることなく廃止となり,ボワソナードは,1895年に帰国した。
しかし,旧民法は,その廃止によっても,価値が損なわれたわけではない。フランス民法典は,担保法改正(2006)によって,第4編として担保編(sûretés)を創設し,人的担保と物的担保とを統一的に規定するに至っているが,旧民法は,それより100年以上も前に,担保法の統合を実現していたことになるのであり,ボワソナードの先見性,旧民法の法典としての完成度の高さが実証されたことになる。
 |
法典論争の結果,旧民法が廃止されたため,現行民法の起草者(穂積陳重(延期派),梅謙次郎(断行派),富井政章(延期派)の3人)が,ボワソナードの作成した旧民法を修正する☆という形で,現行民法(1898)を起草した。 現行民法は,ドイツ民法に倣ってパンデクテン方式を採用したため,債権担保法のうち,人的担保を債権編へ,物的担保を物権編へと分割・移動☆☆することになった。 ただし,現行民法が,旧民法には規定があってドイツ民法に規定がない「先取特権」の規定を有していることは,内容に関しては必ずしも,ドイツ法一辺倒となっているわけではないことを示している。そればかりでなく,個々の条文については,むしろ,旧民法の条文を変更していないものが多い(現行民法の個々の条文が旧民法のどの条項を修正したのかという点については,[民法理由書(1987)]☆☆☆を読めばわかる)。 |
| *図10 現行民法の起草者 左から富井,梅,穂積 |
たとえば,先取特権,質権,抵当権は,ともに,他の債権に先立って自己の「債権の弁済を受ける権利」として定義されている。「債権の弁済を受ける権利」とは,債権の定義そのものであり,物権の定義からはかけ離れている。この点でも現行民法は,旧民法の「債権担保編」の考え方を受け継いでいるといってよい。
本書の考え方は,従来の学説とは全く異なるものであるが,「担保とは,債権の掴取力の強化である」というものであり,理論的には単純で,完結した体系を有している。
第1に,人的担保である保証については,これを債権の掴取力の量的強化,すなわち,責任財産の個数の拡大であると考えており,従来の考え方と矛盾するものではない。第2に,物的担保については,これを債権の掴取力(潜在的な換価・処分権)の質的強化,すなわち,債権者平等の原則の例外としての事実上または法律上の優先弁済権が付与されたものと考えており,優先的に「弁済を受ける権利(債権)」を物権として構成するよりも,はるかに説得的であろう。第3に,物的担保の通有性についても,債権の掴取力が債権に従属するのは当然であるから,付従性,不可分性という例外のない通有性を確保することができる。第4に,物的担保に特有の性質とされてきた直接取立権,追及効,優先弁済権も債権法の内部にこれらを実現する制度が存在していることを明らかにしているのであるから,物的担保を債権の掴取力の強化として捉えても,これらの点について,従来の考え方の結論と同じ結論を導くことが可能である。第5に,人的担保と物的担保とを債権の掴取力の強化として統一的に考察できるようになると,人的担保と物的担保のはざまで,その性質が十分に解明されていなかった物上保証についても,抵当目的物の第三取得者,詐害行為の受益者・転得者との関係を含めて,統一的に理解することが可能となる。
以下の*表6は,本書の体系を示すものである。一見,大きな表に見えるが,各部分をみると,すでに述べた*表4と*表5とを合成し,かつ,それに非典型担保を追加したものであって,これまでの検討を踏まえて作成されたものに過ぎない。
| 担保の分類(大中小) | 性質・内容 | 対象・目的物 | 民法の根拠条文 | ||||
| 大 | 中 | 小 | |||||
| 債 権 担 保 法 |
手 段 ・ 総 論 |
直接取立権 | 債権者代位権 | 第三債務者に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法423条 | |
| 直接訴権 | 第三債務者に排他的に取立てを行う権利 | 債務者の債権 | 民法314条,613条 (自賠法16条) |
||||
| 追及権 | 詐害行為取消権 | 受益者,転得者の財産に追及できる権利 | 第三者の責任財産 | 民法424-426条 | |||
| 優先弁済権 | 同時履行の抗弁権 | 履行拒絶による事実上の優先弁済権 | 対立する債権・債務 | 民法533条 | |||
| 相殺権 | 牽連性ある債権に対する即時・優先回収権 | 受働債権 | 民法511条,468条2項 | ||||
| 実 体 ・ 各 論 |
人的担保 | 保証 | 債務者に代わって債務の弁済をする責任 | 責任財産 | 民法446-465条の5 | ||
| 連帯債務 | 債務と保証(連帯保証)との結合 | 民法432-445条 | |||||
| 物 的 担 保 |
典 型 担 保 |
留置権 | 引渡拒絶の抗弁権(事実上の優先弁済権) | 動産,不動産 | 民法295-302条, 194条,475条,476条 |
||
| 先取特権 | 法律上の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法303-341条,511条 | ||||
| 質権 | 留置的効力を利用した約定の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | 民法342-368条 | ||||
| 抵当権 | 追及効を伴う約定の優先弁済権 | 不動産,財産権 | 民法369-398条の22 | ||||
| 非 典 型 担 保 |
仮登記担保 | 帰属清算型とされる約定の優先弁済権 | 不動産 | 民法482条 (仮登記担保法) |
|||
| 譲渡担保 | 処分清算型の約定の優先弁済権 | 動産,不動産,財産権 | なし(学説・判例) ←立法の必要性大 |
||||
| 所有権留保 | 譲渡担保の一種(割賦販売等で利用) | 動産,不動産 | 民法128-130条 (割賦販売法7条など) |
||||
従来の学説が,担保法全体を統一的に扱うことができなかった最大の原因は,旧民法が人的担保(保証,連帯債務)と物的担保(担保物権)とを債権担保法の中で統一的に扱っていたにもかかわらず,現行民法が両者を切り離し,人的担保を債権法へ,物的担保を物権法へと編入してしまったことにある。すなわち,現行民法は,人的担保を民法第3編の債権の中の多数当事者の債権・債務の中に編入するとともに,物的担保(担保物権:留置権,先取特権,質権,抵当権)を民法第2編物権の中に編入してしまった。このため,従来の学説も,これに倣い,両者を全く別の制度(債権の問題と物権の問題)として論じてきた。また,人的担保と物的担保とをつなぐ役割を果たす重要な制度である直接取立権,追及効,優先弁済効についても,債権の保全の機能を果たすための直接取立権(債権者代位権),追及効(詐害行為取消権)は債権総論で論じ,優先弁済権を実現するもの(同時履行の抗弁権,相殺)は,契約総論と債権総論とで論じるというように,別々に,かつ,無関係のものとして論じられており,統一的な位置づけはなされていなかった。
本書は,第1に,人的担保と物的担保を「債権の掴取力の強化」という共通の観点から両者を統一するだけでなく,第2に,債権法の中に埋もれていた債権の掴取力を強化する手段としての直接取立権(債権者代位権,直接訴権),追及効(詐害行為取消権),事実上または法律上の優先弁済権(同時履行の抗弁権,相殺権)を掘り起こして担保法総論として創設し,第3に,創設した担保法総論の下に人的担保と物的担保とを担保法各論として再配置することを通じて,わが国で最初の担保法の体系を樹立している(担保法革命2009)。
担保物権の学問的出発点は,条文にはない「担保物権」という用語で観念されている担保(物的担保)を1つのグループとして取り扱うために,それらに共通の性質(通有性)を抽出し,新しい債権担保の仕組みが生じた場合に,それが「担保物権」のグループに入るかどうかを決定できる客観的な基準を用意することにあるといわなければならない。
このような学問的な出発点において,わが国の学説は,担保物権の「通有性」といっても「必ずしも共通の性質とはいえず,いちおうの整理に過ぎない」([道垣内・担保物権(2008)8頁],[清水(元)・担保物権(2008)9頁])などと述べて,通有性の概念を等閑視する傾向にある。これに対して,本書の立場は,実に単純・明解である。なぜなら,本書においては,物的担保とは,債権の掴取力を質的に強化するものとして事実上・法律上の優先弁済権を有する権利であり(物的担保の本質),その通有性とは,債権が存在しなければ物的担保も存在せず(付従性),債権が存続する範囲で優先弁済権も存続する(不可分性)という性質であると考えるからである。
| 大分類 | 小分類 | 本質・効力 | 通有性 | 特色 | 対抗要件 (原則) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 的 担 保 |
法 定 担 保 |
留置権 | 債権の 掴取力の 質的強化 |
事実上の優先弁済権 (引渡拒絶の抗弁権) |
付従性 (随伴性), 不可分性 |
債務者から使用・収益権を奪う (留置的効力) |
占有の継続 |
| 先取特権 | 法律上の優先弁済権 (他の債権者に先立って 弁済を受ける権利) |
債務者から使用・収益権を奪わない (優先弁済権そのもの) |
不要 | ||||
| 約 定 担 保 |
質権 | 債務者(設定者)から使用・収益権を奪う (優先弁済権+(留置的効力∨直接取立権)) |
占有の継続 | ||||
| 抵当権 | 債務者(設定者)から使用・収益権を奪わない (優先弁済権+追及権) |
登記 | |||||
第1に,物的担保の内包は,換価・処分権を有する物権かどうかではなく,債権の掴取力に質的な強化が認められているかどうかで決定される。すなわち,一定の債権(被担保債権)に,事実上または法律上の優先弁済権(他の債権者に先立って弁済を受ける権利)が認められるかどうかが物的担保かどうかを判断する基準となる。したがって,事実上の優先弁済権を有する留置権も,法律上の優先弁済権を有する先取特権,質権,抵当権も物的担保であるし,民法以外でも,例えば,明文上優先弁済権が認められている仮登記担保[仮登記担保法13条]も物的担保である。さらに,民法・特別法にも明文の規定はないが,判例によって優先弁済権が認められている譲渡担保も物的担保ということができる(〈最三判昭57・9・28判時1062号81頁,判タ485号83頁〉は,譲渡担保権者は,「優先的に被担保債務の弁済に充てることができる」としている。また,〈最二決平11・5・17民集53巻5号863頁〉は,譲渡担保権に基づく物上代位権の行使を認めている)。
第2に,物的担保は,債権の掴取力の質的な強化として,一定の債権に他の債権者に先立って優先弁済を受けることができるという効力が認められるに過ぎないので,債権が消滅すれば,債権の掴取力も消滅すること(物的担保の付従性)は当然のことであり,物的担保の付従性を特別扱いする必要がなくなる。このことは,先に述べたように,他人の債務を肩代りして弁済する責任に過ぎない人的担保の場合にも,債務が消滅すれば,債務を弁済する責任が消滅すること(人的担保の付従性)は当然のことであるのと同様であり,付従性は,人的担保,物的担保を問わず,すべての担保に共通する性質ということができる。
もっとも,広い意味での付従性に含まれる随伴性については,一定の留保が必要となる。その理由は,民法は,優先弁済権の処分(広い意味での譲渡)を認めており,ある債権の優先弁済権は,他の債権のためにそれを全部,または,一部譲渡することが可能である。そうだとすると,物的担保の随伴性は,必然的とはいえないことがわかる。なぜなら,優先弁済効つきの債権を譲渡する場合に,その優先弁済効だけを元の債権に譲り直すことによって,物的担保の随伴性を破ることができるからである。さらに,法定担保物権である先取特権の場合には,ある債権に優先弁済権を与えることが,弱者保護のためである場合があり,例えば,労働者が一定の範囲で給料債権を銀行に譲渡した場合に,債権の譲渡を受けた銀行が,給料債権の先取特権を行使できるかどうかについては,異論がありうるからである。このようにして,優先弁済権の譲渡を認める限度で,または,法定担保物権の優先順位の授与の理由に基づいて,物的担保の随伴性には例外が認められることになる。したがって,付従性とは異なり,物的担保の随伴性は,厳密な意味での通有性とはいえない。
第3に,物的担保の不可分性は,被担保債権が存続する限りで,物的担保の目的物に対する優先弁済権が存続するとする制度である。債権が消滅すると物的担保も消滅するというように,付従性が物的担保の従属性のうちの消極的な側面を明らかにするものであるのに対して,物的担保の不可分性は,債権が存続する限り,目的物に対する優先弁済権が存続するという,債権に従属する物的担保の積極的側面を明らかにするものである。
もっとも,一方で,優先弁済権の目的物が換価・処分されるまでは,債権が存続する限り優先弁済権は存続するが(物的担保の不可分性),他方で,物的担保が換価・処分されたが,被担保債権が完全には充足されずに,被担保債権が一般債権として存続するという場合には,不可分性は機能しないというという点に注意しなければならない。その理由は,前者の場合には,債権の優先弁済権が消滅していないのに対して,後者の場合には,換価・処分によって債権の優先弁済権はすでに満足を受けており,残りの債権は,優先弁済権のない一般債権として生き残っているだけであり,優先弁済権の作用としての不可分性は問題とならないからである。
このように考えると,物的担保の本質は,債権の掴取力に事実上,または,法律上優先弁済効が付与されたものであり,債権の他に,別個・独立の物権が存在するわけではないことが明らかとなる。すなわち,担保物権の性質は,物的担保が債権の消滅と運命を共にすることであり(付従性),または,債権が存続する限りで目的物から優先弁済権を得ることができるということであり(不可分性),いずれも,物的担保が独立・別個の権利ではなく,債権に従属する債権の優先弁済効に過ぎないことを物語っているのである。
本書は,創設された担保法の体系[加賀山・担保法(2009)]に基づいて記述された最初の教科書である。本書のように,人的担保と物的担保とを債権の掴取力の量的強化と質的強化(優先弁済権)として統一的に捉える考え方と,人的担保は債権・債務関係であり,物的担保は物権法に属すると考える従来の学説では,考え方に大きな違いが生じる。しかし,本書の考え方と従来の説との違いは,結論にはほとんど影響を与えない。したがって,従来の考え方を気にすることなく本書に従って学習しても問題は生じないはずである。そうはいっても,従来の考え方を理解しないでいるのは不安であろうから,以下において,本書の考え方と従来の考え方とを対比しておくことにする。
| 争点 | 通説の考え方 | 本書の考え方(加賀山説) | ||
|---|---|---|---|---|
| 人 的 担 保 |
保 証 |
債務とは「別個・独立」に保証債務という「債務」が存在すると考える(保証=債務)。しかし,本来の債務が消滅すると保証債務も消滅する(保証債務には付従性がある)ことを認めざるをえず,「別個・独立」の債務という出発点と矛盾している。 | 保証人は,債務者に代わって本来の債務を履行する責任を負うだけであり,本来の債務以外に保証債務という別の債務が存在するわけではない(保証=債務のない責任)。付従性は,「別個・独立」の債務が存在しないことの証拠に過ぎない。 | |
| 物 的 担 保 |
典 型 担 保 |
総 論 |
債権とは「別個・独立」に,担保物権という「物権」が存在すると考える(担保物権=物権)。しかし,債権が消滅すると担保物権も消滅する(担保物権は付従性がある)ことを認めざるをえず,「別個・独立」の物権という出発点と矛盾している。 | 担保物権とは,債権者の掴取力に優先弁済効が付加されただけであり,債権以外に担保物権という物権が存在するわけではない(担保物権=債権の優先弁済効)。担保物権の付従性は,「別個・独立」の物権が存在しないことの証拠に過ぎない |
| 留 置 権 |
占有を失うと消滅する点で,物権性は弱いが,同時履行の抗弁権とは異なり,対抗力(ただし,民法177条,178条には従わない)を有する物権である。 | 債権に関連して物を占有している場合に,債権者に与えられる引渡拒絶の抗弁権である(積極的な換価・処分権も有しないのであり,物権ではありえない)。しかし,それが対抗力を持つことによって事実上の優先弁済権が生じている。 | ||
| 先 取 特 権 |
債権に優先弁済効が与えられているのではなく,債権とは別個に存在する,優先弁済権という物権である。ただし,一般先取特権の場合は,物との関連がないため,物権というべきかどうかで説は分かれている。 | 担保目的の「保存」,「供給」,「環境提供」に関連する債権に対して与えられる法律上の優先弁済権。特に,物との関係を有しない一般先取特権が物権でないことは,明らかであると思われる。 | ||
| 質 権 |
留置的効力と優先弁済権を有する,債権とは別個の物権である。ただし,権利質の対象については債権を含むので,物権というべきかどうかで疑問が生じている。 | 債務者の使用・収益権を奪うことによって債務者に心理的圧力を加え,約定と公示を通じて与えられる債権の優先弁済効。債権を対象とする債権質が物権でないことは明らかであると思われる。 | ||
| 抵 当 権 |
登記によって優先弁済権を有する,債権とは別個の物権である。先に登記した抵当権は,後に設定された賃借権を覆滅できる。ただし,使用・収益に関与しない抵当権にそこまでの権利を与えるべきかどうかで疑問が生じている。 | 債務者の使用・収益権を奪うことなく,そこから債権の回収を図るとともに,約定と公示を通じて与えられる債権の優先弁済効。使用・収益権を奪うことはできないので,後に設定されたものを含めて,賃借権を覆滅できないと考える。 | ||
| 非 典 型 担 保 |
非典型担保においては,目的物の所有権が債権者に移転する(非典型担保=所有権が債権者に移転するもの)と考える。しかし,後順位担保権者の承認および帰属清算方式の不合理性の認識(実務上の忌避)を通じて,所有権は移転しないのではないのかとの疑問が生じている。 | 債権者は,担保目的物に対して,換価・処分権を有するだけであり,一時的にでも,目的物の所有権を取得することはないと考える。債権者が所有権を取得できるのは,買受人となった場合に限られる(担保=所有権が債権者に移転しないもの)。 | ||
*表8の対照表によって,従来の教科書が,誰にとっても難解である理由が明らかになったと思われる。従来の教科書が,ほとんどの学生を担保法嫌いにするほどに難解となっていた原因は,以下の通りである。
第1に,人的担保と物的担保を一方は債権に属するものとして,他方は物権に属するものとして,両者を非連続なものとして把握しているため,全体的な理解が困難となっている。
第2に,物的担保を物権として構成してきたために,物権だが債権に従属する(付従性)とか,物権だが,対抗要件については,民法177条に従わない(留置権,先取特権)とか,物権だが対抗要件は178条にも従わない(質権,抵当権の処分)など,原則よりも例外が多く,論理が迷路のように入り込んでいるため,教師も担保法を担当するのを敬遠しがちになるし,学生も担保法を苦手とする者が圧倒的な多数であるというひずみが生じてきた。
本書はそのようなひずみを是正するために,人的担保と物的担保とを架橋する担保法総論を創設することによって担保法の体系を完成するとともに,例外の少ない構造化された担保法の体系(担保法総論,担保法各論(人的担保,物的担保))を構築している。
本書を素直に読めば,担保法全体を有機的に理解することができる。本書の結論は,一部の問題(抵当権と賃借権との調和)で通説の見解と異なるが,その他については,結論は異ならない。したがって,ほとんどの人が途中で挫折するほど難解な通説を勉強する前に,本書で,例外のない担保法の新しい体系を理解しておけば,複雑怪奇な通説を理解するのも極めて容易となる。
つまり,本書を読めば担保法の体系と個々の問題に対する基本的な考え方をすべてマスターできるので,難解な通説をいちいち解説する必要はないと考えている。しかし,読者の中には,本書の立場と通説との違いが気になる人もいるであろう。そこで,本書と通説との違いを一覧表で示したのが上の*表8である。本書を読んでいて,その問題を通説はどのように説明しているのだろうかと不思議に思った場合には,この*表8に立ち返ってみればよい。
担保法の体系に関する以上の問は,これまで,誰も解いたことがない問題である。もしも,読者が,これらの問に答えることができたとしたら,それは,読者が,従来の民法学の水準を超えたことを意味する。
担保法が好きだという学生は稀である(筆者自身はそのような学生を一人も知らない)。担保法を喜んで教えたいという教師にもめったに会えない(民法の担当者を決める際に,担当するのを渋る教師が多いため,教務委員は常に苦労している)。それは,担保法が難解だからである。従来は,その原因は,「担保法の技術的性格」にあるとされてきた。しかし,「担保法の技術的性格」の内容を突き詰めていくと,その意味は,担保法には体系的な理論が存在しないので,暗記に頼るほかないということ,すなわち,担保法学が学問として未成熟であることの裏返しに過ぎないことがわかる。
ここでは,従来の学説が抱えている問題点を理解するとともに,通説がなぜそのような問題点を抱えているのか,その理由について検討する。
現行民法は,物的担保を物権編に編入しているが,物的担保のすべてを物権とすることには,以下に述べるように,もともと無理がある。したがって,物的担保を物権として理論を構築すると,原則よりも例外が多いという美しくない理論を構築せざるを得ないばかりでなく,物権の定義自体が破綻することを覚悟しなければならない。
第1に,通説は,担保物権☆を制限物権(換価・処分権を有する権利)として説明している。しかし,物権法の体系という視点からみると,留置権☆☆は,いかなる意味でも物権(本権)とはいえない。なぜなら,留置権は,物権法の特色といわれている物に対する使用・収益権も換価・処分権(優先権を伴う換価権)も,いずれも有していないからである。物権と債権とに関して厳格な峻別を行っているドイツ民法が,留置権(Zurückbehaltungsrecht)を物権ではなく「給付拒絶の抗弁権」として債務法の中で規定している[ドイツ民法273条]のはまさに正当である(ドイツ民法の研究者が多いわが国おいて,留置権を抗弁権ではなく,物権として認める学者が多いのは不思議でさえある)。
第2に,先取特権および質権については,確かに,それらは優先権を伴う換価・処分権を有するが,対抗要件が物権の対抗要件[民法177条,178条]に従っていないという問題点を抱えている。特に,一般先取特権は,目的物が特定せず,一物一権主義にも服さず,公示も必要としないのであるから,一般先取特権を物権と考えることには無理がある。むしろ,保護すべき特定の「債権について,債権者平等の原則の例外が認められているに過ぎない」[鈴木・物権法(2007)469頁]と考える方が,物権と考えるよりもはるかにわかりやすい。さらに,権利質については,目的物が無体財産(権利)であるため,物権の目的物は有体物に限る[民法85条]としていた現行民法の立法趣旨に反するため,現行民法の起草委員(梅謙次郎)も,無体物を対象とする権利質は物権ではないと言い切っていた[梅・要義巻二(1896)438頁]。
第3に,「物的担保制度の王座を占め」ている[我妻・担保物権(1968)6頁]とされる抵当権だけは,物権の対抗要件[民法177条]に従っているように見える。しかし,その処分(転抵当,抵当権の譲渡,抵当権の順位の譲渡,抵当権の放棄,抵当権の順位の放棄)については,債権譲渡の対抗要件の具備が必要とされており[民法377条],物権変動の対抗要件[民法177条]とは異なっている。さらに,抵当権の冒頭条文である民法369条2項は,地上権・永小作権を目的とする抵当権を規定しているが,無体物である権利を対象とするゆえに,現行民法の立法者自身も,物権としての「真の抵当権とはいい難い」としていた[民法理由書(1987)361頁]。
本書が,物的担保を物権の側面からではなく,債権の優先弁済権の側面から説明しようとする理由は,従来の学説に従って,物的担保を物権と考えると,以上のような解決不能な問題が生じるからである(*表9参照)。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 本質的権能 | 対抗要件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物権 (本権) |
所有権 | 使用・収益権も換価・処分権もある | 物権といえる | 動産:引渡し(民法178条) 不動産:登記(民法177条) |
||
| 制限 物権 |
用益 物権 |
地上権 | 使用・収益権のみがある | 物権といえるが,使用貸借,賃貸借との区別は微妙。自ら対抗要件を備えることのできる賃借権と考えた方がわかりやすい。 | 登記(民法177条にほぼ従っている) | |
| 永小作権 | ||||||
| 地役権 | ||||||
| 担保 物権 |
留置権 | 使用・収益権も,優先権を伴う換価・処分権もない | 物権とはいえない | 動産:占有の継続 不動産:占有の継続 |
||
| 先取特権 | 優先権を伴う換価・処分権がある(ただし,債務不履行がある場合に限る) | 債権とすることも,物権とすることも可能である。しかし,物権とすると,多くの例外を認めざるをえず,原則と例外とが逆転してしまう。 | 動産:不要(民法178条に反する) 不動産:不要(民法177条に反する) |
|||
| 質権 | 動産:占有の継続(民法178条に反する) 不動産:登記(抵当権と同じ) 債権:債権譲渡の対抗要件(物権とはいえない) |
|||||
| 抵当権 | 登記 抵当権の処分には,債権譲渡の対抗要件が必要 (民法177条に反する) |
|||||
このように,担保物権のすべてを物権として構成することは,学問的には,無理があるということになると,次の段階に移る必要がある。すなわち,留置権,先取特権,質権,抵当権をどのように構成すると,これら4つの権利を同じグループとして扱うことができるのかという問題を解かなければならない。
担保物権の通有性とは,担保物権がその類型の違いにかかわらず,共通に有している性質のことをいう。通有性は,物権編に編入されている4つの権利(留置権,先取特権,質権,抵当権)に「担保物権」という「共通の名称」を与えることの実質的理由を明らかにするための概念である。意外に思われるかもしれないが,実は,現行民法には「担保物権」という用語は存在しない。留置権,先取特権,質権,抵当権の4つの権利が,たまたま現行民法の物権編に編入されているという形式的な理由で,「担保物権」という用語法が定着しているに過ぎない。
したがって,「担保物権」という用語法を正当化する形式的な理由ではなく,正当化のための実質的な理由を示そうとすれば,担保物権の本質とか,担保物権の通有性(共通の性質)とかを明らかにする必要がある。本書の立場からすれば,通説が,民法の用語法には存在しない「担保物権」という言葉を使いたいのであれば,それ相応の理由をつけなければならないのであり,そうでなければ,担保物権という用語を使うことの学問的根拠が欠けることになるのである。
| 担保物権の通有性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 付従性 | 随伴性 | 不可分性 | 物上代位性 | ||
| 留置権 | ○ | △ (占有が必要) |
○ | × (法律上の優先弁済権なし) |
|
| 先取特権 | 一般先取特権 | ○ | △ (譲受人に依存) |
○ | × (必要なし) |
| 動産先取特権 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 不動産先取特権 | △ (売却代金,賃料は必要なし) |
||||
| 質権 | 動産質権 | ○ | △ (占有が必要) |
○ | ○ |
| 不動産質権 | △ (売却代金,賃料は必要なし) |
||||
| 権利質 | ×(必要なし) | ||||
| 抵当権 | 普通抵当権 | ○ | ○ | ○ | |
| 根抵当権 | △ (根抵当の場合,その確定前はなし) |
||||
ところが,現在の通説は,「担保物権の本質」といわれるものにせよ,「担保物権の通有性」といわれるものにせよ,その学問的な根拠を示すことに成功していない。それどころか,現在の学説は,担保物権の「通有性」といっても「必ずしも共通の性質とはいえず,いちおうの整理に過ぎない」([道垣内・担保物権(2008)8頁],[清水(元)・担保物権(2008)9頁])などと述べて,通有性の概念を等閑視する傾向にあり,この問題の学問的重要性についての認識を欠いているように思われる。
しかし,担保物権法の本質とか,共通の性質とかが示されないようでは,その分野は,学問として未熟であるといわざるを得ない。そこで,以下では,担保物権法が,なぜそのような事態に陥っているかについて,その理由を考察する。
現行民法においては,留置権,先取特権,質権,抵当権という4つの権利は,物権として位置づけられている(民法295条~398条の22)。このため,学説は,この4つの権利を「担保物権」と呼んでいる。ここでの問題は,この4つの権利を担保物権と呼ぶ場合,その物権は,物権全体の中でどのような地位を占めるのかというものである。
先に述べたように,物権(本権)全体は,大きく分けると,使用・収益も換価・処分もできるオールマイティな権利としての所有権と,その権能のうちの一部だけを有する物権(制限物権)との2つに分類される。制限物権の中では,さらに,使用・収益権能のみを有する用益物権(地上権,永小作権,地役権)と換価・処分権能を有する担保物権(留置権,先取特権,質権,抵当権)とに分類されている。
もしも,担保物権のすべてが本当に換価・処分権を有しているのであれば,これこそが,担保物権の本質であり,かつ,共通の性質ということができる。しかし,担保物権のうち,留置権は,対抗力を有する「引渡拒絶の抗弁権」に過ぎず,目的物に対して優先権を伴う換価・処分権を有していない。確かに,留置権には,形式的競売権[民事執行法195条]が与えられているが,これは,留置権者が長期間債権の弁済を受けることることができない場合に目的物の保管の負担が増大することの不都合を避けるためにのみ与えられものであって,優先権を伴うという本来の意味での競売権(優先権を伴う換価・処分権)を有していない。そうだとすると,物権の定義に則れば,留置権は,担保物権から除外するのが学問的には正しいということになる。そのことは,先に述べたように,概念に最も忠実なドイツ民法においては,留置権(Zurückbehaltungsrecht)を給付拒絶の抗弁権[ドイツ民法273条]として,物権法ではなく,債務法の中で定義していることからも窺い知ることができよう。
しかし,最初の目標に立ち返ると,ここでの目標は,現行民法に規定されている4つの権利に共通する性質を探し出し,それらをまとめる概念を見つけだすことである。したがって,担保物権とは,物権の権能のうち,換価・処分権能を有するものに限定されるという本質論を述べ,留置権をそこから追い出したのでは,4つの権利の共通の性質を見つけだし,4つの権利の本質を明らかにするという当初の目標から逸脱してしまう。
それでは,現行民法に規定されている4つの権利は,いかなる権利であるのか。4つの担保権のうちの留置権が優先権を伴う「換価・処分権能」を持たないこと,さらに,「使用・収益権」も有しないこと[民法298条2項,3項]も明らかとなると,問題は,重大な局面にさしかかることになる。なぜなら,第1に,担保物権全体の本質を優先弁済権を伴う換価・処分権を有する制限物権であるとの通説の議論は破綻していることになる。そればかりではない。第2に,留置権を含む4つの権利を担保物権として論じているわが国の担保物権法学は,実は,「担保物権とは何か」という実質的な理由,すなわち,学問の出発点を見つけだすことができないままに,迷走していることになるからである。
担保物権に共通の性質または共通の効力を目的物の優先権を伴う「換価・処分権」という概念を使って説明する試みは,優先権を伴う「換価・処分権」を有しない留置権を説明できず,その点で破綻していることが明らかになった。これは,担保物権法学がその出発点から危機的状況にあることを示している。そこで,担保物権としての統一性を確保するため,学説は,担保物権の本質論または効力論ではなく,担保物権の性質から,その共通性を明らかにすることを試みている。これが,担保物権の通有性の問題である。
担保物権の通有性(狭義)として挙げられている性質は,付従性(随伴性)と不可分性である。学説によっては,担保物権の通有性の中に不可分性を含めて議論するものもあるが,物上代位性は,担保物権の効力である法律上の優先弁済権の問題であり,留置権には物上代位性は認められない。そこで,本書では,物上代位性は,狭義の通有性には含めないことにする。
通有性のうち,最初の付従性については,実は,すべての担保物権が有しているのであるから,付従性は,最も典型的な担保物権の通有性といってよい。したがって,これを例外のない原則として受け入れるならば,担保物権の出発点は,まがりなりにも整うことになる。
ところが,通説は,付従性を担保物権の通有性とすることに,あらゆる面で抵抗を示す。抵当権の処分(転抵当,抵当権の放棄・譲渡,抵当権の順位の放棄・順位の譲渡)の箇所で抵当権の付従性を否定しようとしたり,根抵当権の箇所で,付従性を否定したりと,付従性を担保物権の通有性として認めることに極めて消極的である。
しかし,そのことが何を意味するかについて,通説は危機感を欠いている。もしも,担保物権の通有性が存在しないとしたら,担保物権という民法にない概念を1つのまとまりのある概念として認めることができなくなってしまう。例えば,新しいタイプの担保が考案された場合に,それを担保物権の問題として取り扱うべきなのか,それとも,保証の一種として,多数当事者の債権・債務関係の問題として取り扱うべきなのかが不明となってしまう。このことは,学問領域の決定基準が存在しないことを意味し,学問としての担保物権法の崩壊を意味する。
担保物権という学問対象の領域の境界(外延)として,留置権,先取特権,質権,抵当権という要素を例示するのはたやすい。しかし,学問対象の内容を性質(内包)として定義できなければ,民法に規定のない担保の仕組み,たとえば,譲渡担保,仮登記担保等の非典型担保,相殺,代理受領,振込指定を担保物権と呼べるかどうかを決定することはできない。
つまり,担保物権については,学問上の明確な定義すら存在しないにもかかわらず,担保物権の通有性をないがしろにする学説が多数を占めているというのが現状なのである。確かに,担保物権の通有性は,通常の債権とは一線を画するものであり,担保物権ならではの性質であると考える学説[近江・講義Ⅲ(2007)12頁]も存在する。しかし,そのような学説も,付従性の例外を認めているために,厳密な通有性を明らかにするものとはなっていない。そればかりでなく,担保物権の通有性は,「必ずしも共通の性質とはいえず,いちおうの整理に過ぎない」と述べて,この考え方を重視しない学説([道垣内・担保物権(2008)8頁],[清水(元)・担保物権(2008)9頁])の方が最近の通説となりつつある。しかし,それは,まさに,担保物権法の学問としての自立を放棄するものであろう。
それでは,どうして,従来の学説は,担保物権の通有性について,本格的な研究を行わずに済ませてきたのか。それが,ここで取り上げる問題である。
その答えは,実は,単純である。もしも,付従性,随伴性,不可分性を担保物権の通有性として認めると,担保物権の物権性・独立性がことごとく否定されるからである。付従性とは,担保物権が債権に従属することを意味し,随伴性とは,担保物権が債権の移転に従属することを意味し,不可分性とは,債権がある限り担保物権としての効力が保たれるという意味であり,いずれも,担保物権といわれるものが独立の権利ではなく,債権に従属する権利であることを明らかにするものだからである。
この問題解決のための解決法は一つではない。しかし,本書のように,民法に規定された4つの権利をまとまりのあるものとするために,物的担保の本質を優先弁済権(事実上の優先弁済権と法律上の優先弁済権を含む)であるとし,共通の性質としての通有性を付従性と不可分性に求めるなら,少なくとも,学問としての担保法の破綻を免れることが可能となる。
以上の点を踏まえるならば,人的担保を債権法の問題とし,物的担保を物権法の問題として考察する従来の考え方と決別し,両者ともに債権の掴取力の強化の問題であると考える方が,論理的な破綻を免れるばかりでなく,原則と例外のバランスがとれたわかりやすい理論を展開できることが理解できるであろう。
担保物権に関する通説は,留置権,先取特権については,物権としての性質が希薄であることを認めつつ,抵当権は,担保物権の「王座を占めるもの」[我妻・担保物権(1968)6頁]であり,換価・処分権を有し,登記を対抗要件とする典型的な物権であると考えている。
しかし,抵当権が物権であるという点について,現行民法の立法者も,それほどの確信を持っていたわけではない。なぜなら,抵当権の最初の条文である民法369条2項の抵当権は,立法者によれば,不動産を目的とするものではなく,権利(地上権,永小作権)を目的とするものであるため,物権としての「真の抵当権とは言い難い」[民法理由書(1987)361頁]とされていたからである。
以下の表は,抵当権が物権だとすると,説明が困難な論点をリストアップしたものである。抵当権を物権であると考える場合には,以下の問題点をすべてクリアする必要があることを認識すべきであろう。
| 通説が嫌がり,触れたがらない論点 | 通説の立場 | 抵当権を債権の優先弁済効に過ぎないとする本書の立場 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 民法369条2項の抵当権の性質 | 地上権,永小作権も不動産上の物権だから抵当権の目的としても不都合はない(ただし,このことを公言する教科書は少ない。有体物ではない権利の上の抵当権について論じはじめると,混乱が生じるからであろう)。 | 地上権,永小作権は,不動産でなく,権利である。現行民法の立法者も,民法369条2項の抵当権は,「真の抵当権とは言いがたい」☆☆としていた。さらに,権利の上の担保権は,質権でなければならないはずであるが,立法者は,地上権,永小作権の上の質権を否定的に解していた。この問題について,立法者の見解に触れた教科書がないのは,民法369条2項の抵当権が不動産ではなく,権利を目的とするものであり,物権とはいえないからであろう。 |
| 2 | 民法372条によって準用される304条(物上代位)の性質 | 民法304条が準用される結果,抵当権の目的物の範囲として,金銭,その他の物にも及ぶことがある(このことを公言する教科書も少ない。物上代位の目的は有体物ではない債権であることがほぼ確定しているからであろう)。 | 抵当権の目的物は,上記のように,地上権,永小作権のような財産権でも,また,第三債務者に対する債権でもよい(物上代位の場合)。その理由は,抵当権が物権ではなく,債権の掴取力に与えられた優先弁済権であり,抵当権を有する債権者は,債権者代位権の場合と同じく,第三債務者に対して債務名義なしに請求することができるからである。 |
| 3 | 民法377条の抵当権の処分の対抗要件 | 民法177条によって登記が対抗要件となるが[民法376条],例外的に,債務者に対する通知が要求されているに過ぎない[民法377条](この理由を説明している教科書は存在しない。物権法からの説明は不可能だからであろう)。 | 物権行為とされる抵当権の処分行為について,債権譲渡の対抗要件の規定である民法467条が適用されるのは,抵当権が物権ではなく,債権の優先弁済権に過ぎないからである。抵当権の順位は,民法373条の類推によって登記が必要とされるほか,債権の優先弁済権の処分(譲渡)に債権譲渡の対抗要件の規定[民法467条]が必要とされるのは,むしろ,当然である。 |
| 4 | 民法339条により,後で登記された先取特権が先に登記された抵当権に優先するという問題 | 民法339条の規定は,物権秩序を害するものであり,削除されることが望ましい(このことを公言する学者は少数である。しかし,抵当権を物権と考える通説の本音であろう)。 | 債権の優先弁済権の根拠は,物権秩序に従っているのではなく,債権秩序を制御する信義と公平の観点に基づき,目的物との牽連性の有無,強弱によって判断されている。目的物の価値の維持・増加に寄与した債権者には,必然的に優先弁済権が与えられ,その優先順位は,物権法秩序とは反対に,後の保存者は先の保存者に優先するという原則[民法330条1項2文]に従うのである。 |
担保法に関する通説を理解することが困難である理由は,結局のところ,通説の出発点が,「保証債務は,主たる債務と別個・独立の債務であるが,この債務は主たる債務に付従する」とか,「担保物権は,被担保債権とは別個・独立の物権であるが,この物権は,被担保債権に付従する」という,論理学的には完全に破綻した命題によって成り立っているからである。
通説が論理的に行き詰っている点は,多岐にわたるが,上記の*表11は,そのような通説の破綻の中から,物権と信じて疑われていない抵当権に関しても,それが物権だとすると,説明が困難な問題を取り上げ,本書の立場から批判したものである。通説を説明する教師は,これらの点に反論できないことを知ってか知らずか,本能的に,これらの話題から逃れようとする傾向にある。
このような話題について,教師に質問すると,「勉強が足りない。質問をする前に,教科書をよく読みなさい」とか,「そのような瑣末な問題は,取り上げるに足りない」とか,「ピントはずれの質問だ」とかいわれるので,深入りしない方が得策である。そのような勧告を無視して,質問を続けると,「そんな問題であれこれ悩むのは,センスが悪い証拠だ」といわれたり,挙句の果てに,「変な学生だ」と思われたりするのが落ちである。教師も自分が理解できない通説・判例を苦労して教えているのであるから,傷口に塩を塗りこむような質問は控えるのが,大人のマナーというものであろう。どうしても,質問して議論を深めたいと思うのであれば,質問の相手が,通説に対する破壊的な学説[加賀山・担保法(2009)]に接したことがあるかどうかを事前に見極めてからにするのが賢明である。
第1編 担保法総論
物的担保が物権と考えられてきた理由は,物的担保には,直接取立権,追及効,優先弁済権という債権には見られない特別の性質があるからだと考えられてきたからである。
しかし,債権も,それを保全するために,実は,債権の効力そのものとして,潜在的な換価・処分権(掴取力)のほか,直接取立権,追及効,優先弁済権を有している。それが,これから紹介する債権者代位権・直接訴権(直接取立権を実現するメカニズム),詐害行為取消権(追及効を実現するメカニズム),同時履行の抗弁権・不安の抗弁権(事実上の優先弁済権を実現するメカニズム),相殺(法律上の優先弁済権を実現するメカニズム)である。
債権自体にこのような効力が備わっているとすると,物的担保を,あえて,物権と考える必要はなくなる。なぜなら,物的担保の効力である直接取立権,追及効,優先弁済権を債権の効力として説明することができるからである。
これまで,債権者代位権,詐害行為取消権,同時履行の抗弁権,相殺について,これらの方法・手段(メカニズム)が,すでに,物的担保の本質である債権の掴取力の強化を実現しているとの観点から分析されたことはなかった。本書は,まさに,このような観点から,債権の対外的効力といわれてきた債権者代位権,詐害行為取消権の特徴を明らかにするとともに,同時履行の抗弁権,相殺の担保的機能に着目して,債権の中に,すでに,優先弁済権を認める規定が存在していることを明らかにする。
債権質の場合に質権者が債務者に対する債務名義なしに,第三債務者に対して直接取立ができる[民法366条]のは,質権が物権だからであると考えられてきた。しかし,債権の内部においても,債務者に対する債務名義なしに直接第三者に対して直接取立を請求できる制度が存在する。それが,債権者代位権,および,その進化系としての直接訴権である。
それでは,債権者代位権や直接訴権は,なぜ,債務者に対する債務名義なしに,直接第三債務者に対する取立が可能なのであろうか。ここでは,債権の取立権の一例として債権者代位権(action oblique)を取り上げ,債権執行との違いを明らかにするとともに,債権者代位権の進化系としての直接訴権(action directe)の2つのタイプ(完全直接訴権:保険金の直接請求権[自賠法15条,16条]と不完全直接訴権[民法613条])を取り上げ,取り立て権として見た場合の債権者代位権と直接訴権との異同を明らかにする。そして,このような問題の探求を通じて,債権における直接取立権がどのような要件で実現されるのかを理解する。
債権は,債務不履行になった場合に,掴取力によって債務者の財産に対する換価・処分権を獲得する。ただし,それは,強制執行という手続きによって初めて実現されるものであり,債権に固有の権利ではないのであるから,物的担保の効力(債務名義を必要とせずに債権の回収を実現できるという効力)を債権の掴取力から導くことはできないというのが従来の考え方である。なぜなら,従来の考え方によれば,債権によって債務者の財産を換価・処分するためには,第1に,債権の存在を明らかにする債務名義が必要であり,その債務名義に基づいて,債務者の財産に対する差押えが可能となり,その差押えの効力として,債権者は,初めて,債務者の財産の換価・処分ができると考えるからである。
しかし,この考え方では,債権者の対外的効力であり,ドイツ民法には存在せずフランス民法に由来する債権者代位権(action oblique),直接訴権(action directe),詐害行為取消権(action paulienne)を説明することができない。
その理由は,この節で第1に取り上げる「債権者代位権」に関しては,債務者が無資力の場合に限ってではあるが,債権者は,債務名義を必要とせず,直接第三債務者に対して債務の弁済を債権者に対してするよう請求できるからであり,第2に取り上げる「直接訴権」または第3に取り上げる「債権者代位権の転用」の場合には,債務者が無資力でなくても,債権者の債務者に対する債権(α債権)と債務者の第三債務者に対する債権(β債権)との間に密接な関係があるならば,債権者は,債務名義を必要とせず,直接第三債務者に対して,β債権の弁済を債権者にするよう請求できるからである。なお,追及効を実現する詐害行為取消権については,次の第2節で詳しく説明する。
この節で最初に取り上げる「債権者代位権」(action oblique)とは,債権者が,自己の債権を保全するために,債務者に属する権利を債務者に代わって行使することのできる制度である[民法423条]。
本来,債務者が自己の財産をどのように管理するかは債務者の自由であるが,資力が悪化した債務者は往々にして債権回収に不熱心となる。そこで,債務者の無資力を要件として債権者が債務者の権利を代位行使することが認められているのである。
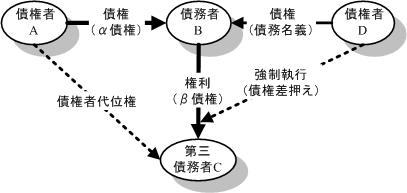 |
| *図11 債権者代位権と債権差押えとの対比 |
債権者代位権の特色は,強制執行手続きとは異なり,債務者に対する債務名義[民事執行法22条]なしに第三債務者に対して,裁判外の請求または訴え(給付訴訟としての代位訴訟)を提起できる点にある。そして,債権者が第三債務者を相手取って訴えを提起した場合の判決の効力は,債務者(中間債務者)に対しても既判力を生じるとされている[民事訴訟法115条1項2号]。
従来は,そのような直接取立権は,債権「質」の権利者だけが,物権の効力としてできるに過ぎない[民法366条]と考えてきたが,債権者代位権,直接訴権の研究が進展するにつれて,債権(α債権)を有する債権者は,債権者の資格で債務者の債権(β債権)を直接に取り立てる権利を有していることが明らかになっている。
債権者は,差押えなしに,債務者の財産(債権)を直接に取り立てることができる。そのため,物的担保者が,差押えなしに,担保権の実行ができることをわざわざ物権の効力として説明する必要はなく,債権の執行として,第三債務者に対して直接取立権があることを説明することが可能となる。
確かに,債権者の債権の弁済期が到来しない間は,保存行為を除いて,裁判上の請求しかなしえない(民法423条2項,非訟事件手続法72条~74条(裁判上の代位))。しかし,債権者が裁判上の代位の申請を行ってそれが認められて,債務者に告知されたときは,債務者は,その権利の処分ができなくなるという効力が生じる[非訟事件手続法76条]。このことからも,債権者代位権は,単に債務者に属する権利を保全するため,かつ,総債権者の利益のために行使する権利にとどまるものではなく,債務者に代わって,相手方に対して直接取立てを行使できる債権者の権利であり,債権担保権として位置づけられるべきことになる。
この意味でも,債権者代位権の構造と,債権の差押えとの違いを理解することが重要となる。
債権者が債権者代位権を行使するためには,民法423条の解釈上,以下の要件が満たされていなければならない。
第1の要件の解釈として,通説・判例〈大判明39・11・21民録12輯1537頁〉は,債権者代位権の行使要件として,債務者が無資力であることという要件を付加している。
もっとも,金銭債権ではなく,特定物債権が問題となる債権者代位権の転用の場合には,判例は,無資力要件を不要としている〈大判明43・7・6民録16輯537頁など〉。以下の判例〈最一判昭50・3・6民集29巻3号203頁〉は,金銭債権についても,無資力要件を緩和したものと考えられているが,事案をよく検討してみると,本権の被担保債権は,金銭債権(残代金債権)ではなく,むしろ,特定物債権(登記受領請求権)として構成すべきであり,債権者代位権の「転用」に当たる事例であり,無資力要件を緩和したものではないことがわかる。
| 最一判昭50・3・6民集29巻3号203頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第12事件 買主〔B,C〕に対する土地所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一部の者〔Y〕が右義務の履行を拒絶しているため,買主が,相続人全員による登記手続義務の履行の提供があるまで代金全額について弁済を拒絶する旨の同時履行の抗弁権を行使している場合には,他の相続人〔X1~X5〕は,自己の相続した代金債権を保全するため,右買主が無資力でなくても,これに代位して,登記手続義務の履行を拒絶している相続人〔Y〕に対し買主の所有権移転登記手続請求権を行使することができる。 |
|
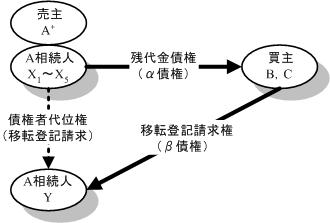 |
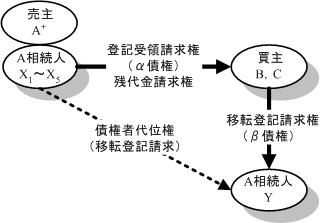 |
| *図12 判例の立場 金銭債権を被保全債権として構成するため, 債権者代位権の無資力要件がネックとなる。 |
*図13 本書の立場(転用事例の活用) 登記関連の請求権を被保全債権として構成するため, 転用事例として無資力要件を不要とすることができる。 |
債務者自身が権利を行使した後は,債権者は,重ねて権利を行使することができない。しかし,いったん,債権者が債権者代位権の行使を債務者に通知するか,債務者が債権者の行使を知った後は,債務者は,その権利の処分ができなくなると解している〈最三判昭48・4・24民集27巻3号596頁〉。
このような判例の立場によると,債権者代位権の場合には,債権者代位権の要件が満たされて(債務名義は不要である),その行使が行われると,差押えと同様の効果が認められることになる。一般的に,担保権に基づく債権執行の場合にも,債務名義によらず,法定文書の提出に基づく,執行裁判所の差押えによって開始するが[民事執行法193条2項による143条の準用],債権者代位権の場合にも,債権者代位権の行使という簡易な手続きとして同様の結果が認められていると考えることもできよう(後述の「包括担保権説」に対する部分的肯定)。
債権者の債権の弁済期が到来しない間は,保存行為を除いて,裁判上の請求しかなしえない([民法423条2項],[非訟事件手続法72条~74条(裁判上の代位)])。しかし,先にも述べたように,債権者が裁判上の代位の申請を行ってそれが認められて債務者に告知されたときは,債務者は,その権利の処分ができなくなるという効力が生じる[非訟事件手続法76条]点が重要である。このことも考慮して,上述の債権者代位権の「差押と同様な効果」が正当化されているからである。
一身専属性については,学説において,判断基準についてさまざまな説がある。この問題を理解する上で,遺留分減殺請求権について,一身専属性が認められ,債権者代位権の行使が否定された最高裁判決〈最一判平13・11・22民集55巻6号1033頁〉が参考になる。
債権者代位権は,債権者が自らの債権を保全するために債務者の権利を債務者に代わって行使する制度であるから,債権者が行使できる債権の範囲は,債権者の債務者に対する債権(α債権)の範囲と債務者の第三債務者に対する債権(β債権)の範囲とによって二重に制限される。
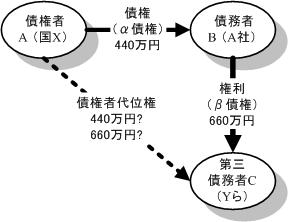 |
最三判昭44・6・24民集23巻7号1079頁 民法判例百選Ⅱ第11事件 債権者〔国X〕が債務者〔A社〕に対する金銭債権〔α債権:約440万円〕に基づいて債務者の第三債務者〔Yら〕に対して有する金銭債権〔β債権:約660万円〕を代位行使する場合においては,債権者は自己の債権額〔約440万円〕の範囲においてのみ債務者の債権〔β債権〕を行使しうると解すべきである。 |
| *図14 債権者代位権を行使できる範囲 |
債権者代位権の行使の範囲が二重に限定されることは,当然のように思われる。しかし,後に述べる債権者代位権の転用の場合には,平成11年の最高裁の大法廷判決〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉は,抵当権者の債務者(設定者)に対するα債権(担保価値維持請求権)は目的物の引渡しを含むものではないにもかかわらず,債務者の第三者に対するβ債権(目的物の引渡請求権)を代位行使できるという初歩的なミスを犯したという例がある。なお,最高裁は,平成17年判決〈最一判平17・3・10民集59巻2号356頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第88事件)〉で先の債権者代位権による明渡構成を放棄している。ただし,抵当権に物権的請求権としての明渡請求権を認めている点では,再び誤りを犯しているので,この点については,「債権者代位権の転用」の最後の箇所(*4C)で詳しく説明する。いずれにせよ,債権者代位権の行使の範囲については,特に,債権者代位権の転用に関して,最高裁でも間違えることがあるほどであるから注意をする必要がある。
「債権者代位権」(action oblique)は,フランス民法を参考にしてわが国に導入された制度であり,ドイツ民法には存在しない。ドイツ民法に存在しない理由は,ドイツでは,債権差押えの制度が発達しており債権者代位権の必要性を認めなかったからである。むしろ,フランスでは,債権差押えの制度が未発達であったために債権者代位権の制度が発達した。
この節で第2に取り上げるのは,債権者代位権(action oblique)の進化系として,特に保険法の分野で世界をリードするフランス起源の直接訴権(action directe)の制度である。
わが国では,直接訴権の制度は教科書レベルではあまり取り扱われていないが,民法613条が直接訴権の制度を取り入れたものであることは,現行民法の起草委員であった[梅・要義巻三(1897)659頁]も認めている。また,自賠法16条が直接訴権の制度を継受したものであることも明らかである(詳しくは,加賀山茂「民法613条の直接訴権《action directe》について(1)」阪大法学102号(1977年3月)65-105頁,(2・完)阪大法学103号(1977年10月)87-136頁を参照のこと)。
そればかりでなく,民法の解釈論として難解な部分を理解するためには(例えば,民法443条における2文の意味を調べたり[梅・要義巻三(1897)131頁],後に述べる平成20年最高裁判決〈最三判平20・2・19民集62巻2号534頁(平成20年度重要判例解説・民法11事件)〉を理解したり,同じく,後に述べる民法613条1項2文の反対解釈の是非を論じる場合など),直接訴権の考え方をマスターすることが必要である。直接訴権の考え方は,確かに,通常の教科書には載っていない考え方ではあるが,民法を深く理解する上で重要な地位を占めるものなので,この考え方をマスターするための努力を惜しむべきではない。
直接訴権の考え方をマスターするには,以下の2点を理解することが必要である。
第1は,債権者代位権と直接訴権との相違点について理解することである。前者(債権者代位権)の場合には,債権者は,自己の債権(α債権)を保全するため,債務者の債権(β債権)である他人の債権を自己の名で行使するに過ぎない。したがって,他人の権利を行使することを正当化するための無資力要件が必要である。これに対して,後者(直接訴権または債権者代位権の転用)の場合には,α債権とβ債権が密接に関連していることが必要であるが,債務者の債権(β債権)を自己の名で,かつ,自己の権利として行使することができるのであり,無資力要件は必要とされない。
| 分類 | 意味 | β債権の移転 | 典型例 | 条文 | 無資力 要件 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債権者代位権 (action oblique) |
通常の 債権者代位権 |
α債権の債権者Aは,債務者Bの債権(β債権)を自己の名で,他人の権利として代位行使 | β債権は,Aに移転しない | 金銭債権の代位行使 | 民法423条 | 必要 |
| 債権者代位権 の転用 |
登記請求権の代位行使 | 不要 | ||||
| 直接訴権 (action directe) |
完全直接訴権 | α債権の債権者Aは,債務者の権利(β債権)を自己の名で,自己の権利として行使 | β債権は,最初から当然にAに移転する | 被害者の保険会社に対する直接訴権 | 自賠法16条 | 不要 |
| 不完全直接訴権 | β債権は,意思表示により,Aに移転する | 賃貸人の転借人に対する直接訴権 | 民法613条 民法314条, 民法105条 |
第2は,直接訴権には以下のような2つの種類があること,すなわち,完全直接訴権(action directe parfaite)と不完全直接訴権(action directe imparfaite)とがあることを理解することである。両者の違いは,前者(例えば自賠法16条)が,債権(α債権)の発生の時点で,すでに,目的債権(β債権)が債権者に移転するのに対して,後者(例えば民法613条)は,債権者の意思表示によってはじめてβ債権が債権者に移転する点にある。ただし,直接訴権が発生した後の効果については,両者に違いはない。
直接訴権の制度は,現在では,特に,保険法の分野において完全直接訴権(action directe parfaite)として発展しており,交通事故の被害者が,加害者に対する損害賠償請求で勝訴するという手続き(債務名義)なしに,加害者の加入している保険会社に対して,保険金の支払いを直接請求できるという制度へと結実した。わが国も,これに倣って,自賠法16条が,被害者の保険会社への直接請求(直接訴権)を認めている。この直接訴権は,自賠法15条の差押え的効力とあいまって,被害者に対して,債権者代位権に優先する効力を有している。
自賠法16条に基づく被害者の保険会社に対する直接請求権は,フランスの直接訴権(完全直接訴権)をわが国に導入したものである。
自賠法(自動車損害賠償保障法) 第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求)
①第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは,被害者は,政令で定めるところにより,保険会社に対し,保険金額の限度において,損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
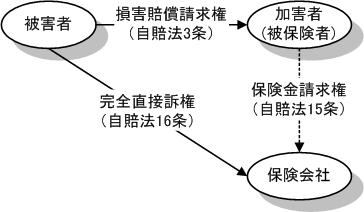 |
| *図15 自賠法16条の直接請求権の構造 |
自賠法16条の直接訴権を理解するためには,自賠法3条の被保全債権(α債権)の存在,加害者の保険会社に対する保険金請求権(β債権)の存在を前提としつつも,事故が発生した段階で,β債権は,被害者に当然に移転し,保険会社は,被保険者(加害者)に対して保険金の支払いを禁じられるという点に注目しなければならない[自賠法15条の反対解釈]。事故が発生した時点で権利の主体はBからAへと変更され,したがって,β債権は,Aへと移転する。β債権を取得したAのBに対するα債権は,本来なら代物弁済として消滅するはずであるが,直接訴権の場合には,民法613条2項に明文の規定があるのと同様,債権者を保護するために,α債権も消滅せずに連帯保証責任として存続する。したがって,もしも,加害者BがAに損害賠償責任を履行した場合には,連帯保証人としてのBは,はじめて,保険会社Cに対して,保険金の請求をすることができるようになるのである[自賠法15条]。
自賠法(自動車損害賠償保障法) 第15条(保険金の請求)
被保険者は,被害者に対する損害賠償額について自己が支払をした限度においてのみ,保険会社に対して保険金の支払を請求することができる。
自賠法16条に関しては,2008(平成20)年に最高裁が注目すべき判決を下しているので,簡単に紹介しておく(詳細については,尾島茂樹「判批」ジュリ1376号(平成20年度重要判例解説)95頁(民法第11事件)を参照のこと)。
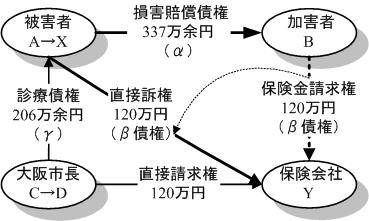 |
最三判平20・2・19民集62巻2号534頁 平成20年度重要判例解説・民法11事件 (事案)自賠法16条に基づく被害者の保険会社への直接訴権と,老人保健法(現在は,高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいて被害者に対して医療行為をした市町村長の保険会社への直接請求(老人保険法41条1項,現行法(高齢者の医療の確保に関する法律)58条1項)とが競合した。最高裁は,被害者の直接訴権と市町村長の直接請求について比例配分による取扱いをしてきた従来の保険実務を否定し,以下のように判示した。 (判旨)自賠法16条に基づく直接訴権は,医療を行った市町村長の直接請求(被保険者〔被害者〕が第三者〔加害者〕に対して有する損害賠償の請求権〔自賠法3条〕を取得する)に優先する。 |
| *図16 直接訴権と債権者代位権の競合 〈最三判平20・2・19民集62巻2号534頁〉 |
このような結果は,債権差押えによる方法では実現できないのであり,フランスで発展した直接訴権の考え方を採用した場合にのみ正当化が可能である。なぜなら,債権間の密接な関連性を理由に認められる直接訴権は,そのような密接な関係を有しない債権者代位権に優先すると考えられているからである。
本件の場合,被害者が保険会社に対して行使する権利は,β債権と密接な関係を有する自動車事故による損害賠償債権(α債権)に基づいて発生する完全直接訴権である。これに対して,被害者に対して治療を行った市町村長が医療保険法41条1項,現行法(高齢者の医療の確保に関する法律)58条1項で取得される直接請求権は,市町村長が被害者に対して有する診療債権(γ)を被保全債権とし,被害者の直接訴権を目的債権(β債権)とする債権者代位権の行使に過ぎないと考えられる。その理由は,第1に,β債権は,事故の当時から当然に被害者のみに帰属しており,自賠法15条は,被害者の権利を確保するために,保険会社が被保険者である加害者に対する支払いをも制限している。第2に,これに対して,被保全債権(γ債権)と自賠法16条に基づくに基づく保険金請求権(β債権)との間には,被害者の損害賠償債権(α債権)と自賠法16条に基づく保険金請求権(β債権)ほどの密接な関係はないからである。
被害者に対して治療を行った市町村長は,確かに,医療保険法41条1項,現行法(高齢者の医療の確保に関する法律)58条1項で取得する。しかし,その理論的根拠は,市町村長が被害者に対して有する診療債権(γ)を被保全債権とし,被害者の直接訴権を目的債権(β債権)とする債権者代位権の行使に過ぎないと考えられる。このため,自賠法16条に基づく直接訴権は,医療を行った市町村長の直接請求に優先することになるのである。
民法613条(賃貸人の転借人に対する直接訴権)は,債権者代位権から進化したフランス民法の直接訴権を取り入れた制度である[梅・要義巻三(1897)659頁]。
民法613条の直接訴権は,自賠法16条の完全直接訴権に較べると不完全直接訴権(action directe imparfaite)といわれる制度であり,前者(完全直接訴権)が事故の発生のときから,β債権が債権者である被害者へと移転するのに対して,後者(不完全直接訴権)の場合には,β債権が債権者(賃貸人)に移転するのは,賃貸人Aが転借人Cに請求した時点である。したがって,AがCに直接請求するまでは,BはCに転貸賃料を請求できるし,また,CはBに対して適法に転借料の支払いをすることができる。しかし,賃貸人Aが転借人Cに直接請求を行使すると,それ以降については,完全直接訴権の同様と同様の結果が生じる。すなわち,賃借人Bは,賃貸人Aに賃料を支払って被保全債権を消滅させない限り,転借人Cに転貸賃料を請求することはできないし,転借人Cも,賃借人Bに対して転借料の支払いをすることが禁じられる。
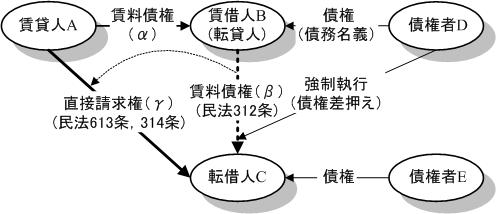 |
| *図17 民法613条の直接請求権の構造 |
なお,不完全直接訴権(民法613条)のメカニズムに関する詳しい説明は,[加賀山・担保法(2009)69-73頁]を参照のこと。
わが国の従来の学説は,フランスで発展し,自賠法を含めて保険法の分野で大きな影響力を有している直接訴権(action directe)の考え方を十分に理解していないのが現状である。
しかし,直接訴権の要件としての被保全債権(α債権)と目的債権(β債権)とが,密接な関係にある場合には,わが国の通説・判例ともに,「債権者代位権の転用」という法理を使って,債権者代位権の要件としての「無資力要件」を緩和し,かつ,債権者代位権とは異なり,債権者が債務者の権利を代位行使するのではなく,債権者が自らの名で債務者の権利を行使すること,すなわち,直接訴権の制度と同じ結果を,それとは気づかずに採用している。したがって,直接訴権の考え方を理解した後であれば,「債権者代位権の転用」の意味,要件を理解することが容易となる。
登記請求権の代位行使の場合には,α債権とβ債権との間に密接な関係(両者ともに登記請求権であり,しかも,β債権がα債権の前提となっている)ため,無資力要件が緩和されている。
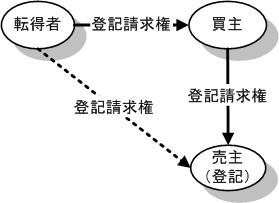 |
大判明43・7・6民録16輯537頁 民法判例百選Ⅱ第13事件 甲(売主)が其所有に属する土地を乙(買主)に売渡し,乙は更に之を丙(転得者)に売渡したる場合に於て,孰れも其売買に因る所有権移転の登記を為さざるときは,丙(転得者)は民法第423条に依り,乙(買主)に対する登記手続の請求権を保全する為め乙(買主)の甲(売主)に対する登記手続の請求権を行使し得るものとす。 民法423条は債権者が保全せんとする債権に付き別に制限を設けざるを以て,同条の適用を受くべき債権は,債務者の権利行使に依りて保全せらるべき性質を有すれば足り,其債務者の資力の有無に関係を有すると否とは必ずしも之を問ふの要なし。 |
| *図18 債権者代位権の転用例(その1) 登記請求権 〈大判明43・7・6民録16巻537頁 民法判例百選Ⅱ第13事件〉 |
明治43年の大審院判例の場合には,転得者は,自らの名で,しかし,他人である買主の権利を行使しているに過ぎないため,あくまで債権者代位権の転用の場合であって,直接訴権の域にまでは達していない。
直接訴権の場合には,債権者は,自らの名で,自らの権利として,売主に対して中間省略登記を請求できるという場合に利用できる。もっとも,わが国の実務では,中間省略登記は認められていない。しかし,中間省略登記ができる例外的な場合も存在しており,その場合には,まさに,直接訴権が認められることになる。
賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求(明渡請求)の場合には,債権者代位権の転用として,無資力要件が緩和されている。
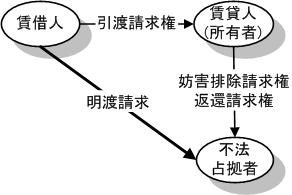 |
大判昭4・12・16民集8巻944頁 民法判例百選Ⅱ〔第5版〕第12事件 土地の賃借人は,賃借権を保全する為,賃貸人たる所有者に代位して,土地を不法に占拠せる第三者に対し,妨害排除の請求権を行使することを得るものとす。 最二判昭29・9・24民集8巻9号1658頁 建物の賃借人が,賃貸人たる建物所有者に代位して,建物の不法占拠者に対しその明渡しを請求する場合には,直接自己に対して明渡しをなすべきことを請求することができる。 |
| *図19 債権者代位権の転用例(その2)賃借人の不法占拠者に対する妨害排除請求権 〈大判昭4・12・16民集8巻944頁,最二判昭29・9・24民集8巻9号1658頁〉 |
|
昭和29年の最高裁判決の場合には,賃借人は,自らの名で,かつ,自らの権利として不法占拠者に対して,明渡請求が認められている点で,単なる債権者代位権の転用にとどまらず,直接訴権への進化という現象が生じている。
抵当権の執行を妨害する不法占拠者に対して,占有を伴わない物的担保権者としての抵当権者は,抵当権設定者が有する不法占拠者に対する所有権に基づく妨害排除請求権・返還請求権を代位行使して,不法占拠者に対して抵当権者への返還請求ができるかどうかが問題とされた。
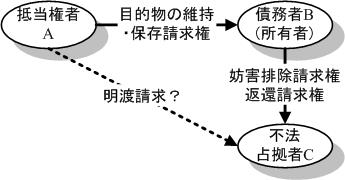 |
最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁 第三者〔C〕が抵当不動産を不法占有することにより,競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど,抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者〔A〕の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,抵当不動産の所有者に対して有する右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するため,所有者〔B〕の不法占有者〔C〕に対する妨害排除請求権を代位行使することができる。 |
| *図20 〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉 |
抵当権とは,抵当権設定者の目的物に対する使用・収益権を奪わずに,目的物の価値から優先弁済権を受けることが権利であり,抵当権者は,いかなる意味でも,自らが抵当目的物を占有する権限を有しない(民法369条1項)。つまり,抵当権者は,占有訴権を有しないのであり,以下に述べる理由により,占有訴権の進化系としてのいわゆる物権的請求権をも有しないと考えるべきである。少なくとも,抵当権者Aは,抵当権設定者(債務者または物上保証人)に対して,目的物の引渡を要求する権利を有しない(β債権を利用するに値するα債権が存在しない)のであるから,抵当権者は,Bの権利(β債権)を代位行使することはできないのである。
本件は,抵当権に対する執行妨害の事例である。執行妨害に対する対策は,あくまで,民事執行法で解決すべき問題であり,実体法の法理をまげてまで解決すべき問題ではない。民事執行法の度重なる改正により,現在では,抵当権者は,以下のように,第三者による執行妨害に対して,必要かつ十分な措置を講じることができるようになっており,占有を伴わない権利しか有しない抵当権者に目的物の明渡請求を認める必要性は存しない。
債権者代位権を理論的にどのように位置づけるか,無資力要件は必要か,債権者代位権を行使する債権者に優先弁済権を認めるべきかどうかについては,学説上,以下のような厳しい対立が見られる。
| 学説 | 主張者 | 学説の概要 | 問題点 | 本書の立場 |
|---|---|---|---|---|
| 責任財産 保全制度説 (通説・判例) |
我妻栄ほか | 債権者代位権は,債務者の責任財産を保全するための制度であり,その効果は総債権者のために生じる。 | 金銭債権については,債権者代位権を行使する債権者が,債務者に代わって取り立てた金銭を債務者に返還する債務について,その債務と債権とを相殺すること等によって,「事実上の優先弁済権」を取得することをやむをえないとする。 | 金銭債権について,債権者代位権を行使する1人の債権者が事実上の優先弁済権を有することを認めるのであれば,それは,すべての債権者のための責任保全の制度であるとの理論の出発点から逸脱しており,整合的な理論とはいえない。 |
| 簡便な債権 回収手段説 |
天野弘「債権者代位権における無資力要件の再検討(上)(下)」判タ280号(1972)24頁,282号(1972)34頁 | 債権者代位権を,迂遠な強制執行手続きを回避する簡便な債権回収手段として位置づける。 | 債務者の無資力要件を必要なしとする。 | 債権者代位権について,債務名義を要しない簡易な債権担保執行として位置づける点は評価できるが,次に述べるように,債権者代位権の行使要件のうち,無資力要件を一律に不要とすることは,行き過ぎであろう。 |
| 包括 担保権説 |
[平井・債権総論(1994)260頁以下] | 債権者は,債務者の財産に対して一種の「包括担保権」を有し,その実行方法として債権者代位権がある | 金銭債権者が債務者の有する金銭債権を代位行使した場合の優先弁済の結果を,債権者代位権の中心的機能として正面から肯定し,これを積極的に正当化しようとする。 | 債権者代位権が包括担保権の実現方法であるということから,一般的に,債権者代位権には無資力要件が不要であるとか,優先権を付与することができるという考え方は,理論的には正当化できない。 |
| 間接訴権・ 直接訴権 区別説 |
[加賀山・担保法(2009)] | 債権者代位権と直接訴権とを区別し,前者の場合には,無資力要件を必要とし,優先弁済権を有しないが,後者の場合には,債権間に密接な関係があるため,無資力要件を必要とせず,事実上の優先弁済権も有するとする。 | 現行民法の立法者は,民法613条の直接請求権は,被保全債権(α債権)と目的債権(β債権)とが密接な関係にある場合であり,フランスの直接訴権の制度を採用したものであると考えていた[梅・要義巻三(1897)659頁]。しかし,この考え方は,わが国ではいまだに普及しておらず,この制度を理解できる人が少ない。 | 債権者代位権はドイツ民法にはないフランス民法由来の制度であり,フランスでは,債権者代位権(間接訴権)と直接訴権は,それぞれ独自の制度として発展してきた。わが国の民法613条も,また,自賠法15条も,直接訴権の制度を採用しており,直接訴権の制度の研究の進展が望まれる。 |
債権者代位権は,債務者に対する債務名義を必要としない点で,債権差押えとは異なり,むしろ,担保権の実行手続[民事執行法193条]と類似する。この側面を重視する点で,本書の立場は包括担保権説[平井・債権総論(1994)260頁以下]に近い。しかし,だからといって,債権者代位権の行使について,無資力要件を不要とし,かつ,優先弁済的効力を認めるというのは,行き過ぎであろう。本書のように,債権者代位権と直接訴権とを区別し,一方で,前者(債権者代位権)の場合には,あくまで債務者の権利を債権者の名で行使するのであるから債務者の無資力要件を必要とする。しかし,他方で,後者(直接訴権,債権者代位権の転用)の場合には,被保全権利と目的債権との間の密接な関係(牽連性)を要件としており,被保全自らの権利として自らの名で法定移転した権利を行使するのであるから,無資力要件は必要でなく,また,事実上の優先弁済権を認めることができるというように,類型的な考察を行うべきであろう。
債権は,当事者間でのみその効力を有するというように相対的であるのに対して,物権は,排他的な支配権であり,誰に対しても主張できる対世権であると考えられてきた。したがって,物が第三者に譲渡されたような場合に,その物に対する権利を主張できること,すなわち,追及効は,物権の特質であり,債権にはない性質であるとされてきた。例えば,抵当権者が債務者に対する債務名義なしに,第三者に譲渡された抵当不動産に対して追及できるのは,抵当権が物権だからであると考えられてきた。しかし,物権とされる先取特権については,追及効が否定されている[民法333条]。留置権や動産質権も,占有を失うと,第三者への追及ができなくなる([民法302条],[民法352条])。反対に,賃借権のように,債権であっても,登記をすると,第三者に対して追及効を有する場合がある[605条]。
ここでは,債権の体外的効力とされている詐害行為取消権が,受益者・転得者の悪意を要件として,債権に追及効を与える制度であること,抵当権が登記(すべての人を悪意とする仕組み)を通じて,追及効を有しているのと連続していること,受益者・転得者は,抵当権の場合の第三取得者と類似の立場に立つに至ることを明らかにする。
債権の相対性を貫くと,債権の掴取力は,債務者の責任財産に限定されるはずである。しかし,債務者が債権者を害することを知って(害意),その責任財産を逸失させた場合には,債権者は,受益者・転得者が悪意である限り,債務者が逸失させた財産に対して,どこまでも追及し,債権の掴取力を及ぼすことができる[民法424-426条]。
このことは,抵当権者が,登記があることを条件に,目的不動産の第三取得者に対して,どこまでも追及できるのと同様である。現行民法に詐害行為取消権(債権者取消権ともいう)[民法424-426条]が存在することによって,これまで,物権に特有の現象として説明されてきた追及効は,決して,物権に特有の効力ではなく,債権の掴取力も,追及効を持つ場合があることがわかる(詐害行為取消権[民法424-426条]=債権の追及効)。
もっとも,債権の掴取力が追及効を持つのは,債務者に害意があり,かつ,受益者・転得者が悪意の場合に限定される。これに対して,物権とされる抵当権の場合には,登記さえあれば第三取得者の善意・悪意とは無関係に追及効が生じるのであるから,詐害行為取消権による追及効と抵当権の追及効とは次元が異なるようにも見える。しかし,抵当権が登記されている場合には,抵当権が登記されている物件を取得する第三者(第三取得者)は,抵当権の存在を知ることができる。そうすると,抵当権の追及効も,物権だから当然に生じるというわけではなく,登記を通じて,第三取得者の悪意が推定されているからに過ぎないと考えることも可能である。
このように考えると,詐害行為取消権による債権の追及効が,債務者の害意を要件とし,受益者・取得者が悪意であることによって成り立っているのと,物権であるとされている抵当権の追及効が,抵当権の登記を要件とし,第三取得者の悪意の推定によって成り立っている(登記があっても,第三取得者が抵当目的物を善意で時効取得した場合には,追及効も消滅する[民法397条]。*第5章第5節9C参照)のと,大差がないともいえる。
詐害行為取消権の追及効と抵当権の追及効とをパラレルに考えることができるようになると,抵当権の場合に,追及を受ける第三取得者が物上保証人と同じ立場に立たされるのと同様,追及を受ける悪意の受益者・転得者も,同様にして,物上保証人と同じ立場に立たされることになることがわかる。したがって,いずれの場合も,目的財産の取得者は,前主に対して追奪担保責任([民法568条]または[民法562条])を追及できることも理解できる(詐害行為取消権[民法424-426条]=債務と責任との分離)。
このようにして,詐害行為取消権についての深い理解が得られると,抵当権を学習する際にも,抵当権が設定された物件の第三取得者の法的地位についての理解が容易となる。そればかりでなく,詐害行為の取消しにおける「取消し」の意味が,破産法上の「否認権」[破産法160-176条]に通じることが理解できるばかりでなく,対抗問題における否認権説における「否認」(例えば,[民法37条5項]にある「否認」は,対抗不能と同じ意味である)と同じであることも理解できるようになる(詐害行為取消権[民法424-426条]=責任財産の逸失の対抗不能)。
このようにして,詐害行為取消権を題材として,追及効のプロセスを①債務と責任の分離,②詐害行為取消権(否認権)の行使,③責任分離の対抗不能というように理解を進めていくと,不動産二重譲渡の対抗問題と,詐害行為取消権における対抗不能説との共通性も理解できようになり,最終的には,民法の中で,理解が最も困難といわれている「対抗不能の一般理論」(詳しくは,[加賀山・対抗不能の一般理論(1986)6頁以下参照]) をマスターすることも可能となるのである。
詐害行為取消権は,ローマ法のパウルスの訴権(actio Pauliana)の系統を引く,フランス民法典1167条(action paulienne)をわが国の民法が継受したものである。パウルスの訴権(旧民法では,これを廃罷(はいひ)訴権としていた)とは,債権者が自己の債権を保全するため,債権の一般的担保を構成する債務者の財産(patrimoine)を不当に減少させる債務者の詐害行為を取り消す裁判上でのみ行使しうる権利,すなわち,訴権であるとされている。
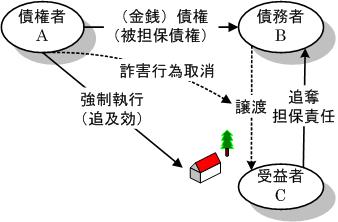 |
| *図21 詐害行為取消権の法的性質(債権に与えられた追及効) |
わが国の民法は,これを詐害行為取消権としている[民法424条~426条]。しかし,ここでいう「取消し」とは,通常の「取消し」とは以下の点で異なっている。
第1に,制限行為能力者(未成年者,成年被後見人,被保佐人,被補助人)の法律行為の取消し(民法5条以下),瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫による意思表示)の取消し(民法96条)の場合には,取消しができるのは,当事者の一方,または,その承継人であって,決して第三者ではない。ところが,詐害行為取消権の場合に取消しを行うのは,当事者の一方ではなく,第三者である債権者である。したがって,この問題は,単純な取消しの問題ではないことが明らかである。フランスでは,この権利(パウルスの訴権)は,第三者の権利であるため,当事者間の詐害行為が第三者である債権者に対抗できない問題(対抗不能の問題)であると解されている(*表14参照)。
すなわち,債権者は詐害行為を取消しによって無効とする必要はなく,詐害行為の効果のうちの,債権者を害する部分(責任財産の逸失)のみを対抗できないとできればそれでよい。つまり,債権者は,債務者の責任財産に対して掴取力を有しているのであり,たとえ,詐害行為によって債務者の責任財産が受益者や転得者へと移転しても,それを名目上のものに過ぎないとみなし,詐害行為によっても債務者の財産は逸失していないとして(責任移転の対抗不能),それらの者に対して直接に掴取力を及ぼすことができればよい。債権者を保護するためには,それ以上の保護(詐害行為自体を取消しによって無効とするすること)を必要としないのである。
| 大分類 | 中分類 | 典型例 | 第三者対抗力 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|---|
| 無効な法律行為 | 法律行為の取消し | 制限行為能力者の法律行為 | 第三者に対抗できる | 民法5条以下 |
| 強迫による意思表示 | 民法96条3項の反対解釈 | |||
| 詐欺による意思表示 | 善意の第三者に対抗できない | 民法96条3項 | ||
| 法律行為の無効 | 公序良俗違反 | 第三者に対抗できる | 民法90条 | |
| 通謀虚偽表示 | 善意の第三者に対抗できない | 民法94条2項 | ||
| 無権代理 | 善意・無過失の第三者に対抗できない →表見代理 |
民法109条,110条,112条 | ||
| 有効な法律行為 | 不動産の二重譲渡 | 不動産の売買 | 登記を具備した第三者に対抗できない | 民法177条 |
| 責任財産の逸失 | 詐害行為 | 債権者に対抗できない | 民法424条 |
第2に,詐害行為の「取消し」によっても,詐害行為自体が無効になるわけではなく,先に述べたように,詐害行為自体は有効のままである。詐害行為取消しとは,名前は「取消し」となっているが,旧民法で「廃罷訴権」(対抗不能訴権)とされていたものを現行民法に取り入れる際に,わかりやすい言葉に改めようとして,かえって誤解を招く「取消し」という用語法を選択したために混乱が生じているのである(詐害行為取消権の最近の学説の中には,「廃罷訴権」の名称を復活させるべきだとするものもあるほどである[佐藤・詐害行為取消権(2001)419頁])。本書の立場では,後に述べるように,民法37条5項と同じく「否認」という用語を用いるのが適切であるということになる。
そこで,詐害行為取消権にいう「取消し」が本来の取消しではなく,詐害行為が第三者である債権者に対抗できなくなるという意味を理解するために,詐害行為取消権(詐害行為対抗不能訴権)と,対抗問題の典型例である二重譲渡の対抗問題とを対比してみよう。
詐害行為取消権と不動産の二重譲渡の対抗問題とは,一方は債権の問題であり,他方は,物権の問題ではあるが,対抗問題という観点から見ると,両者は非常によく似ている。登記を先に得た第2買主を債権者と考え,売主を債務者と考え,登記を怠った第1買主を受益者と考えると,その関係が明瞭となる。不動産の二重譲渡において,登記を先に得た第2買主は,第1売買が有効であるにもかかわらず,第1売買の所有権の移転の効果を否認することができる結果,第1買主は第2買主に対抗できなくなる(民法177条)のと同じである。第1買主は,売買契約が有効であるにもかかわらず,所有権の移転を受けないのであるから,売主に対して,追奪担保責任を追及できる。詐害行為取消権の場合も同様である。すなわち,詐害行為それ自体は有効であるが,受益者・転得者は,債権者によって強制執行を受けることを受忍せざるを得ず,結局,所有権を剥奪される。そして,転得者は受益者に,受益者は債務者に対して追奪担保責任を追及できる。
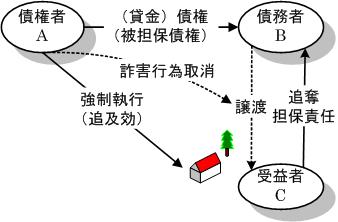 |
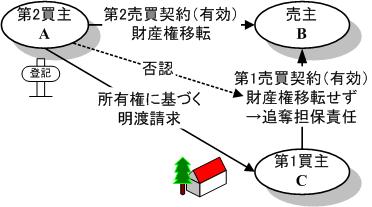 |
|
| *図22 詐害行為取消権と否認 | *図23 不動産二重譲渡と対抗問題と否認 |
このように考えると詐害行為取消権の意味は,詐害行為全体を取り消すことではなく,詐害行為自体は有効であるが,債権者を保護するために,詐害行為による財産の移転にもかかわらず,債務者の責任財産は逸失していないとみなし,名目上は受益者,転得者の財産へと移転している財産に対して,債権者が目的物に対して強制執行を実現できるという制度にほかならないことが理解できる。フランス民法典において,詐害行為取消権とは,当事者間では有効な詐害行為が第三者である債権者に対抗できなくなる制度であると説明されているのは,以上のことを意味する。また,このことは,詐害行為による名目的な財産移転について,債権者を保護するために,責任財産の移転を無効とするドイツの責任無効の制度とも共通点を有する。
詐害行為取消権の名前に惑わされ,これを債権者が詐害行為を取り消して無効とし,目的物を債務者に返還させるものと考えてはならない。債務者は訴訟当事者とはならず,詐害行為取消訴訟の既判力は債務者には及ばないのであるから,債務者は受益者や転得者に移転した財産の返還を請求する権利も有しないし,返還を受ける義務もない。詐害行為は有効であり,それにもかかわらず,債権者の強制執行によって目的財産を追奪された受益者・転得者は,債務者に対して売主の担保責任を追及することができるのである。
詐害行為取消権の法的性質が詐害行為の債権者への対抗不能の問題であること,債権者は,受益者・転得者に対して,譲渡された目的物に対して追及効を有することが明らかとなった。
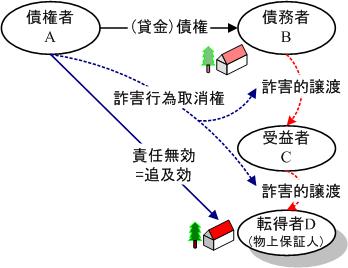 |
| *図24 詐害行為取消権における受益者・転得者の地位 |
このことは,一方で,債権の掴取力の強化を意味するが,他方で,詐害行為の受益者・転得者の地位を危うくさせることを意味する。なぜなら,詐害行為によって目的物を取得した受益者・転得者は,債権者による強制執行を受忍せざるを得ないことになり,債務者に対して売主としての責任を追及できるにしても,いわゆる物上保証人の地位に甘んじなければならないことになるからである。
対抗不能と相対取消しといわれているものとの比較をしてみると,変形規則となっており,同じことの言い換えに過ぎないことに気づくことができる。対抗不能(Yは,Aを具備しないと,Bをもって,Xに対抗することができない)は,否定形であり,一種の受動態である。これに対して,相対的取消しとか,否認権(Xは,Aを具備すると,Bにつき,Yの権利を否認できる)といわれているものは,肯定形であり,一種の能動態である。
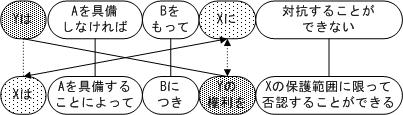 |
| *図25 対抗不能と否認との書換え原則 |
不動産の二重譲渡を2つの形で述べて見て,それを比較してみよう。
詐害行為取消権についても,2つの形で書くことができるので,比較してみよう。
このように比較してみると,フランス法起源の詐害行為取消権がフランスにおいて,対抗不能訴権であるとされていることがよく理解できると思われる。
詐害行為取消権に関する学説は,取消しの意味を通常の法律行為の取消しと同様に考えるという単純な考え方から始まって,債務者を被告とする必要がないことから,逸失財産を回復させることだけを目標とする請求権説を経て,債務者の責任財産からの逸失を債権者に対抗できないとして,債権者に目的財産の追及効を認めるという,対抗不能の考え方へと進化してきたといえよう。その流れを表にまとめたのが,以下の*表15である。
| 取消の意味 | 相手方 | 取消の効果 | 実効性の確保 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債権者・債務者間 | 債務者・受益者間 | 債権者・受益者間 | ||||
| 形成権説 | 詐害行為を債権者が取り消す | 債務者と受益者の双方 | 詐害行為は無効 | 詐害行為は無効 | 詐害行為は無効 | 債権者は,転得者に対して,債権者代位権に基づいて目的物の返還を求める給付訴訟を提起しなければならない。 |
| 請求権説 | 逸失財産の取戻しを請求できる権利 | 受益者のみ | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効 | 債権者は,受益者だけを被告として訴えを提起できる。しかし,債務者には何らの影響も与えないことになるため,登記名義を債務者に回復させたり,動産の占有を債務者に移転させたりすることを強制できないはずで,「取消し」によって,総債権者のために逸失財産を回復して,強制執行を可能にすることを説明できない。 |
| 折衷説 (相対的取消) |
債権者が詐害行為を取り消すとともに,債権者が転得者に対して逸失財産の取戻しを請求できる権利 | 受益者のみ | 詐害行為は有効? | 詐害行為は有効 | 詐害行為は無効 | |
| 責任説 | 責任財産の移転の取り消しを訴求する(責任無効を求める取消訴訟) | 債務者と受益者 | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効・責任無効 | 詐害行為は有効・責任無効 | 債務者に対する債権の満足のために,受益者または転得者の手中にある詐害行為の目的物に対して強制執行をすることができる旨の判決(執行認容判決)を債務名義として,強制執行を行わなければならない。 |
| 訴権説・対抗不能説 | 債務者の責任財産から逸失したという効果のみが債権者に対抗できない | 受益者 | 詐害行為は有効だが,責任移転の効力が否認される(対抗不能) | 詐害行為は有効 | 詐害行為は有効だが,責任移転の効力が否認される(対抗不能) | 債権者は,受益者または転得者へと移転した財産に対して,債務者に対する債務名義でもって(訴権説)または債務名義も必要とせず(債権者代位権の場合と同じ=加賀山説),詐害行為取消権の要件が充足されていることを証明するだけで,受益者または転得者を訴えることによって,債権の強制履行を実現することができる。 |
詐害行為取消権の学説史は,わが国における学説がドイツ法とフランス法にどのように影響されてきたかを知る上で興味深い例を提供している。また,解釈のあり方も,文言解釈から制度の趣旨を生かした解釈まで,さまざまな解釈が出揃っており,1つの条文の解釈をどのようにすべきかを考える上でも重要な問題を提起している。それぞれの学説について詳しい検討したものとして,[佐藤・詐害行為取消権(2001)]がある。
詐害行為取消権は,フランス民法起源の制度であり,旧民法においては,取消権とは異なることが,「廃罷(はいひ)訴権」という言葉で示されていた。このことを熟知していた現行民法成立直後の判例〈大判明44・3・27民録17輯117頁〉は,民法424条の詐害行為取消権の取消しの意味が,通常の法律行為の取消しとは異なることを,以下のように,明確に認識していた。
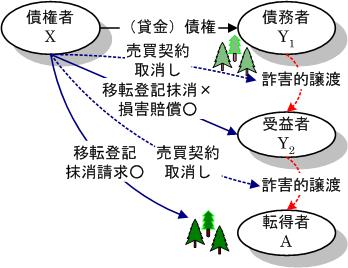 |
1. 民法第424条に規定する詐害行為廃罷訴権は,債権者を害することを知りて為したる債務者の法律行為を取消し,債務者の財産上の地位を其法律行為を為したる以前の原状に復し,以て債権者をして其債権の正当なる弁済を受くることを得せしめて其担保を確保するを目的とするは,此訴権の性質上明確一点の疑を容れざる所なり。 2. 詐害行為の廃罷は民法が法律行為の取消なる語辞を用ゐたるに拘はらず,一般法律行為の取消と其性質を異にし,之が効力は相対的にして何人にも対抗すべき絶対的のものに非ず。 3. 債権者が債務者の財産を譲受けたる受益者又は転得者に対して訴を提起し之に対する関係に於て法律行為を取消したるときは,該財産の回復又は之に代るべき賠償を得ることに因り其担保権を確保するに足るを以て,特に債務者に対して訴を提起し其法律行為の取消を求むるの要なきものとす。 4. 債務者の財産が受益者の手を経て転得者の有に帰したる場合に債権者が受益者に対して廃罷訴権を行使し法律行為を取消して賠償を求むると転得者に対して同一訴権を行使し直接に該財産を回復するとは全く其自由の権内に在るものとす。 |
| *図26 大判明44・3・27民録17輯117頁 民法判例百選Ⅱ第14事件 |
以上が,大判明44・3・27民録17輯117頁における判例の考え方であり,これが,強固な判例理論としてわが国の実務をリードしてきた。もっとも,現行民法の「取消」という用語法に引きずられて,詐害行為取消権の意味を,債務者の詐害行為の責任移転の効力が債権者に対抗できなくなることであるという意味ではなく,「相対的取消し」であるとの結論に落ち着いている点が惜しまれる。なぜなら,この考え方には,以下の2つの問題点があるからである。
第1は,判例は,詐害行為取消しにおける「取消し」を相対的な取消しとするが,その意味があいまいである。取消しによって債務者・受益者間の契約はどうなるのか。取消しを主張できるのは,法律行為の当事者ではなく第三者である債権者のみであるが,債権者の取消しによって法律行為はやはり無効となるのか(相対的無効),それとも,取消しによっても依然として有効であるのか(有効な契約の債権者に対する対抗不能),いずれかが明らかではない。
第2に,詐害行為の取消しによって債権者が転得者に対して請求できることは何かが明らかではない。特に,詐害行為取消権の効果は,債務者に及ばないという判例理論によると,詐害行為の取消しによっても,債務者は目的物の受取りを拒絶することができることになり,このことに,目的物の直接の明渡しや登記請求を否定する判例理論(〈最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁〉など)が結びつくと,取消しによって債務者の財産を債務者に復帰させるという判例理論の中核部分が実現不能となってしまう。
このような問題点を回避するためには,本書のように,詐害行為取消権の意味を,債権者を害することを知ってなされた責任財産の移転の効力を債権者は否認することができると解するのがよい。すなわち,詐害行為の責任移転の効力は債権者に対抗できないと解し,債権者は,悪意の受益者,または,悪意の転得者の財産に対して,債務者の債権の範囲内で,転得者の名義になっている債務者の責任財産に対して強制執行ができると解するのが妥当である。
|
このように考えると,大判明44・3・27民録17輯117頁の事案と,問題解決の方向は,以下のように明確となる。 1. Xと債務者Y1との関係について:XはY1に対して債務不履行に基づく救済手段(強制履行,損害賠償,解除)を行使しうるが,Y1は無資力となっていることが多く,本件のように,重要な責任財産である山林がY2,Aへと譲渡された場合には,債務不履行では,十分な救済を期待できそうにない。 2. XとY2との関係について:目的物はすでにAへと譲渡されており,XはY2には,もはや追及力を有しない。したがって,不法行為に基づいて,Y2に対して損害賠償を請求することができるだけである。 3. XとAとの関係について:詐害行為取消権は,債権における追及効を実現するものだが,それは,抵当権等と同様,目的物の価値を把握するに過ぎないのであり,目的物の競売代金から配当を受けることはできるが,目的物の引渡,移転登記請求まで請求できるわけではない。 |
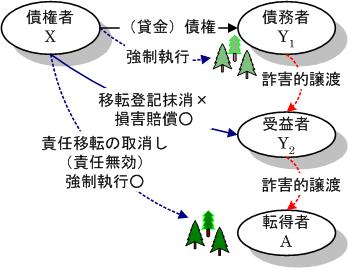 |
| *図27 本書による 大判明44・3・27民録17輯117頁の解釈 |
特定物債権(代物弁済による不動産の引渡債権)に基づく詐害行為取消権の行使の可否が問題となった事例について,最高裁は,債務者がその目的物を処分することによって無資力となった場合には,たとえ,金銭債権に転化していなくても,特定物債権者は債務者の処分行為を詐害行為として取り消すことができると判示している〈最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁〉。
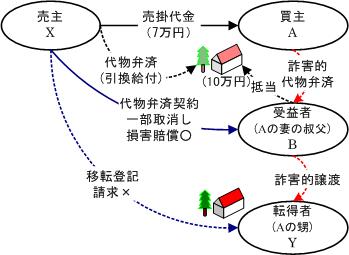 |
1.特定物引渡請求権を有する者も,その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には,右処分行為を詐害行為として取り消すことができるものと解すべきである。 2. 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に,その取消は,家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限って許されると解すべきである。 3. 前項(2.)の場合において,取消の目的物が1棟の家屋の代物弁済で不可分のものと認められるときは,債権者は一部取消の限度で価格の賠償を請求するほかはない(補足意見がある)。 |
| *図28 最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁 民法判例百選Ⅱ第15事件 |
昭和36年の最高裁判決〈最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁〉は,特定物債権を保全するために詐害行為取消権を行使することは認められないとする大審院の判例〈大判大7・10・26民録24輯2036頁,大判昭8・12・26民集12巻2966頁〉を変更し,特定物債権のためにも詐害行為取消権の行使が認められるとした。しかし,その理由には,特定物債権も,「究極において損害賠償債権に変じる」のであるから,金銭債権と異ならないことが付け加えられている。そして,この最高裁判決の補足意見は,特定物債権は,詐害行為時までに金銭債権に変化している必要があるとしている。通説は,これを受けて,取消権行使時までに金銭債権に変じていればよいとしている[我妻・債権総論(1954)180頁]が,被保全債権が金銭債権となっていることは要件とされている。
|
債権者代位権が特定物債権を保全することができるのとは対照的に,詐害行為取消権は,あくまで,金銭債権を保全するために,目的物に対して追及して,目的物に対して強制執行ができる権利である。したがって,詐害行為取消権をもって,目的物の返還請求や移転登記請求を求めることはできないと考えるべきである〈最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁〉。 本件の場合には,受益者に対して,価格の賠償を求めるほかはないことになる。そして,受益者に対する価格賠償は,不法行為に基づく損害賠償に他ならないと考えるべきであろう。 |
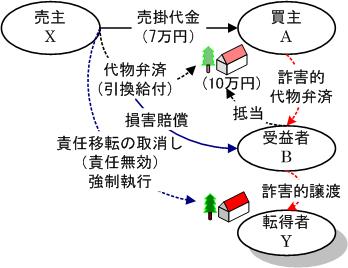 |
| *図29 本書による 最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁の解釈 |
債務者が十分な資力を有しない状態で,一人の債権者〔Y〕だけが主要な財産から弁済を受けたために,他の債権者〔X〕が実質的に債務の履行を受けられなかったという場合,弁済を受けることができなくなった債権者〔X〕が受益者〔Y〕の行為を詐害行為取消権によって取り消した場合,詐害行為取消権の効果は,「すべての債権者の利益のためにその効力を生じる」[民法425条]とされている。そのため,受益者〔Y〕も,債務者に対する強制執行手続きにおいて,債権額に応じた配当要求をして,受益の一部を保持することができるかどうかが問題となる。
この点について,昭和46年最高裁判決〈最二判昭46・11・19民集25巻8号1321頁〉は,債権者〔X〕が,債務者「A〕の受益者〔Y〕に対する弁済行為を取り消し,かつ,取消による弁済額の支払を求める詐害行為取消訴訟手続において,受益者〔Y〕が,弁済額を債権者〔X〕の債権額と自己の債権額とで按分し,受益者〔Y〕に対応する按分額につき,支払を拒むことはできないとして,債権者でもある受益者〔Y〕による分配請求に基づく抗弁を排斥している。
最二判昭46・11・19民集25巻8号1321頁 民法判例百選Ⅱ第19事件
本来,詐害行為取消権は,債務者の一般財産を保全するため,とくに取消債権者において,債務者受益者間の詐害行為を取り消したうえ,債務者の一般財産から逸出したものを,総債権者のために,受益者または転得者から取り戻すことができるものとした制度である。
もし,本件のような弁済行為についての詐害行為取消訴訟において,受益者である被告が,自己の債務者に対する債権をもって,いわゆる配当要求をなし,取消にかかる弁済額のうち,右債権に対する按分額の支払を拒むことができるとするときは,いちはやく自己の債権につき弁済を受けた受益者を保護し,総債権者の利益を無視するに帰するわけであるから,右制度の趣旨に反することになるものといわなければならない。
ところで,取消債権者が受益者または転得者に対し,取消にかかる弁済額を自己に引き渡すべきことを請求することを許すのは,債務者から逸出した財産の取戻しを実効あらしめるためにやむをえないことなのである。その場合,ひとたび取消債権者に引き渡された金員が,取消債権者のみならず他の債権者の債権の弁済にも充てられるための手続をいかに定めるか等について,立法上考慮の余地はあるとしても,そのことからただちに,いわゆる配当要求の意思表示に,所論のような効力を認めなければならない理由はないというべきである。
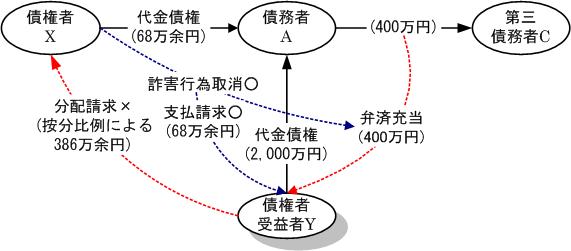 |
| *図30 最二判昭46・11・19民集25巻8号1321頁 民法判例百選Ⅱ第19事件 |
債権の抜け駆け的な回収を計ろうとする債権者が競合した場合に,公平の観点から問題の解決を行うことが,法の最も重要な役割であろう。Yは,債権者を害することを知りながら,抜け駆け的に債権回収を計ろうとした受益者であり,民法425条の趣旨に反する行為であることは明らかである。しかし,昭和46年の最高裁判決のように,競合する債権者Yを排除して,詐害行為取消権を行使するXに,その債権全額についての回収を認めるのでは,結果的に,Yに遅れてやってきた債権者Xによる抜け駆け的な債権回収を許すことになってしまう。その結果が,民法425条の趣旨に反した不公平なものであることは明らかである。
抜け駆けを企図したYの制裁として,Yの債権者としての主張を排斥する最高裁の義憤は理解できるが,その結果は,結局,正義の実現にも,公平の実現にも寄与しておらず,法の解釈を誤っているといわざるを得ない。公平の観点からは,民法425条の趣旨に立ち返り,抜け駆けをしようとした債権者Yと,民法424条を利用して公然と抜け駆けを主張する債権者Xとを平等に取り扱い,Yの債権額に応じた按分額についての支払い拒絶の抗弁を認めるのが妥当である。
詐害行為取消権は,債権者代位権とは異なり,目的物の直接の明渡しや登記請求に利用することができないことを明らかにしたのが,昭和53年最高裁大法廷判決〈最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁〉である。
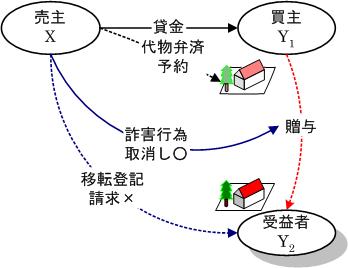 |
1. 特定物引渡請求権(特定物債権)は,窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから,債務者の一般財産により担保されなければならないことは,金銭債権と同様であり,その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には,該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として取り消すことができる(最大判昭36・7・19民集15巻7号1875頁)。 2. しかし,民法424条の詐害行為取消権は,窮極的には債務者の一般財産による価値的満足を受けるため,総債権者の共同担保の保全を目的とするものであるから,このような制度の趣旨に照らし,特定物債権者は目的物自体を自己の債権の弁済に充てることはできないものというべく,目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に,特定物の引渡請求権に基づいて直接自己に所有権移転登記を求めることは許されない。 |
| *図31 最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁 民法判例百選Ⅱ第16事件 |
本書の立場では,最高裁の結論を,より単純に疑問の余地なく説明することができる。
|
本書の立場によれば,詐害行為取消権の本質は,債務者がその責任財産につき,債権者を害する目的で受益者等に移転した場合に,そのような詐害的な責任財産の移転を債権者に対抗できなくなること,すなわち,債権者は,名目上の移転を否認して,受益者・転得者に移転した債務者の財産に対して強制執行をし,債権の満足を得ることである。 ここでいう債権の満足は,金銭債権の満足に限定されるから,債権者が目的物の引渡や移転登記を請求することはできない。その意味で,最高裁が,「不動産の引渡請求権者は,目的不動産についてされた債務者の処分行為を詐害行為として取り消す場合に,直接自己に対する所有権移転登記手続を請求することはできない」としているのは,正当である。 |
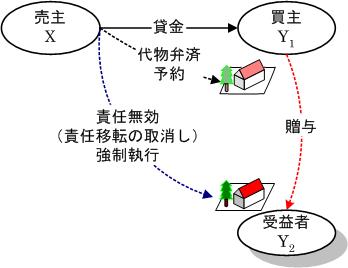 |
| *図32 最大判昭53・10・5民集32巻7号1332頁 民法判例百選Ⅱ第16事件の本書による説明 |
債権者が競合する場合の問題として,債権者と抜け駆け的に債権を回収した受益者との間の競合問題については,前記C.で検討した。ここで取り扱うのは,債権の二重譲渡の場合における詐害行為取消権の行使の問題である。
債務者Aの債権をYらが譲り受けたが,その債権は,Yらの債権の成立以前にすでにXに譲渡されていたために,詐害行為取消権の対象とならないことが明らかであった。しかし,Xへの債権譲渡の対抗要件である譲渡通知は,Yらの債権の成立以後になされていたことが判明した。そこで,Yらは,債権譲渡そのものは取消しできないとしても,対抗要件である債権譲渡通知(準法律行為)に対しては,詐害行為取消権を行使することができるのではないかと考え,詐害行為取消権の行使を行った。第1審,第2審は,このような詐害行為取消権の行使を認めたので,Xが上告した。
平成10年の最高裁判決〈最二判平10・6・12民集52巻4号1121頁〉は,確定日付のある債権譲渡の通知は,債権譲渡行為自体と切り離して詐害行為取消権行使の対象とすることができないとして,詐害行為取消権の対象とならないと判示した。
最二判平10・6・12民集52巻4号1121頁 民法判例百選Ⅱ第17事件
債務者が自己の第三者に対する債権を譲渡した場合において,債務者がこれについてした確定日付のある債権譲渡の通知は,詐害行為取消権行使の対象とならないと解するのが相当である。けだし,詐害行為取消権の対象となるのは,債務者の財産の減少を目的とする行為そのものであるところ,債権の譲渡行為とこれについての譲渡通知とはもとより別個の行為であって,後者は単にその時から初めて債権の移転を債務者その他の第三者に対抗し得る効果を生じさせるにすぎず,譲渡通知の時に右債権移転行為がされたこととなったり,債権移転の効果が生じたりするわけではなく,債権譲渡行為自体が詐害行為を構成しない場合には,これについてされた譲渡通知のみを切り離して詐害行為として取り扱い,これに対する詐害行為取消権の行使を認めることは相当とはいい難いからである。
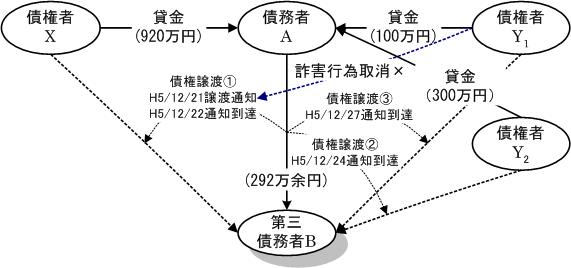 |
| *図33 最二判平10・6・12民集52巻4号1121頁 民法判例百選Ⅱ第17事件 |
民法424条2項は,詐害行為取消権の行使要件に関して,「財産権を目的としない法律行為については,適用しない」と規定しているため,離婚に伴う財産分与に対して,分与者の債権者が詐害行為取消権を行使することができるかどうかが問題となる。
最高裁昭和58年判決は,この点について,「離婚に伴う財産分与は,民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり,財産分与に仮託された財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り,詐害行為として債権者による取消の対象となりえない」と判示して,事案の解決としては,詐害行為取消権の行使を否定していた。
これに対して,最高裁平成12年判決〈最一判平12・3・9民集54巻3号1013頁〉は,離婚に伴う財産分与・慰謝料支払合意について,最高裁として初めて詐害行為取消権の行使を肯定した。
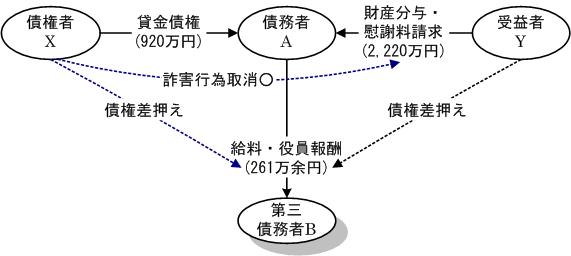 |
|
1. 離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は,民法767条3項の規程の趣旨に反してその額が不相当に過大であり,財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは,不相当に過大な部分について,その限度において詐害行為として取り消されるべきである。 2. 離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は,右損害賠償債務の額を超えた部分について,詐害行為取消権行使の対象となる。 |
| *図34 最一判平12・3・9民集54巻3号1013頁 民法判例百選Ⅱ第18事件 |
詐害行為取消権の第1の行使要件は,債務者自身の行為によって責任財産が減少し,債権者の債権を満足させるのに足りなくなることである。一部の債権者に弁済することは,それだけでは原則として詐害行為とならない〈大判大5・11・22民録22輯2281頁〉。ただし,以下の場合には,債権者に対する弁済であっても,例外として,詐害行為となる。
詐害行為取消権の対象となる法律行為は,財産上の法律行為でなければならない[民法424条2項]。先に述べたように,離婚に伴う適正な財産分与〈最二判昭58・12・19民集37巻10号1532頁〉,認知,相続の放棄等は,たとえ,債務者の財産状態を悪化させるものであっても,詐害行為とはならない。ただし,離婚に伴う財産分与として金銭を給付する旨の合意が,不相当に過大な場合には,その過大部分についてのみ,詐害行為として取り消される〈最一判平12・3・9民集54巻3号1013頁〉。
債務者および受益者・転得者が詐害行為の当時または財産の取得の当時,その行為によって債権者を害することを知っていたことが第2の要件である。
詐害行為の成立には債務者がその債権者を害することを知って行為を行なったことを要するが,必ずしも債権者を害することを意図し,若しくは欲して行なったことを要しない〈最三判昭35・4・26民集14巻6号1046頁〉。
責任財産を減少させる行為と無資力要件とは,密接に関連している。責任財産を減少させても,債権の弁済が可能である(無資力にならない)ならば,それは詐害行為にはならない。その意味で無資力は詐害行為の時点では必要がなく,詐害行為の結果によって無資力になれば,その要件が満たされるという関係にある。反対に,すでに無資力であれば,責任財産を減少させる行為は,常に詐害行為となる。
詐害行為取消権は,必ず裁判所に訴えを提起することを要する[民法424条1項本文]。それでは,裁判上の請求が必要ということは,必ず請求の形式によるべきであって,裁判上であっても,抗弁として主張することは許されないと解すべきであろうか。
確かに,実務では,「裁判所に請求することができる」という条文の意味を一般的に,「抗弁の方法によることは許されない」と解しているようである。しかし,詐害行為取消権と性質を同じくする,破産法上の「否認権」の行使に関しては,破産法173条は,「否認権は,訴え,否認の『請求又は抗弁によって』,破産管財人が行使する」と規定しており,裁判上の請求だけでなく,抗弁による行使を認めている。そして,民法上の詐害行為取消権と破産法上の否認権とは,性質がほぼ同じであることを考えると,「抗弁による行使」に関して明文の規定のある破産法173条の規定を,明文に規定のない民法424条の場合にも準用または類推するというのも,穏当な考え方であるといえよう。
この問題に関して,昭和39年最高裁判決〈最二判昭39・6・12民集18巻5号764頁〉は,以下のように述べて,この考え方(詐害行為取消権の裁判上の「抗弁」による行使)を否定している。
取消しうべき法律行為の取消については民法123条に「相手方ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ為ス」と規定し,否認権の行使については破産法76条〔現行破産法173条〕に「訴又ハ抗弁ニ依リ破産管財人之ヲ行フ」と規定しているのに反し,詐害行為の取消については,民法424条に「裁判所ニ請求スルコトヲ得」と規定しているから,訴の方法によるべく,抗弁の方法によることは許されないものと解するのを相当とする(〈大判明30・10・15民録3輯9巻58頁〉,〈大判大5・11・24民録22輯2302頁〉参照)。
しかし,最高裁の判決理由は,性質を同じくする詐害行為取消権と否認権とについて,なぜ取扱いを別にしなければならないのか,その実質的な説明を欠いており,説得力を有しない。民法424条の文言解釈からしても,「裁判所に対し,請求によってしなければならない」と書かれているわけではなく,単に「裁判所に請求することができる」とされているだけなのであるから,性質を同じくする破産法173条の否認権の場合と同様にして,「請求又は抗弁」によって,裁判所を通じて行使することができると解することも可能であろう。
詐害行為取消権の行使に際しては,債務者は被告とすることができない。したがって,債権者は,受益者または転得者のみを被告として訴えを提起することになる。すでに述べたように,詐害行為取消権は,債務者から受益者または転得者へと逸失した財産に対して,責任移転の効力を否認し(責任的無効),債権者が受益者または転得者名義となっている逸失財産に対して直接に強制執行を行うことを実現する制度である。したがって,詐害行為取消権の相手方は,債務者ではなく,逸失された財産について執行ができる受益者または転得者になるのである。
以上の趣旨からすると,受益者のほかに転得者がいる場合には,本来的には,転得者だけを相手にすべきであるが,受益者に対しても,価格賠償をすることが認められている。これは,先に述べたように,悪意の受益者に対する不法行為に基づく損害賠償として考えることが可能である。なぜなら,悪意の受益者は,たとえ,第三者(転得者)に財産を移転しても,共同不法行為者として連帯責任を負わされるからであり,その責任のとり方として,価格賠償責任を負わされるからである。
留置権者が占有する物に関して生じた債権の弁済を受けるまで,その物の所有者からの返還義務を拒絶できるのは,留置権が物権だからであると考えられてきた。しかし,債権の内部においても,自らの債権の弁済を受けるまで,その債権に牽連する自らの債務の履行を拒絶できるという制度が存在する。それが,同時履行の抗弁権である。この同時履行の抗弁権は,すべての場合ではないにしても,一定の場合,例えば,債権が譲渡された場合には,第三者である債権の譲受人に対して対抗すること,すなわち,第三者に対抗することができる[民法468条2項]。
それでは,同時履行の抗弁権は,なぜ,自らの債権が実現されるまで,自らの債務の履行を拒絶することが可能なのであろうか。ここでは,この問題の探求を通じて,事実上の優先弁済権がどのような要件で実現されるのかを明らかにする。
2つの債権(α債権とβ債権)が対立している場合に,理論上は,一方の債権(α債権)を有する債権者がその権利を行使することを認めざるを得ない。しかし,現実に,一方の当事者が権利を行使した場合に,その権利だけを実現させると,他方の権利の実現が実際上,困難になる危険性がある。例えば,売買契約が締結された場合に,買主が売買目的物の財産権の移転(目的物の引渡を含む)を求める権利(α債権)を有することは疑いの余地がない[民法555条]。しかし,この場合に,買主が売主に対して訴えを提起した場合に,買主の義務(β債権)が履行されるかどうかを度外視して,一方的に,売主に債務(α債権)の履行を命じる判決を下すことは,反対債権である代金債権(β債権)の実現が不確実となり,両債権が同時に実現されるべきであるとの当事者の期待にも,また,公平の原則に反することになる。
そこで,2つの債権が対立している場合に,一方の債権者が債務者に対して,他方の債務が履行されていないことを知りつつ,債務の履行を求めて訴えを提起した場合に,一方だけの権利の実現を求めることは,公平に反し,信義にもとる(詐欺的でさえある)という意味で,ローマ法の時代から,債務者は「悪意の抗弁(exceptio doli)」を主張して,履行を拒絶することが認められてきた。
民法533条の同時履行の抗弁権,民法295条の留置権に基づく引渡拒絶の抗弁権という延期的抗弁権については,現在では,引換給付判決という制度が認められており,民法505条の相殺に基づく債務拒絶の抗弁は,同時履行かつ同時消滅の永久的抗弁として,後に述べるように,担保的機能を営むものとなっている。しかし,歴史的には,同時履行の抗弁権も,留置権の抗弁権も,相殺の抗弁も,いずれも,一方だけの権利行使を認めることは,公平の観点から許されるべきではないという「悪意の抗弁」に由来する制度なのである。
通説の考え方によると,留置権に事実上の優先弁済権が認められるのは,留置権が物権だからである。しかし,物権とは,目的物に対する使用・収益権または換価・処分権を有する権利のことをいい,それが優先弁済権の根拠となっているのである。ところが,留置権は,使用・収益権も,換価・処分権を有していないので,物権ではないし,優先弁済権を有しないので,通説の定義に従えば,担保「物権」とはいえないはずの存在である。
このように,留置権は,使用・収益権も,換価・処分権も存在しないので,物権ではありえない。しかし,被担保債権(α債権)が「物から生じた債権」であって,目的物との密接な関係が認められる場合であり,そのことを通じて,被担保債権と目的物の返還債権(β債権)との間に牽連性が認められる。この牽連性が根拠となって,両債権は,同時に履行されるべきであるという公平の観点から,同時履行の抗弁権と同様に,「履行拒絶の抗弁権」として尊重されているのである。
物権ではなく,公平の観点から認められる「履行拒絶の抗弁権」に過ぎない留置権になぜ,事実上の優先弁済権が認められるかというと,それは,目的物の引渡しを望む人は,「その物に関して生じた」被担保債権を弁済しない限り,その物を取り戻せないからである。
留置権の場合,訴訟上も「引換給付判決」が下されているように,目的物の引渡と同時に被担保債権の支払いが義務づけられる。すなわち,対立する2つの債権は,同時履行が実現されたときに,両債権がともに満足され,被担保債権が確実に回収されるのである。しかも,この履行拒絶の抗弁権は,占有によって公示されており,民法295条によって,第三者に対抗することが認められている。
このようにして,留置権は物権ではないにもかかわらず,目的物の占有の継続という対抗要件によって,すべての第三者に対抗できる「履行拒絶の抗弁権」であるため,その物の返還を求める人に対して,同時に被担保債権の弁済を強制することができ,その結果として,事実上の優先弁済権を有するのである。
物権ではなく,引渡拒絶の抗弁権にすぎない留置権が事実上の優先弁済権を取得しているのであれば,履行拒絶の抗弁権の1つである「同時履行の抗弁権」であっても,それが,第三者に対抗できる場合には,事実上の優先弁済権を獲得できるはずである。
同時履行の抗弁権[民法533条]は,留置権と同様に,訴訟上も引換給付判決[民事執行法31条1項]が認められており,このことによって,債権の回収が確保される。なぜなら,BがAに対してα債権を有しており,反対にAがBに対してβ債権を有している場合に,Aがβ債権の実現を望むならば,同時にBに対してα債務を履行せざるをえないからである。この関係は,目的物の返還を望むAが留置権者Bに対するα債務を履行せざるをえないのと同じである。
従来は,留置権と同時履行の抗弁権とは,前者は物権で第三者にも対抗できるのに対して,後者は,債権に属する抗弁権であって,第三者に対抗できない点で異なるとされてきた。しかし,同時履行の抗弁権であっても,債権譲渡の際には,原則として,第三者である譲受人に対抗できる[民法468条2項]〈最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁〉。
最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁
未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について,債務者の異議をとどめない承諾がされても,譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には,債務者は,右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもって譲受人に対抗することができる。
さらに,特別法によって,同時履行の抗弁権が第三者に対抗できる場合が増えている[割賦販売法30条の4,35条の3の19等]。以上の2点を考慮するならば,第三者の対抗力という点では,留置権と同時履行の抗弁権との差は縮まっているといえよう。
同時履行の抗弁権と留置権の異同を考えるには,売買とともに双務契約の典型をなす請負の2つの例を挙げて説明するのがもっともわかりやすい。
第1の例は,民法632条の請負契約の冒頭条文の例である。この場合には,注文者の仕事の完成を請求する債権と,請負人の報酬債権とが対立しており,民法533条の同時履行の抗弁権がそのまま適用できる。請負人が請負の目的物を占有しているので,この場合には,民法553条の同時履行の抗弁権も民法295条の留置権もともに要件を満たしており,同時に2つの抗弁権が成立する(抗弁権の競合)。
 |
| *図35 修理における留置権と同時履行の抗弁権との競合 (引渡前なので,Bは同時履行の抗弁権と留置権とを有する) |
この例の場合には,修理業者は,民法295条によって留置権を取得するとともに,民法533条によって同時履行の抗弁権も取得する。そして,いずれにしても,報酬を受け取るまで,注文者Aからの引渡請求を拒絶することによって,報酬債権を確実に回収することができる。
同時履行の抗弁権は,公平の観念から導き出されたすぐれた制度であるために,双務契約における対立する2つの本旨に基づく債務ばかりでなく,売買における代金債権と,目的物の引渡後の目的物の検査によって目的物に瑕疵があることが判明した場合の売主の担保責任に基づく損害賠償請求権との間にも,同時履行の抗弁権が準用されている[民法571条]。
また,請負契約においても,双務契約上の対立する債務(請負人の仕事の完成債務・目的物の引渡債務と注文者の報酬支払債務)とに同時履行の抗弁権が適用されるばかりでなく,請負の目的物の検査の結果請負の瑕疵が発見された場合の請負の担保責任に基づく損害賠償債権と請負人の報酬債権との間でも,注文者のために同時履行の抗弁権が準用されている[民法634条2項]。
これが先の第1の例と対照されるべき第2の例となる。すなわち,請負人が仕事を完成させて目的物を注文者に引渡したが,請負の目的物に瑕疵があったため,請負人の報酬請求と注文主の修補に代わる損害賠償請求とが,民法634条2項により,民法533条の同時履行の抗弁権が準用されるという例である。この場合には,民法634条2項によって準用される民法533条によって,注文者は請負人に対して同時履行の抗弁権が成立する。これに対して,請負人は,すでに請負の目的物を注文者に引渡しているため,留置権は成立しない。
 |
| *図36 修理における同時履行の抗弁権 (引渡しが終わっているので,留置権は問題とならない場合) |
修理された自動車の引渡しを受けた注文者Aは,その時に,修理業者Bに修理代金を支払う義務を負うにもかかわらず,修理に瑕疵がある場合には,損害賠償債権を確保するために,Aには,代金支払拒絶の抗弁権が発生する[民法634条2項]。
履行拒絶の抗弁権を有するAは,これによって,修理代金債権と損害賠償債権とを相殺する機会を与えられることになり,損害賠償債権の履行を確保することができる。
この場合の同時履行関係は,相殺によって両債権が対当額によって消滅することを通じて,特別の清算を必要とせずに即時に実現される。このことを通じて,両債権がその範囲で回収されることになる。後に述べるように,相殺の場合には,第三者が介入した場合でも,民法511条により,法律上の優先弁済権を取得する。この点については,項を改めて,6(相殺の担保的機能)で説明する。
同時履行の抗弁権は,双務契約だけではなく,民法に規定がない場合であっても,たとえば,弁済者の弁済受領者に対する受取証書の交付請求権についても,一方の先履行を認めると二重払いの危険という不都合を生じるので,これを避けるという公平の観点から,受取証書の交付を受けるまで,弁済者に弁済を拒絶する同時履行の抗弁権が認められている(〈最三判昭33・6・3民集12巻9号1287頁〉(貸金請求事件),〈最二判昭35・7・8民集14巻9号1720頁〉(売掛金請求事件),〈最三判昭40・8・24民集19巻6号1435頁〉(貸金請求事件))。判例によって認められた弁済拒絶の抗弁権の一種である。
同時履行の抗弁権は,公平の考え方に基づいており,具体的妥当性を確保できる場合が多いため,その適用範囲は拡大していく傾向にある。同時履行の抗弁権の拡大の最先端に位置するのが,不安の抗弁権である。なぜなら,不安の抗弁権の前提は,対立する2つの債権・債務のうちの一方が先履行債務である場合であり,本来ならば,同時履行とは相容れないものである。
しかし,先履行債務を有する債務者が,債権者に対してその債務と牽連する債務を有しており,その債権が実現されないおそれが生じた場合には,その債権が実現されるまで,先履行債務の履行を拒絶することが公平の観点から正当化される場合がある。これが,不安の抗弁権[ドイツ民法321条]である。
ドイツ民法 第321条(不安の抗弁権)
①双務契約に基づいて先給付義務を負う者は,契約締結後,その者の反対給付請求権が相手方の給付能力の欠如により危殆化されることを知ることができるときは,その者が負担する給付を拒絶することができる。反対給付が実現され,またはそのための担保が給付されたときは,給付拒絶権は消滅する。
②先給付義務者は,相手方が給付と引き換えに,その選択に従い,反対給付を実現し,または担保を給付しなければならない,相当期間を指定することができる。その期間が徒過されたときは,先給付義務者は契約を解除することができる。この場合には,323条〔不給付又は不完全給付の場合の解除〕の規定が準用される。
わが国の民法には,不安の抗弁権そのものについての規定はないが,不安の抗弁権に類似するものとして,「弁済拒絶の抗弁権」[民法576条~578条]が規定されている。この弁済拒絶の抗弁権は,自らの債務がすでに弁済期に来ているにもかかわらず,その先履行債務の履行を拒絶しつつ,自らの権利の弁済期が来るのを待ってその債権の回収を実現することができる点で,債権の確保に強力な作用を発揮する。
| 不安の抗弁権 (広義) |
弁済拒絶の抗弁権 [民法576条~578条] |
不安の抗弁権 [ドイツ民法321条] |
| 条文 |
第576条(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶),第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶),第578条(売主による代金の供託の請求) |
ドイツ民法 第321条(不安の抗弁権) |
| 共通点 | 先履行義務が履行されない状態で,対立する債権の履行に不安が生じている。 代金拒絶の抗弁権の場合を具体的に述べると,売買目的物の履行がなされているので,本来なら,代金支払債務が履行されなければならないのであるが,売買の目的に権利の瑕疵があるために,先履行義務(代金支払義務)が履行されない状態で,相手方の債務(売主の担保責任)の履行に不安が生じている。 |
|
| 相違点 | 抗弁権を終了させる効果が,担保請求または供託請求である。 | 抗弁権を収束させる効果が,引換給付,担保請求または解除である。 |
わが国の判決例の中には,この不安の抗弁権を認めるものも存在する(〈東京地判平2・12・20判時1389号79頁,判タ757号202頁〉参照)。
同時履行の抗弁権の準用・類推を通じて,対立する債権が,両者ともに金銭債権となった場合には,相殺が利用できる。この場合には,両債権は引換給付判決を経ることなく,両債権が即時に実現され,消滅に至る。以下の事例(*図37参照)でこのことを説明する。
A(買主)は,売主Cから自動車を購入し,残代金が100万円残っている時点で,交通事故を起こしたとする。A(注文者)は,修理業者B(請負人)に自動車の修理を依頼したところ,修理の見積額が30万円であったのでこれに同意した。期日に修理が完了してBから目的物が引渡されたので,Aが検査したところ,修理に重大な瑕疵があったため,再修理を余儀なくされ,Aに10万円の損害が発生した。その後,Aが売買残代金をCに支払えなくなったため,自動車が競売され,競売代金が60万円だったとする。注文者Aの有する損害賠償債権(10万円),請負人の有する報酬債権(30万円),自動車の売主の有する売買残代金債権(100万円)はどのように調整されて,A,B,Cは,競売代金(60万円)から,それぞれいくらの配当を受けることになるのだろうか。
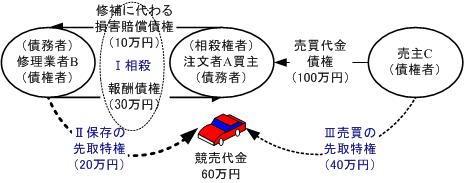 |
| *図37 牽連する債権の同時履行と優先弁済の順位 |
第1に,BのAに対する報酬債権(30万円)とAのBに対する損害賠償債権とは密接に関連しており(報酬の減額請求と同じ機能を有する),民法634条2項によって,同時履行の抗弁権が準用されている。そこで,牽連性のある両債権は同時に履行されることが要請される。そして,相殺権者Aが両債権について相殺の意思表示を行うと,両債権は対当額で消滅し,Aは,即時に10万円の債権を回収することができる。このように,牽連性のある債権が両者ともに金銭債権である場合には,相殺権者は,自働債権を他の債権者に先立って弁済を受けたのと同じ効果を享受できる。これが後に述べる「相殺の担保的機能」と呼ばれるものである。
第2に,相殺によって10万円が消滅した残りの20万円について,修理業者Bは,民法320条により,動産保存の先取特権を有する。その優先順位は,民法330条1項2号により,第2順位である。第2順位の優先弁済権を有する修理業者Bは,相殺によって減額された残りの20万円全額について,競売代金から配当を受ける。
第3に,売主Cは,民法321条により,動産売買の先取特権有する。その先取特権の優先順位は民法330条1項3号により第3順位である。したがって売主Cは,Bに配当された残りの40万円(60万円-20万円)の配当を受けることができるに過ぎない。
このように見てくると,2つの債権の間に牽連性が認められる場合には,それらの債権は,公平の観点から,あたかも運命共同体のように同時に履行されることが要請される。つまり,同時履行の抗弁権および相殺は,いずれも,2つの債権の牽連性に基づいて,公平の観点から認められるものであり,たとえ,両債権の一方が差し押さえられたり,譲渡されたりというように,第三者による介入があったとしても,それらの介入がなかったかのように,他の債権者の権利に事実上優先して(同時履行の抗弁権),または法律上優先して(相殺),両債権の同時履行が貫徹されるのである。
| 要件と効果 | 同時履行の抗弁権が認められる場合 | 同時履行の抗弁権が認められない場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 双務契約上の2つの債務の存在 | 適用 | ・双務契約の原則 ・目的物の引渡債務と登記移転債務〈最一判昭34・6・25判時192号16頁〉 |
・賃貸借,請負,委任などのように,対価が後払いとされる契約(614条,624条,633条,648条2項)の場合 ・先履行の特約がある場合(〈大判大正10・6・25民録27輯1247頁〉,〈大判昭和12・2・9民集16巻33頁〉) |
|
| 準用 | ・解除による当事者双方の原状回復義務の履行[546条], ・売主の代金債権と買主の担保責任に基づく損害賠償債権[民法571条],注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬請求権[634条2項] |
・貸金返還債務と担保物権の登記抹消義務の間の関係-借主が先履行義務を負うので,登記抹消との引換給付を求めることはできない(〈最二判昭和41・9・16判時460号52頁〉,〈最二判昭和63・4・8判時1277号119頁〉) | ||
| 類推 |
・双務契約が無効・取消しにより,不当利得返還義務を双方に生じる場合〈最一判昭47・9・7民集26巻7号1327頁〉 ・弁済と受取証書の交付[民法486条] ・建物買取請求権における代金支払債務と建物引渡債務 ・借地上の建物につき建物買取請求権[借地借家法13条1項,14条]が行使された場合に,建物の引渡しと代金支払いは同時履行の関係に立ち,その反射的効果として敷地の引渡しも拒むことができる〈最三判昭和35・9・20民集14巻11号2227頁〉。 |
・これに反して,借家につき造作買取請求権(借地借家法33条)が行使された場合に,造作代金支払いと対価性があるのは造作のみであるとして,建物引渡しとの間には同時履行の関係を認めない〈最一判昭和29・7・22民集8巻7号1425頁〉。 | ||
| 双方の債務が弁済期にあること | ・双務契約の当事者の一方が先履行義務を負担している場合において,後履行義務者の財産状態が,契約締結後に,甚だしく悪化し,その債務の履行に不安を生じ,先履行義務者に先履行を強いることが信義則に反するとき 後履行義務者が担保を供与するなど債務履行確保措置をとらない限り,先履行義務者は先履行を拒むことができる(〈東京高判昭62・3・30判時1236号75頁〉,〈東京地判平2・12・20判時1389号79頁〉) |
・家屋明渡請求と敷金返還請求 家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務についても,同様に同時履行の関係を否定する〈最一判昭和49・9・2民集28巻6号1152頁〉 |
||
| 相手方が履行又はその提供をしないで履行の請求をすること | 当事者の一方Aがひとたび履行の提供をしても,それが受領されず債務の履行がない間はその債務をまぬがれるわけではないから,両債務の履行上の牽連関係はなお存続し,その提供を継続しない以上,Bは同時履行の抗弁権を主張できる(〈大判明治44・12・11民録17輯772頁〉,〈最一判昭和34・5・14民集13巻5号609頁〉)。 | |||
| 効果 | ・引換給付判決 ・抗弁権の付着した債務の相殺の禁止 ・違法性の阻却 |
同時履行の抗弁権の付着する債権を自働債権として相殺することはできない。例えば,AがBに物を売りBに対して代金債権を取得したとする(Aの物の引渡債務とBの代金支払債務とは,同時履行の関係)。しかし,Aは,Bから金を借りていて,BがAに対して貸金債権を持っているという場合,Aは,物の引渡しについて履行の提供(493条)もしないうちに,自己の代金債権を自働債権とし,Bの貸金債権を受働債権として相殺することは許されない。 なぜなら,もしそれが許されるなら,Aが自己の物の引渡債務を履行するより前に,Bに対し代金の支払いを強制したのと同様の結果(Bが同時履行の抗弁権を失うに等しい結果)となり,公平に反するからである。 |
||
上記の*表21は,同時履行の抗弁権が認められる場合と認められる場合とを対比すると言う観点から同時履行の抗弁権をまとめたものである。同時履行の抗弁権は,公平の考え方の現れであるから,2つの債権に牽連性が認められる場合には,原則として認められるべきものである。したがって,どのような場合に判例がそれを認めていないのかという点に重点を置いてチェックを行うと,全体としての「公平の考え方」の射程についての理解が深まると思われる。
先取特権,質権,抵当権が担保目的物に対して優先弁済権(他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利([民法303条],[民法342条],[民法369条]))を有するのは,それらの権利が物権だからであると考えられてきた。しかし,債権の内部においても,自らの債権(自働債権)と債務(受働債権)とを同時に対当額で消滅させることを通じて,受働債権から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利が存在する。それが,相殺(相殺の担保的機能)である。この相殺の抗弁は,受働債権の差押債権者ばかりでなく,受働債権の譲受人等に対しても対抗することができる([民法511条],[民法468条2項])。
それでは,相殺は,なぜ,自らの債権を実現するため,自らの債務である受働債権から他の債権者に先立って債権回収をすることが可能なのであろうか。ここでは,この問題の探求を通じて,法律上の優先弁済権がどのような要件で実現されるのかを明らかにする。
相殺は,相互に対立する債権が存在する場合に,意思表示のみによって相互に対立する債権を消滅させるという債権の消滅原因として位置づけられている[505条]。しかし,相互に対立する債権・債務のうち,相殺をする側の債権に注目するときは,相殺には,自らの債務(受働債権:β債権に対する債務)を免れることによって自らの債権(自働債権:α債権)を独占的・排他的に回収する機能がある。
このことは,他の債権者がβ債権を差し押さえた場合またはβ債権が譲渡された場合に顕著となる。なぜなら,相殺権者は,そのような場合に,相殺の抗弁をもって差押債権者に対抗できること[民法511条]および相殺の抗弁をもって債権の譲受人にも対抗できること[民法468条2項]を通じて,どの債権者にも優先して自らの債権を回収できるからである(法律上の優先弁済権)。
後に詳しく論じるように,相殺の担保的機能は非常に強力であり,担保物権のうちで,もっとも強力とされる抵当権にもまさる力を発揮することがある。このような強力な担保的機能が債権の分野に属する相殺に見られることは注目すべき点である。それでは,債権の分野に属する相殺が,担保物権を凌駕する担保的効力を有するのはなぜなのか,このことを解明することがここでの課題である。
相殺とは,2人の者が互いに相手に対して同種の債権をもっている場合に,一方から相手方に対する意思表示によってその債務を「対当額」で消滅させることをいう[民法505条1項](なお,用語法の問題であるが,「対当額」であって「対等額」ではない点に注意すること)。
例えば,AがB銀行に50万円預金をし,BがAに対して80万円貸し付けた場合に,A又はBが相殺の意思表示をすれば,AのBに対する50万円の債権が消滅し,AのBに対する30万円の債務が残ることになる。
なお,相殺をする側の債権を自働債権,される側の債権(反対債権)を受働債権という。例えば,先の例で,Aに対して80万円の貸金債権をもつBが,Aの50万円の預金債権に対して相殺する場合,貸金債権80万円が自働債権,預金債権50万円が受働債権である。
AとBとの債権が互いに対立している場合に,AとBとがそれぞれ別々に請求し,別々に弁済することは不便であり,無駄である場合が多い。そこで,AがBに80万円を支払い,BがAに50万円を支払うという手間を省いて,相殺し,AがBに30万円を支払うことによって決済をすることが認められるべきである。これを相殺の簡易決済の機能という。
相殺が認められるのは,A・B双方がその債権を別々に取り立てるという不便を除くためだけでなく,公平のためである。すなわち,Aが破産した場合を考えると,BはAに対し50万円全額支払わなければならないのに,Bの80万円の債権は,債権額に応じて配当されるにとどまって不公平であり,AB相互間に債権債務が成立した時から,対当額において債権が決済されたものとして取り扱うのが公平である。
したがって,BはAの財産状態が悪化しても,50万円については相殺の意思表示をすれば,それだけで簡単に,かつ確実に他の債権者に先立って回収できるから,相殺は債権担保の役割も果たすことになる。
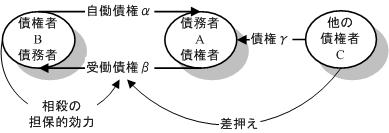 |
| *図38 相殺の担保的機能 |
相殺の担保的機能は,重要な問題であるので,項を改めて説明を行う。
相殺ができるのは,相殺適状にあるときである。相殺適状とは以下の場合をいう。
第1の要件は,対立する2つの債権が同種の債権であることであり,これを相殺に関する「代替性の要件」という。第1の要件は,相殺の本質をなすものであり,この要件を欠く場合には,相殺は不可能である。
相殺の第2の要件は,2つの債権の主体が相互に債権者でありかつ債務者であることであり,これを相殺に関する「相互性の要件」という。この要件も相殺の本質をなすものであるが,これには,「3者間相殺」という例外が存在する。3者間相殺は,非常に難しい問題を含んでおり,理解が困難な問題である。そこで,3者間相殺については,以下において,3つの類型があること,関連条文を掲げるにとどめ,詳しい解説は,専門書[加賀山・担保法(2009)109-115頁]に譲ることにする。
3者間相殺で最も理解が困難なのが,固有の3者間相殺である。固有の3者間相殺の特色は,自働債権と受働債権とが二者間ではなく,最初から三者にまたがって存在しているにもかかわらず,三者のうちの一人の相殺の意思表示によって三者にまたがって存在する債権が消滅するというものである。この類型は,さらに,だれが相殺の意思表示をすることができるかという観点から,以下の3つの類型に分かれる。
第1類型は,相殺権者が受働債権と自働債権とに挟まれるように中間点に位置する場合である。この典型例は,譲渡された債権の債権者から請求を受けた債務者が,債権の譲渡人に対して有していた債権で相殺するという場合である[民法468条2項]。
第2類型は,相殺権者が自動債権と受働債権の連鎖の始点に位置する場合である。この典型例は,債権者から請求を受けた保証人が,自らが債権者に有する債権を自働債権として主たる債務を相殺によって消滅される場合である[民法436条1項の類推]。
第3類型は,相殺権者が自働債権と受働債権の連鎖の終点に位置する場合である。この典型例は,弁済の受領権限のない者(無権限者)が債務者から弁済を受け,債権者が無権限者から利益を受けていたというときに,債務者から不当利得の請求を受けた無権限者が,もともとの債権を自働債権とし,債務者からの不当利得の返還請求権を受働債権として相殺を行う場合である[民法479条参照]。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 根拠条文 | 条文の内容 | 図解 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固有の3者間相殺 (α債権とβ債権 との間の相殺) |
第1類型 | 債権譲渡型 | 民法468条 2項 |
〔債権の〕譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは,債務者は,その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由〔相殺を含む〕をもって譲受人に対抗することができる。 |  *図39 譲渡型Ⅱ |
| 無権限者へ の弁済型 |
民法479条 | 前条〔準占有者への弁済〕の場合を除き,弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は,債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ,その効力を有する。 | 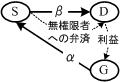 *図40 無権限者への弁済型Ⅰ |
||
| 第2類型 | 保証人 相殺型 |
なし (旧民法財産編521条) |
旧民法521条1項は,「訴追を受けたる保証人は債権者が主たる債務者又は自己に対して負担する債務の相殺を以て対抗することを得」と規定していた。 現行民法の起草者は,先に保証人援用型として述べた民法457条2項を立法する際に,「本条第2項は既成法典財産編第521条第1項の規定と其主意を同じうす」としながら,実際には,この規定のうち,「又は自己」の部分を現行法から脱落させるというミスを犯してしまったのである。 しかし,通説は,保証人が自ら債権者に有する債権で,主債務を相殺することを実質的に認めている[我妻・債権総論(1964)490頁]。 |
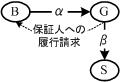 *図41 保証人相殺型 |
|
| 連帯債務者 相殺型 |
民法436条 1項 |
連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において,その連帯債務者が相殺を援用したときは,債権は,すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 | |||
| 第3類型 | 無権限者へ の弁済型 |
民法479条 | 前条〔準占有者への弁済〕の場合を除き,弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は,債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ,その効力を有する。 | 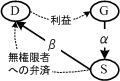 *図42 無権限者への相殺型Ⅱ |
上の*表18の図解における省略記号は,それぞれ,Gは債権者(Gläubiger)を,Sは債務者(Schuldner)を,Bは保証人(Bürge)を意味する。
3者間相殺については,理論が未発達な状況にあり,最高裁の判例も,3者間相殺について十分な理解ができていない。そのためもあって,3者間相殺の第2類型(保証人相殺型)として認められるべき場合について,相殺の効力を否定するに留まっている。
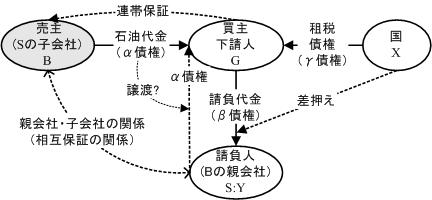 |
最三判平7・7・18判時1570号60頁,判タ914号95頁 B〔日通商事(Yの子会社)〕のG〔近畿運輸(下請人)〕に対する債権〔α債権:石油の売買代金債権〕でもってGのS〔Y:日本通運(請負人)〕に対する債権〔β債権:請負代金債権〕を相殺することができる旨のB・G間の相殺予約契約に基づき,Bがした相殺の意思表示は,実質的にはBからS〔Y〕への〔α債権の〕債権譲渡といえることをも考慮すると,右意思表示前にGのS〔Y〕に対する債権〔β債権〕を差し押さえた差押債権者〔X:国〕に対抗することができないとされた事例 |
| *図43 3者間相殺の否定例 〈最三判平7・7・18判時1570号60頁,判タ914号95頁〉 |
平成7年の最高裁判決は,本件の相殺を民法で認められている3者間相殺の問題として捉えることができず,下請人Bがα債権(石油代金債権)を注文者S(Y:Bの親会社)に譲渡した上で,G・Yの2者間でα債権とβ債権(請負代金債権)とが相殺されたものとみなしている。その結果,Xの差押えに遅れてなされた債権譲渡によって二者間の相殺適状が生じたことになる。すなわち,Yは差押え後に取得した自働債権によって相殺をするということになるため,民法511条により,Yは相殺をもって差押債権者Xに対抗できないと最高裁は判断したのである。
しかし,本件の事案は,中舎寛樹「多数当事者相殺契約の効力」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)334-357頁]が指摘しているように,上記のようなB・G間の相殺予約契約は,「同一グループ内の複数会社〔本件ではY・B)が共通の相手方〔G〕と取引を行う場合に生じる多数の債権の簡易決済をはかり,同時に,契約当事者である会社のひとつ〔G〕に信用不安が発生した場合には,その会社が有する債権に対する第三者〔X〕の強制執行を排除し,グループ内〔Y・B〕での債権回収ないし清算を計る点にメリットがある」とされている。中舎理論にしたがって当事者の意思を忖度して再構成すると,この相殺予約契約は,「各当事者〔親会社Yと子会社B〕には,当事者それぞれが負担している「債務」について相互に協力し,保証しあうとの意思があるものと理解することができる」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)349頁]。
このように,B・G間の「相殺予約契約」は,Y・Bの親子関係会社における相互保証に基づいて,取引先のGに対して,BがSの債務の履行を保証する「保証契約」として組み替えることができると考えると,本件の場合,上記の固有の3者間相殺のうちの第2類型(保証人による相殺)の類型に合致することになり,Bは,Gに対して有する石油売買代金債権を自働債権とし,GのYに対する運送請負代金債権を受働債権として相殺をすることができることになる。
*表18の*図41で示したように,保証人は債権者に対して有する債権でもって主債務者に対する債務を相殺することができる。わが国の民法にこのことを明らかにした規定がないのは,旧民法財産編521条(保証人は,債権者が主たる債務者又は自己に対して負担する債務の相殺を以て対抗することを得)を現行民法457条2項に取り込む際に,「又は自己」の部分を脱落させるという立法上の過誤が生じたからである。しかし,このような3者間相殺が認められることは,通説も認めており[我妻・債権総論(1964)490頁],解釈上も,連帯債務に関する民法436条1項の類推を通じて,保証人が債権者に対して有する債権によってによる主たる債務を相殺することが認められる。また,α債権(燃料の売買代金)とβ債権(運輸の請負代金)との間には牽連性が認められるのであり,この点からも,相殺の担保的機能を認めることができる事案であった。
平成7年の最高裁判決がYを敗訴させた理由としては,相殺予約契約の意味を子会社Bが親会社Yの債務について連帯保証人の立場にあることに気づかなかったためであると思われる。もしも,最高裁が,本件のBはGに対して保証人の立場に立つことを理解していたとしたら,通説に従って,3者間相殺を認めることができたはずだからである。
相殺の第3の要件である請求可能性(弁済期)に関しては,例外が認められ,要件の緩和がなされている。
第1に,相殺しようとする者は,相手方に対して負っている債務,すなわち相殺される債権(受働債権)についての期限の利益を放棄すれば相殺できるから,相殺する債権(自働債権)さえ弁済期にあれば相殺できることになる[民法505条1項]。
第2に,自働債権が弁済期にない場合であっても,自働債権と受働債権との間に密接な関係(牽連性)が認められる場合には,合理的な「相殺の期待」が認められるため,緊密な関係にある債権に「代替性」と「相互性」の要件が満たされた段階で,相殺適状の要件が緩和されて,相殺が可能となる。
以上のような要件の緩和とは反対に,以下のような相殺の障害要件がある場合には,相殺は許されない。
相殺の意思表示は単独行為であり[民法506条1項],意思表示があれば,双方の債権は相殺適状の時にさかのぼって対当額で消滅する[民法506条2項]。
この遡及効が,他の債権者が受働債権を差押えてきたときに,自働債権の債権者に対して,一般債権者の宿命としての按分比例額ではなく,受働債権の範囲で,全額の回収を実現するという,相殺の担保的機能の大きな要素となっていると考えられてきた[深川・相殺の担保的機能(2008)106~134頁]。しかし,比較法的な考察によると,国際的な契約法の傾向は,相殺の遡及効を放棄する方向に向かっており,相殺は将来効を有するものとされてきている(ヨーロッパ契約法原則13:106条,ユニドロワ国際商事契約原則(2004)8.5条(3))。このような中で,遡及効を維持することは,次第に困難な状況になりつつある[深川・相殺の担保的機能(2008)76-85頁]。確かに,現在のところでは,わが国では,なお,相殺の担保的機能を遡及効に基づいて説明することが可能である。しかし,遡及効によって相殺の担保的機能を説明する場合には,受働債権について第三者が差し押さえたり,譲り受けたりする時点で未だ相殺適状に達していなくても,相殺の担保的機能を認める判例法理(最高裁昭和39年〈最大判昭39・12・23民集18巻10号2217頁〉,同45年判決〈最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁〉)を整合的に理解することは困難である。相殺の意思表示主義に立つからには,意思表示の時点で相殺適状が満たされていなければならないはずであるにもかかわらず,上記の判決は,相殺適状にない時点で他の債権者が受働債権を差し押さえた場合にも,相殺の担保的機能を認めているからである。
したがって,将来的には,相殺の担保的効力は,対立する債権が牽連性を有する場合に認められる相殺の優先弁済効(一種の先取特権)として構成するほかないと思われる[深川・相殺の担保的機能(2008)139-149頁]。しかし,現在のところでは,相殺の遡及効も,相殺の担保的効力を説明する際に有用な概念として理解しておく必要がある[深川・相殺の担保的機能(2008)86-96頁]。
なお,先に述べたように,自働債権に抗弁権が付着している場合には,相手方を保護する必要があるため,相殺は認められないのが原則である。つまり,相殺の遡及効は,原則として,同時履行の関係にある相手方に対抗できない(相手方の権利を害することができない)。ただし,同時履行の関係にある場合には,同時履行の抗弁権が,相殺権者のために与えられている場合には,相殺自体は許される〈最一判昭51・3・4民集30巻2号48頁,最一判昭53・9・21判時907号54頁〉。ただし,相殺の遡及効が制限される場合がある〈最二判昭32・3・8民集11巻3号513頁〉。
同時履行の関係にあった2つの債権が対当額で相殺され,残債務が生じた場合,その残債務に関する遅延損害金の発生時期は,相殺の意思表示の翌日からであって,相殺適状の日にまで遡るわけではない〈最三判平9・7・15民集51巻6号2581頁〉。
担保物権法の代表的な教科書である[高木・担保物権(2005)4頁]によれば,非典型担保である譲渡担保,仮登記担保,所有権留保と並べて,「その他の物的担保」として「相殺・相殺予約」が以下のように紹介されている。
債権者と債務者が相対立する債権を有する場合の最も簡便な回収方法は,相殺である。この相殺が,担保の実行という効果をもたらしている。たとえば,Aに対して50万円の債務を負っているBが,Aに100万円融資した場合には,Bは相殺によって50万円は回収しうる。しかも,Aの債権者CがAのBに対する債権を差し押さえても,判例〈最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁〉は,民法511条の解釈として,BのAに対する債権が,差押え以前に取得したものであれば,BはCに対して相殺をもって対抗しうるとしている。AのBに対する債権については,B,Cとも債権の効力として平等に掴取力をもっているはずであるが,上記のごとき相殺によって,BはCに優先して回収しうるわけであり,したがって,AのBに対する債権が,Aにとっては担保財産となっており,相殺が担保実行の方法となっているわけである。銀行のごとき金融機関は,預金をしている者に融資したり,融資の一部を預金させたり(歩積み・両建て)するのが通常であるが,かかる場合には,そのような意味で,預金が担保財産となっているのである。
相殺の担保的機能に関しては,最高裁の昭和45年大法廷判決(最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁)が,銀行実務を集大成する形で,以下のように表現しており,現在では,相殺に担保的機能があることは,ほとんど疑われていないといってよい。
相殺の制度は,互いに同種の債権を有する当事者間において,相対立する債権債務を簡易な方法によって決済し,もって両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であって,相殺権を行使する債権者の立場からすれば,債務者の資力が不十分な場合においても,自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において,受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。
しかし,相殺に担保的機能を認めることは,理論的には,大きな混乱を引き起こすことになる。なぜなら,わが国では,相殺は債権編において,債務の消滅原因の一つとして規定されており,相殺が担保物権でないことは,自明であるとされてきたからである。このため,学説においては,相殺の担保的機能とは,以下のように,債務の消滅を通じた「独占的」な「最優先順位の担保権」と説明されてきた(私法学会シンポジウム[1966:4頁]〔林良平〕)。
〔相殺の〕公平の趣旨は,自働債権〔α〕が受働債権〔β〕を訴訟外で掴取すること,しかも相殺によって受働債権〔β〕を消滅させることによって,受働債権〔β〕は,もはや相手方〔A〕の引当(責任)財産から控除され,自働債権〔α〕の債権者〔B〕以外の他の債権者〔C〕は受働債権〔β〕を引当財産として掴取する途をとざされる,という相殺の構造によって達せられている。この構造に着目すれば,自働債権〔α〕の債権者〔B〕は独占的に受働債権〔β〕を掴取できるものであり,他の債権者〔C〕の発言を許さない意味で,最優先順位の担保権を持つに等しい。この意味では相殺は担保的機能を有するといってよい。(私法学会シンポジウム[1966:4頁]〔林良平〕)
ところが,相殺の担保的機能について,債権の消滅を通じた「独占的」な「最優先の担保権」と考えると,2つの点で,疑問が生じる。第1は,債権の消滅を通じた「独占的」な権利だとすると,他の債権者を害することになり,債権者平等の原則に反して,相殺権者を保護しすぎるのではないかという疑問である。これは,相殺を担保物権として構成する可能性を示唆するものではあるが,そこまで踏み切れるのかという問題が生じている。第2は,そのような「独占的」な権利は,あくまで,相殺適状にある場合に認められるべきものであり,相殺適状にない場合にも,相殺の担保的機能を認める最高裁の判例の立場(無制限説を採用する最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁ばかりでなく,制限説を採用する最大判昭39・12・23民集18巻10号2217頁であっても,同様である)は,相殺の機能を逸脱するのではないかという疑問である。
| 学説 | 自働債権 | 受働債権 | 相殺可能の理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 相殺適状説 | 相殺適状説 | ①弁済期 | 相殺適状が差押えよりも前である | |
| ②弁済期(相殺適状) | ||||
| ③差押え | ||||
| 相殺適状修正説 | ①弁済期 | |||
| (③による相殺適状) | ||||
| ②差押え | ||||
| ③弁済期 (期限の利益の放棄が可能)↑ |
||||
| 制限説 | 制限説Ⅰ (弁済期先後説) (最高裁昭和39年判決) |
①差押え | 自働債権の弁済期が受働債権の弁済期より先である | |
| ②弁済期 | ||||
| ③弁済期 (期限の利益の喪失約款)↑ |
||||
| 制限説Ⅱ (期待利益説) |
①差押え | 相殺に対する合理的な期待 (継続的な取引関係,相殺予約等)がある |
||
| ②弁済期 | ||||
| ③弁済期 (相殺予約) |
||||
| 無制限説 (最高裁昭和45年判決) |
①差押え | 民法511条の反対解釈 差押えよりも先に自働債権が取得されている |
||
| ②弁済期 | ||||
| ③弁済期 | ||||
銀行が貸付けを行なう際には,債務者に相応する金額の預金を求めるのが普通であり,少なくとも,貸金を当初は,その銀行に預金させることを貸付けの条件とすることが多いとされている。
銀行としては,貸金と同額の預金を預っていれば,それは,まさに,預金を質にとって入るようなものであり,いざという時は,優先的に貸金の返済に充当しようと考えたとしても,それほど不思議ではない。
最高裁は,当初は,甲(C)が乙(A)の丙(B)に対する債権を差し押えた場合において,丙(B)が差押前に取得した乙(A)に対する債権の弁済期が差押時より後であるが,被差押債権の弁済期より前に到来する関係にあるときは,丙(B)は右両債権の差押後の相殺をもって甲(C)に対抗することができるが,右両債権の弁済期の前後が逆であるときは,丙(B)は右相殺をもって甲(C)に対抗することはできないものと解すべきであるとしていた〈最大判昭39・12・23民集18巻10号2217頁〉。
最大判昭39・12・23民集18巻10号2217頁
甲が乙の丙に対する債権を差し押えた場合において,丙が差押前に取得した乙に対する債権の弁済期が差押時より後であるが,被差押債権の弁済期より前に到来する関係にあるときは,丙は右両債権の差押後の相殺をもって甲に対抗することができるが,右両債権の弁済期の前後が逆であるときは,丙は右相殺をもって甲に対抗することはできないものと解すべきである。
債権者と債務者の間で,相対立する債権につき将来差押を受ける等の一定の事由が発生した場合には,両債権の弁済期のいかんを問わず,直ちに相殺適状を生ずる旨の契約および予約完結の意思表示により相殺をすることができる旨の相殺予約は,相殺をもって差押債権者に対抗できる前項の場合にかぎつて,差押債権者に対し有効であると解すべきである。(補足意見および反対意見がある。)
この昭和39年大法廷判決(制限Ⅰ説)は,わずか5年半で,昭和45年大法廷判決によって無制限説へと変更される。そして,その無制限説が実務で定着するのであるが,学説においては,現在もなお,制限説Ⅰ(弁済期先後基準説)が通説となっている。その理由は,以下の2つである。
第1の理由は,無制限説によると,いかにも信義則に反するような相殺権者の行為を是認しなければならない。すなわち,受働債権の弁済期が先に到来して,その弁済を義務付けられている第三債務者Bが,後に到来する自働債権の弁済期まで債務の履行を遅延させ,自働債権の弁済期が来るや否や,相殺を主張して自らの債務を免れて自らの債権を完全に回収することになるが,これは,信義則に反する行為といわざるを得ないからである。
第2の理由は,わが国の相殺制度が倣ったとされるドイツ民法392条が,以下のように制限説Ⅰ(弁済期先後基準説)を明文で規定しており,この説によれば,上記のような信義則に反する事態は避けられるからである。
ドイツ民法 第392条(差し押さえられた債権に対する相殺)
債権〔受働債権〕に対して差押えがなされたときは,債務者が差押後に債権〔自働債権〕を取得した場合,または,債権〔自働債権〕の弁済期が差押えよりも後に,かつ,債権〔自働債権〕の弁済期が差し押さえられた債権〔受働債権〕の弁済期よりも後に到来する場合においては,債務者は,その債権者に対して有している債権によって相殺することができない。
そして,このようなドイツ民法392条によってわが国の民法511条を制限的に解釈すべきであるという考え方は,最高裁昭和39年大法廷判決の松田二郎裁判官の反対意見に見事に集約されている。
最大判昭39・12・23民集18巻10号2217頁における松田二郎裁判官の反対意見
差押債権の場合,第三債務者の相殺権につき,多数説の採り,しかして私もまた賛成する見解,すなわち「差押当時自働債権が未だ弁済期に到来していない場合でも,その弁済期が被差押債権である受働債権のそれより先に到来するものであるときは,相殺を以て差押債権者に対抗し得る」との見解〔制限説Ⅰ(弁済期先後基準説)〕は,従来の最高裁判所の判例〔相殺適状説〕の態度を改め,わが民法をドイツ民法第392条後段と同趣旨に解そうとするものである。しからば,ドイツ法上,右条文の下において,第三債務者と債務者との間に,差押より以前に締結された相殺契約が存在するとき,それは差押によって影響されずとし,あるいはこれに優先するものと解されることは注目に値し,このことは卑見を確かめるものである。思うに,多数意見はドイツ民法第392条後段と同旨の見解を採る以上,この点の見解も亦採用すべきであると思われる。
しかし,わが国の最高裁45年判決は,この見解を採用しなかった。その理由は,相互に対立する債権がある場合に,どちらの弁済期が先に来るかは偶然的な事情であって,たとえ,自働債権の弁済期が後に来る場合であっても,継続的な契約関係がある場合には,それらの債務は時間の流れにしたがって,それぞれの債務が適状になれば,相殺されていくのが常態である。したがって,たまたま,その自然の流れの途中に第三者が介入したからといって,それらの債務が相殺されるとの当事者の期待を覆す必要はないというのが,無制限説からの制限説Ⅰ(弁済期先後基準説)に対する反論である。
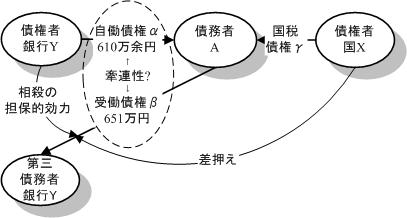 *図44 相殺の担保的機能(最高裁昭和45年判決) |
最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁 〔①相殺の担保的機能〕相殺の制度は,互いに同種の債権を有する当事者間において,相対立する債権債務を簡易な方法によって決済し,もって両者の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的な制度であって,相殺権を行使する債権者の立場からすれば,債務者の資力が不十分な場合においても,自己の債権については確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることができる点において,受働債権につきあたかも担保権を有するにも似た地位が与えられるという機能を営むものである。 |
| 〔②無制限説の採用〕債権が差し押えられた場合において,第三債務者〔B〕が債務者〔A〕に対して反対債権を有していたときは,その債権が差押後に取得されたものでないかぎり,右債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず,両者が相殺適状に達しさえすれば,第三債務者〔B〕は,差押後においても,右反対債権を自働債権として,被差押債権と相殺することができる。(補足意見,意見および反対意見がある。) 〔③相殺契約の効力〕銀行の貸付債権について,債務者〔A〕の信用を悪化させる一定の客観的事情が発生した場合には,債務者のために存する右貸付金の期限の利益を喪失せしめ,同人の銀行に対する預金等の債権につき銀行において期限の利益を放棄し,直ちに相殺適状を生ぜしめる旨の合意は,右預金等の債権を差し押えた債権者に対しても効力を有する。(意見および反対意見がある。 |
|
実務は昭和45年の大法廷判決に即して行われているが,昭和39年判決を評価する学説も多い。無制限説を認めるためには,理論的に解明すべき問題点が残されているからである。この点に関する本書の立場は以下の通りである。
相殺の担保機能に関する無制限説に対して批判がなされている理由は,先にも述べたように,Aに対するBの自働債権の弁済期が到来する前にAの受働債権がAの債権者Cによって差し押さえられた場合に,Bの自働債権の弁済期が来ていないにもかかわらず,Bによる相殺の担保的機能を認めることは,弁済期に弁済をせずに債務不履行状態を継続しつつ,自働債権の弁済期が到来するや否や相殺を行うことによって自働債権の回収を行うという相殺権者Bの行為が信義則に違反すると考えられるからである。
しかし,他の債権者Cが差押えを行う場合というのは,Aの資力に不安が生じている場合であることが多い。このような場合に,受働債権の弁済期が到来したとはいえ,牽連しているBの自働債権の弁済に不安が生じている以上,Bに履行拒絶の抗弁権を与えるべきである。
ドイツ民法は,弁済期先後説を明文で定めているが(ドイツ民法321条),他方で,牽連する債務が「相手方の給付の欠如により危殆化されることが予見できる場合には,その者が負担する給付を拒絶することができる」という,不安の抗弁権を認めている(ドイツ民法321条)。
わが国には,不安の抗弁権そのものを規定する条文は存在しないが,買主が売買代金の支払義務を負う場合について,民法576条は,「買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは,買主は,その危険の限度に応じて,代金の全部又は一部の支払を拒むことができる」として,先履行義務を負う当事者について,実質的な不安の抗弁権を認めている。
このように考えると,2つの対立する債権の間に牽連性がある場合には,たとえ,それぞれの弁済期に差がある場合であっても,一方の債務の履行に不安がある場合には,牽連性に基づく同時履行の要請を理由として,先履行義務を拒絶しつつ,相殺によって同時履行を実現することは,信義則に反する行為ではないということを理論的に説明することができる。
自働債権(α債権:債権者B,債務者A)と受働債権(β債権:債権者A,債務者B)との間に牽連性がある場合には,その後に受働債権(β債権)が第三者C譲渡されたとしても,債権は同一性を保って移転するのであるから,債務者である相殺権者Bは,債権譲渡前よりも不利な地位に置かれるべきではない。したがって,Bは相殺の抗弁をもって受働債権の譲受人Cに対抗することができる[民法468条2項]。
確かに,民法468条2項は,「譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは,債務者は,その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」と規定しており,債権譲渡の対抗要件が備わるまでに,すでに相殺適状が生じている必要があるとの解釈も成り立ちうる[潮見・債権総論Ⅱ(2005)633頁]。しかし,民法468条2項における「通知を受けるまでに生じた事由」とは,例えば,解除の場合であれば,債権譲渡の通知の前に解除の意思表示がなされていることが要求されるわけではないし,そのときまでに解除原因が生じていることが要求されているわけでもない。
昭和42年最高裁判例〈最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁(民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第28事件)〉によれば,以下のように,「債権譲渡前すでに反対給付義務が発生している〔双務契約上の牽連性がある〕以上,債権譲渡時すでに契約解除を生ずるに至るべき原因が存在していたものというべきである」として,債権譲渡の対抗要件(本件の場合には,債務者の承諾)が具備された後にはじめて解除原因が生じた場合においても,債務者は解除の抗弁をもって債権の譲受人に対抗できるとしている。
最二判昭42・10・27民集21巻8号2161頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第28事件
請負契約は,報酬の支払いと仕事の完成とが対価関係に立つ諾成,双務契約であって,請負人の有する報酬請求権はその仕事完成引渡と同時履行の関係に立ち,かつ仕事完成義務の不履行を事由とする請負契約の解除により消滅するものであるから,右報酬請求権が第三者に譲渡され対抗要件をそなえた後に請負人の仕事完成義務不履行が生じこれに基づき請負契約が解除された場合においても,右債権譲渡前すでに反対給付義務が発生している以上,債権譲渡時すでに契約解除を生ずるに至るべき原因が存在していたものというべきである。
そうだとすると,自働債権と受働債権との間に牽連性がある場合には,債権譲渡とその対抗要件が備わるまでに,両債権が相殺適状にある場合に限らず,また,自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも先に到来している場合に限らず,それまでに,受働債権の債務者が,受働債権との間に牽連性のある自働債権を取得しているならば,債務者は相殺の抗弁をもって債権の譲受人に対抗できると解すべきである〈最一判昭50・12・8民集29巻11号1864頁〉。
最一判昭50・12・8民集29巻11号1864頁
債権が譲渡され,その債務者が,譲渡通知を受けたにとどまり,かつ,右通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を取得していた場合において,譲受人が譲渡人である会社の取締役である等判示の事実関係があるときには,右被譲渡債権及び反対債権の弁済期の前後を問わず,両者の弁済期が到来すれば,被譲渡債権の債務者は,譲受人に対し,右反対債権を自働債権として,被譲渡債権と相殺することができる。(補足意見及び反対意見がある。)
この事件においては,債権者と債務者との間には継続的な取引関係があり,受働債権は製品の売掛代金であり,自働債権は約束手形であるが,同日に同一金額の手形債権が成立していることから,継続的な取引において生じた債権を分割したものと推定することができ,対立する両債権の間には牽連性が推定される事案であったことが指摘されている[深川・相殺の担保的機能(2008)425頁]。したがって,上記の判例は,事案の解決としても,妥当な解決がなされているといえよう。
賃貸人は,賃借人の債務不履行に備えて,賃借人から一定の金額を差し出させるのが通常である。これを敷金という。この敷金に対しては,賃貸借契約の終了時に賃借人の損害賠償額を差し引いた額について賃借人が返還請求権を有する。
この返還請求権(将来債権)を賃借人の債権者が差押えた場合に,賃貸人は,賃借人に対する損害賠償請求権を自働債権として,敷金返還請求権を相殺することができるかどうかが問題となる。
敷金の法的性質をどのように考えるかで理論構成は異なる。まず,敷金の返還請求権が,損害賠償額を控除した後の額についてのみ発生するならば,賃貸人は,相殺の抗弁を出すまでもなく,損害賠償額について敷金から優先的に充当を受けることができることになる。また,先に発生した損害賠償請求権と賃借物件を明け渡した後に発生する資金返還請求権とが並立して存在すると考えた場合にも,賃貸人は両債権を対当額で相殺することができると考えることができ,この相殺は,賃借人の債権者による敷金返還請求権の差押えに対抗できることになろう。この点に関しては,敷金による相殺と同じ機能を,敷金の充当として認めた最高裁の以下の判決〈最一判平14・3・28民集56巻3号689頁〉が参考になる。
なお,民法は,敷金について,賃貸借契約の条文[民法619条]においては詳しい規定をおかず,先取特権の箇所で,その本質の一部を明らかにしている[民法316条]。すなわち,民法316条によると,賃貸人は,敷金でまかなえない部分の賃料債権,その他の賃貸借関係から生じた債権についてのみ,第1順位の先取特権[民法330条]を有するとしているのである。これを反対から言えば,敷金は,その第1順位の先取特権を超える最高順位の担保権として扱われていることがわかる。
「振込み指定」とは,債務者Aに対して債権者である金融機関Bが有する債権を担保するため,Aが第三債務者Cに対して有する債権の弁済方法として,AがBに開設した口座にCに振り込ませ,その振込金に対するAの預金返還請求権に対して,金融機関BがAに対して有する債権でもって相殺することである。
これも,相殺の担保的効力を応用したものであり,実質的には,CからのAに対する振込みをもって,Aに対するBの債権の優先的な弁済に充てることになる。裁判例〈名古屋高判昭58・3・31判時1077号79頁〉においては,銀行融資の返済に充てるため退職金を預金することを約束した者が破産宣告を受けた場合につき,その後退職金の振込みによって銀行が負担した預金債務は破産法旧104条二号ただし書きの「前ニ生ジタル原因」に基づく債務であるとして,相殺の担保的効力を認めている。
第1編で担保法の本質が掴取力の強化であること,掴取力の強化には,量的強化と質的強化の2つがあり,それらを実現するメカニズムである直接取立権,追及効,優先弁済権が,債権の中に存在しており,そのことを通じて,担保法の体系を構築することができることを示した。
第2編では,債権の掴取力の量的強化としての人的担保(保証と連帯債務)と債権の掴取力の質的強化としての物的担保(典型担保と非典型担保)について,具体的に論じることにする。
| 編 | 章 | 節 |
|---|---|---|
| 第2編 担保法各論 | 第3章 人的担保 | 第1節 人的担保概説 |
| 第2節 保証 | ||
| 第3節 連帯債務 | ||
| 第4節 不真正連帯債務 | ||
| 第5節 不可分債務 | ||
| 第4章 物的担保 | 第1節 物的担保概説 | |
| 第2節 留置権 | ||
| 第3節 先取特権 | ||
| 第4節 質権 | ||
| 第5節 抵当権 | ||
| 第6節 根抵当権 | ||
| 第5章 非典型担保 | 第1節 非典型担保概説 | |
| 第2節 仮登記担保 | ||
| 第3節 譲渡担保 | ||
| 第4節 所有権留保 |
本書の第2編で展開する担保法各論の特色は,以下の3つである。
人的担保の場合も,物的担保の場合も,債権の他に別個・独立の債務や物権があるわけではないことを明らかにする。
第1に,人的担保に関しては,主たる債務のほかに保証債務という別個・独立の債務が存在するわけではなく,保証債務というのは,実は,債務なき責任(担保)に過ぎないことを明らかにする(保証債務という債務は存在しない)。そのことを通じて,保証人の求償権は確実に回収されるべきであること,もしも,債権者が保証人の求償権を害する場合には,保証人は免責されること[民法504条],さらに,保証人の求償権を害する契約条項は,信義則に反して保証人に過酷な責任を負わすものであり,公序良俗に違反して無効となるとなるべきことを論じる(*第4章第2節4,)。
第2に,物的担保に関しては,被担保債権の他に別個・独立の担保物権が存在するわけではないことを明らかにする(担保物権という物権は存在しない)。すなわち,担保物権というのは,実は,債権の掴取力が優先弁済効によって強化されているに過ぎないことを明らかにする。そのことを通じて,担保物権の効力は優先弁済権に限定されるべきであること,それにもかかわらず,抵当権設定者の使用・収益権を奪わないはずの抵当権者が,その設定登記に遅れて対抗力を取得した目的不動産の賃借人を追い出すことを認めている通説は改められるべきであること,そして,対抗力を有する適法賃貸借は,売買によっても,また,抵当権の実行によっても破られないことを論じる(*第5章)。
第3に,非典型担保については,たとえ,担保設定契約に債権者に所有権が移転するという文言があったとしても,それは,通謀虚偽表示として無効であり,債権者である担保権者は,担保目的物の換価・処分権を取得して,担保目的物から優先弁済権を取得するに過ぎないこと,すなわち,いかなる非典型担保においても,担保権者は決して担保目的物の所有権を取得することはないことを明らかにする(*第6章)。
従来は,非典型担保は「所有権移転型」の担保として,所有権的構成をとる考え方が主流を占めていた。しかし,担保とは,そもそも,債権の保全と回収を確実にするために,債権者に目的物の換価・処分権を与えるのが精一杯のところであり,債権者に所有権まで与える必要はない。債権者に最も大きな力を与える質権でさえ,債権者が所有権を取得すること(流質)は禁じられており[民法349条],競売に代えて私的実行が許される場合でも,裁判所による鑑定人の選任が要件とされている[民法354条]。流質が認められるのは,特別法[質屋営業法19条など]によって,法律と行政庁による監督または公正自由な競争にさらされることにより,実質的に,適正な清算が行われることが保証される場合に限定されているからである。
人的担保に関しては,現在の学説は,手がつけられないほどに混乱している。たとえば,「保証債務は独立の債務であるが主たる債務に従属する」[於保・債権総論(1972)254頁]とか,保証は主たる債務と別個の債務である([平井・債権総論(1994)304頁],[内田・民法Ⅲ(2005)338頁])が,連帯債務は債務であって保証ではないので,付従性の問題は生じない([平井・債権総論(1994)327頁],[内田・民法Ⅲ(2005)372頁])とか,論理学を学習した人なら誰でも誤りだとわかる学説が通説となっているからである。
通説は,このような誤った前提から出発しているために,様々な局面で具体的妥当性を欠く結論を導いており,その弊害は目に余るものがある。特に,連帯債務者間の求償の場面において,通説の考え方は,大きな弊害を生じさせている。
ここでは,人的担保の性質を理解するとともに,連帯債務とは本来の「債務」と連帯「保証」とが結合したものであること,すなわち,相互保証理論の内容を理解する。そのことを通じて,保証人には求償権があるが,債務者には求償権がないため,自らの債務を弁済するのに,保証人に事前に通知する必要もなく,そのことを怠ったからといって,保証人から求償されることもないことを理解する。
人的担保は,保証(通常保証と連帯保証とがある)と連帯債務とに分かれる。物的担保が,債権の掴取力を質的に高めて債権者に優先弁済権をもたらすものであるのに対して,人的担保は,掴取力を量的に拡大し,第三者である保証人の責任財産をも掴取力の対象とする制度である。したがって,人的担保である保証を学ぶことによって,掴取力の対象としての責任財産の量的拡張の考え方,すなわち,「債務のない責任」という考え方を深く理解することができるようになる。
保証は,保証「債務」ともいわれ,債務の一種であるかのように考えられてきた([我妻・債権総論(1954)449頁],[於保・債権総論(1972)253頁],[奥田・債権総論(1992)380頁],[平井・債権総論(1994)303頁],[内田・民法Ⅲ(2005)338頁],[潮見・債権総論Ⅱ(2005)421頁]など)。しかし,すでに,*第1編第2章第2節2(債権の掴取力の量的強化としての人的担保)で詳しく検討したように,保証は決して債務ではない(保証人は求償を通じて最終的には免責されるのであるから,理論的には,保証人は債務を負わないといわざるを得ない)。
保証とは,他人の債務を履行する責任を負わされた状態(債務のない責任)をいう[民法446条1項]のであって,保証人は,主債務者の債務以外に別の債務を負うものではない。すなわち,主債務者の主たる債務がひとつだけ存在し,一定の要件が備わった場合に,第三者である保証人が,主債務者代わって,主たる債務(保証債務ではない)を履行しなければならない責任を負うものに過ぎない(加賀山説)。
このように,保証が債務ではなく,責任に属することは,以下の対照表(*表21)にしたがって「債務」と「責任」とが分離されていることを確認し,その上で,民法446条1項の文言をよく読むと理解できる。
| 責任の態様 | 名称 | 解説 | 具体例 | |
|---|---|---|---|---|
| 債務あり | 責任あり | (本来の)債務 | 債務者が債権者に負う本来の債務であって,他人に転嫁(求償)することができないもの。債権者から裁判所に訴えて履行を求めることができる。 | 通常の債務,連帯債務の負担部分(なお,通説によれば,保証もここに含まれることになる)。 |
| 責任なし | 自然債務 | 債務者が任意に履行すれば有効な弁済となり,債務者は給付したものを不当利得として債権者から取り戻すことはできないが,債権者の方から裁判所に訴えて履行を求めることができない債務。 | いわゆる紳士契約・紳士協定,消滅時効が援用された債務。 | |
| 責任のない債務 | 訴求して給付判決をもらうことまではできるが,強制執行はできない債務。 | 強制執行免脱約款つきの債務。 | ||
| 債務なし | 責任あり | 債務のない責任 | 他人の債務を肩代りして弁済する責任のこと。本来の債務者に対して求償権を有するため,最終的な債務を負わないのが特色。 民法446条1項が「保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う」として,債務と責任とを明確に区別する表現を用いていることに注目すべきである。 |
物上保証,保証,連帯債務の(連帯)保証部分。 |
| 責任なし | - | - | - | |
通説も,物上保証の場合には,物上保証人は,債務を負わず責任だけを負っていること(債務のない責任)を認めている([我妻・担保物権(1968)129頁],[高木・担保物権(2005)62頁,104-105頁],[道垣内・担保物権(2005)81頁],[内田・民法Ⅲ(2005)387頁]など)。物上保証の場合に限らず,通常の保証の場合にも,保証人は,債務者の債務について肩代りの履行責任を負わされているだけであるというのが,本書の立場である。
この点を理解できるかどうかが,保証の本質(保証の付従性と求償権の発生)に迫れるかどうかの分かれ目となっているのであるから,読者にとっては,一大決心が必要となる。確かに,通説に反対する本書の立場に立つことは,読者としては勇気のいることに違いない。しかし,通説によっていたのでは,保証における事前求償,連帯債務の一部免除,連帯債務の求償の要件としての事前・事後の通知の要件等について,条文の意味ばかりか,判例法理を理解することもできなくなることが目に見えている。
これまで,多くの学生を教えてきた経験上,通説を学んだ学生のほとんどすべてが,上記の問題,特に,連帯債務者の1人に生じた事由の他の連帯債務者に対する絶対的効力についての理解に失敗している。このことを考慮するならば,ひとまず本書の立場に立って理解を進めていくことを勧めたい。
本書の立場にしたがって保証の本質が理解できれば,連帯債務に関する難解な問題のすべてを理解することができる。そのような理解をした上で,矛盾と混乱の宝庫となっている通説をじっくり読めばよい。そうすれば,通説の問題点を含めて,人的担保に関する難解な問題をすべてを理解することができるであろう。
債務のない責任である「保証」ばかりでなく,債務としての「連帯債務」が人的担保に含まれるのはなぜであろうか。その理由は,後に詳しく検討するように,連帯債務とは,単なる債務ではなく,本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)とが結合したものだからである(相互保証理論)。
本来の債務と連帯保証との結合は,通常は,当事者の合意によって生じる(約定の連帯債務)。しかし,このような債務と連帯保証との結合は,法律の規定(例えば[民法719条]の共同不法行為者間の連帯債務)によっても生じる(法定の連帯債務)。後者は,通説によれば,「不真正連帯債務」と呼ばれているが,後に詳しく論じるように(*第4章第3節5),その本質は,法定の連帯債務である。したがって,その法律効果は通常の連帯債務と全く同一であり,すべて,相互保証理論によって説明することができる。
なお,保証と連帯債務とが連続していることは,連帯保証を理解すればよくわかる。すなわち,「負担部分ゼロの連帯債務とは,連帯保証のことである」といえば,保証と連帯債務との接点が理解できると思われる(わかりにくければ,*図45(連帯保証の透視図)と*図46(連帯債務の透視図)とを対比してみるとよい)。
債務者と保証人との関係を表したのが,以下の図のうちの左側の図(*図45)である。保証と連帯債務との関係を明らかにするため,ここでは,保証のうち,連帯保証の例を挙げることにする。連帯保証を例とする理由は,連帯保証人は,催告の抗弁権も検索の抗弁権も有しないため[民法454条],連帯債務と同じように,債権者から全額の弁済を求められるからである。
連帯保証の場合も,連帯債務の場合も,債権者Xにとっては,Y1に対しても,また,Y2に対しても全額の弁済を請求できる点で,両者は同じ立場にある。しかし,Y1またはY2がXに全額を弁済した場合の求償関係においては,債務者Y1と連帯保証人Y2とでは,その立場が天と地ほどに異なることに注意しなければならない。
主たる債務者であるY1が債権者Xに弁済した場合には,自己の債務を弁済したに過ぎないので,求償関係は生じない。これとは反対に,連帯保証人であるY2がXに弁済した場合には,Y2は,Y1の債務(主たる債務)を肩代りして弁済したのであるから,Y1に対して全額を求償することができる(結局のところ,保証人Y2は債務の全額を免れる)。すなわち,保証人であるY2は,いったんは,債務者であるY1の債務を履行する責任を負うものの,求償を通じてXに弁済した債務の全額をY1から取り戻すことができるので,結果として債務は負わないことになる(債務のない責任)。
ここで重要なことは,保証人Y2が弁済した場合には,求償が生じるが,債務者Y1が弁済した場合には,求償は絶対に生じないという点である。その理由は,本来の債務(自分の債務)を弁済した場合には債務が完全に消滅するため求償が生じないのに対して,保証債務を弁済した場合には,他人(債務者)の債務(主たる債務)を肩代りして弁済したのであるから,広い意味での不当利得状態が生じ,これを回復するために,保証人に求償が生じるからである。
単純なことなので,保証の場合には,この点を間違える人はほとんどいない。ところが,これが,次に述べる少し複雑な連帯債務の問題になったとたんに,基本を忘れてしまう人が多い。すなわち,連帯債務者が,本来の債務に当たる部分(負担部分)に満たない額を弁済した場合でも,求償が生じるという誤りを犯す人が多い(後に述べるように,これが通説となっている)のであるから,基本をきちんと理解することがいかに大切であるかを実感することができるであろう。
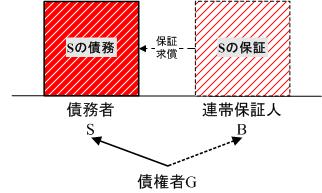 |
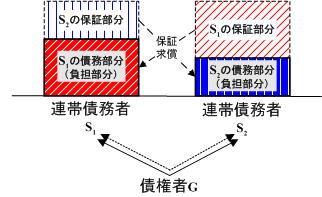 |
| *図45 連帯保証の透視図 (通常の債務に対する負担部分0の連帯債務) Sの債務についてBがGに対して連帯保証している |
*図46 連帯債務の透視図 (通常の債務と連帯保証との結合) S1とS2はGに対して連帯債務を負っている |
保証の場合と比べて,連帯債務の場合の求償関係はどのようになるのだろうか。上の図の右側にある図(*図46)は,連帯債務の内部をいわば透視した図である(従来の学説においては,連帯債務の内部構造はベールに包まれていた)。この透視図(*図46)によれば,連帯債務が本来の債務(負担部分)と連帯保証部分(保証部分)とから成り立っていることが一目瞭然となる。
これまで難解とされてきた連帯債務者の求償関係も,*図46のような透視図を使って分析的に考えると,基本的なミスを犯すことを防止できる。
まず,債権者Xから請求を受けて,連帯債務者の1人であるY1が連帯債務全額を弁済した場合を考えてみよう。弁済した連帯債務の全額のうち,Y1の本来の債務部分(負担部分)はY1自身の債務であるので,その分はY2に求償できない(債務者が弁済しても保証人に求償できないのと同じ)。しかし,全額弁済したうち,Y1の本来の債務(負担部分)を超える部分(保証部分)はY2の債務を肩代りして弁済したのであるから,Y2に求償できる(保証人が弁済したときは,主たる債務者に求償できるのと同じ)。
次に,債権者Xから請求を受けて,連帯債務者の一人であるY2が連帯債務全額を弁済した場合を考えてみよう(各自で実際に考えてみること)。そうすると,先の例と同様に,Y2が弁済した金額のうち,Y2の本来の債務(負担部分)についてはY1に求償できないが,負担部分を超えて弁済した部分(保証部分)については,Y1に求償できることが理解できるはずである。
複雑な連帯債務も,このように,本来の債務と連帯保証との結合であるという連帯債務の構造を知った上で実際に作業をしながら考えてみると理解が容易となる。難解とされる連帯債務者間の求償の問題も,このように,基本に沿って,一つ一つ丁寧に考えていくことによって理解が深まっていく。つまり,基本の理解には,面倒がらず,時間をかけて取り組むべきであって,そのことが,応用問題をこなす原動力につながっていくのである。
基本にしたがって理解を進めれば,連帯債務者の1人が弁済した場合に,他の連帯債務者に求償ができるのは,自らの負担部分を超えた弁済をした場合に限られることがよくわかる。それにもかかわらず,連帯債務者間の求償について,致命的なミスを犯しているのが通説なのであるから,法律学は恐ろしい。ここでいう通説の誤りとは,以下のように,保証人間の求償関係と連帯債務者間の求償関係とで,違う扱いをする点にある。
通説は,民法465条1項が,民法442条1項を準用して,保証人間の求償の要件として「自己の負担部分を超える額を弁済したとき」と規定していることから,保証の場合については,負担部分を超える部分についてのみ他の共同(連帯)保証人に対して求償ができるということを認めており,この点は,正当である。ところが,通説・判例〈大判大6・5・3民録23輯863頁〉は,連帯債務者間の求償に関しては,民法442条が「連帯債務者の1人が弁済をし,その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償権を有する」と規定しており,保証の場合とは異なり,「負担部分を超える額を弁済したとき」という文言がないことを理由として,以下のような反対解釈を行っている。すなわち,保証人間の求償の場合には,負担部分を超えた部分しか求償できないが,連帯債務者間の求償の場合には,負担部分を超えない部分であっても,求償することができる([我妻・担保物権(1968)433-434頁])と解している。
しかし,通説・判例の反対解釈は,ここでも,誤りに陥っている(誤った反対解釈)。その理由は以下の通りである。
第1に,連帯債務者の1人が連帯債務の全額に満たない弁済をした場合には,まず,その連帯債務者の負担部分の弁済に充当され,負担部分を超えた場合に初めて,保証部分に充当されると考えるべきである。このことは,「弁済が全額に満たない場合に,どの部分が弁済として充当されるか」という問題に関する弁済充当の規定が,「債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する」[民法489条2号]と規定しており,まず負担部分から充当される方が弁済者ために利益が多いものであることからも明らかである。
第2に,比較法的な観点からも,ヨーロッパ契約法原則10:106条が,「連帯債務者の1人が自らの負担部分を超えて履行したときは,他のいずれの連帯債務者に対しても,それらの債務者各自の未履行部分を限度として,自らの負担部分を超える部分を求償することができる」[潮見他・ヨーロッパ契約法原則Ⅲ(2008)32頁]と規定しており,これが,世界の趨勢となっていることからも,負担部分に満たない弁済では,求償の問題は生じないことが明らかである。
つまり,連帯債務者が負担部分に満たない弁済をした場合には,その弁済は,すべて負担部分に充当されるのであり,したがって,その場合には,他の連帯債務者に対して求償することはできないのである。このことは,主たる債務者が弁済しても,決して,求償権が生じないのと同様である。
それでは,わが国の通説・判例は,なぜ,このような基本的な問題について誤りを犯しているのであろうか。通説の誤りは,誤った反対解釈に由来しているのであるが,この場合の反対解釈は,単に論理学的な誤りだけでなく,その原因が,現行民法の歴史をないがしろにしたために生じたものであり,立法理由の探求が重要であることを示してくれている。
*表22を見てみよう。旧民法は,起草者であるボワソナードが,連帯債務とは債務と保証との結合であることを理解していたため,保証を先に規定し,その規定を連帯債務に準用していた。
ところが,現行民法は,旧民法とは異なり,保証を債権担保という観点からではなく,多数当事者の債権・債務関係として位置づけた。このため,現行民法においては,債務を含む連帯債務を先に規定し,その規定を保証に準用するという順序の変更を行ったのである。
連帯債務者間の求償[民法442条]の問題および共同保証人間の求償[民法465条]の問題について,現行民法は,旧民法の内容はそのままにして順序のみを変更するという方針をとった。それにもかかわらず,出来上がった現行民法の求償に関する部分は,共同保証と連帯債務とでは,内容が異なるように解釈できる結果となってしまった。現行民法の規定を見てみると,準用されるべき連帯債務の規定[民法442条]には,保証の規定[民法465条]のような「負担部分を超える額を弁済したとき」という限定がないため,連帯債務の場合には,民法465条の反対解釈が行われ,負担部分を超えない額を弁済したときでも,求償が可能であるという見解が通説・判例となったのである。
| 第465条〔共同保証人間の求償権〕 | 第442条〔連帯債務者間の求償〕 | |
|---|---|---|
| ①現行法の立場:連帯債務の規定を保証の規定が準用する | 特別規定: (1) 第442条から第444条までの規定〔弁済した連帯債務者の求償権〕は,数人の保証人がある場合において,そのうちの一人の保証人が,主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため,その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 |
一般規定: (1) 連帯債務者の一人が弁済をし,その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償権を有する。 |
| 立法者の本来の意図を実現するための作業:上欄①の現行民法の条文の内容をそのままにして,旧民法のように,条文の順序だけを入れ替え,保証を先に規定し,連帯債務がそれを準用するという形式に直してみたのが,下欄②である。下欄②にしたがって,現行民法を読み直してみると,現行民法の本当の意味が明らかになる。 | ||
| ②旧民法の立場:保証の規定を連帯債務の規定が準用する | 一般規定: (1) 数人の保証人がある場合において,そのうちの一人の保証人が,主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため,その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときは他の保証人に対し,各自の負担部分について求償権を有する。 |
特別規定: (1) 連帯債務者の一人が弁済をし,その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは,第465条〔共同保証人間の求償権〕の規定を準用する。 |
現行民法の条文を,内容をそのままにして,順序だけを旧民法と同じように,保証を先に規定し,連帯債務で補償の規定を準用するように変更してみると,内容は同じであるのに,「負担部分を超える額を弁済したとき」という文言が,保証の場合だけでなく,連帯債務の場合にも,同じように適用(準用)される。このため,反対解釈の余地はなくなることがよくわかる。その理由は,一般規定で書かれたことは,書かれていない特別規定にも適用(準用)されるからである。
以上の問題については,現行民法の編纂過程を知っておくと,通説のような誤った反対解釈に陥るおそれがなくなることが理解できる一例として記憶にとどめておくとよい。また,パンデクテン方式においては,条文の順序が重要な意味を持っており,したがって,条文の順序を変更する際には,準用関係を慎重に取り扱わなければならないという点でも,記憶にとどめておくべきであろう。
連帯債務を債務と保証との結合であるという考え方(相互保証理論)は,保証と連帯債務の求償関係について統一的な解決指針を与えてくれる点に特色がある。そればかりでなく,この考え方によれば,さらに難解な問題とされる「通知を怠った連帯債務者間の関係」[民法443条]について,混乱に陥っている現在の学説・判例をあるべき解決方向へと導くことも可能となる。
連帯債務者間の求償については,民法443条1項が,求償の要件として事前の通知(連帯債務者の1人が弁済する前に,他の連帯債務者が債権者に対して抗弁を有しているかどうかを確認する義務)を規定するとともに,同条2項が,事後の通知(連帯債務者の1人が共同の免責を得た場合に,他の連帯債務者が債権者に二重弁済をしないよう配慮する義務)を規定している。事前の通知,事後の通知は,ともに他の連帯債務者が求償するための要件であり,この要件を怠った場合には,連帯債務者の1人は,他の連帯債務者に対して求償することができない。二重弁済を受けた債権者から,負担部分を超えて弁済した部分の返還を不当利得に基づいて請求するしかない。
連帯債務者の1人が弁済によって共同の免責を得たが,事後の通知を怠っている間に,他の連帯債務者が事前の通知を怠って二重に弁済をしてしまったというように,事後の通知を怠った連帯債務者と事前の通知を怠った連帯債務者とが競合した場合に,どちらの弁済が有効となるかについては,明文の規定が存在しない。このため,解釈の余地が生じており,古くから以下のような学説の対立がある。
一方で,第1の弁済を有効とし,または,民法443条2項の適用には,同条1項の事前の通知が前提となるとして,事前の通知を怠った連帯債務者に対して民法443条2項の適用を否定する考え方(民法443条2項適用・否定説)が通説として存在する[我妻・債権総論(1954)438頁]。
他方で,民法443条の2項には,1項の事前の通知は要件となっていないとして,第1の弁済者が事後の通知を怠った場合には,事前の通知を怠った第2弁済者に民法443条2項の適用を肯定する考え方(民法443条2項適用・肯定説)や,両者の過失の程度によって,どちらが弁済するかを判断するという考え方(折衷説)も存在する(学説については,辻伸行[民法判例百選Ⅱ〔第6版〕(2009)47頁]参照)。
このように学説が対立している中で,最高裁昭和57年判決は,連帯債務者のうちの1人であるXが,事前の通知と事後の通知の両者を怠って,債権者Aに連帯債務全額を弁済したところ,他の連帯債務者Yが,事前の通知を怠って,負担部分の範囲で債権者Aに弁済をした場合に,全額弁済をしたXがYに対する負担部分の全額について求償請求を行ったという事案について,民法443条2項適用否定説の立場に立ち,以下のように判示して,Yの民法443条2項の抗弁を否定して,Xの求償を認めた。
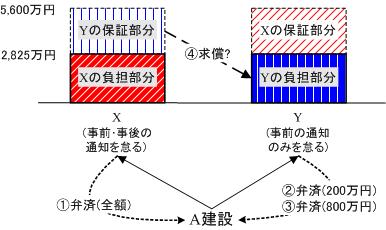 |
連帯債務者の一人〔Y〕が弁済その他の免責の行為をするに先立ち他の連帯債務者〔X〕に対し民法443条1項の通知をすることを怠った場合は,すでに弁済その他により共同の免責を得ていた他の連帯債務者〔X〕に対し,同条2項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない。 |
| *図47 最二判昭57・12・17民集36巻12号2399頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第22事件 | |
昭和57年最高裁の判断は,第1に,抽象的なレベルにおいても,民法443条の解釈を誤っている。その理由は,民法443条が,連帯債務者間の求償権について,事前・事後の通知を怠った連帯債務者は求償権を行使できないとして,求償権の行使を明確に否定しているにもかかわらず,先に弁済をしたという理由でXにYに対する求償を認めているのは,民法443条の趣旨にも,文言にも反しているからである。
昭和57年最高裁の判断は,第2に,事案の解決としても,負担部分の範囲内の弁済をしただけであるため,求償の余地がなく,したがって,事前の通知義務を課されていないYに対して,事前・事後の通知を怠ったため求償権を行使できないはずのXに求償権を認めており,具体的な妥当性を欠いている。その理由を詳しく述べると,以下の通りである。
連帯債務を債務と保証の結合と考える本書の立場(相互保証理論)に立つと,求償の要件としての通知は,負担部分を超える弁済(弁済に類似する出捐行為を含む)の場合と,負担部分を超えない弁済の場合とを厳しく区別する必要がある。先に明らかにしたように,第1に,負担部分を超える部分の弁済は,保証人としての弁済であり共同の免責を生じるために,求償が生じる。これに対して,第2に,負担部分の範囲内での弁済は,主債務者としての弁済に外ならず,求償の問題を生じない。したがって,他の連帯債務者に対して事前に通知する必要はない。このことは,一方で,保証人の場合は,債務者への事前の通知が必要であるのに対して,他方で,債務者の場合は保証人への事前の通知が必要とされないのと同じである。保証人の弁済は求償権を生じるため事前の通知が必要であるが,債務者の弁済は求償を生じないので,事前の通知をする必要がないためである。
もっとも,保証に関する民法463条2項は,「連帯債務に関する民法443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)の規定は,主たる債務者についても準用する」と規定している。この条文からは,主債務者も,保証人に対して,事前・事後の通知を要求されているように見える。しかし,ここでも,本来なら,保証の規定を連帯債務に準用すべきであるのにもかかわらず,逆に,連帯債務の規定が保証に準用されている点で,その解釈には,慎重な態度が要求される。
通説も,民法463条2項の適用に際して,主債務者の弁済については,事前の通知は問題とならないとしており[我妻・債権総論(1954)491頁],その理由については,[潮見・債権総論Ⅱ(2005)487頁]が,以下のように,的確な説明を行っている。
民法463条2項は,主たる債務者が弁済その他の出捐行為をした場合につき,事前の通知,事後の通知に関する連帯債務の規定(民法443条)を準用している。けれども,事前の通知を定める民法443条1項の規定は,主たる債務者が弁済その他の出捐行為をする場合には,準用の余地がない。なぜなら,「事前の通知」の制度は,弁済その他の出捐行為をした者が債権者に対して有する抗弁でもって対抗できるとするものである。ところが,主たる債務者が弁済その他の出捐行為をしたとしても,主たる債務者は保証人に対して求償権を有しない。だから,ここでは,443条1項を準用する基礎が存在しないのである。
このように考えると,通知を怠った連帯債務者間の求償の問題を論じる場合にも,原則に立ち返り,まず,保証人と主たる債務者間の求償の法理を明らかにした上で,連帯債務者間の求償について考察することが賢明であることがわかる。
保証に関しては,民法463条は,通説の立場によっても,以下のように解釈されていることを確認する必要がある。
そうすると,通知を怠った連帯債務者間の事前・事後の通知に関しても,明文の規定はないが,以下のようなルールを導くことができる。
以上の考え方に基づいて,先の最高裁昭和57年判決の事案を検討してみよう。本件の場合,事前・事後の通知が要求されるのは,負担部分を超えて弁済をし,Yに対して求償を求めているXだけである。求償を請求されているYは,自己の負担部分について弁済をしているに過ぎず,先に述べたように,負担部分の範囲内の弁済については主債務者による弁済と同視されるため,民法443条1項の事前の通知は必要とされない。したがって,たとえ,最高裁の見解に従って,一般論としては,連帯債務者の1人は,民法443条2項の適用を受けるための前提として,民法443条1項の事前の通知が必要とされるとしても,本件の場合には,Yの弁済は,負担部分の範囲内であり,求償の問題は生じないので,事前の通知は必要とされない。そのため,本件においては,Yは,事前の通知をしなくとも民法433条2項の効力を受けることができるという,最高裁昭和57年判決の結論とは逆の結論が導かれることになる。
最高裁やそれを支持する学説が,本件について誤りを犯している原因は,民法465条2項の「誤った反対解釈」によって,連帯債務者は,負担部分の範囲内で弁済をした場合にも,他の債務者に求償ができると考えているからに他ならない。連帯債務者の場合も,共同保証人の場合と同様,負担部分を超えて弁済をした場合にのみ求償ができるのであり,負担部分の範囲内の弁済については,事前の通知は問題とならないことを理解するならば,最高裁昭和57年判決が事案の解決に際して,誤った判断を下していることが理解できる。このことからも,保証に関して連帯債務の規定が準用されている場合の解釈については,慎重な判断をすべきことが理解できるであろう。
最後に,事案の解決を離れて,事前求償・事後求償の考え方についてまとめておくことにする。
保証人および連帯債務者に要求される事前・事後の通知は,他人の債務を弁済する際の保証人の注意義務の問題である。他人の債務を弁済する際には,第1に,弁済に先立って,主たる債務者が抗弁を有していないかどうかを確認する義務がある(事前の通知=確認義務)。第2に,弁済後は,主たる債務者が二重弁済をしないように配慮するとともに,自らの求償権を確保するために,事後の通知が義務づけられる(事後の通知=配慮義務)。したがって,もしも,この要件を満たさずに弁済をした場合には,求償権を行使することができなくなる(求償権の消滅)。すなわち,通知義務に違反した保証人は,二重に弁済した分(負担部分を超えて弁済した部分)を債権者から不当利得として取り戻すしかない。
このような保証人の注意義務を連帯債務に応用したのが,民法443条の規定に他ならない。したがって,本書の立場は,民法443条の文言どおりの解釈を行い,両当事者ともに求償の要件を欠いている場合には,両当事者ともに求償権を行使できず,二重弁済を受けた債権者から,負担部分を超えて弁済した分の返還を請求するほかないということになる(加賀山説:求償権の相互消滅説)。
以上の保証人の注意義務に対して,債務者に要求されるのは,事後の通知だけである(民法463条2項は,民法443条を債務者に準用しているが,先に述べたように,債務者は求償権を有しないのであるから,事前の通知は基礎を欠いているとされており,事前通知は必要がない)。しかも,事後の通知も,委託を受けた保証人に対するものに限定されている[民法463条2項]。その理由は,債務者に要求される事後の通知は,自らの求償権を確保するための通知ではなく,委託した保証人に対して二重弁済をしないように配慮・警告するためのものだからである。この通知を怠ると,債務者は,たとえ自らの債務を弁済しても,その効果を二重弁済した保証人に対抗できなくなる。
人的担保の問題については,通常の保証人と物上保証人との関係が問題となるが,従来の学説では,それをどのように位置づけるべきかについて,議論が深められていない。物上保証人については,民法では,物的担保である質権の箇所で規定され[民法351条],抵当権において,この規定が準用されている[民法372条]。しかし,民法351条の物上保証人に関する規定の内容は,人的担保である保証の規定を準用するというものである。したがって,物上保証人の負う責任は,人的担保なのか,物的担保なのか一見したところでは明確でない。
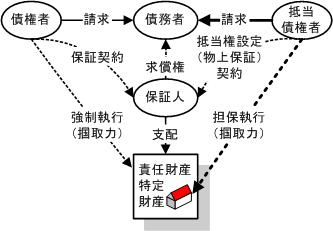 |
| *図48 保証(人的担保:左側)と 物上保証(物的担保:右側)との関係 |
そもそも,保証は,優先弁済権を伴わないからこそ,人的担保として債権法の世界に分類されていたのである。ところが,質権,および,抵当権の箇所で規定されている物上保証の場合には,当然に優先弁済権が問題となるため,物的担保の問題であることに異論はない。しかし,物上保証人が有する求償権は,弁済による代位の規定の箇所で詳しく規定されている[民法501条]。そこでは,「保証人と物上保証人との間においては,その数に応じて,債権者に代位する。ただし,物上保証人が数人あるときは,保証人の負担部分を除いた残額について,各財産の価格に応じて,債権者に代位する」[民法501条5号]というように,保証人と物上保証人との代位の範囲が保証人としてほぼ同質のものであるとの前提で規定されている。
しかも,昭和51年最高裁判決〈最一判昭61・11・27民集40巻7号1205頁〉によれば,通常の保証と物上保証の両資格を1人が負担する場合には,物上保証人の資格は,保証人の資格の中に吸収されるかのような判断を下している。
最一判昭61・11・27民集40巻7号1205頁
複数の保証人及び物上保証人の中に二重の資格をもつ者が含まれる場合における代位の割合は,民法501条ただし書き4号,5号の基本的な趣旨・目的である公平の理念に基づいて,二重の資格をもつ者も一人と扱い,全員の頭数に応じた平等の割合であると解するのが相当である。
ところが,平成2年最高裁判決〈最三判平2・12・18民集44巻9号1686頁〉は,民法460条で認められている事前求償権について,委託を受けた通常の保証人とは異なり,物上保証人に対しては,これを認めないとしている。
最三判平2・12・18民集44巻9号1686頁
債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は,被担保債権の弁済期が到来したとしても,債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできないと解するのが相当である。
最高裁が,事前求償を通常の保証人には認めるが,物上保証人には認めないとして区別をする理由とその批判(筆者)は以下の通りである。
このように,判例の理解によると,物上保証は,一方では,弁済による代位の関係では,人的担保である保証と同様のものとして扱われているが,他方で,事前求償権に関しては,物的担保として,人的担保としての保証とは異なるものとされているのである。
しかし,最高裁が物上保証人に事前求償権を認めない実質的な理由として挙げている,「抵当不動産の売却代金による被担保債権の消滅の有無及びその範囲は,抵当不動産の売却代金の配当等によって確定するものであるから,求償権の範囲はもちろんその存在すらあらかじめ確定することはでき」ないとしているのは誤解である。なぜなら,物上保証人の法的地位は,担保権の実行によって担保目的物の所有権を失う点で,第三取得者と同様であり,その求償権の範囲は,民法566条~568条に明確に来てされており,物上保証人の求償権の範囲は,担保権の実行の前後を通じて,変化するものではなく,明確に確定できるからである。
このように考えると,通常の保証人が債権の額の範囲で無限責任を負うのに対して,物上保証人は,担保目的物の価額の範囲でのみ有限責任を負うため,求償の額については,差が生じるが,事前求償と事後求償とで差をもうける必要は存在しないということができよう。
それでは,担保法の全体の中で,物上保証をどのようなものとして考えるべきであろうか。
| 保証の種類 | 優先権の有無 | 責任を負担する者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人的担保 (無限責任) |
連帯債務 | 約定 | 債権者に 優先権なし |
相互に連帯保証をする債務者(連帯債務者) |
| 保証 | 債務者の債務を肩代りする責任を負う者(保証人) | |||
| 物的担保 (有限責任) |
物上保証 | 法定 | 詐害行為の受益者または転得者(受益者・転得者) | |
| 約定 | 債権者に 優先権有り |
債務者のための質権・抵当権の設定者(物上保証人) | ||
| 法定 | 抵当権が設定された不動産の取得者(第三取得者) | |||
物上保証は債務のない責任である点で,人的保証と同じであるが,その責任が目的物に限定される,すなわち,有限責任である点で,無限責任である保証責任とは異なる。しかし,物上保証を広い視野で捉えると,担保権が設定された物件の第三取得者は,物上保証人とほぼ同じ地位に立つし[梅・要義巻三(1897)315頁],詐害行為の受益者・転得者も,目的物について有限責任を負う点では,物上保証人に類する。このような広い意味での物上保証が常に優先弁済権とかかわるかというと,詐害行為の場合の受益者・転得者のように,有限責任しか負わない上に,優先弁済権にもかかわらないという場合もありうる。したがって,広い意味での物上保証に共通の特色を述べるならば,目的物についてのみ,有限責任を負う制度であるということができる。
現行民法は,タイトルこそ保証債務というタイトルをつけているが,保証の冒頭条文[民法446条1項]では,保証は,主たる債務者の「債務」を履行する「責任」に過ぎないこと,すなわち,責任であって債務ではないことを,以下のように,明確に宣言している。
第446条(保証人の責任等)
①保証人は,主たる債務者がその債務を履行しないときに,その履行をする責任を負う。
保証を理解するための最初のステップは,保証が債務ではなく,責任に過ぎないということを理解することである。保証が債務ではなく,債務者から全額求償されるべき仮の責任であることが理解できてこそ,現行民法における保証の規定のほとんどすべてが,保証人の免責の規定(付従性,補充性,事前・事後求償)で埋め尽くされていることの意味を理解することができる。特に,保証人から奪われてはならないのは,債務者に対して求償できる権利であることを忘れてはならない。求償を妨げる債権者の行為は,民法504条により,信義則に反するということも,そのような考え方によって支えられていることを理解することが重要である。
保証とは,債権者と保証人との間で,第三者である「債務者がその債務を履行しないときに」,保証人が債権者のために債務者に代わって「その債務を履行する責任を負う」という片務契約である[民法446条]。保証契約は,無償で行われるので,保証契約は,通常は,片務・無償の契約である。
それでは,債務者が一定の信用保証料を支払って保証サービスを受ける有償の保証契約,特に,保証協会による機関保証をどのように位置づけるべきであろうか。有償の機関保証も保証の一種であると考える考え方が通説である(詳細は,[潮見・債権総論Ⅱ(2005)422-434頁],三林宏「保証類型論-「期間信用保証」の学説における位置づけを中心として」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)185頁以下]参照)。しかし,有償の機関保証の実態をよく見ると,保証会社は,債務者のために弁済する責任を負っているというよりは,債務者が債務を任意に支払わない場合に,その不良債権を買い取り,債権者に代わって債権回収を行っていることがわかる(無償保証と有償保証とを対比した*図49,*図50参照)。
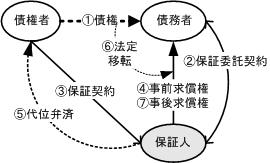 |
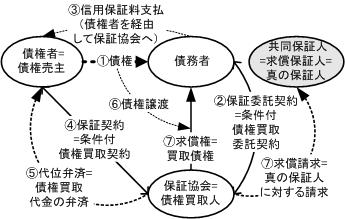 |
| *図49 無償保証(個人保証) 無償で危険を引き受ける保証人の保護として, 保証の求償権の確保が重要な課題となる。 |
*図50 有償保証(機関保証) 有償の保証人は債権買取人とみなされる。 3者間の危険の分担は,債権の売主の 担保責任の問題として解消される。 |
つまり,有償の機関保証は,債務者のために債務者に代わって責任を負うという無償の保証契約(民法446条~465条の5)とは異なり,債権者のために債権者から債権を買い取って,債権者に代わって債権回収を行うという,ファクタリング契約の一種であり,債権の売主の担保責任(民法569条)および債権譲渡の規定(民法466条~473条)が適用されると考えるべきである。
したがって,有償の機関保証と通常の保証契約(無償の個人保証契約)とを同等に論じるべきではない。特に,通常の保証のように,保証人を厚く保護する必要はなく,債権の売買契約として処理すれば足りる。有償の機関保証における保護すべき保証人とは,債権買取人としての信用保証協会ではなく,信用保証協会と同列の共同保証人とされてはいるが,現実には,信用保証協会の求償保証人とされて最終的な責任を押し付けられる中小企業の経営者個人(*図50の網掛け部分)であろう。民法465条の2以下の貸金等根保証契約が法人保証を適用除外としつつ,法人保証の求償保証人(個人)について適用を認めているのは,この理由に基づいている。
信用保証協会の保証が,本来の保証ではなく,債権の買取りであることは,信用保証協会が債務者に代わって弁済したことを理由とする共同保証人(物上保証人)に対する求償権の濫用的行使を追認した昭和59年最高裁判決〈最三判昭59・5・29民集38巻7号885頁(民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第39事件)〉を見れば歴然としている。
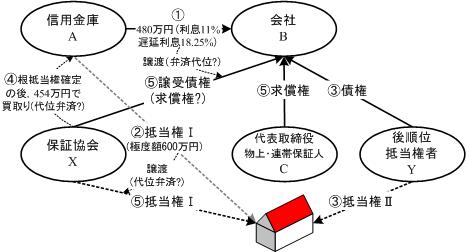 |
1. 保証人〔信用保証協会X〕と債務者〔B〕との間に求償権について法定利息〔商事法定利率の年6%〕と異なる約定利率〔年18.25%〕による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には(①),代位弁済をした右保証人〔X〕は(④),物上保証人〔C〕及び当該物件の後順位担保権者〔Y〕等の利害関係人に対する関係において,債権者〔A〕の有していた債権及び担保権〔確定した根抵当権〕につき,右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として,これを行使することができる。 2. 保証人〔X〕と物上保証人〔C〕との間に民法501条但書5号所定の代位の割合〔XとCの代位割合は等分〕と異なる特約〔Cの代位割合ゼロ〕がある場合には,代位弁済をした右保証人〔X〕は,物上保証人〔C〕の後順位担保権者〔Y〕等の利害関係人に対する関係において,右特約の割合に応じて債権者〔A〕が物上保証人〔C〕に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。 |
| *図51 最三判昭59・5・29民集38巻7号885頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第39事件 |
判旨1は,信用保証協会Xと債務者Bとの間でなされた,民法459条2項によって準用される「民法442条2項の求償権制限に反する約定」について,最高裁が実務慣行として追認したものである。しかし,これは,求償理論をはるかに超えた無体な理論である。信用保証協会Xの行使する権利が,求償権でなく,債権買取によって譲渡を受けた債権の行使と解釈した場合にのみ成り立つ議論であろう。
判旨2は,民法501条5号に反して,物上保証人の代位割合をゼロとする不条理な約定を当事者X・C間のみならず,後順位抵当権者Y等の第三者に対してもその有効性を認めるという債権の相対性を無視した暴論である。この結論は,XがAの債権を買い受けたと考えた場合のみに成り立つ議論である。
このように,有償の保証としての機関保証は,本来の保証ではなく,債権の買取り(ファクタリング)であると考えなければならない。したがって,ここでは取り上げない。本書では,通常の保証契約である無償の保証に限定して論じることにする。
2004年の民法改正によって,保証は,多数当事者の債権・債務関係として位置づけられるばかりでなく,書面を必要とする一種の要式契約として位置づけられることになった。
保証契約の効力要件として,書面によることが要求された理由を本書の立場から説明すると,以下の通りである。
すべての有償契約について売買の規定が準用される[民法559条]のと同様,無償契約である保証契約についても,贈与契約の規定,すなわち,民法550条(書面によらない契約は履行するまでは撤回できる),民法551条(要約者は担保責任を負わない)が準用されるということから出発するのが衡平と思われる。なるほど,贈与の規定には,売買の場合のように,売買の規定はその他の有償契約に準用するという民法559条のような規定は存在しない。しかし,無償契約の一つである使用貸借の規定には,贈与の重要な規定である無担保原則について,贈与の規定を準用するという規定が存在する。これをさらに一般化して,贈与契約の規定に,すべての無償契約に準用されるという規定があってよいというのが,筆者の発想の原点である。
この考え方は,一見すると,過激に見えるかもしれない。しかし,片務・無償の契約である保証契約に関して,贈与に関する民法550条,551条が準用されると考えるならば,以下の点が導かれるとともに,さまざまな疑問点が解明されることになる。
継続的保証(根保証)には,信用取引上の債務を負担する「信用保証」,雇用契約上の被用者の債務を保証する「身元保証」,賃貸借契約における賃借人の債務を保証する「賃貸保証」がある。
このうち,「身元保証」については,学説と判例の集積に基づいて身元保証法(1933年)が制定され,「包括根保証(保証限度額または保証期間が限定されていない保証)」について責任が限定されている。そして,「信用保証」のひとつである「貸金等根保証」については,2004年民法改正によって,保証人にとって過酷な責任を課す「包括根保証」が無効とされ,限定根保証に一本化されるに至った。しかし,2004年の民法改正によって規制されるのは,「貸金債務(金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務)」に限定されている。また,「賃貸保証」については,包括根保証についての規制がいまだに存在しない。
このような法律の規制がなされる以前から,判例によって包括根保証における保証人の保護がなされてきた。そして,判例によって,包括根保証人の解約権の法理が確立されてきた。
第1は,保証人の特別解約権の法理であり,大審院判例〈大判大14・10・28民集4巻656頁,大判昭9・2・27民集13巻215頁〉によって確立された。
大判大14・10・28民集4巻656頁
凡そ将来成立すべき主債務に付,其の時期を制限しあらざる場合は反対の事情の認むべきもの無き限り,保証人は相当の日時経過後は解約権を行使するを得べく(此の解約権は相当の予告期間を存すべきか否かは各場合の事情に依る)若又,主債務の成立に先ち主債務者の財産状態に著しき欠陥を生じたるときは,保証人に直に解約権を行使するを得と解すべきは,此の種の取引に於ける当事者の意思解釈よりずるも又信義の観念に訴ふるも殊に此の後の点は民法第589条〔消費貸借の予約と破産手続きの開始〕の法意を類推するも当然の事に属する。
大判昭9・2・27民集13巻215頁
相当と目すべき時間を経過したる後は,保証人に於て相当の予告期間を以て任意解約権を行使するを得(茲に相当の予告期間と云ふは爾後の分は最早無保証となるが故に債権者に於て此が対策を講するに必要なる期間を指す)と解すること反対の事情無き以上之を以て当事者の意思に諧〔かな〕へるものと云はざるを得ず。
第2は,保証人の任意解約権の法理であり,昭和39年最高裁判決〈最二判昭39・12・18民集18巻10号2179頁〉によって確立された。
最二判昭39・12・18民集18巻10号2179頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第25事件
期間の定めのない継続的保証契約は,保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至った等保証人として解約申入れをするにつき相当の理由がある場合には,右解約により債権者が信義則上看過できない損害をこうむるような特段の事情がある場合を除いて,保証人から一方的に解約できるものと解するのが相当である。
これらの判例法理は,2004年の民法改正によってカバーされない包括根保証契約(例えば,賃貸保証契約,身元保証契約等の貸金等根保証契約以外の契約)に適用されることはもちろんのこと,2004年改正によってカバーされる限定根保証契約においても,元本の確定事由が列挙されているだけであり[民法465条の4],確定事由の一般条項が欠落している以上,上記の判例法理は,今なお,先例としての価値が失われていない(詳細については,平野裕之・民法判例百選Ⅱ〔第6版〕52-53頁参照)。
2004年の民法改正により,保証契約の内容の適正化という観点から,個人保証人の保護を図るため,貸金等根保証契約について極度額,元本確定(根保証の終了)につき,その確定期日・確定事由に関する規定を新設すること,その他の保証債務に関する規定の整備が行われた。その主な内容は次の通りである(立法によっても解決されていない問題点については,吉田光硯「保証制度の改正が保証協会実務に与える影響」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)208頁以下]参照)。
本書では,以上のように,民法の保証に関する規定が,保証人の免責を中心になされているのはなぜなのかを検討することを通じて,片務・無償の保証の特質および保証人の免責の意味を再検討することにする。
すでに述べたように,また,次の*図52によっても明らかなように,保証は債務なき責任である。保証関係においては,債権および債務は主債務ただ1つであり(実線部分),保証人が負うのは,債務ではなく,主債務を肩代りして履行する責任に過ぎない(点線部分)。債務ではなく,責任に過ぎないからこそ,保証人は,債務者に対して求償権を有するのである。点線部分の肩代り責任と求償権とが組み合わされて,実線部分の債権(主債務)へのバイパスが出来上がっていることに注意すべきである。
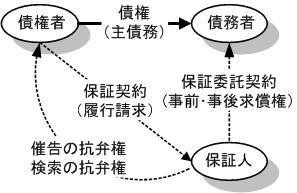 |
| *図52 通常の保証契約の構造 |
保証契約は,必ずしも,債務者による保証委託を必要としない(民法462条参照)。しかし,通常は,債務者の委託([民法459条]参照)に基づいて,債権者と保証人との間で保証契約が締結される。
保証契約は,他人の債務を無償で負担するという片務・無償の契約であるから,非常に危険な契約である。したがって,このような危険な契約については,一方で,「『保証するな』は親の遺言」として,そのような契約を極力回避することが勧められ,他方で,そのような危険な契約を締結した保証人に対しては,以下のような非難の言葉が投げかけられてきた[星野・民法概論Ⅲ(1981)175頁(Heckの表現)参照]。
しばしば,愛他的・楽天的な,情に脆く人を信じ易い,一言でいえば非常に好ましい人物が,軽々しく保証債務を引き受けて財産を失い,自己のみならず家族の没落を招くに至る。
しかし,学生が奨学金を受けるにしても,自立のために住宅を借りるにしても,さらには,起業をめざすにしても,保証人の助けなしには自立の道を歩みがたいのが現実である。社会が保証人を必要としておきながら,無償で社会的な貢献を果たしている保証人に対して,保証人になったこと自体を非難したり,「保証した以上は,責任を負うのは当然である」として保証人だけに危険を押し付けたりすることは,衡平ではなく,社会的正義に反するというべきである。
2004年の民法改正においては,保証の最初の規定に,「保証契約」という用語が用いられており,保証が多数当事者の債権・債務関係に関するものだけでなく,契約の一つであることを明確にした点で評価されるべきである。
もっとも,保証契約に書面性を要求したところで,電磁的記録のように,自書によらない書面でもよいというのでは,保証人を保護できないことは明らかである。そうだとすれば,書面でしなければ保証契約の効力が生じないとされるに至った理由は,保証人の保護というよりは,債権者を保護し,法的安定を確保するため,無償契約の性質として,履行するまでは理由なしに「撤回」できるはずの保証契約を書面契約とし,保証契約を「撤回」できないものとしたと考えるのが妥当であろう。
保証は,債権者と保証人との間の保証契約によって生じる。しかし,保証契約は債権者と保証人との間の保証契約だけでは存在しえない。保証契約が存在するためには,債権者と債務者との間に主たる債務が存在することが必要であり,さらに,通常は,債務者と保証人との間の保証委託契約も存在する。もしも,債権者と債務者との間に主たる債務が存在しない場合には,保証債務も,付従性によって,そもそも不成立となるか,無効となるか,そうでなければ消滅する[民法448条]。
保証契約においては,保証人は,債務者が債務を弁済しなかった場合には,債務者に代わって債権者に債務を弁済することを約する。この保証契約は,保証人は,対価を得ることもなく,しかも,一方的に責任を負うだけである。すなわち,保証契約は,贈与と同じく,片務・無償の契約である。したがって,書面によらない保証契約は,実際に保証の責任が生じるまではいつでも撤回ができると考えるべきである[民法550条の準用]。
先に述べたように,2004年の民法改正によって,「保証契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。」とされたが,この規定は,保証人の保護にとってはほとんど意味をもたない上に,契約自由の原則にも反した無用の改正であり,いずれ再改正が必要と思われる。このように考えると,確かに,現行民法の解釈としては,書面によらない保証契約は,民法446条2項に従って,無効と解すべきである。しかし,今後,民法が改正され,契約自由の要請等から,保証契約の要式性が不用とされた場合でも,保証人の保護は可能である。その場合の保証人保護の考え方は,以下の理由に基づくことになると思われる。すなわち,無償の保証契約には,無償契約の典型である贈与契約の規定が準用されるべきであり,書面によらない保証契約には,民法550条が準用されるため,保証人は,履行がなされるまで,保証契約をいつでも撤回できる。したがって,保証契約がいつでも撤回されるのを防止しようと思えば,債権者は,書面による保証契約を締結するほかない。それが,現行民法446条2項の真の理由でもあり,その規定がなくなったとしても,保証人保護のために使える考え方なのである。
保証人が,何のメリットもなく責任だけ負担させられる保証契約を債権者と締結するのは,通常は,債務者に保証を頼まれるからである(保証委託契約)。この保証委託契約においては,債務者は,保証人に絶対に迷惑をかけないことを約束する。
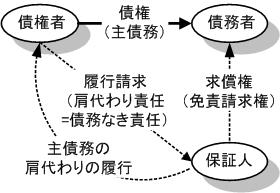 |
保証委託契約の成立例 債務者:保証人がいないと債権者が融資をしてくれません。信用のあるあなたに保証人になっていただきたいのです。もちろん,債務は必ず私が弁済するのであって,あなたに払わすようなことはしません。万が一,債務を弁済してもらうような事態が生じたとしても,必ず私がお返しするのでご迷惑はおかけしません。 保証人:事情は理解しましたので保証人になりましょう。しかし,私はあなたに信用を与えるだけなので,債務は必ず自分で返済してください。 |
| *図53 保証は主債務のバイパス 保証は債務のない責任であり,本来の債務ではない。単に,債権(主債務)のバイパスを形成しているに過ぎない。 |
債務者が保証人にする以上の約束を法律的に分析すると以下のようになる。
以上の約束は,単なるリップサービスに留まらない。民法は,債務者の保証人に対する約束を実現させるため,保証人の権利として,債務者に対する求償権を与えている[民法459条以下]。さらには,後に述べるように,債権者が保証人の求償権を妨害した一定の場合には,保証人を免責する規定まで用意している[民法455条,504条]。
民法446条~465条の5までの「保証債務」の規定をみると,過酷な責任であるはずの保証人の責任が「縮減される」[民法448条]とか,「その義務を免れる」[民法455条]とか,「債権者に対抗できる」[民法457条2項]とか,「主たる債務者に対して求償権を有する」[民法459条1項,462条,464条]とか,「あらかじめ,求償権を行使することができる」[民法460条1項]とか,保証人を免責する条文で埋め尽くされている。
その理由は,先に述べた保証の危険性にある。本来,片務・無償契約においては,債務者は,担保責任を負わないのが原則である([民法551条],[596条])。したがって,片務・無償の契約によって保証人に無限責任(物上保証人との対比で)を負わせることは,契約正義に反する。つまり,片務・無償の保証契約において,保証人に担保責任を負わせることは,消費者契約法10条の趣旨(任意規定と比較して消費者(弱者)の利益を一方的に害する条項は信義則に反しており無効となる)を考慮するならば,契約自体を無効とするおそれがある。
民法が,「保証債務」の規定を保証人の免責の規定で埋め尽くしているのは,見かけだけの問題ではなく,保証契約を無効としないための安全弁である(したがって,このような安全弁を取り除くような債権者有利な契約条項等がある場合には,原則に戻って,その保証契約は無効となると考えなければならない。
| 免責要求の分類 | 名称 | 内容 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 債権者に対する 免責要求 |
保証の付従性 | 責任を債務者以下の責任に限定すること | 債務の縮小・消滅 | 債務者の責任の減少の範囲で免責される[民法448条]。 |
| 催告の抗弁権 | まず,債務者に対して請求すること | 債権者の懈怠 | 迅速な催告をしなかったことから生じた結果に関して免責される[民法455条]。 | |
| 検索の抗弁権 | まず,債務者の財産から執行すること | 迅速な執行をしなかったことから生じた結果に関して免責される[民法455条]。 | ||
| 担保保存義務 | 求償権を確保するため,担保を保存すること | 担保の減少・滅失によって求償権を行使できなかった限度で免責される[民法504条]。 | ||
| 情報提供義務 | 債務者の資力に関する情報を提供すること | 保証契約の締結の回避,解除の機会を失ったことによる限度で免責される。 | ||
| 債務者に対する 免責要求 |
抗弁の援用 | 債務者の有する時効・相殺の抗弁を援用すること | 債務者の抗弁 | 債務者が債権者に対して有する抗弁を援用することによって免責される[民法457条]。 |
| 事前求償権 | 債務者の財産でもって弁済するため,事前に求償すること | 保証委託契約 | 債務者の財産で弁済することによって免責される[民法460条]。 | |
| 事後求償権 | 責任を果たした後に,事後求償すること | 担保責任の実行 | 債務者に事後求償することによって補償を受ける[民法459条,462条]。 | |
| 共同保証人に対する 免責要求 |
事後求償権 | 責任を果たした後に,事後求償すること | 担保責任の実行 | 共同保証人に求償することによって補償を受ける[民法465条]。 |
実務の取扱いにおいては,保証契約の付従性が剥奪されて,独立担保契約とされたり,債務者のみを免責したりすることによって,保証人の求償権が確保されていない場合が多い。このような場合には,原則どおり,無償の保証人は担保責任を負わない。
以下では,保証人の免責に関する個々の問題点(付従性による保証人の免責,債権者の懈怠による保証人の免責)について,くわしく検討することにする。
保証は,民法446条によれば,主たる債務者がその債務を履行しない場合に,主たる債務者に代わって主たる債務を履行する責任のことをいう。したがって,保証は,主たる債務がなければ存在しないし,主たる債務が無効となれば,保証も無効となり,主たる債務が消滅すれば保証も消滅する。これを保証の付従性[民法448条]と呼んでいる。
もっとも,行為能力が制限されている人が負担する債務について,取消し原因があること(その人が責任を制限されていること)を知りつつ保証を行なった場合には,保証を行なった者は,独立の債務を負担したものと推定されることになっている[民法449条]。
民法449条において,制限行為能力者が契約を取り消した場合に保証人が負担する独立の債務は,損害担保契約または独立担保といわれている。この債務の本質は,完全な独立の債務であって,本来の保証ではない。この場合,付従性も求償権も発生しないからである(損害担保契約については,[潮見・債権総論Ⅱ(2005)434-439頁]が詳しい)。
民法449条が,取り消すことができる債務全般について規定せず,制限行為能力者に対する保証に限定して,独立の債務を負担するとしたことには,深い理由がある。そのことは,制限能力者ではなく,詐欺・強迫による取消しの場合を考えればよくわかる。
詐欺・強迫によって契約が取り消された場合には[民法96条],詐欺・強迫による契約は無効となるため,債務者と同様,保証人も責任を負わない。たとえ,保証人がその契約が詐欺・強迫によってなされたことを知って保証をした場合であっても,債権者の詐欺・強迫によって契約をした債務者がその契約を取り消した場合には,取消しによって効力を失った債務について保証人は責任を負わない。もしも,その場合でも保証人が責任を負わなければならないとしたら,詐欺や強迫をする者は,保証人を立てることによって,公序良俗に違反する契約を実質的に有効としてしまうことになる。これでは,詐欺・強迫による意思表示を取り消すことができるとした立法趣旨が無意味になってしまう。
このように考えると,民法449条の射程を,制限能力者の問題を超えて一般化することの危険性が明らかになる。例えば,[内田・民法Ⅲ(2004)342頁]は,立法者が未成年者を含めた制限能力者の起業を支援する保証人の責任の場合だけを想定していたために,民法449条の適用がないとしていた問題,すなわち,債務者が詐欺・強迫をした場合について,以下のように,民法449条の適用範囲を拡大することを主張している。
債務者の側が詐欺をして貸付を受け,債権者が取り消した場合には,詐欺・強迫による取消を449条の適用対象から除外する上述の議論が妥当するとは思えない。449条を類推適用して,債権者保護のために,詐欺を知っている保証人の保証債務を存続させるべきではないだろうか。
しかし,この例は,債務者が詐欺をした場合であって,通常は,付従性が問題とならない事例である。なぜなら,債務者の詐欺によって貸付をした債権者が債権を回収しようと思えば,詐欺による取消しをする必要はなく,そのまま回収を行えばよい場合だからである。取消しをするかどうかは債権者の自由であり,取り消した以上は,付従性の制限に服さなければならないと考えるべきである。もっとも,債権者が契約を取り消して債務者と保証人に請求を行う場合には,消費貸借契約が取り消されたことによって生じる,別の有効な債務,すなわち,民法703条以下の不当利得返還請求権についても,保証人の責任がおよぶかという,民法447条の保証債務の範囲の問題が生じるかもしれない([中田・債権総論(2008)458頁])。しかし,この問題は,付従性の問題とは別の保証債務の範囲の問題であり,この場合についても,保証人の責任が過大にならないような配慮が必要である。
後に詳しく論じるように,保証契約は無償の契約であり,本来担保責任を負わないはず[民法551条,民法596条]の無償の契約について,保証人に無限責任を負わせるという非常に危険な契約である。内田説をはじめ,通説は,「債権者保護」ばかりを強調する。しかし,債権者が債務者に信用を与えるに際して,その担保のためと称して,本来,債権者・債務者間で公平に配分すべきリスクを,無償契約によって,すべてのリスクを保証人に負わせるということになると,保証契約それ自体が,余りにも「債権者保護」に偏し,公平から逸脱した契約ということになり,有効性に疑いが生じることになる。
民法の保証の規定が,そのほとんどの条文を費やして,「保証人の免責」についてなされ,そのような免責の規定(催告・検索の抗弁とその違反による免責,事前求償・事後求償による免責,債権者の担保保存義務違反による免責等)で埋め尽くされていることは,このような保証人保護の条件が満たされた場合にのみ,無償の契約によって過酷な担保責任を負わされる保証人が保護され,「暴利行為=著しい不均衡」という契約の無効原因をかろうじて免れているのだという立法者のメッセージとして,真摯に受け止めるべきである。
このようにして,保証契約そのものが,資本形成期においてのみ許される,債権者を過度に保護する,著しい不均衡を内容とする無償契約であり,民法に規定された数々の保証人の免責規定を通じて,かろうじて契約自体の無効を免れているのだという認識に立つならば,保証契約において,「債権者の保護」を理由に,保証人の責任を拡大したり,類推したりすることは,危険である。
この問題との関係で敷衍すると,2004年の民法典の現代語化に際して民法449条の見出しが,「取り消すことができる債務の保証」と一般化されて規定されているのは問題である。民法449条の見出しは,あくまで「制限行為能力者の債務の保証」とすべきであったと思われる。
保証人は,債権者から債務の履行を請求されたときは,まず,主たる債務者に催告するよう求める催告の抗弁権を有している[民法452条]。また,債権者が主たる債務者に催告をした場合であっても,主たる債務者に弁済の資力があり,かつ,執行が容易であることを証明して,債権者に対して,まず,主たる債務者の財産について強制執行をするよう求める検索の抗弁権を有している[民法453条]。
保証人がこのような催告の抗弁権または検索の抗弁権を主張しているにもかかわらず,債権者が,催告をせず,または,強制執行を怠っているうちに,主たる債務者の資力が悪化し,債務者から全部の弁済を受けることができなくなってしまった場合には,債権者が直ちに催告または強制執行をしていたならば弁済を得ることができたであろう範囲で,保証人は免責される[民法455条]。
保証人は,主たる債務者がその債務を履行しない場合に,主たる債務者に代わって債務を弁済する責任を負うのであるから,債権者は,主たる債務者に履行を請求しようと,保証人に履行を請求しようと自由な立場にあり,債務者への履行請求が遅れたからといって,非難される筋合いではないはずである。債権者が非難されるのは,保証人が催告・検索の抗弁権を主張しているにもかかわらず,主たる債務者に対する催告・執行を怠ったため,債務者の資力が低下し,本来ならできたはずの保証人の求償権が確保されなくなったためであると考えるのが正当であろう。
債権者は,保証人と保証契約を締結した結果,信義則上,保証人の求償権を確保するための配慮義務を負うに至ると考えるならば,その配慮義務を怠った債権者に対して,保証責任の消滅という制裁が課せられるとしても,不思議ではない〈静岡地判昭31・9・4下民7巻8号2334頁〉。
静岡地判昭31・9・4下民7巻8号2334頁,判時95号18頁
債権者が債務者から抵当権の設定を受けるため,その登記に必要な一切の書類の交付を受けたが,その登記をせずに放置しているうち債務者は抵当物件を他に売却してしまったので,債権者はその登記をすることができなくなってしまったという事案において,それが,連帯保証人を免責する事由となるとされた事例
上記の判決例に即して考えると,保証人が催告または検索の抗弁権を主張しようとしても,債権者が抵当権の登記を怠っていて,すでに債務者の財産は競落されているため,これらの抗弁を主張しても意味がないように思われる。しかし,債権者が抵当権の登記をしておれば,債権者は債務者の財産に対して容易に執行することが可能だったのであるから,もしも,債権者が保証人の財産を当てにして,保証人の検索の抗弁権の行使を妨害するため,故意に抵当権の登記をしなかったのであれば,民法130条により条件は成就したものとみなして,民法455条に基づき免責を主張することも可能であろう。
債権者の行為によって保証人の求償権が害される典型例は,債権者の担保保存義務に違反する行為である。この場合に,民法504条によって保証人が免責されるのは,先の場合と同様,債権者の義務違反行為によって,保証人の求償権が害されたからである。
このように考えると,保証契約を締結した債権者は,信義則上,保証人の求償権を害しないような配慮義務を負うと解すべきである。このように考えることによって,民法455条と民法504条における保証人の免責を統一的に理解することが可能となるのである。
この考え方は,通常の保証人だけでなく,物上保証人,および,それに類似する地位に立つ,抵当権が設定された不動産の第三取得者,または,その譲受人にも妥当する〈最三判平3・9・3民集45巻7号1131頁〉。
最三判平3・9・3民集45巻7号1131頁
債務者所有の甲不動産と第三者所有の乙不動産とが共同抵当の関係にある場合において,債権者が甲不動産に設定された抵当権を放棄するなど故意又は懈怠によりその担保を喪失又は減少したときは,第三取得者はもとより,その後の乙不動産の譲受人も債権者に対して民法504条に規定する免責の効果を主張することができる。(意見がある。)
もっとも,最高裁平成8年判決〈最二判平8・12・19金法1482号77頁〉は,以下のように判示して,債権者が担保保存義務を特約によって免責することを認めている。
最二判平8・12・19金法1482号77頁
債権者である被上告人のした根抵当権放棄により,これをしないでC銀行に対する弁済がされなかった場合に比べて,被上告人の株式会社Aに対する求償金債権で物的担保により満足を受けることのできないものの額がより多額になったということはできないから,債権者である被上告人の右行為は,金融取引上の通念から見て合理性を有するものであり,連帯保証人である上告人Bが担保保存義務免除特約の文言にかかわらず正当に有し,又は有し得べき代位の期待を奪うものとはいえない。したがって,被上告人が右特約の効力を主張することが信義則に反するものとは認められないとした原審の判断は,結論において是認することができる。
しかし,民法504条の母法であるフランス民法[フランス民法典2314条]においては,このような免責特約は,信義則に反することを理由に無効となるという立法的な解決がなされている。
フランス民法典 第2314条
債権者の行為によって保証人が債権者の権利,抵当権及び先取特権について代位ができなくなるに至ったときは,保証人はその責任を免れる。これに反するすべての条項は書かれなかったものとみなす。
保証は無償の片務契約とされており,義務を負うのは保証人だけであって,債権者は保証人に対して何らの義務も負わないとされてきた。それにもかかわらず,債権者が保証人に対して担保保存義務を負うのはなぜか。それは,債権者といえども,保証人が債務者に対して有している求償権を害してはならないという信義則上の義務を負うからである。契約外の第三者も債権者の担保義務違反を援用することができる〈最三判平3・9・3民集45巻7号1131頁〉のは,それが,信義則上の義務だからである。
これに反して,民法504条に規定された担保保存義務を免責する特約は,故意による信義則違反であり,特段の事情がない限り,無効である。したがって,そのような免責条項は,第三者に対して効力を有しない。最高裁は,このような信義則に反する特約の第三者に対する効力を認めている〈最二判平7・6・23民集49巻6号1737頁〉。
最二判平7・6・23民集49巻6号1737頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第41事件
債権者甲の債務者乙に対する債権を担保するために所有不動産に根抵当権を設定した丙が甲との間に民法504条に規定する担保保存義務を免除する旨の特約をしていた場合に,甲が乙から設定を受けた担保を喪失〔本件では放棄〕し,又は減少させた時に右特約の効力により丙について同条による免責の効果が生じなかったときは,その後丙から右不動産の譲渡を受けた丁は,甲に対し,同条による免責の効果を主張することはできない。
しかし,この判例は,民法504条の解釈を誤っている。なぜなら,民法504条の条文自体が,信義則に基づいて債権者に担保保存義務を課した規定(信義則に基づく強行法規)であり,それを免責すること自体が,信義則に反しており,そのような免責条項が,契約の当事者以外の第三者に対して効力を有するとすること自体が,信義則に著しく違背するからである。
信義則から認められる担保保存義務が,当然に,第三者に対しても効力を有する〈最三判平3・9・3民集45巻7号1131頁〉からといって,信義則に反しており,当事者間でも無効とすべき担保保存義務免除特約が第三者に対しても効力を有すると考えるのは,全くの誤りである。
最高裁をはじめ,最高裁の立場に追随する通説が,このような誤りに陥っている理由は,保証に関する最も重要な問題が,無償で無限責任を負わされている保証人を免責することであることを理解していないからである。保証人の免責については,付従性の問題ばかりでなく,保証人の求償権を確保することも重要な課題である。保証人の求償権を故意に妨害してはならないという債権者の担保保存義務[民法504条]は,保証人に対する債権者の信義則上の義務であり,当事者の特約によって変更することができない保証に固有の問題である。保証の問題を解決するに当たっては,このことを肝に銘ずべきである。
連帯保証は,保証の一種であり,付従性を有する。すなわち,主たる債務者について生じた事由は,すべて連帯保証人にその効力を及ぼす[民法448条,457条2項]。しかし,連帯保証人は,補充性がない,すなわち,催告の抗弁権も検索の抗弁権も有しない点[民法454条],さらに,連帯保証人が数人いても分別の利益[民法456条]をもたない点で通常の保証と区別されている。このように,連帯保証は,通常の保証よりもさらに厳しい責任であり,債権者にとって有利である。このため,実際の取引界では,通常の保証よりも頻繁に用いられており,その弊害は目に余るものがある。
たとえば,学生がアパートを借りる場合を考えてみよう。賃貸借契約に際しては,賃借人には,通常,保証人が求められる(学生のいわゆる保護者(親)が保証人となることが多い)。賃借人が賃料不払いとなった場合に,頼りになるのが保証人だからである。その際に,保証人は,通常の保証ではなく,連帯保証人となることが求められるのが実務の慣行となっている。しかし,この場合に,実際に保証人は連帯保証人として扱われているかどうかを調査してみると,理論と実務とは乖離していることが多いことがわかる。もしも,賃貸借契約における保証人が連帯保証人であるならば,賃借人が賃料の支払いを怠った場合に,賃借人に催告することなく,直ちに,保証人に賃料の請求ができることになる。しかし,実際は,まず賃借人に催告し,それでも支払いがない場合に,いわゆる保護者に催告するのが現実であり,いきなり保護者に催告する例は,本人が行方不明になっている等,本人に連絡ができないという場合を除いてほとんどない。賃料支払いの遅れがあったからといって,当事者を差し置いて,いきなり保護者に請求することは,当事者の信頼関係を破壊するおそれがあるからである。
したがって,このような場合の連帯保証は,書面の上では慣行となっているが,実際の運用は,通常の保証と同じように扱われており,債権者に行き過ぎた権利を与えるといういわゆる通謀虚偽表示が行われているに過ぎない。したがって,市販の契約書を利用して,「連帯保証」契約がなされていても,当事者の真の意思は,通常の保証契約が締結されていると考えるのが,契約の解釈として妥当である(例文解釈)。
もしも,実務の運用が補充性のある通常の保証であるにもかかわらず,それが,連帯保証であると主張する債権者がある場合には,それは,通謀虚偽表示として無効となるか,実体が保証であるにもかかわらず,保証人の催告の抗弁権と検索の抗弁権とを奪う契約は,先にも述べたように,公序良俗に反する契約として無効となると考えるべきであろう。
このように,市民が市販の契約書を使って契約する場合には,連帯保証契約のほとんどは,通常の保証契約に過ぎず,連帯保証契約を締結することは,通謀虚偽表示か,公序良俗に違反する契約として無効である。そうだとすると,連帯保証の意義はどこにあるのであろうか。
連帯保証の本来の意義は,次に述べる「連帯債務」とこれまで述べた「通常の保証」との橋渡しをすることにある。なぜなら,次に述べる連帯債務は,本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)とが結合したものであり,負担部分がゼロになった場合の連帯債務が連帯保証だからである。
連帯債務は,実務的に重要な意義を有する。そこに組み込まれた連帯保証は,債務者と債権者との利害関係を調整する法理として重要な役割を果たしており,特に,共同不法行為の連帯責任の場合のように,被害者の救済を図る上でも,重要な役割を果たしている。しかし,連帯保証が重要な役割を果たしいているのは,連帯債務の中に組み込まれた場合のみである。
通説は,保証といえば,通常保証ではなく,むしろ,連帯保証が原則であると考えている。しかし,連帯債務と切り離された連帯保証は,債権者に一方的に有利であり,債務者に過酷な責任を課すものであり,特別の事情がない限り,信義則に反して無効となるのが原則と考えるべきである(加賀山説)。
連帯債務
人的担保の最難関の領域は,連帯債務である。保証と連帯債務の理論が発展していない時代には,連帯債務の内容はベールに覆われていた。しかし,相互保証理論の出現によって,連帯債務を覆っていたベールは完全に取り除かれ,連帯債務とは,本来の債務(負担部分)と他の連帯債務者に対する連帯保証(保証部分)の結合に過ぎないことが明らかにされた。
この相互保証理論によれば,現行民法における連帯債務の規定の意味をすべて理論的に説明することができる。そればかりでなく,連帯債務に関して学説・判例が対立している点(例えば,連帯債務者の1人に対する一部免除の他の連帯債務者に及ぼす影響等)の困難な問題も,すべての説を透視図として図示した上で,どの説を採るのが妥当かを明確に説明することが可能となる。確かに,通説は,未だに相互保証理論を理解できず,誤解に基づいた批判を続けているが,連帯債務の内容と変動を透視図によって説明可能な相互保証理論が,現存するどの説にも勝っていることは明白である。
ここでは,相互保証理論にしたがって,連帯債務の基本から,最も難しいとされてきた問題を含めて,すべて,透視図に基づいて図示する方法によって,明快な議論を組み立てることができることを明らかにする。
不真正連帯債務と不可分債務
不真正連帯債務と不可分債務とは,同じ運命をたどることになる。不真正連帯債務と同様,名称にインパクトがあるため,多数当事者関係の債務の内容を説明する道具として便利な側面があることは疑いがない。
しかし,その内容は,負担部分がある限りで,連帯債務の内容から一歩も出ることができない。ここでは,不可分債務は,不真正連帯債務の場合と同様,名称だけは残るが,その内容は,団体理論(法人論)に帰着するか,連帯債務と同じ結果となることを明らかにする。
連帯債務とは,本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)とが組み合わされたものである(連帯債務における相互保証理論)。連帯債務をこのように分析的に考えると,連帯債務が人的担保であることを理解することが容易となる。ところが,従来の通説は,相互保証理論のような分析的な思考を採用せず,連帯債務を債務の一種(特別の「債務」)だと考えている。このような通説の考え方は,連帯債務が「債務」と債務ではない「保証」との組合せによる人的担保であるという本質を見誤ることになるばかりでなく,連帯債務のさまざまな性質・機能を論理的に説明することができない。特に,連帯債務者の一人に生じた事由が絶対的な効力を有するか,相対的効力にとどまるかの問題をめぐって,通説は大混乱に陥っている。そこで,ここでは,通説がなぜ大混乱に陥っているのかを明らかにするところから出発することにする。
通説を代表する[我妻・債権総論(1954)401頁]によれば,連帯債務とは,以下のように定義されている。
連帯債務とは,数人の債務者が,同一の給付について,各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し,しかもそのうちの一人の給付があれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務である。
しかし,この定義は,「各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担する」としているところに「ごまかし」があり,以下のような破綻をきたしている。
このような論理的な破綻が明らかな定義が,何の反論も受けずに,通説として幾世代にも亘って保持されてきたことは,重大な問題である。
この点に関しては,[太田・法律(2000)Ⅴ-Ⅵ頁]は,以下のように述べて,社会科学としての法律学の無価値性に言及している。
このように,社会科学者から,法律学とは,「権威主義的カルト集団の学問」と揶揄されていても,当人たちは,全くそれに気づかないところに法律学の悲劇がある。
ここでは,先に述べた社会科学の方法論に従い,以下の順序で,連帯債務を科学的に分析し,通説の地位を占めつづけているが論理的に破綻している従来の通説に代わる理論(相互保証理論)を検証することにしよう。
連帯債務の性質として一般に認識されている点を以下に列挙する。連帯債務の理論モデルは,これらの性質をすべて矛盾なく説明できるものであることが必要であり,かつ,そのモデルに従って推論を行なうと,条文に従って解決したのと同様の結果が生じるものでなければならない。
連帯債務に関する通説の定義や解説では,連帯債務の多数性・独立性と,一人の債務者が負担部分を超えて支払ったときに,他の債務者がそれに影響されること,すなわち,連帯債務の従属性とを矛盾なく説明することができないことは,すでに述べた通りである。
以下では,連帯債務における多数性・独立性と,一人の債務者の一定の行為によって他の債務者が影響を受けるという連帯債務の従属性とを矛盾なく説明できるモデルを提示することにする。そして,そのモデルに従ってシミュレーションを行なうと,連帯債務の規定にしたがった解釈と同じ結論を導くことができる上に,通説よりも分かりやすく説明することができることを示すことにする。
連帯債務における債務の複数性と目的の単一性とを同時に説明し得るモデルとして,固有の債務と連帯保証との組合せという相互保証理論モデルを提示する。
この相互保証理論というのは,以下の図26のように,連帯債務のモデルを,各債務者が負担する債務(負担部分)の上に,他の債務者の負担部分を連帯して保証する連帯保証(保証部分)が乗っているものとして理解しようとするものである。
例えば,XからY1,Y2,Y3がそれぞれ,600万円,400万円,200万円を借り受けて,連帯して弁済することを約した場合,Y1,Y2,Y3は,以下のように,各自の負担部分のほか,他の債務者を相互に連帯保証するという負担を負うことになる。
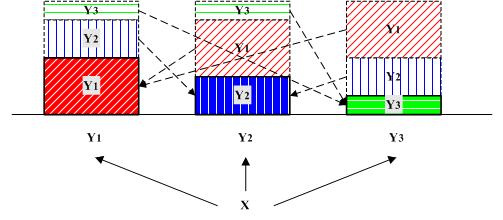 |
| *図54 相互保証モデルによる連帯債務の構造 |
相互保証理論モデルは,連帯債務を通常の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)との結合と考える理論(相互保証理論)に基づいたモデルであり,そのモデルでシミュレーションを行なう場合の適用法理は,連帯債務に関する規定は,すべて弁済の規定と保証の規定から導くことができるという試みを実現するために,債務の消滅に関する理論及び保証の理論に限定する。
相互保証モデルに基づくシミュレーションに用いられる法理のうち,当面利用されるのは,具体的には以下の4つの法理のみである。
ここで,連帯債務者の一人であるY1が,連帯債務の全額である1,200万円をXに弁済した場合に,相互保証モデルでは,他の債務者の債務がどのように変化するのかを見てみることにしよう。
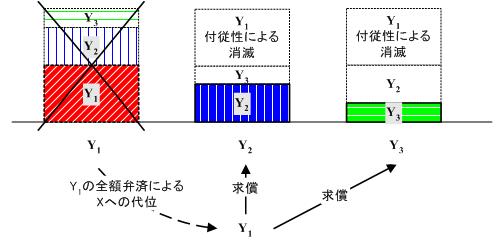 |
| *図55 連帯債務者の一人による弁済が連帯債務に及ぼす影響 |
従来の学説では,一人の債務者が連帯債務の全額を弁済すると,なぜ,独立の債務であるはずの他の債務も消滅するのか,また,なぜ,他の債務者に対して求償権を取得できるのかが十分に説明できなかった。
しかし,相互保証理論のモデルによれば,一人の債務者が連帯債務の全額を支払うことには,第1に,自らの固有の債務である負担部分を支払うこと,第2に,他の債務者の債務を連帯保証人として弁済すること,という性質の異なる2つの行為が含まれていることが明らかとなる。
そして,第1の行為によって,他の債務者が負担していた保証部分が付従性によって消滅すること,第2の行為によって,他の債務者が負担していた残りの保証部分が目的到達によって消滅すると同時に,他の債務者に対する求償権とそれを担保するための債権者への代位が発生するというメカニズムを説明することができることが明らかになったと思われる。
相互保証モデルの特色は,連帯債務を固有の債務としての負担部分と連帯保証としての保証部分とに分解して再構成した点にある。従来の通説が説明できなかった連帯債務の独立性と従属性という矛盾する性質を,このモデルは,負担部分が債務の独立性を,保証部分が付従性によって従属性をそれぞれ説明することによって,矛盾なく整合的に説明することができるようになったのである。
Xに対してY1,Y2,Y3がそれぞれ600万円,400万円,200万円を借り受け,各自がXに対して1,200万円の連帯債務を負担する場合に,XがY1の債務を全額免除したとしよう。その場合,Xは,Y2,Y3に対して,いくらの請求ができるか。
債権者が,連帯債務者の1人に対して債務を免除した場合の他の連帯債務者に対する効力について,通説[我妻・債権総論(1954)416頁]によれば,以下のように説明されることになる。
債権者が連帯債務者の一人に対してその債務を免除したときは,民法437条により,その債務者の負担部分について,他の債務者も債務を免れる。Xに対してY1,Y2,Y3がそれぞれ600万円,400万円,200万円を借り受け,各自がXに対して1,200万円の連帯債務を負担する場合に,XがY1の債務を免除するときは,Y2もY3もY1の負担部分600万円について債務を免れる。その結果,Y2,Y3が600万円の連帯債務を負担することになる。
この規定は,当事者間の法律関係を簡易に決済しようとする-転償(求償の循環)を避ける-ものと説かれる。このような規定がなければ,XはY2,Y3からなお1,200万円を請求し,弁済者はY1に600万円求償し,Y1はこれをXから不当利得として償還させることになるからである。そして,この規定は,債権の効力を弱めるものとして批判されている。
通説が,連帯債務者の一人が弁済した場合と異なり,連帯債務者の一人が免除された場合に,他の連帯債務者に対して絶対的効力が及ぶことに批判的なのは,以下の理由に基づいている。
債権者Xが連帯債務者の一人Y1に対してその債務の全額を免除したときは,Y1の固有の債務である600万円が消滅するので,Y1の債務について連帯保証していたY2,Y3の保証部分が,それぞれ,600万円の範囲で付従性によって消滅する。したがって,Y1の連帯債務は消滅し,Y2の連帯債務は,600万円(負担部分400万円,保証部分200万円)となり,Y3の連帯債務も600万円(負担部分200万円,保証部分400万円)となる。
このように考えると,民法437条は,連帯債務の本質から必然的に導かれる当然の規定であり,転償(求償の循環)を避けるために,やむなく規定された不合理な規定ではないことがわかる。
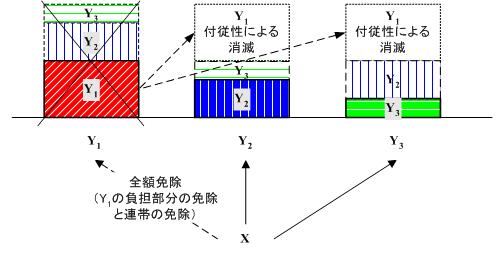 |
| *図56 連帯債務者の一人に対する免除が他の連帯債務者に及ぼす影響 |
連帯債務者の一人によって連帯債務の全額が弁済された場合と連帯債務者の一人が全額を免除された場合の相違は,以下の点にある。
Xに対してY1,Y2,Y3がそれぞれ,600万円,400万円,200万円を借り受け,各自がXに対して1,200万円の連帯債務を負担する場合に,XがY1の債務を半額免除したとしよう。その場合,Xは,Y2,Y3に対して,いくらの請求ができるか。
半額免除とは,いかなる意味であろうか。その解釈によって,結果は異なる。以下の解釈がありうる。相互保証理論モデルは,いずれの説をとっても,それぞれをうまく説明することが可能である。
半額を免除することについて,債権者が明確な指定をしていない場合には,判例のように,負担部分と連帯部分とをその割合に応じて比例的に免除すると考えるのが正当であろう。
連帯債務の半額免除について,判例のように,負担部分と連帯部分とをそれぞれの割合に応じて比例的に免除すると解釈すると,XがY1の連帯債務を半額免除することによって,他の連帯債務者の債務は以下のように変化する。
債権者Xが連帯債務者の一人Y1に対してその債務の半額を免除したときは,Y1の固有の債務である600万円の半額(300万円)が消滅するので,Y1の債務について連帯保証していたY2,Y3の連帯部分が,それぞれ300万円の範囲で付従性によって消滅する。したがって,Y1の連帯債務は600万円(負担部分300万円,連帯部分300万円)となり,Y2の連帯債務は900万円(負担部分400万円,連帯部分500万円)となり,Y3の連帯債務も900万円(負担部分200万円,連帯部分700万円)となる。
このように,連帯債務を本来の債務(負担部分)と連帯保証(保証部分)との結合だと考えると,連帯債務者の1人に生じた事由が他の債務者に影響を及ぼす場合(絶対的効力)と他の連帯債務者に影響を及ぼさない場合(相対的効力)とを,負担部分の消滅による保証部分の消滅という保証の付従性によって理論的に説明できる。
これに対して,通説は,連帯債務内部構造(透視図)を理解していないため,わが国の代表的な教科書の一つである[内田・民法Ⅲ(2005)372頁]でさえ,連帯債務と「保証債務との違いは,誰かの債務に対する従たる債務ではない,ということで,付従性…はない」としており,連帯債務においても,負担部分の消滅が付従性によって他の連帯債務者の保証部分に影響することを全く理解していない。
その結果として,「絶対的効力事由を広く認めることは,債権者に有利な場合〔民法434条の請求の絶対効〕もあるが,むしろ,連帯債務の担保的効力を弱め,債権者に不利な場合〔民法435条~439条〕が多い」[内田・民法Ⅲ(2005)373頁]として,債権者保護の視点から,絶対的効力に対して消極的な評価を下すに至っている。
しかし,連帯債務者の1人に生じた事由が,他の連帯債務者に影響を及ぼす場合と及ぼさない場合というのは,すでに述べたように,1人の連帯債務の負担部分に対する請求による他の連帯債務者の保証部分に対する影響,および,連帯債務者の1人の負担部分の消滅による他の連帯債務者の保証部分の付従性に基づく消滅であり,以下のように,論理必然的な結果である。
第1に,絶対的効力[民法434条~439条]とは,連帯債務者の1人の負担部分に対する請求によって保証部分に影響が出ること[民法457条1項],または,負担部分の消滅(更改,相殺,免除,混同)による付従性によって,他の連帯債務者の保証部分が消滅する現象である。
第2に,相対的効力[民法440条]とは,連帯債務者の1人の保証部分の消滅によっては,他の連帯債務者に何らの影響も生じないという現象である。
このように,連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に対して影響を及ぼしたり,及ぼさなかったりすることは,通説が考えているように,あるときは,債権者に有利となるように,その他の場合には,債務者に有利となるようにというような,立法政策的上の恣意的な判断によって生じる現象ではない。これらの現象は,先に述べたように,保証の規定(債務者に対する請求は,保証人に対しても効力を生じる[民法457条]),および,保証の本質(保証の付従性)から導かれる論理必然的な結果であることをしっかりと理解することが大切である。
連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に対して絶対的な効力を有する場合として,ここでは,債権を満足させて消滅させる弁済(履行)と,債権を満足させないで消滅させる免除について論じた。そのほかにも,債権を満足させて消滅させる更改,相殺,混同,並びに,債権を満足させずに消滅させる時効等について説明する必要がある。しかし,相殺の絶対的効力については,すでに,相殺の箇所(*第3章第4節3相殺の相互性の要件の例外としての「3者間相殺」)で詳しく解説したので,ここでは省略する。また,更改,混同については,次の4(相互保証理論に対する批判と再批判)で簡単に触れることにする。
連帯債務者間の求償の問題は,すでに,*第4章第1節1A(連帯債務は,本来の債務と連帯保証の結合と考えると,連帯債務の本質が理解できる)で詳しく論じたのでここでは繰り返さない。要点を簡略に述べるに留める。
第1に,保証人が債権者に弁済した場合には,保証人の主たる債務者に対する求償が生じる[民法459条-465条]。これに対して,主たる債務者が債権者に弁済した場合には,求償は生じない。これが保証に関する基本の中の基本である。
単純なことなので,第1の点については争いがない。ところが,少し複雑な連帯債務の問題となると,この基本を忘れてしまい,主たる債務の弁済に過ぎない負担部分の弁済によっても求償権が発生するという誤りを犯す人が多いので注意を要する。「基本が応用に活かせない」という典型例といってよい。
連帯債務者間の求償の問題は,一見難しそうに見えるが,保証人から主たる債務者への求償の問題の応用に過ぎない。すなわち,連帯債務者が債権者に弁済した場合にも,*Aで述べたことが,そのまま適用できる。連帯債務者の1人が自らの負担部分を弁済しても,求償は生じない(主たる債務者が主たる債務を弁済しても求償が生じないのと同じである)。連帯債務者の1人が負担部分を超える弁済をした場合にのみ,他の連帯債務者に求償できる(保証人が主たる債務者に求償できるのと同じである)。
ところが通説は,連帯債務者の場合は負担部分の支払いをした場合でも,他の連帯債務者に対して求償が可能であると解している([我妻・担保物権(1968)433-434頁],[内田・民法Ⅲ(2005)377頁])。
その解釈論上の根拠は,連帯債務者間の求償を定める民法442条を準用している共同保証人間の求償を定める民法の規定が,求償の要件として「自己の負担部分を超える額を弁済したとき」という要件を課しているのに対して,準用元の民法442条が,そのような要件を課していないので,民法465条の反対解釈として,連帯債務者間の求償の場合には負担部分を超えない「一部の弁済でも,負担部分の割合で求償できる」([内田・民法Ⅲ(2005)377頁])と解している。
しかし,通説の見解は,立法の経緯から見ても,また,比較法の観点から見ても,さらに,解釈論上の見地からも,誤った解釈であるといわざるを得ない。その点については,すでに*第4章第1節1A(c)で詳しく論じたので繰り返さないが,条文の解釈としても誤っている点についてのみ,言及しておく。連帯債務者は,自己の債務に過ぎない負担部分の弁済を超えて,他の連帯債務者のために保証部分の弁済まで行い,それによって「共同の免責を得たとき」にのみ,他の連帯債務者に対してその負担部分の範囲で求償できるに過ぎない[442条1項]。負担部分を超えない弁済は,自己の免責であって,共同の免責には達していないからである。
第3に,求償のために必要とされる「事前の通知,事後の通知」[民法443条]についても,負担部分の弁済であるのか,それを超えて共同の免責を得るための保証部分の弁済であるのかが,区別されなければならない。なぜなら,負担部分の弁済は,主たる債務者が債権者に弁済するのと同じであり,主たる債務者は,自らの弁済に際して,保証人に対する事前の通知は必要がないからである。これに対して,保証部分の弁済は,保証人が,債権者に弁済する場合と同じである。そして,保証の規定を見れば,保証人は,求償のために,事前の通知,事後の通知が必要である[民法463条による443条の準用]。したがって,連帯債務者の1人が負担部分を超えて弁済をする場合には,求償の問題が生じるために,事前・事後の通知が必要となるのである。
つまり,「事前の通知」が必要なのは,他人の負担部分を支払うのであるから,他人の負担部分について,免責事由が生じているかどうかを調査すべきであるからである。これに対して,「事後の通知」が必要なのは,他人の負担部分を支払った者として,すでに,共同の免責を得ていること,したがって,弁済は,債権者にではなく,代位権者である連帯債務者に支払うべきことを認識させるためである。
通説・判例は,事前・事後の通知が必要なのは,連帯債務者の1人が負担部分を越える弁済をした場合にのみ求償が生じるという点を理解していないために,負担部分の範囲内の弁済の場合にも,事前・事後の通知が必要であるとして,大混乱に陥っている。この点については,*第4章第1節1Bにおいて,昭和57年最高裁判決〈最二判昭・57・12・17民集36巻12号2399頁〉に関連して詳しく説明したので,ここでは説明を省略する。
不真正連帯債務という用語は,制定法上の明文の規定を欠いている。このような概念の意味を知るには,法律辞書で確認するのがよい。[有斐閣・法律学小辞典(2004)]によれば,「不真正連帯債務」とは,次のように定義されている。
同一内容の給付を目的とする債務が偶然に競合した場合をいう。多数の債務者が同一内容の給付について全部の履行をしなければならない義務を負い,一債務者の弁済によって他の者も債務を免れる点で連帯債務と近似するが,債務者間に主観的共同関係がなく,したがって弁済を除いて債務者の1人に生じた事由が他の債務者に効力を及ぼさない[民法434条~440条参照]点でそれと区別される。
例えば,他人の家屋を焼いた者の不法行為に基づく賠償義務と保険会社が保険契約に基づいて負うてん補義務,受寄物を不注意で盗まれた受寄者の債務不履行に基づく賠償義務と窃取者の不法行為に基づく賠償義務などのように,同一の損害を数人がそれぞれの立場においててん補しなければならない義務を負担する場合などに生ずるとされる。共同不法行為者の賠償義務は連帯と規定されている〔民法719条〕が,不真正連帯であるとする学説が有力である。
しかし,連帯債務を正確に理解した上で,上記の解説を読むと,その問題点が明らかとなる。
第1に,「債務者間に主観的共同関係がなく,したがって弁済を除いて債務者の1人に生じた事由が他の債務者に効力を及ぼさない」点で連帯債務と区別されるという点が問題である。なぜなら,連帯債務の場合にも,連帯債務者の1人について生じた事由が他の連帯債務者に影響を与えるのは,決して,連帯債務者間に代理関係等の主観的な共同関係があるからではなく,単に,相互に保証し合うという関係が生じてさえいればよいからである。連帯債務の発生原因を当事者間の合意に限定する必要はない。例えば,被害者を救済するために,複数の加害者について,相互に保証する関係を生じさせること,すなわち,法定連帯債務を課すことも可能だからである。
第2に,不真正連帯債務者が負う債務は,一方で,それぞれ,別個・独立の債務であると考えられているが,他方で,「一債務者の弁済によって他の者も債務を免れる」とされている。このことは,それぞれの債務に依存関係があることを示している。すなわち,不真正連帯債務も,保証部分を含んだ債務であり,連帯債務と同様,それぞれは別個・独立に存在している債務ではないことになる。
不真正連帯債務は,ドイツ普通法以来の歴史的産物であり,不真正連帯債務という概念が必要とされたのは,共同不法行為者の「連帯」債務を説明するためであった(詳しくは,[潮見・債権総論Ⅱ(2005)546-548頁,584-588頁]参照)。不真正連帯債務の概念が誕生した当時は,共同不法行為者間には負担部分は存在しないと考えられており,したがって,1人の共同不法行為者が被害者に損害賠償額の全額を弁済すると,不真正連帯債務は消滅し,かつ,弁済した共同不法行為者は,他の共同不法行為者に求償することができなかった。不法行為を行った者が,求償を求めて訴えを提起することは,広い意味でのクリーン・ハンドの原則によって認められないと考えられたためである。
しかし,このような場合に求償を否定すると,まじめに全額を賠償した加害者だけが負担を負い,不誠実な加害者が免責されるという正義に反する結果が生じる。そこで,判例は,不真正連帯債務の場合においても,求償を認めざるを得なくなる(〈最一判昭46・9・30判時646号47頁,判タ269号194頁〉,〈最二判昭63・7・1民集42巻6号451頁〉,〈最二判平3・10・25民集45巻7号1173頁〉など)。そして,不真正連帯債務者間の求償が認められる理由が,相互に負担部分が存在するからであることが判明すると,不真正連帯債務の概念は,存在理由を失ってしまう。なぜなら,負担部分が存在するのであれば,保証部分も存在することになり,連帯債務者の1人に生じた事由は,保証の付従性に基づき,他の不真正連帯債務者にも影響を与えることになるのであって,不真正連帯債務の唯一の存在理由である「弁済を除いて債務者の1人に生じた事由が他の債務者に効力を及ぼさない」という特色が消滅するからである。
このようにして,判例によって不真正連帯債務者間の求償が認められたため,不真正連帯債務の存在理由(raison d'être)も消滅してしまった。そして,不真正連帯債務の概念を肯定する人の間でさえ,不真正連帯債務についての統一的な学説は存在しなくなっている。学説も,従来の概念を死守して不真正連帯債務者間の求償をあくまで認めないとするもの,求償は認めるとしつつ,不真正連帯債務者の1人について生じた事由は,弁済を除いて影響を及ぼさないとするもの(ただし,弁済とその他の事由とを区別する理由は不明である)など,主張する人ごとに異なるほど,多岐に分かれている。
民法719条が「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と規定し,「連帯債務」と考えるのではなく,わざわざ,法律に規定がなく,多義的な概念である「不真正連帯債務」にこだわるのだろうか。
通説・判例が,民法719条の共同不法行為者の連帯責任を,不真正連帯責任と考える原因の一つは,共同不法行為の因果関係について,共同不法行為の各当事者の寄与率は不明であり,かつ,寄与率を考える余地はない(したがって,初期の不真正連帯債務理論は,求償を認めていなかった)と考えているからであると思われる。通説・判例が,このような偏った見解に凝り固まっている原因は,共同不法行為に関して,共同不法行為者の責任には負担部分が存在しないと考えているからである。
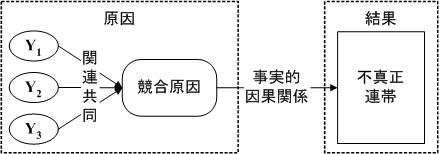 |
| *図57 共同不法行為における事実的因果関係(通説)と 加害者の負担部分のブラック・ボックス化→不真正連帯債務 |
これに対して,因果関係について,オール・オア・ナッシングの考え方ではなく,量的な因果関係を是認する新しい因果関係論によれば,共同不法行為者も,損害について,部分的な因果関係を有していると考えることが可能となり,共同不法行為者の責任も,部分的因果関係(寄与分)に相当する負担部分を有する連帯責任と考えることが可能となる。
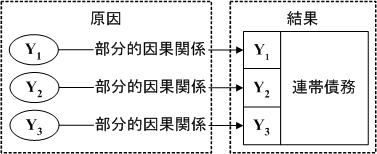 |
| *図58 共同不法行為における部分的因果関係と 加害者の負担部分の可視化→連帯債務 |
複数の加害者が原因となって被害者に損害が生じた場合,共同不法行為者の1人1人は,被害者が被った損害について,それぞれ,損害全額を賠償する責任を負っている(民法719条)。しかし,複数の加害者の行為を仔細に検討してみると,それぞれの加害者は,1人だけで損害を引き起こしたわけではなく,結果全体に対して部分的にのみ寄与している(部分的因果関係)。そのことは,それぞれの加害者の負担する責任は,自らの寄与部分(負担部分)と他の加害者の負担部分に対する法定の連帯保証部分から成り立っている。これは,まさに連帯債務(負担部分と保証部分の結合)であり,その原因が,当事者の意思(連帯債務を負う合意)ではなく,被害者を救済するために,法律が定めた法定の連帯債務(いわゆる不真正連帯債務)である。
不真正連帯債務は,もともとは,共同不法行為において寄与部分を観念できなかった時代に,求償が生じない不真正な連帯債務として位置づけられた歴史的な産物に過ぎない。共同不法行為において,加害者間の求償が認められるに至った(〈最一判昭46・9・30判時646号47頁,判タ269号194頁〉,〈最二判昭63・7・1民集42巻6号451頁〉,〈最二判平3・10・25民集45巻7号1173頁〉など)現代においては,無用の概念である。もしも,不真正連帯債務の用語を残すのであれば,その効果については,連帯債務と全く同じであるが,その発生原因については,当事者の意思ではなく,法律の規定によって生じるという意味で,不真正連帯債務という用語を用いることが許されるに過ぎない。
通常の連帯債務が当事者の合意によって生じること(約定連帯債務)との対比で,不真正連帯債務を「法律の規定によって生じる連帯債務」(法定連帯債務)として再定義すると,不真正連帯債務においても,不真正連帯債務者の1人について生じた事由が他の不真正連帯債務者に影響する場合(絶対的効力効)があり,連帯債務に関する民法の規定([民法434条~439条])が不真正連帯債務にも適用されること,および,その理由が明らかとなる。
不真正連帯債務において,弁済以外の事由について,絶対的効力を否定し続けてきた判例(〈最二判昭48・2・16民集27巻1号99頁〉,〈最一判昭57・3・4判時1042号,判タ470号121頁〉,〈最一判平6・11・24判時1514号82頁〉など)といえども,最近になってその考え方を実質的に変更し,不真正連帯債務の場合にも免除の絶対効を認める傾向を示しつつあり〈最一判平10・9・10民集52巻6号1494頁〉,相互保証理論をマスターすることがますます重要となっている。
第1の事例は,配偶者間における単なる債務不履行(不貞行為)の事例であり,他方配偶者と第三者による共同不法行為といえるかどうか微妙な問題であり,第三者に対する請求を最小限に抑えるべき事案において,最高裁は,あえて,免除の絶対効を否定している。
平成6年最高裁判決の事案は,原告(一方配偶者)が他方配偶者に対して連帯債務全額を免除しており,かつ,他方配偶者と第三者(不倫相手)との間に明らかに主観的関連共同が認められる場合である。したがって,不真正連帯債務において,1人の不真正連帯債務者に生じた事由が他の不真正連帯債務者に影響を及ぼすべきでないという理由,すなわち,不真正連帯債務者間には,主観的な関連共同がないからという理由も存在しない。それにもかかわらず,最高裁は,そのような重要な事情を無視し,「不真正連帯債務であるから」という唯一の理由に基づいて,第三者の責任を全額認めるという不条理な判決を下している。
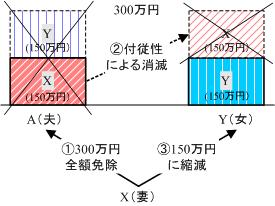 |
(事案)X(妻)がA(夫)との婚姻関係を継続中,Y(女)がA(夫)と不貞行為に及び,そのため右婚姻関係が破綻するに至ったとして,Y(女)に対し,不法行為に基づく慰謝料300万円等を請求した事件。 原審は,X(妻)がA(夫)に対して債務を免除したことを理由に,YがXに支払うべき慰謝料は150万円が相当であると判示した〔本書の立場と同じ〕。これに対して,最高裁は,原審の判断を覆し,以下のように判示して,Xの請求の全額を認めた。 (判旨)民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから,その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないものと解するのが相当である(最二判昭48・2・16民集27巻1号99頁参照)。 |
| *図59 最一判平6・11・24 判時1514号82頁 |
この判決の不当性は,判決に応じて,Y(女)がX(妻)に全額である300万円の損害賠償をした場合に明らかになる。その場合,共同不法行為者間においても,求償を認める判例準則によれば,Y(女)は,A(夫)に対して,その負担部分に当たる150万円(原審で確定されている)を求償することができる。そうだとすると,これは,いわゆる民法437条の趣旨説明として通説が認めるいわゆる回り求償(転償)が生じることになる。それを防止するために,民法437条が起草されたのであり,このような場合にこそ,民法437条を適用して債権者の全額賠償を制限すべき場合であった。つまり,平成6年最高裁判決は,理論的な面からも,また,事案の具体的な解決の面からも,何らの合理性も認められない。
このような不条理な判決理由が長続きするはずはない。最高裁は,最近になって,「不真正連帯債務だから…」というような硬直的な判断に修正するに至っている。
第2の事例は,自動車販売業者Yの従業員Bが,信販会社Aと提携関係にある自動車販売業者Xを巻き込んで,架空の自動車販売契約によって,クレジット会社(信販会社A)から3,303万円を詐取した詐欺事件である。XはAとの間の和解に基づき和解金2,000万円を支払った後,Bの負担部分について,使用者であるYに対して求償金として1,600万円および遅延損害金の支払を求めた〈最一判平10・9・10民集52巻6号1494頁(民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第23事件)〉。
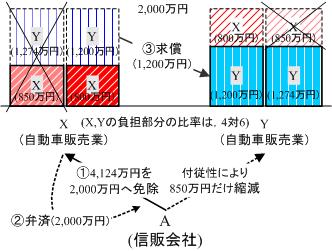 |
(判旨)①〔不真正連帯債務における負担部分の承認と求償の承認〕 XとYが共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において,XがYとの責任割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは,XはYの負担部分について求償することができる。 ②〔不真正連帯債務における免除の絶対効の形式的な否定〕 XとYが負担する損害賠償債務は,いわゆる不真正連帯債務であるから,XとA(被害者)との間で訴訟上の和解が成立し,請求額の一部につき和解金が支払われるとともに,和解調書中に「被害者はその余の請求を放棄する」旨の条項が設けられ,被害者がXに対し残債務を免除したと解し得るときでも,連帯債務における免除の絶対的効力を定めた民法437条の規定は適用されず,Yに対して当然に免除の効力が及ぶものではない(最二判昭48・2・16民集27巻1号99頁,最一判平6・11・24裁民173号431頁参照)。 |
| ③〔不真正連帯債務における免除の絶対的効力の実質的な承認〕 しかし,被害者Aが,右訴訟上の和解に際し,Yの残債務をも免除する意思を有していると認められるときは,Yに対しても残債務の免除の効力が及ぶものというべきである。そして,この場合には,Yはもはや被害者から残債務を訴求される可能性はないのであるから,XのYに対する求償金額は,確定した損害額である右訴訟上の和解におけるXの支払額を基準とし,双方の責任割合に従いその負担部分を定めて,これを算定するのが相当であると解される。 仮に,本件和解における上告人の支払額2,000万円を基準とし,原審の確定した前記責任割合〔4対6〕に基づき算定した場合には,本件共同不法行為におけるXの負担部分は800万円となる。したがって,XはYに対し,その支払額のうち1,200万円の求償をすることができ,右の違法はこの範囲で原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。 |
|
| *図60 最一判平10・9・10民集52巻6号1494頁 民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第23事件 | |
不真正連帯債務を法定の連帯債務として再定義し,その内容は通常の連帯債務と同じであるとして,連帯債務者の1人に生じた事由のうち負担部分に関するものは,付従性に基づき,他の連帯債務者の保証分に影響を与えるとする本書の立場に立つと,最高裁の結論は,理論的にも説明することができる。
その理論的説明は,以下の通りである。
第1に,債権者Aが連帯債務者の1人であるXに対して,連帯債務4,124万円を2,000万円へと縮減したことは,Xの連帯債務のうち,2,124万円を免除したことを意味する。この一部免除の意味については,XとYとの負担割合に応じた免除がなされるというのが判例の考え方である〈大判昭15・9・21民集19巻1701頁〉。そうすると,本件の場合,債権者Aは,Xの負担部分を850万円,保証部分を1,274万円,合計で,2,124万円を免除したことになる。
第2に,債権者Aの連帯債務者の1人Xに対する一部免除の結果は,民法437条により,その負担部分に関する免除(850万円)のみが,付従性によって,他の連帯債務者であるYに対して絶対的効力を有する。したがって,Yの連帯債務は,850万円の範囲で消滅する。
第3に,連帯債務者の1人であるXが免除された連帯債務の全額である2,000万円の弁済をすると,その負担部分(800万円)を超えた保証部分(1,200万円)の弁済のみについて,他の連帯債務者であるYに対して求償することができる。
最高裁は,免除の絶対効を認めないとしつつ,「被害者Aが,右訴訟上の和解に際し,Yの残債務をも免除する意思を有していると認められるとき」は「Yに対しても残債務の免除の効力が及ぶものというべきである」と述べている。しかし,被害者Aと加害者Xとの和解の効力は,当事者外のYには及ばないのであるから,結局のところ,最高裁の結論は,不真正連帯債務において不真正連帯債務者の1人に対する免除が他の不真正連帯債務者に影響を及ぼすという,免除の絶対効を認めたことになっている。
このようにして,和解の効力が当事者以外に及ばないことを前提にすると,最高裁の結論を理論的に説明できるのは,本書が採用する相互保証理論のみであることが明らかとなったと思われる。
現行民法は,連帯債務と保証の規定を,民法第2編(債権)第1章(総則)第3節(多数当事者の債権及び債務)に位置づけている。「多数当事者の債権及び債務」という概念は,同一の給付について,債権者又は債務者のいずれか一方もしくは双方が複数である場合を意味する。このため,「多数当事者の債権及び債務」の節には,人的担保として位置づけられる連帯債務と保証のほかに,分割債権・債務,不可分債権・債務という規定が含まれている。
このうち,分割債権・債務は,本書では,連帯債務を「分割債務と連帯保証の結合」であると構成しているため,連帯債務の考え方の中に吸収して論じることができる。たとえば,負担部分の額が不明なときには,分割債権・分割債務の総則規定である民法427条の「各債務者は,それぞれ等しい割合で権利を有し,又は義務を負う」を準用して,負担部分の割合を平等と推定することができる。
不可分債務は,債務が可分か不可分かによって分類された概念の1つであるが,本書で主として問題にする金銭債務については,債務が「性質上」不可分ということはありえない。また,当事者の意思によって不可分にすることができるとしても,それは,つまるところ,可分の金銭債務を連帯債務とするという意味しか持ち得ない。確かに,有体物については,可分か不可分かを問うことができる。しかし,債権または債務は,無体物であり,観念上の存在であるので,どのような債権・債務も分割することが可能である。たとえば,不可分の物の所有権については,共有概念によって,分割が可能である。債権・債務の場合も,準共有[民法264条]という概念を通じて,債権・債務の共有的帰属(広義の共有)を観念することが可能である。
したがって,債権法における問題解決の視点からは,可分の債権・債務を前提にした上で,債務の対象となっている給付について,目的物をいつ分割できるのか,分割できない期間の権利関係はどうなるのか,分割できるようになった場合には,どのような割合で,どのような手続きで分割できるのかを,個別的に検討すればよい。
たとえば,共有概念の内部でも,目的物の分割請求がいつでも可能な狭義の共有[民法256条]と,特定目的の実現のために,一定期間に限って目的物の分割許さない合有(組合算に関する[民法676条2項],相続財産に関する[民法898条,民法906条以下]など)とを区別することができる。合有のように,一定期間に限って,目的物の分割ができないときの債権・債務関係は,その関係を制御する組合や相続財産に関する個々の規定に従って処理をすれば足りる。このような具体的な条文を無視して,抽象的に可分債務か不可分債務かを論じても,その実益はない。
そもそも,不可分債務という概念を創設したところで,その内容は,すべて,分割債権,分割債務の規定または連帯債務(先に述べたように,分割債務と連帯保証の組み合わせ)の規定が準用されるだけであり[民法430条],不可分債務という概念の独自性は存在しない。
確かに,債務者の1人について生じた事由については,民法430条は,連帯債務の場合に認めている絶対的効力の規定[民法434条~440条]の準用を排除している。しかし,その理由は,「債務者相互の間には,代理其他連帯の場合に於ける如き関係の存するものに非ず。故に,本条を以て其一人に付き生じたる事項は他の債務者に対して効力を生ぜざることを明示するの必要あるなり」[民法理由書(1987)413頁]というものである。
この点に関しては,連帯債務において,1人に生じた事由が絶対的効力を生じるのは,債務者間に代理関係があるからではなく,負担部分に対する相互保証の付従性によるものであり,合理的な規定であることは,すでに詳しく論じた。また,現行民法の立法者も,連帯債務について,旧民法が認めていた「代理関係」の考え方を採用せず,「近来の立法例は代理関係を認めざるの主義に傾けり。故に,本案に於いても亦た,此の主義を採用し,代理関係の存在を認めず」[民法理由書(1987)419頁]として,代理関係を否定している。そうだとすると,たとえ,性質上の不可分債務といえるものが存在するとしても,本書で問題とする金銭債務については,常に,負担部分を観念することができるのであるから,1人に生じた事由について,結局は,絶対的効力を認めざるを得ない。民法430条のように,絶対的効力を認めない代わりに,民法429条の不可分債権の規定を準用して,不当利得に基づき,債権者が得た利得を債務者に償還するという迂遠な方法[民法430条で準用されている民法429条1項]を採用するよりも,連帯債務の絶対的効力の規定を準用した方が,はるかに合理的である。
結局,不可分債務の規定について,旧民法が連帯債務の規定をすべて準用していたにもかかわらず,現行民法の立法者は,不可分債務には,代理関係(主観的な関連共同)が存在しないとして,1人の債務者に生じた事由の絶対的効力を極力抑えようとしたのである。しかし,このような試みは,すでに,不真正連帯債務の箇所で触れたように,必然的に破綻する。
一部の学説も,条文上は,民法430条によって,民法436条(相殺の絶対効)の適用が排除されているにもかかわらず,不可分債権の場合には債権者が複数であるため相対的効力しか認められないとしても,不可分債務の場合には,債権者は一人しかいないとの理由で,相殺の絶対効を認めている([於保・債権総論(1972)196,219頁],[潮見・債権総論(1994)510頁])。
また,条文には規定がないが,不可分債権の場合について,学説は,「履行を受けた債権者は,他の債権者に対して,内部関係の割合に応じて分与すべきである」[篠塚・条解民法Ⅱ(1982)105頁]としている。このことは,不可分債務の場合にも,同様の内部関係,すなわち,負担部分が当然に想定されることになる。そうだとすると,不可分債務についても,負担部分に応じた絶対的効力を否定することはできなくなるのであり,民法430条の適用除外規定にもかかわらず,結局,不可分債務についても,負担部分が関係する広い範囲で,連帯債務の絶対効を承認せざるを得なくなるのである。その意味で,上記の有力説が,相殺ばかりでなく,民法430条によって準用される429条によって絶対的効力が否定されている代物弁済についても絶対的効力を認めているのは,大きな意味を有している。
このように考えると,少なくとも,金銭債務に関しては,不可分債務という概念を利用する実益はない。確かに,一般論としては,不可分債務という概念が存在することによって,ある債務を単純な分割債務とするか,連帯債務とするかどうかを判断する場合の当事者意思の解釈にとって,説得的な結論を得ることができる場合がありえよう。判例は,多数当事者の債権・債務関係に関して,分割債務を原則としている(〈最一判昭44・11・13判時580号49頁,判タ242号167頁〉(継続的な物品供給契約における父と子の売掛代金債務について,連帯債務であることを否定した事例),〈最三判昭45・10・13判時614号46頁,判タ614号46頁〉(一船分の木材を二人が共同して買い受けた場合について可分債務とした事例))。したがって,連帯債務であることを証明する際に,不可分債務であるから,連帯債務の規定が準用されるという論理は,場合によっては説得的であり,その意味で不可分債務の概念に有用性が認められないわけではない。
しかし,そのような有用性は,つまるところ,連帯債務とすべきかどうかに関する当事者の意思解釈の問題であるので,不可分債務という概念がなければ,問題が解決できないというわけではない。そうだとすると,不可分債務という考え方は,説得技術としては有用な概念であるが,理論的には,連帯債務または準共有や合有関係に解消されるべき概念である。そして,多数当事者の債権・債務関係は,先に述べたように,それぞれの法律関係を制御する個々の条文によって問題を解決すべきであり,「不可分債務だからこうなる(たとえば,債務者の1人に生じた事由は他の債務者に影響を及ぼさない)」というような乱暴な議論は避けるべきであろう。
連帯債務について
不真正連帯債務について
不可分債務について
担保法各論のうち,債権の掴取力の量的強化としての人的担保の解説を終えたので,これから,債権の掴取力の質的強化としての物的担保の解説を始める。
物的担保とは,債権の保全と回収とを確実にするために,債権の掴取力を質的に強化するものであり,具体的には,債権の掴取力に事実上の優先弁済権(留置権),または,法律上の優先弁済権(先取特権,質権,抵当権)を与えるものである。
物的担保として,民法は,4つの権利を規定しており,それらは典型担保と呼ばれている。民法には規定されていないが,判例によって認められている譲渡担保,特別法によって認められている仮登記担保(仮登記担保に関する法律),所有権留保(割賦販売法7条など)は,非典型担保と呼ばれている。非典型担保も,典型担保と同様に,法律上の優先弁済権が認められており,しかも,物的担保の通有性である付従性,不可分性という性質を有している。したがって,本書では,非典型担保も物的担保として論じることにする。
物的担保は,その性質と効力にしたがって,以下のように分類されている。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 本質・効力 (債権の掴取力の質的強化) |
通有性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 物的担保 | 典型担保 | 法定担保権 | 留置権 | 事実上の優先弁済権(引渡拒絶の抗弁権) | 付従性(随伴性), 不可分性 |
| 先取特権 | 法律上の優先弁済権 (他の債権者に先立って弁済を受ける権利) |
||||
| 約定担保権 | 質権 | ||||
| 抵当権 | |||||
| 非典型担保 | 約定担保 | 仮登記担保 | |||
| 譲渡担保 | |||||
| 所有権留保 |
従来の考え方によれば,これらの物的担保は,被担保債権とは別個・独立の物権である担保物権であるとされ,物権法の中で,所有権が有する換価・処分権を潜在的に制限する制限物権として位置づけられてきた。
| 物権 | 物権の分類 | 備考 | ||||
| 占有権 | 本権を取得したり証明したりする機能を有する権利。 物権だけに認められるわけではなく,物権にも債権にも属 さない独自の権利(本来は,民法総則に規定すべき権利)。 |
|||||
| 本権 | 所有権 | 使用・収益権,換価・処分権のすべての権限を有する。 | ||||
| 制限 物権 |
用益物権 | 地上権,永小作権,地役権 | 使用・収益権のみを有する物権。 | |||
| 担保物権 | 典型担保 | 留置権,先取特権,質権,抵当権 | 換価・処分権を有する物権(留置権はそれを有しない)。 独立の権利のはずが,債権に付従するという性質を有する。 |
|||
| 民法に規定されていない 担保物権 |
非典型担保 | 譲渡担保,所有権留保,仮登記担保 | 売買・買戻し,代物弁済予約等によって構成されており, 物権といえるかどうか明確ではない。 |
|||
もっとも,従来の考え方に関しては,*表26の備考欄でも一部触れているように,3つの点で問題があることに留意しなければならない。
第1は,通説によれば,担保物権とは,一方で,被担保債権とは別個・独立の物権であると定義されているが,他方で,被担保債権が消滅すると担保物権も消滅するという性質(付従性)を有するとしており,被担保債権に対する独立性と従属性という矛盾する性質を与えている点で,理論的に大きな問題を抱えている。
本書では,物的担保とは,「債権の掴取力を質的に強化するもの」と定義しているため,債権が消滅すれば,債権の掴取力も消滅するのは当然であり,物的担保の定義と付従性との間に矛盾点は存在しない。むしろ,付従性は,債権の掴取力の強化という人的担保にも,また,物的担保にも共通する当然の性質として,統一的に理解することができる。
第2は,担保物権を換価・処分権を有する物権であると定義しているが,その中に入っている留置権には,換価・処分権はおろか,使用・収益権も認められておらず,物権の定義からすると,決して,物権とはいえない。物権と債権との区別を厳密に考えるドイツ民法が留置権(Zurückbehaltungsrecht)を物権ではなく,給付拒絶の抗弁権と考え,債権法の中で規定している[ドイツ民法273条]のは理由があるというべきである。
本書では,物的担保を債権の掴取力の質的強化,すなわち,特定の債権に与えられた事実上,または,法律上の優先弁済権として定義しているため,物権ではない留置権であっても,物的担保の通有性を有するばかりでなく,事実上の優先弁済権を有している以上,物的担保の1つとして取り扱うことができる。
第3は,物的担保の分類として,従来は,担保権者が目的物を占有するかどうかで,占有を伴う物的担保(留置権,質権),占有を伴わない物的担保(先取特権,抵当権,非典型担保)との2つに分類していた。しかし,質権の場合,権利質については,債権者が必ずしも占有を得る必要がないため,このような分類基準を貫徹することができなくなっている。
| 債務者等から目的物の使用・収益権を奪うもの (いわゆる占有担保物権) |
典型担保 | 留置権 | |
| 質権 | 動産質 | ||
| 不動産質 | |||
| 権利質 | |||
| 債務者等から目的物の使用・収益権を奪わないもの (いわゆる非占有担保物権) |
典型担保 | 先取特権 | 一般先取特権 |
| 動産先取特権(債権先取特権を含む) | |||
| 不動産先取特権 | |||
| 抵当権 | 普通抵当 | ||
| 根抵当 | |||
| 非典型担保 | 仮登記担保 | ||
| 譲渡担保 | 動産譲渡担保 | ||
| 不動産譲渡担保 | |||
| 債権譲渡担保 | |||
| 所有権留保 | |||
本書では,物的担保の分類として,債権者が目的物を占有するか,占有しないかという観点からではなく,*表27のように,「設定者から目的物の使用・収益権を奪うものであるかどうか」という基準によって分類しており,通説とは異なり,分類基準を貫徹することができる。
非典型担保というと,非典型契約を思い出す人がいるかもしれない。物権と債権とでは,世界が違うようにも思うかもしれないが,実は,関連しあっている。典型契約と非典型契約とが存在する契約法の世界と,典型担保と非典型担保とが存在する物的担保の世界を比較してみると,非典型担保の存在理由が理解できるとともに,物的担保の過去,現在,未来までもが見えてくる。
第1に,比較のため,契約の世界を見てみよう。典型契約は,融通無碍の契約自由の下では,当事者の意思を補充・補完するものとして位置づけられる。非典型契約は,むしろ,契約自由の所産である。契約法において非典型契約が認められるのは当然であるが,自由は,常に濫用の危険を伴う。そこで,現代においては,契約正義等の理念の下に,優越的な地位を利用した濫用的な契約を規制する法理が発展している。補充規定に過ぎないとされてきた任意規定に反して消費者を一方的に害するすべての契約は無効とし[消費者契約法10条]任意規定で補完するというの考え方は,現代における契約正義を実現するための1つの到達点といえよう。つまり,契約自由の世界では,力の強いものが契約条項を予め定め,力の弱いものはこれを押し付けられるという優越的地位の濫用が多発し,これを規制するために,契約正義という名において,契約自由を制御する必要がある。
第2に,物的担保の世界においては,典型担保は,最初から法によるコントロール下に置かれている。これに対して,非典型担保は,以下に詳しく論じるように,融通の利かない物権法定主義をすり抜けるために「嘘も方便」として「所有権移転型」として生成したため,所有権を取得する債権者の濫用が必然的に生じているのであり,これを制御する必要がある。
第3に,非典型契約と非典型担保の両者を優越的地位の濫用という観点で比較してみよう。
一方で,契約自由の当然の結果として生成した非典型契約においては,自由の名の下で,強者による弱者に対する支配すなわち優越的地位の濫用が生じている。これを防止するため,契約法の世界では,公序良俗,信義則,契約的正義という原理を用いて,典型契約で規定された標準的なルールとしての任意規定によって非典型契約の行き過ぎをコントロールするという必要が生じている[消費者契約法10条参照]。他方で,物権法定主義の制約の中で,立法の不備のために,その潜脱行為として生成した非典型担保においては,債権者が,担保権を逸脱する所有権の移転まで要求するため,その濫用が必然的に生じている。このような濫用を防止するために,非典型担保においては,債権者に対して,典型担保におけると同様のコントロールをする必要が生じているのである。
このように考えると,非典型「契約」と非典型「担保」の出発点は,契約自由と物権法定主義という全く正反対のものであるが,非典型契約,非典型担保における優越的地位の濫用を制御するためには,いずれの場合にも典型契約および典型担保における法理(民法の規定)が,非典型契約および非典型担保における優越的地位の濫用をコントロールするという重要な役割を演じているのである。すなわち,非典型契約においては,任意規定と一般条項が,非典型担保においては,優越的な地位は義務を伴う(ノブレス・オブリージュ)および,清算義務の法理が,優越的な地位の濫用をコントロールするための基準とされなければならない。
| 非典型契約 | 非典型担保 | |
|---|---|---|
| 出発点 | 「契約自由」の当然の帰結 | 「物権法定主義」からの逸脱またはそれからの解放 |
| 問題点 | 優越的の濫用による不公正な取引および消費者被害 | 所有権移転構成による不公正な取引および債務者被害 |
| 解決の方向 | 任意規定によるコントロール([消費者契約法10条]参照) | 帰属清算の廃止と処分清算のコントロール(立法の課題) |
非典型担保に対するこのようなコントロールが可能になった後は,翻って,典型担保における債権者の優越的の地位の濫用についても,当然に,メスが振るわれなければならない。その典型例が,王座を占める抵当権による賃借権の覆滅であることは,すでに述べた通りである。この問題が,我妻民法[我妻・担保物権(1968)8-9頁,297-298頁]で提起されながら,抜本的な解決が図られていない担保法の最大の課題となっているといえよう。
物的担保が物権だとすると,物権法定主義[民法175条]に基づき,典型担保だけが許され,非典型担保は禁止されるはずである。それにもかかわらず,譲渡担保に始まり,仮登記担保法が制定された経緯を見てみると,以下に詳しく述べるように,「民法の不備」と,物権法定主義の網の目をくぐろうとして,「国民が嘘つきになる」という構図が透けて見えてくる。
「民法の不備」とは,債務者に担保目的物を使用・収益させつつ,債権の回収を図り,債務が履行されない場合に限って担保目的物を換価・処分する権限を債権者に与えるという,物的担保の理想である抵当権について,これを動産および債権に認めることを怠ったことである。もちろん,これには,それなりの理由がある。不動産については,公示方法として登記制度が存在するが,これまでは,動産および債権については,明確な公示制度が存在しなかったからである。しかし,第1に,動産の場合にも,古くから明認方法という公示制度が認められており,最近では,動産登記[動産・債権譲渡特例法]までもが実現しているのであるから,実務の要請が高い動産抵当の制度が民法で規定されていないというのは,立法の怠慢というほかない。第2に,債権については,債権質の場合にも[民法364条以下],抵当権の処分にも[民法377条],債権譲渡の対抗要件[民法467条]が準用されており,最近では,債権登記[動産・債権譲渡特例法]が実現しているのであるから,債権の抵当権を認めないのも,これまた,立法の怠慢である。このような不備があるために,実務は,譲渡担保と仮登記担保という所有権移転型といわれる嘘で固めた非典型担保を生み出し,判例がこれを追認してきたのである。
「国民が嘘つきになる」という意味は,[末弘・嘘の効用(1923)31頁]に明確に述べられているように,「親が厳格だと,子供はうそつきになる。法律に融通性がないと,国民は実を取るために嘘をつく。立法者は,国民が嘘をつくようになったら,立法の改正を行わなければならない」という趣旨である。
つまり,非典型担保は,民法の不備(動産抵当・債権抵当の原則的否定)から生じる,国民のやむにやまれぬ「嘘」であり,通謀虚偽表示である。民法が動産および債権の上の抵当権を認めていないため,国民は担保の目的で動産および債権を譲渡するという,目的を超えた概観を作り出さざるを得なかったのである。真意(担保の設定)と表示(所有権の移転)とが完全に食い違っているのであるから,非典型担保としての所有権移転型担保は,例外なく,通謀虚偽表示である。譲渡担保の場合には,当事者は,担保設定時に,所有権が債権者に移転するという大きな嘘(設定時所有権移転)を表示する。仮登記担保の場合には,債務者が債務不履行に陥ったときに,初めて,所有権が債権者に移転するという小さな嘘(債務不履行時所有権移転)を表示する。大きな嘘は,判例によって見抜かれるようになり,所有権的構成は,担保的構成へと徐々に組みかえられてきた。しかし,小さな嘘は,なかなか見抜けない。立法者も,仮登記担保が通謀虚偽表示であることを見抜くことができず,所有権移転を前提とする受戻制度や帰属清算制度を構築したため,実務から見捨てられ,利用されない制度へと堕している。
| 譲渡担保 | 仮登記担保 | 抵当権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 嘘の程度 | 大 | 小 | 嘘がない(真意) | |
| 嘘 の 内 容 |
所有権の移転とその時期 | 契約時に所有権が移転する(売買代金は,実は貸金に過ぎない) | 債務不履行または清算期間終了時に所有権が移転する(実は,債権者は換価・処分権を取得するだけで,所有権は移転しない) | 所有権は移転しない |
| 設定者の利用権 | 実行まで設定者が目的物を賃借する(賃料は,実は利息に過ぎない) | 設定者の賃借の必要なし(嘘はない) | 設定者の賃借の必要なし | |
| 弁済による原状回復 | 設定者が弁済して所有権を買い戻す(買戻しは,実は弁済に過ぎない) | 債務不履行または清算期間終了後に設定者が所有権を買い戻す(買戻しは,実は,弁済) | 弁済により,付従性によって担保権は消滅する | |
| 注意点 | 嘘が大きいため,嘘が見抜かれて次第に,所有権移転構成から担保権的構成へと移行しつつある。 | 嘘が小さいため,所有権の移転が嘘であることがわかりにくい。このため,帰属清算方式が採用され,それがあだとなって,自滅の方向にある。 | 競売のメリットである公正さともに,市場価格よりも低価格でしか換価・処分できないというデメリットをかかえている。 | |
見抜かれる嘘は罪が少ない。真実への矯正が可能だからである。見抜かれない嘘は罪が深い。プロフェッショナルでもだまされ,矯正の機会が失われるからである。しかし,その結果は,長い目で見れば,そのような嘘で固めた存在は,それ自体の自滅へと向かうことになる。
国民がやむにやまれずにつく嘘としての通謀虚偽表示は,それ自体がすべてが無効となるというわけではない。非典型担保は,通謀虚偽表示であるが故に,所有権的構成が無効となるだけで,担保的構成が有効となる。なぜなら,通謀虚偽表示においては,当事者間では真意が尊重され(担保の設定が有効),表示が無効(所有権の移転が無効)となるからである。しかし,善意の第三者との関係では,表示(所有権の移転)が優先する。したがって,担保の目的であるにもかかわらず,所有権まで移転するという概観を作らざるをえない非典型担保は,債権者がこれを濫用するという危険を防止することが困難となる。
そこで,判例は,虚偽の概観を作り出している非典型担保について,債権者の濫用を防止し,債務者を保護するため,第1に,債権者に清算義務を課すことにした。これは画期的なことであり,物権法定主義に反するという疑いのあった非典型担保が適法なものとして正当化される最初のステップとなった。非典型担保を,典型担保と同様の地位に置くための第2のステップは,非典型担保を所有権の移転的構成から担保的構成へと組み換え,第1ステップで確立した債権者の清算義務について,抵当権と同じく,債権者の権限を目的物の換価・処分に限定し,所有権の移転を前提とした帰属清算を廃し,処分清算の原則を確立することである。譲渡担保においては,判例は,所有権的構成をとりつつも,徐々にそこから抜け出し,処分清算を広く認め,最近では,後順位譲渡担保権者の存在をも認めるようになっている。所有権について,後順位所有権などという,段階的な所有権を認めることは,物権法定主義に反することが明らかであり,後順位の譲渡担保権を認めるに至った判例は,譲渡担保についても,所有権的構成から担保的構成へと移行しているといってよい。
今後の課題としては,さらに一歩を進める必要がある。
第1は,譲渡担保の法理を進展させ,所有権移転的構成(帰属清算)から決別し,処分清算方式を発展させつつ,公平の観点から,その手続きを公正かつ透明にする方法を追求していかなければならない。
第2は,所有権的構成を採用したために,清算方式を帰属清算方式とせざるをえず,実務から見放されている仮登記担保について,公正かつ透明な手続きを保持しつつ,所有権的構成を担保的構成へと組み換え(立法論すれすれの解釈論),処分清算を可能とする解釈方法が探究されなければならない。
本書では,以下において,従来の解釈を前提としつつ,最終目標を達成するための新しい解釈方法を提案することにする。
非典型担保は,すべて,債務者が目的物を使用・収益することを認める物的担保(いわゆる非占有型物的担保)である。非典型担保は,さらに,代物弁済型の仮登記担保,買戻・再売買予約型の買戻,譲渡担保,所有権留保,債権質型の代理受領,相殺予約,振込指定に分類できる。
*表30 非典型担保の分類
| 契約形態 | 物権としての説明 | 債権の優先弁済権としての説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 代物弁済予約型 | 仮登記担保 | 借金を弁済できない場合に,担保目的物をもって弁済に代えるもので,その状態を予約法理と仮登記によって保全するもの。ただし,担保目的物の価額が債権額を超える場合には,清算が義務づけられており,厳密な意味での代物弁済ではない。 | 弁済期前の契約をもって,債務を弁済できない場合には目的物によって債務の弁済に充てることを約することであり,「抵当直流れ」として説明できる。 | 弁済期前の契約をもって,債務を弁済できない場合には目的物から優先弁済を受ける権利を仮登記によって保全するもの。 |
| 譲渡・買戻型 | 譲渡担保 | 借金の担保を貸主に売却し,かつ,担保目的物を貸主から借り受けるが,一定期間内に借金の返済が可能になった場合には,担保物を借主から買い戻す権能が借主に留保される契約。 | 買戻しまたは再売買の予約を利用して,担保目的物の私的実行を行うことによって抵当権よりも効率的な担保を実現するもの。 | 債権(貸金債権等)の担保として所有名義と対抗要件を得た物権から優先弁済を受けることができるもの。 |
| 所有権留保 | 割賦販売に際して,買主が代金を完済するまで,売主が所有権を留保する契約。 | 売主が所有権を移転した後に,残代金債権の担保として,売買目的物を譲渡担保にすること。 | 債権(貸金債権等)の担保として所有名義と対抗要件を得た物権から優先弁済を受けることができるもの。 | |
| 債権充当・相殺型 | 代理受領 | 債権者(銀行)が融資するにつき,融資先(債務者)が第三債務者に対して有する債権の弁済受領の委任を受け,その融資金の弁済に充当するという契約 | 融資先が第三債務者に対して有する債権に対する銀行の取立のためにする委任(譲渡担保)契約。 | 融資先の債務者(第三債務者)から代理受領(取立のための債権譲渡)の承諾を得ていることを対抗要件として銀行が第三者に対して優先的に弁済を受けることができるもの。 |
| 振込指定 | 債権者(銀行)が,債務者(融資先)の債務者(第三債務者)に対して有する債権の支払い方法を銀行の融資先名義の口座に振り込むことを指定し,それによって振り込まれた金銭(預金債権)を銀行が融資先への貸金債権と相殺する契約。 | 貸金債権と相手方の預金債権による相殺(相殺の担保的機能)を実現するための振込み指定。 | 貸付債権を自働債権とし,預金債権を受働債権として相殺し,実質的な優先弁済を受けることができるための振込みの指定。 | |
| 相殺契約 | 銀行が顧客に貸付債権を有し,顧客が銀行に預金債権を有している場合に,相殺契約(期限の利益の喪失条項等)によって相殺適状を繰り上げ,預金債権の範囲内で他の債権者に優先して貸付債権の回収を行うための契約。 | 顧客に対する銀行の貸付債権を被担保債権として,銀行に対する顧客の預金債権の上に設定された債権質。 | 貸付債権を自働債権として,融資先の銀行に対する預金債権を相殺契約に従って繰り上げ相殺し,預金債権は貸付債権の額の範囲ですでに消滅しているとして,融資先からの預金債権の返還請求,第三者の差押えを拒絶することにより,優先弁済を確保するもの。 |
これらの非典型担保のうち,相殺については,すでに説明したので,以下においては,仮登記担保,譲渡担保,所有権留保について解説する。
留置権は,すべての者に対して対抗できることから,従来は,それが物権であると説明されてきた。しかし,「物権だから第三者に対抗できる」という言い方は,正確な表現ではない。なぜなら,債権でも,対抗要件を備えれば第三者に対抗できるし[民法605条],反対に,所有権でさえ,対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない[民法177条,178条]からである。留置権の対抗要件として重要なのは,被担保債権が占有する「その物に関して生じた債権」であること[民法295条],すなわち,債権者の「被担保債権と返還義務(いわゆる物権的返還請求権に対応する義務を含む)との間に牽連性があること」という実質的な要件である。
牽連性の重要性は,すでに,同時履行の抗弁権の箇所(*第3章第3節)で「双務契約における履行上の牽連性」として,対立する債権・債務が引換給付判決を通じて同時に履行されるべきことを学習済みである。また,相殺の箇所(*第3章第4節)でも,相殺の担保的機能の実質的要件は,対立する債権・債務との間の牽連性であり,第三者の介入(差押えまたは譲渡)があったとしても,牽連する債権・債務が同時に消滅することを通じて,債権者に受働債権に対する優先弁済権が実現されていることを学習済みである。さらには,次に論じる先取特権の箇所(*第5章第3節)でも,優先弁済権の根拠は,被担保債権と目的物の価値の維持との間に牽連性が認められるからであることを学習する。このように考えると,法定の物的担保における事実上の優先弁済権,および,法律上の優先弁済権の実質的な根拠は,いずれの場合も,被担保債権と目的物(目的債権)との間に牽連性があることに求められることがわかる(いずれの場合も,必ずしも公示は要件とならない)。このようにして,被担保債権と目的債権との間に牽連性がある場合には,たとえ第三者からの介入(差押えまたは譲渡)があったとしても,両者はあたかも運命共同体のように,同時に履行され(引換給付),同時に消滅するのであり(第三者の介入が排除される),いずれの場合も,牽連性によって被担保債権に事実上または法律上の優先弁済権が成立するのである。
ここでは,留置権の牽連性要件(民法295条にいう「物に関して生じた債権」であること」)に焦点を当て,①留置権が成立するために,なぜ,「被担保債権と返還義務との間に牽連性があること」が必要とされるのか。②留置権における「被担保債権と物の返還義務との間の牽連性」は,具体的には,どのような基準によって判断されるのであろうかという2つの問いに答えることができることを目標に検討を行うことにする。
留置権とは,他人の物について適法に占有を取得した者が,その物に関して生じた債権(被担保債権)の弁済を受けるまで,相手方(所有者等)からの返還債務の履行を拒絶してその物を留置し続けることのできる権利(履行拒絶の抗弁権)であり,この権利を通じて,債権の事実上の優先弁済権を確保するものである[民法295条以下]。
留置権は,物権として要求される換価・処分権(優先権を伴う競売権)を有しておらず,目的物の使用・収益権をも有しない。このため,通説によれば,留置権は,「他の担保物権のように,目的物の価値を物権的に支配する権利ではない」とされている。また,留置権による被担保債権の履行は,質権とは異なり,先履行ではなく,債権法に属する同時履行の抗弁権と同じく,引換給付判決によるものとされる。その結果,留置権の性質は,「著しく同時履行の抗弁権に接近せしめることとなっている」[高木・担保物権(2005)15頁]。さらに,留置権は,「占有を失えば消滅する(追及権もなし)ものである点では極めて弱い物権であるのみならず,その競売権は大いに争われ,…担保物権としてもいわば例外的存在である。…いわば一の変態的性質を有するものである」[我妻・担保物権(1968)23頁]とされている)。すなわち,留置権は,通説によれば,最も物権らしからぬ担保物権であるということになる。
通説が,留置権を積極的な権利としての物権的性格が希薄な権利であるとしている真の理由は,本書の立場によれば,留置権は,同時履行の抗弁権[民法533条],代金支払拒絶の抗弁権[民法576-578条]等と同様に,「引渡拒絶の抗弁権」に他ならず,物権ではないからである。また,他の担保物権の箇所ではあまり論じられることのない「物の返還義務と被担保債権との間の牽連性」が留置権にだけ要求される理由も,それが同時履行の抗弁権と同様の「引渡拒絶の抗弁権」であって,積極的な権利ではないからである。
このように,留置権は,使用・収益権も,換価・処分権を有しておらず,物権の対抗要件(引渡しまたは登記)にも従っていないのであり,いかなる意味でも物権(本権)ではないのであるから,いかなる意味でも物権本権ではない。
しかし,留置権には,事実上のものとはいえ,物的担保の本質的効力としての優先弁済権を備えており,物的担保の通有性としての付従性,不可分性を有している。したがって,留置権は物権ではないにもかかわらず,本書の立場によれば,先取特権,質権,抵当権と同様に,掴取力を質的に強化するもの,すなわち,債権に事実上の優先弁済権,または,法律上の優先弁済権を与えるもの(物的担保)として,同一グループに属するものとして分類することができる。
したがって,上記のように ,留置権を同時履行と同様の「引渡拒絶の抗弁権」として捉えるならば,2つの債権(被担保債権と引渡請求権)との間に牽連性が要求されるのは当然のことであり,しかも,それが3者間にまたがる場合についても,整合的な判断基準(物的牽連性と人的牽連性)を確立することが可能となったであろう。ところが,従来の学説は,留置権を同時履行の抗弁権とは異なる物権であると定義しながらも,同時履行の抗弁権に要求される2つの債権の間の牽連性という要件が留置権にも必要であるとし,しかも,その牽連性の判定基準を確立してこなかった。このため,留置権は,初心者にとっても,また,専門家にとっても,理解が困難となってきたのである。
以下のような事例を留置権の典型例として提示しておく。留置権をめぐるすべての問題は,この典型例のバリエーションとして理解できるので,この典型例について,しっかり把握しておくことが大切である。
留置権に関する古典的な問題とは,伝統的には,目的物の修理(従来は時計の例が多かったが,最近では,自動車,電気製品,パソコン等の修理が多い)に関して,注文者(債務者A)に依頼されて目的物を修理した者(債権者B)は,その物に関する請負契約から生じる修理代金債権(報酬債権)[民法632条,民法633条]を保全するために,注文者(債務者A)または債務者から目的物を譲り受けた所有者(第三者C)からの引渡請求に対して,その引渡しを拒絶し,被担保債権(報酬債権)が弁済されるまで,その目的物を留置することができるかどうかを問うものである。そして,それが肯定されたときに,Bは留置権を有するという。
なお,本書では,留置権の記号表記について,Aを債務者,Bを留置権者,Cを第三者とする。留置権者は常にBである。
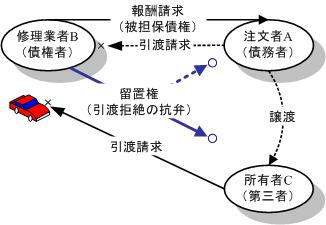 |
| *図61 留置権に関する典型例 |
修理業者Bの有する報酬請求権(被担保債権)は,第3節で論じる先取特権とも関連する。そこで,両者の違いと関係について付言しておくことにする。
修理業者Bは,留置権のほか,次節で検討する動産保存の先取特権[民法311条4号]を有しており,被担保債権が任意に履行されない場合には,目的物である自動車を競売し,その売却代金から,他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有している[民法303条]。
先取特権の特色は,後に述べるように,占有を要件としないことにある。したがって,Bが修理を終えて目的物をAに返還すると,留置権は消滅する[民法302条]が,先取特権は存続する。もっとも,先取特権の場合には,目的物がAに返還された後,さらに,第三者Cに譲渡されてCが引渡しを受けたときは,追及効を失う[民法333条]。この場合には,Bは,AがCに対して有している売買代金債権に対して物上代位権を行使するしかない[民法304条]。
このように,留置権と先取特権とは,要件も効果も異なる別の制度である。しかし,同一の債権について,留置権と先取特権とが並存することがありうる。例えば,修理業者Bが占有を継続し,留置権と動産保存の先取特権という2つの権利を併せ持っている場合には,Aに対しては留置権のほか,動産先取特権者として,法律上の優先弁済権を行使することができる。しかも,たとえ,目的物が第三者Cに譲渡されたとしても,留置権者として第三者からの引渡請求を拒絶することができるため,売主としてのBの先取特権としての順位は,第3順位に過ぎないが[民法330条1項3号],留置権と組み合わさると,実質的には,最高順位の優先弁済権を享受することができることになる。なぜなら,留置権者は,第1順位の先取特権者に対しても,留置的効力を主張することができるからである([民法347条の反対解釈])。
留置権の典型例を説明したので,民法295条の成立要件について検討する。留置権の成立要件は,以下の4つである。
このうち,抽象的過ぎてわかりにくくなっているのが,第3の要件である「被担保債権が,『その物に関して生じた債権』であること」という要件(牽連性の要件)である。そこで,以下では,留置権の成立要件のうち,牽連性の要件について検討する(2,3,4)。
留置権で理解が最も困難であるとされる第3の牽連性の要件について説明した後に,「占有が不法行為によって始まった場合でないこと」,反対からいえば,「債権者の占有取得が正当の原因に基づくものであること」という第2の要件についてついて検討を行うことにする(5)。
民法295条の要件のうち,最も抽象的でわかりにくいのが,被担保債権が「物に関して生じた債権」であることという要件である。この要件はあいまいなため,わが国の通説は,「物に関して生じた債権」という民法295条の要件を以下の*表31のように,①「債権が物自体から生じた場合」,②「債権が物の返還義務と同一の法律関係または事実関係から生じた場合」という2つに分類し,抽象的な要件を具体化しようとしている([我妻・担保物権(1968)28頁以下],[柚木=高木・担保物権(1973)19-20頁],[近江・講義Ⅲ(2005)22-29頁]など)。
その中で,通説の立場を最も鮮明に記述しているのは,[近江・講義Ⅲ(2007)15頁以下]である。そこで,ここでは,その記述にしたがって通説の見解を見ていくことにする。
| 牽連性 | 牽連性の要件の2分類 | 牽連性の要件の具体例 | |
|---|---|---|---|
| 物に関して生じた債権 | ①債権が物自体から生じた場合 | 費用 | 占有物にかけた必要費または有益費の費用償還債権の場合(借家の修理など) |
| 損害 | 自動車が飛び込んできて玄関を壊したり,隣家の犬が入り込んで盆栽を壊したりなど | ||
| ②債権が物の返還義務と同一の法律関係(または事実関係)から生じた場合 | 法律関係 | 売買契約から生じる物の返還義務と代金債権,物の修理委託契約から生じる修理物返還義務と修理代金債権など | |
| 事実関係 | 2人の者が互いに傘を取り違えて持ち帰ったときの,相互の返還義務の場合(ただし,[鈴木・物権法(2007)421-422頁]は,この場合の留置権を否定する) | ||
*表31は,通説の見解を検討する上で,何度も引用するので,具体例を含めて,よく理解しておくことが大切である(特に,*表31の①,②の重要概念については,何も見ずに言えるようになるまで,繰り返し復習する必要がある)。
通説は,民法295条が規定する被担保債権が「物に関して生じた債権」の意味を,先に述べたように,①債権が物自体から生じた場合と,②債権が物の返還義務と同一の法律関係(または事実関係)から生じた場合とに分類している。通説によるこのような要件の2分類がどのようになされるようになったのかは,歴史をさかのぼって検討しなければならない。
以下の*表32を見ると,第1に,旧民法債権担保編92条に明確に規定されていた総論(一元論)と各論(2分類)のうち,現行民法295条の立法過程で総論(「物に関して生じた債権」)だけが生き残り,肝心の各論(2分類)の部分が脱落してしまったことがわかる(詳細については,[加賀山・担保法(2009)202-208頁参照])。
第2に,通説は,現行民法の立法の過程で脱落してしまった各論(2分類)を解釈論として補うに際して,旧民法の規定に立ち返るのではなく,むしろ,ドイツ民法273条(物権ではなく,給付拒絶の抗弁権として規定されている留置権の権の成立要件)の2分類をに注目し,それに基づいて,現在の2分類を形成してきたことがわかる。
| 出典 | 第1類型 | 第2類型 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① 2 分 類 の 脱 落 |
旧民法 債権担保編92条 (1890) |
総論 | 其物に関し又は其占有に牽連して生じたるとき | 旧民法は,総論と各論とを有していた。ただし,各論の第1類型と第2類型の順序は条文では逆となっている。 | |
| 各論 | 其物の保存の費用に因り或は其物より生じたる損害賠償に因りて…其物に関し…生じたるとき | 債権が其物の譲渡に因り…其物に関し…生じたるとき | |||
| 現行民法295条 (1989) |
総論 | 債権がその物に関して生じた債権であること | 総論しかなく,一元論(抽象的)でわかりにくい。 | ||
| ② 2 分 類 の 復 活 |
ドイツ民法273条 (1900) |
各論 | 目的物を返還すべき義務を負う者がその目的物に加えた費用または目的物によって生じた損害について,すでに弁済期に達した請求権を有するとき | 債務者が債務を負担したのと同一の法律関係に基づき,債権者に対して弁済期に達した請求権を有する場合 | 総論はないが,各論がある。旧民法と同じく,第1類型と第2類型の順序は逆となっている。 |
| 富井・物権下 (1929)316頁 |
各論 | 物が事実上債権発生の原因と為りたる場合 | 債権と同一の原因より生じたる債権の目的たる場合 | ドイツ民法273条(給付拒絶の抗弁権としての留置権)の影響を強く受けている。 | |
| 三潴・担保物権 (1921)43頁 |
各論 | 物自身が債権発生の直接原因を為したる場合 | 債権と物の占有取得とが同一の取引関係から又は目的に因りて生じたる場合 | ||
| 薬師寺・留置権 (1935)76,271頁 |
各論 | 債権が直接に物自体を原因として発生した場合 | 債権と物の引渡請求権とが同一の生活関係から生じたる場合 | ||
| 我妻・担保物権 (1968)29-32頁 |
各論 | 債権が物自体から生じている場合 ・その物に加えた費用の償還請求権 ・その物によって受ける損害の賠償請求権 | 債権が物の返還請求権と同一の法律関係(または同一の生活関係)から生じた場合 | 現在の通説。ただし生活関係(事実関係)は不要とされつつある。 | |
上の*表32で明らかなように,現行民法295条の「物に関して生じた」という抽象的な牽連性の要件は,学説およびそれに従う判例によって,①「被担保債権が物自体から生じた場合」(より具体的には,「被担保債権が物の費用の償還債権,または,物から生じた損害の賠償債権である場合」),または②「被担保債権が返還義務と同一の法律関係から生じた場合」というように2つに分類されて具体化され,結果的に,旧民法債権担保編92条と同様,総論と各論とが復活したことが重要である。
民法295条の「物に関して生じた債権」であるという要件は,誰もが認めるように,その意味がわかりにくい。したがって,学説・判例がこの抽象的な要件を2つに類型化し,1つは,「債権が物自体から生じている場合」,すなわち,「物に加えた費用の償還請求権,または,その物によって受ける損害の賠償請求権」,もう1つは,「物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合」というように,被担保債権の具体的なイメージを明らかにしたことは,大きな功績である。すなわち,留置権の牽連性要件に関して,抽象的ですべてを包括する総論(被担保債権が物に関して生じたこと)と具体的な各論(類型論)とが組み合わされたことにより,留置権の成立の要件がわかりやすくなったことは高く評価されなければならない。
もっとも,通説の2分類を詳しく検討してみると,実際問題を扱う上で,いろいろな不都合が生じていることがわかる。なぜなら,せっかくの具体化にもかかわらず,初めて学習する者にとっては,通説の2分類自体を理解することが困難となっているからである([山野目・物権(2009)208-210頁]は,「通説の説明は,あまり成功しているようには思えない」として,旧民法による分類に従った説明を行っている)。
通説の分類の不都合さは,突き詰めていくと,以下の3点に集約される。
第1に,第1類型である「債権が物自体から生じた場合」については,そもそもその表現自体が適切ではない。債権は,契約,事務管理,不当利得,不法行為という4つの発生原因から生じるのであって,人と人との関係である債権が物自体から生じることはないからである。
第2に,通説の2分類の不都合さは,通説の見解をまとめた*表31に立ち返り,そこに挙げられている具体例を仔細に検討すると明らかとなる。留置権の典型例である自動車の修理代金の例について通説の分類を当てはめようとした場合に,修理「費用」と考えると,第1類型に該当することになる。ところが,同じ修理費用を,請負契約に基づく「報酬債権」と考えると,第2類型に該当することになる。このように,通説の分類は,留置権の典型例においてさえ,そのあてはめに重複が生じるという致命的な欠陥を有している。具体例のあてはめに重複が生じる原因は,第1に述べたように,「債権が物自体から生じた場合」という概念が的確ではなく,分類の基準自体が明確とはいえないからである。
第3に,通説自身が自覚しているように,第2類型の例として挙げられている「傘の取り違えの場合」については,[鈴木・物権法(2007)421-423頁]が,3人が傘を取り違えた場合を念頭において,「このような場合には,そもそも,留置権を認めるべきでない」としているように,分類の正確性自体に疑義が生じているからである。
そこで,本書では,通説の分類を踏まえた上で,民法295条の牽連性の要件を以下のように再構成することにする。
第1類型の「債権が物から生じた場合」の名称を「物的牽連性」として単純化し,その内容を,「物に対する費用(保存費用だけでなく購入費用を含む)」,および,「物から受けた損害の賠償」として明確化する。ここで,第1類型に該当する被担保債権としての「費用」に,保存費用だけでなく購入費用を含めたのは,そのような被担保債権は,いずれも,先取特権として保護されるほどに,債権と物との間に強い牽連性が認められるからである。
通説の2分類説が難解であるのは,*表31に見られるように,修理費用は第1類型で,修理代金は第2類型としているためである。同1人が同じ行為をして同じ金額の債権が生じているのに,それが,第1類型にも,また,第2類型にも分類可能であるというのでは,何のための分類かわからなくなってしまう。
このように考えると,留置権における2分類は,牽連性の要件が緩やかに認められる第1類型と牽連性の要件が厳しく求められるべき第2類型とをはっきりと区別することが求められており,第1類型と第2類型とは,被担保債権と物との間の牽連性の強弱を基準として,以下のように,(a)物的牽連,(b)人的牽連の2分類として再構成されるべきである。
物の必要費・有益費の償還請求権については,いわゆる物自体から生じた債権として物的牽連性があると考えるべきであり,たとえ,それが,請負契約から生じている場合であっても,第1分類とすべきである。同様にして,損害がその物の瑕疵等から生じている場合には,被担保債権である損害賠償債権はいわゆる物自体から生じた債権であり,たとえ,それが不法行為から生じていても,事務管理から生じていても,さらには,債務不履行から生じていても第1類型に分類すべきである。
これに対して,二重譲渡の場合の損害賠償債権のように,被担保債権がいわゆるその物自体から生じたのではなく,その物に関連する二重譲渡という債務不履行から生じているに過ぎない場合には,第1分類ではなく,第2分類型と考えるべきである。
| 牽連性の 要件 |
2分類 | 具体例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 物に関して 生じた債権 |
①物的牽連 被担保債権が物の保存もしくは供給費用・代金または物による損害から生じた場合 |
費用・ 代金 |
保存 | 占有物の保管・修理費用または保管・修理代金債権(必要費または有益費) |
| 供給 | 占有物の購入費用または購入代金債権 | |||
| 損害賠償 | 自動車が暴走して家に突っ込んできた,隣家の犬が盆栽を壊したなどによって生じた損害賠償債権 | |||
| ②人的牽連 債権が物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合 |
その他の 法律関係 |
・処分清算型の譲渡担保において,譲渡担保の実行によって生じる譲渡担保設定者の譲渡担保権者に対する清算金支払債権(判例肯定) ・売主の不動産二重譲渡によって生じる第1買主の売主に対する損害賠償債権(判例否定) |
||
この*表33によって,わが国の通説に依拠しつつ,その改善を示した本書の第1類型と第2類型とが旧民法によっても,また,ドイツ民法によっても支持されうるものことがわかる。第1類権は,牽連性のうち,被担保債権の性質が物との強い牽連性を有するものであり,物的牽連性(被担保債権の性質自体が物の返還義務に対抗できる性質のものであること)を意味しており,第2類型は,人的牽連性(被担保債権と物の返還義務とが同一の法律関係から生じていること)を意味している。両者ともに,被担保債権と物の返還義務が同時に履行されること,すなわち,被担保債権が履行されるまで,返還を拒絶できることを正当化するものとなっている。
このように,物的牽連性と人的牽連性という牽連性の2分類に関しては,以上のような具体的で明確な基準が示されるべきである。これらの2類型に関して,従来の学説および判例がどのように考えているのかを順次見ていくことにしよう。
通説の第1類型にいう「債権が物自体から生じている」という意味は,被担保債権と物との間の関係が,物の保存・供給の費用,物による損害の発生というように,非常に密接であるため,「被担保債権と物の引渡債務との牽連性が同一の法律関係から生じている」という,第2類型で必要とされる牽連性のテストを問題とすることなく,常に,第三者に対抗できるものとすることができる場合である。本書では,このような被担保債権と物との間の強い牽連性のことを物的牽連性と呼ぶことにする。
(i) 物の保存・供給の費用・代金
物的牽連性のうち,物の保存・供給に関する債権については,先取特権によっても,動産,不動産を問わず優先弁済権が認められている(保存につき[民法311条4号,325条1号],売買につき[民法311条5号,325条3号])。
したがって,Aの注文を受けて,自動車を修理した請負人Bの留置権という典型例についても,通説とは異なり,以下のように,請負人Bを確実に保護できる。
通説は,BがCに対して留置権を主張できるのは,先に述べたように,その前提としてA・B間で成立した留置権が成立しているからであり,いったん成立した留置権は,目的物が譲渡されても第三者Cに対抗できるとしている。しかし,そうだとすると,修理が完成する前にAが目的物を譲渡した場合には,BのAに対する修理代金債権は弁済期にない[民法633条]のであるから,A・B間でも留置権は成立しない[民法295条ただし書き]。このため,この時点でAが目的物をCに譲渡すると,Aは占有を失うので,BのAに対する関係では,留置権が成立しないし,対抗力も生じない。したがって,B・C間でも留置権は成立しないことになり,たとえBが修理を完成しても,Cからの所有権に基づく返還請求権を拒絶できなくなる。このことが不当であることは明らかであり,通説の説明は十分でないことがわかる。
これに対して,本書の立場によれば,留置権の典型例である自動車の修理の事例の場合,被担保債権であるBの修理代金債権(報酬請求権)[民法632条,633条]は,目的物が動産の場合[民法311条4号,320条],不動産の場合[民法325条1号,326条]を問わず,先取特権によって保護されている。すなわち,Bの被担保債権は,それ自体について先取特権が認めらる第三者に対抗できる権利であり,目的物に関して物的牽連性を有している。したがって,Bは契約当事者Aからの目的物の引渡請求[民法633条]だけでなく,第三者Cからの所有権に基づく返還請求権に対しても,被担保債権が弁済されるまで引渡を拒絶することによって,事実上の優先弁済権を確保できる。したがって,修理が完成しない前にAがCに目的物を譲渡したとしても,修理が完成した後は,BはCとの関係でも留置権を主張することができることになる。
(ii) 物から生じた損害
これに対して,物から生じた損害については,先取特権による保護はないが,歴史的な経緯に基づいて,世界各国で留置権が認められてきた。通説も,先の*表31で示したように,「自動車が飛び込んできて玄関を壊したり,隣家の犬が入り込んで盆栽を壊したなど」,物から生じた損害に関する損害賠償債権について,留置権の成立とその対抗力を認めている。
例えば,第1類型とされている暴走トラック突っ込み事件[近江・講義Ⅲ(2007)15頁]を例にとってみよう。この場合,家に突っ込んできた車が盗難車であって,車の返還を求める所有者には責任がない場合のように,加害者(窃盗者)が逃亡してしまって,被害者(債権者)と加害者(窃盗者)という当事者間では留置権が問題とならず,いきなり,被害者と第三者(盗難車の所有者)との間で留置権が成立するかどうかが問題となる場合であっても,留置権の成立要件としての牽連性が認められる。
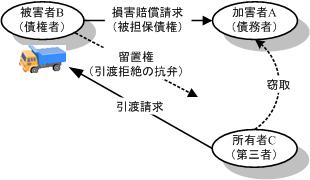 |
A(加害者)がCから借りた,または,Cから窃取したC所有のトラックを暴走させてBの家に突っ込んできたという不法行為の事例(トラック暴走・突込み事件)の場合に,トラックの所有者Cが被害者Bに対してトラックの返還を求めても,被害者であるBは,壊された家屋を修繕するための損害賠償債権の満足を受けるまで,留置権を根拠にして,第三者であるCに対しても,そのトラックを留置できると解説される(損害賠償債権に関する留置権の肯定)。 |
| *図62 三者型の肯定例 暴走トラック突っ込み事件 [近江・講義Ⅲ(2007)15頁] |
この事件において被担保債権の債務者Aは,被担保債権の発生時点において,すでに無権利者であり,そもそもBに対して返還請求権を有しておらず,二者間では留置権は発生しない。しかし,被担保債権と目的物の返還義務との牽連性は,被担保債権が物自体が原因となって生じた損害に関するものであり(第1類型),物自体に関する保存の費用の場合と同様,物の引渡を求めるすべての人に対して牽連性を主張できる(物的牽連性)。したがって,Bには,留置権が認められることになる[近江・講義Ⅲ(2007)15頁]。
似たような例として,ボールによる窓ガラス破損事件[鈴木・物権法(2007)424頁]がある。
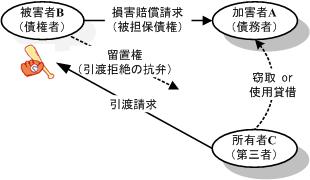 |
Aが打ったボールがそれて,Bの家の窓ガラスを割って,Bの部屋に飛び込んできたとする。Bが外を見ると,Aが全速力で逃げて行くのが見えた。しばらくして,ボールの所有者Cが訪れて,事情を説明してくれた。Cのボールを知人のAが勝手に持ち出してノックの練習をしていて,Bの窓ガラスを割ってしまった。その後,Aは行方をくらましてしまってみつからない。しかし,Cのボールは,有名選手のサインボールなので,Cに返してほしいという。 ボールの所有者Cからその返還を請求されたBは,割られた窓ガラスの損害賠償の支払いがなされるまで,そのボールを留置し,その引渡を拒絶することができる[鈴木・物権法(2007)424頁]。 |
| *図63 三者型の肯定例 ボール窓ガラス破損事件 [鈴木・物権法(2007)424頁] |
トラック暴走・突っ込み事件およびボール窓ガラス破損事件においては,被担保債権が物自体が原因となって生じた損害に関するものであり(第1類型),物自体に関する保存の費用の場合と同様,物の引渡を求めるすべての人に対して牽連性を主張できる(物的牽連性)。
物的牽連性と次に述べる人的牽連性と比較した場合,物的牽連性の場合には,被担保債権と物との関係が密接なため,被担保債権と引渡義務との間が同一の法律関係から生じたものに限定されないという特色がある。たとえば,被担保債権と引渡義務との間に,もう1つの債権が介在した場合,人的牽連性の場合には,被担保債権と引渡義務とが同一の法律関係から生じたとはいえないため,牽連性が否定されるが,被担保債権が物と密接に関連している物的牽連性の場合には,被担保債権である売買債権と,介在したもう1つの債権との間にも,例えば,トラックの窃盗と盗難トラックの暴走の間には密接な関連があるため,被担保債権と引渡義務との間の牽連性が認められるのである。
通説のいう第2類型は,被担保債権と物との牽連性が第1類型ほどには強くないために,原則に戻って,被担保債権と物の返還義務との間の牽連性の厳格なテストが必要とされ,両者が同一の法律関係から生じていることが認められる場合にのみ,留置権の成立と第三者対抗要件が認められるのである。本書では,このような牽連性を人的牽連性と呼ぶことにする。
物的牽連がある場合には,被担保債権が占有物と密接な関係を有するため,被担保債権と返還義務との間の牽連性を証明する必要はなく,その物の返還を求めるすべての人に対して,債権の弁済を受けるまで,その返還を拒絶できる。これに対して,人的牽連にとどまる場合には,その物の返還を求める人に対して,牽連性の存在を同一の法律関係から証明しなければならない。したがって,留置権を第三者に対抗する場合には,従来は,いったん成立した留置権は,物権だから,第三者にも対抗できるという論理が使われてきた。しかし,人的牽連性は,そのような場合に限らず,債権者と第三者の間においても,被担保債権と返還義務との間の牽連性,すなわち,被担保債権と返還義務とが同一の法律関係から生じたことが証明できれば,第三者に対しても留置権を対抗できる。
二者間の牽連性ではなく,第三者との間の牽連性を認めた判例は少ないが,平成15年最高裁判決〈最一判平15・3・27金法1702号72頁〉は,数少ない肯定例の1つである。
最高裁の平成15年判決〈最一判平15・3・27金法1702号72頁〉は,処分清算型の譲渡担保(土地・建物)について,債権者Aの譲渡担保設定者Bに対する清算義務と譲渡担保の実行によって所有権を取得した第三者CのBに対する返還請求権との間に直接の牽連性(同時履行の関係)を認めて留置権を肯定しており,特筆に価する。
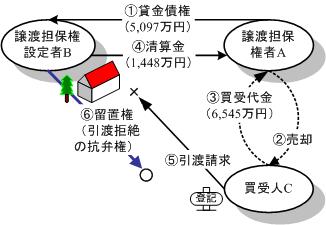 |
最一判平15・3・27金法1702号72頁 譲渡担保権の実行に伴って譲渡担保権設定者が取得する清算金請求権と譲渡担保権者の譲渡担保契約に基づく当該譲渡担保の目的不動産についての引渡しないし明渡しの請求権とは同時履行の関係に立ち,譲渡担保権者は,譲渡担保権設定者から上記引渡しないし明渡しの債務の履行の提供を受けるまでは,自己の清算金支払債務の全額について履行遅滞による責任を負わないと解するのが相当である。 |
| *図64 譲渡担保物件処分清算型 (留置権の対抗力を肯定) 〈最一判平15・3・27金法1702号72頁〉 |
上記の事案とは異なり,仮登記担保の場合のように,帰属清算型の担保の場合には,牽連性が当事者間で発生するので,留置権の成立が認められやすい。なぜなら,Aの清算義務に基づいて,いったんA・B間で留置権が成立した後は,たとえAが清算金を支払わないままに目的物をCへ譲渡した場合にも,Bは留置権をもってCに対抗できるからである〈最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁〉。
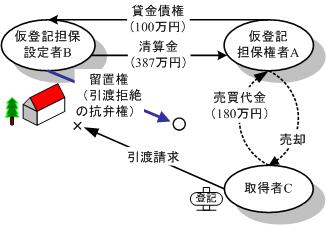 |
最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁 清算金の支払のないまま仮登記担保権者から第三者が目的不動産の所有権を取得した場合には,債務者は,右第三者からの右不動産の明渡請求に対し,仮登記担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。 |
| *図65 仮登記担保の清算金未払状態での 物件譲渡事件 (留置権の対抗力を肯定) 〈最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁〉 |
ところが,本件のように,処分清算型の場合には,AのBに対する清算義務の発生とCのBに対する返還請求権とが同時に生じるため,いきなり,A・B間とB・C間との3者間の牽連性を問題とせざるを得ない。しかし,この類型においても,被担保債権(清算金債権)と返還義務が同一の法律関係(目的物の処分)から生じているのであるから,3者間で留置権の牽連性の要件が充足されているのであり,3者間の牽連性が問題となる事件において,最高裁が留置権の成立を認めたことは高く評価されるべきである。
もっとも,最高裁は,上記以外の3者間の牽連性が問題となる事件については,ことごとく留置権の成立を否定している。人的牽連性の場合に,判例(通説も同じ)がBにCに対する留置権の主張を認めない理由は,被担保債権の債務者Aと物の返還請求権者Cとが,留置権の発生の当初から別人であるという点にある。
しかし,物的牽連性の場合には,被担保債権の性質(被担保債権がいわゆる物自体から生じた場合である)が物との間に強い牽連性を有していることから,3者間での牽連性の要件が緩和されているに過ぎないのであり(牽連性の要件の立証責任の緩和),人的牽連性の場合には,被担保債権と物の返還義務との間の牽連性が,「同一の法律関係から生じている」という厳格な要件の証明によって担保されているのであるから,留置権の成立を認める障害にはならないと解すべきである。
このように考えると,以下に列挙する三者間の人的牽連性が問題となる事例について,留置権を否定した最高裁判決((i)賃借物件の譲渡型,(ii)譲渡担保物件の無断譲渡型,(iii)二重譲渡型,(iv)無効・無断売買型)は,すべて,変更が必要であろう。
(i) 賃借物件の譲渡型〈大判大9・10・16民録26輯11号1530頁〉
この類型は,民法295条の「物から生じた債権」という要件を満たすものとして通説が確立した第2類型(債権が目的物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合)に該当する事案であるにもかかわらず,大正9年大審院判決〈大判大9・10・16民録26輯11号1530頁〉が,このような場合は,「民法第295条に所謂其物に関して生じたる債権に非ず」として,留置権の成立を否定している。これは,2者間の牽連性と3者間の牽連性を不当に区別するものとして合理性を欠いているといわなければならない。
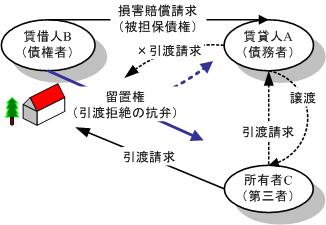 |
大判大9・10・16民録26輯11号1530頁 |
| *図66 賃借物件譲渡型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈大判大9・10・16民録26輯11号1530頁, 大判大11・8・21民集1巻498頁〉 |
通説・判例が,3者間での人的牽連性が問題となっている場合に,留置権の成立および対抗力を否定する背景には,3者間でいきなり留置権を認めると,「売買は賃貸を破る」とか,「二重譲渡の場合,登記を先に得た者が完全な所有権を取得する」という物権法の法理が機能しなくなり,「物権法秩序が破壊される」という危惧があるからであろう(大審院判例の中には,「売買は賃貸借を破る」という原則を背景にして,通説が認めた牽連性の要件(第1類型)が満たされている場合でさえ,留置権の成立を認めないとしているものさえ存在する〈大判大11・8・21民集1巻498頁〉)。
しかし,これらの場合に留置権者が主張しているのは,被担保債権の弁済が確保されることだけであり,決して,第三者Cの所有権の帰属を争っているわけではない。したがって,これらの場合に留置権を認めたからといって,物権秩序が破壊されることはなく,そのような懸念は杞憂に過ぎない。
本類型の場合,賃貸借契約において,賃借人が請求しているのは,債務不履行の基づく損害賠償請求や敷金の返還請求権という金銭債権の確保に限られており,賃貸借契約そのものを第三者に対抗しようとしているわけではない。
賃貸人Aが賃借権の対抗要件(登記等)を具備していない賃借物件をCに譲渡した場合,賃借人は,賃貸借契約をCに対抗できない結果,Cに賃借物件を引渡さなければならない(売買は賃貸借を破る)。そのことを承知で,賃貸人が賃借物件をCに譲渡することは,目的物の使用・収益を約束した契約違反が存在する。すなわち,この類型においては,賃貸人Aによる賃借人Bの同意を得ない賃借物件のCへの譲渡と登記の移転というAの債務不履行という1つの法律関係から,一方で,賃貸人Aの債務不履行に基づくBの損害賠償請求権が発生し,他方で,BのCに対する目的物件の返還義務が同時に発生する。したがって,Bの被担保債権とBの返還義務との間には,通説が民法295条の被担保債権が「その物に関して生じた債権を有する」という要件の解釈として確立している「債権が目的物の返還義務と同一の法律関係から生じた場合」という牽連性の要件を完全に満たしており,BはCに対して留置権をもって対抗できることが明らかである。
債権が物に関して生じたものであれば,留置権が成立し,占有の継続という対抗要件を通じて,A・B間に生じた被担保債権が支払われるまで,第三者対して物の引渡しを拒絶できるのが留置権の特色であり,そうだからこそ,昭和47年最高裁判決〈最一判昭47・11・16民集26巻9号1619頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第79事件)〉は,3者間にわたる引換給付判決を実現しているのである。
法政策的にも,賃貸物件を譲り受ける第三者は,現況を調査すれば,賃借人が占有していることがわかるのであるから,そこでの損害賠償債権が弁済されるのを見届けてから賃貸物件の譲渡を受けるべきであり,そのような現況調査を怠った譲受人が損害賠償債権の弁済まで,物件の引渡しを受けることができなくなったとしても,やむをえないと思われる。
(ii) 譲渡担保の目的物の無断譲渡型〈最一判昭34・9・3民集13巻11号1357頁〉
譲渡担保権者Aが譲渡担保の設定者Bとの担保設定契約に違反して,目的物件を第三者Cに譲渡した場合にも,(i)で論じたのと同じ問題が生じる。なぜなら,BとAとの関係は,名目上は,Bが目的物件の賃借人であり,Aが賃貸人となっており,そのような外観が生じているからである。
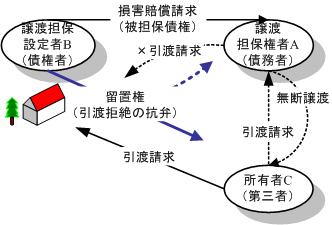 |
最一判昭34・9・3民集13巻11号1357頁 不動産を売渡担保に供した者〔B〕は,担保権者〔A〕が約に反して担保不動産を他に譲渡したことにより担保権者に対して取得した担保物返還義務不履行による損害賠償債権をもって,右譲受人からの転々譲渡により右不動産の所有権を取得した者〔C〕の明渡請求に対し,留置権を主張することは許されない。 |
| *図67 譲渡担保物件無断譲渡型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈最一判昭34・9・3民集13巻11号1357頁〉 |
この場合も,目的物件の無断譲渡,すなわち,譲渡担保権者の債務不履行という1つの法律関係によって,一方で,BのAに対する被担保債権が発生すると同時に,他方で,BのCに対する目的物の返還義務が生じており,被担保債権は,民法295条にいう「物に関して生じた債権」といえるのであり,BはAから被担保債権の弁済を受けるまで,Cに対して目的物の引渡しを拒絶できると考えるべきである。
(iii) 二重譲渡型〈最一判昭43・11・21民集22巻12号2765頁〉
二重譲渡事件については,留置権が発生するかどうか,留置権が登記を先に得た第2買主に対抗できるかどうかをめぐって,大いに議論がされている。本書の立場は,通説によって確立された,「債権と物の返還義務とが同一の法律関係から生じている」という牽連性の要件を忠実に適用し,被担保債権と物の返還義務とは,売主の二重譲渡に基づく登記の移転という同一の法律関係(債務不履行)から生じている。したがって,留置権の成立要件も対抗要件も満たされているというものである(その論理的帰結は,通説と反対となる)。
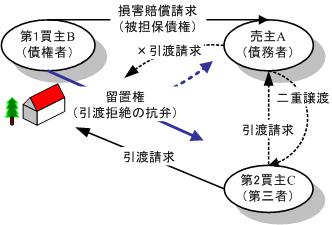 |
最一判昭43・11・21民集22巻12号2765頁 不動産の二重売買において,第2の買主〔C〕のため所有権移転登記がされた場合,第1の買主〔B〕は,第2の買主〔C〕の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し,訴外Aに対する売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもって,留置権を主張することは許されない。 |
| *図68 二重譲渡型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈最一判昭43・11・21民集22巻12号2765頁〉 |
最高裁が留置権の成立を否定した理由は,この場合,当事者間で留置権がすでに発生した後に,目的物が第三者へと譲渡された場合とは異なり,損害賠償債権の債務者Aと物の引渡請求権者Cとが当初より別人であり,債権と牽連関係を有すべき引渡請求権を債務者は有していない([内田・民法Ⅲ(2005)505頁])。しかも,理論的には,第三者Cが有効に引渡請求権を持つことに確定して初めて損害賠償請求権が生ずるのであるから,留置権の発生を認めるべきでないというものである。
この場合に,留置権の成立要件としての牽連関係を認めて,留置権は発生するとする説[道垣内・担保物権(2008)16-17頁]が存在する。しかし,この説も,留置権の人的効力の範囲を限定しており,留置権の成立時点で債務者Aが債権者Bに対してその物の引渡請求権を有しない場合には,債権者Bと債務者Aとの間で留置権の成立が認められても,その効力を目的物所有者に対して主張できないと解すべきであるとして,結果的に,BのCに対する留置権の主張を否定している[道垣内・担保物権(2008)21,29頁]。
[道垣内・担保物権(2008)31頁]は,留置権の人的効力の範囲の問題を牽連関係の問題とすることは,制度や原理間の衝突・調整という実質的判断をわかりにくくするので適切でないと反論している[道垣内・担保物権(2008)31頁]。
しかし,この問題に関する限り,道垣内説は,説得的ではない。なぜなら,第1に,制度や原理間の衝突・調整という「実質的な判断」をするのであれば,自らが述べているように,「少なくとも留置権者はその物を占有しているのであるから,ある程度の公示は図られているし,また,法が特に保護すべき債権者として留置権者を処遇する以上,避けえない結果である」[道垣内・担保物権(2008)31頁]としているのであり,むしろ,留置権の効力の人的範囲の面からも,留置権を肯定すべきである。第2に,留置権の成立の問題は,まさに,引渡請求権と被担保債権との間の牽連性をどのように考えるかが問題なのであって,その判断を避けて,人的範囲の限定の問題であるとすることの方が,問題をわかりにくくすることになり,適切ではない。第3に,留置権は,同時履行の抗弁権とは異なり,占有を伴う引渡拒絶の抗弁権であることから,常に第三者に対抗できる点に意味があるのであって,第三者に対抗できない留置権を成立させても,意味がない。
(iv) 無効・無断売買型〈最一判昭51・6・17民集30巻6号616頁参照〉
最後の類型は,二重譲渡の逆のバージョン,すなわち,第1買主(C)が登記を先に得たが,第2買主(B)が売主A(非権利者)から先に引渡しを受けた場合と考えることができる事例である。しかも,この類型は,盗品の善意取得の不動産バージョン,すなわち,次に述べる,所有者Cが所有物をAに侵奪され,非権利者Aがその物件を善意のBに売却した場合と考えることもできる事例である。
 |
最一判昭51・6・17民集30巻6号616頁 自作農創設特別措置法(自創法)に基づきその所有土地であった本件各土地を国に買収された被上告人〔C〕が,右買収処分の前提である買収計画に瑕疵があったため買収計画取消訴訟を提起したところ,被上告人〔C〕が勝訴し,本件各土地がなお被上告人〔C〕の所有であったことが確定したとして,原状回復の請求として,上告人〔B〕らに対し,その占有にかかる各土地の返還及び建物収去並びに所有権移転登記の抹消等を求めた事案において,他人の物の売買における買主〔B〕は,その所有権を移転すべき売主〔A〕の債務の履行不能による損害賠償債権をもって,所有者の目的物返還請求に対し,留置権を主張することは許されないと判示して,上告人〔B〕らの留置権の主張を退けた原判決を支持して,上告を棄却した事例。 |
| *図69 無効・無断処分型 (判例は留置権の対抗力を否定) 〈最一判昭51・6・17民集30巻6号616頁〉 |
この類型においても,被担保債権と物の返還義務とは,非権利者Aによる処分という1つの法律関係から,一方で,BのAに対する被担保債権が発生し,他方で,同時に,Bの真の所有者Cに対する目的不動産の返還義務が生じている。したがって,この場合も,被担保債権と物の返還義務とが同一の法律関係から生じているという留置権の成立要件が充足されており,BのCに対する留置権の主張が認められるべきである。
留置権の対抗要件は,目的物が動産であれ,不動産であれ,占有の継続である[民法295条の解釈]。「引渡拒絶の抗弁権」である留置権の成立要件が,債権者の被担保債権と物の返還義務との間の牽連性に基づくことはすでに述べた。留置権の対抗力は,この牽連性が,留置権の成立・存続要件である「占有の継続」にって,第三者に公示されているからである。すなわち,留置権の対抗力は,債権者の被担保債権と物の返還義務との間に牽連性を前提とし,占有の継続が牽連性についての公示機能を果たしているからである。
「引渡拒絶の抗弁権」と起源を同じくする「同時履行の抗弁権」が一般的には第三者対抗力を有していないのは,留置権に見られる「占有の継続」のような対抗要件を欠いているからに過ぎない。
最初に紹介した留置権の典型例の場合について,Bの留置権がCに対抗できることの理由を通説は以下のように説明してきた。すなわち,A・Bの二者間で成立した留置権を前提として,目的物が第三者であるCに譲渡されても,占有の継続という対抗要件が備えられているから,留置権は第三者Cに対抗できるのである。
確かに,Bの被担保債権とBの物の返還義務とは,民法は633条によって,直接の牽連性があることは明らかであるが,この返還義務は,Aに対する関係で債権的な請求権に対応する義務であり,Cに関する関係では,物権的請求権に対応する義務であって,通説のいうように,その発生根拠が異なる。しかし,そのような考え方とは別に,BのAに対する被担保債権とBのCに対する物の返還義務との間に直接の牽連性を認めて,留置権を認めるということも,また,可能である。
判例の中にも,2者間の留置権の存在を前提にすることなく,3者間での牽連性を判断したものが存在する。
たとえば,昭和38年最高裁判決〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉は,被担保債権と物の返還請求権が相互に対立しないことを理由に留置権を否定した原審判決を破棄し,二者間での留置権の発生を問題にすることなく,BのAに対する被担保債権は,物(本件土地)に関して生じたものであるという理由で,第三者に対する留置権を有するとしている。
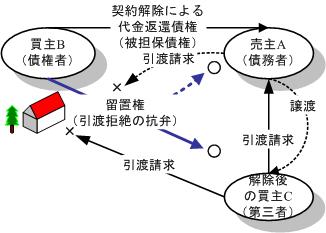 |
最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁 Bが本件土地についてAと売買契約を締結したが代金の一部を支払ったのみで残金を支払わなかったため解除され,その後本件土地をCがAから購入した事案につき,BのAに対する代金返還請求権は,Cに対する債権ではないことからBはCに対し留置権の主張をなしえないとして,CからBに対する家屋明渡等の請求を認めた原判決を破棄し,民法295条1項の「他人の物」とは,債権者以外の物の所有する物をいい,債務者以外の者の所有する物も含むと解すべきであり,BはAに対する代金返還請求権を有し,これは本件土地に関し生じたものであるから,本件土地を占有するBは,弁済を受けるまで右土地につき留置権を有し,Cに対しこれを主張することができると判示した事例 |
| *図70 解除物件譲渡型 (判例も留置権の対抗力を肯定) 〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉 |
この事例において,Bの被担保債権(解除に基づく代金返還請求権)とBの物の返還義務との間に牽連性があることは,民法546条が,解除の場合について,同時履行の抗弁権[民法533条]の規定を準用するとしていることから明らかである。したがって,通説の考え方によれば,A・B間で成立した留置権は第三者対抗要件を備えているため,たとえ,目的物が第三者Cに譲渡されても,BはCに対して留置権をもって対抗できるということになるはずである。
しかし,民法295条は,留置権の要件として,被担保債権が,「その物に関して生じた債権」であればよいとしているのであるから,Bの被担保債権が,第三者が引渡を求めているのと同一の「物に関して生じた債権」であれば,留置権は,Aを経由することなく,いきなりB・C間でも成立すると考えることも可能である。昭和38年最高裁判決〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉が,「BはAに対する代金返還請求権を有し,これは本件土地に関し生じたものであるから,本件土地を占有するBは,弁済を受けるまで右土地につき留置権を有し,Cに対しこれを主張することができる」と判示したのは,A・B間で成立した留置権の第三者Cに対する対抗力の問題について,債権が返還義務の目的物に関して生じた債権であることを理由に,いきなり,A・C間3者間で留置権が成立することを認めることも可能である。
昭和38年最高裁判決〈最三判昭38・2・19民集21巻9号2489頁〉が,「BはAに対する代金返還請求権を有し,これは本件土地に関し生じたものであるから,本件土地を占有するBは,弁済を受けるまで右土地につき留置権を有し,Cに対しこれを主張することができる」と判示したのは,A・B間で成立した留置権の第三者Cに対する対抗力の問題について,債権が返還義務の目的物に関して生じた債権であることを理由に,いきなり,A・C間3者間で留置権が成立することを認めることも可能であることを示しているといえよう。
民法545条1項を本件に適用すると,BはAに対して支払代金の返還請求権を有し,BはAに対して目的物の返還義務を負う。そして,民法546条により,Bの被担保債権とBの民法545条1項ただし書きの反対解釈により,解除後の第三者(既得権を有していない)は,民法546条の準用による同時履行の抗弁権を対抗できると解することができる。すなわち,解除に基づくBの支払代金の返還請求権と解除後に目的物を譲り受けた第三者Cに対する目的物の返還義務とは,第三者に対抗できる同時履行の抗弁権(物的牽連性)を有しており,そのような場合には,Bは直接Cに対して留置権をもって対抗できると考えることができる。
このようにして,留置権における牽連性の要件は,二者間であれ,3者間であれ,被担保債権と返還義務とが物的牽連性を有している場合には,第三者に対する対抗力が生じており,第三者に対して,直接に留置権の抗弁を対抗できると考えるべきである。
二者間で成立する留置権の場合には,引換給付判決は,2者間でなされる。ところが,二者間で成立した留置権において,目的物が第三者に譲渡された場合には,訴外となったAに対する被担保債権が弁済されることを条件に,CのBに対する引渡を認めるという,B・C間での引換給付判決が下される。
以下の判決は,表向きは,2者間で認められる留置権の抗弁が第三者にも対抗でき例として紹介されているが,その内容を詳しく検討すると,次に論じる3者間での留置権の成立を可能にするものとして位置づけることのできる判例でもあり,注目に値する。
最一判昭47・11・16民集26巻9号1619頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第79事件
訴外Aからの代物弁済により本件建物及びその敷地の所有権を取得した被上告人〔C〕が,本件建物を占有する上告人〔B〕に対し,所有権に基づき,建物を明け渡すよう求めて提訴した事案の上告審において,訴外Aから被上告人〔C〕への代物弁済に先立ち,上告人〔B〕らが訴外Aに対して本件建物及びその敷地を売渡しており,訴外Aと上告人〔B〕との契約により,上告人〔B〕は訴外Aに対し残代金の支払に代わる提供土地建物の引渡し請求権を有しているところ,右請求権は本件土地建物との間に牽連関係がないとした原審を破棄し,残代金の支払に代えて提供土地建物を上告人〔B〕に譲渡する旨の本件契約は,代物弁済の予約がなされたものと解するのが相当であると判示して上告人〔B〕の留置権の主張を認め,上告人〔B〕は訴外Aから残代金の支払を受けるのと引換えに被上告人〔C〕へ本件建物を引渡せとの引換給付判決を言渡した事例。
| 留置権が認められた同一事件について,異なる解釈が可能な事例 〈最一判昭47・11・16民集26巻9号1619頁民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第79事件〉 |
||
 |
⇔ | 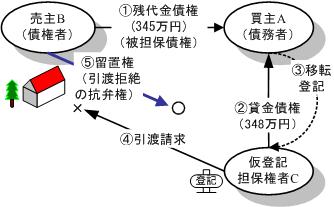 |
| *図71 三者型の肯定例(通説による解釈) 連鎖売買があったと見るため, 2者間の留置権の抗弁が第三者に対抗できる, すなわち,二当事者の留置権の接続型と考える。 平凡な判決に過ぎない |
*図72 三者型の肯定例(本書の解釈) 売主の先取特権と仮登記担保の競合と見るため, 固有の三者型と考え,不動産売買の先取特権が 留置権によって対抗力を強化された場合と考える。 画期的な判決 |
|
上記の平成47年最高裁判決の事案は,一見,目的不動産がBからAへ,AからCへと転々譲渡された場合に,最初の売主(B)が最初の買主(A)に対する残代金債権を被担保債権として,転得者Cからの目的物の引渡請求に対して,留置権を主張し,それが認められた事件(二当事者型留置権の対抗問題)のように見える。そうであれば,AB間で発生していた留置権について,目的物が第三者Cに譲渡された場合であっても,Bは留置権の抗弁を主張することができるという平凡な事例に過ぎないということになる(藤原正則「留置権の対抗力」[民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)161頁]は,本件を売買が連鎖した事件として構成している)。しかし,別の角度から見ると,実は,目的物の二重譲渡事件と同じように,三当事者型の留置権が認められた事件(三当事者型の留置権)として評価することができる。
その理由は,以下の通りである。BはAに対して,残代金債権を被担保債権として不動産売買の先取特権を有している。これに対して,CもAに対して貸金債権を被担保債権として代物弁済予約に基づく担保権(仮登記担保権)を有している。この場合の三当事者の関係は,転売から生じる2者間の留置権の対抗力という単純な問題ではなく,より高度な三当事者型の留置権の問題として構成されるべきである。なぜなら,代物弁済予約に基づいて建物収去・土地明渡しを請求するCに対して,Bは,Aに対する残代金債権を有しており,それが,「その物に関して生じた債権」であることを主張して,留置権を主張することができるからである。
このように考えると,昭和47年最高裁判決は,A・Bの2者間で成立した留置権が第三者Cに対して対抗力を有するという転売事件に関する平凡な判決ではなく,Aに対する残代金債権に基づいて不動産売買の先取特権を有するBは,たとえ登記を有しない場合でも,その代わりに占有を継続している場合には,留置権によってその優先弁済権が強化され,Aから登記を有する抵当権と同等の効力を有する仮登記担保権を得たCに対しても,実質的な優先弁済権を取得できることを認めた画期的な判決であるということになる。なぜなら,この判決は,不動産売買の先取特権と仮登記担保とが競合した場合について,登記を有しないが占有を有するために留置権を有する不動産売買の先取特権者に,仮登記担保権者に優先する権利を与えたことになるからである。
本判決は,留置権の効果としての引換給付について,新しい判断を行っている。すなわち,2者間で留置権が問題になる場合には,Y・Bは,相互に債権・債務を負担しているから,引換給付判決を下すことには何の問題も生じない。しかし,3者間で留置権が問題になる場合には,第三者Xは,YのBに対する売買代金債権を負担しているわけではないので,Xに対して,引換給付判決を下すことができるかどうかが問題となる。最高裁は,この点について,Xが被担保債権の弁済の義務を負っていない場合でも,Yに留置権を認める場合には,Yと第三者Xとの間で引換給付判決を下すことの妨げにはならないことを宣言している。この点は,引換給付判決に関する新判例として位置づけられている。
留置権の抗弁が理由のあるときは,引渡請求を棄却することなく,その物に関して生じた債権の弁済と引換えに物の引渡を命ずべきであるが(最高裁昭和31年(オ)第966号同33年3月13日第一小法廷判決・民集12巻3号524頁,同昭和30年(オ)第993号同33年6月6日第二小法廷判決・民集12巻9号1384頁),前述のように,XはYに対して残代金債務の弁済義務を負っているわけではないから,Bから残代金の支払を受けるのと引換えに本件建物の明渡を命ずべきものといわなければならない(なお,XがBに代位して残代金を弁済した場合においても,本判決に基づく明渡の執行をなしうる)。
つまり,BがAに請負代金を支払わない以上は,Cは,Bに代位して請負代金を支払わなければ,Bに対して,目的物の返還を実現することはできない。それと同時に,本判決には,留置権の効果としての引換給付が債権者と第三者との間でなされる場合の不都合を以下に解決すべきかについての示唆が示されている。すなわち,引換給付判決を受けたXが所有権に基づいてYに目的物の返還請求を実現するためには,BがYに対して,被担保債権を弁済することが条件となる。しかし,BがYに弁済しない場合にはXは,どうすればよいのかが問題となる。判決は,その場合には,XがBに代わって弁済し,その後,Bに求償すればよいこと(代位弁済)を示唆している。
留置権の成立要件である①占有要件,②権原要件,③牽連性要件,④弁済期要件という4つの要素のうち,最も難解とされる③「牽連性要件」について検討を終えたので,最後に,②「権原要件」(これを裏から表現すると,②’「占有が不法行為によって始まったのでないこと」となる)について検討する。
留置権の成立要件のうち,②権原要件は,一方で,③牽連性の要件が満たされた場合でも留置権の成立を否定することができる点で,牽連性要件とも関連している。すなわち,たとえ被担保債権と引渡義務との間に牽連性が認められる場合でも,債権者による占有の取得が正当な原因に基づかない場合には,その牽連性は不正な牽連性として,留置権の成立が否定されるのである。他方で,②権原要件は,以下に述べるように,いったん成立した留置権が,占有の正権原を喪失すると,それに一定の要件(期限の許与の裁判)が加わることによって,留置権の消滅をもたらす[民法299条2項]という点で,消滅要件にも関連するという特色を有している。
留置権の成立に関する4要件のうち,②権原要件を最後に検討するのは,以上の理由に基づいている。
民法295条2項(占有が不法行為によって始まった場合には〔前項の規定を〕適用しない)の意味は,旧民法債権担保編92条が,留置権の成立要件の1つとして,「債権者の占有が正当の原因に因りて…生じたるとき」としていたのを以下の2つの観点から変更したものである[民法理由書(1987)312頁]。
第1は,正当の原因があればよいということであれば,占有の始めは不正の原因によって始まったときでも,その後に正当の原因を取得した場合には留置権が成立するようにも読める。そこで,現行民法は,そのような解釈上の疑義を避けるために,旧民法を修正することにした。そして,占有が「不法行為によって生じた場合には,留置権は成立しない」というように,占有取得の正権原を「裏側から」規定することによって,占有の最初の段階で成立要件を判断できる仕組みを実現したのである。
第2は,旧民法の規定のように成立要件を裏側から規定すると,留置権を否定する側が成立要件が充足していないことを立証しなければならないことになる。このことによって,旧民法の規定の仕方よりも,現行民法の方が,留置権者を保護することになると考えたからである。
さらに,現行民法の起草に当たって参照されたドイツ民法草案[現行ドイツ民法273条2項]が,立証責任を考慮して,「故意の不法行為によってその目的物を取得した場合はこの限りでない」としていたことが,現行民法の起草委員に大きな影響を与えたからであろう(*表34参照)。
| 旧民法 (留置権) |
ドイツ民法 (留置権:給付拒絶の抗弁権) |
現行民法 (留置権) |
|
|---|---|---|---|
| 占有の態様 | 旧民法債権担保編第92条 留置権は,…債権者が既に正当の原因に由りて其債務者の動産又は不動産を占有し,…其占有に牽連して生じたるときは,其占有したる物に付き債権者に属す。 |
ドイツ民法273条2項 ただし,債務者〔留置権者〕が故意に加えた不法行為によってその目的物を取得したときはこの限りでない。 |
民法295条2項 前項の規定は,占有が不法行為によって始まった場合には,適用しない。 |
| 現行民法の立法理由[民法理由書(1987)312頁] | 既成法典〔旧民法〕は,占有の原因を表面より観察して正当の原因に基くことを要すと規定せり。然れども,単に正当の原因に因りて占有すと云ふときは,其始め不正の原因たるも後に至りて正当と為るときは留置権は存立する如く解せしむるに足るべし。之れ本案の避けんとする疑点にして,占有が詐欺の如き不正の原因に因りて始まりたるときは,其後に至り,正当の名義を得るも法律は之に因りて留置権を生ぜしむべきにあらず。故に本案は此主意を明了ならしむる為め,本条第2項に於て,既成法典の正当の原因なる字句を裏面より解して,占有が不法行爲に因りて始まりたるときは,留置権を生ぜしめざることを明かにせり。又既成法典の規定に依れば,留置権者は正当の原因たることを証明せざるべからずと雖も,本条第2項の如くなれば,証明の責任は留置権を攻撃する者に存し,之に因りて,又,権利保護の趣旨に適せしむることを得べし。 | ||
それでは,占有の始めに正当な原因を有していた(占有が不法行為によって生じたのではない)が,その後に正当な原因を失った場合にはどうなるのであろうか。それは,以下に述べるように,抵当権の成立要件の問題ではなく,実は,留置権の消滅要件の問題である。
この問題は,留置権の成立要件と消滅要件とが交錯する重要な論点を含んでいる。そこで,この問題に関してよく引用される昭和46年最高裁判決〈最二判昭46・7・16民集25巻5号749頁〉を取り上げることにする。その理由は,この最高裁判決が,第1に,適用条文を誤るという極めて初歩的なミスを犯しているにもかかわらずリーディングケースのような扱いを受け続けていること,第2に,適用すべき条文の解釈に際しても,安易な先例頼みと安易な類推解釈に陥っており,民法を学ぶ者として,他山の石とすべき判例だからである。したがって,最高裁判決が,なぜ,そのような初歩的なミスを犯しているのか,その原因の解明を含めて,詳しく検討しておくことにする。
Xは「常盤堂」の屋号で本件家屋で菓子の販売および喫茶店を営んでいたが,営業不振となったため,昭和26年12月10日にすし屋営業のA(Yらの先代)に対し本件建物を同月15日以降期限の定めなく賃料1ヶ月5万円,毎月28日翌月分持参払いの約定で賃貸した。
その後XはAの懇請により昭和28年5月分から賃料を1ヶ月4万5,000円に減額したが,Aは同年5月28日に支払うべき6月分の賃料および6月28日に支払うべき7月分の賃料を支払わなかった。Xは6月29日付けの書面で7月2日までに延滞賃料を支払うよう催告したがAはこの支払いをしなかったため,右賃貸借契約はAの賃料債務不履行により解除された(①)。
Yらは,その後,本件建物上に造作を加え,修理費等有益費を支出したとして(②),Xの建物明渡請求(③)に対して,留置権の抗弁を主張した(④)。
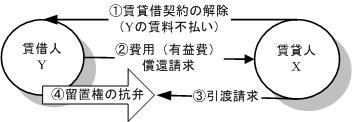 |
| *図73 最二判昭46・7・16民集25巻5号749頁の図解 (賃貸借契約の解除,占有者悪意の場合) 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第80事件 |
原審は,本件の有益費は,契約解除によってAが不法占有者となり,かつこれを知った以降に行った工事の支出費用であるから,「公平の原則により民法295条2項を解釈すると,元来その占有につき正権原のない目的物につき,あらたに留置権を発生せしめる根拠としては是認し得ない」として留置権を否定した。
建物の賃借人が,債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち,権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても,その者は,民法295条2項の類推適用により,右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。
〔①占有の態様〕Aは,本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有していた。
〔②占有が不法行為によって始まった場合に準じるかどうか〕Aが右のような状況のもとに本件建物につき支出した有益費の償還請求権については,民法295条2項の類推適用により,Yらは本件建物につき,右請求権に基づく留置権を主張することができないと解すべきである(最高裁判所昭和39年(オ)第654号同41年3月3日第一小法廷判決,民集20巻3号386頁参照)。
本件の場合,契約を解除された賃借人Xは,有益費を支出したことを理由に留置権を主張しているのであるが,民法299条2項によれば,裁判所は,所有者(Y)の請求により,その〔有益費の〕償還について相当の期限を許与することができる」と規定している。もしも,裁判所が期限を許与することを認めると,履行拒絶の抗弁権は効力を失い,その物の占有を所有者に返還しなければならなくなるので,留置権は消滅する。つまり,正当の原因によって始まった占有がその正当な原因を失った場合には,たとえ,有益費の支出を根拠に留置権を主張しても,民法299条2項により,裁判所が所有者のために期限の許与を認めれば留置権は消滅するのである。つまり,本件の場合,留置権の消滅の問題なのであるから,留置権の成立に関しては,民法295条2項の文言どおりに,「占有が不法行為によって始まった場合」でなければ,特別の事情がない限り,留置権の成立を認めてよいということになるのである(民法295条2項の反対解釈)。
したがって,反対からいえば,民法295条の条文の趣旨に従った解釈(反対解釈)によれば,「占有が不法行為によって始まった場合」でないことが明白な場合には,たとえ,占有の開始後に占有の正権原を失った場合であっても,上記の手続き(期限の許与の手続き)等,消滅原因に該当する事由がない限り,留置権は消滅しないことになるはずである。
それでは,本件のように,「占有が不法行為によって始まった場合」でないことが明白な場合にもかかわらず,すなわち,民法295条2項が適用できないことが明白な場合にもかかわらず,裁判所はどのような考えに基づき,どのような解釈方法に基づいて,民法295条2項を利用(類推適用)することができると判断したのであろうか。これが,本件における最大の問題である。
民法295条の立法理由によれば,民法295条2項は,留置権の成立要件の1つとしての「占有が正当な理由で取得されたこと」を裏側から規定されたものに過ぎない[民法理由書(1987)312頁]。したがって,占有が正当な理由で取得されている場合,すなわち,占有が不法行為によって始まった場合に当たらない場合には,当然に,留置権は成立することになる。
民法の解釈論でいうと,「占有が不法行為によって始まった場合でない」場合には,民法295条2項は適用されないのであるから,原則に戻って,民法295条1項が適用されることになり,原則どおりに留置権が成立することになる(民法295条の文理解釈)。確かに,民法295条2項だけに注目して解釈するとすれば,民法295条の反対解釈ということになる,しかし,正確には,民法295条2項の要件が満たされないため,原則に戻って民法295条1項が適用されると考えるのが正しく,民法295条2項の反対解釈ではないことに注意を要する。
したがって,民法の解釈論の王道から言えば,本件の場合に,民法295条2項の適用の余地はないことになる。しかし,民法295条の立法理由の解釈を別の観点から見ると,民法295条2項の適用の余地が残されている。それは,立法理由の以下の部分[民法理由書(1987)312頁]を違った方向から解釈することである。
〔旧民法のように,〕単に正当の原因に因りて占有すと云ふときは,其始め不正の原因たるも後に至りて正当と爲るときは留置権は存立する如く解せしむるに足るべし。之れ本案の避けんとする疑点にして,占有が詐欺の如き不正の原因に因りて始まりたるときは,其後に至り,正当の名義を得るも法律は之に因りて留置権を生ぜしむべきにあらず。
旧民法が留置権の成立要件として,単に「正当の原因に由りて…占有を生じたるとき」としていたのを現行民法が,「占有が不法行為によって始まった場合」には,留置権は成立しないというように修正したのは,「始めに占有が不正の原因によって取得されたが,後になって正当の原因が備えられた場合」に留置権の成立を否定するだけでなく,「始めに占有が正当の原因によって取得されたが,後になって正当の原因を失った場合」も同様であると解することも不可能ではない。すなわち,留置権における「占有は,始めから終わりまで正当の原因を有するものでなければならない」と解釈するのである。
もしも,そのような解釈が立法理由として認められるのであれば,民法295条2項の文言とは異なり,たとえ,「占有が不法行為によって始まった場合」でないことが明らかである場合でも,「留置権における占有は,常に正当な原因を有していなければならない」という,こじつけ的ではあるが,「立法趣旨」を考慮して,民法295条2項を「類推適用」することが許されるのである。
「占有が不法行為によって始まった場合」に該当しないにもかかわらず,あえて,民法295条2項を適用することを可能にするもう1つの方法は,占有の正当な原因を失った時点をもって占有取得が始まった場合と解釈するという離れ業を使うことである。
本件における最高裁の判決理由が,占有が始まった時点では正当な原因を有していたことには全く触れず,以下のように,いきなり,契約が解除された時点から説き起こしていることからも,最高裁が,この第2の方法を使っていることが推測される。
Aが,本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有していた旨の原判決の認定・判断は,挙示の証拠関係に徴し首肯することができる。
このように考えると,占有が不法行為によって始まったのではないが,賃貸借契約が解除された後についていえば,占有が不法行為によって始まったのと同様であるとして,民法295条2項を類する適用することが可能となりそうである。
本件における法適用の問題は,占有が不法行為によって始まったのではない以上,民法295条2項を反対解釈する(留置権の成立を認める)べきであるのか,それとも,占有が不法行為によって始まったのではないが契約の解除によって占有の正当な原因を失った後に留置権者が有益費を支出した場合には,民法295条2項を類推解釈(留置権の成立を否定する)べきであるのかが争われているように見える。
しかし,そもそも,民法295条2項は,同条1項の成立要件である「占有が正当な原因によって取得されたこと」を裏から規定したものであり,1項のただし書きに該当することが立法理由書によっても明らかにされている。したがって,民法295条2項を独立した条文として考え,その反対解釈とか類推解釈とかを問題にするのは,そもそも誤りであることに注意しなければならない。
本件のように,「占有が不法行為によって始まった場合」に該当しないことが明らかな場合には,民法295条2項は,1項のただし書きの性質を有する以上,厳格に解釈すべきであり,類推を含めて,全く適用の余地はないと考えるべきである。本件の場合は,民法295条2項の反対解釈ではなく,あくまで,原則に戻って,民法295条1項を適用し,留置権の成立を認めた上で,その後の事情の変化を考慮して,留置権の消滅に関する民法299条2項を問題とすべきなのである。
そして,ただし書きは厳密に解釈されることが要求されるとの原則に則り,民法295条2項の解釈においては,安易な類推解釈は避けなければならない。判例が,民法295条2項について,安易な類推解釈をしていることは,この点からも,厳しく批判されるべきである。
したがって,本件は,最高裁判所でさえ,適用条文を誤るという最も初歩的なミスを犯すことがある(民法299条2項を適用すべき問題を民法295条2項を(類推)適用した)という例として,さらには,誤って適用した条文の解釈論としても,類推適用の濫用に陥っているという例として,他山の石となる判決であるといえよう。
現行民法は,旧民法とは異なり,留置権を民法295条~302条に集中して規定し,その他の箇所には留置権を規定しないという方針を採用している。しかし,現行民法においても,民法295条~302条とは異なる箇所に,留置権と同様の権利が点在している。これを,本書では,「隠れた留置権」として,以下に立法理由とともに列挙しておく。
読者は,以下の「隠れた留置権」の規定を読んで,現行民法295条の抽象的な規定が,具体的な場面で,それらを吸収できるものとなっているかどうかを検討してみるとよい。
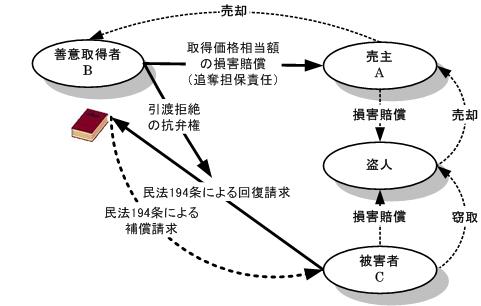 |
| *図74 民法194条における「隠れた留置権」 |
第194条(理由)本条は既成法典証拠編第146条第1項の字句を修正したるに過ぎず。又同条第2項は損害賠償の一般原則に従ふべきものなれば,之を除せり。
旧民法 証拠編 第146条
①盗取せられ又は遺失したる物を競売又は公の市場に於て又は此類の物の商人若くは古物商人より善意にて買受けたる者あるときは所有者は其買受代価を弁償するに非ざれば回復を為すことを得ず
②此場合に於ては右の代価に付き所有者は売主に対し又売主は譲渡人に対して求償権を有し終に盗取者又は拾得者に遡る
民法194条の規定は,通常は,盗品・遺失物に関する民法192条の善意取得の特則であって,留置権に関する規定であるとは考えられていない。しかも,最高裁の平成12年判決〈最三判平12・6・27民集54巻5号1737頁〉が,盗品・遺失物の善意取得者による原所有者に対する「代価の弁償」に関して,大審院以来の抗弁説〈大判昭4・12・11民集8巻923頁〉を捨てて,請求権説を採用したことから,現在においては,民法194条と留置権との関係は,ますます希薄となっている。
しかし,本書の立場からすると,民法194条は,原所有者(C)から善意取得者(B)に対する盗品・遺失物の返還請求に対して,善意取得者(B)が前主である売主(A)に対する追奪担保に基づく請求権(代価の賠償請求権)を保全するため,善意取得者(B)が代価の弁償を受けるまで,盗品・遺失物の返還を拒絶できる抗弁権(留置権)と解することができる。
確かに,善意取得者(B)は,回復を求める原所有者(C)に対して,民法194条に基づいて,取得価格の補償を直接に請求できると解するのが一般的であろう。しかし,民法194条が善意取得者(B)に取得価格の補償を認めた理由は,上記の理由に基づくと考えた方がわかりやすい。なぜなら,善意取得者に対して補償を行うなら,取得価格ではなく,取得価格を限度とする市場価格(時価)と考える方がより説得的だからである。さらに,民法196条の元となった旧民法証拠編146条2項(上記参照)によれば,上の図のように,売主は盗人へ,所有者も盗人へと求償がさかのぼることが規定されており,その前提として,善意取得者(B)から売主(A)への追奪担保責任の存在が前提とされているからである。
代価の弁償について,善意取得者に代価弁償請求権を与えることと,善意取得者に対して,代価の弁償を受けるまで履行拒絶の抗弁権を与えることは矛盾しない。したがって,最高裁が,代価の弁償について,善意取得者の請求権だから抗弁権ではないと判断したことは一面的に過ぎると思われる。なぜなら,民法194条は,善意取得者を保護するために,善意取得者に,前主である売主に対するだけでなく,目的物の回復を求める所有者に対しても,代価弁償請求権を認めるともに,さらに,その請求権の履行を担保するために,引渡拒絶の抗弁権(留置権)をも与えたと解することが可能だからである(詳細については,[加賀山・担保法(2009)210-212頁参照])。
留置権は,引渡し拒絶の抗弁権であり[民法295条],被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物の全部について引渡を拒絶することができる[民法296条]。しかし,占有者として,目的物を善良な管理者の注意をもって管理しなければならないのであって,債務者の承諾を得なければ,留置物を使用し,賃貸し,または担保に供することができない。もしも,留置権者がこれに違反したときは,債務者は,留置権を消滅させることができる[民法298条]。
留置権の効果として,通常は,被担保債権について,事実上の優先弁済権が与えられるに過ぎないが,占有の継続中に占有物から生じる果実については,法律上の優先弁済権を有する[民法297条]。また,留置権者は,通常の占有者[民法196条]と同じく,費用の償還請求権を有し,この権利を確保するためにも留置権が成立する[民法299条]。
このように,留置権は占有を前提としているので,留置権は占有を失うと消滅する([民法302条],もっとも[203条ただし書き]の例外がある)。また,同時履行の抗弁権の場合と異なり,留置権の場合には,例えば,500万円の自動車の修理代金が5万円であるなど,被担保債権の価値が目的物の価格よりも低いことがあるため,債務者は相当の担保を提供して留置権の消滅を請求することができる[民法301条]。
留置権の効力は,他人の物を占有する債権者に対して,その物に関して生じた債権の弁済を確保するために,第1に,債権者にその物に関する引渡拒絶の抗弁権を与えて債務者を心理的に圧迫するとともに,第2に,その引渡拒絶の抗弁権を第三者にも対抗できるものとすることによって,債権者に事実上の優先弁済権を与えているものに他ならない。
留置権の規定は,発生と消滅に関する規定を除いて,効力に関する規定すべてが,質権によって準用されている。反対から言えば,質権の効力と比較して理解することが,留置権の効力を深める上で有用である。この点に関しては,留置権を法定質権と考えることにメリットがある。
留置権の効力は,先にも述べたように,物に関して生じた債権が弁済されるまで物の占有を継続することによって,債務者または債務者から物を譲り受けた第三者に対して心理的圧力を加え,債務の弁済を確保することにある。留置権の効力は,第1に,物の占有を継続できることにあり,これは,物の返還請求に対して,引渡拒絶の抗弁権として現れる。
しかし,この抗弁権は,債務の弁済を確保するために限定されており,債務者や所有者の引渡請求訴訟に対して留置権を認める判決は,原告の敗訴判決ではなく,債務の弁済を条件に引渡請求を認めるという,原告勝訴の引換給付判決である[民事執行法31条1項]。
引換給付判決に基づいて,債務者または所有者が物の引渡を執行するためには,債務額を証明する文書裁判所に提供した後に,はじめて,執行文の付与[民事執行法26条以下]を受けることができるのであって,執行文の付与を受けてから強制執行が開始されるまでの間に債務額を証明する文書を裁判所に提供すればよいというものではない。
つまり,債権者が物の引渡の執行をする場合に,債務者が留置権の抗弁を主張した場合には,債権者は,まず,反対給付の債務額を証明する文書を提出して,執行文付与を受けることができる。債権者は,次に,執行機関(執行官)に対して,執行の申し立てを行うことになるが,その際に,債権者は,引換給付判決で命じられた反対給付の弁済の提供をしなければならない。これを執行機関が確認することによって,民事執行法31条1項の執行開始要件が満たされたことになり,実際の執行が行われることになるのである。
民法300条は,「留置権の行使は,債権の消滅時効の進行を妨げない」と規定しているが,この意味は,留置権の行使,すなわち,単に物を留置しているだけでは,債権の消滅時効は中断しないという意味に解すべきである。
これに反して,訴訟における留置権の主張,すなわち,引渡拒絶の抗弁権の行使は,引換給付判決へと帰結することからも明らかなように,反対給付を求める主張(催告)が潜在的に含まれていると解すべきである。したがって,留置権の効力の第2として,留置権の訴訟上の行使は,債権の時効を中断する効力を有する〈最大判昭38・10・30民集17巻9号1252頁〉。
物に関する双務契約において,代金・報酬・費用償還請求権と物の引渡請求権とが対立している場面では,留置権と同時履行の抗弁権の要件がともに満たされるという事態が発生する。そして,この場合には,留置権の引渡拒絶の抗弁と同時履行の抗弁とが競合すると考えるべきである。
しかし,留置権と同時履行の抗弁権が同時に発生する場合でも,目的物が第三者に譲渡された場合には,同時履行の抗弁権は,原則として,第三者には主張できないと解されており,留置権の主張のみが認められる。さらに,同時履行の抗弁権は,双務契約,または,これと類似する関係が生じている場合にのみ発生するのであり,迷い犬・猫の飼育や,飛び込んできたボールやトラックの事例のように,事務管理や不法行為に関して留置権が発生する場合には,同時履行の抗弁権は発生しない。
これとは逆に,請負人の注文者に対する報酬請求権と注文者の請負人に対する損害賠償請求権とは,同時履行の関係にあり[民法634条2項],この同時履行の関係は,請負の目的物が注文者に引き渡された後も存在する。しかし,留置権の方は,請負の目的物が注文者に引き渡された後は,請負人は,占有を失っており,もはや留置権を行使することができない。
質権については,民法342条が「物を占有し,かつ,その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と規定しているのに対して,留置権については,民法295条が,「債権の弁済を受けるまで,その物を留置することができる」と規定しているに過ぎない。
したがって,法定質権としての留置権と質権との効力の差異は,質権が留置的効力と同時に競売代金に対する優先弁済権が確保されているのに対して,留置権は,留置的効力のみで,留置権者が自ら競売を望んだ場合,競売代金に対する優先弁済権が認められていない点にある。
もっとも,留置的効力による事実上の優先的効力は,債権者が占有を失うと優先的効力を失うため,いわゆる追及効は存在しないが,占有を継続している以上は,目的物の所有権が譲渡されても,誰に対しても,事実上の優先弁済権を主張しうる非常に強力なものである。
しかも,留置権の留置的効力は,民事執行法により十分に保障されている。なぜなら,他の債権者が競売を申し立てた場合,不動産の競売については,競売の買受人は,留置権の目的となっている債権をまず弁済しなければならないし[民事執行法188条,59条4項],動産の競売については,留置権者の同意なしには競売自体が開始できないことになっている[民事執行法124条,190条]からである。
しかし,留置権者が競売を望んだ場合[民事執行法195条]には,換価金に対する優先弁済権は認められておらず,一般債権者として平等の割合で配当を受けることになっている。この点に,本来の優先弁済権と留置的効力による事実上の優先弁済権との差があるといえよう。さらに,留置権の場合は,本来の優先弁済権が認められていないため,優先弁済権を前提とする物上代位も認められない。
もっとも,留置権の場合も,次に述べるように,留置する物から生じる果実に関しては,果実を収取して,そこから優先的に債権の弁済に充当するという,本来の意味の優先弁済権が認められている[民法297条]。
不可分性とは,担保物権をもつ者は,被担保債権の全部の弁済があるまで,その目的物の全部について権利を行使しうるという性質をいう。この不可分性により,被担保債権の一部が弁済等によって消滅しても,その残額がある限り,担保物全部の上に担保物権の効力が及ぶ。元本の全部が弁済されたが,利息・損害金が残っているという場合でも同じである。
さらに,判例〈最三判平3・7・16民集45巻6号1101頁〉は,土地の宅地造成工事を請け負った債権者が造成工事の完了した土地部分を順次債務者に引き渡した場合につき,債権者が右引渡しに伴い宅地造成工事代金の一部につき留置権による担保を失うことを承認した等の特段の事情がない限り,債権者は,宅地造成工事残代金の全額の支払を受けるに至るまで,残余の土地につきその留置権を行使することができるとしており,不可分性の意味が拡張されている。
留置権の箇所で規定されている不可分性[民法296条]は,他の担保物権にも共通の性質であるため,先取特権「民法305条],質権[民法350条],抵当権[民法372条]のそれぞれの箇所で準用されている。ただし,共同抵当の場合には,各不動産の負担額が限定されるなど[民法392条],不可分性に対する例外が規定されている。
留置権の場合,留置物本体については,質権とは異なり,これを換価・処分してそこから他の債権者に先立って優先弁済を受けるという効力は認められていない。しかし,留置権も,留置する物から生じる果実に関しては,果実を収取して,そこから優先的に債権の弁済に充当するという,本来の意味の優先弁済権が認められている[民法297条]。
ところで,占有理論によれば,他人の物の占有者は,善意の場合は,占有物から生じる果実を取得することができるが[民法189条],悪意の場合は,悪意の不当利得の場合[民法704条]と同様,収取した果実を返還し,消費した果実の代価を償還しなければならない[民法190条]。
留置権者の場合,占有は適法に始まったとはいえ,他人の物を悪意で占有しているわけであるから,本来なら,果実を収取する権利を有しないはずである。しかし,民法は,他人の物の悪意の占有者である留置権者に占有物につき善管注意義務を負わせる[民法298条]ことによって,バランスをとっているのである。
他人の物の占有を適法に開始した占有者が,占有物に必要費または有益費を投じ,費用償還請求権が発生した場合には,民法295条に基づいて,その費用償還請求権者に留置権が発生する。そして,すでに留置権を有する債権者が,留置物の保存・改良のために費用を投じると,民法299条によって,その費用償還請求権のために,さらに留置権が発生する。民法295条と民法299条を対比した場合,留置権の発生を判断するだけならば,民法295条さえあれば,民法299条の規定は,不必要ではないかと思われるかもしれない。
しかし,留置権者は適法に他人の物の占有を開始したといっても,占有については悪意の場合もあるし(悪意の占有者の費用償還請求権に対しては,所有者の請求によって期限の許与が認められている),留置権者は,民法297条により,占有物から生じる果実を収取してそこから優先弁済を得ることができることになっている(占有の規定によれば,果実を収取した占有者に対する費用償還請求権は否定されている)。他方で,留置権者は,占有物の保管について善管注意義務を負わされ,しかも,債務者の承諾なしに,占有物を使用・賃貸・担保提供することを禁じられているという,かなり微妙な立場に置かれている。
このような状況のもとで,留置権者が,留置物に対して保存費用や改良費用を出した場合に,そもそも,費用償還請求権が発生するのかどうか([民法196条1項ただし書]は,果実を収取した占有者に対する費用償還請求権を否定する),費用償還請求に対して期限を許与することが許されるのかどうか([民法196条2項ただし書]は,悪意の占有者の費用償還請求権に対して期限の許与を認めている)という問題を解決しておく必要がある。
民法299条は,留置権者のおかれた微妙な立場に対して,単なる他人の物の占有者の場合における費用償還請求権の場合とは異なる解決を与えようとするものである。
留置権者の費用償還請求権の規定[民法299条]と,一般的な占有者の費用償還請求権の規定[民法196条]とを注意深く対比することによって,留置権が単なる占有権とは異なり,債権の担保のための占有であることが明らかになるであろう。
| 留置権者の言い分 | 債務者・所有者の言い分 | 民法の規定 | |
|---|---|---|---|
| 必要費償還請求権 | 留置権者は,管理について善管注意義務を課せられる一方で,使用・賃貸・担保供与の自由が与えられていない[民法298条2項]のであるから,必要費の償還請求が認められるべきである。 | 留置権者は果実収取権を有するのであるから,占有の一般原則である民法196条1項ただし書き(占有者が果実を取得したときは,通常の必要費は占有者の負担に帰する)の規定に従って,必要費償還請求権は否定されるべきである。 | 民法299条1項 ①留置権者は,留置物について必要費を支出したときは,所有者にその償還をさせることができる。 |
| 有益費償還請求権 | 占有者には,一般的に,有益費の償還請求権が認められているのであるから[民法196条2項],留置権の場合にも,有益費の償還請求権が認められるべきである。 善意占有者の場合には,有益費の償還請求権につき期限の許与が認められないのであるから,留置権の場合にも,期限の許与は認めるべきではない。 |
悪意の占有者に対しては,有益費の償還請求権につき期限の許与が認められている[民法196条2項ただし書き)。 また,契約関係がある場合には,有償・無償の区別を問わず[民法583条2項,595条2項,608条2項],期限の許与が認められているのであるから,留置権の場合にも,期限の許与が認められるべきである。 |
民法299条2項 ②留置権者は,留置物について有益費を支出したときは,これによる価格の増加が現存する場合に限り,所有者の選択に従い,その支出した金額又は増価額を償還させることができる。 ただし,裁判所は,所有者の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる。 |
留置権者が留置物について必要費を出したときは,所有者にその償還を請求できる[民法299条1項]。留置権者の必要費償還請求権は,物の占有に関して生じた債権であるため,この債権に基づく目的物の留置権も認められる。
ところで,占有の規定によれば,他人の物の占有者がその物の保存のために必要費を支出した場合には,その償還を請求できるのが原則である[民法196条1項本文]から,留置権者の必要費償還請求権は,一般原則の適用に過ぎないようにもみえる。
しかし,占有の規定では,占有者が果実を取得する場合には,通常の必要費は占有者が負担することになっている[民法196条1項ただし書き]。そして,留置権者の場合,果実を収取して優先弁済を受けることができる[民法297条1項]のであるから,占有理論に従えば,留置権者は,必要費の償還は請求できないはずである。
それにもかかわらず,留置権者に必要費償還請求権が認められている理由は,留置権者は,留置物の管理について善管注意義務を負わされ,かつ,債務者の承諾なしに留置物を使用し,賃貸し,担保に供することが禁止されており,賃料収入などの果実収取の機会が大幅に減じられていることの配慮であると思われる。
これに対して,以下に述べる有益費の償還請求権については,必要費の場合とは異なり,有益費の額は,果実収取権では賄えない額になることが多いため,果実収取とは関係なしに償還請求権が認められている。ただし,有益費の償還請求権については,権利そのものは認められても,以下に述べるように,その権利を確保するための留置権の主張は制限されているので注意を要する。
留置権者が留置物について有益費を出したときは,その価格の増加が現存する場合に限って,所有者の選択に従い,その費やした金額または増価額の償還を請求できる[民法299条2項本文]。
留置権者の有益費償還請求権は,物の占有に関して生じた債権であるため,この債権に基づく目的物の留置権も認められる。しかし,必要費の場合とは異なり,有益費の償還請求の場合には,裁判所は,所有者の請求によって相当の期限を許与しうる[民法299条2項ただし書き]ので,その場合には,留置権は発生しない。
ところで,占有の規定によれば,他人の物の占有者がその物の改良のために有益費を支出した場合には,その価格の増加が現存する場合に限って,所有者の選択に従い,その費やした金額または増価額の償還を請求できるのが原則である[民法196条2項本文]から,留置権者の有益費償還請求権は,一般原則の適用に過ぎないようにもみえる。
しかし,占有の規定では,占有者が善意の場合と悪意の場合とを区別し,悪意の場合に限って,裁判所は,所有者の請求によって相当の期限を許与しうると規定している[民法196条2項ただし書き]。留置権者の場合,占有は適法に始まっているとはいえ,悪意占有であるから,占有の規定では,悪意占有者にのみ認められている期限の許与の制度が,留置権の場合には,一律に取り入れられたものと思われる。
民法299条が,必要費の償還請求の場合は常に留置権を認める一方で,有益費の償還請求に関しては,留置権の存否を裁判所の判断に委ねた理由は,有益費は必要費に比して高額に上る場合があること,および,留置権の保管を簡素なものに抑えようとする民法298条の趣旨を考慮して,裁判所が所有者に有益費の償還につき期限を許与することが望ましいと判断する場合には,留置権を認めないことができるようにしておき,裁判官の総合判断によって結果の具体的妥当性を確保することを狙ったためである。
留置権の消滅原因として,従来の学説は,第1に,物権に共通の消滅原因として,目的物の滅失・混同・放棄等を挙げ,第2に,担保物権に共通の消滅原因として,付従性から導かれる被担保債権の消滅(弁済,代物弁済,相殺,免除,混同,消滅時効,契約の解除等)を挙げ,第3に,留置権固有の消滅原因として,留置権の消滅請求[民法298条3項],代担保の供与による消滅[民法301条],占有の喪失[民法302条本文]を挙げてきた。
しかし,留置権は,正当な原因によって他人の物の占有を開始した債権者に対し,その物を留置することによって事実上の優先弁済権を与える制度であるとの本書の立場に立てば,留置権の消滅原因は,物権とか付従性を持ち出すまでもなく,第1に,担保物権に共通の債権そのものの消滅,第2に,留置権と質権に共通の消滅原因,第3に,留置権に固有の消滅原因という3種類の原因によって説明することができる。
ここでは,第1の債権そのものの消滅原因(弁済,代物弁済,相殺,免除,混同,消滅時効,契約の解除等)は担保物権すべてに共通する問題であるので省略することとし,第2の留置権と質権に共通の消滅原因,すなわち,債権者の義務違反に対する債務者側からの留置権の消滅請求[民法298条3項],第3の留置権に固有の消滅原因,すなわち,事実上の優先弁済権を裏付けている占有の喪失[民法302条本文]および債務者側からの代担保の供与による消滅[民法301条]を取り上げることにする(なお,民法299条の期限の許与による留置権の消滅については,すでに説明したので,ここでは省略する)。
| 留置権の消滅原因 | 条文 | ||
|---|---|---|---|
| 留置権・質権に共通の消滅原因 | 留置権の消滅請求 | 第298条(留置権者による留置物の保管等) ①留置権者は,善良な管理者の注意をもって,留置物を占有しなければならない。 ②留置権者は,債務者の承諾を得なければ,留置物を使用し,賃貸し,又は担保に供することができない。ただし,その物の保存に必要な使用をすることは,この限りでない。 ③留置権者が前2項の規定に違反したときは,債務者は,留置権の消滅を請求することができる。 |
|
| いわゆる留置権に固有の消滅原因 | 動産質の場合と類似の消滅原因 | 占有の喪失 | 第302条(占有の喪失による留置権の消滅) 留置権は,留置権者が留置物の占有を失うことによって,消滅する。 ただし,第298条第2項〔債務者の承諾を得た留置物の使用・賃貸・担保供与〕の規定により留置物を賃貸し,又は質権の目的としたときは,この限りでない |
| 留置権に固有の消滅原因 | 代担保の供与による消滅 | 第301条(担保の供与による留置権の消滅) 債務者は,相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる。 |
|
| 債務者の破産 | 破産法66条(留置権の取扱い),186条(担保権の消滅の許可の申立て),192条(商事留置権の消滅請求) | ||
| 会社更生 | 会社更生法29条(商事留置権の消滅請求) | ||
留置権は,他人の物を占有することを許す権利である。そして,民法は,他人の物を有償(留置権者は果実収取権を有している)で占有する者の一般原則に従い,「善良な管理者の注意をもって,留置物を占有しなければならない」という善管注意義務を課している[民法298条1項]。
上記の注意義務の結果として,留置権者は,債務者と所有者の承諾なしに留置物を使用し,賃貸し,担保に供することはできない。もっとも,使用に関しては,保存に必要な使用は認められている[民法298条2項]。
例えば,借家人が修繕費の償還請求権の担保のために,借家契約終了後,借家を留置する場合に,従来通り居住を継続することについて,当初の判例は,借家人が居住を継続することは,留置物の「使用」にあたり,家主の同意がないときは許されないとして,家主の留置権消滅請求を認めた〈大判昭5・9・30新聞3195号14頁〉。しかし,その後,見解を変更し,借家人の居住は,留置物の保存にあたり,家主の承諾なしになしうるとしている〈大判昭10・5・13民集14巻876頁〉。
留置権者が善管注意義務に違反した場合[民法298条1項]または留置物を無断で,保存目的以外の使用をしたり,留置物を賃貸したり,担保に供したりした場合には[民法298条2項],その制裁として,債務者および所有者は,留置権の消滅を請求できる[民法298条3項]。
例えば,判例は,借地の場合に関して,地上の建物を第三者に賃貸することは,保存に必要な使用ではないとして,留置権の消滅請求を認めている〈大判昭10・12・24新聞3939号17頁〉。また,船舶上の留置権に関して,貨物の運送業務のため,遠距離(和歌山から山口あたりまで)を航行したことは航行の危険性に鑑み,留置物の保存に必要な使用とはいえないとして,船舶所有者の留置権消滅請求を認めている〈最二判昭30・3・4民集9巻3号229頁〉。
最二判昭30・3・4民集9巻3号229頁
木造帆船の買主が,売買契約解除前支出した修繕費の償還請求権につき右船を留置する場合において,これを遠方に航行せしめて運送業務のため使用することは,たとえ解除前と同一の使用状態を継続するにすぎないとしても,留置物の保存に必要な使用をなすものとはいえない。
留置権の消滅請求は,形成権と考えられており,留置権者の違反行為が継続しているかどうか,違反行為によって損害を受けたかどうかを問わず〈最二判昭38・5・31民集17巻4号570頁〉,上記の違反行為があれば,債務者または所有者の意思表示によって,留置権は当然に消滅する[民法298条3項]。
最二判昭38・5・31民集17巻4号570頁
留置権者が民法298条1項および2項の規定に違反したときは,当該留置物の所有者は,当該違反行為が終了したかどうか,またこれによって損害を受けたかどうかを問わず,当該留置権の消滅を請求することができるものと解するのが相当である。
留置権は,占有の喪失によって消滅する[民法302条本文]。留置権は占有を通じて事実上の優先弁済権を確保する制度であり,占有によってその効力が発生し,占有の喪失によって消滅することとしているのである。
(α) 占有回収の訴えによって占有を回復した場合 留置権が占有を効力要件とする以上,留置権者が占有自身の保護機能としての占有訴権を利用することは当然に許されている。したがって,占有回収の訴えによって占有を回復した場合には,留置権も回復すると解されている。その理由は,民法203条により,占有者が占有回収の訴えを提起したときは占有権は消滅しないと規定されているからである。
(β) 間接占有 留置権の効力要件としての占有は,間接占有でもよいとされる。留置権者が,債務者および所有者の承諾を得て,留置物を「賃貸し又は質権の目的としたときは」,直接占有は喪失するが,間接占有は保持するため,留置権は消滅しないとされている[民法302条ただし書き]のがその理由である。
もちろん,債務者および所有者の承諾を得ずに留置物を「賃貸し,又は担保に供」した場合には,民法298条3項による留置権の消滅請求によって消滅することはあるが,承諾を得ずに留置物を「賃貸し又は質権の目的とした」からといって,当然に留置権が消滅することはない。ただし,留置権者が債務者や所有者に留置物を返還した後,占有改定によって占有した場合には,動産質の場合と同様に考えて([民法344条]参照),留置権は消滅するとする学説がある。確かに,約定担保権である質権の場合には,当事者の意思が意味を持ちうるかもしれない。しかし,法定担保権である留置権の場合には,「正当の原因」によって占有が継続されているかどうかで判断すればよく,その占有に間接占有が含まれるとするのであれば,たとえ留置物を返還しても,占有改定によって占有が継続している以上,留置権は消滅しないと考えるべきであろう。
債務者または留置物の所有者は,留置物の代りに「相当の担保を供して,留置権の消滅を請求することができる」[民法301条]。留置権の場合,すでに述べたように,債権額と留置物の価格が均衡していることは要件とされていないので,債権額に比較して留置されている物の価格が著しく大きい場合に,この制度の意義があるとされている。
しかし,債権額に比較して物の価格が著しく大きい場合というのは,反対からいえば,債権額が著しく小さい場合であるから,債務者または留置物の所有者は,著しく小さい債権額を弁済することによって,債務を消滅させ,いわゆる付従性の原則により,留置権を消滅させることができる。したがって,この場合の実益は,理論上ほど大きくはないと思われる。
むしろ,この制度は,債権額と留置物の価格が均衡し,かつ,債権額が大きい場合に,留置物に代わる代担保を提供することによって留置権を消滅させることができる点に実益がある。例えば,債務者には,留置物と同等の価値をもつ手持ちの物件があるが,それが,すぐには換価できない状態にあり,かつ,債権額を支払うだけの金銭的余裕もないといった場合に,手持ちの物件を代担保にして留置権を消滅させることができれば,債務者にとって利益が大きいといえよう。
通説([富井・物権下(1929)33頁],[柚木=高木・担保物権(1973)38頁],[高木・担保物権(2005)30頁],[近江・担保物権(1992)32頁])は,代担保の提供には,留置権者の承諾を要するとしているが,この代担保提供による留置権の消滅請求権は,民法298条3項の留置権の消滅請求の場合と同様,形成権と考えるべきであり,代担保が相当であるとの要件を備えていれば,留置権者の承諾は不要であると解すべきである([我妻・担保物権(1968)46-47頁],[鈴木・物権法(1994)293頁])。
債務者の破産に際しては,商事留置権(商法又は会社法の規定による留置権)が「特別の先取特権(ただし,その順位は,一般先取特権には優先するが,民法その他の法律の規定による他の他の特別の先取特権に劣後する)」とみなされ[破産法66条1項],その結果,別除権をも有する(破産法65条]のとは異なり,留置権は,破産財団に対し対抗することができない[破産法66条3項]。民事再生の場合も同様である[民事再生法53条1項]。また,会社更生の場合にも,商事留置権が「更生担保権」として扱われるのとは異なり,民法上の留置権は更生担保権として扱われていない(会社更生法2条10項参照)。
したがって,民法上の留置権については,債務者の破産,民事再生,会社更生によって,事実上の優先弁済権も否定されるに至るため,留置権は消滅すると解さざるをえない。つまり,この場合には,留置権は,一般債権者の債権と同じ扱いを受けることになる。
一定の債権(例えば,雇用関係から生じる債権)について,その性質(例えば,労働者の生活基盤の維持)を考慮して,その債権を特別に保護すること,すなわち,「他の債権者に先立って弁済を受けるに値する」と判断されることがある。そして,その場合には自動的に,当事者間の合意も公示も必要とせずに,当該債権に優先弁済権が与えられる。これが先取特権[民法303条]の制度である。
先取特権は,①被担保債権,②目的物,③優先順位の3つの要素から成り立っている。①被担保債権は先取特権の名称(共益費用の先取特権,不動産賃貸の先取特権,不動産保存の先取特権など)に表れており,②目的物は,先取特権の種類(一般先取特権,動産先取特権,不動産先取特権)に表れている。また,③優先弁済の順位は,民法329条以下に規定されているが,先取特権が規定されている条文の順序にほぼ従っている。先取特権を理解するには,以上の3要素(被担保債権,担保目的物,優先順位)を確実に理解することが必要である。
なお,先取特権の優先順位の与え方については,民法330条がそのエッセンスを規定している。保存については,「後の保存者が前の保存者に優先する」というルールが特に重要である。債務者に目的物が導入される場合,その順序は,①目的物の供給(売買),②目的物の保存(修理)となるのが通常であるが,先取特権の順序は,その逆をたどることになる。動産先取特権の場合に,動産売買の先取特権よりも動産保存の先取特権が優先するのも,また,不動産保存の先取特権が,不動産工事の先取特権,不動産売買の先取特権よりも優先するのは,「後の保存者が前の保存者に優先する」というルールの適用に他ならないことを理解することが重要である。
先取特権は,優先弁済権そのものである。現行民法においては,法律上の優先弁済権は,法定の物的担保では先取特権だけに,約定の物的担保では質権と抵当権の両者に与えられている。優先弁済権とは,債権者平等の原則の例外として,特定の債権者に与えられた権限である。優先弁済権を有する債権者は,目的物を「担保権の実行としての競売」[民事執行法180条-195条]に付し,競売で得られた配当金から,他の債権者に先立って優先弁済を受けることができる。
優先弁済権の本質,優先順位の確定に関する原則,他の優先弁済権との調整方法等,優先弁済権にまつわる複雑な法理を理解するには,優先弁済権そのものである先取特権の規定を理解することから始めるのがよい。そして,先取特権のさまざまな規定の裏に隠された原理を知るためには,民法の立法理由にさかのぼって,それぞれの条文を導いた原理をマスターする必要がある。
物的担保を理解する上で,なぜ先取特権が最も重要な役割を果たしているかというと,それは,以下の3つの理由(①目的物の豊富さ,②被担保債権の性質への考慮,③優先順位決定のルール)に基づいている。
第1に,先取特権における優先弁済権は目的物(対象)の種類が豊富だということである。先取特権には,一般先取特権,動産先取特権,不動産先取特権というように,豊富な種類が用意されている。民法以外の特別法で規定されている先取特権は,後に(*1D(c))で述べるように,現在では200以上に増加している。物権の対象は,原則として有体物(動産,不動産)に限定されるはずであるが[民法85条],先取特権の対象は,有体物としての動産(動産先取特権),不動産(不動産先取特権)から,無体物としての債権([民法304条]における売買代金債権,賃料債権,損害賠償債権,[民法314条]における売買代金債権,転借料債権),債務者の全財産(一般先取特権)に至るまで,あらゆる種類の目的物を対象とすることができる。したがって,先取特権の目的物を理解すると物的担保の対象についての理解を深めることができる。
第2に,先取特権においては,被担保債権の性質(特別の保護に値するかどうか)および機能(目的物の価値の維持にいかに貢献しているか)が優先順位の決定に大きな役割を果たしている。その他の物的担保の場合には,被担保債権の性質・機能は優先弁済権の順位に影響を及ぼさないのが原則であるが,先取特権の場合には,抵当権,質権に遅れて設定されても,それらに優先するもの(不動産保存の先取特権[民法339条])から,同順位となるもの(動産質権は,第1順位の先取特権とみなされる[民法334条]),それらに劣後するもの(一般先取特権[民法329条,335条,336条])まで,さまざまな優先弁済権が優先順位とともに規定されている。
第3に,その優先順位の決定ルールが,必ずしも登記の先後とか,契約の先後とか,保存の先後によるわけではないということである。例えば,保存については,後に保存した者が先に保存した者に優先するなど[民法330条1項2文),物権の優先順位とは,まるで無関係,むしろ,正反対の順位決定のルールが出現する。このようなルールについて精通するようになると,従来の学説が解決に難渋している,譲渡担保と動産売買の先取特権との優先順位の基準(*第14章第4節(動産売買の先取特権と集合物譲渡担保との競合)で説明する),抵当権に基づく物上代位と相殺権者との優先順位の基準(*第16章第5節E(c)(iv)(物上代位の対象となる賃料債権に対する賃借人による相殺)で説明する),さらには,非典型担保としての譲渡担保に物上代位が類推されるかどうかという問題(*第20章第1節C(典型担保権の規定の類推適用))等についても,明確な基準を提示できるようになる。
先取特権とは,法律の定める特別の債権をもつ者が,債務者の総財産あるいは特定の動産・不動産から,「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」(優先弁済権)のことをいう[民法303条]。
たとえば,社会政策上,特別の保護に値する給料または雇用関係から生じたその他の債権(労働災害に基づく損害賠償債権,退職金債権,年金債権など)を有する使用人(労働者)は,債務者である雇い主(使用者)の総財産(一般財産・責任財産)から,他の債権者に先立って優先的に弁済を受ける権利を有している[民法306条2号,308条]。
先取特権は,フランス法起源の制度であり,ドイツにはこの制度がないために,これまで,理論的な研究が手薄の状況にあった。そのため,後に詳しく論じるように,一部の研究者からは,先取特権の廃止論まで提案されるに至っている[椿他・民法改正を考える(2008)140頁]。しかし,このような提案は,時代に逆行しており,後に詳しく述べるように,採用されるべきではない[椿他・民法改正を考える(2008)145頁]。なぜなら,わが国においては,特別法を含めた先取特権の数は,時代が進むにつれて,質・量ともに,ますます増加する傾向にあるからである(詳しい理由は,*1Dで述べる)。特に,特別法上の先取特権は,行財政改革の進展にともなう独立行政法人の信用を確保するために,近年になって急激に増加しており,先取特権の研究も,むしろ,その必要性が増大しているといえる。
先取特権,特に,一般先取特権が研究者や法曹実務家から嫌われるもう1つの理由は,先取特権の中でも特に一般先取特権については,それを物権として説明することができないからである。それもそのはずで,民法の起草者(梅謙次郎)は,すべての一般先取特権ばかりでなく,物上代位,動産先取特権の一部(不動産賃貸の先取特権の一部について,それらが物権ではないことを明らかにしていた[梅・要義巻二(1896)285頁]。
〔民法〕第304条〔物上代位〕,第306条乃至第310条〔一般の先取特権〕,第314条〔2文(賃料・転借賃料債権に対する先取特権)〕及び〔旧〕第320条〔公吏保証金の先取特権(2002年の現代語化に際して削除された)〕の場合においては,先取特権は債権,其他有体物以外の物の上に存することあり。此場合に於いては,先取特権は物権に非ず。
一部の先取特権(一般先取特権および債権先取特権)についてではあるが,以上のように,民法の起草者によって,「先取特権は物権ではない」と宣言されているのであるから,担保物権を物権として体系化しようとしているわが国のほとんどすべての学者にとって,先取特権が「嫌われもの」となる理由も,なんとなく見えてくる(ここでも研究者・法曹の姿勢が学生の先取特権嫌いを助長している)。
確かに,従来の学説は,優先弁済権を債権者平等原則に反するものとして,物権における目的物の換価・処分権能の一つとして説明してきた。昭和54(1979)年に廃止された競売法(明治31年法15)は,まさに,この考え方に基づいており,担保物権の換価機能に基づく競売を強制執行とは別のものとして,すなわち,債務名義を前提とせず,かつ,差押えを要しないとするなど,特別のものとして規定していた。しかし,現行の民事執行法では,通常の強制執行と担保権の実行としての競売(担保執行)とは,同一の法律の中で規定され,担保権の実行には,強制執行の規定が広く準用されるにいたっている。さらに,手続き法の中でも,会社更生法に至ると,物的担保は,更生債権として,優先権のある「債権」としての扱いがなされており,現在においては,優先弁済権を物権として構成する必然性は,手続法との関係でも,次第に失われつつあるといえよう。
通説は,優先弁済権を物権の換価機能として説明しようとする。しかし,物権の換価権能といっても,つまるところ,所有者である債務者が債務不履行に陥った場合にしかその権能が認められないというのであれば,物権ではなく債権の側面から説明する方が説得的であろう。そして,第1に,特別に保護すべき債権には,債権者平等の原則を排除して他の債権者に優先して弁済を受ける権利が与えられる(法定担保権としての先取特権),第2に,債権者と債務者との間の合意と公示(占有の継続,債務者に対する通知・債務者の承諾,登記・登録等)がなされた場合には,その債権者に優先弁済権が与えられる(約定担保権としての質権,抵当権)というように理解するならば,他の債権者に先立って弁済を受ける権利としての優先弁済権の意味をより深く理解することが可能となる。
そこで,この章では,特定の債権者に先取特権が付与される理由にはどのようなものがあり,その理由はどのように分類できるのか,特に,その理由が先取特権の順位をどのように左右するのかを検討することを通じて,物的担保(いわゆる担保物権)の本質に迫ることにする。このような探求によってこそ,先取特権に対する偏見(軽視・嫌悪)が解消されることになると思われる。
優先弁済権を物権の換価機能であると学んだ人の中には,物権の排他性と優先弁済権とを混同し,競売後の配当計算を苦手とする者が多い。そこで,以下では,先取特権が問題となる典型的な事例を挙げることによって,法律上の優先弁済権とは何かを理解するための検討を行うことにする(不動産に備え付けられた動産の例としては,賃借人が自らの費用で設置したエアコンの方がわかりやすいかもしれないが,ここでは,便宜上,借家人がアパートに設置したパソコンセットの例を採用している)。
|
【設例】Aは,Bのアパートに下宿しており,1年前に50万円で大型のスクリーンを備えたパソコンと周辺機器(パソコンセットという)をC電気店から購入した。しかし,生活費を親の仕送りに頼っていて金銭的な余裕はなく,購入代金のうち,頭金以外の残代金20万円の支払を待ってもらっている。その上,保証期間が切れた直後にハードディスクが故障してしまい,D修理業者に出張修理してもらった修理代金5万円をまだ支払っていない。また,分をわきまえない派手な生活のため,貸金業者Eに25万円の借金があり,家賃も2カ月分10万円を滞納している。とうとうAは,債権者たちにパソコンセットを差し押さえられてしまった。 【問題】パソコンセットが30万円で競売された場合,Aの債権者はどのような割合で配当を受けうるか。ただし,訴訟費用,配当表等の作成費用は無視するものとする。 |
 |
| *図75 先取特権相互間の優先関係 |
パソコンセットが30万円で競売された場合,もしも,先取特権の制度がないと仮定した場合には,債権者は債権額に応じて平等に配当を受けることができる。したがって,各債権者の配当額は,次の表のように比例配分されるはずである。
| 債権額 | 按分比 | 配当額 | |
|---|---|---|---|
| B(賃貸人) | 10万円 | 10/60 | 5万円 |
| C(修理業者) | 20万円 | 20/60 | 10万円 |
| D(売主) | 5万円 | 5/60 | 2.5万円 |
| E(貸金業者) | 25万円 | 25/60 | 12.5万円 |
ところが,先取特権が存在する場合は,原則として,債権額に従った比例配分ではなく,優先順位に従った配当がなされる。同一目的物につき同一順位の先取特権者が複数存在するときにのみ,例外的に比例配分(按分比例)がおこなわれるに過ぎない[民法332条]。
先取特権の順位は,民法329条から332条の4ヵ条に規定された原則によって決定される。その原則を理解するためには,先取特権の規定が債権を責任財産との関係でどのように分類しているかを知る必要がある。
先取特権は,まず,一般財産を責任財産とする一般先取特権と特定財産を責任財産とする特別先取特権とに分類される。そして,次に,特別先取特権は,動産を責任財産とする動産先取特権と不動産を責任財産とする不動産先取特権とに分類されている。そして,先取特権の順位は,それぞれの先取特権ごとに順位がつけられている(一般先取特権,動産先取特権,不動産先取特権の順位表を自作してみるとよい)。
先取特権の順位は,債権の種類に応じて決定されているので,設例の場合の先取特権の順位を知るためには,各債権者がAに対してどのような種類の債権を有しているのかを確認しなければならない。
そこで,B,C,D,Eが,それぞれ,どのような債権を有しているかをチェックしてみると,以下のようになる。読者も,答えを見る前に,六法を見ながら,?の箇所に用語と順位を書き込んでみるとよい。
| 債権の種類 | 目的物 | 先取特権の種類 | 優先順位 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 借家の賃料債権 | 借家に持ち込まれたパソコンセット | ? | ? |
| C | 動産売買の代金債権 | 売却したパソコンセット | ? | ? |
| D | 動産保存の報酬債権 | 修理したパソコンセット | ? | ? |
| E | 貸金債権(一般債権) | 一般財産 | ? | ? |
これらの債権について,目的物であるパソコンセットとの関係でどのような先取特権が存在し,その順位がどうなっているのかを,民法330条に基づいて検討すると,次の表のようにまとめることができる。
| 債権の種類 | 目的物 | 先取特権の種類 | 優先順位 | |
|---|---|---|---|---|
| B | 借家の賃料債権 | パソコンセット | 不動産賃貸の先取特権[民法312条,330条1項1号] | 1 |
| C | 動産売買の代金債権 | 動産売買の先取特権[民法321条,330条1項3号] | 3 | |
| D | 動産保存の報酬債権 | 動産保存の先取特権[民法320条,330条1項2号] | 2 | |
| E | 貸金債権(一般債権) | 一般財産 | なし | - |
以上の作業を通じて,各債権者の優先順位は,1.家屋賃貸人B,2.修理業者D,3.売主C,4.貸金業者Eとなることが確定された。そこで,パソコンセットの競売表価額30万円を,先取特権の優先順位に従って,各債権者の債権額を割り付けていくと,次の表のようにまとめることができる。
| 順位 | 債権額 | 評価残額-債権額=残額 | 配当額 | |
|---|---|---|---|---|
| B(賃貸人) | 1 | 10万円 | 30-10=20 | 10万円 |
| D(修理業者) | 2 | 5万円 | 20-5=15 | 5万円 |
| C(売主) | 3 | 20万円 | 15-20<0 | 15万円 |
| E(貸金業者) | 4 | 25万円 | 0 | 0万円 |
配分結果は,B:10万円,D:5万円,C:15万円となり,Eは配当を受けることができない。もしも,パソコンセットの評価額が15万円にしかならない場合は,配分結果はB:10万円,D:5万円となり,CもEも配当を受けることができなくなる。
以上の作業を通じて,債権額に応じて単純に比例配分した場合と,先取特権を考慮して,優先順位に従って配分した結果は,全く異なるものとなることが理解できるであろう。
設例の場合に即して,債権の種類によって優先順位がつけられ,順位の高い債権者が優遇される理由を考えてみよう。
第1順位の家屋の賃貸人は,パソコンセットの設置場所を提供し,責任財産の保全に貢献している。もしも,家賃を払わない債務者が契約を解除されてそこから追い出されていたら,パソコンセットを差し押えることすらできなかったと思われる。家賃が払われないままに,パソコンセットの設置場所を提供し続けた賃貸人は,パソコンセットが差押えられ換価されるのに大きく貢献していることになる。
第2順位のパソコンセットの修理業者は,壊れたパソコンセットを修理し,価値を保全した功績がある。もしも,パソコンセットの修理がなされていなければ,30万円で評価されることはなく,配当額はもっと少なくなっていたはずである。
第3順位のパソコンセットの売主は,代金の全額の支払いを受けていないにもかかわらず,パソコンセットの所有権を債務者に移転し,債務者の責任財産に組み込んだ功労者である。もしも,売主がパソコンセットを債務者に引き渡していなかったら,パソコンセットを差し押えることすらできなかったのである。
第4順位の貸金業者は,一般債権者であって,債務者の責任財産の拡大には貢献しているが,パソコンセットの購入・保全に関しては,何の貢献もしていない。
このように考えると,先取特権が債権の種類と債権の目的物(責任財産)の種類とに応じて優先順位を決定していることの合理性を理解することができる。しかも,その順位のつけ方には,債権の目的物(責任財産)の存在と価値の保全に対して,その債権者がどの程度貢献しているかという考慮が働いている。
そして,価値の保全に関しては,「数人の保存者があるときは,後の保存者が前の保存者に優先する」[民法330条1項柱書]という原則,すなわち,より直近の保存者を優先するという原則が働いていることも理解することができる。
設例の場合のパソコンセットの価値の保全の順序は,(1)売買によるパソコンセットの搬入と保全,(2)修理による価値の保全,(3)修理されたものが元の持主の下に戻って保全されるという順序を経ており,優先順位は,反対に,最後のものから最初のものへと遡る形式をとっているのである。
上記の問題は,単純に考えると,それほど難しい問題ではない。しかし,条文の細かい解釈をする場合には,もう少し複雑な考慮を必要とする。民法330条を詳しく検討してみると,その複雑さが理解できる。
たとえば,330条1項1号・2号・3号にあたる先取特権者が一人ずついたとして,第一順位の先取特権者が第三順位に当たる先取特権者の存在のみを知っていた場合には,優先順位はどのようになるのであろうか。
民法330条1項1号にあたる先取特権者(以下「1号先取特権者」とする。同法同条の2号・3号にあたる先取特権者も同様とする)は,2号先取特権者には優先できるものの,3号先取特権者には劣後し,一方,3号先取特権者は1号先取特権者には優先できるものの,2号先取特権者には劣後するのだから,三すくみ状態になってしまい,優先順位が決せられないようにも思われる。
しかし,この場合の結論を述べると,順序は,2号先取特権者,3号先取特権者,1号先取特権者の順となり,三すくみ状態にはならない。その理由は,立法理由[民法修正案理由書(1896/1987)第304条]を読まないと出てこない。その理由を簡単に述べると以下の通りとなる。
1号先取特権者は場合によって,順序が変わり,第3順位にまで落ちるが,2号先取特権者は,順位が上がることはあっても,2位以下に下がることはない。したがって,2号先取特権と3号先取特権との順序〔序列〕は入れ替わることはないので,3号先取特権者は,第2順位以上になることはない。3号先取特権者は2号先取特権者には,常に劣後するのである。
その理由は,旧民法を知っているとわかりやすい。なぜなら,旧民法においては,1号先取特権者(環境提供者)は,2号先取特権者(保存者)または3号先取特権者(供給者)を知らないときだけ第1順位になることができるたのであり,1号先取特権者(環境提供者)は第3順位にまで下がることがあるが,2号先取特権者(保存者)は第1順位となることはあっても,第2順位より順位を下げることはないからである。このことを考慮するならば,実質的な第1順位は2号先取特権者(保存者)だということが,よく理解できる。現行民法は,以下のように,この旧民法債権担保編164条を下敷きにして起草されたからである。
[現行民法 第330条の立法理由]
(理由)本條は,既成法典担保編第164條に修正を加ヘたりと雖も,其実質に於て大差あるにあらず。
既成法典は原則として先取特権の目的物の保存者に第一の順位を与ヘ,不動産賃貸人等に第二の順位を与ふと雖も,不動産賃貸人の如き者は,所謂「黙示の質権」を有するものなれば,恰も既成法典同條第6項に於て動産質設定の時其目的物の存保費用が未だ支払はれざることを知らざりし質取債権者に第一の順位を与ふる如く,黙示の質取債権者にも之と同様の順位を得せしむるを以て至当と認めたれば〔なり〕。
本案は原則として不動産賃貸の先取特権を第一位に置き,動産保存の先取特権に第二の順位を与ヘ,動産売買の先取特権は既成法典の如く之を第三の順位に置くと雖も,本條第二項の規定に依りて之に例外を設け第一の順位に在る者を債権取得の当時に第二又は第三の順位に在る先取特権の存在を知りたるときは之に先つことを得ざる旨を掲ぐるを以て,其実質に於ては既成法典と別に異なる所なしとす。…
このように,現行民法が,旧民法の趣旨を受け入れて,「実質に於ては既成法典と別に異なる所なし」として起草されたことを理解していると,先の問題においても,三すくみの状態が生じないことがわかる。1号先取特権者は,2号先取特権者と3号先取特権者とを知らない場合にのみ,2号先取特権に優先できる。むしろ,旧民法では,2号先取特権者が原則として最優先順位を得ていた。現行民法でも,実は,1号先取特権者は,2号先取特権者や3号先取特権者を知らないときだけ2号先取特権者に優先できるのである。1号先取特権者が,2号先取特権者か3号先取特権者かを知っている場合には,常に,2号先取特権者に劣後する。したがって,1号先取特権者が,2号先取特権者のみを知っている場合には,順序は,2号先取特権者,1号先取特権者,3号先取特権者の順になる。
| 順位の変動 | 旧民法 | 現行民法 |
|---|---|---|
| デフォルト値 (初期状態) |
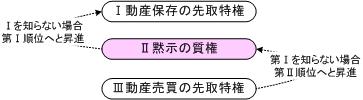 |
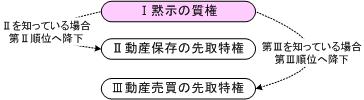 |
| 先取特権の順位が変動する実際の場合分け | ||
| 黙示の質権者が 他の先取特権を 知らない場合 |
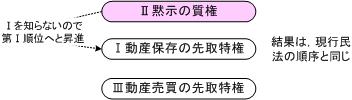 |
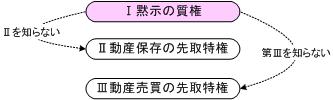 |
| 黙示の質権者が 保存の先取特権 を知っているが, 売買の先取特権 を知らない場合 |
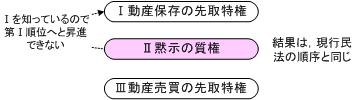 |
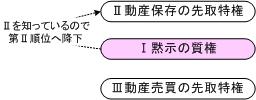 |
| 黙示の質権者が 売買の先取特権 を知っている場合 |
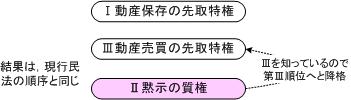 |
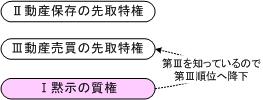 |
本書の立場は,旧民法とも現行民法とも結果は同じである。もっとも,本書の立場は,デフォルト値を①保存,②供給,③環境設定の順にしているため,出発点が異なる。上記の*図76を参考にして,本書の立場に従った場合,先取特権の順位がどのように変動するのかを図示してみると,異なる考え方でも,同一の結果を生じさせることができること,および,民法330条1項~3項までの結論を統一的に説明するには,本書の立場がもっともわかりやすいことを理解することができるであろう。
上記の設例を解決する過程で明らかになったように,先取特権の種類を理解するには,被担保債権の種類と先取特権の目的(物)との関係をよく理解する必要がある。そうすれば,「不動産賃貸」の先取特権がなぜ,「動産」先取特権なのかという疑問にも,容易に答えることができる。なぜなら,不動産賃貸の先取特権は,優先権を有する被担保債権は,「不動産」賃貸借から生じる債権なのであるが,優先権を有する債権の目的物の範囲が不動産賃貸における賃借人の「動産」に限定されている。したがって,不動産賃貸の先取特権は,被担保債権の視点からは,不動産賃貸に関する問題なのであるが,目的物の視点からは,動産先取特権だということになる。
そこで,以下では,民法が規定する先取特権について,それぞれの特色をよく理解するため,大きく3つに分類され,それぞれの分類に応じた合計15種類の先取特権(第1:一般先取特権(4種類),第2:動産先取特権(8種類),第3:不動産先取特権(3種類))について,3分類のそれぞれについて,種類と優先順位を表の形で整理した後,個々の先取特権の内容と特色を検討することにする。
民法は,306条~310条において,以下の4種類の一般先取特権を規定している。これらの先取特権は,順位において,それ以外の先取特権に劣後するのが原則であるが[民法329条2項本文],共益費用の先取特権[民法306条1号,307条]は,その利益を受けたすべての債権者に優先する効力を有しているので[民法329条2項ただし書き],注意が必要である。
| 先取特権の種類 | 優先 順位 |
条文 | 債権の種類 | 責任財産の種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 先取特権 |
1 | 共益費用の 先取特権 |
1 | 民法307条 | 債務者の財産の保存,清算又は配当に関する費用 | 債務者の総財産 |
| 2 | 雇用関係の 先取特権 |
2 | 民法308条 | 給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権 | ||
| 3 | 葬式費用の 先取特権 |
3 | 民法309条 | 債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額, 債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額 |
||
| 4 | 日用品供給の 先取特権 |
4 | 民法310条 | 債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品,燃料及び電気の供給 | ||
各債権者に共通の利益のための費用(債務者の財産の保存,清算または配当に関する費用)について,公平の観念に基づいて先取特権が認められている[民法306条1号,307条1項]。
第1の要件としての「財産の保存」とは,債務者の財産の現状を維持する行為であり,債務者の財産の①物理的な保存と②法律的な保存とがある。法律的な保存の例としては,債務者に代位して債務者が有する権利について時効中断のために権利を行使したり[民法423条],詐害行為を取り消したり[民法424条]することが挙げられる。第2の要件としての「清算」とは,清算人,管財人,執行官等が,債務者の財産の換価,債権の取立て,債務の支払い,財産目録の作成等をすることをいう。第3の要件としての「配当」とは,債権者の債権を調査して配当表を作成し,債務者の財産を換価して配当を実行することをいう。
共益の費用のうち,それがすべての債権者に有益でなかった場合,たとえば,法律的な保存の場合として,抵当権が設定された不動産の売却行為を詐害行為として取り消した場合を想定してみよう。この場合には,一般債権者は財産の保全によって利益を受けるが,すでに追及効を有する抵当権者は,これによって利益を受けることはない。したがって,この場合には,先取特権は,その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。すなわち,詐害行為を取り消した債権者は,一般債権者に対しては先取特権を主張できるが,抵当権者に対しては先取特権を主張することができない[民法307条2項]。これに反して,債務者の財産の物理的な保存の場合には,その費用によってすべての債権者が利益を受けるのであるから,すべての債権者に対抗できることになる。
共益費用の先取特権の特色は,最初に述べたように,その他の一般先取特権が特別の先取特権(動産先取特権,不動産先取特権)に劣後するのに対して,共益費用によって利益を受けたすべての債権者に対して優先する点にある[民法329条]。
雇用に関する債権(給料債権,退職金,労災等に関する損害賠償債権等)について,労務を提供している者を保護すべきであるという社会政策的理由に基づいて,先取特権が認められている[民法306条2号,308条]。
雇用関係の先取特権の詳細については,田山輝明「労働債権と先取特権」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)95頁以下]を参照するのがよい。立法の沿革から,立法論に至るまで,重要な問題点が指摘されている。特に,以下の記述は,質権や抵当権等の約定担保権のほかに,法定担保権としての先取特権がなぜ必要であるのかについて説得力の記述となっている(先取特権の廃止論者であっても,雇用関係の先取特権については,その必要性を認めている)。また,一般先取特権と後に学習する根抵当権との意外に近い関係を明らかにしている点でも参考になる。
労働契約の締結(入社)に際して,自己の労働債権を被担保債権として会社(使用者)の不動産に根抵当権を設定することは極めて困難であるし,入社後に労働組合を通じて団体交渉などによりこれを実現することも,また極めて困難であろう。企業の倒産が具体化しつつある状況になってから会社との間で労働者(組合)に有利な協定を結んでも,破産法に基づいて「否認」される恐れがある(同法162条)。そのため,社会政策的考慮から法定担保物権によって保護を図る必要は依然として大きい(田山輝明「労働債権と先取特権」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)99頁])。
葬式の費用について,財力の十分でない者にも葬式を営む場合の金融を受けやすくしようという公益上の理由に基づいて先取特権が認められている[民法306条3号,309条]。
死者本人が,自己の葬式に関連する債務を負担した場合には,その債権者は,債務者の遺産に対して先取特権を有する。また,夫の死後に,妻が夫の社会的地位に応じて支弁した葬式費用は,相続財産の負担となる〈東京地判昭59・7・12判時1150号205頁〉。
日用品の供給に関する債権について,主として小規模の商人を保護するという社会政策上の理由に基づいて先取特権が認められている[民法306条4号,310条]。この場合の債務者は,自然人に限られ,法人は含まれないとされている〈最一判昭46・10・21民集25巻7号969頁〉。
[民法311条~324条]は,以下の8種類の動産先取特権を規定している。この中には,動産先取特権だけでなく,債権の先取特権が含まれている。
2004年に民法が現代語化される以前の民法旧311条4号,旧320条には,公吏保証金の先取特権が規定されており,これは,厳密には,動産先取特権ではなく,債権先取特権という重要な性質を有していた。しかし,この規定は,現代では使われていないという理由で,削除されてしまった。したがって,現行民法で債権先取特権について明文で規定しているのは,民法304条(物上代位)と民法314条2文(賃借権の売買代金債権および転借料債権に対する先取特権)のみとなっている。なお,民法314条2文の債権先取特権とは,賃貸人Aが賃借人Bに賃料債権等の債権を有しているときに,Bが賃借権をCに譲渡した場合,または,Bが賃借権をC転貸した場合に,Aが,その売買代金債権の上に,または,転借料債権等の債権の上に先取特権を取得するというものであり,物上代位と同一の趣旨の規定であるとされている。
債権の先取特権との関係では,さらに,民法316条が重要である。民法316条に規定された敷金について,立法者は,公吏保証金の先取特権と同様,賃貸人は,「不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務」[民法312条]につき,「敷金返還債務」とを相殺することによって,賃料債権等について確実な回収を期待できるため,賃貸人は,敷金返還債務の上に最優先の先取特権を有していると考えていた[梅・要義巻二(1896)318-319頁]。賃貸人は,そのような最優先の先取特権を有しているのであるから,「賃貸人は,敷金を受け取っている場合には,その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する」[民法316条]と規定されたのである。
動産先取特権については,以上のように,通常の教科書では触れられていない,さまざまな興味深い話題が潜んでいる。以下では,そのような,敷金と先取特権とに関する興味深い話題についても,詳しい検討を行うことにする。
| 先取特権の種類 | 優先 順位 |
条文 | 債権の種類 | 責任財産の種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動産 先取特権 |
1 | 不動産賃貸の 先取特権 |
1 | 民法312~316条 | 不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務 ・賃借人の財産のすべてを清算する場合には,前期,当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務 ・敷金を受け取っている場合には,その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ |
賃借人の動産,果実 |
| 2 | 旅館宿泊の 先取特権 |
民法317条 | 宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料 | 旅館にある宿泊客の手荷物 | ||
| 3 | 運輸の 先取特権 |
民法318条 | 旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用 | 運送人の占有する荷物 | ||
| 4 | 動産保存の 先取特権 |
2 | 民法320条 〔旧320条【公吏保証金の先取特権】(実は,債権上の先取特権)を削除,旧321条1項,2項の項番号を削除して繰上げ〕 |
動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存,承認若しくは実行のために要した費用 | 保存された動産 | |
| 5 | 動産売買の 先取特権 |
3 | 民法321条 〔旧322条を繰り上げ〕 |
動産の代価及びその利息 | 売買された動産 | |
| 6 | 種苗・肥料供給の 先取特権 |
民法322条 〔旧323条を繰り上げ〕 |
種苗又は肥料の代価及びその利息 | 種苗又は肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた果実 (蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む) |
||
| 7 | 農業労務の 先取特権 |
民法323条 〔旧324条の一部〕 |
農業労務従事者の最後の1年間の賃金 | 労務によって生じた果実 | ||
| 8 | 工業労務の 先取特権 |
民法324条 〔旧324条の一部〕 |
工業労務従事者の最後の3ヶ月間の賃金 | 労務によって生じた製作物 | ||
賃貸借関係から生じる債権(賃料債権,損害賠償債権等)について,賃借人が賃貸不動産に持ち込んだ動産の上に先取特権が認められている[民法311条1号,312条]。
この先取特権は,従来は,当事者の意思の推測に基づいて法が認めたものであり,黙示の質権(gage tacite)であるとされてきた[林・注釈民法(8)(1965)119頁]。しかし,賃貸人の不動産に賃借人が持ち込んだ動産に賃借人が質権を設定するという意思は存在しない上に,賃借人は,その動産の直接占有を放棄せずに使用を続けているのであるから,占有改定による設定を認めない質権とは異なり,むしろ,賃借人の動産の価値の維持に資する環境を提供している賃貸人を保護するために,法定の動産抵当というべき優先弁済権を賃貸人に与えたものと考えるべきであろう([深川・相殺の担保的機能(2008)145-146頁],深川裕佳「第1順位の先取特権について-黙示の質権"gage tacite"の法的性質」東洋法学52巻1号(2008)72-91頁参照)。
不動産賃貸の先取特権の優先順位は,その他のいわゆる「黙示の質権」(旅館宿泊および運輸の先取特権)と同様,第1順位の先取特権とされている[民法330条1項1号]。しかし,この第1順位は,脆弱である。なぜなら,この「第1順位の先取特権者は,その債権取得の時において第2順位又は第3順位の先取特権者があることを知っていたときは,これらの者に対して優先権を行使することができない」[民法330条2項1文]。この点については,先に説明した通りである。それだけでなく,この第1順位の先取特権は,「第1順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても」劣後する[民法330条2項2文]。例えば,借家人の備え付けた家具に対して賃貸人の第1順位の先取特権が成立した後にその家具を保存〔修理等〕した者(第2順位の先取特権者)があるときは,賃貸人は,その保存者に対して優先権を行うことができない。しかも,その保存は,賃貸人の利益に帰すれば十分であり,賃貸人の委託を受けてしたものであることを必要としない。また,賃貸人の善意・悪意も問題とならないとされている[我妻・担保物権(1968)90頁]。
不動産賃貸の取特権が及ぶ目的物の範囲は,第1に,土地の賃貸借の場合には,①その土地に備え付けられた動産(たとえば,土地に備え付けられている排水用または灌漑用のポンプなど),②その利用のための建物に備え付けられた動産(賃借地の納屋に備え付けられている農具,家畜,家具など)または③賃借人が占有する土地の果実(天然果実)に及ぶ[民法313条1項]。
第2に,建物の賃貸借の場合には,賃借人がその建物に備え付けた動産に及ぶ[民法313条2項]。建物に備え付けた動産の意味に関しては,判例は,これを広く解し,継続的に置いておくためにその建物に持ち込まれたものには,宝石,金銭,有価証券,商品なども含まれるとしている〈大判大3・7・4民録20輯587頁〉。これに対して多数説は,建物の使用に関連して常備されるものに限ると解し,家具,調度,機械,器具,営業用什器などは含むが,賃借人の個人的所持品,建物の使用と関係のない金銭,有価証券などは含まないとしている。
第3に,賃借権の譲渡または転貸の場合には,不動産賃貸の先取特権は,譲受人または転借人の動産にも及ぶ[民法314条]。そして,賃借権の譲渡の場合は,被担保債権の譲渡に伴って先取特権も随伴するために先取特権の範囲に変化はなく,また,転貸の場合にも,被担保債権が民法613条の直接請求権の範囲に限定されるため,転借人が不測の損害を被ることはない。
民法314条の先取特権によって転借人が不測の損害を被ることがない理由は,以下の通りである。
以上のように,民法の場合には,不動産賃貸の先取特権の目的物は「動産」に限られ,地上の建物には及ばない。ただし,この原則にも例外がないわけではない。なぜなら,借地借家法の場合には,最後の2年分の地代について,借地権者がその土地において所有する建物の上にも先取特権が及ぶとして,先取特権の拡張を行っている[借地借家法12条]からである。
被担保債権は,賃料または賃貸借関係から生じるその他の債権(損害賠償債権,解除に伴う返還請求権等)である。賃料の場合も,原則としては,その額に制限があるわけではない。しかし,以下の場合には,被担保債権の範囲が限定される。
第1に,賃借人の破産,賃借人の遺産相続についての限定承認[民法922条以下],賃借人である法人の解散等により,賃借人の財産すべてを清算するという例外的な場合には,賃貸人の先取特権は,前期,当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する[民法315条]として,先取特権の範囲が制限されている。賃借人の破算等によって総清算が行われる場合には,賃貸人の保護だけでなく,賃貸人以外の債権者を害することがないよう,すなわち,総債権者の利益をできる限り平等にするという配慮が必要だからである。
第2に,賃貸人が敷金(不動産,特に家屋の賃借人が,賃料その他の債務を担保するために,契約成立の際,あらかじめ賃貸人に交付する金銭)を受け取っている場合には,賃貸人は,「敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する」[民法316条]として,被担保債権の範囲が,敷金で弁済を受けない範囲に限定されている。その理由はなぜか。[髙橋・担保物権(2007)40頁]のように,「賃貸借終了時において,賃貸人は賃借人に対し,敷金相当分を控除した残額についてのみ債権を有するに過ぎないから」とし,債権の付従性によってこの理由を説明する学説も存在する。そうだとすると,先取特権の制限は,「敷金の性質上当然のことである」ということになりそうである。しかし,本書では,敷金返還請求権について,賃料が当然に充当されるのではなく,賃貸人または賃借人の相殺の意思表示を必要とすると考えるので,この説は採用できない。不動産賃貸人の動産先取特権が敷金で弁済を受けない債権の部分に限定されているのは,付従性の問題ではなく,以下のような深い意味が隠されていると考える。
旅館(対価を得て客を宿泊させることを業とする者)が宿泊客に対して有する債権(宿泊料債権,飲食料債権)について,宿泊客の手荷物がその旅館にある場合について,その手荷物の上に先取特権が認められている[民法311条2号,317条]。
この先取特権は,従来は,当事者の意思の推測に基づいて法が認めたもの(黙示の質権(gage tacite))とされてきた。しかし,旅館に携帯した動産に客が質権を設定するという意思は存在しない上に,客が手荷物を特別に預けた場合(この場合には留置権が発生する)を除き,客は手荷物の直接占有を放棄せずに使用を続けているのであるから,占有改定による設定を認めない質権とは異なる。この先取特権は,むしろ,宿泊客の動産の価値の維持に資する環境を提供している旅館を保護するために,法定の動産抵当というべき優先弁済権を旅館に与えたものと考えるべきである。
運送人(運送を業としている者に限らない)が旅客または荷送人・荷受人に対して有する債権(旅客の運送賃,荷物の運送賃,および付随の費用(荷物の荷造り費,関税の立替金等))について,運送人が占有する荷物の上に先取特権が認められている[民法311条3号,318条]。
この先取特権は,従来は,当事者の意思の推測に基づいて法が認めたもの(黙示の質権(gage tacite))とされてきた[林・注釈民法(8)(1965)132頁]。しかし,運送人が占有する荷物に顧客が質権を設定するという意思は黙示にも存在しない。この先取特権は,顧客の動産の価値の維持に資する環境を提供している運送人を保護するために,運送人に優先権を与えたものと考えるべきである。
以上の3つの動産先取特権,すなわち,不動産賃貸の先取特権,旅館宿泊の先取特権,運輸の先取特権は,従来は,主として当事者の意思の推測に基づいて先取特権が認められてきたとして,黙示の質権(gage tacite)といわれてきた。
しかし,先にも述べたように,債務者に質権を設定する意思もそのつもりもないことが指摘されており,また,質権というには,債務者が占有を継続しているものが多いために,黙示の質権というよりは,黙示の担保権(黙示の動産抵当権)と呼ぶべきであり,結局のところ,目的物の価値を維持するための環境を与えた債権者(不動産賃貸人,旅館,運送人)を保護するために,法が与えた優先弁済権であるとするのが適切であろう。
これらの3つの動産先取特権は,後に述べるように,原則として第1順位の先取特権としての地位が与えられているが,その順位は不動のものではなく,前の保存者を知っているかどうかで,順位が下がる場合があることは,先に述べたとおりである(本書の立場では,黙示の質権は,環境設定の先取特権として,もともとは,第3順位にあるが,先順位の先取特権を知らない場合には,第1順位に至るまで順位を善意取得できると考えることになる)。また,民法192条~194条までの即時取得の規定が準用されており[民法319条],ここでも,債権者が善意かどうかが決定的な要件となっている。
例えば,不動産に持ち込まれた動産について,旅館に持ち込まれた手荷物について,または,運送を引き受けた荷物について,それらの動産が,実は,債務者の所有の物ではないのに,賃貸人,旅館または運送人がそうであると誤信し,かつ誤信することについて無過失であった場合には,賃貸人,旅館,運送人は,それぞれの目的物について先取特権を取得する。
この理由については,歴史的な経緯からして,これらの3つの先取特権が,当事者の意思の推測に基づいて認められたものであるとの理解があり,そのことから,債権者が悪意の場合にはその順位下げられるが,反対に,善意無過失の場合には即時取得がありうるとして債権者のいっそうの保護がなされるという制度が構築されてきたのである。
動産保存の先取特権の典型例は,動産を修理した者(請負人)の報酬債権(動産の保存費用)に優先弁済権を与える場合である。民法が動産保存の先取特権を認めた理由は,目的物について保存費を費やした者を他の債権者よりも保護しようとするからであり,公平の理念に基づくものとされている。法と経済学等の現代的視点からは,目的物が競売されたとき,保存された目的物は,保存される前よりも価値が上昇しており,配当を受けるに当たって,保存をしていない他の債権者が保存の費用を出した者と平等な配当を受けるのは,いわゆる「ただ乗り(free rider)」であり,保存の費用を出した者にその限度で優先権を与えようとするものであると説明することもできる。
現代語化前の旧条文[民法旧321条]では,1項の物理的な保存費用,2項の法律的な保存の費用とが分離して規定されていたが,現代語化によって,両者が1つにまとめられ,かえって,意味がわかりにくくなっている。
第1の物理的な保存費用(保存費)としての「動産の保存のために要した費用」とは,債務者の所有する目的物を債権者自らが修理する場合および債権者が他人に依頼して修理をしてもらう場合とが含まれる。
第2の法律的な保存としては,権利の保存,権利の承認,権利の実行のために要した費用が含まれる。それぞれの行為の意味は以下の通りである。
動産の売買代金について,売主を保護する規定である。動産が売主から買主へと引渡されていない場合には,売主は,同時履行の抗弁権[民法533条],留置権[民法295条]によって保護されるので,動産の先取特権が実益を発揮するのは,目的物がすでに買主に引渡された場合である。民法が「動産売買の先取特権」を認めた理由は,代金は未払いだが,動産の引渡しによって所有権が買主に移転した場合でも,売買目的物の上に先取特権が成立するとして,売主を保護するものであり,公平の理念に基づくものといわれている。
動産先取特権については,従来は,執行官への動産の提出や債務者の差押承諾書の提出が要求されたために,その実行が困難であった。しかし,2003(平成15)年の担保法・執行法改正により,動産競売開始決定の制度[民事執行法190条]が創設されたことにより,動産売買の先取特権を含めて動産先取特権の実行が容易となっている(詳しくは,荒木新五「動産先取特権の現状と課題」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)117頁以下]参照)。
種苗または肥料の供給者に先取特権が与えられた理由は,上記の動産売買の先取特権と同様,当事者間の公平を図るという理由のほか,農業金融を促進しようとするねらいがあったとされている。
後者のねらいは,その後,1933(昭和8)年の農業動産信用法の制定によって実現されることになる。農業金融を行う者に対して広範な先取特権(農業経営資金貸付の先取特権)が,農業用動産,農業生産物の保存,農業用動産の購入,種苗又は肥料の購入,蚕種又は桑葉の購入,薪炭原木の購入等に関して認められたからである。
このような先取特権が認められたのは,賃金労働者を保護しようとするものであり,雇用関係の一般先取特権[民法308条]を強化しようとするものである。
2つの条文は,もともとは,1つの条文(旧・324条)の1項と2項に規定されていたものであった。2つの条文の立法の趣旨は同じであり,わざわざ条文を2つに分離する必要はなかった。民法旧320条(公吏保証金の先取特権)を削除したため,条文の間隙が生じるのを嫌う法務官僚の美学に従って,つじつま合せのために条文が2つ分割されたに過ぎない[民法の現代語化に便乗した不毛な条番号の変更,重要な条文の削除に対する批判については,[加賀山・民法学習法(2007)131頁以下(140-141頁)]参照)。
民法は,325条~328条において,以下のように,3種類の「不動産の先取特権」を規定している。これらの先取特権は,その他の先取特権が公示を必要としないのに対して,その効力を保存するためには登記を必要としている点に特色を有する。
| 先取特権の種類 | 優先 順位 |
条文 | 債権の種類 | 責任財産の種類 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産 先取特権 |
1 | 不動産保存の 先取特権 |
1 | 民法326条 〔旧326条1項,2項の項番号を削除〕 |
不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存,承認若しくは実行のために要した費用 | 保存された不動産 |
| 2 | 不動産工事の 先取特権 |
2 | 民法327条 | 工事の設計,施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用 (工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り,その増価額についてのみ存する) |
工事された不動産 | |
| 3 | 不動産売買の 先取特権 |
3 | 民法328条 | 不動産の代価及びその利息 | 売買された不動産 | |
民法325条1号,326条が「不動産保存の先取特権」を認めたのは,公平の理念に基づくものであり,現代的な視点から見れば,他の債権者による「ただ乗り(free rider)」を認めない趣旨と考えることができる。
これは,動産保存の先取特権を認めたのと同じ理由に基づく。現行民法の土台となった旧民法には,動産については,動産「保存」の先取特権の規定が存在したが,不動産に関しては,不動産「工事」の先取特権の規定があるものの,不動産「保存」の先取特権は規定されていなかった。もっとも,不動産「工事」の先取特権は,その被担保債権が,「工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合」に限定されている(旧民法債権担保編175条1項,現行民法327条2項)ことから,旧民法の場合には,不動産工事の中に,保存の工事が含まれていたと思われる。しかし,現行民法の立法者は,以下のように述べて,動産保存の先取特権の規定に倣って,不動産保存の先取特権を創設した[民法理由書(1987)330頁]。
(理由)既成法典は,不動産保存者の先取特権を認めずと雖も,既に動産保存者の先取特権を認むる以上は,不動産の保存に本づく債権にも先取特権を付するを以て至当と信じたれば,本案は,不動産の保存を以て先取特権の一原因とし,新に之を加ヘたり。
現代語化以前の規定は,「不動産保存」の先取特権について,「動産保存」の先取特権の規定を準用するという構成をとっていたため,両者の結びつきが明確であった。現代語化に際して,このような準用規定をなくし,それぞれの条文を独立したものとして書き直したことは,一見,個々の条文の意味をわかりやすくするための配慮のように見えるが,実は,条文間の関連を断ち切るものであり,現代語化としては,行き過ぎであったと思われる。
動産保存の先取特権と不動産保存の先取特権との違いは,動産保存の先取特権が対抗要件を必要としないのとは異なり,不動産保存の先取特権の場合には,その効力を第三者に対抗するためには,保存行為が完了した後,遅滞なく登記をしなければならないとされている点にある[民法337条]。民法がこのような厳格な要件を定めたのは,この先取特権には,それ以前に登記された抵当権に優先するという強い効力が認められているからである[民法339条]。
この理由について,詳しく検討してみよう。そもそも先取特権は,法定の物的担保であり,かつ,債権者が目的物を占有する必要のない(債務者の使用・収益を認める)物的担保である。したがって,動産先取特権の場合も目的物の引渡しを受けることを要しないし,また,一般先取特権の場合にも,対抗要件を必要としない([民法336条本文]参照)。しかし,不動産に関しては,登記が重要な意味を持つので,その点を考慮して,一般先取特権については,さすがに,登記をした第三者には対抗できないとしている[民法336条ただし書き]。
しかし,ここで問題としている不動産保存の先取特権に関しては,先に述べたように,それ以前に登記された抵当権にも優先する効力を有するという非常に強力な効力を生じるのであるから[民法337条],民法は,不動産保存の先取特権にも,例外的に,第三者対抗要件としての登記を要求したのである[民法337条]。この登記は,民法325条1号,326条ですでに効力が認められている不動産保存の先取特権に対して,第三者対抗要件として登記を要求したものである。不動産保存の先取特権における登記の意味を効力発生要件であると解している多数説および判例〈大判大6・2・9民録23輯244頁〉の見解とは異なるが,効力要件として登記を要求したものではないと解すべきである([我妻・担保物権(1968)98頁]も,登記を効力要件ではなく,第三者対抗要件としている)。立法者も,この点について,以下のように述べている[民法理由書(1987)337頁]。
(理由)本条は,不動産保存の先取特権を保存する手続を定むるものにして,本案が,既に325条の規定に依りて此の特権を認めたる自然の結果に出づるものなり。而してその保存の方法は,他の不動産の先取特権の如く,登記せしむるを以て適当と認めるに因り,保存行為完了の後直ちに登記を為すべきものと定めたり。
不動産保存の先取特権は,保存行為が完了した後に,遅滞なく登記を行うと,民法339条により,登記の先後を問わず,抵当権に優先する効力を有する。このことは,不動産物権変動に関する民法177条の原則を大きく修正するものであり,先取特権を「物権」と考える場合には,理解に苦しむことになる。例えば,通説を代表する我妻説は,「排他性を本質とする物権の一般理論によれば,先取特権の順位はその成立の時の順序によるべきである」とし,民法がこの理論に従わない理由を説明しかねている[我妻・担保物権(1968)88頁]。
しかし,動産先取特権の箇所でも詳しく論じたように,目的物の保存に寄与した債権者に対して先取特権が与えられる場合には,民法330条1項2文の「保存の先取特権について数人の保存者があるときは,後の保存者が前の保存者に優先する」という,物権法の法理では説明することができない,「保存に関する優先順位決定のルール」が思い起こされなければならない。
なお,民法330条1項2文の「後の保存者が前の保存者に優先する」というルールは,動産先取特権のみに適用されるルールではない。通説も,「保存または工事の先取特権が数個あるときは,その順位は後のものが優先すると解すべきであろう」[我妻・担保物権(1968)91頁]として,上記のルールが不動産先取特権にも適用されることを認めている(旧民法には,このことを認める明文の規定があった[旧民法債権担保編187条1項第1本文])。しかも,考えてみれば,不動産先取特権について,第1順位が不動産先取特権であり,第2順位が不動産工事の先取特権であることは,民法331条1項によって明らかであるが,その順序自体が,第1に工事の完成,第2にその保存という,本来的な成立の順序とは反対になっており,ここでも,広い意味での「後の保存者〔不動産保存者〕が前の保存者〔不動産工事者〕に優先する」というルールが実現されているのである。
この「保存に関する優先順位決定のルール」が適用されることにより,その結果として,抵当権者の登記に遅れたとしても,最後に保存した不動産保存の先取特権は,この原則通りに,最優先の先取特権が与えられるのである[民法339条]。
民法339条によって認められている抵当権の登記に遅れて登記した先取特権が,先に登記した抵当権に優先するという法理は,非常に大きな意味を持っている。後に詳しく検討するように,抵当権の登記に遅れて発生した相殺権が先に登記した抵当権に基づく物上代位に優先するという法理,すなわち,先に登記した抵当権に基づく賃料債権に対する物上代位に対して,賃借人が賃料債務と敷金返還請求権とを相殺した場合に,相殺の担保的効力が抵当権に優先する(〈最三判平13・3・13民集55巻2号363頁〉はこれを否定したが,〈最一判平14・3・28民集56巻3号689頁〉は,結果的にこれを肯定している),並びに,抵当権の登記に遅れて登記された賃借権および抵当権の登記に遅れて対抗力を獲得した借地・借家権が,先に登記された抵当権に対抗できるという法理(後に詳しく論じる)を導く上でも,重要な役割を果たすことになる。
民法325条2号,327条が「不動産工事の先取特権」を認めたのは,当事者の意思の推測および公平の理念に基づくものであるとされている。不動産保存の先取特権との違いは,不動産の「工事」が不動産を「創設」するものであるのに対して,不動産の「保存」は,不動産の存在を前提にして,その「維持・改良」を行う点にある。したがって,新築・増築工事は,不動産の「工事」であり,建物の修理は不動産の「保存」である。
もっとも,「工事」と「保存」との境界はあいまいであり,多くの問題が生じている。特に,不動産保存の先取特権は,保存の後に登記をすれば第三者に対抗できるが[民法337条],不動産工事の先取特権は,工事の前に工事の費用の予算額を登記しなければならない([民法338条],[不動産登記法83条,85条~87条])。そこで,事前の登記を怠った請負人は,遅れて登記をした後に,それまでの工事と登記後の工事とを2分し,前半を不動産の工事,後半を不動産の保存として,後半部分について,先取特権の効力を第三者に主張しようとする傾向にある。
しかし,判例は,このような主張を認めない。建築工事完成後に登記しても,これについて先取特権の効力を保存することはできない〈大判明43・10・18民録16輯699頁〉。また,登記前の工事と登記後の工事は単一の工事であるから,その工事全体のはじめに先取特権の登記をしなければ,登記後の工事についても効力はない〈大判大6・2・9民録23輯244頁〉。
ところで,建物の新築工事の際の登記はどのようにして実現可能なのであろうか。新築工事の場合には,先取特権の登記の時点では建物の所有権の保存登記が存在しないため,どのような登記をすべきなのかが問題となる。その手続きは,不動産登記法83条,85条~87条,不動産登記規則161-162条,不動産登記令の別表43号に規定されている。新築工事の先取特権保存の登記申請がなされると,不動産登記法86条に基づき,登記官は,登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録する[不動産登記規則161条]。そして,建物が完成した場合には,建物の所有者(登記義務者)は,遅滞なくその建物の所有権の保存の登記をしなければならない[不動産登記法86条]。したがって,不動産工事の先取特権の保存登記をした者は,建物完成とともに,建物所有者に対してその所有権保存登記手続きを請求することができることになる〈大判昭12・12・14民集16巻1843頁〉。
不動産工事の先取特権は,不動産保存の先取特権に比べて,その保存の登記を事前にしなければ第三者に対抗できないという点が短所となっている。不動産の工事をする者が,あらかじめ登記をしないで工事に着手すると,この先取特権を第三者に対抗できない。新築の工事の場合には,そもそも建物の登記がないのであるから,手続がめんどうであり,実行が困難な上に,工事に着手してから債務者の資力が乏しいことがわかったという場合には,不動産工事の債権者の救済が困難となる。そこで,立法論としては,不動産保存の先取特権の場合と同様,工事着手後に登記しても,その後に登記された抵当権に優先する効力を認めるのが妥当であるとの見解が主張されている([我妻,有泉・コンメンタール(2008)533頁],立法論に関しては,執行秀幸「不動産工事の先取特権-アメリカ合衆国における統一建設リーエン法の検討」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)138頁以下]およびそこで参照されている文献が有用である)。
立法者も,旧民法における不動産工事の先取特権の保存の手続が煩瑣に過ぎることは気づいており,現行法は,以下のように,それを改善するために修正されたという経緯がある。
(理由)既成法典は担保編第175条に於て3種の調書を作るべきこと,及び,同第183条に於て,此等の調書に依る登記の時に関し,精密なる規定を掲くと雖も,如斯手続は,従来の慣習上到底行はれ難く,之れが爲めに先取特権の便益を減殺する虞あるを以て,本案は務めて之を簡略にし,工事著手前に一度予算額を登記せば,之に依りて先取特権を保存することを得とし,且,此登記に依りて増価額評定の標凖を定めたり。
このような立法趣旨を活かすためには,上記の立法論ではまだ不足であり,不動産を創設した債権者にも,不動産保存の先取特権と同様,工事の後,遅滞なく登記をすれば,第三者に対しても,対抗できるとすべきであろう。
また,[山野目・物権(2009)219頁]は,保存後遅滞なく登記がなされなかった不動産保存の先取特権や,公示前に登記がなされなかった不動産工事の先取特権であっても,それらには,339条の定める特典が否定されるにとどまり,それらの先取特権が登記されたのちは,それに遅れて登記された抵当権には優先するとの考え方(民法373条・341条参照)も成り立たちうるとしている。時間の先後を重視する考え方ではあるが,民法の規定の不備を補充する解釈として注目に値する(詳しくは,執行秀幸「不動産工事の先取特権-アメリカ合衆国における統一建設リーエン法の検討」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)138頁]参照)。
民法が不動産売買の先取特権を認めたのは,動産売買の先取特権の場合と同じく,公平の理念によるものである。この先取特権をもって第三者に対抗するためには,売買契約と同時に不動産の代価またはその利息について,その弁済がなされていない旨を登記しなければならない[民法340条]。
この登記の効力には,民法339条が適用されない。このため,不動産保存の先取特権および不動産工事の先取特権の場合とは異なり,常に抵当権に優先するとは限らない。すなわち,不動産売買の先取特権と抵当権との優劣は,登記の先後によって決まることになるからである。
もっとも,不動産売買の先取特権と抵当権との優劣については,明文の規定がない。しかし,不動産先取特権のうち,不動産保存の先取特権と不動産工事の2つの先取特権については,適法に登記した先取特権は,抵当権に優先することが定められている[民法339条]。この反対解釈として,不動産売買の先取特権は,必ずしも抵当権に優先するとは限らないということになる。「不動産売買の先取特権は,必ずしも抵当権に優先するとは限らない」という意味は,決して,抵当権に劣後するということではない。民法340条は,「不動産売買の先取特権の効力を対抗するためには,登記をしなければならない」と規定しており,その意味するところは,不動産売買の先取特権は,登記をすれば,抵当権と同等の効力を有するということだからである。
それでは,登記をした不動産売買の先取特権と登記をした抵当権の優先順位は,どのようにして決せられるのであろうか。不動産売買の先取特権の優先順位に関する民法331条によれば,売買の前後によることになり,抵当権の順位に関する民法373条によれば,登記の前後によることになる。それでは,いずれの規定を適用すべきであろうか。結論から言えば,どちらの規定によっても登記の先後によることになる。なぜなら,民法340条によれば,不動産売買の先取特権が対抗力を有するためには,売買契約と同時に登記をしなければならないのであるから,民法331条の順位決定のルールは,結局,売買契約と同時になされる登記の先後によることになり,抵当権の順位決定のルールである民法373条と同じとなる。
このことから,抵当権と不動産先取特権との関係は,次のようにまとめることができる。
それでは,抵当権が,不動産保存の先取特権および不動産工事の先取特権には劣後し,不動産売買の先取特権と同順位とされる理由は何か。それは,不動産の売買により,目的物は,代金未済の不動産買主(債務者)の責任財産に取り込まれているが,それは,売買代金の支払いを猶予してくれている売主(直近で貢献した債権者)のおかげである。しかし,その目的物が存在するのは,目的物を建築した不動産工事の先取特権者のおかげであり,さらに,その目的物が現在の価値を有するのは,その価値を維持・増加させた不動産保存の先取特権者のおかげである。保存に関しては,「後の保存者が前の保存者に優先する」というルールがあり[民法330条1項2文],そのルールが適用されることになる。
その結果,最後の保存者である不動産保存の先取特権が,登記の先後にかかわらず,第1順位となり,最初に目的物を創設・保存した不動産工事の先取特権が,工事に先立って登記をしていると第2順位となり,目的物の価値の保存に関与しない不動産売買の先取特権は売買と同時に登記をした場合に限り第3順位となり,占有を伴わず,不動産の管理に関与しない抵当権も,不動産売買の先取特権と同じく第3順位となる。そして,第3順位の内部での優先順位は,民法331条2項に従い,売買の前後ということになるが,不動産売買の先取特権は,売買契約と同時に登記をしなければならず[民法340条],結局は,民法373条と同じく,対抗要件としての登記の順序によることになる。
先取特権の順位決定のルールの特色は,民法330条に代表されるように,対抗要件を先に備えた方が優先権を獲得するというような単純な方式を採用しているわけではない。優先すべき債権の性質,すなわち,その債権が債務者の責任財産にどのような価値をもたらしているか,さらに,当事者の態様(善意・悪意等)を考慮しつつ,優先順位を確定するという,柔軟なルールを採用している。
そのような考慮の結果,抵当権が,不動産売買の先取特権と同順位の第3順位に位置づけられていることが重要である。売買の売主も,抵当権者も,目的物の保存者とは異なり,目的物の価値の創設・保存・維持に関与せず,目的物の取得に間接的に寄与しているに過ぎない点が考慮されているからである。したがって,以下で問題とするように,動産の先取特権と,動産抵当権ともいわれる譲渡担保とが競合する場合にも,このような優先順位を決定するための基本的な考え方に基づく考慮が必要となる。
先取特権と典型担保との優先順位について検討したので,次に,先取特権と非典型担保(譲渡担保)との優先順位について考察する。以下の事実関係において,Xの動産売買の先取特権とYの集合物譲渡担保とは,どちらが優先権を有するか。Xの競売申立てに対して,Yはどのような手段を講じることができるか。根拠条文とその解釈について検討することにしよう。
|
(1) Y会社は,昭和50年2月1日,訴外A会社との間で,大要次のような根譲渡担保権設定契約(以下「本件契約」という。)を締結した。 |
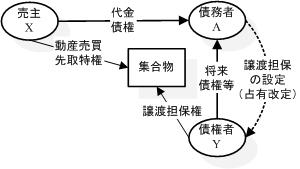 |
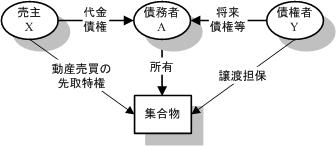 |
| *図77 先取特権と 譲渡担保権(所有権移転説)との競合 |
*図78 先取特権と 譲渡担保権(担保権説)との競合 |
最高裁〈最三判昭62・11・10民集41巻8号1559頁〉は,民法333条適用説を採用している。譲渡担保によって目的物は譲渡担保権者に引渡されるので,民法333条により,先取特権の効力はその目的物に及ばないというのがその理由である(図45)。
しかし,譲渡担保について,最高裁は所有権的構成から,徐々に,担保的構成へと移行しているのが現状である(〈最一判昭41・4・28民集20巻4号900頁〉(会社更生手続きが開始した場合,譲渡担保権者は,物件の所有権を主張して,その取戻を請求することはできない),〈最三判昭57・9・28判時1062号81頁,判タ485号83頁〉(譲渡担保設定者に,不法占拠者に対する明け渡し請求を認める),〈最二決平11・5・17民集53巻5号863頁〉(譲渡担保権者に抵当権と同じく物上代位の権利を認める),〈最一判平18・7・20民集60巻6号2499頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第98事件)〉(譲渡担保に先順位権者と後順位権者とがともに存在することを認める),〈最二判平18・10・20民集60巻8号3098頁〉(弁済期前の譲渡担保設定者に第三者異議の訴えを認める))。したがって,現在においても,最高裁が,以下のように,民法333条適用説を維持できるかどうかについては,疑問が生じている。
譲渡担保権者は,所有権を取得するのではなく,目的物の占有を設定者から奪うことなく使用・収益を許しつつ,債務者が任意に債務を履行しない場合には,目的物を市場で処分し,そこから自己の債権を優先的に回収する担保権(いわゆる私的実行を許す動産抵当)に過ぎないと考えるべきである(譲渡担保の担保的構成)。そして,譲渡担保を担保的に構成する最近の学説・判例の傾向を重視するならば,譲渡担保に関しては,所有権的に構成することによって民法333条を適用するのではなく,担保的構成にしたがって,民法334条の適用を視野に置くべきである(図46)。
もっとも,民法334条は,譲渡担保ではなく,質権について,それを民法330条1項1号の先取特権とみなす規定であって,譲渡担保に関する規定ではない。しかも,譲渡担保は,質権との対比においては,引渡しを受けていない(占有を伴わない)担保権といわざるを得ないのであり,質権を対象としている民法334条の適用の余地はないとも考えられる。
しかし,民法334条によって準用されている民法330条1項の第1順位の先取特権(黙示の質権)の実態を検討してみると,そこに規定されている黙示の質権の権利者(賃貸人,旅館の店主,運送人)は,担保目的物に対して間接占有を有しているに過ぎず,民法345条によって直接占有を要求されている本来の意味での質権者ではないことがわかる。
動産先取特権の第1順位とされるいわゆる「黙示の質権(gage tacite)」に関する最新の論文(深川裕佳「第1順位の先取特権について-黙示の質権"gage tacite"の法的性質」東洋法学52巻1号(2008)72-91頁)によると,いわゆる黙示の質権(不動産賃貸,宿泊,運輸の先取特権)は,もともとは,農業動産に関する黙示の「動産抵当」から発展したものであるという。そうだとすると,動産譲渡担保は,まさに,「黙示の動産抵当」として,黙示の質権と同様,第1順位の先取特権が与えられてしかるべきことになる。
確かに,民法334条は動産質権を対象にした条文ではあるが,その内容を見ると,動産質権者を民法330条1項1号の先取特権者,すなわち,黙示の質権者とみなすというものである。しかし,民法330条1項1号の黙示の質権者は,本来の質権者とは異なり,目的物に対して間接占有しか有しない債権者であり,間接占有しか有しない譲渡担保権者と同じ立場にあることがわかる。
そうすると,民法334条の適用対象は,一見したところでは,動産質権に限られているように見えるが,民法334条を動産譲渡担保権に類推するが可能となる。むしろ,譲渡担保に関して民法334条を類推適用することこそが,黙示の質権の起源が農業動産の動産抵当(譲渡担保)であったという事実に最もよく適合するとさえいえるのである。
動産売主の先取特権と譲渡担保権との競合に関して,民法330条2項を類推適用すべきであるとの本書の立場に関しては,すでに,千葉恵美子「流動集合動産を目的とする譲渡担保の効力」『担保法の判例Ⅱ』別冊ジュリ(1994)4-5頁,[髙橋・担保物権(2007)60頁]が主張するところと結論において同じである。本書は,この理由づけとして,深川理論に基づき,民法330条1項1号のいわゆる「黙示の質権」には,歴史的に,「黙示の動産抵当」が含まれており,したがって,動産抵当に類似する譲渡担保を民法330条1項1号の先取特権と同順位となることについての別の理由を付加したことになる。
物上代位の制度は,まず,特別先取特権の目的物が滅失・損傷した場合に,それに代わるものとして債務者が損害賠償債権を有する場合には,その損害賠償債権に先取特権を及ぼすことができるという考え方に基づいている。この考え方は,次に,先取特権の目的物に対する追及効が制限されている[民法333条]ことを補完するためも利用される。すなわち,目的物が売却,賃貸によって第三者に引渡され,先取特権の効力が目的物に及ばなくなっても,債務者が目的物の代わりに取得している売買代金債権,賃料債権の上に先取特権が成立するのである[民法304条]。物上代位の制度で重要なことは,以下の2点である。
第1は,これが債権先取特権であるということである。物上代位の目的物は,条文上は,「債務者が受けるべき金銭その他の物」[民法304条1項本文]とされているので,一見したところ,その目的物は,有体物である「金銭その他の物」であるかのように見える。しかし,その前にある「受けるべき」という用語に注意しなければならない。民法が「受けるべき金銭」と規定しているときは,それは,金銭という有体物ではなく,常に金銭債権を意味している([民法314条2文]も同様である)。したがって,民法304条1項本文に規定されている物上代位の目的物としての「債務者が受けるべき金銭その他の物」とは,決して,「金銭その他の物」という有体物ではなく,それは,債務者が受け取るべき金銭=金銭債権(代金・賃料・損害賠償債権),または,それに代わる物(当時はお米が金銭の代用物であった)の引渡債権のことであること,すなわち,いずれの場合も,物上代位の対象は有体物ではなく,無体物としての債権であることを理解しなければならない。
第2は,目的物である債権が弁済等(弁済,相殺等,債権の相対的消滅としての債権譲渡もこれに含まれる)によって消滅する前に「差押え」をしなければならないという点である。物上代位の制度は,優先弁済権を有する担保権者だけに与えられており,その実行は,担保権の実行手続き[民事執行法180条以下]にしたがって行われる。すなわち,物上代位権の実行は,民事執行法193条1項2文で規定されている。その内容は,債権及びその他の財産権についての担保権の実行として,債権者が執行裁判所に担保権の存在を証明する文書(法定文書)を提出し,これに対して執行裁判所が債権差押命令を下すことによって開始することになる[民事執行法193条1項1文,民事執行法143条]。したがって,債権者としては,執行裁判所に先取特権の存在を証明する文書を提出するだけでよい。なぜなら,民法304条に規定されている差押えは,債権者の法定文書の提出に基づいて,執行裁判所が差押命令を下してくれるからである。
最後に,優先順位決定のルールの概略を述べて,先取特権のまとめとする。
先取特権の担保目的物が売却・賃貸・滅失・破損等によって金銭債権等(売買代金債権,損害賠償請求権,保険金請求権等)に転化したときは,これらの上にも効力が及ぶことが目的物の交換価値の減少を防ぐ上で必要となる。そこで,民法304条は,担保物権の目的物に代わる物・金銭にも担保物権の効力が及ぶこととした。これを物上代位と呼んでいる。
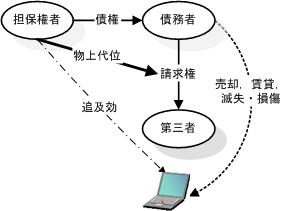 |
| *図79 物上代位の構造 |
物上代位は,イタリア民法起源の制度である。わが国の民法は,ボワソナードが起草した旧民法債権担保編133条の物上代位(subrogation réelle)[Boissonade, Projet(1891)p. 267]の制度を字句の修正を施しただけで,そのまま採用したものである[民法理由書(1987)304条]。したがって,民法304条の物上代位を理解するには,旧民法の規定を含めて理解する必要がある。
旧民法債権担保編 第133条
①先取特権の負担ある物が第三者の方にて滅失し又は毀損し,第三者此が為め債務者に賠償を負担したるときは,先取特権ある債権者は他の債権者に先だち此賠償に於ける債務者の権利を行ふことを得。但其先取特権ある債権者は弁済前に合式に払渡差押を為すことを要す。
②先取特権の負担ある物を売却し又は賃貸したる場合及び其物に関し権利の行使の為め債務者に金額又は有価物を弁済す可き総ての場合に於ても亦同じ。
現行民法304条は,先に述べたように,「既成法典〔旧民法債権担保編〕第133条の字句を修正したるに過きず」とされている。しかし,両者を比較すると,驚くべきことに,旧民法の方が,現行民法よりも遥かに出来がよく,物上代位が債権差押えとされている現在の実務にも適合していることに気づく。なぜなら,現行民法は,物上代位の目的物を「債務者が受けるべき金銭その他の物」としているが,もしも,目的物が有体物である「金銭その他の物」だとすれば,それは,債務者ではなく,第三債務者に帰属しており,債権者である先取特権者が執行できない財産だからである(先取特権には追及効がないのであるから,第三債務者の財産に追及できるはずがない)。これに対して,旧民法の規定は,物上代位の対象を無体物である「債務者の権利〔債権〕」としており,債権者が差し押さえることのできる財産であることが明らかであり,現在の実務にも適合しているからである。
もっとも,民法の起草者の一人である梅謙次郎は,民法304条の物上代位は,先取特権の目的物に代わるべき債権の上に存在するものであり,この先取特権は,物権でないとして,正しい解釈を行っていた[梅・要義巻二(1896)289頁]。
本条〔民法304条〕は,先取特権が其目的物に代はるべき債権の上にも亦存在すべきことを定めたるものなり。此場合に於いては,先取特権は,物権なりと云うことを得ず。
しかも,現行民法の立法者は,債権の上に先取特権を及ぼす場合の表現については,民法314条(不動産譲渡・転貸の場合の先取特権)の場合には,「譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭について」とか,民法旧320条(公吏保証金の先取特権)の場合には,「其保証金の上に存在す」とかいうように,原則として,「受けるべき金銭」に限定しており,そのことによって,先取特権の対象が有体物ではなく債権であることを暗示するように起草していた。
しかし,条文の文言を「債務者が受けるべき金銭その他の物」と表現したことは,上記の旧民法(債権担保編133条)と比較するといかにも不適切であった。これでは,物上代位の目的物が債権ではなく,金銭その他の物(有体物)であるかのように見えてしまうからである。そして,このような不適切な表現が,その後の物上代位の学説に混乱をもたらすことになったのである。
民法304条を理解するには,まず民法304条の要件を理解することから始めなければならない。民法304条の要件は,3つの部分から成り立っている。すなわち,①担保(先取特権)の目的物が責任財産から逸失(売却,賃貸,滅失・損傷)したこと,②逸失した目的物に代わる物(代用物:代金,賃料,賠償金等)が債務者の責任財産に存在すること,③代用物の払渡し又は引渡しの前に担保権者(先取特権者)が差押えをすることである。
物上代位権の行使要件としての差押えの時期に関する「払渡し又は引渡しの前」とは,立法者の意図によれば,「金銭の弁済(払渡し),又は,代替物の引渡しの前」という意味であるが,上記のように,第三債務者に帰属する金銭や代替物を債権者が差し押さえることはできないのであるから,この意味は,「金銭債権の弁済を受ける前または代替物による弁済を受ける前」と解すべきである。そして,厳密には,弁済ではなく,代物弁済・相殺・更改・譲渡を含む,債務の消滅・移転のことである。その理由は,先取特権には追及効がないため,差押えの対象となる債権が消滅したり,移転したりする前に差し押さえなければ,差押えは意味を失うからである。
現行民法304条と旧民法債権取得編133条とを以下のように対比してみると,現行民法304条の不適切な表現のために,通常の解釈では誤りに陥りやすい状況が少しずつ解消されると思われる。
| 物上代位 | 旧民法 [債権担保編133条] |
現行民法[304条] に関する通常の解釈 |
備考(旧民法と現行民法との違い) |
|---|---|---|---|
| 原因の種類 | ①滅失又は毀損 ②売却,賃貸 |
売却,賃貸,滅失又は損傷 | 順序が異なる。(滅失又は損傷は絶対的逸失,売却・賃貸は,相対的逸失) |
| 目的の種類 | 債務者の権利 (無体物) |
債務者が受けるべき金銭その他の物 (有体物と誤解されやすい) |
代物が無体物(権利=債権)か,有体物(金銭その他の物)か,という違いがあるように見える。 |
| 差押えの時期 | 第三債務者による弁済の前 | 金銭の払渡しの前又は物の引渡しの前 | 上記の違いに基づき,債権の弁済か,または,金銭の払渡しか,もしくはその他の物の引渡しか,という違いがある。 |
このように対比してみると,民法304条における「払渡し又は引渡し」の意味が,実は,第三債務者による金銭の払渡し又はその他の物(例えば,賃料としての代替物である米・麦)の引渡しではなく,債務者による目的財産の逸失と牽連性を有する「債権」の弁済(消滅)であることが明らかとなる[我妻・担保物権(1968)284頁,293頁]。そして,先取特権者は,担保目的物の責任財産からの逸失に関して生じた債権に対しても,債権差押えによって優先弁済権を行使することができること,そして,その債権差押えは,第三債務者による「債権」の消滅(正確には絶対的消滅(弁済等)または相対的消滅(移転),すなわち,「弁済,代物弁済,相殺,更改,免除,混同,譲渡」の前にしなければならないことが確定できる。
上記の理解を前提にして,通説(ここでは,通説を代表する[近江・講義Ⅲ(2005)56-67頁]を引用する)の見解を眺めてみると,その問題点がわかるようになる。
通説の解釈は,物上代位の対象に「代償物」という用語を用いており,民法304条の債務者が受けるべき「金銭その他の物」という文言に忠実のように見える。「代償物」という考え方は,物という用語の語感から「金銭その他の物」と同様に,物権の対象である有体物のように思われるからである。
「物上代位」とは,担保物権の目的物が,「売却,賃貸,滅失または損傷」によって,債務者が,金銭その他の物(代償物。Surrogat)を受け取ることになったときは,担保権者はその「代償物」に対しても権利を行使することができる,とする制度である[民法304条本文]。
しかし,この考え方も,実務が物上代位を債権執行としている点を無視するわけにはいかず,結局,物上代位の対象である「代償物」を有体物ではない「債権」であると認めている。
物上代位の「目的物」,すなわち債務者が受けるべき「金銭その他の物」とは,現物自体ではなく,その物に対する「請求権」(債権)を指している。「物」自体に対する効力は,物上代位の問題ではなく,担保権の直接的効力(追及力)の問題だからである。したがって,物上代位権の行使は,具体的には,「債権執行」となる[近江・講義Ⅲ(2005)56頁]。
この点については,民法の起草者も,民法304条の物上代位の場合には,この先取特権は,有体物に対する権利ではないことから,「物権に非ず」としていた[梅・要義巻二(1896)285頁]。
現行民法の立法者と同じく,物権の対象を有体物に限るべきだとしている通説が,物権であるはずの先取特権および抵当権の物上代位の対象を有体物ではない「債権」であるとは認めることは,「物権原則を否定することになる」。そこで,通説は,「代償物に対して担保権の効力が及ぶのは,法律が特別に定めた政策的判断によるものだと考える」[近江・講義Ⅲ(2005)57頁]として,理論的な説明を放棄せざるを得なくなっている。
さらに,通説は,民法304条における「払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない」の解釈において,混乱のきわみに陥っている。
物上代位を行使するには,「差押え」が必要である。このことの意味は,「代償物」が債務者に払い渡される(又は引き渡される)と債務者の一般財産を構成することになるが,担保権は特定物に対する処分権であるから,一般財産に対する処分権限を持たない。したがって,その代償物が債務者の一般財産に混入する(=払渡し・引渡)前に,当該請求権を特定する必要があるということである[近江・講義Ⅲ(2005)58頁]。
この点は,明らかに通説の誤解である。代償物が債権であるとすれば,それは,発生のときから消滅するまで常に特定されており,かつ,債務者の「一般財産に帰属する」からこそ,先取特権者による差押えが可能なのである。しかも,代償物である債権は,金銭その他の物(米,麦等)のような代替物ではないのであるから,「一般財産に混入する」ことはありえない。払渡し・引渡し前に代償物(特定された目的債権)に対して差押えをしなければならない理由は,決して,金銭のように一般財産に混入されてしまうからではない。債権は,払渡し・引渡し(弁済等)によって消滅してしまうから,その前に差押えをしなければならないのである([民事執行法193条1項2文]参照)。
以下の判例〈最一判昭59・2・2民集38巻3号431頁〉は,先取特権者は,債務者が破産宣告を受けた場合であっても,目的債権を差し押えて物上代位権を行使することができると判示したものであるが,物上代位を行使する際に,「金銭その他の払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない」理由を,通説を踏まえた上で,簡潔に表現している点で重要な意義を有している。
最一判昭59・2・2民集38巻3号431頁(供託金還付請求権存在確認請求本訴,同反訴事件)
民法304条1項ただし書きにおいて,先取特権者が物上代位権を行使するためには金銭その他の払渡又は引渡前に差押をしなければならないものと規定されている趣旨は,先取特権者のする右差押によって,第三債務者が金銭その他の目的物を債務者に払渡し又は引渡すことが禁止され,他方,債務者が第三債務者から債権を取立て又はこれを第三者に譲渡することを禁止される結果,物上代位の対象である債権の特定性が保持され,これにより物上代位権の効力を保全せしめるとともに,他面第三者が不測の損害を被ることを防止しようとすることにあるから,第三債務者による弁済又は債務者による債権の第三者への譲渡の場合とは異なり,単に一般債権者が債務者に対する債務名義をもって目的債権につき差押命令を取得したにとどまる場合には,これによりもはや先取特権者が物上代位権を行使することを妨げられるとすべき理由はないというべきである。
この判例は,物上代位の法的性質(学説における特定性維持説,優先性維持説,第三債務者保護説)ばかりでなく,物上代位制度の存在理由を明らかにした優れた判決といえる。「払渡し又は引渡し」の例として,弁済だけでなく,譲渡を含めている点にも注目すべきである。
しかし,この判例においては,全体としては,物上代位の目的が債権(無体物)であることが明らかにされているにもかかわらず,差押えの効力について述べている「第三債務者が金銭その他の目的物を債務者に払渡し又は引渡すことが禁止され」という箇所では,物上代位の目的物を「金銭又はその他の物(有体物)」としており,次に続く,正しい文章である「他方,債務者が第三債務者から債権を取立て又はこれを第三者に譲渡することを禁止される」との整合性が取れていない点が惜しまれる。なぜなら,上記の判決文においては,「金銭その他の目的物の払渡し又は引渡し」という「物の処分」と,「債権の取立て又は譲渡」という「債権の処分」という性質の異なる処分が,なぜ,先取特権者のする差押えによって同時に実現されるのか,わかりにくい表現となっているからである。
上記の判例の考え方(物上代位に基づいて目的債権について優先弁済権を行使する債権者は,たとえ,差押えが競合した場合でも,優先弁済権を保持するという考え方)は,その後の判例,たとえば,〈最二判昭60・7・19民集39巻5号1326頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第82事件)〉(物上代位に基づく転付命令と他の債権者の差押えとが競合したために,第三債務者が供託をした場合の物上代位に基づく優先弁済権の効力を肯定した事例)によっても,そのまま援用されている。
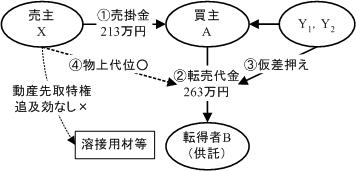 |
差押命令の送達と〔動産売買先取特権に基づく物上代位によって〕転付命令の送達とを競合して受けた第三債務者のした供託が民事執行法156条2項〔第三債務者の供託〕の類推適用により有効である場合において,右供託金について転付命令が効力を生じないとの〔誤った〕解釈のもとに配当表が作成されたときは,効力の生じた転付命令を得た債権者は,配当期日における配当異議の申出さらには配当異議の訴えにより転付命令に係る債権につき優先配当を主張して配当表の変更を求めることができる。 |
| *図80 最二判昭60・7・19民集39巻5号1326頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)第82事件 |
つまり,他の債権者が差押えをした段階では,まだ,債権は消滅していない(いわゆる「金銭その他の物の払渡し又は引渡し」には至っていない)ので,先取特権者は,物上代位による優先権を保持している。したがって,先取特権者は,担保権の存在を証する文書を提出して目的債権を二重に差し押え,配当要求をすることによって,優先弁済権を受けることができることになる。
ただし,物上代位に基づいて債権差押えを行う債権者であっても,配当要求の終期までに,担保権の存在を証する文書を提出して先取特権に基づく配当要求又はこれに準ずる先取特権行使の申出をしなければ,優先弁済を受けることができないのであり,この点は注意を要する〈最一判昭62・4・2判時1248号61頁〉。
さらに,物上代位に基づく優先弁済権の行使には,配当要求では足りず,自ら差押えをすることを要求している判決〈最一判平13・10・25民集55巻6号975頁〉がある点にも注意が必要である。
もっとも,物上代位における差押えを,債権に対する担保権の実行の一つとして考える場合には,差押えの必要性は,目的債権が弁済・譲渡等によって債務者の責任財産から消滅することを防止するために行うためのものに過ぎない。つまり,目的債権に対して,弁済禁止効が生じさえすれば十分なのであり,理論的には,自ら差押えをする必要ことまで要求することの必然性はないというべきであろう[田髙・物権法(2008)233頁]。
先に述べたように,金銭又はその他の物の「払渡し」又は「引渡し」とは,文言上は,「金銭の払渡し,または,その他の物の引渡し」という意味であるが,そのように解すると,先取特権者は,第三債務者の所有する金銭又はその他の物に対して追及効を有することになり,先取特権の物上代位の制度そのものと矛盾してしまう。そこで,金銭又はその他の物の「払渡し」又は「引渡し」とは,目的物の逸失と牽連する債権(代金債権,賃料債権,損害賠償債権)の絶対的消滅としての「弁済」または相対的消滅としての「譲渡」であると解さざるをえない。
判例も,目的債権が譲渡され,第三者対抗要件を備えた場合には,物上代位は行使することができないとしている〈最三判平17・2・22民集59巻2号314頁〉。
もっとも,抵当権に基づく物上代位の場合には,目的債権が譲渡された場合にも,物上代位を行使することができるとしている(〈最二判平10・1・30民集52巻1号1頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第87事件)〉,〈最三判平10・2・10判時1628号3頁〉,〈最一判平10・3・26民集52巻2号483頁〉)。これらの判決は,第三債務者保護説によっており,他の学説から厳しい批判にさらされている。
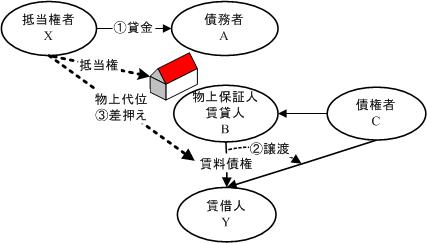 |
民法372条において準用する304条1項ただし書き〔の〕趣旨目的は,主として,抵当権の効力が物上代位の目的となる債権にも及ぶことから,第三債務者は,右債権の債権者である抵当不動産の抵当権設定者に弁済をしても弁済による目的債権の消滅の効果を抵当権者に対抗できないという不安定な地位に置かれる可能性があるため,差押えを物上代位権行使の要件とし,第三債務者は,差押命令の送達を受ける前には抵当権設定者に弁済をすれば足り,右弁済による目的債権消滅の効果を抵当権者にも対抗することができることにして,二重弁済を強いられる危険から第三債務者を保護するという点にあると解される。 右のような民法304条1項の趣旨目的に照らすと,同項の「払渡又ハ引渡」には債権譲渡は含まれず,抵当権者は,物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後においても,自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるものと解するのが相当である。 |
| *図81 最二判平10・1・30民集52巻1号1頁 (取立債権請求事件) 〔第三債務者保護説を採用した判例〕 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第87事件 |
抵当権に基づく物上代位の場合でも,目的債権について,転付命令が出された場合には,もはや,物上代位を行使することができないとされている〈最三判平14・3・12民集56巻3号555頁〉。上記の一連の平成10年判決は,この平成14年判決(転付命令の場合は特例とする)によっては変更されないといわれているが,転付命令の実体法的な意味は,他の債務者への債権譲渡による代物弁済であることは疑いがない。そうすると,上記の一連の平成10年判決は,この判決によって,その本質部分が変更された(対抗力を生じた債権譲渡が生じた場合には,物上代位はもはや行使し得ない)ということができる。
反対から言えば,物上代位に基づく差押えは,目的債権(先取特権の目的物の逸失(消滅・損傷を含む)と牽連して生じる債権(売買代金債権,賃料債権,損害賠償債権等)が消滅(絶対的消滅としての弁済等のほか,相対的消滅としての債権譲渡も含まれる)していない限り,物上代位を行使することができる。つまり,以下の判例が明らかにしているように,目的債権が差し押さえられたり,債務者が破産したりした場合でも,物上代位を行使することができる〈最一判昭59・2・2民集38巻3号431頁〉。
物上代位を規定している民法304条は,先取特権の総則として,先取特権一般について,目的物の売却,賃貸,滅失・損傷の場合に,物上代位が認められるとしている。しかし,一般先取特権,動産先取特権,不動産先取特権のそれぞれの特性を無視して,一律に考えることはできない。
一般先取特権は,債務者の動産,不動産,債権を問わず,すべての一般財産に対して優先弁済権を有するので,物上代位はそもそも問題となりえない(物上代位を認める必要がない)。つまり,民法304条は,一般先取特権には適用されない(学説に異論がない)。
動産の先取特権は,不動産の先取特権については,追及効がないため[民法333条],目的物の売買の場合に,物上代位を認める必要があることについては異論がない。また,目的物の賃貸の場合にも,動産の賃貸は,必然的に目的物の価値の低減を生じることから,目的物の賃料は,目的物の価値の代償物としての性格(物的牽連性)を有する。したがって,賃料債権についても,物上代位を認める必要がある。さらに,目的物の滅失・損傷の場合につき,その損害賠償債権または保険金請求権についても物上代位を認める必要がある。
問題となるのは,売買代金ではなく,請負代金の場合である。大審院は,目的物が売却された場合の売買代金債権に対する物上代位ではなく,目的物が原材料となって仕事が完成された場合の請負代金に対する物上代位については,これを否定していた。しかし,最高裁平成10年判決〈最三判平10・12・18民集52巻9号2024頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)第81事件)〉は,請負工事に用いられた動産の売主は,原則として,請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが,請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を右動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には,右部分の請負代金債権に対して右物上代位権を行使することができるとしている。
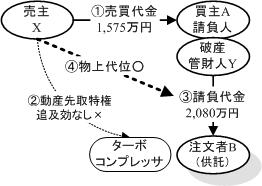 |
甲から機械の設置工事を請け負った乙が右機械を代金1,575万円で丙から買い受け,丙が乙の指示に基づいて右機械を甲に引き渡し,甲が乙に支払うべき2,080万円の請負代金のうち1,740万円は右機械の代金に相当するという事実関係の下においては,乙の甲に対する1,740万円の請負代金債権につき右機械の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情があるということができ,丙は,動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができる。 |
| *図82 最三判平10・12・18民集52巻9号2024頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)第81事件 |
上記の場合に,物上代位を担保目的物が滅失・損傷した場合を中心として,その場合に,「目的物の代償物(Surrogat)に対して」担保物権が及ぶものであるという考え方[近江・講義Ⅲ(2005)56頁]によれば,動産先取特権は,債務者の下にあった目的物が,第三債務者に引渡されて追及効が及ばなくなるのと引換えに,債務者の第三債務者に対する請負代金債権が,それに代わる「代償物」となっているかどうか,すなわち,「新たに発生した請負代金債権が,動産の売却代金債権と『代償』関係にあるかどうか」が問題となる(近江幸治「動産売買先取特権の物上代位(1)-請負代金債権」[民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)165頁])。この考えによると,請負代金債権が物上代位の目的となりうるかどうかについて,上記の最高裁平成10年判決は,物上代位の目的債権が民法304条にいう「売却」代金債権と同視できるかどうかを基準としているので,最高裁の結論を理論的に導き出すことができることになる。
先取特権を物権ではなく,債権の優先弁済権だと考え,物上代位とは,債権者代位権の機能に優先弁済権が付加されたものと考えることができるとする本書の立場に立つと,以下に述べるように,この問題について,何が考慮されなければならないのかが一段と明確になると思われる。
本書の立場に立つと,ここで問題となっている「物上代位の目的の範囲」について,従来の考え方とは異なり,目的物(本件では,ターボコンプレッサ)とそれから転化した目的債権(本件では,請負代金債権)との間の同一性が必要だとか,目的債権は,目的物の変形物(代償物)に限定されるとかいう制約から離れることができる。そして,この問題を物的担保に共通のテーマ,すなわち,「被担保債権と担保目的との間に,優先弁済権を正当化するのに十分な牽連性があるかどうか」という問題として考察することが可能となる。
本件の問題は,「物上代位の目的は,『売却,賃貸,滅失又は損傷』以外の債権,例えば,『請負』の報酬債権にも適用可能か」という問題として要約することができるが,本書の立場によれば,この問題についても,被担保債権(本件では,売買代金債権)と,債務者の第三債務者に対する目的債権(本件では請負代金債権)との間の牽連性の問題として考察することが可能となる。
そのように考えると,本件の場合,被担保債権である売買代金債権(α債権)と目的債権である請負代金債権(β債権)との間には,「β債権(2,080万円)=α債権(1,575万円)+労務の提供(505万円)」という図式が成り立っており,両者には強い牽連性が認められる。別の観点からいえば,被担保債権(α債権)は,目的債権(β債権)の維持・増加に大きく寄与していることが明らかである。したがって,α債権の債権者に対して,β債権に対する優先弁済権(物上代位権)を与えることが正当化できる。
不動産の先取特権の場合には,動産先取特権と異なり,抵当権と同様に追及効があることが考慮されなければならない。したがって,目的物の売却の場合には,抵当権の場合と同様,物上代位を認める必要はない。また,目的物の賃貸の場合も,土地の賃貸借の場合は,賃貸によって目的物の価値が減少することはないので,物上代位を認める必要はない。ただし,目的物が建物の場合は,動産の賃貸の場合と同様,賃貸によって価値が低減し,家賃は,目的物の価値のなし崩しという意味をもつため,物上代位を認める必要がある。目的物の滅失・損傷の場合に物上代位を認める必要があることは,動産先取特権の場合と同様である。結果的には,不動産先取特権の物上代位の要件は,抵当権の物上代位の要件と同一である。
先取特権は,物的担保共通の消滅原因(被担保債権の消滅に伴う付従性による消滅,担保権の実行による消滅)によって消滅する。また,動産を目的とする先取特権は,民法333条により,その目的動産が第三取得者に引渡されることによって消滅し,不動産を目的とする先取特権の場合には,抵当権の規定が適用されるため[民法341条],代価弁済[民法378条]または抵当権消滅請求[民法379-386条]によって消滅する。
先取特権の3要素は,被担保債権,目的物,優先順位である。このうち,優先順位については,民法は,一般先取特権,動産先取特権,不動産先取特権について別々に規定しているだけである。また,先取特権とその他の物的担保のとの優先順位についても,動産質権,抵当権に関して個別の規定を有するだけで,統一的な優先順位決定のルールを明らかにしていない。しかし,動産先取特権の優先順位に関する民法330条は,非常に示唆的な規定であり,ここで明らかにされている「後の保存者は,前の保存者に優先する」というルールは,見方によっては,不動産先取特権における不動産保存の先取特権と不動産工事の先取特権の順位にもその考え方が応用されているし,果実に関する先取特権について民法330条3項が,「第1の順位は農業の労務に従事する者に,第2の順位は種苗又は肥料の供給者に,第3の順位は土地の賃貸人に属する」と規定していることも,この考え方によって説明可能である。なぜなら,この順序は,①農地という環境の設定→②種苗または肥料の供給→③農業労務による収穫・保存という作業の流れと全く逆の順序となっており,「後の保存者は前の保存者に優先する」という法理に適合的だからである。
本書の仮説である第1順位:保存の先取特権,第2順位:供給の先取特権,第3順位:環境設定の先取特権という順位にしたがって,民法330条1項,2項の動産先取特権の優先順位を読み解いてみよう。まず,本来は,環境設定の先取特権(黙示の質権)は,第3順位の先取特権に過ぎないが,この先取特権には,民法319条が適用される。このため,第3順位の先取特権者(黙示の質権者)が保存・供給の先取特権について善意・無過失の場合には,第3順位から第1順位へと昇進して,第1順位の先取特権となる(民法330条1項の順序となる)。しかし,供給の先取特権についてのみ善意・無過失の場合には,民法319条によって第2順位となりうるが,その他の場合には,原則どおり,第3順位となる(民法220条2項の結果と同じになる)。
| 類型 | 権利者 | 順位 | 順位の変動 | 順位内での優先関係 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 般 |
共益費用 | 共益費用負担者 | 第0[民法329条2項] | なし(常に第1順位)[民法329条2項ただし書き] | 平等[民法332条] | |
| 動 産 ・ 債 権 |
環境提供 | 不動産賃貸人, 旅館主,運送人 (黙示の質権者) |
第1[民法330条1項1号] | 悪意の場合には,第3順位まで順位が下降する[民法330条2項] | 平等[民法332条] | |
| 質権者 | 第1[民法334条] | |||||
| 保存 | 保存者 | 第2[民法330条1項2号] | 第1順位まで順位の昇進あり[民法330条2項] | 後の保存者が先の保存者に優先する[民法330条1項2文] | ||
| 供給 | 売主, 譲渡担保権者 |
第3[民法330条1項3号] | 第2順位まで順位の昇進あり[民法330条2項] | 先の設定者が後の導入者に優先する[民法331条の類推] | ||
| 不 動 産 |
保 存 |
後の 保存 |
保存者 | 第1[民法331条1項] | 登記をすると,先に登記をした抵当権に優先する[民法339条]。登記をしない場合には,登記をした第3順位にも劣後する。 | 後の保存者が先の保存者に優先する[民法330条1項2文の類推] |
| 先の 保存 |
工事者 | 第2[民法331条1項] | ||||
| 供給 | 売主 譲渡担保権者, 抵当権者 |
第3[民法331条2項] | 売買契約と同時に登記が必要[民法340条]。第1順位者が登記をしない場合には,第1順位となる。 | 先の設定者が後の導入者に優先する[民法331条2項] | ||
| 果 実 |
保存 | 農・工業労務提供者 | 第1[民法330条3項] | 変更なし[民法330条3項] | 平等[民法332条] | |
| 供給 | 種苗・肥料の供給者 | 第2[民法330条3項] | ||||
| 環境提供 | 土地賃貸人 | 第3[民法330条3項] | ||||
| 一 般 |
供給 環境提供 |
雇用者 | 第4[民法329条] | 変更なし[民法329条] | 平等[民法332条] | |
| 葬式備品供給者 | 第5[民法329条] | |||||
| 日用品供給者 | 第6[民法329条] | |||||
先取特権の優先順位決定のルールは,上記のように,典型担保権ばかりでなく,非典型担保権にも応用が可能である点でも有用である。
質権は,法律上の優先弁済権を有するだけでなく,質権設定者(債務者または物上保証人)から目的物の使用・収益権を奪い,その留置的効力によって設定者に心理的な圧迫を加えることを通じて,優先弁済権がさらに強化された物上担保である。
しかし,皮肉なことに,この強力な留置的効力があだとなって,質権の利用状況は,近年では,著しく低下している。質権として利用できる物は,結局,設定者が通常利用しない物に限定されるからである。これとは逆に,質権設定者の使用・収益権が奪われない(留置的効力のない)質権,例えば,指名債権質,知的財産に対する質権(設定者は実施権を奪われない)の利用率は高くなっている。しかも,このような債権者が留置的効力を有さない(非占有質)は,その実質は,質権ではなく,権利の上の抵当権である。
ここでは,質権は,無担保金融(サラ金)と比較した場合に安全な庶民金融としての役割を果たしつつ,設定者から使用・収益権を奪わない抵当権へと次第に変異していく運命にあること,その意味でも,次節で述べる権利の上の抵当権(民法上は[民法369条2項]に限定されている)が,ますます重要となってくることを明らかにする。
質権とは,債権者と債務者または債権者と第三者(物上保証人)との間で,債権者が債権の引当てとなる特定の財産から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けることを合意し,かつ,その財産を債権者から受け取ることによって債権の優先弁済権を確保するものである[民法342条]。
質権を有する債権者は,被担保債権が弁済されるまで,その物を留置することができ[民法347条],その留置作用によって債務の弁済を間接的に強制することができる。それでもなお債務者が債務を弁済しない場合には,債権者は,目的物を競売し,その売得金から他の債権者に先立って弁済を受けることができる。そこで,質権は,当事者間の契約(債権者と質権設定者との間の質権設定契約)によって生じる約定の担保物権であるとされてきた。
ところで,質権には,動産質,不動産質,権利質の3つの種類がある。上記の質権の定義[民法342条]は,第1の動産質および第2の不動産質には当てはまるが,第3の権利質には,正確には当てはまらない(権利質の場合には,債権者は,必ずしも,対象となる権利を受け取る必要がない[民法363条,364条]。そこで,民法は,質権の総則,動産質,不動産質のそれぞれの規定を権利質に「準用」しているだけであり[民法362条2項],債権質には,質権の定義(冒頭)条文[民法342条]についても,正確に「適用」されるわけではない点に注意が必要である。
なお,民法362条2項が,質権の総則を権利質に「準用する」という表現を用いたのには,先に述べたように,深い意味がある。すなわち,物権の対象は,原則として有体物[民法85条]に限定されるべきであり,本来なら,権利(債権を含む)の上に物権を設定することはできない。なぜなら,権利の上に物権を設定することを認めると,債権の上の所有権をも認めざるを得なくなり,そうすると,物権と債権とを区別している現行民法の体系が破壊されてしまうからである。民法の起草者は,このことをおそれて,権利質を物権とすること,特に,債権質を物権と認めることをはばかり,権利質については,質権の総則を「適用」するのではなく,「準用」することにしたのである。
質権は,当事者間の合意で発生(設定)される物的担保であり,その点では,後に検討する抵当権と同じである。しかし,質権と抵当権との違いは,大雑把に言えば,イソップの寓話における,「北風と太陽」とが採用する戦略に似ているところがある。
質権は,人質とまではいかないが,債務者または物上保証人から目的物の占有を奪って不自由を感じさせ,心理的に圧迫して債務の弁済を促すというものである(大切なものを奪い,それを返してほしければ,借金を返せという戦略)。これに対して,抵当権は,債務者または物上保証人に目的物の占有を許し,むしろ,それを使用・収益させて,その収益から間接的に債務の弁済を促進するというものである(大切なものを取り上げず,むしろ,それをうまく使って収益を得て,借金を返せという戦略)。
担保とは,もともと,債務の履行を確保するためのものであるから,債権者がとる戦略としては,所有者から占有を奪って,目的物の使用・収益を禁じるよりも,所有者に目的物を使って使用・収益を行わせ,そこから弁済を確保する方が勝っていると思われる。つまり,使用・収益できるものは,それをする方が効率的である。質権の目的物が,債務者や物上保証人が普段使用しない古着,装飾品,骨董品等に集約されていくのは,当然といわなければならない。目的物が使用・収益に適した物である場合には,そして,目的物に関する公示が可能である場合には,質権は,基本的に,抵当権に劣るといわなければならない。
通説によれば,質権は,債権者が目的物を占有する(反対からいえば,債務者は占有を剥奪される)物的担保であり,抵当権は,債権者が目的物の占有をしない(反対からいえば,債務者または物上保証人が占有を継続する)物的担保であるというものである。例えば,[近江・講義Ⅲ(2005)10頁]は,質権と「抵当権との差異は,目的物の占有の移転の有無と考えてよい」としている([内田・民法Ⅲ(2005)487頁],[田髙・物権法(2008)184頁])。
| 債権者による目的物の占有の有無 | |
| 質権 | あり |
| 抵当権 | なし |
しかし,債権者が目的物の占有をするかしないか(占有担保か,非占有担保か)という基準によって質権と抵当権との区別をすることには,限界がある。特に,権利質に関しては,質権は,必ずしも,目的である権利を占有する必要がないため[民法363条,364条],同じく権利の上に設定される地上権または永小作権を目的とする抵当権[民法369条2項]との区別が不明確となる。すなわち,権利質については,抵当権と同じく,いわゆる「非占有型担保」がありうる。
| 目的(物) | 債権者による目的物の占有の有無 | |
| 質権 | 動産質 | あり |
| 不動産質 | ||
| 権利質 | なし | |
| 抵当権 | 不動産 | なし |
| 地上権又は永小作権 |
そこで,質権と抵当権との区別の基準を変更する必要が生じる。区別の基準が問題となるのは,権利を目的とする質権[民法362条以下]および権利(地上権または永小作権)を目的とする抵当権[民法369条2項]の場合である。
そもそも,「物とは有体物をいう」[民法85条]とする民法の立場からすると,権利(有体物ではない)を占有すると考えることには無理がある。確かに,民法205条は,物の占有を伴わない財産権について,準占有という概念を用いて,占有の規定を準用するとしている。しかし,権利の行使が当然に目的物の占有を伴う場合には,準占有は成り立たない。たとえば,所有権,地上権,永小作権,賃借権,質権の場合には,その権利を行使すれば当然に占有そのものが成立するのであるから,準占有は問題とならない。
もっとも,鉱業権や知的財産権等に関しては準占有[民法205条]を問題にすることは可能であるが,民法の規定が準用されるかどうかは個別的に検討しなければならず,必ずしも,占有の規定が準用されるとは限らない。たとえば,準占有については,善意取得の規定[民法192条~194条]は準用されないと解されている〈大判大8・10・2民録25輯1730頁〉。さらに,通常の債権の場合,特に1回で消滅する債権の場合には,準占有は問題とならない。また,債権の準占有者[民法478条]という概念は,債権者であるとの外観を呈していることをいうのであって,目的物に対する事実上の支配という意味での占有ではない。
このように考えると,財産権に関する質権と抵当権との区別の基準を「占有」に求めることは無理がある。占有を区別の基準としていたのでは,権利質と権利(地上権・永小作権)の上の抵当権とを区別することができないからである。
財産権に関する質権と抵当権との区別を明確にするためには,使用・収益の主体に着目すべきであり,「債権者」が目的物を占有しているかどうかではなく,以下のように,「債務者または担保設定者」が目的物に対して使用・収益権を有するかどうかで区別すべきだということになる。
| 目的物 | 設定者の目的物の使用・収益権 | |
| 質権 | 動産質 | なし(奪われる) |
| 不動産質 | ||
| 権利質 | ||
| 抵当権 | 不動産 | あり(奪われない) |
| 地上権又は永小作権 |
従来の考え方とは若干異なるが,質権と抵当権との区別の基準を(債権者の)占有の有無ではなく,(担保設定者,すなわち,債務者または物上保証人の)使用・収益権の有無であると考えると,不動産の地上権または永小作権に対する担保権が,権利質ではなく,抵当権でなければならないということ,すなわち,民法369条2項(地上権及び永小作権を目的とする抵当権)の存在理由も見えてくる。その理由がどのようなものなのかは,権利質の箇所で詳しく検討するが,以下に結論だけ示しておく。
地上権または永小作権は,使用・収益のみを目的とした権利であり,その使用・収益権を債権者が設定者(債務者または物上保証人)から奪ってしまうと,権利そのものが意味を失ってしまうため,使用・収益権の場合には,質権の設定が制限されざるを得ない。例えば,権利者自身がその権利を行使することを要請されている権利については,質権の設定は禁じられている[鉱業法13条,72条,漁業法23条2項]。確かに,観念的には,地上権または永小作権の上に質権を設定することは可能である(例えば,旧民法債権担保編118条は,地上権に対する不動産質権の設定を認めていた。ただし,現行民法の立法者は,以下のように述べて,地上権に対する質権の設定を否定している[民法理由書(1987)346頁])。
(理由)債権担保編第118条は不動産売の目的物及び質権設定の能力を規定せり。然れども,不動産質の目的の何たるは敢て之を言ふを要せず。質権設定の能力に付きても亦た特に明文を設くるの必要を見ざるなり。彼の地上権の如き権利を以て質権の目的と爲す場合に至りては,次節〔抵当権〕に於て之を規定する処あり。是れ同条を削りたる所以なりとす。
現行民法が,地上権・永小作権につき,民法369条2項において,権利質ではなく抵当権の設定を認めたのは,地上権の本質が不動産の使用・収益にあり,債務者から使用・収益権を奪うことになる質権よりも,債務者の使用・収益を許す抵当権を認める方が用益権の制度目的に適合すると考えたためと思われる。
そして,このことは,特許権,実用新案権,意匠権,著作権等のいわゆる無体財産権を担保にする場合に,債権者は無体財産権に対して質権を設定できるが,この質権は,実は,債権者による使用・収益権が制限され,債務者が使用・収益をすることが認められている([特許法95条],[実用新案法25条],[意匠法35条],[著作権法66条])。このため,これらの質権の実質は,「質といっても抵当と差はない」[我妻・担保物権(1968)106頁]ということになる。
質権は,先に述べたように,原則として,目的物を留置し,設定者(債務者または物上保証人)に心理的圧迫を加えて弁済を促進することができる。したがって,優先弁済権を利用しなくても,留置的効力のみによってその目的を達することが可能である。したがって,理論的には,法律上譲渡できないものでも,設定者にとって重要な値打ちのあるものであれば,その占有を奪って質権の目的物とすることも不可能ではない。しかし,民法は,質権の優先弁済権を重視し,目的物の譲渡可能性を質権の不可欠の要素としている[民法343条]。すなわち,優先弁済権の確保は,競売等によって行われるため,債権の引当てとなる財産(「目的物」という)は,原則として,譲渡性のあるすべての物,譲渡性のあるすべての権利を対象とすることができる[民法343条の反対解釈]。
ただし,特別法によって,動産抵当制度が設けられている動産について質権の設定が禁止されている場合には([自動車抵当法2条,20条],[商法850条],[航空機抵当法23条],[建設機械抵当法25条]など),質権を設定することができない([我妻・担保物権(1968)101-102頁]の対照表がわかりやすい)。さらに,先に触れたように,地上権または永小作権を担保にする場合には,質権ではなく抵当権を設定しなければならないのと同じ理由で,権利者自身がその権利を行使することを要請されている権利については,質権の設定は禁じられている[鉱業法13条,72条,漁業法23条2項]。
これに対して,抵当権は,登記によって優先弁済権を公示するものであるから,目的物が,登記が可能な物または権利に限定される。民法は,不動産および地上権・永小作権のみを抵当権の目的物としているが,各種動産抵当制度(農業動産信用法,自動車抵当法,航空機抵当法,建設機械抵当法)によって,登記・登録のできる動産も抵当権の目的物とする道が開かれており,さらに,各種財団抵当制度(工場抵当法,鉱業抵当法,軌道抵当法,運河法,漁業財団抵当法,港湾運送事業法,道路交通事業抵当法,観光施設財団抵当法)によって,特定の不動産ばかりでなく,有機的な統一体としての企業財産全体を目的物とすることも可能となっている。それでもなお,登記・登録になじまない物および権利は,依然として,抵当権の目的物とすることができない。
このように,質権と抵当権とを比較すると,先に述べたように,抵当権よりも質権の方が,目的物としてとりうる対象範囲は格段に広い。しかし,現実には,先に述べた理由のほか,質権は目的物の占有を債権者に移さなければその効力が発生せず,かつ,占有を失うと対抗力を失うため,実際には,目的物の範囲はかなり限定されてしまう。例えば,機械,器具等の企業の生産手段の占有を債権者に移転すると企業活動が停止してしまうので,これらの動産を質権の目的物とするわけにはいかない。また,不動産質は,債権者が不動産の管理をしなければならないため,現実には,ほとんど利用されていない。したがって,現実に質権の対象とされているは,下の表に掲げるように,他人に引き渡しても生活が成り立ちうる衣服,宝石,時計,骨董品等を対象とする動産質および有価証券,無体財産権等の財産権を対象とする権利質である。
| 種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 質権の目的物 | 動産 | 衣服,宝石,時計,骨董品など |
| 不動産 | 土地,建物など | |
| 権利 | 債務者の第三債務者に対する債権など |
もっとも,このような事態は,平成10年(1998年)6月12日に成立し,平成10年10月1日施行された債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(債権譲渡特例法)が,平成17年(2005年)7月26日に改正され,平成17年10月1日から施行されている「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(動産・債権譲渡特例法)によって変化がもたらされつつある。この法律によって,法人が譲渡人となる動産及び債権について登記を対抗要件とすることができるようになったからである。この法律は,動産及び債権を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため,法人がする動産の譲渡につき登記による新たな対抗要件の制度を創設するものであるが,この法律によって利用できる担保は,現在のところ,動産譲渡担保と債権譲渡担保,債権質に限定されている(動産質権の設定には利用できない)。しかし,譲渡担保は,抵当権と同じような働きをするものであり,動産及び債権について登記が可能となったことは,動産及び債権に対する抵当権の設定も夢ではなくなったわけであり,将来的には抵当権の対象がすべての物に拡大する可能性をもたらしているといえよう。
ところで,消費者金融の観点から,質権を再評価すべき事態が生じている。質屋営業法2条1項に基づく許可件数は,1958年の2万1,539件をピークに減少を続け,2007年末における質屋営業の許可件数は,3,579件となっている(http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki79/h19_kobutsu.pdf)。これは,無担保でローンができる消費者金融の発展の影響である。しかし,無担保で融資を行う場合には,過剰融資が原因で,いわゆるサラ金地獄,カード破産等の消費者被害が発生するというという深刻な問題が発生している。この点,質屋による融資は,質物に預けることのできる担保物の限度に限られており,担保物を失う以上の損失が生じるおそれがないため,安全な庶民金融として再評価がなされている。
債権の引当てとなる特定財産を指定して,債権者が,その特定財産から他の債権者に先立って優先的に弁済を受けうることを約し,この優先弁済権を確保するため,特定財産を債権者に引き渡すことを「質権の設定」と呼んでいる[民法344条]。
[高木・担保物権(2005)57頁],[近江・担保物権(1992)73頁)])は,質権の設定行為を物権契約であると解している。しかし,少なくとも,債権質については,その物権性を否定する現行民法の立法者の立場からは,物権契約ではありえないということになる。動産質,不動産質についても,特定財産を引当てとして債権に優先弁済権を付与し,これを公示する債権行為であって,債権譲渡,不動産賃貸借の登記と同様,物権契約と考える必要はない。もっとも,物権契約(物権行為)の意味をドイツ流に,単なる「処分行為」の意味で使うのであれば,これらすべてを物権契約または物権行為ということが可能である。しかし,債権譲渡等を処分行為ではなく物権行為というのは,用語法として不適切であろう。
質権の設定は,(1)目的物からの優先弁済権を債権に付与する合意および(2)目的物の引渡という2つの行為からなる。優先弁済権の付与の合意だけで質権の効力が発生するとすれば,それは諾成契約であり,合意のほかに引渡行為も必要だとすると要物契約ということになる。
質権設定契約が諾成契約だとすると,質権者は,質権の設定契約の後に,債務者または物上保証人に対して目的物の引渡を求める請求権を有するということになる。これは,民法344条の文言に抵触するおそれがあるばかりでなく,代理占有の禁止を規定する民法345条の規定との整合性が問題となる。したがって,通説([我妻・担保物権(1968)129頁],[高木・担保物権(2005)62頁],[近江・講義Ⅲ(2007)89頁])においては,質権設定は,目的物の引渡を要する要物契約と解している。
しかし,将来質権を設定しようという合意も当事者を拘束するから,要物性ということをとくに強調する必要はないとする見解([鈴木・物権法(2007)324頁])も存在する。確かに,質権設定契約は,(1)目的物からの優先弁済権を債権に付与する合意で成立し,(2)目的物の引渡と占有の継続を優先弁済権の対抗要件とすることで足りるのであるから,質権を要物契約とする必要はないと思われる。
最近の有力説も,合意のみで質権設定契約は成立し,質権者は質権設定者に対する目的物の引渡請求権を有するに至ると解している([道垣内・担保物権(2008)81-82頁],また,[内田・民法Ⅲ(2005)489頁],[平野・民法総合3(2007)220頁],[山野目・物権(2009)224頁])も,要物契約性には疑問を持つとしている)。質権の典型とされる動産質に関して,民法352条が質物の占有の継続を対抗要件として要求していることを重視するならば,質物の占有,および,その継続は,質権の成立要件でも効力要件でもなく対抗要件であると解するのが,担保法全体の体系という観点からは一貫しているといえよう。
質権の効力で最も重要な点は,第三者に対抗できる優先弁済権であり,占有を伴わない質権は,結局のところ,優先弁済権を第三者に対抗できないことになるのであるから,上記のように解しても,民法344条の「目的物を引渡すことによって,その効力を生じる」という文言にも反しないということができる。「その効力を生じる」の意味を「対抗力を生じる」と解することが可能だからである。
質権の目的物については,譲渡性が必要とされる等の制限があるが,質権の設定によって優先弁済権を取得する債権(被担保債権)の種類には,制限がない。一般的には金銭債権に対して質権が設定されるが,「金銭に見積もることができない」債権[民法399条]に質権を設定することも可能である。それらの債権も,質権の留置作用によって担保しうるからである。また,それらの債権が債務者の債務不履行によって金銭債権に転化すれば,優先弁済権によっても担保される。
質権設定契約は,通説によれば,要物契約であり,将来質権を設定しようという合意だけでは質権は効力を生じないとされている。しかし,質権設定の合意と目的物の引渡があれば,質権によって担保されるべき債権自体は,将来発生する債権でもよい。すなわち,被担保債権は,質権設定時に現存する債権であることを要しない。
将来において発生・消滅を繰り返す債権群(不特定債権)を担保すること,すなわち,「根質」も可能である。「根」という概念は,「枝葉は違っても根は同じ」,「枝葉は枯れても根は残る」という喩えから,一定の継続的な取引関係から生じて増減変動する多数の債権を枠に入れてその枠内で変動する債権を対象とする場合に用いられるものである。根担保についても付従性が問題となる。しかし,枠内で変動する債権については付従性は問題とならず,担保権の確定によって枠がはずされると,確定した債権との間では担保権の付従性の問題が復活するのであって,根担保について,付従性の問題がなくなるわけではない。この問題については,根抵当のところで詳しく論じることにする。
質権の被担保債権の範囲については,民法346条に規定がある。質権の被担保債権の範囲は,質権設定契約に別段の定めがない限り,債権者である質権者の有する元本,利息(不動産質の場合には,特約がない限り利息を請求できないし[民法358条],その特約を登記しないと第三者に対抗できない[不動産登記法95条]),違約金(不動産質の場合には,登記しなければ対抗できない[不動産登記法95条]),質権実行の費用[民事執行法194条,42条],質物保存の費用[民法350条による,民法299条(留置権による費用の償還請求)の準用],債務不履行による損害賠償[民法415条]および質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償(質物の瑕疵拡大損害)についての請求権に及ぶ。
このような質権の被担保債権の範囲は,抵当権の被担保債権[民法375条]と比較すると,相当に広い。この理由については,質権者が目的物を占有するため,後順位質権者が生じることがまれであり,被担保債権の範囲を広く認めても第三者を害することがほとんどないからであると考えられている。
質権の設定は,債権者と債務者との間だけでなく,債権者と第三者との間でもなすことができる(民法342条は,債務者または第三者という表現を用いている)。質権の設定が債務者以外の第三者によってなされた場合,この第三者を「物上保証人」と呼んでいる。
物上保証人が債務者の債務を債務者に代わって弁済したり,質権の実行によって質権の目的物の所有権を失った場合のように,自らの弁済によって債務を消滅させた場合には,保証人が主債務者の債務を弁済したときと同じ関係が発生する。そこで民法は,物上保証人が,保証に関する規定に従って,債務者に求償権を行使することを認めている[民法351条]。
物上保証人の法的地位については,*第4章第1節(人的担保総論)2で詳しく論じているので,ここでは繰り返さない。
質権の対抗要件は,動産質権の場合には,占有の継続[民法352条]であり,不動産質権の場合は,目的物の引渡しと登記([民法361条],[不動産登記法3条6号])であり,権利質の場合には,(i)指名債権質については,債務者への質入れの通知または債務者の質入れの承諾[民法364条],(ii)記名社債質については,質権者の氏名・住所の社債原簿への記載と質権者の氏名の社債券への記載[会社法688条],(iii)記名国債については,証書の継続占有(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律,民法362条2項,352条),(iv)指図債権質については,質権設定の裏書と交付[民法365条,363条]となっている。
以上のように,質権の対抗要件は,動産質,不動産質,権利質によって,同一ではない。したがって,対抗要件の詳しい説明は,それぞれの質権の箇所で個別的に論じることにし,ここでは,質権の基本形としての動産質の対抗要件について,以下でその基本的な考え方を説明する。
動産質を通説に従い物権と考えると,物権の対抗要件は,民法176条によれば引渡(占有の移転)であり,いったん引渡を受ければ,それで対抗力を取得するはずである。そして,たとえ占有を奪われたとしても,物権の権利者は,占有訴権の外に,物権的請求権に基づく返還請求ができるはずである。
ところが,動産質権の場合,対抗要件は,一般原則とは異なり「占有の継続」である。したがって,質権者がひとたび占有を喪失すると,留置権の場合と異なり,質権自体は消滅しないものの,第三者に対する対抗力を失うため,優先弁済権を発揮することができなくなる。
しかも,質権者が,質物の占有を喪失した場合,質権者は,占有回収の訴え[民法200条]によってしか質物の返還を求めえない[民法353条]。物権であるはずの質権は,いわゆる物権的請求権を持たないのであり,この点でも,動産質権を物権と構成することには問題があるといえよう。
通説は,質権を物権であると主張し,物権である質権に物権的返還請求権が与えられていないのは疑問であるとして,このことは,「動産質権の物権性を弱めるものとして立法の当否が問題とされている」[高木・担保物権(2005)59頁]と論じている。
しかし,「物権である以上こうあるべきだ」という議論は,あまり建設的ではない。たとえ質権が物権だとしても,物権にも,先取特権のように占有を伴わないものなど,いろいろな種類が存在するのであって,質権者が占有を喪失した場合に,いかなる回復手段を与えるのが相当であるかを具体的な利益衡量によって明らかにすべきであろう。通説の立場に立つ場合には,同じく物権とされている留置権の場合には,占有を喪失すると権利自体が消滅するとされている[民法302条]ことについて,なぜ質権の場合のように「立法上の当否」を問題としないのかについても再検討すべきであろう。
質権者が目的物を自発的に返還した場合には,留置権の場合とは異なり,質権自体は消滅しないが〈大判大5・12・25民録22輯2509頁〉,質権は対抗力を失い,他の債権者に対して優先弁済権を主張しえなくなる[民法352条]。
ところが,通説は,「動産質権者は,継続して質物を占有しなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない」という民法352条の文言にもかかわらず,質権者が目的物を自発的に返還した場合には,質権の対抗力が失われるだけでなく,質権自体が消滅するとしている([内田・民法Ⅲ(2005)492頁])。
留置作用は質権の本質的効力であり,民法345条(占有改定の禁止)を潜脱する行為を封ずる必要があるからというのがその理由であるが,ドイツ民法1253条1項が,「質権は,質権者が質物を質権設定者または所有者に返還したときは消滅する。質権存続の留保は無効とする。」と規定していることが影響を与えていると思われる[我妻・担保物権(1968)130頁参照]。
しかし,占有を失った動産質権は対抗力を失い,他の債権者に優先して弁済を受ける権利を失うのであるから,質権自体は消滅しないとしても,民法345条が潜脱されるおそれは全くない[山野目・物権(2009)225頁]。ドイツ民法が,「質権者が質物を質権設定者または所有者に返還したときは消滅する」と規定していたとしても,ドイツ民法は,フランス民法と異なり,対抗要件の制度を知らないために,そのように規定するほかないのであって,わが国のように,対抗要件の制度を有する場合は,それに倣う必要はない。
質権を物権と考えると,すでに述べたように,動産質に関しては,対抗要件が引渡ではなく占有の継続であるため,一般の物権変動の対抗要件との間に齟齬が生じ,しかも,質権者が占有を失うと,第三者に対して質権に基づく返還請求権を行使しえないなど,追及効のない不完全な物権[高木・担保物権(2005)56頁]ということになってしまう。
この点,質権を設定者の使用・収益権を奪うことによって債権者が目的物に対して優先弁済権を取得する約定の物的担保であると考えると,すでに詳しく述べたように,質権における物的担保の通有性をすべて無理なく説明することができる。
質権の最初の箇所で述べたように,質権は,留置的効力と優先弁済権という2つの機能を持つことによって,他の物的担保と区別されている。留置的効力を裏付けるのが,質権設定者にようる代理占有の禁止[民法345条]であり,優先弁済権の実現のための強制競売権を裏付けるのが,民法342条および民事執行法の規定[民事執行法180条以下]である。
質権の目的物の返還請求に対しては,留置権の場合とは異なり,引換給付判決[民事執行法31条1項]ではなく,原告(債務者,所有者)の敗訴判決が下される。このことは,留置権の場合には同時履行の抗弁権と同じく引換給付判決が下されるのに対して,質権の場合には債務者側に敗訴判決が下されるのはなぜかを問うことになる点で,重要である。その答えは,留置権は,同時履行の抗弁権と同じく,履行拒絶の抗弁権であって,積極的な権利ではないからであり,これに対して,質権には,競売権を含めて,積極的な権利としての法律上の優先弁済権が認められているからである。
しかし,そのことは,逆説的ではあるが,留置権に比べて質権の効力を弱める結果を生じさせている点に留意すべきである。留置権は,引換給付判決を得ることができるに過ぎない権利ではあるが,相手方の目的物の引渡請求に対して,自らの債権が満足されるまでは,どのような権利者に対しても留置的効力を主張することができる[民事執行法124条,190条]。そればかりでなく,不動産の場合のように,留置権者の意に反して目的物の強制執行が行われたとしても,留置権者は,買受人に対しても,自らの債権の弁済を受けるまで,目的物を留置することが認められている[民事執行法59条4項,188条]。このように,留置権は,事実上の優先弁済権を有しているに過ぎないが,債権の回収という観点から見ると,留置権は,実質的には,最高順位の優先弁済権を有しているといえる。
これに対して,質権の場合には,法律上の優先弁済権を有するにもかかわらず,その優先権の順位が常に最高順位とは限らないために,その留置的効力に制限が課せられている[民法347条ただし書き]。この点は,重要な問題であるので,以下で詳しく検討する。
質権に優先する権利を有する者がいる場合には,その質権の留置的効力は,優先権を有する債権者に対抗することができない[民法347条ただし書き]。この民法347条ただし書きは,2つの点で重要な意味を有している。
第1は,例えば動産質に関しては,その優先順位は,第1順位の先取特権と同一の権利を有するとされており[民法334条],最優先順位を確保しているようにみえる。それにもかかわらず,第1順位の先取特権であっても,さらに,それに優先する権利があることを再確認させる点で重要である。
民法347条ただし書きにいう,質権に対して「優先権を有する債権者」とは,以下の権利者(通説によると物権を有する者)である。
民法347条ただし書きの「優先権を有する債権者に対抗できない」,すなわち,「留置的効力を主張できない」という意味は,質権に優先する上記の優先権を有する権利によって強制執行,担保執行が行われた場合には,質権者はその引渡しを拒絶することができないこと,したがって,質権者は,売却代金から優先権の順位に従って配当をうけることができるに過ぎないことを意味する。
なお,同順位の質権が競合した場合には,動産質権の場合には,質権の順位は設定の前後によって定まる[民法355条]。不動産質については,民法361条によって抵当権の規定が準用されるため,不動産質の順位は,登記の前後によって定まる[民法373条]。権利質については,対抗要件の具備の先後によって定まることになろう([民法363条~365条]参照)。
質権者が質権を実行して優先弁済を受けるためには,債務者が債務不履行に陥っていることが必要である。また,被担保債権が金銭債権でない場合には,それが金銭債権に変化している必要がある。
質権者が優先弁済権を実現するための方法としては,以下の2つの方法がある。第1は,競売である。質権者は,民事執行法190条,192条に基づき,質物の競売を申し立て,その売得金から優先弁済を受けることができる。第2は,配当要求である。他の債権者が動産執行または動産競売の申立てをしたときは,質権者は,民執行法133条,192条に従い,その手続内で配当要求をして,その売得金から優先弁済を受けることができる。
なお,質権設定者が破産したときは,質権者は,破産手続き上の別除権を有する[破産法2条9項]。民事再生手続上も別除権を有する[民事再生法53条1項]。ただし,質権設定者に対して会社更生手続きが開始した場合には,質権者は,更生担保権者(優先権を有する債権者)の地位に甘んじなければならない[会社更生法2条10項]。
これまでの質権の全体にかかわる問題においても,動産質は,その典型例として説明をしてきた。特に,質権の第三者に対する対抗力については,他の質権とは異なる動産質の特質についても解説を行っている。これからの問題も,質権全体にかかわる問題であるが,特に,動産質について問題が生じることが多いため,動産質を例にとって説明をする。
質権設定者は,設定行為または債務の弁済期前の契約で,質権者に弁済として質物の所有権を取得させ,その他法律に定めた方法によらずに質物を処分させることを約することができない[民法349条]。
流質契約の禁止といっても,禁止されるのは債務の弁済期前に締結された流質契約に限られる。したがって,弁済期以後に,流質契約を締結することは禁止されていない。また,債務者の方で,目的物をもって弁済に当てる権利を持つという特約は,弁済期前になされた場合も有効である。
ところで,質権の場合に,原則として,私的実行である流質契約が禁止されるのは,清算義務を課すことが困難だからである。すなわち,もしも,比較的値段の低い動産をも目的物とする質権に関して,常に清算手続を義務づけるとすれば,質権の実行は費用倒れになるおそれが大きいからである。流質契約が許されている質屋の質に関しても,質屋に清算義務を課すのではなく,行政的な監督の下での競争を促進することで問題の解決を図っているのはこの理由に基づく。動産の場合であっても,行政的な監督の及ばない動産譲渡担保の場合には,私的実行を許す代りに,判例によって清算義務が課されているのは,この意味でバランスのとれた解決というべきであろう。
| 質権の種類 | 条文 | 動産の私的実行 |
|---|---|---|
| 民法上の質権 | 民法349条 | 原則的禁止(流質契約の禁止)。 |
| 民法354条 | 一定の要件(正当な理由,鑑定人の評価)の下で,裁判所の許可を得て,私的実行を行うことができる(簡易な弁済充当)。 | |
| 商法上の質権 | 商法515条 | 契約による質物の処分の禁止の適用除外(流質の承認)。 |
| 営業質 | 質屋営業法19条 | (行政的監督の下に)公正競争が実現されるとの考え方によって私的実行が許可される。 |
| 譲渡担保 | - | 清算義務を課すことにより,私的実行が許されている。 |
質屋の質については,質屋営業法が各種の規制を設けて質権設定者の保護を図る一方で,民法の質権実行の方法は費用・手数を要し,少額の金融については不適切であるとの考慮から,流質を許容している[質屋営業法1条1項,19条]。
質屋営業法は,一方で,「質屋は,流質期限を経過した時において,その質物の所有権を取得する」[質屋営業法19条1項本文]と規定するとともに,他方で,「質屋は,当該流質物を処分するまでは,質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払ったときは,これを返還するように努めるものとする」[質屋営業法19条1項ただし書き]として,質置主の受戻権を規定している。
このように,質屋の質においては,流質契約が許容されており,質物の価格が債権額に不足する時でも,質屋は残額の弁済を質権設定者に請求しえない,すなわち,質権設定者の一般財産に執行するすることはできない。
このこと,および,質屋営業法20条2項が,「災害その他質屋及び質置主双方の責に帰することのできない事由に因り,質屋が質物の占有を失った場合においては,質屋は,その質物で担保される債権を失う」と規定していることから,「営業質屋への質入れは,担保物権の設定ではなく,一定期間(流質期限)内の物権的受戻し約款つきで,質屋に質物を譲渡する行為で,質権設定者の債務は初めから存在しないと考えることも可能であろう」との説[鈴木・物権法(2007)329頁]が主張されている。
確かに,営業質の場合には,質物の価格が債権額に不足する時でも,質屋は残額の弁済を質権設定者に請求しえないこと,反対に,質物の価格が債権額を超える場合でも,質屋に清算義務が生じない。このことを考慮すると,営業質は,清算を本質とする,いわゆる担保物権ではない。しかし,「質権設定者の債務はもともとない」と考えるのは行き過ぎであり,受戻し期間(流質期間)は,債権の弁済期の定めと考えることに不都合はない。
むしろ,質屋営業法1条が,「この法律において,『質屋営業』とは,物品(有価証券を含む。第22条を除き,以下同じ。)を質に取り,流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは,当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して,金銭を貸し付ける営業をいう。」と規定し,明文で「金銭の貸付け」,「債権の弁済」という用語を用いている以上,質屋は質置主に対して,質物の質入れ後も,貸金債権を有していると考えるべきであろう。
このように考えると,営業質の法的性質は,質物の管理・保存について,質屋に厳格責任を課すとともに[質屋営業法20条2項],流質期限後においても,質物が実際に処分されるまでは債務者による受戻しが認められるという留保つき[質屋営業法19条1項]ではあるが,「貸金債務が期限内に支払われない場合には,質物でもって代物弁済がなされるという契約(清算を伴わない代物弁済予約)」であるといえよう。
民法350条は,留置権者による留置物の保管に関する民法298条を準用している。民法298条2項によると,「留置権者は,債務者の承諾を得なければ,留置物を使用し,賃貸し,又は担保に供することができない」。この条文の反対解釈によって,承諾を得て質物を担保に供することは可能であり,これを承諾転質と呼んでいる。これに反して,承諾なしに質物を担保に供することは,できないことになりそうである。しかし,それでは,江戸時代から使われてきた質権者の資金調達手段(質物をさらに質に出して,資金を調達すること)を封じてしまうことになる。現在においても,転質は,例えば,小規模の質屋が顧客から受け取った質物を,資本の大きい質屋に質入れして,顧客に貸し付けた資金の代りの資金を借り受けるというように,固定した資金の流動化を促進する作用を有しているのであり,この作用を封じてしまうことは得策とはいえない。
そこで,民法348条は,承諾を得ないで,質物を担保に供することを認めることにしている。すなわち,質権者は,その権利の存続期間内に,自己の責任で質物を転質とすることができる。この場合には,質権者は,転質をしなければ生じなかったはずの不可抗力による損失についても責任を負う。
責任転質の要件と効果は以下の通りである。
責任転質については,さまざまな説(質物質入れ説,質物・債権共同質入れ説等)があって,厳しく対立している。
しかし,転質は,すでに質権が設定された債権に対する権利質であると構成することによって,上記の要件・効果をすべて矛盾なく説明することができる(転質=原質権付き債権に対する債権質説(加賀山説))。
この説の利点は,転質という概念を特別のものとして捉えるのではなく,質権のついた債権に質権を設定することができるというだけで,すなわち,一種の債権質に過ぎないと考えることで,転質の機能を過不足なくすべて説明ができるだけでなく,転抵当についても,抵当権のついた債権に質権を設定すると考えることによって,統一的に考えることができる点にある。
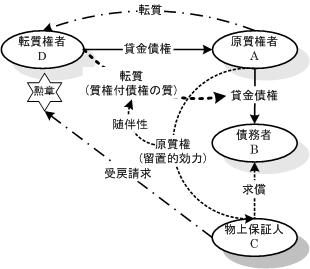 |
| *図83 責任転質の構造 |
原質権が設定された債権に対して権利質を設定することを転質と考える立場に立つと,債権に対する質権の設定は債権の処分行為に当たるとされているので,民法87条2項(従物は主物の処分に従う)によって,転質権者は,原質権を伴った債権質を取得することになる。
このように,転質を原質権付き債権に対する質権の設定と考えると,その対抗要件は,民法364条以下の対抗要件,すなわち,民法467条以下の対抗要件と同様の対抗要件(債務者への通知又は債務者の承諾)を備えることが必要となる。このことは,転抵当に関して,民法377条が民法467条の対抗要件を要求していることと整合的であり,通説が,転質に関して,転抵当における民法376条の類推を主張していることに対して,その根拠を提供することにもなる。
承諾転質とは,民法350条によって準用される民法298条2項に基づく,質権設定者の承諾を得た転質であり,民法348条の責任転質とは性質の異なる転質であると解されている。そして,その性質は,原質権とは別個の新たな質権設定であり,原質権の把握する担保価値に左右されないとされている。すなわち,原質権の債権の弁済期が到来しなくても,転質権の債権が弁済期にあれば転質権を実行できるし,また,質権設定者が原質権者に弁済しても,転質権は消滅しないものとされている[我妻・担保物権(1968)154頁]。
このような解釈が生じたのは,民法348条が責任転質について転質権者の責任を加重していることの反対解釈として,承諾転質については転質権者の責任を軽減する必要があると考えられたからである。しかし,反対解釈は,往々にして極端な解釈を導くことが多く(例えば,民法613条1項の反対解釈),常に細心の注意が必要である。承諾転質について,転質権者の責任を完全に軽減するのみならず,転質権者の権利を原質権者の権利を超えて認めることは,そもそも,転質の本質に反しており,反対解釈の域を超えている。銀行取引では,責任転質は行われておらず,責任転質を回避して,承諾転質をすることにしているという(堀内仁・民法判例百選Ⅰ〔第2版〕(1982)184頁)。このような実務を考慮するならば,転質によって,転質権者は原質権者・原質権設定者の犠牲の上に,原質権者が有する以上の権利を取得することになり,不当である(公序良俗に違反する結果となる)。
承諾転質は,承諾を得ない責任転質の場合とは異なり,転質権者の責任が軽減される(不可抗力によって質物が滅失・損傷した場合には,転質権者は免責される)だけであり,原質権者以上の権利を有するものではないと解するのが,民法348条の正しい反対解釈と思われる。すなわち,転質の性質と構造においては,責任転質も承諾転質も全く同じであり,承諾転質をしたからといって,転質権者の権利が原質権者の権利よりも大きくなることは認められない(加賀山説:承諾転質=責任転質∧不可抗力の場合の転質権者免責)。
質権は,動産を目的として発展し,目的物の範囲を不動産,そして,権利へと拡大してきた。しかし,質権は,債務者から目的物の使用・収益権を奪う点で,債務者にとって不便であり,質物の管理を債権者がしなければならない点で,債権者にとっても面倒であるという欠点を内在している。したがって,質権の典型例としての動産質さえも,債務者から目的物の使用・収益権を奪わず,債権者による管理を必要としない動産譲渡担保(いわゆる動産抵当)に取って代わられつつある。そして,質権で利用頻度が高いのは,必ずしも占有の移転が必要とならない権利質だけであるという状況に陥っている。権利質のみが,現在においても利用頻度が高い理由は,権利質が,債務者にとっての不便と債権者にとっての面倒臭さを免れている,すなわち,権利質については,必ずしも,占有の移転が必要ではなく[民法363条,364条],債務者の不便と債権者の面倒臭さが緩和されているからである。
これに対して,質権の欠点が集中的に表れている不動産質は,債権者が目的物を使用・収益することができるものであり[民法356条],債務者は不動産の占有と使用・収益権を奪われ,かつ,債権者は,目的不動産を自ら,または,他人に貸して占有管理しなければならないため,現在の金融取引ではほとんど利用されていない。
もっとも,賃貸マンション等について,後に述べる指図による占有移転を利用した不動産質を設定する場合には,収益が債務者と債権者とに分属する可能性があるため,今後の発展の可能性を秘めていると考えられている([鈴木・物権法(2007)329-330頁],[道垣内・担保物権(2008)82頁])。
質権の設定と対抗要件の箇所(第4節2,3)で述べたように,質権設定の成立要件は,当事者の合意である。従来は,不動産質権の成立には,質権設定の合意のほかに,目的物の引渡しが必要(要物契約)とされてきたが,目的物の引渡は,登記とともに対抗要件に過ぎない。
不動産質権の目的物は土地と建物だけである。特別法によって不動産とみなされる立木[立木法2条1項]は,抵当権を目的とするために不動産と認められるのであり[立木法2条3項],不動産質権の目的物とすることはできない。工場財団[工業抵当法14条],鉱業財団[鉱業抵当法3条]も同じである。また,特別法で不動産と同様に取り扱われるものとして,鉱業権[鉱業法12条,13条(採掘権)],漁業権[漁業法23条]などがあるが,これらの権利は,権利者自身に行使させることが法の目的となっているため,質権の目的とすることができない。
不動産質の存続期間は,10年を超えることができない。更新は可能だが,それも10年を超えることができない[民法360条]。不動産質の存続期間が定められているのは,通説によれば,不動産の用益権,特に,耕作権能を所有者以外の者の手にゆだねることは,不動産の効用を害するおそれがあるとする考え方に基づいている。永小作権の存続期間[民法278条]および買戻しの期間[民法580条]が制限されているのと同じ理由であるとされている。
従来は,不動産質権の対抗要件は登記であり,目的物の引渡しは,すべての質権についての成立要件であるとされてきた。しかし,質権は合意だけで成立し,引渡しは対抗要件と解すべきである。したがって,不動産質の場合にも,目的物の引渡は質権の成立要件ではなく,対抗要件と解することになる。また,不動産質には抵当権の規定が準用され[民法361条による民法373の準用],対抗要件として登記も要求される。このため,不動産質権の対抗要件としては,引渡しおよび登記の2つが要求されることになる。
対抗要件が2つ要求されることは,不思議なことではない。後に述べるように,権利質のうちの指図債権質の場合には,証書の裏書および証書の交付の2つが対抗要件として要求されている[民法363条,365条]。さらに,抵当権の処分の場合には,その対抗要件として,登記だけでなく[民法376条2項],債権譲渡の対抗要件も要求されるのであって[民法377条1項],対抗要件として複数のものが要求されることは,不動産質権だけに見られる例外現象ではない。
不動産質権の対抗要件については,不動産質に関する特別の規定がないため,第1に,通則である民法344条が適用される。つまり,不動産質権の対抗要件としては,目的物の引渡し(占有の移転)が必要である。第2に,民法361条による民法373の準用によって登記も必要となる(登記については,次に述べる)。
目的物の引渡しとしては,現実の引渡しに限らず,簡易の引渡し[民法182条]でも,指図による占有移転[民法184条]でもよいが,占有改定[民法183条]によることはできない[民法345条]。
質権において占有改定のみが許されない理由を突き詰めていくと,債務者に使用・収益権が残されることが質権の本質に反することがわかる。そこで,債権者が不動産に質権を設定しておきながら,それを質権設定者に賃貸すること(占有改定)は,許されない。反対に,賃借人に占有させている賃貸物件について指図による占有移転によって質権を設定し,果実である賃料について質権者が優先弁済を受けるということは許される。債務者に使用・収益権が残されていないからである。
このように考えると,債権者Aのために,債務者であるマンションの所有者Bが,賃借人Cに対して,以後,債権者Aのために占有するように指図して,賃貸マンションに不動産質を設定することができる(指図による占有移転による質権の設定)。債権者Aは,これにより,債務者Bの収益である賃料から,被担保債権を優先的に回収することが可能となる。
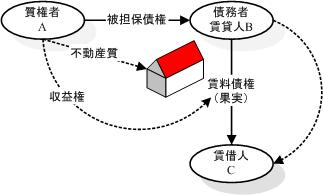 |
| *図84 指図による占有移転による不動産質の設定 |
賃貸中の不動産を質入れするためには,賃貸人の地位を質権者に移転すべきであって,これをせずに設定者が依然として賃貸人として賃料収取権を有する場合には,質権は成立しないといわなければならないという見解が存在する[我妻・担保物権(1968)168頁]。この見解は,賃貸中の不動産の質入れには,原則として賃貸人の地位の移転の合意を伴うと解するのが適当であるとする(〈大判昭9・6・2民集13巻931頁〉参照)。
しかし,不動産質における質権者は,自ら目的物を使用・収益することができるばかりでなく,第三者に賃貸することもできるのであるから,債務者を賃貸人として管理をまかせ,収益の一部を優先的に自らの債権の回収に当てることは,許されるべきであろう。もっとも,収益をすべて回収する場合には,賃貸物件の管理に支障が生じるため,上記の説のように,債務者に代わって賃貸人の地位を引き受けるべきであろう。
不動産質権の対抗要件は,目的物の引渡しだけでなく,登記も必要となる([民法361条による民法373の準用],[不動産登記法3条6号])。登記をするに際しては,被担保債権を確定しなければならない[不動産登記法83条,95条]。
対抗要件を備えた不動産質権者は,質権設定者が目的不動産を第三者に処分しても,その第三取得者に対して質権を対抗することができる。したがって,不動産質権が実行されると,第三取得者は権利を失うことになる。
この場合を想定して,民法は,売主の担保責任の箇所で第三取得者を保護するための規定をおいている。すなわち,第三取得者は,登記された不動産質が実行される前に,質権消滅請求の手続きをとることができ,その手続きが終わるまで,目的不動産の代金の支払いを拒むことができる[民法577条2項による民法577条1項の準用]。
不動産質の被担保債権の範囲は,民法346条の通則に従う。ただし,不動産質の場合には,利息は特約のある場合のみ請求しうる[民法358条,359条]。しかも,その特約は,登記をしなければ第三者に対抗できない[不動産登記法95条]。さらに,特約の登記がある場合でも,抵当権に関する375条の準用による制限があるかどうかが問題となる。この点について明文の規定はないが,不動産質においては,次に述べるように,質権者は目的物の使用・収益ができるのであり,それと管理の費用と利息とは相殺されるとするのが合理的である。したがって,質権者が利息を請求できるとする特約も,制限的な解釈が必要であり,利息等は最後の2年分に制限されるという抵当権に関する民法375条の規定が準用されると考えるべきであろう。
不動産質について,民法358条により,債権の利息を請求することが禁止された理由は,以下のように,不動産質権者が使用・収益することによる利益(費用を差し引いた純益)と債権の利息とがほぼ対応すると考えられたためである。
不動産質には,特別の規定のない限り,抵当権の規定が準用される[民法361条]。そこで,抵当権に関する目的物の範囲に関する民法370条が準用されるが,果実に関する民法371条は準用されない。その理由は,不動産質権者は,自ら天然果実を収取することもできるし,第三者に収益させて賃料としての法定果実を収取することができるからである[民法356条]。
不動産質も質権であるから,一般論としては,物上代位が認められる[民法350条による民法304条の準用]。しかし,不動産質権者は使用・収益権を有しているので,不動産質権者は,設定者の承諾なしに自由に目的物を第三者に賃貸することができ,物上代位の規定によることなく,自ら賃料を収取することができる。このため,物上代位のうち,賃貸による物上代位については,物上代位の余地はないと解されている[我妻・担保物権(1968)173頁]。
これに対して,抵当権の場合は,通説・判例は,目的物の賃貸の場合に物上代位を認めている〈最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件)〉など。使用・収益権が認められる不動産質権の場合に,賃料債権に対する物上代位が不要であるのに対して,使用・収益権が認められない抵当権の場合に,賃料債権に対する物上代位を認めることは,背理ではないのかとの疑問が生じる。この点については,抵当権の物上代位の箇所(第5章第5節5)で,抵当権の物上代位の場合の賃料債権に対する行使の制限の必要性として,詳しく論じることにする。
(i)原則 一般論としては,質権者は,質権設定者の承諾がなければ,質物を使用・収益できない[民法350条による民法298条の準用]。しかし,不動産質は用益質と呼ばれるように,質権者は,質物を使用・収益することができる[民法356条]。ただし,その反面,不動産質権者は,自ら用益するか,他人に貸すかして,不動産を活用しなければならない。そして,民法357条により,質権者は,不動産の管理費用を自弁し,かつ,その他不動産に関する負担を負う。それだけでなく,先に述べたように,民法358条により,原則として,債権の利息を請求することができないため,質権利者には相当に重い負担が課せられることになる。もっとも,利益の存するところに負担も存するという考え方によるときは,果実を収取する権利を持つ者が,管理の費用等を負担するのが合理的であろう。
(ii)例外 当事者が特約で,質権者に使用・収益権を与えないという特約をした場合には,質権者は使用・収益権を有しない[民法359条]。ただし,この特約は,不動産登記法95条の登記をしなければ対抗力を有しない。
民事執行法180条2号の担保不動産収益執行が開始されると,担保不動産の使用・収益権が管理人に移転し,管理人が費用等を負担する。それとの均衡上,不動産質権者は,使用・収益権を失うとともに,利息を請求できるようになる[民法359条]。
不動産質権者も民法347条の一般原則に従って,債権の弁済を受けるまでは質物を留置することができる。ただし,不動産質権に優先する債権者には対抗することができない。不動産「質権者に優先する債権者」とは誰かについては,通有性の解説(第4節4)で述べたので,ここでは繰り返さない。
不動産質権には,抵当権の規定が準用されるので[民法361条],その実行方法は,競売による[民事執行法181条]。不動産質権相互間および抵当権との関係は,登記の前後によって優先関係が決まる[民法361条による民法373条の準用]。先取特権との関係は,抵当権との場合と同じとなる(民法336条~339条に規定がある)。
不動産質権に関しても,民法348条の転質の規定が適用される。ただし,不動産転質の対抗要件は,占有の継続ではなく,目的物の引渡しと登記である。
民法は,無体物である権利を目的とすることができる物的担保として,権利質の規定を設けている。その中心は,債権質であり,民法362条以下の規定は,債権質の設定[民法363条],債権質の対抗要件[民法363条~366条],債権質の簡易な実行方法[民法367条]について定めている。
質権の特色は,他の物的担保が,原則として,有体物[民法85条]のみを対象としているのに対して,無体物としての権利を目的(物)とすることを認めている点にある。
もっとも,他の物的担保においても,無体物である権利を目的とするものが存在する。第1は,先取特権に関するものである。民法306条~310条の一般先取特権は,債務者の全財産を対象とするため,その中には,無体物である権利が含まれる可能性がある。また,民法304条の物上代位は,無体物である売買代金債権,賃料債権,損害賠償債権を目的としている。さらに,民法314条2文は,賃貸借の売却代金債権または転借賃料債権という無体物を目的としている(なお,民法の現代語化によって削除されたが,旧304条も,公吏保証金の返還請求権という無体物を目的としていた。第2は,抵当権に関するものである。民法369条2項は,抵当権の目的を無体物である地上権・永小作権(物権)とすることができることを明文で定めている。しかし,これらは例外的な規定であり,すでに述べたように,現行民法の起草者は,これらは有体物を目的としない点で,物権ではないことを明らかにしていた([梅・要義巻二(1896)285頁]参照)。
質権においては,無体物である財産権(特に債権)を目的とすることが,例外としてではなく,原則として認められることが,明文で規定されている。特に,約定担保として債権を担保に取る方法としては,民法上は質権だけが認められており,その意味でも権利質は重要な意義を有している。
上記のように,質権の特色として,無体物である権利をもその目的とすることができるということが挙げられる。しかし,権利の上の物権という概念は自己矛盾である。なぜなら,物権の対象は有体物に限定されるべきであって,もしも,物権が,無体物である債権を対象とすることができるとすると,債権の上の所有権という概念が成立することになり,すべての債権は所有権の中に埋没することになってしまう。そうすると,物権と債権とを峻別するというわが国の民法の体系は根底から覆ることになるからである。
民法の立法者はこのことを十分に意識しており,権利質は,物権でないことを意識していた[梅・要義巻二(1896),438頁]。この点については,通常は見過ごしそうになる民法362条2項の「準用」という微妙な表現に注目すべきである。民法362条2項で,権利質には「総則」が「準用される」という一見意味不明の表現をわざわざ用いているのには,深い意味がある。そもそも,総則と各論との違いは,一般法と特別法との関係になっており,特別法は一般法を破る,一般法は特別法を補充するといわれるように,各論に規定がある場合には総論は適用されず,各論に規定がない場合には総論が適用される。このように,総則は必ず,適用されるか適用されないかのかいずれかであって,総則が準用されるということはありえない。したがって,立法者が,権利質には質権の「総則」が「準用」されるとしたのは,特別の意味がこめられているのである。すなわち,権利質は物権としての質権とは異なる,つまり,権利質は物権ではありえないため,質権の総則は適用できない,しかし,権利質も質権に似ているので,質権の規定を準用することにしたというのが立法者の見解である。
権利質の全体像は,以下のように,取立権限の独占型から使用・収益認容型への変遷としてまとめることができる。
このような流れは,質権の本来の姿(留置型)の弱体化傾向であり,使用・収益を必要とする権利に関しては,最終的には,「権利の抵当権」化へと変容していく過程が示されているように思われる。
民法363条以下の規定は,権利質の成立要件,対抗要件について規定しているように見えるが,実際の規定は,権利質のうち,債権質の対抗要件が定められているだけである。その他の権利質の成立要件,対抗要件については,会社法,無体財産権等の特別法の規定にゆだねられている。
民法は,権利質についても,要物性を要求するように見える,以下のような規定をおいていた。
旧・第363条【要物契約性】
債権ヲ以テ質権ノ目的ト為ス場合ニ於テ其債権ノ証書アルトキハ質権ノ設定ハ其証書ノ交付ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生ス
この規定によると,指名債権の場合でも,債権の証書がある場合には,証書の交付をしなければ債権質の効力が生じないこととされていた。これは,質権一般に要求されると考えられていた要物性との整合性をはかり,債権質の公示と留置的効力を重視するという趣旨であった。
しかし,有体物ではなく無体物である権利について,本来の意味における要物性を要求することは不可能である。しかも,証書が存在しない場合には,旧363条は意味をなさない。また,証書の存否が不明な場合,証書が失われた場合などについて,旧363条をどのように扱うべきかが問題とされていた。
そこで,2003年民法改正の際に,363条は改正され,まず,指名債権については,証書の交付が成立要件とされることはなくなった。次に,その他の債権についても,必ずしも要物性は要求されないことが明らかにされた。
証書が必要とされる債権としては,指図債権(手形,小切手,倉庫証券,貨物引換証,船荷証券),記名式所持人払い債権([民法471条],[小切手法5条2項]),無記名債権[民法86条3項]があるが,後の2つは,無記名債権と同様,動産質に準じて扱われるため,民法467条は適用されず,対抗要件は,証券の引渡とその継続ということになる[民法352条]。
その結果,民法363条が適用されるのは,証券化された債権のうちの指図債権だけとなる。そして,指図債権の対抗要件については,民法365条が併せて適用されるため,民法363条にいう「証書の交付」だけでなく,民法365条にいう質権設定の「裏書」が必要となる。すなわち,指図債権の質権設定には,質入れの裏書をした証書の交付が対抗要件として必要となる。
本書の立場は,通説とは異なるが,民法の条文に忠実に,質権には要物性は要求されず,動産質における占有の継続[民法352条]も,不動産質における登記も[民法361条],成立・効力要件ではなく,すべて対抗要件と解するというものである。債権質についても,後に詳しく論じるように,証券等の引渡しは,債権質の成立・効力要件ではなく,民法365条の文言どおり,対抗要件に過ぎないと考えるべきである。
指名債権は,証券化されていない債権のことであり,なんらかの証書が作成されていたとしても,それは,証拠としての意味を持つに過ぎず,債権者は,その証書の交付を受けることなく,債権質を設定することができ,その対抗要件としては,債権譲渡の対抗要件の規定が準用されて,質権の設定を第三債務者へ通知するか,第三債務者が承認することが要求されている。この場合に,第三債務者には,債権者自身である場合も含まれるかどうかが問題となる。判例〈大判昭11・2・25新聞3959号12頁〉は,銀行が自己に対する定期預金債権の上に,質権者となって質権を設定しても有効であるとしている。また,民法364条は,民法467条だけを準用しているが,468条も準用されると解されている。
質権者が対抗要件を具備した場合の効力については,民法には規定がないが,通説・判例は,民法481条を類推して,債務者および第三債務者は,質権が設定された債権を消滅させたり,変更したりすること(債権を取り立てたり,弁済を受領したり,免除したり,相殺したり,更改することはできないと解している(〈大判大5・9・5民録22輯160頁〉,〈最二決平11・4・16民集53巻4号740頁〉,〈最一判平18・12・21民集60巻10号3964頁〉)。
後に述べる集合債権の担保(集合債権の譲渡担保)の場合とは異なり,特定の債権を担保する場合には,もしも,債務者に債権の自由な処分を許すと,債権は消滅・移転してしまい,その結果,担保権もいわゆる付従性,随伴性によって消滅・移転してしまう。そうすると,債権の履行を確保するために担保を設定した意味がなくなってしまう。したがって,質権が設定された債権については,民法481条の場合と同様,債務者の処分行為が禁止されると考えることは,質権の本質にかかわる当然の結果といわなければならない。
指図債権とは,特定の人またはその指図する人に弁済しなければならない証券化された債権(証券債権)のことをいう。債権者Aが債務者Bに対し,Cを新権利者として指定(指図)することによって譲渡できる。指定されたC又はCがさらに指定する者を明らかにする必要から,指図債権の行使には必ず証書を伴うことになる。現在,実際に使われている指図債権には,手形[手形法11条,77条],小切手[小切手法14条],倉庫証券[商法603条,627条],貨物(かぶつ)引換証[商法574条],船荷証券([商法767条,768条],[国際海上物品運送法6条])があり,いずれも法律上当然に指図債権とされる。
指図債権に関しては,民法と商法とで別々に規定している([民法365条,469条,470条,472条],[商516~519条])。民法は,指図債権の譲渡,質入れは意思表示だけにより行われ,裏書・交付は対抗要件にすぎない[民法365条,469条]としているのに対して,商法は,裏書・交付を効力要件とするという不統一がある。民法と商法とで整合性が欠けている原因は,民法の対抗要件主義はフランス法に由来しており,商法の効力要件主義は,対抗要件主義を知らないドイツ法に由来しているからである。
会社法と保険法が独立し,海商法の独立もいずれ時間の問題であるとすれば,近い将来,商法には,総則(32カ条)と商行為法(128カ条)の160カ条しか残らないことになる。そうだとすれば,商法は,いずれ,民法の契約法に吸収される運命にあり,民法との整合性をとることが必要な時代となってきている。国際条約に基づく国際海上物品運送法が船荷証券の交付について,成立・効力要件ではなく,運送契約成立後の運送人等の債務として構成していることからも,商法的な解釈が普遍的なものではないことが明らかである。したがって,わが国の解釈としては,国際条約に近づけて,裏書・交付は対抗要件に過ぎないとして,民法と商法とを整合的に解することができると思われる。
第365条(指図債権を目的とする質権の対抗要件)〔旧・366条〕
指図債権を質権の目的【物】としたときは,その証書に質権の設定の裏書をしなければ,これをもって第三者に対抗することができない。
民法365条で,債権質の設定の対抗要件とされている「債権の設定の裏書」とは,指図債権の債権者がその債権者のために質権を設定する旨を証券に記載することである。指図債権には,民法365条のほか,民法363条も適用されることから,両者を合わせて,証券に裏書し,かつ,その証券を交付することが,指図証券の質入れの対抗要件ということになる。
指図債権の質権に関しては,実際の利用形態を知らないと理解が困難である。そこで,指図債権に対する質権が設定される例として,国際貿易において商業信用状(L/C: Letter of Credit)と組み合わされて利用されている荷為替手形について説明しておくことにする([我妻・担保物権(1968)164-167頁]の2つの例を合成し,一部を修正して説明する)。
A商社(輸入業者:日本)が特定の農産物をB商社(輸出業者:アメリカ)から購入し,その運送をN海運に依頼し,シアトル(乙地)から横浜(甲地)まで運送してもらうことにしたとする。①A商社は,まず,甲地の取引銀行Dに依頼し,購入しようとする商品の代金支払いについて,②商業信用状(荷為替信用状)を発行してもらい,③これをB商社に送付して,売買契約の履行を万全なものとし,売買契約の成立を容易とすることができる。
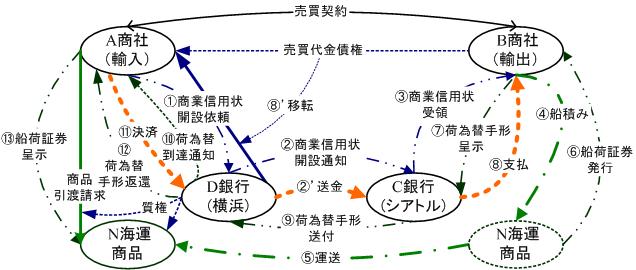 |
| *図85 荷為替手形と質権の設定 1点破線:物の流れ; 2点破線:書類の流れ; 太い点線:お金の流れ |
商業信用状とは,この例では,輸入業者Aの取引銀行Dが輸入業者Aの依頼により,輸出業者Bに対して,信用状発行銀行Dを支払人とする為替手形を振り出す権限を与えるとともに,輸出業者Bが振り出す為替手形にN海運が発行する運送証券(貨物引受証・船荷証券)を添付することによって手形の担保が実現されるならば,その為替手形(荷為替手形)の引受け・支払をする旨を約定するもので,輸入業者Aから輸出業者Bに送付される。これにより輸出業者Bは,輸入業者Aの資力・信用を調査する必要はなく,また輸入業者Aの債務不履行をおそれる必要もないところから,国際取引において盛んに利用されている。
商業信用状を発行する甲地のD銀行は,A商社のためにB商社が発行することになる荷為替手形を引き受ける義務を負い,売買・運送代金に相当する額を乙地のC銀行に送金することになるが,その代わりに,D銀行は,最終的に,A商社に対して,手形金債権を取得するとともに,それを担保するための運送証券の交付を受け,それを換価してその代金から優先的に弁済を受ける権利を取得することになる。
商業信用状の交付を受けた乙地のB商社は,A商社を支払人とする代金その他A商社から請求すべき金額の為替手形を振り出し,④商品をN海運業者の船に乙地で船積みし,⑤甲地までの運送を委託し,⑥自らを荷受人として,船荷証券(B/L: Bill of Landing)の発行を受ける。この後,B商社は,⑦乙地における自らの取引銀行Cに上記の為替手形と船荷証券を併せて(荷為替手形という)を裏書・交付して,⑧C銀行に手形を割り引いてもらう(輸出による売買代金の先行受領)。C銀行は,⑨この荷為替手形を甲地の自分の支店または取引銀行Dに送付し,銀行決済システムによってB商社への融資を回収する。次に,D銀行は,⑩手形の支払人である買主A商社に荷為替手形の到着を通知し,⑪荷為替手形を呈示して,その支払いを求める。
A商社が,手形金,すなわち,売買代金を支払うことができれば,⑫A商社は船荷証券を入手し,⑬N海運業者から商品の引渡しを受けることができる。これに対して,A商社が為替手形の支払いをしない場合には,D銀行は,C銀行を通じて,手形上の権利として,売主B商社に対して償還請求を行うことができるだけでなく,さらに,その船荷証券を換価して,その代金から優先的に弁済を受けることができる。
上記の例の解釈としては,3つの考え方が可能である。第1は,証券の表象する商品の引渡請求権に質権(権利質)が設定されたと考えるものである(通説)。第2は,売買代金債権を確保するために振り出された手形金を担保するために,流通する商品に動産質または譲渡担保が設定され,その公示方法として,占有に代わって,運送証券(貨物引受証・船荷証券)が用いられていると考えるものである[我妻・担保物権(1968)160-167頁]。第2の見解は,権利質の実質が何かを知る上で,興味深い見解であるが,法的には,指図債権によって表象される引請求権対する権利質の設定または譲渡担保(債権譲渡担保)の設定と考えることで十分と思われる。
証券債権には,先に述べたように,指図債権,記名式所持人払い債権([民法471条],[小切手法5条2項]),無記名債権があるが,指図債権の質入については,すでに述べたように,民法363条と民法365条とが適用される。残りの記名式所持人払い債権と無記名債権については,いずれも,無記名債権と同様に扱われている。
ところで,無記名債権は,民法86条3項によって動産とみなされるため,無記名債権の質入れに関しては,動産質の規定が適用されることになる。動産質については,民法352条により,目的(物)の占有の継続が対抗要件として規定されているため,無記名債権の質入れの対抗要件は,証書の占有の移転とその継続が対抗要件ということになる。そして,記名式所持人払い債権の場合も,結果は同じである。
権利質にも,質権の総則が準用される。したがって,権利質の被担保債権の範囲は,民法346条により,元本,利息,違約金,質権実行の費用,質権保存の費用,債務不履行による損害賠償,質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償に及ぶ。
民法366条2項は,旧条文[民法旧367条2項]では「質権者ハ自己ノ債権額ニ対スル部分ニ限リ」とされていたが,2004年の改正に際して,「質権者は,自己の債権額に対応する部分に限り」というように変更された。この意味は,債権質の目的(物)は,質入れの目的となった「債権自体」だけでなく,質権者の有する債権額の範囲内で,目的となる「債権の利息」に及ぶことを意味すると解されている。
質権の総則である民法350条によって,質権にも,先取特権に関する民法304条が準用されることが規定されているため,権利質においても,物上代の規定が準用されるように思われる。しかし,債権質の場合には,先にも述べたように,質権の目的債権に対する質入れの対抗力として,民法481条類似の拘束力が生じるため,物上代位の規定は必要がない。したがって,債権質の場合には,民法304条の物上代位の規定は準用されないと解すべきである。
有体物について規定する民法347条は,債権質については,意味を持たない。債権質の場合,目的(物)の留置的効力に対応するのは,すでに述べた質権の対抗力としての「債権質権の拘束力」である。
権利質も,民法342条によって優先弁済権を有する。その実行は,以下に述べる直接取立によることができる。
本来ならば,債権質権者は,質入債権を差し押さえ,債権に対する強制執行手続きに従って優先弁済権を得るという方法によるべきであるが,これを簡略化するために,質権者が自分の名で質入債権について質権者に弁済するよう請求することができることを認めたのが民法366条の規定の第1の特色である。
債権質権者は,第三債務者に対して,債権質の存在さえ証明すれば,裁判所の手を借りずに([民事執行法193条]などによらずに)請求できる。この点では,債権質の直接取立権は,債権執行というよりは,債権者代位権の進化系としての直接訴権に似ている。しかも,一般債権者に先立って直接取立てができるので,先取特権つきの直接訴権(例えば,民法314条の先取特権つきの民法613条の直接訴権)ともいうべき性質を備えることになる。
債権に対する質権の設定は,債権の処分の一種であるので,民法87条により「従物は主物の処分に従う」ことになる。したがって,債権質権者は,債務者の第三債務者に対して債権に付随している担保権を行使することができると解されている。
債権の弁済期の到来が質権者の債権の弁済期前に到来した場合には,第三債務者に供託させることができる。その場合には,債権質権者のために,質権設定者の有する供託金還付請求権の上に質権が成立することになる。この考え方は物上代位に似ているが,質権者は差押えを必要としない点で,物上代位そのものとは異なる。
1979年に民事執行法が制定されたことにより削除された民法旧・368条は,「質権者ハ前条ノ規定ニ依ル外,民事訴訟法ニ定ムル執行方法ニ依リテ質権ノ実行ヲ為スコトヲ得」と規定していた。民事執行法が制定される以前の民事訴訟法は,債権その他の権利に対する実行方法を定めており,民法旧・368条は,権利質の質権者は,債務名義を要せずに権利質の実行方法を利用できる旨を定めていた。現在では,民事執行法の整備により,権利質の質権者は,債務名義なしに債権に対する担保権の実行を行うことができるようになった[民事執行法193条,194条]。
債権質の債務者に対する拘束力については,民法364条の対抗要件の箇所ですでに述べた。この拘束力は,その他の質権が有する留置的効力に代わるものとして,債権質の強力な効力となっている。
物的担保に共通の消滅原因があるほか,それぞれの類型に応じて異なる消滅原因がある。
承諾を得ない質物の使用,賃貸又は担保の設定([民法348条]の責任転質を除く)に基づく消滅請求によって動産質権が消滅する[民法350条による民法298条3項の準用]。
なお,質物を質権の設定者に任意に返還した場合には動産質権が消滅するとする説があるが,民法352条は,「動産質権者は,継続して質物を占有しなければ,その質権をもって第三者に対抗することができない」としており,質権者が質物を任意に質権設定者に返還しても,対抗力を失うだけで,質権自体が消滅すると考える必要はない。
民法361条によって抵当権の規定が準用されている。したがって,第三取得者による代価弁済[民法378条]および不動産質権の消滅請求[民法379条以下]によって,不動産質権は消滅する。存続期間(10年以内)の経過によっても消滅する。
担保権の通有性である付従性(被担保債権の消滅)に基づく消滅原因によって消滅する。権利質の場合,占有は要件とならないため,指図債権の裏書返還を除き,債権証書を返還しても債権質は消滅しない[民法481条の類推]。
これまで,物的典型担保(民法上の物的担保)について,第1に,履行拒絶の抗弁権として事実上の優先弁済権を有する留置権(*第2節),第2に,法律上の優先弁済権の典型として理論上重要な地位を占める先取特権(*第3節),第3に,留置的効力によって法律上の優先弁済権を強化しようとする質権(*第4節)について学んできた。第4に,物的典型担保の最後を締めくくるものとして,抵当権について学ぶことにする。
抵当権は,債務者に担保目的物の使用・収益を許すと同時に,登記による追及効によって法律上の優先弁済権を強化しており,理想的な約定担保という意味で,「近代物的担保制度の王座を占めて」いる[我妻・担保物権(1968)6頁]とされたり,「担保物権の女王」[田髙・物権法(2008)197頁]と呼ばれたりしている。
この節では,A.抵当権の意義,B.抵当権をめぐる利害関係人(登場人物)について概観した後,C.先順位抵当権者と後順位抵当権者との関係,および,それに関連して,D.いわゆる「近代抵当権の原則」としての「順位確定の原則」について,わが国が採用する「順位昇進の原則」と対比して,批判的に検討する。
抵当権の設定に関連する問題のうち,抵当権の成立・対抗要件は第2節で説明し,抵当権の被担保債権の範囲,並びに,抵当権の目的物に関する民法369条1項,民法369条2項の問題,抵当権の効力の及ぶ範囲に関する民法370条,371条の問題および一般財産への追及の制限[民法394条]は,併せて,第3節の抵当権の効力の箇所で説明する。
抵当権とは,債務者又は第三者(物上保証人)が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について,他の債権者に先立って債権の弁済を受ける権利であると定義されている[民法396条1項]。そして,抵当権の性質は,この定義に従って,以下のように分析されている。
第1に,抵当権の目的物は登記ができるもの(不動産および地上権・永小作権)に限定されている。
したがって,動産を担保するには,現状では,質権によるほかない。もっとも,2004(平成16)年の動産・債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)によって,動産登記制度が創設されたため,理論的には,動産に対して抵当権を設定することも可能な状態にある。しかし,特別法(船舶抵当権[商法848条],工場抵当法,農業動産抵当法,自動車抵当法,航空機抵当法,建設機械抵当法など)で認められている以外の一般的な動産抵当は,現行の制度としては認められていない。このため,動産抵当を実現するために譲渡担保(*第20章参照)が発展することになった。
第2に,不動産の占有を設定者から抵当権者に移さないという意味で,「非占有担保」であるとされる。
つまり,抵当権には,留置的効力が伴わないのであり,この点で,留置権,質権とは異なる。もっとも,この点については,注意が必要である。これまで,目的物の占有を債権者に移転しないことが抵当権と質権との相違として強調され,上記のように,抵当権は「非占有担保」といわれてきた。しかし,質権についても,2003(平成15)年民法改正によって,権利質に関しては,証書等の占有の移転は必要とされないことになったため,質権と抵当権との差は,占有の有無ではなく,むしろ,担保設定者の使用・収益権を奪うもの(質権)と使用・収益権を奪わないもの(抵当権)として区別することが必要となっている(*第5章第4節1B(c)(質権と抵当権との対比)参照)。
第3に,占有を移転しないことと関連して,抵当権には収益的効力も伴わない。
このため,抵当権設定者は,債務不履行に陥るまでは,目的物の使用・収益権を継続し,そこから収益を上げて,債権の弁済にあてることができる。この点(設定者の使用・収益権を奪わないこと)こそが,抵当権と質権とを区別する最も重要な点である(なお,権利の上の担保権として,質権があるにもかかわらず,用益物権である地上権・永小作権の担保としては,質権ではなく抵当権が選ばれたこと[民法369条2項]の理由については,*4節1B(質権と抵当権との機能の対比),*第4節7C(a)(地上権・永小作権を担保目的(物)とする場合における権利質と抵当権との競合問題),および,*第5節2B(a)(無体物(地上権・永小作権)を目的とする抵当権))参照)。
第4に,債務者が債務不履行に陥った場合は,抵当権の効力は,目的物の果実にも及び,収益も抵当権の優先弁済権の対象に入る[民法371条]。
したがって,抵当権者は,担保権の実行として,不動産収益執行の申立てを行い,使用・収益から優先弁済を受けることができる[民事執行法180条2号,188条2文]。これは,抵当権の部分的な実行方法である。なお,担保不動産収益執行に適さない場合に,抵当権者が物上代位によって抵当目的物の賃料債権から優先弁済を受けることができるかどうかについては,民法372条によって民法304条が準用されているため,判例〈最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件)〉は,これを認めている。しかし,学説上は,抵当権の場合に,売買代金債権,賃料債権に民法304条が準用されるかどうかについて,大いに争われている(*第6章第5節5(抵当権の物上代位)参照)。
第5に,抵当権者は,担保不動産競売の競売によって,その売却代金から他の債権者に先立って弁済を受けることができる[民事執行法180条1号,188条前段]。
その結果,たとえ,被担保債権を完全に回収できないとしても(その場合,被担保債権の残額は,一般債権として存続する),抵当権は優先弁済権の満足によって消滅する[民事執行法59条1項]。そして,抵当不動産の使用・収益権と所有権は,ともに買受人に移転する[民事執行法184条]。
抵当権をめぐる法律関係には,多くの利害関係人が登場する。それらの利害関係人の名称をしっかり把握することが抵当権をめぐる法律関係を理解する最初の一歩となる。それは,小説等を読む前にその物語の登場人物の名前を把握しておくのが便利であるのと同様である。
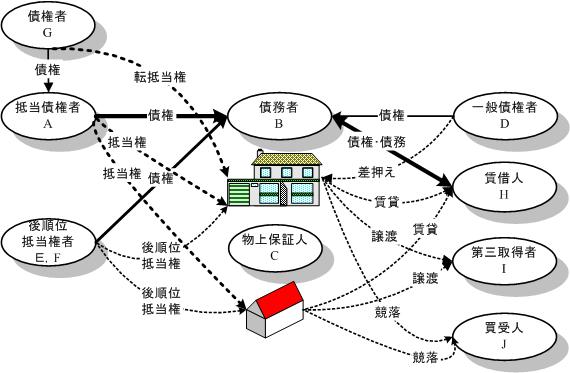 |
| *図86 抵当権をめぐる法律関係の登場人物 |
これらの登場人物を債権者側と債務者側とに分類すると以下の表のようになる。
| 登場人物(利害関係人) | 名称 | 記号 | 主な登場場面 | |
|---|---|---|---|---|
| 債 権 者 側 |
債権者の債権者 | 転抵当権者 | G | 抵当権の処分(転抵当) |
| 優先弁済権を有する債権者 | 抵当権者 | A | 抵当権の設定~抵当権の消滅(あらゆる場面) | |
| 後順位抵当権者 | E,F | 抵当権の処分(順位の譲渡・放棄・変更),共同抵当,抵当権の実行,根抵当 | ||
| 優先権を有しない債権者 | 一般債権者 | D | 優先弁済権との関係[民法394条],抵当権の処分,抵当権の実行 | |
| 競売による目的物の所有権の取得者 | 買受人 | J | 抵当権の実行 | |
| 債 務 者 側 |
抵当権設定者 | 債務者 | B | 抵当権の設定~抵当権の消滅(あらゆる場面) |
| 物上保証人 | C | 抵当権の設定,抵当権の実行 | ||
| 債務者からの目的物の所有権の取得者 | 第三取得者 | I | 抵当権の実行,抵当権の消滅請求 | |
| 債務者からの目的物の賃借権の取得者 | 賃借人 | H | 抵当権の効力の範囲,物上代位,法定地上権,抵当権との利害調整 | |
上記の表にある後順位抵当権者について,ここで説明しておく。後順位抵当権は,先順位抵当権(例えば,第1順位の抵当権)に対立する概念であり,2番抵当権者,3番抵当権者,…というように,先順位抵当権者に優先権の順位が劣後する抵当権者のことである。
抵当権を物権であると考えると,先順位,後順位の抵当権という概念を理解することが困難となる。なぜならば,このような制度は,物権の本質とされる,排他性および一物一権主義の原則に反するものだからである。上記の図表に登場する後順位抵当権者について,ここで説明しておくのは,抵当権を物権と考える人にとっては,理解が困難となるので,あらかじめ注意を喚起しておく必要があるからである。
後順位抵当権者について考える際の例として,例えば,債権者Aが,3,000万円の債権に基づいて,債務者Bから甲建物(6,000万円)に第1順位の抵当権の設定を受け,その後,債権者Eが,2,000万円の債権に基づいて,同じく債務者Bから甲建物に第2順位の抵当権の設定を受け,債権者Fが1,000万円の債権に基づいて同様にして第3順位の抵当権の設定を受けたとしよう。債務者Bが債権の弁済を滞ったため,Aによって抵当権が実行されたが,甲建物が値下がりしていて,5,000万円でしか売却されなかったとする。この場合には,第1抵当権者であるAは,3,000万円,第2順位の抵当権者であるEは,2,000万円の配当を受けることができるが,第3順位の抵当権者Fは,配当を受けることができない。また,このような状況の場合には,配当を受ける可能性のない後順位抵当権者Fは,先順位抵当権者A,Eの債権および手続費用を弁済してもなお剰余が生じる見込みがないときは,F自身がそれらの債権と費用とを弁済できる価格で買い受けるとの保証をしない限り,競売の申立ても認められない[民事執行法188条によって準用される民事執行法63条]。
しかし,後順位抵当権者にも好機がないわけではない。もしも,債務者Bが債権者Aに3,000万円を弁済したとする。付従性によって,第1順位の抵当権は消滅する。すると,Eの第2順位の抵当権が第1順位の抵当権へと,また,Fの第3順位の抵当権が第2順位へと格上げされる。これを順位昇進の原則という(これも,付従性の原則の一形態である)。したがって,その後,債務者Bが債務不履行に陥って,抵当権が実行され,甲建物が競売により4,000万円で売却されたとすると,Eが2,000万円,Fが1,000万円というようにいずれも債権額全額の配当を受けることができ,残りの1,000万円は,一般債権者Dに配当され,なお残額があれば,債務者に返還される。そして,抵当権は消滅するため([民事執行法59条1項]:消除主義),甲建物の買受人は,抵当権の付かない物件を取得することになる。このことは,たとえ,甲建物が2,500万円でしか売却されず,Fが500万しか配当を受けることができなかった場合でも同様である。Fの残債権は,無担保債権として存続することになる。
「順位昇進の原則」に対立するものとして,ドイツで採用されており,わが国では,[我妻・担保物権(1968)214頁以下]によって,極端に理想化され,近代的抵当権の原則(公示の原則,特定の原則,順位確定の原則,独立の原則,流通性確保の原則という5つの原則)の1つとして,通説によって高く評価されている「順位確定の原則」という概念がある。ドイツでは,わが国とは異なり,順位昇進の原則を採用せず,「順位確定の原則」が採用されている。このため,ドイツでは,たとえ先順位の抵当権が消滅しても,後順位の抵当権の順位が昇進することはない。
わが国では,この意味での順位確定の原則は採用していない。もっとも,順位確定の原則の意味については,抵当権の優先権の順位がその登記の先後によって定まり[民法373条],先に登記された抵当権が後に登記された抵当権に順位を奪われることはないという意味で用いられることがある([我妻・担保物権(1968)216頁],[鈴木・物権法(2007)232頁])。確かに,この意味での順位確定の原則は,わが国でも一部採用されている[民法373条]。しかし,これには,[我妻・担保物権(1968)216頁]も認めているように,不動産保存の先取特権は抵当権の登記に遅れて登記されても,抵当権に優先するという重大な例外がある[民法339条]。その上,抵当権の順位が確定されているといっても,その順位を譲渡したり[民法376条],変更したりする[民法374条]ことが明文で認められている。反対に,根抵当を設定すれば,その範囲では,順位を確定しておくことも可能となる。したがって,「原則」という意味を個々の条文の趣旨を統合して統一的な概念を形成したり(例えば,権利外観法理),個々の条文の不備を補充したりするもの(例えば,信義則)と理解するのであれば,「順位確定の原則」は,わが国では採用されていないといってよい。
[我妻・担保物権(1968)214頁以下]によって主張されてきた「近代的抵当権」の5つの原則の有用性については,その後,[鈴木・抵当制度(1968)26頁以下],[星野・民法概論Ⅱ(1976)240-241頁]等によって,例えば,以下のように批判されている。
公示の原則,特定の原則,順位確定の原則,独立の原則,流通性確保の原則の5つを,ドイツの学者にならって近代抵当権の特質などと呼ぶことがある。…しかし,前の2つ〔公示の原則,特定の原則〕は,第三者を害しないためであって当然だが,後の2つ〔独立の原則,流通性の確保の原則〕は,ドイツのかなり特殊な事情から生じたもので,これがないと近代的抵当権でない,とはいえない(不動産登記簿に公信力がないことが,別に近代的でないとはいえないように)。順位確定の原則のうち,第1原則〔先に登記された抵当権が後に登記された抵当権に順位を奪われることはない〕はもっともだが,第2原則〔たとえ先順位の抵当権が消滅しても,後順位の抵当権の順位が昇進することはない〕についても同様である[星野・民法概論Ⅱ(1976)240-241頁]。
近代的抵当権論とその批判について興味がある人は,松井宏興「抵当権(6)基礎理論」[椿・担保物権(1991)167-183頁],および,そこで引用されている文献を参照するとよい。
ドイツの抵当制度を理想化した近代的抵当権という概念を用いて,わが国に存在しない付従性のない「土地債務」,所有者が自らが自己の所有物に抵当権を設定できる「所有者抵当」を前提としなければ成り立たない「順位確定の原則」があることが望ましいとか,順位昇進の原則は,近代的抵当権とはいえないといって非難するのは的外れである。しかし,順位確定の原則が存在する場合を想定し,それとの比較を通じて,わが国の順位昇進の原則に対する問題点を指摘するという方法は有用である。その点で,抵当権による優先権を享受できないかもしれないため,高利で貸付を行う後順位抵当権者が,偶然の事情で先順位抵当権が消滅した場合に,高金利のまま,優先弁済権が確保できる安全圏に入ってくるというのは問題であるとの批判[近江・講義Ⅲ(2005)114頁]は,正当である。後に述べるように(第6節F(物上保証人との関係(異主共同抵当))),後順位抵当権者の民法392条2項に基づく代位は,物上保証人の民法500条に基づく法定代位に劣後するという法理も,このような配慮から生じているからである。したがって,上記の批判を受け入れ,順位の昇進した後順位抵当権者は,先順位抵当権者の承継者として先順位の金利も受け継ぐという解釈または立法の必要が生じているというべきであろう。
抵当権は債権の物的担保の1つであり,物的担保に共通の性質であるいわゆる「担保物権の通有性」を有している。後に述べるように,根抵当の場合には,抵当権が確定するまでは付従性,随伴性が緩和されるが,普通抵当の場合には,(a)優先弁済権,(b)付従性・随伴性,(c)不可分性,(d)物上代位性,(e)追及効のいずれの性質をも具備している。この意味でも,抵当権は,典型的な物的担保ということができる。
民法369条1項において明確に規定されているように,抵当権は,「他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」であり,優先弁済権を有する。
優先弁済権が,一般債権者との関係でどのような優先関係に立ち,どのような制限に服するかという具体的な計算例については,第3節D(抵当権者の一般債権者としての権利行使の制限[民法394条]-ノブレス・オブリージュ(Noblesse oblige))で検討する。また,後順位抵当権者との関係については,この節のC(先順位者と後順位者との関係)で概略を説明したが,第4節(抵当権の処分)の箇所で詳しい検討を行うとともに,第6節(共同抵当)の箇所で,後順位抵当権者の代位の問題として,詳しく検討する。
抵当権も,あくまで,債権を担保するものに過ぎないから,債権が存在しなければ抵当権も存在せず,債権が消滅すれば,抵当権も消滅する。この点については条文に明文の規定はないが,通説および判例〈最二判昭41・4・26民集20巻4号849頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第7事件)〉ともに,抵当権の付従性を認めている。
最二判昭41・4・26民集20巻4号849頁
農業協同組合が組合員以外の者に対し,組合の目的事業と全く関係のない土建業の人夫賃の支払のため金員を貸し付けた等の事情のもとにおいては,当該貸付は組合の目的の範囲内に属しないと解すべきであり,無効である。
消費貸借が上記の理由により無効である以上,右保証もまた無効であり,従って右保証債務を担保するためなされた右抵当権設定契約もまた無効である。
ただし,員外貸付けの場合には,有効と判断される場合もあり,たとえ,無効であったとしても,以下の判例〈最二判昭44・7・4民集23巻8号1347頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第83事件)〉のように,不当利得返還請求権が存在することが考慮されて,信義則上,抵当権の無効の主張が許されない場合も生じる。
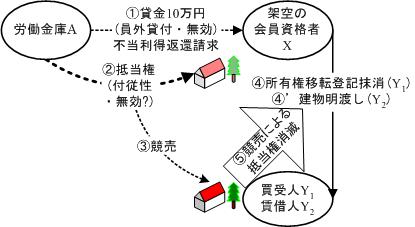 |
A労働金庫のXへの員外貸付が無効とされる場合においても,Xは,その金員を不当利得としてA労働金庫に返済すべき義務を負っているものというべく,結局債務のあることにおいては変りはない。本件抵当権も,その設定の趣旨からして,経済的には,債権者たるA労働金庫の有する右債権の担保たる意義を有するものとみられるから,Xとしては,右債務を弁済せずして,右貸付の無効を理由に,本件抵当権ないしその実行手続の無効を主張することは,信義則上許されないものというべきである。ことに,本件のように,右抵当権の実行手続が終了し,右担保物件が競落人の所有に帰した場合において,右競落人またはこれから右物件に関して権利を取得した者に対して,競落による所有権またはこれを基礎とした権原の取得を否定しうるとすることは,善意の第三者の権利を自己の非を理由に否定する結果を容認するに等しく,信義則に反するものといわなければならない。 |
| *図87 最二判昭44・7・4民集23巻8号1347頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第83事件 |
民法372条が民法296条を準用することによって,抵当権にも不可分性,すなわち,抵当権者は,債権の全部の弁済を受けるまで,目的物の全部について優先弁済権を行使できることが明らかにされている。例えば,債務が一部弁済された場合にも,抵当権は,目的物全体に対して,優先弁済権を保持する。したがって,一部弁済によっては,抵当権の抹消または変更はできない。ただし,抵当権の設定当時に,すでに,被担保債権の一部が弁済されていた場合には,抵当権の優先弁済権は,残存する債権額まで縮減するのであるから,古い判例(〈大判明42・3・12民録15輯263頁〉,〈大判明39・6・29民録12輯1053頁〉)は反対であるが,債権額の変更登記手続きを請求できると解すべきである[清水(元)・担保物権(2008)19-20頁]。
そして,例えば,被担保債権の一部が譲渡された場合でも,抵当権は分割譲渡されず,譲渡当事者は被担保債権の額に応じて抵当権を準共有する(〈大判大10・12・24民録27輯2182頁〉,[清水(元)・担保物権(2008)19頁])。
なお,通説は,共同抵当制度および抵当権消滅請求制度は,抵当権の不可分性の制約であると考えている(共同抵当制度については,[我妻・担保物権(1968)257頁]参照。抵当権消滅請求については,[清水(元)・担保物権(2008)20頁]は,抵当権消滅請求制度によって抵当権の不可分性は著しく減じられているとしている)。
しかし,第1に,共同抵当の場合には,先順位抵当権者は,いずれの担保目的物全体に対しても優先弁済権を行使できるのであるから[民法392条],不可分性が制限されているわけではない。同時配当における割付のルールは,重要な役割を果たすものではあるが,あくまで,異時配当でも同じ結果を目標とすべきことを示すモデルとしての意味を持つに過ぎないからである[山野目・物権(2009)284]。
第2に,抵当権消滅請求制度も,目的物全体から優先弁済権を受けることができるのであるから,不可分性の制約ではない。抵当権消滅請求の結果,目的物全体から優先弁済権を受けた後に,なお,残債務があれば,それは,優先権のない一般債権として存続するだけである。この結果は,競売によって優先弁済権である抵当権が消滅し,残債務は,一般債権として存続するというのと同じであって不可分性の制約とは異なると考えるべきである(なお,フランスにおいても,担保権消滅請求制度は,不可分性の原則に反するものではないと解されている(中島弘雅,高橋智也「担保権消滅請求制度と担保権の不可分性―フランス民法・倒産法からの示唆―」銀行法務21・564号(1999)60頁))。
第4に,物上代位性については,物上代位に関する先取特権の規定[民法304条]が抵当権にも準用されている[民法372条]。しかし,抵当権における物上代位については,次の抵当権の追及効との関係で,先取特権の物上代位とは異なる考慮が必要となる。そこで,抵当権の物上代位については,*第5節5D(抵当権の物上代位)の箇所で詳しく検討する。
第5に,抵当権の追及効については,登記の箇所および分離物に対する追及効の限界の箇所(*第5節2D)で論じることにする。ここでは,(d)の物上代位性と(e)の追及効の関係についてだけ,言及しておく。
「物上代位」は,目的物が第三者に移転され,債権者が目的物の追及が不可能または困難になったことを前提にして,債務者の財産に帰属している目的物に代わる債権(代金債権,賃料債権,損害賠償債権など)に対して優先弁済権を確保しようとするものである。これに対して,物的担保の「追及効」は,債務者以外の第三者に移転した目的物に対する物的担保の効力が及ぶかどうかを問題とするものである。このように,物上代位と追及効とは,目的物の追及をあきらめて,目的物の代わりに債務者に帰属している債権に対して優先弁済権を及ぼすことができるか,それとも,第三者に移転した目的物に対しても,担保権の効力をそのままおよぼすことができるかどうかを問題とする点で相違がある。
抵当権は,債務者または第三者(物上保証人)から占有を移さないで債務の担保として提供された不動産について,他の債権者に先立って債権の弁済を受けることができる権利である[民法369条]。
抵当権設定契約は,諾成契約であり,債権者・債務者間または債権者・物上保証人間の契約のみによって成立する。しかし,抵当権の効力(主要な効力は,優先弁済権である)を第三者に対抗するためには,対抗要件としての登記が必要とされる(民事執行法181条1項1号,2号は,未登記抵当権の実行方法を否定していない。しかし,民事執行法181条1項3号によれば,換価力が認められるのは,原則として,登記された抵当権である)。抵当目的物を占有しないのであるから,他の債権者に対する優先弁済権を公示する手段としては登記しかありえない。
抵当権の設定,消滅,変更は,その登記をしなければ第三者に対抗できないとされ,その根拠は,物権法総則の177条にあるとするのが通説の考え方である。抵当権の章[民法第第2編第10章]には,抵当権そのものに関する対抗要件についての規定がない。したがって,物的担保を物権と考えるならば,個別の条文がない場合に,物権の総則[民法177条]の規定が適用されることは至極当然のように思われる。
しかし,このことは,以下に述べるように,物的担保のすべての場合に適用できるわけではない。
第1に,留置権の場合にも,留置権の対抗要件に関する明文の規定はない。したがって,通説の見解によれば,抵当権の場合だけでなく,不動産留置権の場合にも,物権総則の規定である民法177条の適用があると考えなければならないはずである。しかし,不動産留置権の場合には,登記は対抗要件ではない[不動産登記法3条]。したがって,学説は,民法295条の条文の趣旨を考慮して,留置権の対抗要件を「占有の継続」と解釈している。
第2に,一般先取特権の効力は,債務者の不動産にも及ぶ[民法306条]。その場合の対抗要件については,民法336条本文により,「一般の先取特権は,不動産について登記をしなくても,特別担保を有しない債権者に対抗することができる」とされており,通説によれば,先取特権は物権であるはずなのに,民法177条に反して,登記が対抗要件とされていない。また,第三者との関係が問題となる民事執行手続きにおいても,一般先取特権の不動産に対する実行に関して,登記は必要とされていない[民事執行法181条1項4号]。このように,不動産に関する物的担保の対抗要件については,必ずしも民法177条に従うとは限らないことがわかる。
第3に,不動産先取特権(不動産保存の先取特権,不動産工事の先取特権,不動産売買の先取特権)については,民法337条,338条,340条のそれぞれは,「先取特権の効力を保存するためには,…登記をしなければならない」と規定している。立法者は登記を対抗要件と考えていたが,判例は,これらの条文の意味を不動産先取特権の効力要件と解している。民法177条によれば,登記は不動産物権変動の対抗要件とされているにもかかわらず,不動産先取特権について登記が効力要件だとすると,不動産先取特権は,物権とは異なる法理に服することになるはずである。
さらに,不動産保存の先取特権については,保存行為が完了した後に登記をすると,先に抵当権が登記されていたとしても,民法339条によって,不動産保存の先取特権は,「抵当権に先立って行使することができる」ことになる。「後に登記をした物権が,なぜ,先に登記した物権に優先するのか」,物的担保を物権と考えたのでは,この優先関係を説明することは不可能である。先に述べたように,動産保存の先取特権の場合においても,先取特権の順位は,最後に保存した者の債権が先に保存した者の債権よりも優先して弁済を受ける[民法330条1項2文]と規定されているように,先取特権は,被担保債権の性質がどの程度保護に値するかという基準から優先順位が定められているのであり,このような優先順位の法則は,物権法の法理からは決して導き出すことはできないのである。
このように考えると,抵当権の対抗要件について明文の規定がないから民法177条が適用されると考えるのは,安易に過ぎることが明らかである。抵当権における優先弁済権の対抗要件は,民法373条により,「抵当権の順位は,登記の前後による」とされていることから,解釈によって導かれるべきである。この条文は,先に述べた民法339条が,不動産先取特権と抵当権との優先関係は,必ずしも登記の順序によらないことを明らかにしていることを考慮して,抵当権同士の場合には登記の順序が優先順位を決定するもの,すなわち,登記が抵当権同士の対抗要件であることを明らかにしたものと解することができる(加賀山説)。
このように解することは,たとえ,抵当権同士の優先順位は登記によって決定されるとしても[民法373条,376条2項],抵当権と他の権利との間では,登記の順位は,以下のように,必ずしも優先順位を制御するものではないということも明らかとなる。つまり,抵当権の効力に関して,対抗要件とされる登記によって,すべてを一律に決しようとする一般的な態度に反省を促す点でも重要である。
第1に,先に登記した抵当権といえども,後で適切に登記された不動産保存の先取特権には対抗できない[民法339条]。このことは,登記の先後によって排他性を確保するという物権の性質からは導くことができない。
第2に,抵当権の効力のうち,抵当権の順位の変更は,登記をしなければその効力を生じないとされており[民法374条2項],登記が対抗要件ではなく,効力要件であることが明文上明らかである。このことは,登記を効力要件ではなく,対抗要件としている物権法の総則[民法177条]に反している。したがって,登記が抵当権のすべての対抗要件であるとの命題は,正確ではないことになる。
第3に,抵当権の効力のうちで最も重要なものとされている優先弁済権に関する処分(転抵当,抵当権の譲渡・放棄,抵当権の順位の譲渡・放棄)についての対抗要件は,登記だけでなく,債権譲渡の対抗要件としての民法467条の通知または承諾が必要である[民法377条1項]。このことも,抵当権が物権であるとする通説の考え方からは,決して導くことができない(抵当権も,債権の掴取力の強化に過ぎないとする本稿の立場によってのみ,このことを説明することが可能である)。
第4に,先に登記した抵当権といえども,後に登記した賃借権であって,抵当権者の同意とその登記がある場合には,その賃借権に対抗できない[民法387条]。この条文は,2003年民法改正の際に新設された,賃借人の保護のために抵当権の対抗力を制限するものである。後に述べるように,この規定が提供されるための要件は厳格に過ぎ,実際の利用は望めない(賃借権を登記することは稀であるし,借地借家法の対抗要件を備えただけでは要件を満たさないので,ほとんど利用されていない)という中途半端な保護規定である。このため,後に述べるように,本書では,賃借人の保護をさらに一歩を進めた解釈論を展開している。もっとも,民法387条の規定も,抵当権の他の権利に対する効力を登記の先後のみによって判断しようとする一般的な傾向に対する警告としては意味を有している。
抵当権設定登記は,優先弁済権の存在だけでなく,優先弁済権の範囲をも公示するものとされている。すなわち,債権額(元本額:[不動産登記法83条1項1号]),利息[不動産登記法88条1項1号],債務不履行後の遅延損害金[不動産登記法88条1項2号]等が登記事項として定められている。
無登記の抵当権が存在する理由は以下の通りである。第1に,登録免許税が高いことがあげられる。任意弁済さえ受ければ必要のない権利にわざわざ登録免許税を払うのはもったいない。いつでも登記できるように,権利証,白紙委任状,印鑑証明をもらっておけば,ほぼ安心というわけである。第2に,祖先から伝来の不動産の登記簿を汚すのはご先祖様に申し訳ないという考え方が残っていることも確かである。第3に,登記のない抵当権も,実行の道が完全にふさがれているわけではない。登記のない抵当権に基づく競売の場合,債務名義に相当する謄本が必要であるが,抵当権の存在を証する確定判決もしくは家事審判またはこれらと同一の効力を有するものの謄本[民事執行法181条1項1号]または抵当権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本[民事執行法181条1項2号]によって抵当権の実行の道が開かれている。
債権が弁済され,抵当権が付従性によって消滅した場合,無効となった抵当権登記を新たに設定された抵当権の登記に流用することが可能かどうかが,ここでの問題である。
第1に,不動産登記法の原則からすると,無効登記は抹消されるべき登記であり,流用登記は効力を有しないとしなければならないはずである。しかし,当事者間では,無効登記の流用の効力を否定する必要はない。すなわち,利害関係を有する第三者がいない場合には,流用登記有効とすることも許される。
第2に,旧抵当権が消滅する以前から後順位抵当権が存在していた場合には,第三者は,抵当権の存在を前提として不動産を買い受けたのであるから,新抵当権の設定登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないとして,流用登記を有効とする説がある。しかし,多数説は,第三者が抵当権が消滅することによって得た利益を尊重すべきであるとして,流用登記を無効としている。
第3に,旧抵当権消滅後,流用前に後順位抵当権が生じた場合には,学説は,一致して,流用登記を無効としている。抵当権の消滅を知って利害関係を取得する第三者が登場しうるのであり,そのような第三者を保護すべきだからである。
第4に,流用後に第三取得者が生じた場合には,流用登記は無効としつつも,第三者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないとして結果的に流用登記の対抗力を認めている(〈大判昭11・1・14民集15巻89頁〉。仮登記担保の仮登記の流用については,〈最三判昭49・12・24民集28巻10号2117頁〉)。
抵当権の特色は,法律上の優先弁済権と対抗要件である登記に基づく強力な追及効である。
ここでは,第1に,抵当権の被担保債権の範囲,目的物の範囲について理解する。被担保債権については,他の債権者を害さないよう,利息が実行のときから最後の2年分に限定されることを理解する。
第2に,目的物については,原則として不動産に限定されるが,不動産上の権利(地上権および永小作権)の上の抵当権が認められること,不動産の構成物,不動産の付合物に及ぶこと,債務不履行後の果実にも及ぶこと,不動産から分離された動産についても,一定の限度でその効力が及ぶことを理解する。
なお,抵当権の物上代位の問題は,不動産収益執行との関係が問題となるので,抵当権の実行手続きの後に学習することにする。
抵当権は,債権者と債務者または第三者(物上保証人)との間で,優先弁済をうけるべき目的物(責任財産)を特定し,その目的物の占有を移すことなく,所有者の使用・収益に委ねつつ,登記によって目的物に対する債権者の優先弁済権を公示し,目的物が譲渡されても,なお,責任財産として追及を可能にする制度である。
優先弁済権が特定の責任財産に限定され,一般財産に対しては,原則として,優先弁済を受け得ない限度でしかかかっていけない(責任財産特定の原則)という制限を受けるが[民法394条1項],特定された責任財産については,それが第三者に譲渡されようとも,その財産から優先弁済を受けることができる(責任財産保持の原則)という2つの点が,抵当権の効力の特色となっている。
以下では,抵当権の設定に関するB.抵当権の被担保債権の範囲,C.抵当権の及ぶ目的物の範囲について,無体物(地上権・永小作権),有体物(不動産)に分けて説明した後,D.民法394条の抵当権の権利制限,すなわち,高い地位としての優先権は義務を伴うというノブレス・オブリージュ(Noblesse oblige)の問題,E.抵当権の追及効の限界について説明する。
抵当権の優先弁済権が生じるもともとの原因は,債権にある。その債権の掴取力について,当事者の合意と登記に基づいて,第三者に対抗できる優先弁済権が確保される。この債権は,担保権の本体となるものであるが,担保権の側面からいうと,担保権の絶対的要件として「被担保債権」と呼ばれている。被担保債権は,抵当権の設定時点で存在しているのが原則であるが(貸金債権の場合には,要物性の要件を満たす必要がある),将来の報酬債権,売掛代金債権等,将来の債権および条件付債権も被担保債権とすることができる。なぜなら,抵当権は,その登記に際して,債権額(元本),利息に関する定め等が登記事項となっているが[不動産登記法88条],その実行は,被担保債権に債務不履行が生じた場合にのみ問題となるので,設定の段階では,弁済期等が到来していなくても,実行段階で被担保債権が確定していれば,それで問題がないからである。
抵当権者が,利息,その他の定期金(終身定期金,有期年金,定期扶養料,地代,家賃など)を請求する権利を有するときは,元本については,全額が優先弁済を受けうることに疑いがないが,利息,定期金については,その満期となった最後の2年分(競売を開始した時から遡って2年分,収益執行の場合には,数回に分けて配当がなされる場合が多いが,通算して2年分)についてしか,優先弁済を受けることができない。ただし,最後の2年分以前の定期金についても,満期後に特別の登記(権利変更登記:[不動産登記法56条,57条])をしたときは,その登記の時から優先弁済権が生じる[民法375条1項]。
例えば,金銭債権の元本を1,000万円として,優先弁済を受けることができる金額が,利息を含めてどの程度になるか考えてみよう。最後の2年分の利息については,最高額は,利息制限法の規定によると年利15%を限度とするから,優先弁済を受けることができる利息の額は300万円(1,000万円×0.15×2=300万円)となる。したがって,全体としては1,300万円について抵当目的物から優先弁済を受けることができる。
元本の支払いを遅延している場合には,損害賠償すなわち遅延賠償(遅延利息)を支払わなければならないが,この遅延利息についても,利息その他の定期金と合わせて2年分を超えない部分についてのみ優先弁済を受けることができる[民法375条2項]。最後の2年分の遅延利息の最高額は,利息制限法の規定によると,年利30%であるから,優先弁済を受けることのできる遅延利息の額は600万円(1,000万円×0.3×2=600万円)となる。つまり,元本が支払われていない場合には,全体としては最高1,600万円について,抵当目的物から,他の債権者に先立って優先弁済を受けることができることになる。
| 元本 | 2年分の利息・損害金 (利息制限法) |
最高限度額 | |
|---|---|---|---|
| 支払い遅延がない場合 | 1,000万円 | 300万円 | 1,300万円 |
| 支払い遅延がある場合 | 1,000万円 | 600万円 | 1,600万円 |
ただし,根抵当権の場合には,極度額の範囲内ではあるが,利息,定期金等の「最後の2年分」という制限を受けないので注意が必要である(第6節5B参照,なお,根抵当の場合の遅延利息の制限に関しては,〈最三判昭49・11・5金法738号34頁,金商445号7頁〉,〈最三判昭59・5・29民集38巻7号885頁(民法判例百選Ⅱ〔第6版〕第39事件)〉*第4章第2節1A(b)(有償の保証)参照)。
以上は,後順位抵当権者の保護のための優先弁済権の制限の規定であるから,債務者自身が任意弁済する場合には,すべての利息,遅延損害を含めて,債務の全額を弁済しなければならない。
抵当権の目的物の範囲は,民法369条1項の通常の抵当権の場合および民法362条2項の地上権・永小作権の上の抵当権の場合とで,問題の性質を異にする。そこで,ここでは,あまり利用されていないが,抵当権の法的性質に関する根本問題にかかわる(a) 民法369条2項の地上権・永小作権を目的とする抵当権について解説した後,(b) 民法396条1項の不動産を目的物とする通常の抵当権の目的物の範囲について説明する。また,抵当権の設定時には目的物となっていないが,その後に抵当権の目的物になるものとして,(c) 将来の物に対する抵当権として,増担保請求権を中心に解説を行う。
抵当権の目的物は,原則として,不動産に限定されている。ただし,不動産上の権利(登記が可能な権利)である地上権・永小作権を目的(物)として,抵当権を設定することもできる[民法369条2項]。
不動産上の権利とはいえ,有体物としての不動産ではなく,いわゆる「権利の上の抵当権」が認められるべきかどうか,また,なぜ,それが権利質ではなく,抵当権の箇所に規定されているのかという問題点については,すでに,*第5章第4節1B(質権と抵当権との対比)および*第5章第4節7C(a)(地上権・永小作権を担保目的(物)とする場合における権利質と抵当権との競合問題)でも取り上げて説明した。しかし,この問題は非常に重要な問題を提起しているので,ここで,さらに詳しく論じることにする。
地上権・永小作権の上の抵当権[民法369条2項]を認めることは,先に述べたように(*第15章第7節C(a)(地上権・永小作権を目的(物)とする場合における,権利質と抵当権との競合問題)参照),物権と債権との峻別を企図する民法の体系を破壊しかねない「権利の上の物権」という概念を認めるべきかどうかという,物的担保の最大の問題の1つにかかわることになってしまう。
民法369条2項の地上権・永小作権を目的とする抵当権は,「物権というべきかどうか」という重大な問題をかかえているにもかかわらず,現在の担保法の概説書は,これに目をつぶり,民法396条2項の内容の説明をすることを放棄しているのが現状である。
確かに,従来の学説のように,抵当権を「不動産上の物権」だと考えると,「権利の上の抵当権」という概念は,まさに破壊的な概念となってしまい,以上の学説のように,これを無視したくなるのも理解できる。しかし,視点を変えて本書のように,抵当権とは,物権ではなく,「物であれ,権利であれ,設定者の使用・収益権を奪わずに,その目的(物)に設定される優先弁済権である」であると考えるならば,集合動産,集合債権,無体財産権等,不動産上の権利とはいえない権利を含めて,それらに対して抵当権を設定できる道が開かれることになる。その意味で,民法369条2項は,たとえ現在はその利用がほとんどないとしても,「権利の上の抵当権」を実現しているという点で,将来の抵当制度を考える上でも,重要な意義を有していることに留意しなければならない。
現に,特許権,実用新案権,意匠権,著作権等のいわゆる無体財産権を担保にする場合には,債権者は,無体財産権に対して質権を設定できるが,この質権は,実は,債権者による使用・収益権が制限され,債務者が使用・収益をすることが認められている([特許法95条],[実用新案法25条],[意匠法35条],[著作権法66条])。このため,これらの質権は,その実質は,本来の質権ではなく,「権利の上の抵当権」の一種ということができると考えることができる(もっとも,これらの質権については,詳しい検討を必要とするので,その法的性質については,今後の研究課題としておく。このテーマで博士論文を書く人があれば,高い評価を得ることができるであろう)。
無体物を目的とする抵当権との関係で,建物(有体物)を目的とする抵当権は,その敷地賃借権に及ぶかという問題がある。抵当権が物権であるとすると,目的の範囲は,有体物(不動産・動産)に限定されるのであって,無体物(権利)には及ばないはずである。しかし,通説・判例ともに,建物を目的とする抵当権は,敷地賃借権に及ぶとしている〈最三判昭40・5・4民集19巻4号811頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第85事件〉。
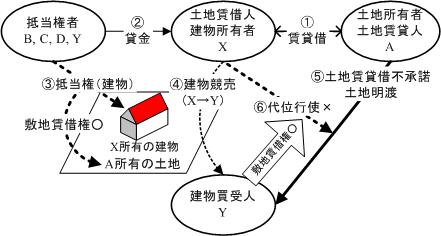 |
土地賃借人〔X〕が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には,原則として,右抵当権効力は当該土地の賃借権に及び,右建物の競落人〔Y〕と賃借人〔X〕との関係においては,右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人〔Y〕に移転するものと解するのが相当である。 賃借人〔X〕は,賃貸人〔A〕において右賃借権の移転を承諾しないときであっても,競落人〔Y〕に対し,土地所有者たる賃貸人〔A〕に代位して右土地の明渡を請求することはできない。 |
| *図88 最三判昭40・5・4民集19巻4号811頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第85事件 |
本件は,昭和41年に借地法9条の3によって,建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可の裁判の制度が創設される前の事件である。借地法のこの規定は,借地借家法20条に引き継がれており,現在では,借地上の建物を競売または公売によって取得した第三者は,借地権設定者(土地所有者)が賃借権の譲渡を承諾しないときでも,裁判所に申し立てて,借地権者の承諾[民法612条]に代わる許可を得ることができることになっている。
抵当権は,抵当地の上に存する建物を除くほか,その目的不動産に付加してこれと一体を成した物に及ぶ。ただし,設定行為において別段の定めをした場合および第424条の規定によって債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合には,抵当権の効力は付加物には及ばない[民法370条]。
欧米の国々は,「地上物(建物を含む)は土地に属する(superficies solo cedit)」とのと原則に則り,建物を土地の一部としている。わが国は,これとは異なり,土地と建物を別の不動産としている。建物を土地と離れた独立の動産とするのは,わが国に独特の法制である。わが国においても,民法86条によれば,建物は「土地の定着物」とされており,建物は土地に付合するようにも見える[民法242条]。しかし,民法370条は,「抵当権は,抵当地の上に存する建物を除き,その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」と規定しており,土地と建物が別個独立の不動産であることを明らかにしている(土地と建物とを別個・独立の不動産としたことによって生じる問題について,特に,法定地上権の問題については,*第5節7で詳しく論じる)。
抵当権の目的不動産とその付加物の場合とは異なり,抵当権の効力は,債務者が債務不履行に陥るまでは,果実には及ばない[民法371条]。天然果実は不動産とは別個の動産(抵当不動産の付加一体物ではない)からであり[民法88条,89条],法定果実(利息債権,賃料債権等)は債権であって,抵当権の対象となるとしても,それは,民法372条によって準用される民法304条が適用される場合のみだからである。
2003年民法改正前の旧規定によれば,抵当権の効力は,原則として,果実には及ばないとし,抵当権が実行されて,目的不動産の差押えがあった後にはじめて果実に及ぶとしていた[民法旧371条1項本文]。「差押え以後の果実は不動産化する」というフランス方の考え方を継受したものである。
2003年民法改正前の第371条〔果実に対する効力〕)
①前条ノ規定ハ果実ニハ之ヲ適用セス但抵当不動産ノ差押アリタル後又ハ第三取得者カ第381条〔滌除権者への実行の通知〕ノ通知ヲ受ケタル後ハ此限ニ在ラス
②第三取得者カ第381条ノ通知ヲ受ケタルトキハ其後1年内ニ抵当不動産ノ差押アリタル場合ニ限リ前項但書ノ規定ヲ適用ス
2003年民法改正により,債務不履行以後は,抵当権の効力は,天然果実だけでなく,法定果実にも適用され,むしろ,賃料などの法定果実を主眼とするものとなったと理解されがちである。しかし,2003年の改正理由は,民事執行法の改正により,担保不動産収益執行手続き(内容的には,従来からの強制管理が準用される)が新設され[民事執行法180条2号,188条],これにともなって,この手続きが,抵当権の効力を担保不動産そのもの[民事執行法180条1号]だけでなく,賃料などの収益にまで及ぼすことができ,この収益を対象とする手続きを開始するには被担保債権の債務不履行が前提であることを示すためであった。したがって,担保不動産収益手続き以外の場合にも,抵当権の効力が,差押え以前の段階において果実に及ぶと考えるべきではない(物上代位も差押えが行使の要件となっている[民法304条1項])。
債務不履行が生じた後も,抵当権の設定者(債務者又は物上保証人)は収益権を有していることは疑いがない。抵当権の設定者は,差押えがあるまでは従来どおりに果実を収取することができるのであり,民法371条は,債務不履行が生じた後,差押えがあるまでの果実が抵当権実行による買受人に帰属することを意味するものではない。したがって,抵当権が実行され,目的不動産が差し押さえられたり,担保不動産収益執行手続きが開始された場合に,設定者がいまだ収取していない果実があれば,そのうちの債務不履行発生後のものについて抵当権が及ぶのであって,以下のように,抵当権の実行によっても設定者の使用・収益は拘束されないというのが民法371条の意味であるということになる。
抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲については,従来は,不動産の付加物に従物が含まれるかどうかが議論の中心になっていた。民法370条は,不動産の付加物の中に従物が含まれるとするフランス法を参照して起草されたものであるのに対して,民法87条に規定されている従物は,ドイツ法由来の概念であり,両者の関係が明確でなくなってしまったことから複雑な問題が生じたのである(民法370条立法の沿革については,角紀代恵「民法370条・371条」[広中=星野・百年Ⅱ(1998)593頁以下参照])。また,抵当権の及ぶ目的物の範囲に関しては,目的不動産,付加物[民法370条],果実[民法371条]だけでなく,さらに視野を広げて,その他の一般財産[民法394条]を見通した上で,物上代位[民法372条]の及ぶ範囲等を総合的に考察しなければならない。
そのような広い観点から,抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲を全体として表にまとめると以下のようになる。
| 目的物の範囲 | 不履行まで | 不履行後 | 根拠条文 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 不動産 | 目的不動産 | 土地又は建物 | ○ | ○ | 民法369条 |
| 不動産の付加一体物 | 不動産の構成部分 | 樹木,塀等 | ○ | ○ | 民法370条 |
| 不動産に従として付合した物(付合物) | 土地の石垣,建物の造作 | ○ | ○ | 民法242条,370条 | |
| 従物 | 土地の所有者が所有する石灯籠,取り外しのできる庭石, 建物に備え付けられた畳,障子,家具 |
○ | ○ | 民法87条,370条 | |
| 果実 | 天然果実 | 樹木の果実,乳牛の牛乳など | × | ○ | 民法88条1項,371条 |
| 法定果実 | 土地の地代,建物の家賃,元本の利子など | × | ○ | 民法88条1項,371条 | |
| 一般財産 | 目的物の滅失・損傷による損害賠償・保険金債権 | ○ | ○ | 民法372条による民法304条 | |
| 目的物売却の代金債権 | × | × | 民法394条の趣旨 | ||
| その他の一般財産 | × | × | 民法394条 | ||
抵当権の及ぶ範囲としての不動産に付加して一体となっている物の位置づけについては,以下の表によるのがよいであろう。
| 不動産 | 土地 | ||||
| 土地の定着物 | 建物 | ||||
| 立木ニ関スル法律に規定する立木 | |||||
| 土地の構成部分となって土地の所有権に吸収される物 | 不動産に従として付合した物[民法242条] | 不動産に付加して一体となっている物[民法370条](通説) | |||
| 明認方法を施すことにより,独立の物としての取引が可能な物。 権原ある者が附属させると,その者の所有に属する[民法370条の例外]。 |
|||||
| 従物 | 土地の所有者が所有する,石灯籠,取り外しのできる庭石など[民法87条] | ||||
ただし,従物が民法370条の「不動産に付加して一体となっている物」といえるかどうかについては,争いがあった。大審院の初期の判例は,動産である従物に対する抵当権の効力を否定していた〈大判明治39・5・23民録12輯880頁〉。しかし,その後,大審院は連合部判決〈大連判大8・3・15民録25輯473頁〉で,抵当権の効力が抵当権設定時の従物に及ぶことを認めたが,その理由は,民法87条2項であるとしていた。その後も,大審院は,抵当権設定後の従物に関する事案について,従物に対する抵当権の効力を認めるものの([民法87条2項]を根拠とする),従物は,民法370条の「不動産に付加して一体となっている物」には含まれない〈大判昭5・12・18民集9巻1147号〉と解していた。
その後,昭和44年最高裁判決〈最二判昭44・3・28民集23巻3号699頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第84事件)〉は,抵当権設定前に持ち込まれた石灯篭および庭石(従物),並びに,庭木等(構成部分)について,民法370条の「抵当不動産に付加して一体となっている物」に従物(石灯篭および庭石)が含まれると判断するに至っている(学説の変遷については,湯浅道男「抵当権の効力の及ぶ範囲」[星野・講座3(1984)61頁以下]参照)。
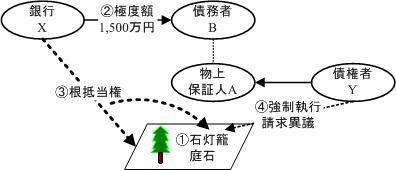 |
宅地に対する抵当権の効力は,特段の事情のないかぎり,抵当権設定当時右宅地の従物であった石灯篭および庭石にも及び,右抵当権の設定登記による対抗力は,民法370条により右従物についても生ずる。 |
| *図89 最二判昭44・3・28民集23巻3号699頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第84事件 |
さらに,最高裁〈最一判平2・4・19判時1354号80頁,判タ734号108頁〉は,借地上のガソリンスタンドの店舗建物を対象として設定された抵当権が,設定当時から存在している地下タンク,ノンスペース型計量機,洗車機等に及ぶかどうかが争われた事案(抵当権が実行され,建物の買受人が抵当権の設定者に対して,建物明渡等を求めた事件)について,それらの物件が建物の従物であるとして(ただし,地下タンクは,建物価格の4倍以上であり,価格的には,主物よりも,従物の方が価値が高いという逆転現象が生じている),抵当権の効力が及ぶとしている。
なお,付加物が分離された場合の抵当権の効力については,E(b)(分離物(分離された付加物)に対する抵当権の追及効)の箇所で説明する。
次に述べる抵当権者の有する優先弁済権の行使に際して,抵当権の行使につき,一定の制限を課していることとの関連で,民法370条ただし書きについて,触れておく。第1の設定行為に別段の定めがある場合に,抵当権の範囲が不動産の付加物に及ばないとしているのは,この規定が,公の秩序に関するものでないことを示している。だたし,別段の定めも,登記がなければ第三者に対抗できないので注意を要する[不動産登記法88条]。第2に,債務者が,一般債権者を害する目的で(抵当権者と債務者とが通謀するのがその例),抵当不動産に工作を加え,一般財産に属する物を抵当不動産に付加して一体としてしまった場合には,詐害行為取消権の場合に責任財産からの逸失を否定するのと同様,抵当権の付加物となった物について,責任財産からの逸失を否定することにしている。すなわち,債務者が工作によって一般財産に属する物を抵当不動産に付加した場合に,その物を付加して一体となった物ではないとみなして,抵当権の効力を及ぼさないこととしているのである。
抵当権の被担保債権については,債務の履行期までに確定できるものであれば,将来債権でも差し支えないことはすでに述べた。また,根抵当の場合には,一定の枠に属する変動する債権を対象とすることができる。これに反して,抵当権の目的物は,原則として,抵当権の設定の時に存在するものであることが必要である。ただし,この原則にもいくつか例外が存在する。
第1は,抵当不動産の付合物[民法242条],従物[民法87条]を含めた「抵当不動産に付加して一体となっている物」[民法370条]および「債務不履行後に生じた抵当不動産の果実」[民法371条]については,抵当権の設定後に付加され,または,生じた場合でも,抵当権の効力が及ぶことになる。
第2は,企業体そのもの,または,企業の一定の場所において財産の内容が常時入れ替わる物に対して抵当権を設定する場合である。特別法によって,特定の企業施設を構成し,その内容が変化する不動産と動産とを1個の物とみて抵当権を設定したり(財団抵当),企業施設の基礎となっている個々の不動産(土地・建物)を基盤とし,それに付属する動産を一体として抵当権を設定したり(工場抵当)することが認められている。
第3に,抵当権の設定者の故意または過失によって抵当不動産の損傷等によって価値が減少した場合に,抵当権者は,設定契約において増担保(ましたんぽ)を請求できるとするだけでなく,特約がなくても,そのような場合には増担保請求をすることができるというのが通説の考え方であり,このことは,現存する目的物のみを抵当権の目的とすることができるという原則の例外をなすことになる。
第4は,抵当権の目的建物が滅失し,同一敷地に新しい建物が建築された場合に,その新しい建物に対して抵当権が及ぶことを抵当権の設定時に予め定めることができるか,また,そのような特約がない場合にも,当然に抵当権の範囲が新しい建物に及ぶかどうかが問題となる。
第1の問題については,先に論じた。また,第2の問題は,民法の特別法であるので,ここでは概要を述べるに留める。また,第4の問題については,フランスの担保法改正により,同一敷地の上の建物についても抵当権の効力が及ぶとされたが[フランス民法典2420条3項],わが国においては,今後の立法の課題であるため,ここでは,第3の増担保の問題を論じるにとどめる。
旧民法は,以下のように,抵当権者の増担保請求権を明文で定めていた[旧民法債権担保編201条2項,3項]。
旧民法債権担保編 第201条
①意外若くは不可抗の原因又は第三者の所為に出でたる抵当財産の滅失,減少又は毀損は,債権者の損失たり。但先取特権に関し第133条に記載したる如く,債権者の賠償を受く可き場合に於ては其権利を妨けず。
②若し抵当財産が,債務者の所為に因り又は保持を為さざるに因りて減少又は毀損を受け,此が為め,債権者の担保か不十分と為りたるときは,債務者は抵当の補充(supplément d'hypothèque)を与ふる責に任ず。
③此補充を与ふること能はざる場合に於ては,債務者は担保の不十分と為りたる限度に応じ,満期前と雖も,債務を弁済する責に任ず。
現行民法の立法者は,以下の理由で,この条文全体を削除している。すなわち,第1項は賛成であるが,当然のことであるとして削除している。また,増担保に関する2項,3項については,民法137条2号で,「債務者が担保を滅失させ,損傷させ,又は減少させたとき」は,「債務者は,期限の利益を喪失する」ことにしており,その場合には,債権者は,即時に弁済を請求できる。旧民法のように,増担保を請求した後でなければ,即時に弁済を請求できないというのでは,抵当権者に不利であるという理由で削除している[民法理由書(1987)356-358頁]
しかし,事情によっては,抵当権を実行して金銭消費貸借関係を清算するよりも,債務者に対して増担保を請求して,貸借関係を継続することの方が有利である場合もあり,そのようなときには,抵当権の侵害を理由として期限の利益を失わせただけでは,抵当権者の利益は十分に確保されない。したがって,民法137条2号と3号とを,以下のように,総合的に解釈するのが妥当である[我妻・担保物権(1968)387-388頁]。
第1に,債務者が故意もしくは過失によって担保を滅失させ,損傷させ,または減少させた場合には,民法137条2号によって債務者が自動的に期限の利益を喪失するのではなく,抵当権者は,あえて,増担保を請求することができる。そして,債務者がその請求に応じない場合には,民法137条3号によって,抵当権者は,即時に,抵当権を実行することができる。
第2に,債務者の責めに帰すことができない事由によって担保価値が減少した場合には,抵当権設定時の特約等によって,債務者が担保価値を維持する義務を負っている場合のみ,増担保請求ができる。
抵当権者は,一方で一般債権者に対して強力な優先権と追及権を有する最大の権限を有するのであるから(抵当権は担保物権の王といわれている),他方で,一般債権者に対する配慮(使用・収益権を害さない,一般財産権にみだりに介入しないこと)が求められることになる。そして,民法394条は,抵当権者にノブレス・オブリージュ(Noblesse oblige)を求めた規定と解することができるというのが,ここで論じようとするテーマである。
抵当権者は,債権者であるから,本来なら,抵当目的物以外の財産からも,一般債権者としての立場で弁済を受けることができるはずである。しかし,抵当権者が別に抵当目的物から優先弁済を受ける権利を確保しておきながら,さらに債務者の一般財産からも弁済を受けることができるということになると,他の一般債権者を害することになる。
そこで民法は,一般債権者を保護するために,抵当権者の一般債権者としての資格での権利行使に一定の制限を設けている。すなわち,抵当権者は,原則として,抵当不動産の代価から弁済を受けられない債権の部分についてしか,抵当目的物以外の財産から弁済を受けることができない[民法394条1項]。
例えば,AがBに対して1億円の債権を有し,その担保として価額5,000万円の甲不動産上に抵当権を有しているとする。Bには,Aのほかに,5,000万円の一般債権を有する債権者Cがおり,その他の財産としては,甲不動産以外に,価額6,000万円の乙不動産があるとする([鈴木・物権法(2007)255頁]参照)。
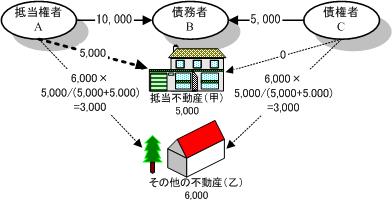 |
| *図90 抵当権者の一般財産に対する効力 |
この場合,Aが先に抵当権を実行し,その競売代金5,000万円で弁済を受け,残債権5,000万円でBの他の財産乙に対して一般債権者の資格でかかっていくと,乙財産からのAとCの取り分は,同額の3,000万円となる。
これに対して,もしも,Aが債権額全額について乙財産にかかっていくことを許すと,乙財産からのAの取り分は4,000万円,Cの取り分は2,000万円ということになり,Aの取り分は甲財産・乙財産を合わせると9,000万円となるのに対して,Cは本来の取り分から1,000万円減少して,2,000万円となってしまい,Cにとって酷な結果となる。
したがって,抵当権者は,抵当権者として優先弁済権を行使できる限度で,一般債権者として権利行使することを制限され,優先弁済権を行使できる債権額を除いた額でしか,一般財産に対して,一般債権者として配当加入することは許されない。抵当権者が先に一般財産に執行しようとすれば,一般債権者は異議を述べることができる〈大判大15・10・26民集5巻741頁〉。
大判大15・10・26民集5巻741頁
民法394条1項の規定は,抵当権者が抵当不動産以外の債務者の財産に付,先づ弁済を受け又は之を受けんとする場合に普通債権者に対し異議権を与へたるに止まり,抵当権者が債務者に対し先づ抵当不動産に付,其の弁済を受くべき義務を定めたるものに非ざるを以て,抵当権者が抵当不動産以外の債務者の財産に付,先づ其の弁済を受け又は之を受けんとしたる場合に,債務者は何等之を拒否すべき権利なきものとす。
上記の判例〈大判大15・10・26民集5巻741頁〉が,一般債権者は一般財産に対して執行を行うことに対して異議を述べることができるとしつつも,抵当権者の執行を停止できないとするのは矛盾しており,抵当権者の一般財産に対する担保不動産執行に対しては,一般債権者は,抵当権の目的物の範囲を超えており,抵当権の効力が生じないとして,執行異議の申立て[民事執行法182条]をすることができると解すべきである。ただし,例外として,抵当権者が競売を行う前に他の債権者が債務者に対して強制執行を行う場合のように,抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当する場合には,抵当権者も一般債権者として,一般財産から,債権の割合に応じて配当を受けることができる[民法394条2項本文]。
もっとも,この場合においては,他の各債権者は,抵当権者がまず抵当不動産から優先弁済を受け,その後に一般財産から配当を受ける場合と同様の配当が実現されるようにするため,優先弁済を受ける抵当権者に対して,配当されるべき金額を供託するよう請求することができる[民法394条2項]。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
このため,結果的には,抵当権者は,抵当目的物によってカバーされる優先弁済額を除いた額に基づいて計算される配当額に等しい額しか配当を受けることができない。
民法394条による優先弁済権を有する抵当権と優先弁済権を有しない一般債権者との利害調整の方法は,優位な立場に立つ者に対して,劣後する者への配慮を求めるものであり,高く評価されるべきである。このことは,神聖不可侵の権利であっても,相隣関係等において,さまざまな義務を求められるという法原理,すなわち,「所有権は義務を伴う」のと同様に,「優位な立場に立つものは,そうでない者に対する義務を伴う(ノブレス・オブリージュ:Noblesse oblige)」という格言を「担保物権の王」とされる抵当権に対して適用したものと考えることができるであろう。
このように考えると,目的不動産に対して優先弁済権と追及効という最大の権利を有する抵当権者が,目的不動産が滅失・損傷もしていないのに,目的不動産に対する担保不動産執行を温存しつつ,さらに目的不動産以外の債務者の一般財産に属する賃料債権に対して,物上代位によって優先弁済権を行使することの不当性,そして,その結果,賃貸借の維持・管理に必要な賃料収入が断たれ,賃貸借を成り立たせなくさせることの不当性がよく理解できるようになる。この点については,抵当権に基づく物上代位の箇所(*第16章第5節E(抵当権における物上代位とその範囲))で詳しく論じることにする。
抵当権は,債務者または物上保証人の財産の中から特定の財産を債務の弁済のために引当となる不動産を登記によって特定させ,債務の任意の弁済が得られないときは,その特定の不動産から,他の債権者に先立って優先弁済を受けることのできる権利である[民法369条]。
通常の債権の場合は,債務者の一般財産の中に存在する特定の財産が譲渡された場合には,その財産は,原則として,債務者の責任財産から離脱する。
しかし,これには,3つの例外がある。第1は,詐害行為取消権[民法424条]によって,債務者の責任財産を保全し,受益者または転得者に対して追及できる場合であり,第2は,財産の譲渡,賃貸,滅失・損傷の見返りとして,債務者に代金債権,賃料債権,損害賠償債権等が発生した場合に,その債権に対して,債権者が債権者代位権または物上代位を行使しうる場合であり,そして,第3が,責任財産が抵当権(譲渡担保を含む)の登記または代物弁済の仮登記によって特定されている場合である。
抵当権の場合,通常は,物権だから追及効があると説明されているが,先に述べたように,物権であっても,登記を有しない不動産物権には追及効がない。また,担保物権内部においても,留置権や動産質権は,占有によって,それぞれ,事実上の優先弁済権または真の優先弁済権を確保するのであり,占有を失えば,追及効がなくなってしまう。さらに,担保物権といわれる一般先取特権,動産先取特権には,そもそも追及効は存在しない。したがって,通説のいうように,物権であるから追及効があるということにはならない。
このように考えると,担保物権の追及効というのは,動産の占有の継続または不動産等の登記によって責任財産を特定させ,その責任財産について優先弁済権を確保することに他ならない。
債権の場合であっても,不動産賃貸借契約については,登記をすれば,目的不動産が第三者に譲渡された場合であっても第三者に対抗できる[民法605条]とされているのであり,抵当権の追及効も,物権の効力ではなく,登記による,優先弁済権の生じる責任財産の保全の効果と考えるのが正当であろう。
(i) 抵当権の分離物に対する追及効 抵当権の目的物の使用・収益権能は,抵当権の設定者(債務者または物上保証人)にあるため,通常の使用・収益によって付加物が抵当不動産から分離されて付加物である状態でなくなったときは,その分離物には抵当権の効力は及ばない。
問題が生じるのは,抵当山林の木材が,正当な利用の範囲を超えて伐採された場合のように,抵当権の目的物である不動産が,付加物が分離された状態では債権を満足させることができない場合である。なお,現代的な問題としては,劇場の建物から照明器具等の数億円に上る高価な舞台装置が搬出されるという例〈東京高判昭53・12・26下民集29巻9-12号397頁〉を考えることができよう([内田・民法Ⅲ(2005)443頁],[田髙・物権法(2008)206頁])。
判例は,当初は,立木が伐採されると不動産の性質を失って動産となるから,物上代位の可能性はあるが,抵当権の効力は及ばないとしていた〈大判明36・11・13民録9輯1221頁〉。しかし,その後,抵当権が実行され,競売が開始されたときは,差押えの効力が生じるため,それ以後の伐採・搬出は禁止されるとしている〈大判大5・5・31民録22輯1083頁〉。また,判例は,抵当権実行後に搬出された材木に対しても追及することができるとしており,競売が開始されない時点でも,抵当権自体に基づき搬出禁止を認めるに至っている〈大判昭7・4・20新聞3407号15頁〉。ただし,競売が開始されない段階で搬出されてしまった木材に追及効が及ぶかどうかについては,明らかではない。
抵当権の追及効の観点からすると,分離物に抵当権の効力が及ぶといっても,分離された付加物は,最終的には独立の動産となり,したがって,独立の所有権の対象となりうる。したがって,分離物がどのような状態であれば,依然として抵当権の追及効が及ぶのかという基準時が,ここでの主要な問題となる。
本書の立場を先取りして述べると,抵当権の追及効の限界について,民法397条は,抵当不動産の第三取得者が「取得時効に必要な要件を具備する占有をしたとき」に抵当権の追及効が消滅することを明らかにしている。したがって,分離された付加物の場合にも民法397条を類推し,目的物が第三者によって善意取得されるまでは追及力が保持されると考えるのが正当であろう。
(ii) 分離物に対する追及効の限界時点 抵当権の効力が分離された付加物にも及ぶことについては争われていないが,分離物は,やがては独立の動産となるため,追及効の限界はどこにあるのか,すなわち,分離物に対する抵当権の追及効はどの時点で消滅するのかについては,以下の学説が対立している。
(A) 搬出基準(場所的一体)説 分離物が抵当不動産と場所的一体性を保っている限りにおいて抵当権の効力は及ぶが,それを失えば効力は及ばないとする説である。この説は,理論構成によってさらに2説に分類されている。
(a) 対抗力喪失説 この説によれば,抵当権は,付加物を含めて目的物全部を支配する物権なので分離物にも支配力が及んでいるという。しかし,抵当権は登記を対抗要件とする権利だから,分離物が抵当不動産の上に存在し,登記により公示に包まれている限りにおいてだけ第三者に対抗できるということになる。つまり,不動産の所在場所から搬出されると対抗できなくなるという考え方である([我妻・担保物権(1968)268頁],[鈴木・物権法(2007)240-241頁])。
(b) 効力切断説 分離物が取引観念上,不動産と一体的関係にあれば,民法370条の付加物に含まれるが,搬出されると付加物ではなくなり,抵当権の効力は切断されるとする[川井・担保物権(1975)53頁]。
上記の両説は,第三者が木材を不当に搬出した場合に,抵当権に基づく物権的請求権が発生するかどうかで結論を異にする。しかし,追及効に関しては,結論に相違はない。
(B) 即時取得基準説 分離物は,第三者が即時取得するまでは,抵当権の効力が及ぶとする説である。
抵当権の効力の及ぶ範囲を広く認めようとする背景には,悪意の第三者は排除されるべきであるとの考慮が働いていたり[星野・民法概論Ⅱ(1976)252頁],工場抵当法5条1項(抵当権は第2条の規定に依りて其の目的たる物が第三取得者に引渡されたる後と雖も其の物に付之を行ふことを得),同法同条2項(前項の規定は民法192条乃至第194条の適用を妨げず)の考え方を尊重すべきであるとの考慮が働いている([高木・担保物権(1993)123頁])。工場抵当の事案ではあるが,最高裁は,工場から搬出された動産について,即時取得されない限り,元の据付場所である工場へ戻すことを請求できるとしている〈最二判昭57・3・12民集36巻3号349頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第89事件)〉。
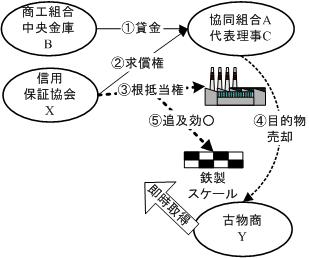 |
工場抵当法2条の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が,備え付けられた工場から抵当権者の同意を得ないで搬出された場合には,第三者において即時取得をしない限りは,抵当権者は,搬出された目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。 |
| *図91 最二判昭57・3・12民集36巻3号349頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第89事件 |
しかし,工場抵当の場合には,抵当権の効力の及ぶ付合物・従物をすべて目録に記載しなければならず[工場抵当法3条],その目録は登記簿の一部とみなされ,目録の記載は登記とみなされており[工場抵当法3条2項,4項],それを前提にして,即時取得が成立するまで,追及効が特別に認められている。したがって,その理論を,付加物について登録がなされない通常の抵当権の場合に持ち込むのは,妥当ではない[我妻・担保物権(1968)269頁]との反論が成り立ちうる。ただし,この説(搬出基準説)によるときは,悪意者の扱いが問題となる。背信的悪意者に対しては,信義則の法理に基づいて,または,詐害行為取消権の法理を用いて追及効を認めることを可能としなければならないことになろう。
民法397条は,「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは,抵当権は,これによって消滅する」と規定しており,この規定が,第三者の取得時効による抵当権の追及効の限界を示すものであることは,第9節C.(d)(債務者または抵当権設定者以外の者による抵当不動産の取得時効による抵当権の追及効の消滅[民法397条])で詳しく論じる。この点からも,即時取得基準説の結論は,妥当である。
(C) 物上代位性説 抵当権の物上代位性から勿論解釈として,抵当権は分離物の上に及ぶとする。ただし,それを実現するためには,304条による差押えが必要であるとする[柚木=高木・担保物権(1973)277頁]。
しかし,物上代位の制度は,抵当権の目的物の価値の減少を生じさせるのと同一事実に基づいて債務者または物上保証人の一般財産が増加した場合に,抵当権者にその増加した権利(代金債権,賃料債権,損害賠償債権・保険金債権)に対する権利行使を認める制度である。
したがって,分離物の搬出によって追及効が及ばなくなった場合に,分離物の代金債権に対して物上代位が認められることはあっても,分離物は,抵当権の登記によって特定される目的物からは離脱しており,代償物の場合とは異なり,債務者・物上保証人の責任財産にとどまっているものではないため,物上代位の考え方を利用することはできないといわなければならない。
抵当権の目的物の範囲は,当事者間では合意で定まるが,第三者に対する効力は,登記によって判断するほかない。したがって,分離物が不動産と場所的一体性を保っている間は,登記の公示力を付加物であった分離物に対しても認めることが可能であり,抵当権の効力を及ぼすことが許される。しかし,不動産の分離物が搬出された後は,分離物に対する抵当権の追及効は弱められ,最終的に消滅すると考えるのが正当であろう。しかし,公示は,第三者に権利の所在を周知させるためであり,分離した途端に抵当権は消滅するとして悪意の第三者を保護する必要はない。そうすると,第三取得者の善意・無過失を要件として抵当権の消滅を認める即時取得基準説が妥当である。
抵当建物が崩壊して木材となった場合,判例・通説は,抵当権の目的物である不動産は,木材という動産となることによって不動産としての本質を失ったのであるから,抵当権は,物権法の一般原則によって消滅するとしている(〈大判大5・6・28民録22輯1281頁〉,[我妻・担保物権(1968)269頁],[川井・担保物権(1975)58頁])。
しかし,ここでも,抵当権は物権だからというだけの理由で,付合物が分離されたが不動産と同一場所にとどまっている場合の解決方法とは,極端に異なる結論が導かれている。判例は,さすがに,抵当権の実行着手後の建物崩壊の場合には,木材に抵当権の効力が及ぶとしているが〈大判大6・1・22民録23輯14頁〉,抵当権の実行の着手がなされていない場合であっても,利益状況は同様のはずである。
山林の木材が,正当な理由の範囲を超えて,すべて伐採されて分離物となったが,その場所にとどまっている場合は,その動産に抵当権の効力が及ぶ。しかし,抵当建物が倒壊して動産になった場合には,抵当権の効力が及ばないというのは奇妙である。
抵当権を物権とは考えない本書の立場では,建物の倒壊をもって,直ちに,物権である抵当権も消滅すると考える必要はない。むしろ,建物の崩壊の場合も,抵当権の効力を公示する登記の効力は,倒壊木材にも及んでいると考えることが可能である。
この場合,物上代位の問題が発生しないことは,分離物の箇所で論じた通りであり([柚木=高木・担保物権(1973)277頁]は,物上代位の効力として倒壊木材に抵当権の効力が生じるとするが,倒壊木材は,抵当目的物の代償物ではない),抵当権の追及効は,分離物の場合と同様,登記建物と一体性を保っていると考えられるので,倒壊木材に及ぶと考えるべきである[鈴木・物権法(2007)241頁]。
第三者が抵当目的物である建物等を損傷しても,抵当山林を伐採した場合でも,残存価値が被担保債権額を超える場合には,抵当権者には,原則として,損害賠償請求権は発生しない〈大判昭3・8・1民集7巻671頁〉。
抵当権侵害に対する抵当権者の救済手段としては,第1に,債権者の立場として,債権侵害に基づく損害賠償を請求することと,第2に,優先権を有する債権者として,執行妨害等の優先弁済権を害する行為について,優先弁済が実現できない限度で,債権侵害に準じて不法行為に基づく損害賠償を請求すること,第3に,債権の優先弁済権者として,目的物の価値減少によって,被担保債権の優先弁済が受けられなくなることに対して,損害賠償を求めること,債権者代位権を使って,抵当権設定者(目的物の所有者)が有する請求権を代位行使することに限定される。
この点に関しては,所有権者である抵当権設定者の権利を代位行使すること以外に,抵当権者に抵当目的物の直接の引渡請求を認めようとする見解があり,最高裁もこの見解を採用している〈最一判平17・3・10民集59巻2号356頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第88事件)〉。
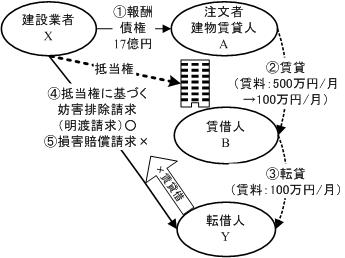 |
抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者であっても,抵当権設定登記後に占有権原の設定を受けたものであり,その設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ,その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは,抵当権者は,当該占有者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として,上記状態の排除を求めることができる。 抵当不動産の占有者に対する抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,当該占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる。 抵当権者は,抵当不動産に対する第三者の占有により賃料額相当の損害を被るものではない。 |
| *図92 最一判平17・3・10民集59巻2号356頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第88事件 |
しかし,抵当権者に管理占有を認めることは,設定者から使用・収益権を奪わないという抵当権の本質に反することになる。抵当権に物権的請求権を認めると,第1に,複数の抵当権者が存在する場合に,誰に明渡しをすべきかについて,特定ができないという難問が生じる。第2に,抵当権者に引渡しを認めると,抵当権者に不動産の管理を義務づけることになるが,管理のノウハウを持たない抵当権者は,第三者への管理委託に頼らざるを得ないが,そうすると,高額の管理コストが発生する上に,抵当権者は,工作物責任をも負担することになる。第3に,そのようなコストは結局,抵当不動産の買受人の負担となるため,競売価格を低下さることになり,抵当権者による競売妨害のおそれさえ生じさせかねない[清水(元)・担保物権(2008)37-38頁]。このような点を考慮するならば,債権者に過ぎない抵当権者に物権的請求権を認めるべきではない。
そもそも,物権的請求権という用語は,条文にない学術用語であり,占有を伴わない物権(占有の本権ではない場合)に認められるかどうかの検証は十分になされていない。確かに,物権的請求権は,すべての物権に備わっているかのように,安易に用いられる傾向がある。しかし,物権的請求権は少なくとも,占有を伴わない先取特権には認められない。また,占有を伴う物権であっても,留置権には占有訴権とは区別される本権としての物権的請求権は存在しない[民法302条]。さらに,質権の場合には,明文で占有訴権だけが認められ,本権としての物権的請求権は認められていない[353条]。このように考えると,明文で「占有を移転しない」[民法369条1項]とされ,占有訴権すら否定されているている抵当権に,本権に与えられるべき物権的請求権が認められるとする根拠は存在しない。
なお,抵当権者が債権者として,抵当権設定者の権利をどの範囲で代位できるかについては,債権者代位権の箇所で詳しく論じた(*第5章第4節)。ここでその問題を繰り返すことはしないが,要点だけを述べると以下の通りである(この問題については,コンパクトかつ緻密な議論を展開しているものとして[清水(元)・担保物権(2008)34-38頁]参照)。
ここでの問題は,抵当権に対する執行妨害をいかに解決するかという問題であり,それは,実体法上の問題ではなく,もともと執行法上の問題である。執行法は,その相次ぐ改正を通じて,買受人のために,①引渡命令[民事執行法83条],②売却のための保全命令[民事執行法55条1項1号],③買受けの申出をした差押え債権者のための保全処分[民事執行法77条]を整備し,かつ,抵当権者のためにも,④不動産競売開始前の保全処分[民事執行法187条]を整備している。
最高裁は,当初は,抵当権は非占有担保であり,したがって,執行妨害者に対しても,明渡しを請求することはできないという実体法的には正当な判断をしていた〈最二判平3・3・22民集45巻3号268頁〉。しかし,平成11年当時は,上記の③,④の制度が不備であったために,抵当権者を保護するため,従来の判決を覆し,抵当権者に債権者代位権による明渡請求を認めたり〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉,目的物の占有権を有しない抵当権者に対して,物権的返還請求権を認めたり〈最一判平17・3・10民集59巻2号356頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第88事件)〉という,民法の体系を無視したなりふり構わない暴挙に出てしまったのである。
当時としては,それなりの理由があったかもしれないが,執行妨害についての民事執行法の整備が進んだ現在においては,上記の平成11年の大法廷判決〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉および抵当権に基づく物権的請求権を認めた平成17年判決は,完全に意味を失ったというべきであり,平成3年判決〈最二判平3・3・22民集45巻3号268頁〉の正当な法理に立ち返るべきである。
最二判平3・3・22民集45巻3号268頁
抵当権者は,抵当不動産を占有する者に対し,抵当権に基づく妨害排除請求として又は抵当権設定者の所有物返還請求権の代位行使として,その明渡しを求めることはできない。
抵当権の処分には,①転抵当,②抵当権の譲渡,③抵当権の放棄,④抵当権の順位の譲渡,⑤抵当権の順位の放棄,⑥抵当権の順位の変更の6種類がある。
ここで注目すべきは,抵当権の放棄であり,この用語法の中に,抵当権の本質がうまく表現されている。もしも,抵当権が物権だとすれば,抵当権の放棄によって抵当権自体が消滅するはずである。ところが,抵当権の放棄とは,抵当権者が一般債権者に対して優先権を放棄し,ともに,同順位の抵当権者として,平等の配当を受けることを意味する。このことは,「抵当権」の放棄が,「優先弁済権」の放棄と読みかえられていることを意味する。すなわち,「抵当権」とは,「債権の優先弁済権」(債権の掴取力の強化)に過ぎないことが,民法の条文[民法376条]からも明確となっている。このように考えると,抵当権の処分の対抗要件が債権譲渡の対抗要件の具備をも要求している[民法377条]のは,抵当権が物権ではなく,債権の優先弁済権」に他ならないことの1つの表れであることが理解できる。
抵当権の処分とは,物権の処分ではなく,債権の優先弁済権の処分であると考えると,上記の6つの類型についての理解が格段に容易となる。なぜなら,それらの類型は,それぞれ,①は債権者に対する優先弁済権と順位の譲渡として,②・③は一般債権者に対する優先弁済権の譲渡・放棄として,④・⑤は後順位抵当権者に対する優先弁済権の順位の譲渡・放棄として,⑥は抵当権者同士での優先順位の変更として,すべて統一的に位置づけることができるからである。
抵当権の処分の6つの類型,すなわち,(1)転抵当,(2)抵当権の譲渡,(3)抵当権の放棄,(4)抵当権の順位の譲渡,(5)抵当権の順位の放棄,(6)抵当権の順位の変更について,具体的な事例によって,それらの概念を明確に区別することが,この節での第1のねらいである。
次に,抵当権の処分の対抗要件が,抵当権の順位の変更を除く5つの類型を通じて共通であり,しかも,それが登記以外に債権譲渡の場合と同様の対抗要件が求められていることから,抵当権の処分に共通の理念を発見することが重要な課題であることを理解する。すなわち,「抵当権の処分」とは,「抵当権における優先弁済権を債権とは切り離して譲渡(全部譲渡・一部譲渡を含む)することである」ということを明らかにするのがこの節での第2のねらいである。
この2つの作業を通じて,抵当権の処分である「優先弁済権」の譲渡と「抵当権」の譲渡とが同様に扱われていることの意味,すなわち,「優先弁済権(担保物権の本質)」と「抵当権」との同一性を確認することが,この節での第3のねらいである。
本書の記述は,体系的な記述を行うために,上に述べた民法典の条文の順序(民法374条,376条)とは逆になっているが,抵当権の処分のそれぞれの具体例から入り,次に,抵当権の処分における共通の理念を発見するという順序で解説を行う。
抵当権の処分とは,民法376条に規定されている転抵当(1項前段),抵当権の譲渡,抵当権の放棄,抵当権の順位の譲渡,抵当権の順位の放棄(1項2文)および民法374に規定されている抵当権の順位の変更の6種類の処分のことをいう。
| 抵当権の処分の効果 | |||
|---|---|---|---|
| 相手方 | 効果 | ||
| 処分の種類 | 1. 転抵当 | 抵当権者の債権者 | 優先弁済権の譲渡 |
| 2. 抵当権の譲渡 | 債務者の一般債権者 | 優先弁済権の譲渡 | |
| 3. 抵当権の放棄 | 債務者の一般債権者 | 優先弁済権の準共有 | |
| 4. 抵当権の順位の譲渡 | 後順位抵当権者 | 優先弁済権の譲渡 | |
| 5. 抵当権の順位の放棄 | 後順位抵当権者 | 優先弁済権の準共有 | |
| 6. 抵当権の順位の変更 | 抵当権者間 | 優先弁済権の相互譲渡 | |
転抵当が,抵当権者自身の資金調達の便宜のために,抵当権を利用して融資を受ける制度であるのに対して,他の5つの制度,すなわち,抵当権の譲渡・放棄,抵当権の順位の譲渡・放棄・変更は,反対に,債務者への資金調達の促進を図るために,抵当権者の優先順位を後退させ,債務者の新たな融資者(債権者)に対して優先順位を昇進させる制度である。
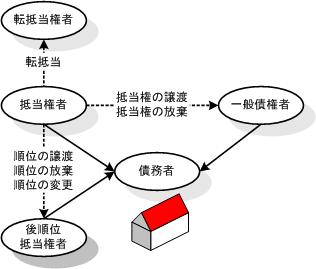 |
| *図93 抵当権の処分の相手方 |
従来の説によれば,抵当権の処分は,抵当権者の債権者への抵当権への担保の設定(転抵当),債務者の一般債権者への抵当権の譲渡・放棄,後順位抵当権者への順位の譲渡,放棄,変更というように複雑な用語によって説明されてきた。
しかし,抵当権=債権の掴取力の強化説によれば,これらは,「優先弁済権の譲渡」というキーワードによって統一的に説明することができる。
なぜなら,転抵当は,抵当権者の債権者に対する優先弁済権の一部譲渡であり,抵当権の譲渡・放棄は,債務者の一般債権者に対する優先弁済権の全部譲渡・一部譲渡(準共有)であり,抵当権の順位の譲渡・放棄・変更は,後順位抵当権者に対する優先弁済権の全部譲渡・一部譲渡(準共有)に他ならないからである。
転抵当とは,抵当権者自身が融資を受けるため,抵当権を他の債権の担保にすることである[民法376条1項前段]。転抵当を設定するのに原抵当権の設定者である債務者または物上保証人の承諾は必要ないと解されている(責任転抵当)。原抵当権の設定者の承諾があれば,原抵当権者がその債権者のために担保権を設定すること(承諾転抵当)ができるのは当然であり,民法376条1項前段が定めているのは,承諾転抵当ではなく,原抵当権の設定者の承諾なしに自己の責任で転抵当をすることができることを定めたものと解されている[鈴木・物権法(2007)271頁]。
転抵当権者Aに対して,抵当権者Bは,原抵当権設定者Cの所有物の上にさらに抵当権を設定する形式をとってはいるが,実質は,転抵当権者Aの原抵当権者Bに対するα債権を担保するために,第1に,原抵当権者Bが債務者Cに対して有する抵当権(優先弁済権)つきのβ債権の上に抵当権を設定するとともに,第2に,両者の債権額の最小範囲で,優先弁済権を一部譲渡(順位を譲渡)するという2つのステップを同時に行っている。
転抵当権の設定が,通常の抵当権の設定とは異なり,「権利の上の抵当権」の設定であることは,その対抗要件にも現れている。物権の設定であれば,民法177条に基づく登記で足るはずであるが,転抵当の場合には,第1に,抵当権の設定である登記とともに,第2に,優先弁済権の設定としての債権譲渡と同様の対抗要件が要求される。すなわち,第1の転抵当の第三者対抗要件として,付記登記[不動産登記法4条2項]が要求され[民法376条2項],第2に,債務者,保証人,抵当権設定者に対する対抗要件として,債務者への通知または債務者の承諾が要求される[民法377条1項]。もっとも,第2の対抗要件については,第1の対抗要件,すなわち,付記登記による第三者対抗要件[民法376条2項]が備わっているため,民法467条の債権譲渡の場合とは異なり,民法377条1項の通知・承諾には,確定日付は要求されていない。
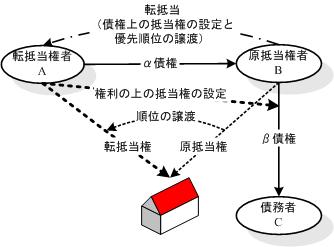 |
| *図94 転抵当の法的性質 |
従来の学説は,転抵当等の抵当権の処分を抵当権が債権から切り離された独立の存在として処分される制度として考えてきた。抵当権を債権に付従する物権と考える従来の説によれば,転抵当等は,付従性に対する重大な例外と考えざるを得ない([鈴木・物権法(2007)271頁])。これに対して,抵当権を合意と登記によって優先権を有する債権と考える本書の立場からは,すでに存在するα債権のためにβ債権上に抵当権を設定するとともに,抵当権者のために優先権の順位を譲渡する制度とみることになり,債権が消滅するわけではないので,付従性の例外とみる必要もない。
抵当権を有しないα債権の債権者Aのために,転抵当権設定者Bがβ債権の上に新たに抵当権を設定した上で,Aのために,Bの優先順位をAに譲渡するという2つのステップを踏む点で,転抵当は,その他の抵当権の処分よりも複雑であるが,優先弁済権を譲渡するという内容面では,転抵当は,後に述べる債務者の一般債権者や後順位抵当権者に優先弁済権を譲渡する,抵当権の譲渡・放棄,順位の譲渡・放棄と,法的性質に変りがあるわけではない。
これまで,転抵当を説明するために,第1に,抵当権だけの単独処分を認め,抵当権の目的不動産上(または,交換価値(無体物))に再度抵当権を設定したものと考える抵当権再度設定説[我妻・担保物権(1968)390頁],第2に,抵当権だけの単独処分を認めた上で,抵当権という権利(無体物)を質入れするものと考える抵当権質入れ説[鈴木・物権法(2007)271頁],第3に,端的に,抵当権に担保権を設定することであると考える抵当権担保設定説[内田・民法Ⅲ(2005)453頁],第4に,以上の広義の単独処分説とは異なり,抵当権の付従性を重視して,抵当権と被担保債権を共同して質入れするものと考える債権・抵当権共同質入れ説[柚木=高木・担保物権(1973)304頁]が主張されてきた。
本書の立場は,これらとは異なる第5の考え方である。本書においては,物には,有体物のほか,無体物(権利がその代表)が含まれ,物権の対象とは異なり,債権(物的担保を含む)は,債権譲渡がその例であるが,無体物をも目的物とすることができると考えるため,抵当権の目的物として権利(地上権・永小作権だけでなく,公示可能なあらゆる権利)をも認めることが理論的に可能となる。そして,転抵当とは,原抵当権の被担保債権に抵当権を設定するとともに(債権の上の抵当権の設定(公示は付記登記と債務者への通知または承諾の2つが必要)および原抵当権者から転抵当権者へ抵当権の順位の譲渡がなされるものと考える。
| 学説 | 原抵当権者の債権の取立て 債務者の原抵当権者への弁済 [民法377条2項] |
原抵当権者の 競売申立て |
転抵当権者の 直接取り立て |
|
|---|---|---|---|---|
| 単独処分説 | ①抵当権再度設定説 | × (ただし,債権に対する拘束力の説明は困難) |
○ (判例と同じ) |
× |
| ②抵当権質入れ説 | ||||
| ③抵当権担保設定説 | ||||
| 共同処分説 | ④債権・抵当権共同質入れ説 | ○ (債権に対する拘束力の説明が容易) |
× (判例と異なる) |
○ (質権の効力として認める) |
| 債権抵当説 | ⑤債権抵当・順位の譲渡説 (加賀山説) |
○ (判例と同じ) |
○ (債権者代位権が可能) |
|
上の表で明らかなように,第1の抵当権再度設定説は,当事者の意思に忠実である反面,抵当目的物の所有者ではない抵当権者がなぜ抵当権の目的不動産に抵当権を設定できるのかの説明が困難であるし,もしも,転抵当の目的物が抵当目的物である不動産ではなく,抵当権が把握している交換価値であるとするならば,今度は,民法369条で定められた抵当権の範囲との整合性の説明が困難となる。そして,第2の抵当権質入れ説の場合には,転抵当といっているのになぜ質権が設定されるのかが疑問であるし,この説では,転抵当による原債権に対する拘束力[民法377条2項]が説明できない。また,第3の抵当権担保設定説によれば,民法369条2項で規定されている地上権または永小作権を超えて,抵当権の上に抵当権を設定することになり,そのような抵当権は物権とはいえなくなるが,それでよいのかどうかが問題となる。さらに,第4の債権・抵当権共同質入れ説の場合は,当事者意思と離れて,抵当権が二重の質権設定へと変質することの説明が困難である。
この点,「抵当権=合意と登記の対抗力に基づく債権の優先弁済権」という考え方に立てば,転抵当は,抵当権者がみずからの債権者のために,優先弁済権を譲渡するものであると考えることができる。厳密に言えば,転抵当とは,第1に,原抵当権者が,抵当権が設定された債権の上に抵当権を設定して自らの債権に対する拘束力を課すと同時に,第2に,自らの優先権について,転抵当権者に優先権の順位の譲渡を行うことを意味することになる。
そして,転抵当権者が,対抗要件を備えると,「抵当権の処分の利益を受ける者(転抵当権者)の承諾を得ないでした(債務者から原抵当権者への)弁済は,その受益者(転抵当権者)に対抗することができない」[民法377条2項]。この規定によって,転抵当が付従性の例外ではないことが示される。その理由は,以下の通りである。
転抵当権者Aは,α債権の債務者でも物上保証人でもないCの所有する不動産に対して抵当権を実行することができるのであるから,転抵当権者は,β債権の存在とは無関係にCに対して優先弁済権を取得しており,一見したところ,付従性の例外のように見える。しかし,民法377条2項によって,原抵当権者Bから転抵当の設定通知を受けた債務者Cは,たとえBに対してβ債権の弁済をしても,β債権の消滅をもって転抵当権者Aに対抗できないのであり,これによって,付従性と両立させつつ,原抵当権の被担保債権であるβ債権の存在が確保されたことになる。すなわち,この規定[民法377条2項]によって,原抵当権の存在を前提とする転抵当の正当性が確保されるのである。
第1に,転抵当権者AのBに対するα債権の弁済期が到来していない間は,転抵当権者Aは転抵当権の実行をすることができない。さらに,質権の場合とは異なり,抵当権の実行があるまでは,転抵当権の設定者であるBは,β債権の使用・収益権を有しており,したがって,利子の弁済を受けることはできるが,処分権までは有しないため,元本全額の支払いを受けることはできない。
しかし,第2に,α債権の弁済期が到来すれば,たとえ原抵当権者Bの債務者Cに対するβ債権の弁済期が到来していない場合であっても,債務者Cは,債権額を供託することができ,転抵当権者Aは,民法366条3項を類推して,その供託金に効力を及ぼすことができると解されている。[内田・民法Ⅲ(2005)454頁]は,これを「一種の物上代位である」としているが,「一種の」が何を意味するのか不明である。通説が,質権の規定を準用する,または,この結果を認めるのであれば,転抵当においては,β債権も担保に供されていると解すべきであり,この点でも,転抵当の性質を単独処分とする説には難点があることになる。
第3に,α債権,β債権ともに弁済期が到来している場合には,転抵当権者Aがまず配当を受け,剰余金は,原抵当権者Bに配当される。また,剰余が予想される限り,原抵当権者Bも,抵当権の実行をすることができる(大決昭7・8・29民集11巻1729頁)。
この点についても,転抵当権者は,転抵当権の設定によって原抵当権者の債権を担保に取ると同時に,原抵当権者の順位の譲渡を受けていると考えると説明が容易である。
民法376条1項後段文に規定された抵当権の処分(抵当権の相対的処分ともいう)について,第1順位の抵当権者A(債権額:1,000万円),第2順位の抵当権者B(債権額:2,000万円),第3順位の抵当権者C(債権額:3,000万円),一般債権者D(債権額:4,000万円),債権額の合計1億円に対して,抵当物件の評価額は5,000万円であるという想定の下で,抵当権が処分された場合の各当事者の配当額の変化を説明する。
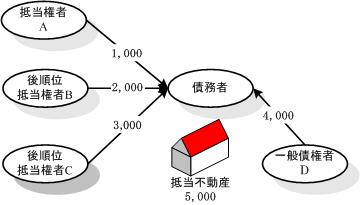 |
|
||||||||||||||||||||||||
| *図95 抵当権の処分に関する共通の設例 | |||||||||||||||||||||||||
(A) 抵当権の譲渡の意味
抵当権の譲渡とは,抵当権者が,抵当権を有しない債権者に対して,自分の有している債権額の範囲で相手方に抵当権を与え,その範囲で自らが無担保債権者となることをいうとされてきた。
ここで大切なことは,抵当権の譲渡の場合には,債権の譲渡とは切り離して,抵当権だけが,被担保債権の額の範囲内で一般債権者に付与されるという点である。このことは,債権とは別に,債権額の枠内で,優先弁済権だけを譲渡することが可能であることが法律上認められていることを意味する。
「抵当権=合意と登記の対抗力に基づく債権の優先弁済効」という立場に立てば,抵当権の譲渡とは,抵当権者が,債務者の一般債権者に対して,その債権額(厳密には債権の配当額)の制約の下に,自らの有している債権額の範囲で優先弁済権を譲渡し,その範囲で自らが無担保債権者となることであるということができる。
(B) 抵当権の譲渡と配当額の変化
統一的な例で,AからDへと抵当権が譲渡された場合の各債権者の配当額は以下のように変化する。
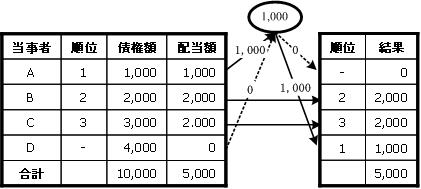 |
(A) 抵当権の放棄の意味
抵当権の放棄とは,抵当権者が,抵当権を有しない債権者に対して,自分の有している優先弁済の利益を放棄し,抵当権者が有する抵当権の被担保債権額相当分について優先弁済を分けあうことをいうとされてきた。
抵当権の放棄といわれているが,放棄の相手方とともに,抵当権を放棄した者も,依然として元の順位の抵当権者として残るのであるから,厳密には抵当権の放棄でなく,むしろ抵当権の準共有である。
「抵当権=合意と登記の対抗力に基づく債権の優先弁済効」という立場に立てば,抵当権の放棄とは,抵当権者が自らの債権額の範囲内で,債務者の一般債権者に対して,各々の債権額に比例配分させて優先権を一部譲渡し,相手方とともに優先権を準共有するものであると考えるべきであろう(抵当権者がその優先権の範囲で「優先関係を放棄」して,抵当権者と一般債権者とが「平等の優先権者の立場になる」ことだといえば,さらに,わかりやすいかもしれない。なぜなら,優先関係の放棄によって平等(しかもレベルの高い平等)が実現されているからである)。
(B) 抵当権の放棄と配当額の変化
統一的な例で,AからDへと抵当権が放棄された場合の各債権者の配当額は以下のように変化する。
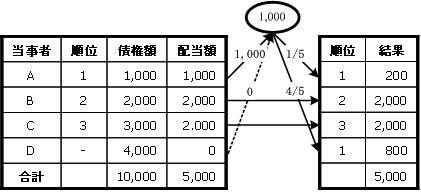 |
(A) 抵当権の順位の譲渡の意味
抵当権の順位の譲渡とは,先順位の抵当権者が後順位の抵当権者に,優先弁済を受ける権利を譲渡することをいい,順位の譲渡を受けた後順位の抵当権者は,自分が本来有する優先弁済を受ける権利に加え,先順位の抵当権者が有していた分についても優先弁済を受けることになる制度であるといわれてきた。
「抵当権=合意と登記の対抗力に基づく債権の優先弁済効」という立場に立てば,抵当権の順位の譲渡とは,抵当権者が,後順位抵当権者に対して,その債権額の制約の下に,自らの有している債権額の範囲で優先弁済権を譲渡し,その範囲で自らが相対的に後順位者となることであるということができる。
(B) 抵当権の順位の譲渡と配当額の変化
統一的な例で,AからCへと抵当権の順位が譲渡された場合の各債権者の配当額は以下のように変化する。
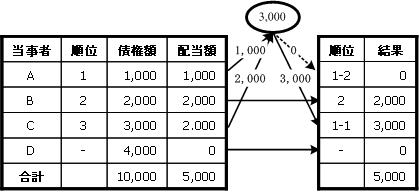 |
(A) 抵当権の順位の放棄の意味
抵当権の順位の放棄とは,先順位の抵当権者が後順位の抵当権者のために,自らが有する優先弁済の利益を放棄し,双方の配当部分について平等の立場にあるようにする抵当権の処分方法であるとされている。
抵当権の順位の放棄といわれているが,放棄の相手方とともに,抵当権の順位を放棄した者も,依然として元の順位の抵当権者として残るのであるから,厳密には抵当権の順位の放棄でなく,むしろ抵当権の順位の準共有である。
「抵当権=合意と登記の対抗力に基づく債権の優先弁済効」という立場に立てば,抵当権の順位の放棄とは,抵当権者が自らの債権額の範囲内で,後順位抵当権者に対して,優先弁済権の一部を譲渡し,相手方とともに債権額に比例して優先権を準共有するものであると考えるべきであろう。
(B) 抵当権の順位の放棄と配当額の変化
統一的な例で,AからCへと抵当権の順位が放棄された場合の各債権者の配当額は以下の図のように変化する。
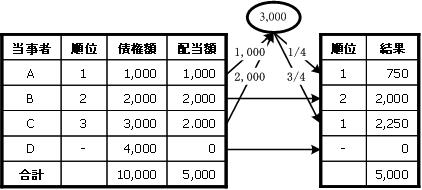 |
(A) 抵当権の順位の変更の意味
抵当権の順位の変更とは,抵当権者相互間で,その順位を被担保債権と完全に切り離して入れ替えることをいう。
先の例で,Cを1番抵当権者,Aを2番抵当権者,Bを3番抵当権者とすることは,もしも,各抵当権者の債権額が同じであれば,下のように,抵当権の順位の譲渡を複数回繰り返すことによって可能となるが,先の例のように,各債権者の債権額が異なる場合は,優先順位の譲渡の場合の債権額を調整しなければならず,理論的には問題がないとしても,実際の実現手続は困難であることが予想される。
 |
そこで,民法は,1971(昭和46)年の改正によって,抵当権の順位の変更手続を新設し,立法的な解決を行った。
(B) 抵当権の順位の譲渡等との相違点
抵当権の順位の変更は,各抵当権者が被担保債権をそのまま保持しつつ順位を入れ替え,処分の後の抵当権の各順位の被担保債権額に変動が生じる点で,処分後も各順位の被担保債権の額に全く変更を生じない抵当権の順位の譲渡と異なる。
これまでに取り上げた5つの抵当権の処分は,いずれも抵当権の処分の当事者のみに影響を及ぼし,他の後順位抵当権者には影響を与えないため,当事者間以外の者の承諾は必要がなかった。しかし,抵当権の順位の変更の場合は,当事者以外の抵当権者に影響を与えるので,影響を受ける抵当権者全員の合意と,利害関係人の承諾が必要である[民法374条1項]。
なお,他の抵当権処分の登記が効力要件ではなく,対抗要件とされているのに対して,抵当権の順位の変更登記は,法律関係が複雑になることを避けるため,効力要件とされている[民法374条2項]。
債務者が債務を任意に履行しないときは,抵当権者は抵当権を実行し,実行によって得られる金銭から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる。その場合の実行方法は,目的物が不動産の場合には,担保不動産競売[民事執行法180条1号]と担保不動産収益執行[民事執行法180条2号],動産の場合には,動産競売[民事執行法190条],債権の場合(物上代位権の行使の場合)には,債権についての担保権の実行[民事執行法193条1項2文]の各手続きにしたがって実行される。そして,最終的には,目的物の所有権は買受人に移転する[民事執行法79条,184条]とともに,抵当権者は目的物の売却代金から優先的に配当を受ける。そして,抵当権は優先弁済権の満足によって消滅する(消除主義)[民事執行法59条1項]。
担保権の実行手続きについては,代表的な担保不動産競売手続きを例にとって,その開始決定と差押え,換価準備,換価,そして,満足による抵当権の消滅という手続きの流れを理解する。また,平成15年に創設された不動産収益執行についても,その手続きの流れと特色を理解する。
抵当権の実行手続について,競売手続のあらましと私的実行である抵当直流れについて概観するのがここでのねらいである。
民事執行法の第3章(180条~195条)が,「担保権の実行としての競売等」を規定しているため,抵当権の実行については,民事執行法の規定を参照することが必要となる。
| 抵当権の実行の種類 | 条文 | |
|---|---|---|
| 民事執行 | 担保不動産競売 | 民事執行法180条1号,188条で強制競売の規定を準用 |
| 担保不動産収益執行 | 民事執行法180条2号,188条で強制管理の規定を準用 | |
| 私的実行 | 抵当直流れ(流抵当) | 代物弁済予約と同じ |
| 任意売却 | 破産法78条(破産管財人が管理処分権に基づき,裁判所の許可を得て行う) |
民事執行法に基づく担保不動産競売と担保不動産収益執行とは,並存的に認められ,抵当権者は,いずれを選ぶこともできるし,両者を同時に行うこともできる。すなわち,抵当権者は,担保不動産収益執行によって賃料から優先弁済を受けつつ,それで満足できない場合には,担保不動産競売で最終的な満足を受けるということができる。
抵当権の実行による実体法上の問題としては,抵当権は,抵当権の実行によって消滅するという点が重要である。抵当不動産が他の債権者によって強制執行に付された場合にも,抵当権は消滅する(消除主義:[民事執行法59条])。抵当不動産に対する他の担保権者(後順位抵当権者を含む)がこれを担保不動産競売に付した場合も同様である[民事執行法188条]。また,担保不動産競売が実施されると抵当権は消滅するから[民事執行法59条1項],担保不動産収益執行も終了することになる。
担保不動産競売および担保不動産収益執行の詳細は,民事執行法の解説書([中野・民事執行概説(2006)],[上原他・民事執行法(2006)]など)を参照されたい。ここでは,それぞれの概略について解説するに留める。
不動産を対象とする民事執行のほとんどは担保不動産競売であり,その件数は,通常の強制競売の10倍以上を占めている[上原他・民事執行法(2006)217頁]。担保不動産競売のなかでも,抵当権に基づくものが大半を占めるとされている。
担保権の実行としての執行手続きは,概略,①債権者の申立て,②担保目的財産の差押え,③換価の準備,④換価,⑤配当,⑥満足という経過をたどる点で,「原則として,金銭債権の強制執行におけると同一の手続きによることになった」[中野・民事執行概説(2006)281頁]。
不動産を目的とする担保権の実行は,抵当権による場合を含めて,執行裁判所に対する書面(申立書)による申立てによる[民事執行規則1条]。申立書には,債権者,債務者のほか,目的物の所有者,担保権・被担保債権・目的物の表示などが記載されなければならない[民事執行規則170条]。
| 債権者 | 執行裁判所 | |||
| 手続きの流れ | 根拠条文 | 手続きの流れ | 根拠条文 | |
| 競売の申立て | 担保不動産競売の申立て | 民事執行法181条 | 抵当権の存在を証する 文書の目録等の 相手方への送付 |
民事執行法181条4項 |
| 抵当権の存在を証する文書 (執行名義) (通常は,「登記事項証明書」) |
民事執行法181条 | |||
| 不動産競売の申立書の提出 | 民事執行規則170条 | |||
担保不動産競売を開始するには,強制執行の場合とは異なり,債務名義は要求されない。それに代えて,担保権の存在を証する一定の文書(法定文書)の提出(いわゆる執行名義)が必要である[民事執行法181条]。通常の債権に基づく強制執行の場合と担保権の実行とでこのような区別が生じた理由は,以下のような歴史的な経緯に基づくものである[中野・民事執行概説(2006)275-277頁]。
民事執行法の成立(1979年)以前には,旧民事訴訟法第6編に規定されていた強制執行とは異なり,担保権の実行は競売法(1980年廃止)に規定されており,両者は,完全に区別されていた。担保権を有しない一般債権者の債権を満足させるために,国家の強制執行権に基づいて債務者の一般財産を差し押さえて換価するのが強制執行の手続きであるから,一般債権者の債権の存在を公証する文書である判決等の債務名義を必要とする(この例外が債権者代位権,詐害行為取消権である)。これに対して,担保権の実行は,物権者である担保権者が担保権に内在する換価権を行使して担保目的物である特定財産を換価し,被担保債権の優先的弁済に充てる手続き(任意競売)であるから,債務名義は必要ないと考えられてきたのである。
もっとも,担保権の実行手続きである任意競売においては,強制競売の場合よりも開始要件は緩やかであるが,後になって担保権が存在しないことが証明されると,競落人(買受人)の代金納入後もその所有権取得を争うことができるとされており〈最三判昭37・8・28民集16巻8号1799頁〉,強制競売の場合に比べて,買受人の地位は不安定なものであった。しかし,一般債権者であれ,担保権を有する債権者であれ,債務者が債務不履行になった場合には,債権の効力として掴取力を有しており,その作用として実体法上も債権の満足を得ることのできる範囲で換価権を有するのであるから,両者を区別する実質的な理由は存在しない。そこで,民事執行法の制定により,競売法は廃止され,強制執行も担保権の実行も,同一の法典の中に組み込まれることになった。
その際,立法論としては,さらに一歩を進め,担保権の実行についても,国家の執行権行使の前提として債務名義を要求すべきであり,かつ,強制執行の一部として同一の法典の中に規定すべきであると主張されていた。そして,担保権の実行手続きにも,公正証書や受忍判決などの債務名義(物的債務名義)を要求する方向で検討がなされた。しかし,担保権の実行には債務名義を必要としないという慣行が定着していたことを尊重して,民事執行法においても,従来どおり,担保権の実行には債務名義が要求されないことになったのである。
ただし,民事執行法における担保権実行の規定については,強制執行の場合と比較した場合に,以下の問題が生じていた。入口の要件が厳しく,確定判決等の有効な債務名義が要求されるために,仮に現実には執行債権が存在しない場合でも,目的物が債務者の財産に属する限り,買受人は所有権を取得しうる(ただし,民法568条の担保責任の問題が生じる)と解されている強制執行と比較してみよう。担保権の実行は,入り口の要件が緩く,債務名義が要求しないにもかかわらず,出口の公信的効果として,買受人が代金を納入すれば,たとえ担保権が存在しない場合にも,買受人の競売による所有権の取得は妨げられないと規定されている[民事執行法184条]。これでは整合性が保たれていないといわざるを得ない。
そこで,民事執行法における担保権の実行においては,入口の要件が緩く,債務名義を要求しないにもかかわらず,出口の公信的効果を認めていることを正当化するために,旧競売法とは異なる,以下のような手続上の手当てが行われている[中野・民事執行概説(2006)279-280頁]。
| 旧競売法 (1980年廃止) |
民事執行法(1979年制定) | ||
| 担保権の実行 | 強制執行 | ||
| 競売開始の要件 | 債務名義も法定文書も必要としない(旧競売法22条1項参照)。 | 債務名義は必要としないが,法定文書の提出が必要[民事執行法181条]。 | 債務名義が必要[民事執行法22条]。 |
| 競売開始決定 に対する異議 |
明文の規定なし。 判例は,実体上の理由に基づいて異議を申し立てることができるとしていた(大決大2・6・13民録19輯436頁等)。 |
執行異議[民事執行法11条],執行抗告[民事執行法10条]という「決定手続き」によって,債務者・所有者は,担保権の不存在や消滅(実体異議)を,買受人の代金納付に至るまで主張することができる[民事執行法182条]。さらに,担保権不存在確認の訴え等を提起して,判決手続きによる救済を求めることもできる([民事執行法183条1項1号,2号]参照)。 | 実体法上の不服申立ては,請求異議等の「訴訟手続き」による必要がある。 |
| 手続きの 停止・取消し |
明文の規定なし。 異議の申立てがあっても,競売手続停止の効力を有しないとされていた。 |
担保権の登記抹消に関する登記事項証明書など,担保権の実行を妨げる事由を証する法定の公文書があれば,担保権の実行手続きを停止し,執行処分を取り消すことができる[民事執行法183条]。 | 民事執行法39条に掲げられた裁判の正本等の「執行取消文書」が提出された場合に限定されている。 |
| 買受人の 権利の確保 |
明文の規定なし。 判例は,競売に公信的効果はないとしていた〈最三判昭37・8・28民集16巻8号1799頁〉。 |
競売に公信的効果がある[民事執行法184条]。 ただし,第1に,目的物の所有者が担保権のないことを理由に競売手続きを阻止する機会を十分に保証されなかった場合(偽造文書によって競売が行われた場合など),第2に,買受人が担保権のないことを知っていた場合など,買受人の信頼利益を保護する必要がない場合にも,公信的効果は否定される。 |
競売に公信的効果はない。 目的物に権利の瑕疵がある場合には,買受人は追奪を受けるので,買受人は,民法568条によって保護される(ただし,民法570条の保護はない)。 |
上の表からもわかるように,担保権の実行手続きは,①担保権を通常の債権とは異なる権利(物権)として,特別法(旧競売法)によって処理され,過剰に優遇された時代から,②通常の金銭債権と同様に,民事執行法という同一の法典の下で,かつ,強制執行手続きを準用する[民事執行法188条,192条,194条]という形で統一化が進行する時代へと移行しているといえよう。
本書の立場のように,物的担保を物権ではなく,保護されるべき法定の債権の場合(留置権,先取特権)または一般債権でも,物的担保とする合意と公示とがある場合(質権,抵当権,仮登記担保,譲渡担保)には,債権の掴取力が強化され,一定の範囲で他の債権者に先立って弁済を受けることができるに過ぎないと考えるならば,担保権の実行手続きは,金銭債権の強制執行と区別する必要はなくなるのであるから,将来的には,担保権の実行手続きは,強制執行と全く同一の手続きに組み込むことも可能となろう。
なお,上の表でも明らかなように,民事執行法184条で規定された公信的効力は,担保権実行の入口で債務名義が要求されないにもかかわらず,競売手続きにおける実体法上の理由に基づく異議を広く認めていることに基づいて認められたものであり,以下の判例〈最三判平5・12・17民集47巻10号5508頁〉のように,所有者が悪意の場合であっても,所有者が手続き上当事者として扱われていない場合には,買受人は,民事執行法184条による所有権の取得を主張できないとしている点に注意を要する。
最三判平5・12・17民集47巻10号5508頁
民事執行法184条を適用するためには,競売不動産の所有者がたまたま不動産競売手続が開始されたことを知り,その停止申立て等の措置を講ずることができたというだけでは足りず,所有者が不動産競売手続上当事者として扱われたことを要する。
抵当権の実行手続きを含めて,担保権の実行手続きの第1段階は,強制執行と同様に,執行機関による担保目的物の差押えによって開始される[民事執行法188条,45条1項]。旧競売法には,強制競売の場合とは異なり,債権者のために不動産の差押えを宣言する旨の規定がなかった[斎藤・競売法(1960)116頁]。このため,差し押えの効力がいつ,どのように生じるのか等を含めて,手続きの不安定が生じることもあった。民事執行法は,担保権の実行においても,強制執行の差押えに関する規定を準用することによって,この問題を解消したのである。すなわち,担保権者が法定文書(抵当権の場合には,登記事項証明書が一般的)を提出して不動産競売の申立てをすれば,執行裁判所が不動産競売の開始決定をし,不動産を差し押さえる旨を宣言することによって開始する[民事執行法188条による45条1項の準用]。
担保権の実行の開始としての不動産競売の差し押さえについては,以下の表のように,基本的に,強制執行の競売に関する規定が準用される。ここでは,担保権の実行に関する特則だけを説明するに留める。
競売開始決定前の保全処分 担保不動産競売手続きについては,不動産占有による価値減少行為を防止するため,独自の類型として,開始決定前の保全処分が認められている[民事執行法187条]。
平成15(2003年)年の担保法改正(「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」(平成15年法134号)に基づく一連の改正)以前は,この規定は,滌除に関連した執行妨害を防止するための規定として存在していたが,滌除制度が廃止されて,滌除に関連する抵当権の実行通知制度[民法旧381条]が廃止された後も,抵当権の実行直前に執行妨害が行われることを考慮して,開始決定前の保全処分が存続されることになった。
強制執行における売却のための保全処分[民事執行法55条]は,競売申立てと同時か,それ以降でないと申し立てることができないが,担保権執行では,担保不動産に対する価値減少行為があるときは,競売開始決定前でも,担保権者の申立てによって執行裁判所は,売却のための保全処分とほぼ同等の行為命令・執行官保管命令,公示保全処分ができる[民事執行法187条1項]。
競売開始決定前の保全処分は,債務者または不動産の所有者・占有者が不動産の価格を減少させる行為をするおそれがある場合に,執行裁判所が特に必要があると認められるときに命じられる[民事執行法197条1項本文]。申立権者は,担保権を実行しようとする者であり,処分の内容は,禁止命令,行為命令,執行官保管命令,公示保全命令であり,売却のための保全処分と同じである[民事執行法187条1項,55条1項の準用]。
競売開始決定前保全処分の特則として重要な点は,第1に,競売開始決定が将来なされるであろうことを明らかにするために,担保権実行に必要な文書を提出しなければならないこと[民事執行法187条3項],第2に,申立人が保全処分の決定の告知から3ヶ月以内に競売申立てをしたことを証する文書を提出しないときは,保全処分の相手方または不動産の所有者の申立てにより,保全処分が取り消されること[民事執行法187条4項]である。
この競売開始決定前の保全処分は,競売開始後も継続し,引渡命令まで引き継がれて行く。この点は,売却のための保全処分と同じである[民事執行法187条,55条の準用]。
競売開始決定-差押え-の効力 差押えの効力については,強制競売の差押えに関する規定が準用されている[民事執行法188条]。差押えの効力は,開始決定が債務者に送達されたときに生じるが,差押えの登記がこの送達よりも前のときは,登記のときに生じる[民事執行法46条1項の準用]。
債務者は,差押えの効力発生後も,通常の用法により,不動産を使用・収益することができる[民事執行法46条2項の準用]。差押えの処分禁止の効力は,「手続相対効」と解されている(詳しくは,[中野・民事執行法(2006)388頁]参照)。すなわち,差押えの効力発生後に所有者のする処分は,所有権の譲渡,抵当権の設定,用益権の設定を問わず,差押債権者のほか,手続きに参加する他の債権者に対抗できない。したがって,差押えの効力が発生した後の処分は,競売手続上,すべて無視されることになる。例えば,差押登記後に抵当権の設定登記を受けた債権者は,たとえ抵当権の実行としての二重競売開始決定を受けたとしても,それだけでは,配当にあずかることはできない。
担保権の実行手続きの第2段階として,差し押さえられた目的財産を金銭化する換価の手続きについても,金銭債権の強制執行の換価についての規定が準用され,これと同一の手続きによって処理される[民事執行法188条]。
換価を適正に行うためには,関係者が,目的不動産およびそれに付随する物の現況,ならびに,不動産上の権利関係の内容を正しく把握することが必要である。これが,不動産の換価のための準備である。
不動産換価のための準備として,第1に,執行裁判所は,執行官に不動産の現況調査を命じなければならない[民事執行法188条による57条の準用]。また,執行裁判所は,評価人を選任して,不動産を評価させなければならない[民事執行法188条による58条の準用]。
第2に,執行裁判所は,評価人の評価に基づいて,不動産の売却額の基準となるべき価額(売却基準価額)を定めなければならない[民事執行法188条による60条の準用]。
第3に,裁判所書記官は,物件明細書を作成して,売却実施の日の1週間前までに裁判所にその写しを備置き,一般の閲覧に供し,または裁判所規則で定める措置(インターネットに接続された自動公衆送信装置を使うなど)を講じて,不特定多数の者がその内容の提供を受けることができるようにしなければならない[民事執行法188条による62条2項,民事執行規則31条1項,2項の準用]。
これらの措置は,買受けの申出をしようとする者が,正確な情報を事前に,かつ,容易に入手できるようにし,買受人が不足の損害を受けないようにするとともに,売却価額が不当に安くなることを避けるために規定されたものである。
不動産の換価の準備に引き続き,換価手続きが行われる。不動産執行の強制競売に関する規定がそのまま準用される結果[民事執行法188条],旧競売法の下で,担保権実行の特色として強制執行とは異なる手続きによっていたものが,強制執行と統一的に解決されることになったものが多い。
第1に,強制執行における剰余主義[民事執行法63条]を準用する結果として,旧競売法下では,担保権に内在する換価権の行使であることを理由に無剰余換価を認めていた実務が改められることになり,担保権の実行と金銭債権の強制執行の差がさらに縮められたことになる。先順位抵当権者の債権および手続費用を弁済してもなお剰余が生じる見込みがないときは,後順位抵当権者自らが,それらの債権と費用とを弁済できる価格で買い受けるとの保証をしない限り競売の申立てが認められないのは,以上の経緯による。
第2に,超過売却禁止の原則,すなわち,数個の不動産を売却した場合において,あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは,執行裁判所は,他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならないという原則[民事執行法73条]についても,旧競売法下では準用されていなかった[旧競売法32条2項]。立法者は超過競売を許す趣旨であったとみられるが,通説・判例は超過競売を許さないとしていた[斎藤・競売法(1960)160頁]。そこで,民事執行法は,上記の原則を適用して,超過競売を禁止した。ここでも,担保権の実行手続きと金銭債権の強制競売の手続きが統一化されている。
なお,担保不動産競売の場合に法定地上権の規定[民事執行法81条]が準用されない理由は,もともと,民法には,担保不動産の実行の場合に,法定地上権の条文[民法388条]が用意されているからである。もっとも,現代語化前の民法旧388条の規定には不備があったが,現代語化の際に,民事執行法81条と同様の規定に改められ,ここでも,担保法の実行手続きと金銭債権の強制執行手続きの統一化が実現されている。
ここでいう「民法旧388条の不備」とは,第1は,民法旧388条は,「抵当権設定者は競売の場合に付き地上権を設定したるものと看做す」と規定していたことである。これでは,建物のみに抵当権が設定された場合の解決策だけが規定されただけであり,土地のみに抵当権が設定された場合については,何の解決策も示されていなかった。第2は,第1点と関連するが,民法旧388条が,法定地上権の成立について,「抵当権設定者は…地上権を設定したるものと看做す」と規定していたため,法定地上権の目的が,本来は「建物の保護」という客観的な基準であるにもかかわらず,「当事者の意思の推測」という主観的な基準であるかのような誤解を招くことになった。この2つの不備を補うため,現代語化に際して,現行民法388条は,民事執行法81条の規定にならって,「土地又は建物につき抵当権が設定され,その実行により所有者を異にするに至ったときは,その建物について,地上権が設定されたものとみなす」と規定した。このことによって,法定地上権は,建物を保護するという客観的な目的のために,建物の利用権を確保するものであるということが明確となったのである。
上に述べたように,民法388条と民事執行法との間で完全な疎通が図られたため,民事執行法188条は,抵当権の実行(担保不動産競売)の場合に,不動産強制執行の規定を準用するに際し,法定地上権の成立の重複を避けるために,民事執行法81条の準用だけを除外したのである。したがって,民法388条の解釈においては,仮に民事執行法が適用されたならば,法定地上権が成立するという場合(抵当権設定時には土地およびその上の建物の所有権が同一人に帰属していないが,抵当権の実行の時には同一人に帰属している場合など)について,民法388条の適用を除外してはならないという点に留意すべきである。なぜなら,民法388条による法定地上権の成立の範囲を狭めるならば,同調(シンクロ)が取れていたはずの両規定の間に隙間ができ,建物の保護という民事執行法と民法との共通目的が実現されないことになるからである。
不動産の売却によって,抵当権は消滅する[民事執行法59条1項]。また,抵当権に対抗できない権利も同時に効力を失う[民事執行法59条2項]。
不動産競売の買受人は,代金を納付することによって不動産の所有権を取得する[民事執行法188条による79条の準用]。そして,この効果は,担保権の不存在または担保権の消滅によって妨げられない[民事執行法184条]。
この規定によって,担保不動産競売に公信的効果が認められたことになる。この点については,(i)「担保不動産競売の申立て」の箇所において,旧競売法,担保権の実行,強制執行との比較を通じて,詳しく論じたので,ここでは繰り返さない。
なお,競売による買受に関しては,民法390条は,「抵当不動産の第三取得者は,その競売において買受人となることができる」としている。抵当目的物の所有者である第三取得者が自分の物の買受人になるというのは,一見したところでは,奇妙である(通説は,「自己が自己に売る関係になるので,特に規定を置いたものであるが,当然のことである」[内田・民法Ⅲ(2005)449頁]と説明している)。そこで,民法の立法理由を見てみると,「当然のこと」ではなく,以下のように記述されていることがわかる。
(理由)本条は既成法典担保編第280条に文字の修正を加ヘたるのみ。原文に「原証書確認の証書」としてと云ヘるは啻〔タダ〕に法文としての体裁宣しきを得さるのみならず,第三取得者が競落人となりたる場合に於ては,寧ろ,新権原に由りて之を取得したるものと視るを妥当とす。而して唯権原の更まるのみにして取得者は其人を同じうするを以て,単に附記を爲せば足れるものとするなり。殊に「証書確認」と言ふは頗る解し難きものなり。或は草案に於て「権原(titre)の確認」と云ひしを誤りて「証書確認」と訳したるものならん。
旧民法債権担保編 第280条
①総ての場合に於て,解除の請求なく又は其認許なきときは,第三所持者は競売の際競買人と為ることを得。
②第三所持者の利益に於て競落を宣告したるときは,其判決は原証書確認の証拠として,其原証書に依る登記に之を附記するのみ
以上のように,民法の立法者によれば,民法390条は,競売によって,第三取得者に抵当権が消滅した物件を,「新権原」として取得することを認めるものであった。このように,一見,意味が不明の条文の立法理由をたどると,現行民法の立法者の意図を理解することができるとともに,旧民法には,ボワソナードの作成した草案(Projet)の趣旨を読み誤った誤訳(旧民法に「原証書」とあるのは,実は,「権原(titre)」の誤訳)が存在することも明らかとなって興味深い。
担保権の実行手続きも,金銭債権の強制執行と同様に,その最終段階(第3段階)として,目的物の換価金から債権者に満足させることによって終了する。債権者が1人であるか,2人以上でも,換価金から執行費用および債権額全額を弁済できれば,それで終了するが[民事執行法84条2項],競合する債権者の全員を満足させることができないときは,配当手続きによって換価金を分配しなければならない。
配当手続きにおいては,第1に,第三取得者に対して,「他の債権者より先に」その支出した費用が償還される[民法391条]。これは,第三取得者に一種の共益費用の先取特権[民法329条2項]を認めたものである。その理由は,第三取得者が支出した必要費または有益費は,抵当不動産の価値を維持するのに最も密接な関連を有するものだからである。
配当手続きにおける担保権の実行としての二重の競売申立ての取扱い,配当要求の範囲および配当手続きについても,強制執行と同一の手続きによって処理される。
旧競売法の下では,不動産に対する任意競売と強制競売の競合の取り扱い,任意競売についての配当要求の可否,配当手続きの有無について説が分かれており,判例は,競売法による競売手続きには,強制執行の配当手続きに関する規定の準用はないとしてきた(〈大判大2・10・28民録19輯875頁〉ほか)。
この問題を解決するため,民事執行法は,いずれの場合にも,不動産の強制競売と同様の手続きによって処理することにしている[民事執行法188条]。すなわち,第1の競合の問題については,強制競売または担保権実行としての競売開始決定がなされた不動産について,さらに担保権の実行または強制競売の申立てがなされた場合には,二重の競売開始決定がなされる[民事執行法188条による47条1項の準用]。第2に,配当要求の可否については,担保不動産競売においても,強制競売と同様,債務名義のある債権者,仮差押えの登記をした債権者および一般の先取特権者だけが配当要求をすることができる[民事執行法188条による51条1項の準用]。第3に,配当手続きについては,担保不動産競売においても,強制競売と同様の配当手続きが行われることになる[民事執行法188条による84条以下の準用]。
平成15(2003)年の担保・執行法の改正以前は,抵当不動産の第三取得者による滌除の制度をめぐって,さまざまな問題点が指摘され,改正が要望されていた。担保・執行法の改正によって,滌除の仕組み自体は廃止されず,従来からその弊害とされていた点を改め,名称も,滌除から,「抵当権消滅請求」へと変更された[民法379条~386条]。
抵当権消滅請求[民法379条~386条]の実体法上の意義については,後に,第9節C(b)で詳しく論じるが,その手続きの概略は,以下の通りである。
第1に,抵当権の第三取得者は,抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に,抵当権の登記をした各債権者に対して,抵当不動産の代価等,法定の要件を記載した書面を送付して,抵当権の消滅請求を行う。第2に,抵当権の登記をした各債権者が抵当権消滅請求の書面の送付を受けた後2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは,送達された書面によって提供された代価等を債権優先の順位に従って弁済(供託)する旨を承諾したものとみなされる。第3に,抵当不動産の第三取得者がその代価等を払い渡すか,供託したときに抵当権は消滅する。
抵当権者も債権者であるから,一般債権者の立場で債務者の一般財産に対して強制執行をすることもできる。しかし,抵当権者は,抵当目的物に対して優先弁済権を確保しておきながら,債務者の一般財産に対して強制執行をすることを認めたのでは,他の一般債権者を害することになる。そこで,民法394条は,抵当権者の一般財産への執行を制限している。すなわち,抵当権者は,まず,抵当目的物に対して担保執行を行い,その代価で弁済を受けられなかった債権の部分についてのみ債務者の強制執行をすることができるに過ぎない[民法394条1項]。
しかし,抵当権の実行前に他の財産が強制執行される場合には,抵当権者は,債権全額について,強制執行の目的となった財産から他の債権者と平等の立場で配当を受けることができる[民法394条2項1文]。ただし,この配当に対しては,他の債権者は,その後抵当権が実行されて抵当権者が優先弁済を受けうる額についてはそれを控除すべきであることを根拠として,抵当権者に優先弁済を受ける額を控除した債権額での按分比例による配当額のみを受け取らせるために,抵当権者に配当すべき金額を供託するように請求することができる[民法394条2項2文]。そうなると,結果的には,抵当権者は,民法394条1項の場合と同じ配当しか得られないことになる。
国税[国税徴収法8条]および地方税[地方税法14条]の租税債権は,納税者の総財産の上に効力を及ぼす一般の先取特権として扱われる。国税,地方税の法定納期限等以前に抵当権が設定されているときは,抵当権が国税,地方税に優先する。なお,滞納処分(国税徴収法)と強制執行(担保権の実行としての競売を含む)との競合に関しては,滞納処分と強制執行との手続の調整に関する法律が,両者の手続きの調整を図っている。
2003(平成15)年の担保・執行法改正以前は,抵当権などの不動産担保権の実行方法としては,競売のみが認められ,不動産の収益を対象とする強制管理類似の制度は認められていなかった。しかし,抵当不動産が大規模のテナントビルであるような場合には,抵当不動産の売却には時間を要するが,賃料等の収益が継続的に認められることがあり,抵当不動産の賃料から優先弁済を受けることのできる制度を求める声が高まっていた。
また,抵当不動産の賃料に対する抵当権の行使を認めた判例〈最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件)〉を契機として,抵当権に基づく物上代位による賃料差押えの手続きが実務上定着するようになった。この手続きによって,抵当権者は,債務者の債務不履行後は,実質的に目的不動産の収益を把握できることになった.。
しかし,抵当権に基づく賃料債権に対する物上代位の手続きについては,以下のように,さまざまな弊害が指摘されている。
第1に,物上代位によると,不動産の賃料の中に含まれている管理費相当額まで取り立ててしまうため,所有者は,抵当不動産の管理を適切に行うことができなくなり,不動産がスラム化するおそれがある。第2に,担保不動産に多数の賃借人がいるときは,賃借人を特定して賃借人ごとにその賃料債権を差し押さえる必要があり,債権者にとっても面倒である。第3に,債権者は,賃料不払いなどを理由に賃貸借契約を解除したり,新たに賃貸借契約を結ぶことができないなど,不動産自体を管理することができない。第4に,執行妨害のおそれがある場合には,不動産自体を占有する管理手続きでなければ適切に対処できない。
このような点を考慮して,2003(平成15)年の担保・執行法改正によって,担保不動産収益執行制度[民事執行法180条以下]が新たに導入されるに至った。
この担保不動産収益執行制度は,従来の担保不動産競売手続きと別個に規定するのではなく,ともに不動産担保権実行の方法として,一括して両者に適用される規定が置かれることになった[民事執行法180条~183条]。そして,不動産担保権の実行は,担保権者が,担保不動産競売の方法と担保不動産収益執行の方法のいずれか,または,双方を選択して申し立てることができる[民事執行法180条]。
さらに,抵当権に基づく物上代位による賃料差押えも,担保不動産収益執行制度と引換にその廃止論が唱えられたにもかかわらず,廃止することなく維持されることになったため,担保権者は,事案に応じて,担保不動産収益執行の手続きか,物上代位の手続きかを選択できる。双方の関係は,理論的には,賃借人の数が少なく賃料額も低いような不動産には,物上代位の手続きが適し,賃借人が多数で不法占拠者の排除や新規契約等の管理行為を必要とするような不動産には,担保不動産収益執行の手続きが適しているとされている。しかし,現在においても,賃料が高くて効率のいい物件に対して,物上代位手続きが濫用的に用いられている。このような実態からみても,2003(平成15)年に担保不動産収益執行の制度が創設された時点で,抵当権に基づく賃料債権に対する物上代位の制度は廃止されるべきであった[内田・民法Ⅲ(2005)461頁]。したがって,解釈論としても,物上代位の及ぶ範囲は,少なくとも,管理費用に及ぶことがないよう,限定的に解釈すべきであると思われる。
担保不動産収益執行の開始要件は,担保不動産競売の場合と同じであり,法定文書の提出を要する[民事執行法181条]。
担保不動産収益執行における開始決定・差押えについても,担保不動産競売と同じ規定が適用され[民事執行法181条以下],担保不動産収益執行については,強制管理の規定が準用される[民事執行法188条]。
したがって,担保権者が法定文書を提出して,担保不動産収益執行の申立てをすれば,執行裁判所は,担保不動産収益執行の開始を決定し,担保不動産の差押えを宣言し,債務者に対して収益の処分禁止を命ずるとともに,管理人を選任して,不動産の賃借人に対して賃料等を管理人に交付すべき旨を命ずる[民事執行法188条による93条,94条の準用]。
担保不動産の収益執行においては,未収穫の天然果実,未払いの法定果実については,差押えの処分禁止効が及ぶが,差押時に収穫済みの天然果実については,差押えの処分禁止効は及ばないと解されている。そこで,平成15(2003)年の担保・執行法改正によって,強制管理と担保不動産収益執行における差押えの処分禁止効の範囲を統一するため,民事執行法93条2項の規定から,「既に収穫した天然果実」を削り,「後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し,又は後に弁済期が到来すべき法定果実」に差押えの処分禁止効が及ぶことになった。両手続きにおける処分禁止効の範囲が異なることになれば,二重開始決定をした場合の処理が複雑になるからである。
不動産収益執行における換価としての収益の収取および換価についても,強制執行における強制管理の規定が準用される[民事執行法188条]。したがって,執行裁判所による不動産収益執行開始決定とともに管理人が選任される[民事執行法94条]。
管理人は,不動産を管理し,また不動産の収益を収取することができる[民事執行法95条1項]。管理人は,不動産につき第三者と賃貸借契約を締結し(長期の場合は抵当権設定者の同意が必要である),賃借人を抵当不動産に入居させることができる[民事執行法95条2項]。また,管理人は抵当権設定者の占有を解いて管理人自らが不動産を占有することもできる([民事執行法96条],ただし[民事執行法97条]は,執行裁判所が抵当権設定者および同居の親族の建物使用の許可をすることができる旨を規定している)。さらに,担保不動産収益執行により,抵当権設定者の生活が著しく困窮することとなるときは,執行裁判所は,申立てにより,管理人に対し,収益又はその換価代金からその困窮の程度に応じ必要な金銭又は収益を債務者に分与すべき旨を命ずることができる[民事執行法98条]。管理人は,一方で,善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならず,注意を怠ったときは,管理人は,利害関係を有する者に対し,連帯して損害を賠償する責任を負う[民事執行法100条]が,他方で,管理人は,強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる[民事執行法101条]。
この不動産の収益は,すでに述べたように,「後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し,又は後に弁済期が到来すべき法定果実」[民事執行法93条2項]である。管理人は,天然果実を売却し,地代・賃料を取り立てるなど,これらの収益の収取および換価をするため,必要な裁判上・裁判外の行為をすることができる([民事執行法95条~98条]参照)。
不動産収益執行・強制管理において配当を受ける債権者は,執行裁判所の定める期間ごとに,その期間の満了するまでに執行の申立て等の手続きを経た以下のような者である[民事執行法188条による107条の準用]。
強制執行とは異なり,不動産上に登記を有する担保権者であっても,上記に該当しない者は配当を受けることができないことになるが,収益執行の場合は,担保権が消滅するわけではないこと,すなわち,不動産収益執行は競売に代替する終局的な優先弁済の方法ではないことが,このような規定が制定された理由となっている。
配当等に充てるべき金銭は,第98条第1項の規定(抵当権設定者困窮の場合)による分与をした後の収益又はその換価代金から,不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用(賃貸ビルや賃貸マンション等の管理会社の報酬・共用部分の電気代・ガス代・水道代・エレベータの保守管理費用等)を控除したものである[民事執行法106条]。
管理人は,執行裁判所の定める期間ごとに,配当等を実施しなければならない[民事執行法107条1項]。債権者が1人である場合又は債権者が2人以上であって配当等に充てるべき金銭で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には,管理人は,債権者に弁済金を交付し,剰余金を抵当権設定者に交付する[民事執行法107条2項]。これ以外の場合で,配当等に充てるべき金銭の配当について債権者間に協議が調ったときは,管理人は,その協議に従い配当を実施する[民事執行法107条3項]。協議が調わないときは,管理人は,その事情を執行裁判所に届け出なければならない[民事執行法107条5項]。その場合には,執行裁判所が直ちに配当等の手続を実施しなければならない[民事執行法109条]。
担保不動産収益執行の差押えと強制管理および物上代位による差押えが重複して申し立てられた場合に,相互を調整する規定が置かれている[民事執行法188条による93条の2,93条の3,93条の4]。
第1に,強制管理または他の収益執行の開始決定が先行した不動産について収益執行(または強制管理)の申立てがなされた場合には,二重の開始決定をする[民事執行法188条による93条の2の準用]。
第2に,不動産収益の給付請求権について,物上代位等の債権執行による差押命令または仮差押命令が先行した後に収益執行等の開始決定の効力が生じた場合には,先行手続きを吸収して収益執行等の手続きに一本化するため,先行する物上代位等の差押命令等の効力は停止することになった[民事執行法188条による93条の4第1項本文,同条2項の準用]。
担保不動産執行は,抵当権者による物上代位の行使が,自らは管理も何もせずに,賃料全額を収奪するものであるため,賃貸物件のスラム化を招く等大きな弊害をもたらしているのに比較して,弊害の少ない制度ということができる。
しかし,第1に,制度設計の根本にさかのぼるならば,この制度は,不動産質を管理会社に委ねたのと同じ機能を有することになる。したがって,いわゆる非占有担保権(厳密には,使用・収益を奪わない担保権)である抵当権に,いわゆる占有担保物権である不動産質と同じ権能を認めることが理論的に許容されるかどうかという問題を抱えている。
第2に,担保不動産収益執行の実際の運用は,管理人が抵当権者のために長期にわたり債権の優先回収を図るという制度趣旨に沿ったものになっておらず,「近い将来申し立てる担保不動産競売申立て(これによって,抵当権の設定登記に遅れて成立した賃貸借契約をすべて覆ることができる)を効率的に行うために,管理人に不動産を管理させ,抵当権実行妨害目的の占有者等の入居を阻止したり,占有者の実態を把握させる」ために(担保不動産競売の補完的役割を果たすに過ぎないものとして)利用されているという(詳細については,生熊長幸「担保不動産収益執行制度-物上代位との関係」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)43-44頁]参照)。
このような実態からすると,いわゆる非占有担保権としての抵当権者にいわゆる占有担保権としての不動産質権者の権能まで認めることには,せいどっ設計上無理があったのであり,「単に抵当権に基づく賃料債権への物上代位を合理化するだけの制度設計のほうが現実的ではなかったか」生熊長幸「担保不動産収益執行制度-物上代位との関係」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)44頁]という説が説得的である。後に述べるように*第5節5(抵当権の物上代位),物上代位については,それを合理化するために,効力の及ぶ範囲を「担保目的物のなし崩し的減価」(賃料から管理費等を差し引いた部分)に限定するという解釈論が採用されるべきであろう。
債権の弁済期前の特約で,債権者である抵当権者に目的不動産を取得させることが可能である。このような特約を抵当直流れ(じきながれ)という。
抵当直流れは,抵当権の実行に関して,通常の実行手続を回避して,抵当権者に「抵当権の私的実行」を認めるものであり,その性質は一種の代物弁済の予約である[高木・担保物権(2005)183頁]。
質権の場合には,私的実行である流質契約は原則的に禁止されているが[民法349条],抵当権については禁止規定がないため,通説・判例〈大判明41・3・20民録14輯313頁〉は,これを有効と解してきた。
担保権の私的実行が問題とされるのは,担保目的物の価値が債権額を大きく上回る場合であり,この場合に私的実行を有効と解すると,債権者の暴利行為を認めることになり,妥当ではないからである。したがって,私的実行の場合にも,債権者に清算義務があると解することができれば,私的実行を禁止する必要はなくなる。
質権の場合に原則的に私的実行が禁止されているのは[民法349条],比較的値段の低い動産をも目的物とする質権に関して,常に清算手続を義務づけるとすれば,質権の実行が費用倒れになるおそれが大きいからであり,営業質の場合にも清算義務は課されていないことはすでに論じた。したがって,流質の禁止原則を脱法する結果を生じる動産譲渡担保の場合は,私的実行が認められている代りに譲渡担保権者に清算義務が課せられている。
抵当直流れを認めるとともに,抵当権者に清算義務を課すという解釈をとる場合,抵当直流れと仮登記担保との関係が問題となる。抵当直流れも,一種の代物弁済予約であると考えると,抵当直流特約が仮登記によって保全されている場合には,それは,仮登記担保と解することができる。
これに反して,抵当直流れの特約が仮登記によって保全されていない場合が,純粋の抵当直流れということになる。もっとも,この抵当直流れに関しても,清算義務や受戻権等につき,仮登記担保法の規定が類推適用されるべきである。
抵当権が目的物が滅失・損傷した場合に,これに代わって債務者が取得する損害賠償債権,保険金債権に対して物上代位を行使することができる。この点は,先取特権の場合と同じである。しかし,先取特権の場合には,追及効がないことを理由として認められていた売買代金と賃料債権に対する物上代位については,抵当権には追及効があるためにこれを認める必要性は小さい。現状では,むしろ,これを認める弊害の方が大きい。特に抵当権者による賃料債権に対する物上代位権の行使は,賃貸借の管理にかかわらないにもかかわらず,管理費が含まれている賃料を根こそぎ収奪するため,賃貸物権のスラム化が問題となっているからである。
平成元年最高裁判決〈最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件)〉は,バブル崩壊後不動産の価格が暴落したまま低迷しているという経済状況の下で,不動産競売よりは不動産の賃料等の収益によって優先弁済を受ける方が有利であるという抵当権者の便宜を図って,賃料債権に対する物上代位を認め,これが判例理論として定着を見ている。
しかし,管理に関与しない抵当権者が賃料から優先的に賃料債権をすべて回収することによって,賃貸物件の維持ができなくなるという弊害は甚大であり,賃貸借との調和を保つために,平成15年に不動産収益執行手続が創設された[民事執行法180条2号]。不動産収益執行においては,物上代位の場合とは異なり,不動産の管理と並行して賃料債権に対する執行がなされるため,賃借物権のスラム化が防止できる。このような現状を考慮するならば,抵当権に基づく賃料に対する物上代位権の行使の大義名分は,民法394条の観点からも,大きく後退していること,したがって,賃料債権のうち,少なくとも,管理にかかる費用は,物上代位の効力の範囲から排除する解釈論が要請されていることを明らかにする。
民法372条は,民法296条(留置権の不可分性),民法304条(先取特権による物上代位)および民法351条(質権における物上保証人の求償権)の規定を抵当権に準用すると規定している。そして,民法372条によって準用される民法304条を,抵当権に即して書き換えると,以下のようになる。すなわち,「抵当権は,その目的物の売却,賃貸,滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭,その他の物に対しても,行使することができる。ただし,抵当権者は,その払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない」となる。
しかし,抵当権は追及効を有するのであるから,先取特権の場合の物上代位とは異なり,目的物の売却,賃貸の場合には,その行使が制限されるべきである。
抵当目的物の売却の場合には,その目的物に対して抵当権の追及効が及ぶのであり,さらに重複して,その他の財産(売却代金債権)に対する効力を認めることになる物上代位は,「抵当権者は,抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ,〔かつ,優先権を有さない一般債権者の立場においてのみ〕,他の財産から弁済を受けることができる」としている民法394条の精神に反して許されない。
目的物の賃貸の場合には,目的物の賃料債権は,債務者の法定果実を構成しており,使用・収益権能を持たない抵当権者が,管理にも関与せずに,旨みのある賃料債権に対して優先的な効力を有する物上代位を行使することは認められない。ただし,賃料債権が,抵当権の目的物の滅失・損傷に類似するような以下の場合には,物上代位が認められるべきである。
第1に,目的物が家屋の場合において,賃貸借によって,目的物の価値が低減することが確実であり,賃料が目的物の実質的な「なし崩し」を実現するとみられる場合には,目的物の滅失に対する債権との類推により,管理費用を除いた賃料債権への物上代位が認められてよい。
第2に,目的物が土地の場合には,賃貸によって土地の価値が下落することはないので,原則としては,物上代位は認められるべきではない。しかし,抵当権設定後の土地の賃貸借の場合においては,抵当権設定時には更地だった土地に建物が建てられて賃貸借がなされた場合も含めて,賃貸借が目的物の価値を減少させるものであり,賃料債権が目的物の価値の低減の代償と同視できる場合には,例外的に,土地の賃料債権に対する物上代位が認められてよい。
目的物の滅失・損傷の場合の損害賠償債権,保険金債権に対する物上代位は,民法394条にも,民法371条にも抵触するものではなく,民法304条がそのまま準用されるべきである。
| 一般財産の 価値の増加 |
抵当目的物の 価値の減少 |
物上代位の正否 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価値の± | 増加した権利 | 価値の± | 理由 | 正否 | 理由 | ||
| 売却 | 目的物の売却 | + | 代金請求権 | ±なし | 追及効がある | × | 目的物の価値の減少がない |
| 賃貸 | 建物の賃貸 | + | 家賃請求権 | - | 建物のなし崩し | ○ | 目的物の価値の減少がある |
| 建物付土地の賃貸 | + | 地代請求権 | ±なし | 土地自体の価値は減少せず | × | 目的物の価値の減少がない | |
| 更地に建物を建築して賃貸 | + | 地代請求権 | - | 更地の価値が減少 | ○ | 目的物の価値の減少がある | |
| 滅失・損傷 | 目的物の滅失・損傷 | + | 損害賠償・保険金請求権 | - | 滅失・損傷による減少 | ○ | 目的物の価値の減少がある |
抵当目的物が売却された場合においても,登記を有する抵当権者は,売却された目的物に対して追及効を有する。すなわち,抵当目的物が売却されても,抵当権者は,それを債務者の責任財産とみなして,それに対して優先弁済権を主張できる。
動産先取特権の場合においては,目的物に対する追及効が存在しないため,目的物の売却の場合に,その売却代金債権に対して物上代位を認める必要性が存在する[民法304条]が,抵当権の場合には,上に述べたように追及効があるため,目的不動産の価値はすべて保存されており,それに代わるものとして物上代位を認める必要性は存在しない[清水(元)・担保物権(2008)39-40頁]。
もしも,抵当権者が抵当目的物に追及効を有しているにもかかわらず,売却代金債権に対しても物上代位を行使しうるとすると,結果的には,抵当権者は,抵当不動産の代価をもって弁済を受けうるのに,目的不動産の売却代金債権(抵当目的物以外の債務者の他の財産)からも弁済を受けることになってしまう。このことが,民法394条の趣旨に反すること,すなわち,抵当権者は,抵当不動産の代価から弁済を受けられない債権の部分についてしか,しかも,優先権を有さない一般債権者としての立場でしか,他の財産から弁済を受けることができないという原則に反することは明らかである。
例えば,債務者B所有の5,000万円の不動産に対して,Aが2,000万円の債権を担保するために抵当権を有するとしよう。この抵当権につき不動産をCがBから購入する契約を締結したとする。この場合,BC間の売買代金をどのように決定すべきかは,Aの物上代位が認められるか否かで多大な影響を受ける。
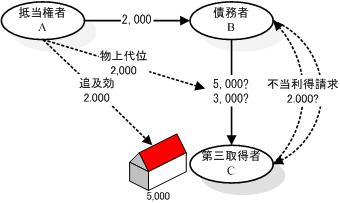 |
| *図96 追及効と物上代位の競合 |
Bから不動産を購入しようとするCが,Aの追及を考慮して,抵当不動産を抵当権のついたまま3,000万円で購入することにしたとしよう。この場合,Bは,Cから3,000万円を取得して,すべてが清算されたと考えるはずである。ところが,意に反して,AがBの代金債権に物上代位を行使してきたとする。
もしも,Aの物上代位が認められるとすると,Bは,3,000万円の代金債権のうち1,000万円しか取得できず,その見返りとして,Cは代金3,000万円で負担のない5,000万円の不動産を取得することになってしまう。もちろん,この場合は,Bは,Cに対して,2,000万円の不当利得の返還請求を行うことになるであろう。しかし,もともとAは,民法394条の精神に従って,追及効による抵当権の行使ができる場合には,抵当目的物以外の財産に対する権利行使としての物上代位の行使が否定されるべきなのである。
これとは反対に,Aからの物上代位を予想して,BC間で,抵当不動産の代金を5,000万円に定めたとしよう。この場合に,Aが意に反して追及効を行使したとすると,Cは,代金5,000万円のほかに,土地の競売を防止するために,さらに,2,000万円をAに支払わなければならなくなってしまう。この場合には,Cが,Bに対して,2,000万円の担保責任の追及[民法567条]または不当利得の返還請求を行うことになろう。
このように考えると,抵当権の場合には,先取特権の場合と異なり,その性質上,目的不動産の売却の場合には,物上代位は生じないと解すべきである。
もっとも,山林の立木(目的物の付加物)が不当に伐採されて売却された場合のように,目的物自体の問題ではなく,目的物の付加物が分離されて売却された場合には,抵当権の追及効は,分離物に及ばないため,分離物の売却代金債権に対して物上代位を認めることは必要であり,例外的に物上代位が認められるべきである(第3節E.(b)(分離物に対する追及効の限界時点)参照)。
物上代位を規定している民法304条は,先取特権の総則として,先取特権一般について,目的物の売却,賃貸,滅失・損傷の場合に物上代位が認められるとしている。しかし,そもそも,先取特権の場合ですら,物上代位について,一般先取特権,動産先取特権,不動産先取特権のそれぞれの特性を無視して,一律に考えることはできない。
確かに,動産先取特権の場合には追及効がないため,売買代金債権,賃料債権,損害賠償・保険金債権のすべてについて物上代位が認められるのは当然である。しかし,先取特権の場合に限定しても,一般先取特権の場合には,売却代金債権,賃料債権,損害賠償債権を含めて,債務者の全財産について先取特権の効力が及ぶため,物上代位は全く問題にならない。また,不動産先取特権の場合には追及効があり,土地の賃貸の場合は価値の減少をもたらさないため,売却,賃貸の場合は,原則として物上代位は認められず,目的物の滅失・損傷の場合にのみ物上代位が認められるべきである。もっとも,建物の賃貸の場合は,賃貸が目的物の価値の減少をもたらし,賃料が目的物の価値の「なし崩し」とみなしうる場合に限って,動産先取特権の場合に準じて,例外的に物上代位が認められるべきことはすでに述べた通りである。
抵当権の場合の物上代位は,先取特権における民法304条が準用されているが,動産先取特権を念頭において規定された民法304条をそのまま抵当権に準用すべきではない。抵当権に準用されるべき物上代位は,動産先取特権における物上代位ではなく,不動産先取特権における物上代位であると考えなければならない。
抵当権の目的物の賃貸の場合に,原則として物上代位を認めないものの,建物賃貸の場合において,賃貸が目的物の「なし崩し」とみなすことができる場合に限って賃料債権に対する物上代位を認めると,そのことは,民法371条が不動産収益執行の場合を念頭において賃料(法定果実)に対して抵当権の効力が及ぶとしていることに反するのではないかという点が問題となる。
しかし,建物から生じる法定果実について物上代位の効力が及ぶのは,建物の価値を維持したままさらに独立した物を創造するという果実としての性格を有していない場合,すなわち,建物の使用によって建物の価値が減少する場合に限られると考えるべきであり,その場合には,法定果実は,むしろ建物の代償としての性格を有していると考えるのが適切である。したがって,建物の賃貸の場合には,賃料債権は,建物の損傷の代償に類するものとして,それに対して物上代位を認めることは,民法371条に違反しないと解すべきである。
また,土地の賃貸の場合であっても,抵当権設定後になされた土地の賃貸借の場合,抵当権設定当時は,更地であったのに,その後,抵当権設定者がその土地に建物を建てて,他人に土地を貸したという場合も含めて,もしもそれが土地の価値を減少させるものである場合には,賃料はその代償物という性格を有するため,その場合には,抵当権者による賃料に対する物上代位が認められるべきである。
従来の判例は,賃料に対する物上代位を否定していた〈大判大6・1・27民録23輯97頁〉が,平成元年以来,最高裁判決は,建物賃貸借に関して,賃料が供託された場合に,還付請求権に物上代位を認めることを通じて,賃料債権に対する物上代位を認める方向を打ち出している〈最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件)〉。
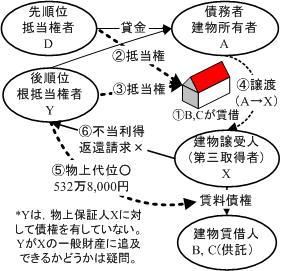 |
抵当不動産が賃貸された場合においては,抵当権者は,民法372条,304条の規定の趣旨に従い,賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる。 目的不動産に対して抵当権が実行されている場合でも,実行の結果抵当権が消滅するまでは,賃料債権ないしこれに代わる供託金還付請求権に対しても抵当権を行使することができる。 |
| *図97 最二判平1・10・27民集43巻9号1070頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第86事件 |
最高裁が判例を変更したのには,バブル経済の崩壊により地価を含めた不動産価格が低迷し,抵当権の実行によっても債権の回収が進まなくなったため,不良債権の解消のため,抵当権者が債権回収の方法として,抵当目的物の賃料に対する物上代位を多用するようになったという時代背景がある。
最高裁は,その後の一連の平成10年判決〈最二判平10・1・30民集52巻1号1頁〉,〈最一判平10・3・26民集52巻2号483頁〉)により,賃料債権に対する物上代位を賃料債権が譲渡された場合にも認めたり,物上代位の対抗要件を,民法304条で定められた物上代位に基づく差押えではなく,抵当権の登記であるとしたりという判断を下すに至っている。
上記の一連の最高裁平成10年判決は,第三債務者保護説を採用したものとしても有名である。後に,物上代位の差押えの意義の箇所で詳しく検討するように,平成10年判決は,第三債務者の保護のため,物上代位権の行使には,担保権者自身による差押えが必要であり,かつ,その差押命令の送達が第三債務者に到達することが,物上代位権に基づく優先弁済権の対抗要件であることを明らかにしており,この点は,高く評価できる。しかし,結果的には,賃料債権が譲渡されたとの通知を受けたり,一般債権者からの差押えを受けたりした場合にも,賃借人に対して入居した物件に抵当権があるかを登記簿で確認した上で,それ以前に抵当権の登記がある場合には,後になされる抵当権者の物上代位を優先して弁済せよという酷な要請をすることになる点で,第三債務者保護説の立場を一貫させていないように思われる。また,抵当目的物に対する追及効を有している抵当権者に無制限に物上代位を認めることについては,学説からは,強い批判がなされている。その理由は,以下のとおりである。
2003年の担保・執行法改正によって,担保不動産収益執行の制度[民事執行法180条2号]が導入されたときに,代替的措置としての賃料に対する物上代位を廃止するかどうかが議論された。上記のような理由で,賃料に物上代位を認めることには,批判も強かったが,結果的に,物上代位も並存させることになった。小規模不動産等については,特に,物上代位の簡便さが収益執行によっては代替困難である点などが考慮されたからである。しかし,以下のように,現実には,物上代位のターゲットになっているのは,小規模のマンションではなく,大規模なオフィスビルだという(東京弁護士会弁護士研修委員会編『不動産競売にからむ諸問題』商事法務研究会(1999)148頁)。
ワンルームマンションに限らず,マンション・アパート等では,…差押えをかけても結局空振りに終わるこということになります。正直なところ,金融機関側から見ますと一番ターゲットにし易いのは,やはり優秀な企業の入ったオフィスビルということになろうかと思います。
抵当不動産が転貸された場合に,抵当権者は,賃料債権ではなく,転貸賃料に対しても物上代位権を行使しうるかどうかについて,最高裁〈最二判平12・4・14民集54巻4号1552頁〉は,以下のように,原則として否定する方向に向かっている。
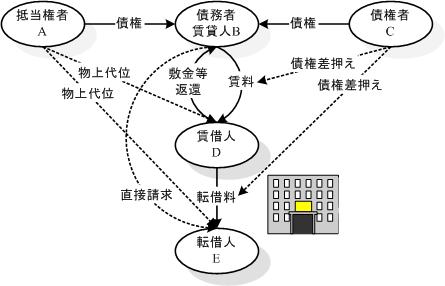 |
| *図98 抵当権に基づく賃料債権に対する物上代位 |
最二判平12・4・14民集54巻4号1552頁(債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件)破棄差戻
抵当権者は,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合を除き,右賃借人が取得する転貸賃料債権について物上代位権を行使することができない。
民法372条によって抵当権に準用される同法304条1項に規定する「債務者」には,原則として,抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれないものと解すべきである。けだし,所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものであるのに対し,抵当不動産の賃借人は,このような責任を負担するものではなく,自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にはないからである。同項の文言に照らしても,これを「債務者」に含めることはできない。また,転貸賃料債権を物上代位の目的とすることができるとすると,正常な取引により成立した抵当不動産の転貸借関係における賃借人(転貸人)の利益を不当に害することにもなる。もっとも,所有者の取得すべき賃料を減少させ,又は抵当権の行使を妨げるために,法人格を濫用し,又は賃貸借を仮装した上で,転貸借関係を作出したものであるなど,抵当不動産の賃借人を所有者と同視することを相当とする場合には,その賃借人が取得すべき転貸賃料債権に対して抵当権に基づく物上代位権を行使することを許すべきものである。
最高裁の結論はもっともであるが,その理由は説得力を持たない。なぜなら,民法613条は,転借人に対して,転借人は賃貸人に対して「直接に義務を負う」と規定している。したがって,賃料債権に対して物上代位を認める最高裁の立場に立てば,抵当権者が転貸賃料に対して物上代位を認めることについて,転借人は「債務者」ではないというのは,理由として成り立たないからである。
賃料債権に対して物上代位権による差押えがなされたときに,賃借人は,賃貸人(抵当権の設定者・債務者)に対して有する債権を自働債権として賃料債権との相殺をすることができるか。民法511条の反対解釈〈最大判昭45・6・24民集24巻6号587頁〉によれば,賃借人は,差押え前に取得した保証金返還債権や敷金返還債権を自働債権として,賃料債権を相殺によって消滅させることができるはずである。
ところが,最高裁は,保証金返還債権の場合において,賃料債権の相殺による消滅の効力を否定した〈最三判平13・3・13民集55巻2号363頁〉。
最三判平13・3・13民集55巻2号363頁(取立債権請求事件)上告棄却
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできないと解するのが相当である。けだし,物上代位権の行使としての差押えのされる前においては,賃借人のする相殺は何ら制限されるものではないが,上記の差押えがされた後においては,抵当権の効力が物上代位の目的となった賃料債権にも及ぶところ,物上代位により抵当権の効力が賃料債権に及ぶことは抵当権設定登記により公示されているとみることができるから,抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と物上代位の目的となった賃料債権とを相殺することに対する賃借人の期待を物上代位権の行使により賃料債権に及んでいる抵当権の効力に優先させる理由はないというべきであるからである。
そして,上記に説示したところによれば,抵当不動産の賃借人が賃貸人に対して有する債権と賃料債権とを対当額で相殺する旨を上記両名があらかじめ合意していた場合においても,賃借人が上記の賃貸人に対する債権を抵当権設定登記の後に取得したものであるときは,物上代位権の行使としての差押えがされた後に発生する賃料債権については,物上代位をした抵当権者に対して相殺合意の効力を対抗することができないと解するのが相当である。
一般に保証金といわれるものには,第1に,敷金としての性質を有するもの,第2に,返還義務のない権利金としての性質を持つもの,金銭消費貸借としての性質を有する建設協力金に該当するもの等があるとされている[田髙・物権法(2008)186頁]。本件の場合,保証金は,賃貸借契約の終了時に返還される敷金と同視しうるものであり,賃料債権と密接な関連を有している。それに対して,抵当権を有する債権は,単なる貸金債権であり,賃料との間に密接な関連を有していない。このような場合には,保証金返還債権の発生の時期,抵当権の設定登記の時期,物上代位の差押えの送達の時期等の時間的順序に注目して優先順序を決定することは,不動産先取特権と抵当権の優先順位の箇所(*第14章第3節C(不動産先取特権とその優先順位))でも述べたように,無意味である。異なる優先弁済権が競合した場合の優先順位の決定基準は,何よりも,どちらの債権が目的物または目的債権の維持・増加に貢献したかという考慮であり,その際に重要な役割を果たしているのが,担保目的と,それぞれの債権との間の牽連性の強弱である。そして,賃料と密接な関連を有する保証金返還債権に基づく相殺と,貸金債権に基づく抵当権による物上代位とを比較すれば,目的債権である賃料債権と最も密接な関連を有するのは,保証金返還債権であり,それに基づく相殺を優先すべきである。
上記の最高裁平成13年判決〈最三判平13・3・13民集55巻2号363頁〉は,このような競合する債権間の牽連性の問題について,全く考慮しておらず,学説によって,厳しく批判されることになった([深川・相殺の担保的機能(2008)427-439頁],[田髙・物権法(2008)232-232頁])。
賃借人に対し自身が入居した物件に抵当権があるかを登記簿で確認せよとするのは酷であり,だからこそ差押えが賃借人保護のために必要なのだ,という文脈で理解できるものであった。13年判決は,抵当権登記があるから,相殺による賃借人の敷金返還への期待が封じられることも正当化できると述べるが如くであるが,これは妥当とはいえまい[田髙・物権法(2008)232-232頁]。
そして,敷金の場合には,上記の最高裁の13年判決と抵触しないように,敷金の充当という法理を使って,実質的には,敷金返還債権と賃料債権の相殺を,抵当権に基づく物上代位よりも優先する結果を導いている〈最一判平14・3・28民集56巻3号689頁〉。
最一判平14・3・28民集56巻3号689頁(取立債権請求事件)上告棄却
敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
賃貸借契約における敷金契約は,授受された敷金をもって,賃料債権,賃貸借終了後の目的物の明渡しまでに生ずる賃料相当の損害金債権,その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することとなるべき一切の債権を担保することを目的とする賃貸借契約に付随する契約であり,敷金を交付した者の有する敷金返還請求権は,目的物の返還時において,上記の被担保債権を控除し,なお残額があることを条件として,残額につき発生することになる(最高裁昭和46年(オ)第357号同48年2月2日第二小法廷判決・民集27巻1号80頁参照)。これを賃料債権等の面からみれば,目的物の返還時に残存する賃料債権等は敷金が存在する限度において敷金の充当により当然に消滅することになる。このような敷金の充当による未払賃料等の消滅は,敷金契約から発生する効果であって,相殺のように当事者の意思表示を必要とするものではないから,民法511条によって上記当然消滅の効果が妨げられないことは明らかである。
また,抵当権者は,物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前は,原則として抵当不動産の用益関係に介入できないのであるから,抵当不動産の所有者等は,賃貸借契約に付随する契約として敷金契約を締結するか否かを自由に決定することができる。したがって,敷金契約が締結された場合は,賃料債権は敷金の充当を予定した債権になり,このことを抵当権者に主張することができるというべきである。
以上によれば,敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅するというべきであり,これと同旨の見解に基づき,上告人の請求を棄却した原審の判断は,正当として是認することができ,原判決に所論の違法はない。
この判決は,優先弁済権が競合する場合には,それぞれの債権と目的債権との牽連性との強弱を考慮して判断すべきであり,抵当権に基づく物上代位は,賃借人の敷金返還債権に基づく相殺に劣後すると考える本書の立場と結論において同じであり,その意味で,高く評価されるべき判決であると考えている。
なお,債権譲渡と相殺との関係に関しては,以下の最高裁判決があり,弁済期のいかんを問わず相殺ができるとしている〈最一判昭50・12・8民集29巻11号1864頁〉。
抵当権者は,第三者が目的物を滅失・損傷した場合に,所有者が取得する不法行為に基づく損害賠償債権(請求権)に対して物上代位を行うことができる〈大判大6・1・22民録23輯14頁〉。また,抵当権者は,建物が焼失したことにより,所有者が取得する火災保険金債権(請求権)に対しても物上代位を行うことができる〈大連判大12・4・7民集2巻209頁〉。
これに対しては,保険金請求権は,保険契約に基づき,保険料支払の対価として生じるものであり,目的物の代償物または変形物ではないとする批判が,主として保険法学者からなされている(民法学者の中にも,保険金は可能な限り物件の修復・補修に用いるべきであるという観点から,保険金請求権に対する物上代位を否定すべきだとする学説[清水(元)・担保物権(2008)42-43頁]が存在する)。
しかし,物上代位の制度は,担保目的物の価値減少を引き起こしたのと同一事実によって債務者または物上保証人の一般財産に債権が増加した場合に,それを担保目的物と同等の物とみなし,目的物の価値が減少した範囲で,担保権者にその債権に対して優先弁済権を付与する制度である。保険金請求権は,目的物の焼失という担保目的物を減少させるのと同一の事実によって発生するのであるから,物上代位制度の趣旨に照らしても,保険金請求権に対して物上代位の行使を認めることは,何らの妨げとならないと解すべきであろう。
確かに,エコロジーの観点からは,保険金は可能な限り物件の修復・補修に用いるべきであるということが強調されるかもしれない[清水(元)・担保物権(2008)42-43頁]。その場合でも,保険金に対する物上代位を全面的に否定する必要はないと思われる。なぜなら,保険金を建物の修復・補修に用いるためにも,以下のように,保険金に対する修復・補修業者による不動産保存の先取特権に基づく物上代位の利用が考えられるからである。
もしも,修復・補修によって抵当建物の担保価値が減少しないのであれば,抵当権者の物上代位は,その根拠を失うことになる。したがって,抵当目的不動産が損傷したが,その修補・補修が可能である場合には,抵当権設定者は,建物の補修を業者に依頼し,その事業者が,不動産保存の先取特権に基づく保険金上の物上代位を行使するという解決方法をとるのが妥当であろう。その場合には,抵当権に基づく物上代位は,担保価値が保全されたことによって意味を失うため,抵当権設定者は,執行異議もしくは執行抗告を申立て[民事執行法182条],または,それに伴う仮処分を通じて執行停止[民事執行法183条]を求めることができると思われる。また,たとえ,抵当権に基づく物上代位が可能であるとしても,民法339条により,それは,不動産保存の先取特権に基づく物上代位には劣後することになるので,保険金を建物の補修に役立てるという目的を達成することができるであろう。
債権者が同一の債権の担保として,数個の不動産の上に抵当権を有するものである共同抵当について,それぞれの不動産について利害関係を有する債権者との間でどのような配当が行われるのかを具体例を通じて理解する。さらには,物上保証人と後順位抵当権者との間で,どのような配当が行われるのかを具体例を通じて理解する。
共同抵当とは,同一の債権の担保として数個の不動産の上に設定された抵当権のことである。わが国では,土地と建物とが別個・独立の不動産とされているため,数筆の土地とか,数個の建物を抵当に取る場合ばかりでなく,1箇所にある土地と建物とを一括して抵当にとる場合でも,それは単独抵当ではなく,共同抵当となる。したがって,共同抵当は,広く用いられている。
ところが,債務者の不動産が共同抵当の目的物とされた場合(同主共同抵当)でさえ,先順位抵当権者と後順位抵当権者との利害が複雑に絡むため,その調整は単純ではない。債務者と物上保証人の別々の不動産が共同抵当の目的物とされた場合(異主共同抵当)には,物上保証人の求償権を担保するための代位弁済の制度が問題となるため,さらに複雑な問題が生じる。そこで,以下では,まず,同主共同抵当について設例によって解説を行った後,異主共同抵当について,設例を通じて解説を行うことにする。
債務者が所有する価額3,000万円の甲不動産,2,000万円の乙不動産,1,000万円の丙不動産があり,第1に,甲・乙・丙上にAの債権額3,000万円の共同抵当権が設定され,第2に,甲・乙上にBの債権額1,500万円の共同抵当権が設定され,第3に,甲・乙上にCの債権額1,000万円の共同抵当権が設定され,第4に,丙上にDの債権額500万円の単独抵当権が設定されたとする。
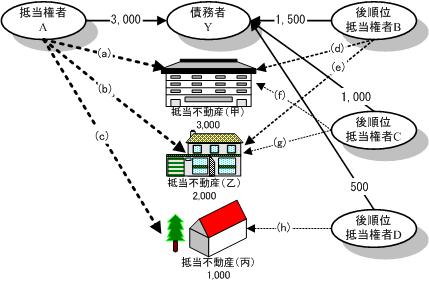 |
| *図99 共同抵当の設例(同主共同抵当) |
甲・乙・丙の不動産が同時に競売された場合,A・B・Cは,それぞれの不動産から,いくらの配当を得ることができるだろうか。下の表の形式の配当表によって,各債権者が債務者所有の不動産甲乙丙の競売代金からそれぞれいくらの配当を受けうるか,(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h)の配当金額を計算しなさい。
問題の意味を表であらわすと以下のようになる。(a)~(h)までの空欄を埋めることが求められている。
| 債権者 | 不動産上の順位 | 不動産評価額と債権者への配当額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 甲 (3,000) |
乙 (2,000) |
丙 (1,000) |
||
| A(3,000) | 1(甲・乙・丙) | (a) | (b) | (c) |
| B(1,500) | 2(甲・乙) | (d) | (e) | - |
| C(1,000) | 3(甲・乙) | (f) | (g) | - |
| D( 500) | 2(丙) | - | - | (h) |
最初に述べたように,共同抵当とは,債権者が,同一の債権の担保として,数個の不動産の上に抵当権を有するものをいう[民法392条1項]。債権を担保するために,土地と建物を一括して抵当権を設定することは,ごく普通に行われている。わが国においては,土地と建物は別個の不動産とされているため,そのような抵当権はすべて共同抵当となる。また,外形上は一区画の敷地であっても,登記簿上は数筆の土地ということがある。その場合,その敷地全部につき抵当権を設定すると共同抵当となる。このような事情を考慮するならば,わが国においては,共同抵当制度を理解することが,単独抵当を理解するのと同等に重要な意味をもつことが理解できよう。
(i) 担保価値の増大
いくつかの不動産を集めて共同抵当にすると,個々の不動産では債権の担保として不十分な場合に,担保価値を増大させることができる。
(ii) 危険の分散,担保価値の維持
共同抵当は,共同担保物件の一部の価格が値下りしても,他の共同担保物件の価格が値上りしていると,それで従来の担保価値を維持できる。
土地とその上にある同一所有の建物について,土地だけを担保の目的にすると,抵当権の実行の結果,建物のために法定地上権[民法388条]が成立する。そのため,土地だけを抵当に取ると,土地の評価が下がってしまう。そこで,土地と地上建物を共同担保にとり,同時に競売できるようにしておくと,予想通りの担保価値を維持できる。このため,共同抵当は,超過担保となることが多い。この場合の弊害については,後に述べるように,民事執行法が一定の制約を設けている[民事執行法188条の準用による73条]。
(i) 競売に関する共同抵当権者の自由裁量の確保
債権者Aは,共同抵当の目的物件,例えば,甲・乙・丙の各不動産を同時に競売してもよいし,まず甲・不動産を競売し,もし代金が不足するなら,次に乙・丙不動産を競売してもよいし,あるいは,甲・丙の評価額が減少していれば,乙不動産だけを競売することもできる。
(ii) 共同抵当の実行と後順位抵当権者の保護
(A) 同時配当の場合 同時配当の場合には,抵当権の債権額を不動産の価額に応じて割り付け,債権者はその割合に従って各不動産から優先弁済を受けることができるとして,共同抵当権者と後順位抵当権者の利害の調整を図っている[民法392条1項]。
(B) 異時配当の場合 これに対して異時配当の場合には,後順位抵当権者の利益が害されるおそれがあるため,同時配当の場合であれば配当を受け得たはずの後順位抵当権者は,共同抵当権者に代位できるとして,後順位抵当権者を保護している[民法392条2項]。
共同抵当の目的物の評価額が債権額を上回る場合には,全部の不動産を同時に競売することは不必要である。そこで,民事執行法73条は,「数個の不動産を売却した場合において,あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは,執行裁判所は,他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない」(1項),「前項の場合において,その買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは,執行裁判所は,売却の許可をすべき不動産について,あらかじめ,債務者の意見を聴かなければならない」(2項)と規定し,超過競売が予想される場合には,抵当権設定者を保護するため,不要な競売を制限している。
共同抵当は,登記によって公示される。共同抵当の登記に当っては,共同抵当であることを示し,共同担保目録を添付しなければならない[不動産登記法83条1項4号・2項,不動産登記規則166条]。
登記簿謄本を見ると,抵当権の登記事項の末尾に「共同担保目録(あ)第○○号」という記号番号が記載されているだけで,共同担保の具体的な内容はわからない。そこで,「共同担保目録」の謄本を調べると,どのような不動産が共同担保とされているかが,初めて具体的にわかる仕組になっている。
この共同担保目録の登記によって利益を受けるのは後順位抵当権者であるが,登記をするのは後順位抵当権者ではないので,この登記は,後順位抵当権者等の,共同抵当関係の成立によって保護される者に対する対抗要件となるものではない。したがって,この登記がなくても,後順位抵当権者は,実体関係に基づき,共同抵当である旨を主張して民法392条の利益を受けることができると解されている。
最初に挙げた設例を通して,共同抵当の実行における,競売代金の配当額の算出方法について説明する。
異時配当の場合も,同時配当の場合と同様の結果が生じるように,後順位権者に代位権を与えるという方法がとられているので[民法392条2項],まず,同時配当の場合のルールを理解することが大切である。
(i) 同時配当における配当計算
共同抵当権者が目的不動産すべてに対して抵当権を実行し,同時に代価を配当すべき場合には,その各不動産の価額に応じてその債権の負担を分配する[民法392条1項]。
設例において,第1順位の抵当権者Aが甲・乙・丙不動産を同時に競売した場合には,Aは,債権額3,000万円を各不動産の評価額に応じて比例配分した額につき,それぞれの不動産から配分を受ける。すなわち,以下の計算式に従い,Aは,甲不動産から1,500万円,乙不動産から1,000万円,丙不動産から500万円の弁済を受ける。
(a):3,000×3,000/(3,000+2,000+1,000)=1,500(万円)
(b):3,000×2,000/(3,000+2,000+1,000)=1,000(万円)
(c):3,000×1,000/(3,000+2,000+1,000)=500(万円)
次に,第2順位の抵当権者の配当を行う。第1順位の債権者Aへの配当によって,各不動産の価額は,以下のように変化する。
甲不動産:3,000-1,500=1,500(万円)
乙不動産:2,000-1,000=1,000(万円)
丙不動産:1,000- 500= 500(万円)
したがって,甲・乙不動産に関して第2順位の抵当権を有するBは,債権額1,500万円につき,甲不動産の残額1,500万円,乙不動産の残額1,000万円から配分を受ける。すなわち,以下の計算式に従い,甲不動産から900万円,乙不動産から600万円の弁済を受ける。
(d):1,500×3,000/(3,000+2,000)=900(万円)
(e):1,500×2,000/(3,000+2,000)=600(万円)
なお,丙不動産につき第2順位の単独抵当権を有するDは,丙不動産の残額500万円から,全額弁済を受ける。
(h):500(万円)
最後に,第3順位の抵当権者の配当を行う。第2順位の抵当権者Bへの配当によって,甲・乙不動産の価額は,以下のように変化する。
甲不動産:1,500-900=600万円
乙不動産:1,000-600=400万円
したがって,甲・乙不動産に関して,第3順位の抵当権を有するCは,債権額1,000万円につき,甲不動産の残額600万円,乙不動産の残額400万円から配分を受ける。すなわち,以下の計算式に従い,甲不動産から600万円,乙不動産から400万円の弁済を受ける。
(f):1,000×600/(600+400)=600(万円)
(g):1,000×400/(600+400)=400(万円)
以上の計算を配当表上で行うと,下の表のようになる。
| 債権者 | 不動産上の順位 | 不動産評価額と債権者への配当額 | 配当額, 残額の 区別 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 (3,000) |
乙 (2,000) |
丙 (1,000) |
|||
| A(3,000) | 1(甲・乙・丙) | (a)1,500 | (b)1,000 | (c)500 | 配当額 |
| 1,500 | 1,000 | 500 | 残額 | ||
| B(1,500) | 2(甲・乙) | (d)900 | (e)600 | - | 配当額 |
| 600 | 400 | 500 | 残額 | ||
| C(1,000) | 3(甲・乙) | (f)600 | (g)400 | - | 配当額 |
| 0 | 0 | 500 | 残額 | ||
| D( 500) | 2(丙) | - | - | (h)500 | 配当額 |
| 0 | 0 | 0 | 残額 | ||
なお,債権者Aの共同抵当の目的である甲・乙・丙不動産のうち,例えば,乙不動産について,B’がAと同順位の抵当権を有する場合には,その計算方法が問題となる。最高裁は,まず乙不動産についてAとB’の債権額の割合で按分した額を算定し,その額および他の甲・丙不動産の価額に応じて各不動産の負担を分けるべきものとしている〈最三判平14・10・22判時1804号34頁〉。
最三判平14・10・22判時1804号34頁
共同抵当の目的となった数個の不動産の代価を同時に配当すべき場合に,1個の不動産上にその共同抵当に係る抵当権と同順位の他の抵当権が存するときは,まず,当該1個の不動産の不動産価額を同順位の各抵当権の被担保債権額の割合に従って案分し,各抵当権により優先弁済請求権を主張することのできる不動産の価額(各抵当権者が把握した担保価値)を算定し,次に,民法392条1項に従い,共同抵当権者への案分額及びその余の不動産の価額に準じて共同抵当の被担保債権の負担を分けるべきものである。
(ii) 同時配当における配当結果
配当表に従った計算結果をまとめると,以下のような配当表が完成する。これが,設例に関する解答である。
| 債権者 | 不動産上の順位 | 不動産評価額と債権者への配当額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 甲 (3,000) |
乙 (2,000) |
丙 (1,000) |
||
| A(3,000) | 1(甲・乙・丙) | (a)1,500 | (b)1,000 | (c) 500 |
| B(1,500) | 2(甲・乙) | (d) 900 | (e) 600 | - |
| C(1,000) | 3(甲・乙) | (f) 600 | (g) 400 | - |
| D( 500) | 2(丙) | - | - | (h) 500 |
(i) 異時配当手続
共同抵当において,ある不動産の代価のみを配当すべきときは,抵当権者は,その代価につき全部の弁済を受けることができる[民法392条2項1文]。その代り,後順位抵当権者を保護するため,次順位の抵当権者には代位権が発生する。すなわち,民法392条2項の規定に従い,先順位抵当権者が他の不動産につき弁済を受けるべき金額に達するまで,これに代位して抵当権を行うことができる[民法392条2項2文]。
設例において,Aが甲不動産の抵当権のみを実行する場合を考えてみよう。Aは,甲不動産から債権額3,000万円全額の弁済を受けることができる。そうすると,次順位の抵当権者Bは,甲不動産から弁済を受けることができなくなる。そこでBは,本来の配当額600万円のほか,民法392条2項によって,乙不動産につきAに割り付けられるべき1,000万円の中から,Bの債権額1,500万円に達するまで(900万円)の範囲で,Aに代位しうる。
Cは,乙不動産について,本来の配当額400万円のほか,BがAに代位した残りの100万円の弁済を受けることができるが,乙不動産だけでは,債権額1,00万円全額の弁済を受けることができない。そこでCは,Aが丙不動産につき,Aに割り付けられていた500万円についてAに代位し,第1順位で丙不動産から弁済を受けることができる。
設例について,Aが甲不動産のみから配当を受けた場合の計算方法を配当表上で示すと,以下の通りである。
| 債権者 | 不動産上の順位 | 不動産評価額と債権者への配当額 | 配当額, 残額の 区別 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同時・ 異時 |
甲 (3,000) |
乙 (2,000) |
丙 (1,000) |
|||
| A(3,000) | 1(甲,乙,丙) | (同時) | (1,500) | (1,000) | (500) | (基準額) |
| 異時 | (a)3,000 | (b)0 | (c)0 | 配当額 | ||
| 0 | 2,000 | 1,000 | 残額 | |||
| B(1,500) | 2(甲,乙) | (同時) | (900) | (600) | (-) | (基準額) |
| 異時 | (d)0 | (e)1,500 | - | 配当額 | ||
| 0 | 500 | 1,000 | 残額 | |||
| C(1,000) | 3(甲,乙) | (同時) | (600) | (400) | (-) | (基準額) |
| 異時 | (f)0 | (g)500 | (g')500 | 配当額 | ||
| 0 | 0 | 500 | 残額 | |||
| D( 500) | 2(丙) | (同時) | (-) | (-) | (500) | (基準額) |
| 異時 | - | - | (h)500 | 配当額 | ||
| 0 | 0 | 0 | 残額 | |||
(ii) 異時配当における配当結果
異時配当の結果を配当表によって示すと,以下の通りである。異時配当の場合も,民法392条2項の代位により,各抵当権者は,同次配当の場合と同様の満足を受けうる。ただし,配当を受けるべき不動産には変更が生じうる。特に,Cは,本来抵当権の目的としていない丙不動産から弁済を受けていることに注目すべきである。
| 債権者 | 不動産上の順位 | 不動産評価額と債権者への配当額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 甲 (3,000) |
乙 (2,000) |
丙 (1,000) |
||
| A(3,000) | 1(甲・乙・丙) | (a)3,000 | (b)0 | (c)0 |
| B(1,500) | 2(甲・乙) | (d)0 | (e)1,500 | - |
| C(1,000) | 3(甲・乙) | (f)0 | (g)500 | (g')500 |
| D( 500) | 2(丙) | - | - | (h)500 |
民法392条2項の代位は,先順位抵当権者にとって不要となった先順位抵当権の他の不動産に対する抵当権が,保護されるべき後順位抵当権者へと法律上当然に移転するものと解されている。
法定移転の場合,一般的には,対抗要件としての登記は不要であるのが原則であるが,民法392条2項の代位は,代位すべき抵当権の登記にその「代位」を付記することもできる([民法393条],[不動産登記法91条])。
共同抵当の配当に関して先に述べたことは,共同抵当の目的物である各不動産が同一人に属すること(同主共同抵当)を前提としていた。しかし,共同抵当の目的物である各不動産が別々の者に属する場合(異主共同抵当)には,別の考慮が必要となる。なぜなら,この場合には,債務者の他に物上保証人が登場し,後順位抵当権者と物上保証人との利益調整を行うことが要請されるからである。
判例・通説は,物上保証人と後順位抵当権者との利益が対立する場合には,同主共同抵当に関し後順位抵当権者に認められた民法392条1項の按分比例および同条2項の後順位抵当権者の代位よりも,物上保証人の弁済による代位[民法499条,500条]を優先させるべきであるとする。その結果,異主共同抵当の場合には,民法392条は適用されないとしている(〈大判昭11・12・9民集15巻24号2172頁〉,〈最一判昭44・7・3民集23巻8号1297頁〉,[我妻・担保物権(1968)457頁],[柚木=高木・担保物権(1973)404頁],[鈴木・物権法(1994)234頁])。
最一判昭44・7・3民集23巻8号1297頁
第二順位の抵当権者と物上保証人との関係についてみるに,…乙不動産が第三者〔物上保証人〕の所有であった場合に,たとえば,共同抵当権者が乙不動産のみについて抵当権を実行し,債権の満足を得たときは,右物上保証人は,民法500条により,右共同抵当権者が甲不動産に有した抵当権の全額について代位するものと解するのが相当である。けだし,この場合,物上保証人としては,他の共同抵当物件である甲不動産から自己の求償権の満足を得ることを期待していたものというべく,その後に甲不動産に第二順位の抵当権が設定されたことにより右期待を失わしめるべきではないからである(大審院昭和2(1927)年(オ)第933号,同4年1月30日判決参照)。これを要するに,第二順位の抵当権者のする代位と物上保証人のする代位とが衝突する場合には,後者が保護されるのであって,甲不動産について競売がされたときは,もともと第二順位の抵当権者は,乙不動産について代位することができないものであり,共同抵当権者が乙不動産の抵当権を放棄しても,なんら不利益を被る地位にはないのである。したがって,かような場合には,共同抵当権者は,乙不動産の抵当権を放棄した後に甲不動産の抵当権を実行したときであっても,その代価から自己の債権の全額について満足を受けることができるというべきであり,このことは,保証人などのように弁済により当然甲不動産の抵当権に代位できる者が右抵当権を実行した場合でも,同様である。
物上保証人が登場しない同主共同抵当の場合と,物上保証人が登場する異主共同抵当の場合で,後順位抵当権者の地位に変化が生じるのは当然のことであり,その結果として配当額に差が生じても不思議ではない。
しかし,その結果が,民法392条を適用した場合にも説明可能である場合,または,たとえ結果が異なるとしても,妥当な結果が導かれるのであれば,あえて異主共同抵当の場合に,民法392条の適用を否定する必要はない。[佐久間・共同抵当(1992)75頁]は,少数説である我妻旧説(担保物権法・旧版296頁),鈴木旧説(抵当制度の研究235頁)を再評価すべきであると述べるが,まさに正当である。
判例も,同一の物上保証人所有の不動産が共同抵当権の目的物となった場合には,民法392条2項の適用を認めるに至っているのであるから〈最二判平4・11・6民集46巻8号2625頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第94事件)〉,共同抵当権の目的物の所有権が債務者と物上保証人とにまたがっている場合でも,民法392条2項の適用を認めることに支障はないと思われる。
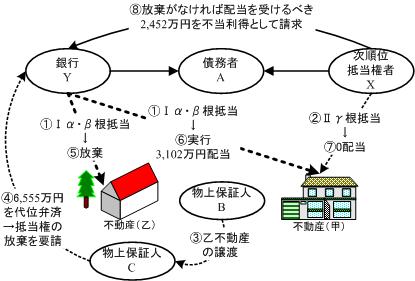 |
共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人(B→C)の所有に属する場合において,甲不動産の代価のみを配当するときは,甲不動産の後順位抵当権者(X)は,民法392条2項後段の規定に基づき,先順位の共同抵当権者(Y)に代位して乙不動産に対する抵当権を行使することができる。
けだし,後順位抵当権者(X)は,先順位の共同抵当権の負担を甲・乙不動産の価額に準じて配分すれば甲不動産の担保価値に余剰が生ずることを期待して,抵当権の設定を受けているのが通常であって,先順位の共同抵当権者(Y)が甲不動産の代価につき債権の全部の弁済を受けることができるため,後順位抵当権者(X)の右の期待が害されるときは,債務者がその所有する不動産に共同抵当権を設定した場合と同様,民法392条2項後段に規定する代位により,右の期待を保護すべきものであるからである。 右の場合において,先順位の共同抵当権者(Y)が後順位抵当権者(X)の代位の対象となっている乙不動産に対する抵当権を放棄したときは,先順位の共同抵当権者(Y)は,後順位抵当権者(X)が乙不動産上の右抵当権に代位し得る限度で,甲不動産につき,後順位抵当権者(X)に優先することができないのであるから(最高裁昭和41年(オ)第1284号同44年7月3日第一小法廷判決・民集23巻8号1297頁参照),甲不動産から後順位抵当権者(X)の右の優先額についてまで配当を受けたときは,これを不当利得として,後順位抵当権者(X)に返還すべきものといわなければならない(最高裁平成2年(オ)第1820号同3年3月22日第二小法廷判決・民集45巻3号322頁参照)。 |
| *図100 最二判平4・11・6民集46巻8号2625頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第94事件 |
以下において,異主共同抵当の場合にも,民法392条と民法500条を同時に適用することによって,通説・判例と同一の結果を保ちつつ,より統一的な説明が可能であるか,通説・判例よりも妥当な結果を導くことができることを示すことにする(民法392条・民法500条双方適用説)。
ところで,異主共同抵当の場合に関しては,後順位抵当権が債務者の財産に設定されたのか物上保証人の財産に設定されたのかで利益状況が異なるため,これを区別して論じるのが有用である。従って,以下では,この2つの場合のそれぞれについて,民法392条がどのように適用されるのかを示すことにしよう。
(i) 事例1:債務者と物上保証人の不動産に共同抵当権が設定され,債務者に後順位抵当権者がいる場合
(A) 事例1とその図解
債権者Aが,800万円の債権を担保するために,債務者Bの不動産(評価額800万円)および物上保証人Cの不動産(評価額800万円)に共同抵当権を設定したとする。債務者Bには,他に債権者Dがおり,800万円の債権を担保するために,債務者の不動産の上に第2順位の抵当権を設定しているとする。
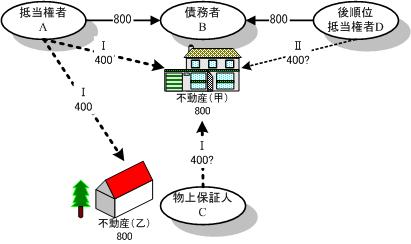 |
| *図101 異主共同抵当の事例1(同時配当) |
(B) 通説・判例による説明
(a) 債務者Bの不動産が先に競売された場合 債務者B所有の不動産上の後順位抵当権者Dは,Aが物上保証人所有の不動産上に有する抵当権には民法392条2項の規定に基づいて代位することはできない〈最一判昭44・7・3民集23巻8号1297頁〉。その理由は,物上保証人は,他の共同抵当物件である債務者所有の不動産から自己の求償権の満足を得ることを期待していたものというべきであり,その後に設定された債務者所有の不動産上の第2順位の抵当権の代位権によってその期待を失わせるべきではないというものである。
その結果として,債務者所有の不動産が先に競売されれば,Aが800万円の弁済を受け,Dの配当は0となり,抵当権の付従性によって物上保証人C所有の不動産上の抵当権は消滅する。この結果は,後順位抵当権者Dには酷とも思えるが,甲不動産(800万円)に800万円の債権を有する第1順位の抵当権者がすでに存在するのに,さらに甲不動産に第2順位の抵当権を設定したDに配当が回らなくても,やむをえないといえよう。
(b) 物上保証人Cの不動産が先に競売された場合 これに対して,物上保証人C所有の不動産が先に競売される場合には,まずAが800万円の配当を受け,自己の不動産で弁済をしたCが,債務者B所有の不動産上の抵当権800万円につき民法500条により代位する。そして,債務者の不動産の競売によってCが代位取得した抵当権から800万円の配当を受ける。したがって,この場合も,Dの配当は0となる。
(C) 本書の立場からの説明
(a) 同時配当の場合 共同抵当権者Aは,民法392条1項により,債務者所有の不動産の評価額と物上保証人所有の不動産の評価額に応じて,それぞれの不動産につき400万円ずつ,全額で800万円の配当を受ける。
物上保証人Cは,自己所有の不動産の競売代金から,Aの配当額を控除した残額400万円を取得する外,共同抵当権者Aに自己の不動産から400万円を弁済したことに基づき,民法500条の規定により,債務者所有の不動産の競売代金の残額400万円につき共同抵当権者AのBに対する抵当権に代位して,第1順位で求償権を行使しうる。
後順位抵当権者Dは,本来ならば,債務者の財産について,第1順位の共同抵当権者Aの配当額を控除した残額400万円について第2順位の抵当権者として配当を受けることができるはずである。しかしこの抵当権は,物上保証人Cが求償債権を確保するために代位によって取得する第1順位の抵当権に劣後し,後順位抵当権者Dは配当を得ることができない。
民法392条2項2文によると,後順位抵当権者は,共同抵当権者Aが物上保証人の抵当目的物に対する割付額である400万円について,第1順位の抵当権者として代位ができそうである。しかし,この場合に,もしも後順位抵当権者による代位を許すと,物上保証人はその額について債務者Bに対して求償権を有するが,その求償権について担保権を行使することができなくなり,物上保証人の利益を害することになってしまう。物上保証人Cと後順位抵当権者Dとの関係は,判例〈最一判昭44・7・3民集23巻8号1297頁〉が明らかにしているように,「第2順位の抵当権者のする代位と物上保証人のする代位とが衝突する場合には,後者が保護されるのであって,甲不動産について競売がされたときは,もともと第二順位の抵当権者は,乙不動産について代位することができない」からである。
結果的には,債務者所有と物上保証人の不動産を競売してAが800万円の配当を受け,物上保証人Cも同様に800万円の配当を受けることになる。
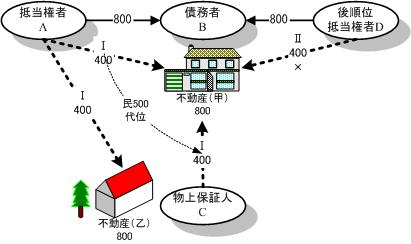 |
|
|||||||||||||||||
| *図102 異主共同抵当の事例1(同時配当,民法392条適用説) | ||||||||||||||||||
もっとも,Aが,債務者所有の不動産の競売のみによって債権全額の満足を得ることのできる場合には,物上保証人Cの不動産の競売は不要であり,Cは保証人の検索の抗弁権によって,AによるC所有の不動産の競売を阻止しうるであろう([民事執行法73条]参照)。
(b) 異時配当の場合
債務者Bの不動産が先に競売された場合 債務者B所有の不動産が先に競売されて,共同抵当権者Aが800万円の配当を受けた場合,本来なら,債務者B所有の不動産上の後順位抵当権者Dは,Aが物上保証人所有の不動産上に有する抵当権につき,民法392条2項の規定に基づいて代位することができるはずである。しかし,すでに同時配当の場合について述べたように,後順位抵当権者Dは,共同抵当権者に民法500条によって代位する物上保証人の求償権に劣後するのであって,配当要求をなしえない。民法392条1項に基づく配当請求をなしえない後順位抵当権者Dが,民法392条2項に基づく代位をなし得ないのは当然の成り行きである。
本来なら,次に,物上保証人C所有の不動産が競売されるはずであるが,債権者Aの債権は,全額が満足され,しかも,債務者Bの不動産上の後順位抵当権をDは,先に述べた理由により,物上保証人C所有の不動産につき,民法392条2項に基づく代位権を有しないのであるから,物上保証人Cの不動産の競売は行われずに,すべての配当が完了する。
| 甲不動産 | 乙不動産 | 合計 | |
| 先順位抵当権者A | 800万円 | 0円 | 800万円 |
| 物上保証人C | 0円 | 800万円 | 800万円 |
| 後順位抵当権者D | 0円 | 0円 | 0円 |
物上保証人Cの不動産が先に競売された場合 物上保証人C所有の不動産が先に競売されて,共同抵当権者Aが800万円の配当を受けた場合,自己の不動産で弁済をしたCが,債務者B所有の不動産上の抵当権800万円につき民法500条により代位する。Dは,同時配当の場合にも配当額が0とされるのであるから,この場合も配当を受けないことは当然である。
| 甲不動産 | 乙不動産 | 合計 | |
| 先順位抵当権者A | 0円 | 800万円 | 800万円 |
| 物上保証人C | 800万円 | 0円 | 800万円 |
| 後順位抵当権者D | 0円 | 0円 | 0円 |
(ii) 事例2:債務者と物上保証人の不動産に共同抵当権が設定され,物上保証人に後順位抵当権者がいる場合
(A) 事例2とその図解 債権者Aが,800万円の債権を担保するために,債務者Bの不動産(評価額800万円)および物上保証人Cの不動産(評価額800万円)に共同抵当権を設定したとする。さらに,後順位抵当権者Dが,800万円の債権を担保するために債務者Bの不動産上に第2順位の抵当権を設定しているほか,物上保証人の債権者Eが,800万円の債権を担保するため,物上保証人Cの不動産の上に,第2順位の抵当権を設定しているとする。
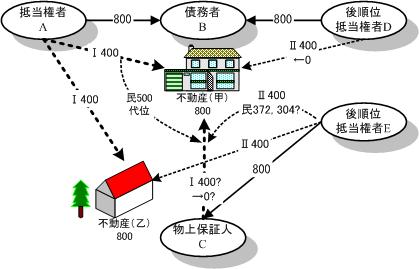 |
| *図103 異主共同抵当の事例2 |
(B) 通説・判例による説明
(a) 債務者Bの不動産が先に競売された場合 債務者B所有の不動産が先に競売された場合には,共同抵当権者Aが800万円の配当を受け,債務者B所有の不動産上の抵当権は消滅する。
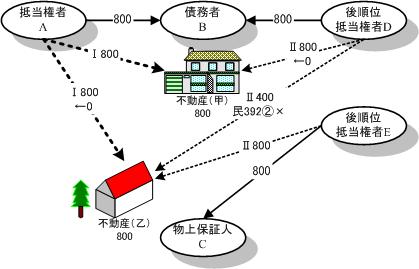 |
|
|||||||||||||||||||||
| *図104 異主共同抵当の事例2(異時配当1・通説) | ||||||||||||||||||||||
そして,次に,Eによって物上保証人C所有の不動産が競売されると,Cの債権者である抵当権者Eが800万円の配当を受ける。
(b) 物上保証人Cの不動産が先に競売された場合 判例は,物上保証人所有の不動産を競売することによって,物上保証人Cは,債務者Bに対して求償権を取得するとともに,代位により債務者B所有の不動産上の抵当権を取得する。しかし,後順位抵当権者Eは,物上保証人に移転したこのAの抵当権から優先して弁済を受けることができるとしている〈最三判昭53・7・4民集32巻5号785頁〉。
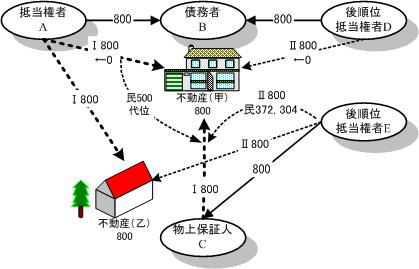 |
|
|||||||||||||||||||||
| *図105 異主共同抵当の事例2(異時配当2・通説) | ||||||||||||||||||||||
この場合においても,異主共同抵当である以上は,民法392条は適用されず,したがって,物上保証人の抵当権者Eに対して,後順位抵当権者としての代位権を認めることはできないとしつつも,物上保証人Cに移転した債務者B所有の不動産上のAの抵当権は,Eの被担保債権を担保するものとなり,あたかもこの抵当権の上に物上代位[民法372条,304条]するのと同様に,優先弁済を受けることができるというわけである〈最三判昭53・7・4民集32巻5号785頁〉。
最三判昭53・7・4民集32巻5号785頁,金法869号45頁
債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産とを共同抵当の目的として順位を異にする数個の抵当権が設定されている場合において,物上保証人所有の不動産について先に競売がされ,その競落代金の交付により一番抵当権者が弁済を受けたときは,物上保証人は債務者に対して求償権を取得するとともに代位により債務者所有の不動産に対する一番抵当権を取得するが,後順位抵当権者は物上保証人に移転した右抵当権から優先して弁済を受けることができるものと解するのが,相当である。けだし,後順位抵当権者は,共同抵当の目的物のうち債務者所有の不動産の担保価値ばかりでなく,物上保証人所有の不動産の担保価値をも把握しうるものとして抵当権の設定を受けているのであり,一方,物上保証人は,自己の所有不動産に設定した後順位抵当権による負担を右後順位抵当権の設定の当初からこれを甘受しているものというべきであって,共同抵当の目的物のうち債務者所有の不動産が先に競売された場合,又は共同抵当の目的物の全部が一括競売された場合との均衡上,物上保証人所有の不動産について先に競売がされたという偶然の事情により,物上保証人がその求償権につき債務者所有の不動産から後順位抵当権者よりも優先して弁済を受けることができ,本来予定していた後順位抵当権による負担を免れうるというのは不合理であるから,物上保証人所有の不動産が先に競売された場合においては,民法392条2項後段が後順位抵当権者の保護を図っている趣旨にかんがみ,物上保証人に移転した一番抵当権は後順位抵当権者の被担保債権を担保するものとなり,後順位抵当権者は,あたかも,右一番抵当権の上に民法372条,304条1項本文の規定により物上代位をするのと同様に,その順位に従い,物上保証人の取得した一番抵当権から優先して弁済を受けることができるものと解すべきであるからである(大審院昭和11(1936)年(オ)第1590号同年12月9日判決・民集15巻24号2172頁参照)。
そして,この場合において,後順位抵当権者は,一番抵当権の移転を受けるものではないから,物上保証人から右一番抵当権の譲渡を受け附記登記を了した第三者に対し右優先弁済権を主張するについても,登記を必要としないものと解すべく,また,物上保証人又は物上保証人から右一番抵当権の譲渡を受けようとする者は不動産登記簿の記載により後順位抵当権者が優先して弁済を受けるものであることを知ることができるのであるから,後順位抵当権者はその優先弁済権を保全する要件として差押えを必要とするものではないと解するのが,相当である。
学説もこの判例理論を支持しており,結果として,物上保証人Cの不動産が先に競売された場合には,Aが800万円の配当を受け,後順位抵当権者Dの配当は0となる。そして,物上保証人Cが債務者B所有の不動産上の抵当権の800万円全額につき代位する。
しかし,次に,債務者Bの不動産が競売されると,物上保証人Cが代位取得した抵当権からEが,物上代位を通じて,800万円の配当を受ける。したがって,結果的には,物上保証人Cの配当額は0となる。
(C) 本書の立場からの説明
(a) 同時配当の場合 共同抵当権者Aは,民法392条により,債務者所有の不動産の評価額と物上保証人所有の不動産の評価額に応じて,それぞれの不動産につき400万円ずつ,全額で800万円の配当を受ける。通説は,同時配当の場合も,債務者B所有の甲不動産から割付けを行うべきだとするが,その根拠は薄弱である。同時配当というからには,物上保証人C所有の乙不動産も視野に入れて,割付けを行うべきだからである。
Dは,Aの後順位抵当権者として,甲不動産の競売代金から400万円の配当を受けるはずであるが,これは,すでに述べたように,物上保証人Cの求償権に劣後するために,配当を受けることができない。
物上保証人Cは,共同抵当権者Aに自己の不動産から400万円を弁済したことに基づき,民法500条の規定により,債務者所有の不動産の競売代金の残額400万円につき共同抵当権者AのBに対する抵当権に代位して,400万円の限度で抵当権を行使しうる。
この物上保証人Cの権利に対して,Cの抵当権者Eは物上代位権を行使しうるかどうかが問題となる。物上代位権は,民法372条による民法304条によって,抵当権者にも与えられているが,それには,民法394条による制限が課せられている。抵当権者は,先に目的物に優先弁済権を行使し,それでも不足な部分は,一般債権者として配当を受けるべきであるとの制約である。後順位抵当権者Eは,先順位抵当権者Aに劣後するのであり,乙財産から配当を受けることができるのは,せいぜい400万円であることを予期すべきであるから,たまたま,抵当権者Aが甲財産から満足を受け,優先順位が上昇したからといって,債務者の債務を肩代りして弁済し,抵当権者に代位して第1順位の抵当権を行使しうる物上保証人Cの権利を害することはできないと解すべきである。
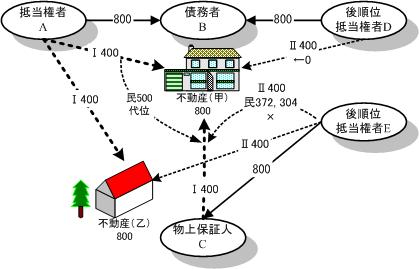 |
|
|||||||||||||||||||||
| *図106 異主共同抵当の事例2(同時配当・民法392条適用説) | ||||||||||||||||||||||
結果的には,債務者と物上保証人の不動産を競売してAが甲不動産から400万円,乙不動産から400万円,合計800万円の配当を受ける。そして,物上保証人Cは,400万円の限度で甲不動産から求償を受ける。次に,物上保証人Cの抵当権者Eは400万円の配当を受けることになる。
これが,民法392条適用説の理論的な結論である。しかし,もしも,この理論に,本書の上記の立場とは異なるが,民法500条に基づく物上保証人の権利は,物上保証人の抵当権者Eの権利行使には劣後する〈最一判昭60・5・23民集39巻4号940頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第93事件)〉とする例外原則を取り入れるならば,結果は,通説と同じになる。
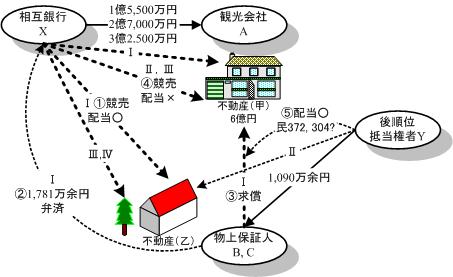 |
共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産及び物上保証人所有の乙不動産にそれぞれ債権者を異にする後順位抵当権が設定されている場合において,乙不動産が先に競売されて一番抵当権者(Xの1番抵当権)が弁済を受けたときは,乙不動産の後順位抵当権者(Y)は,物上保証人に移転した甲不動産に対する一番抵当権から甲不動産の後順位抵当権者(Yの2番,3番抵当権)に優先して弁済を受けることができる。 債権の一部につき代位弁済がされた場合,右債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については,代位弁済者(Y)は債権者(X)に劣後する。 |
| *図107 最一判昭60・5・23民集39巻4号940頁(配当異議事件) 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第93事件 |
すなわち,債務者と物上保証人の不動産を競売してAが甲不動産から400万円,乙不動産から400万円,合計800万円の配当を受ける。そして,物上保証人Cは,400万円の限度で甲不動産から求償を受けることになるはずであるが,物上保証人の抵当権者には劣後するため,求償を得ることができない。そして,物上保証人Cの抵当権者Eが800万円の配当を受けることになる。
(b) 異時配当の場合
債務者Bの不動産が先に競売された場合 債務者B所有の不動産が先に競売されて,共同抵当権者Aが800万円の配当を受けた場合,本来なら,後順位抵当権者Dは,民法392条2項によって,乙不動産に対して400万円の範囲で配当請求ができるはずである。しかし,すでに述べたように,この権利は物上保証人Cに劣後し,Cは,保証人として400万円の範囲で,民法392条2項によってDに与えられた権利に代位する権利を有する。
次に乙不動産が競売された場合,民法392条2項によって先順位抵当権者に代位する後順位権者Dの権利をさらに代位によって取得する物上保証人Cと,乙不動産に対して,第2順位の抵当権を有するEの権利という2つの権利が対立することになる。Eは,後順位抵当権者として割り付けられた400万円については,Cに優先する権利を有するため,400万円の配当を受ける。しかし,残りの400万円については,Cの抵当権者として,CがDに代位した権利に対して物上代位を行使して,Cに優先弁済権を取得することができるかどうかが問題となる。先に述べたように,民法372条が準用する民法304条の物上代位権は,抵当権の場合には,民法394条によって制限を受けており,物上保証人Cの権利には代位できないと考えるべきである。
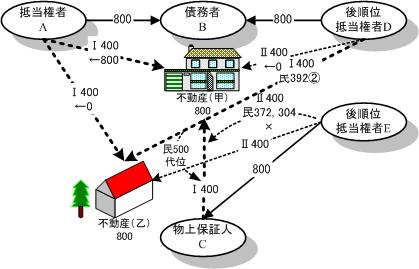 |
|
|||||||||||||||||||||
| *図108 異主共同抵当の事例2(異時配当1・民法392条適用説) | ||||||||||||||||||||||
次に,物上保証人C所有の不動産が競売されると,Cの抵当債権者であるEが自らの第2順位の抵当権に基づいて400万円の配当を受ける。そして,第1順位の抵当権に代位する物上保証人Cが,後順位抵当権者Dに優先して400万円の配当を受ける。そして,これによって,すべての配当が完了する。この場合の結論は,同時配当の結果と同じである。
物上保証人Cの不動産が先に競売された場合 物上保証人C所有の不動産が先に競売されて,共同抵当権者Aが800万円の配当を受けた場合,次に競売される債務者の不動産の競売代金について,自己の不動産で弁済をしたCが,債務者B所有の不動産上の抵当権800万円につき民法500条により代位するはずである。
しかし,本書の立場では,民法392条の適用を否定しないため,物上保証人Cの抵当債権者であるEは,債権者Aが行使しなかった抵当不動産甲に対する第1順位の抵当権を民法392条2項により,400万円の限度で甲不動産から配当を受けることになる。
そうすると,物上保証人が求償権の行使として,民法500条によって代位できるのは,甲不動産の抵当権のうち,400万円の範囲にとどまることになる。
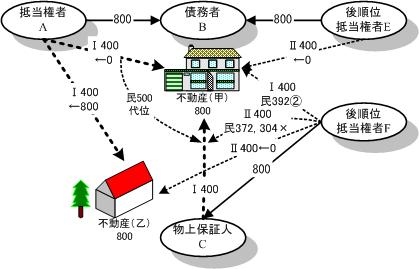 |
|
|||||||||||||||||||||
| *図109 異主共同抵当の事例2(異時配当2・民法392条適用説) | ||||||||||||||||||||||
結果として,Aは,乙不動産から800万円を取得し,乙不動産に抵当権を設定していた後順位抵当権者Eは,民法392条2項によって甲不動産から400万円の配当を受け,物上保証人は,民法500条により,400万円の配当を受けることができることになる。
ただし,先にも述べたように,物上保証人の求償権は,物上保証人の抵当権者の権利に劣後するという最高裁の考え方〈最一判昭60・5・23民集39巻4号940頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第93事件)〉を受け入れるならば,結論は通説と同じとなる。
本書の立場は,あくまで,債務なしに債務者の肩代り責任を負わされている物上保証人の求償権と,それを担保するための代位権は最大限に尊重されるべきであるというものである。物上保証人の求償の利益は,第1抵当権者の出方次第で債権全額の回収を期待することができなくなる後順位抵当権者の利益よりも優先されるべきであり,本書の結果は,物上保証人とその抵当権者(後順位抵当権者)との利害調節が,ほぼ,互角というところに落ち着いており,全面的に後順位抵当権者を優先させる結果となる通説よりも妥当であると考えている。
わが国の民法は,欧米の国々とは異なり,土地と建物を別の不動産としている。そこで,土地または建物の一方だけに抵当権が設定された場合に,例えば,抵当権の実行によって抵当目的物の所有権が買受人に移転し,土地とその上の建物所有権が強制的に分離されると,建物には利用権が設定されていないため,建物を収去しなければならないという事態が生じる。
民法は法定地上権[民法388条]を創設して,他人の土地上の建物を取り壊すことなく,存続させることとしている。 ここでは,法定地上権が成立する要件を明らかにした上で,法定地上権の成否が問題となっている事例を類型化し,具体的な紛争解決のために,法定地上権の要件のうち,どの要件をどのように修正して解釈すべきかを明らかにする。
わが国の民法は,欧米の国々とは異なり,土地と建物を別の不動産としている。確かに,民法86条によれば,建物は「土地の定着物」とされており,建物は土地に付合するようにも見える[民法242条]。しかし,民法370条は,「抵当権は,抵当地の上に存する建物を除き,その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ」と規定しており,土地と建物が別個独立の不動産であることを明らかにしている(民法370条の立法の経緯,および,それに関連して急遽起草された民法388条(法定地上権),民法389条(一括競売)に関する立法の経緯とその後の展開については,村田博史「法定地上権」[星野・講座3(1984)139-174頁]および松本恒雄「民法388条(法定地上権)」[広中=星野・百年Ⅱ(1998)645-689頁]が詳しい)。
ところで,土地と建物とを別個独立の不動産とすると,土地または建物の一方だけに抵当権が設定された場合に問題が生じる。その理由は以下の通りである。まず,民法においては,同一の土地の上の所有権と制限物権(地上権など)が同一人に帰属すれば,制限物権は混同によって消滅する[民法179条]。また,債権と債務が同一人に帰属する場合にも,その債権は混同によって消滅する[民法520条]。したがって,現行法上は,自らが所有する土地の上の建物だけに抵当権を設定する場合に,あらかじめその建物に借地権(自己借地権)を設定しておいてから,借地権付建物に抵当権を設定するわけにいかない。次に,抵当権の実行によって抵当目的物の所有権が買受人に移転し,土地の所有者と建物の所有者とが別人となる,すなわち,土地とその上の建物所有権が強制的に分離されると,建物には利用権が設定されていないため,建物を収去しなければならないという事態が生じる。
実際にも,借地上の建物に抵当権を設定していたXが,抵当権が実行されて建物の所有権を取得したYに対して,Yは土地賃貸人Aの承諾を得ていないとして,Aに代位してYに対して,建物収去・土地明渡を求めるという事件が発生している〈最三判昭40・5・4民集19巻4号811頁民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第85事件〉(詳しくは,*第5章第5節2(b)建物抵当権の敷地利用権(無体物)に対する効力参照)。
昭和40年最高裁判決は,信頼関係破壊の法理を使って,抵当権設定者Xの建物買受人Yに対する不当な建物収去・土地明渡請求を排斥しているが,抵当権の効力が敷地の賃借権に及ぶという点については,権利の上の抵当権という観点からの理論的な検証が必要であろう(この問題については,[借地借家法20条](建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)によって一定の解決がなされている)。いずれにせよ,建物所有者の権利は,確実に保護されるべきである。
民法は法定地上権[民法388条]を創設して,より広い適用領域において,このような問題を解決している。すなわち,土地と建物とを別個の不動産とした上で,法定地上権の創設によって,他人の土地上の建物を取り壊すことなく,存続させることを可能としている。もっとも,土地と建物の所有権が別人に属し,建物になんらかの用益権が設定されている場合には,あえて,法定地上権を認める必要はないことになりそうである。しかし,建物に用益権が設定されている場合でも,その用益権が第三者には対抗できないものである場合には,第三者に対する対抗力を有する法定地上権を認めるべきである。
ところで,土地とその上の建物の強制的分離は,抵当権の実行以外にも生じる。その場合にも,同様の措置が必要となる。強制執行による場合[民事執行法81条]はすでに述べたが,その外にも,租税滞納処分による公売処分の場合[租税徴収法127条],仮登記担保の実行による場合[仮登記担保法10条]が,民法388条と同様の規定を用意している。法定地上権は,一定の要件が充足されると,法律上,当然に発生する。法定地上権の及ぶ範囲は,抵当権の範囲が及ぶ範囲と同じである。そして,法定地上権の地代は,当事者の協議が整わなければ,裁判所が定めることになっている[民法388条2文]。また,存続期間は,当事者の協議が整わなければ,借地借家法3条によって30年となる。この意味で,法定地上権は,法定借地権と考えてもよい。現に,仮登記担保法の場合は,法定「地上権」ではなく,法定「借地権」となっており,法定地上権の一般理論に関する限りは,借地借家法2条1号によって,法定地上権と法定借地権は同等のものとして考える必要が生じているのである。したがって,「法定地上権は約定借地権よりも有利な権利であり,約定利用権が認められる場合に法定借地権の成立を認めることは,抵当権者に損害を与える」とか,「建物所有者に過ぎたる保護を与える」というような,建物所有を目的とする地上権と借地権との相違を強調する通説の論理によっては,もはや,法定地上権を体系的に理解することはできないことを銘記すべきであろう。
ここまでで,法定地上権について抽象的な説明を行ったが,以下では,もう少し具体的に,すなわち,第1に,建物だけに抵当権が設定された場合,および,第2に,土地だけに抵当権が設定された場合というように,もう少し具体的な例に基づいて,法定地上権の機能について検討することにする。
(i) 建物だけに抵当権が設定された場合
第1の類型として,A所有の土地・建物のうち,Bのために建物だけに抵当権が設定され,建物が競売されてCが建物を買い受けたとする。土地の所有者Aの上にあるC所有の建物は,この段階では,Cが正当な権限を有しないため,存亡の危機に瀕する。このため,建物買受人Cの利益を保護すべきか,土地の所有者Aの利益を図るべきかで問題が生じる。第1の解決策は,建物買受人Cは土地の利用権を有しないのであるから,Cはこれを収去してAに明け渡さなければならないとする方法であり,第2の解決策は,建物を保護するため,土地の所有者Aは,建物の買受人Cのために地上権を設定したものとみなすという方法である。第1の方法は,抵当権者Bの利益のために,建物買受人Cの権利を反故にするものであり,しかも,有用な建物を破壊するという国民経済的な損失を招くものであって,採用することができない。
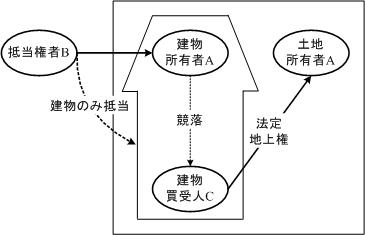 |
・民法 旧・第388条〔法定地上権〕 |
| *図110 建物に抵当権が設定された場合の法定地上権 | |
そこで,民法の立法者は,民法388条を制定して,「抵当権設定者は競売の場合に付き地上権を設定したるものと看做す」(2004年の民法現代語化以前の民法旧388条)としたのである。なお,建物の保護のために与えられる利用権として地上権が選ばれたのは,当時としては,建物所有目的の利用権としては,通常は,地上権が設定されるであろうと考えられていたためである。現在では,建物所有目的の利用権としては,借地権がその典型であるので,仮登記担保法の場合には,法定地上権ではなく,法定借地権が付与されることになっている[仮登記担保法10条]。いずれにせよ,現行法では,建物所有を目的とする利用権は,地上権であれ,賃借権であれ,いずれも,借地権として厚く保護されている[借地法2条1号]。したがって,法定地上権とは,法定借地権のことだと考えても問題はない。
ところで,立法当時の法定地上権の規定[民法旧388条]は,第1の類型である建物のみに抵当権が設定された場合の解決策だけが規定されており,土地のみに抵当権が設定されるという第2類型については,そのままでは適用できないものであった。土地のみに抵当権が設定された場合に,地上権を設定したものとみなされるのは,抵当権設定者ではなく,抵当権者または土地買受人の側だからである。民法立法理由には,「無償にて建物の所有者に当然地上権を与ふべきものとすれば,土地の抵当権者の利益を害すること甚しく」[民法理由書(1987)379頁]と書かれているのであるから,立法者も,土地のみに抵当権が設定される第2類型のことは,当然に予定していたと考えらる。それにもかかわらず,民法旧388条が,建物のみに抵当権が設定される第1類型だけに適用可能であり,土地のみに抵当権が設定される第2類型には適用できないという拙劣な条文となった理由は,次のように推測されている。すなわち,民法370条の審議によって,はじめて,土地と建物とを別個独立の不動産とすることが決定されたために,民法388条が急遽起草されることになったが,参考にすべき規定がドイツ法にもフランス法にも,また,旧民法にもなく,しかも,十分な時間をかけずに(22日間で)起草されたからであろう([松本恒雄「民法388条(法定地上権)」[広中=星野・百年Ⅱ(1998)653頁]参照)。
(ii) 土地だけに抵当権が設定された場合
第1の類型が,建物のみに抵当権が設定された事例であるのに対して,第2の類型は,A所有の土地・建物のうち土地だけにBのために抵当権が設定され,土地が競売されて,Cが土地を買い受けたとする事例である。
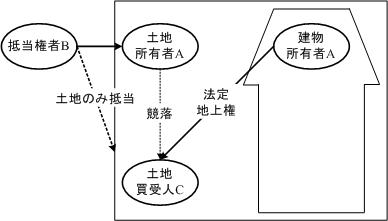 |
・民事執行法 第81条(法定地上権) 土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において,その土地又は建物の差押えがあり,その売却により所有者を異にするに至ったときは,その建物について,地上権が設定されたものとみなす。この場合においては,地代は,当事者の請求により,裁判所が定める。 ・第388条(法定地上権) 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において,その土地又は建物につき抵当権が設定され,その実行により所有者を異にするに至ったときは,その建物について,地上権が設定されたものとみなす。この場合において,地代は,当事者の請求により,裁判所が定める。 |
| *図111 土地に抵当権が設定された場合の法定地上権 | |
土地の所有者Cの上にあるA所有の建物は,この段階では,Aが正当な権限を有しないため,存亡の危機に瀕する。このため,土地の買受人Cの利益を図るべきか,建物の所有者Aの利益を図るべきかで問題が生じる。第1の解決策は,建物所有者Aは土地の利用権がないのであるから,Aはこれを収去してCに明け渡さなければならないとする方法であり,第2の解決策は,建物の所有者Aのために,土地の所有者Cは地上権を設定したものとみなすという方法である。第1の方法は,抵当権者および買受人の利益にはなるが,建物が収去されることになって,国民経済的な損失が生じる。第2の方法は,建物の所有者Aに無償で地上権を与えるものであり,抵当権者Bおよび買受人Cには不利益となるが,建物の破壊という国民経済的損失を防止するには,この方法が優れており,しかも,Aは相当の地代をCに支払うことになるのであるから,公平性も確保される。
しかし,この場合は,民法旧388条の文言通りに解釈することはできなかった。なぜなら,旧条文の文言通りに解釈すると,「抵当権設定者Aは,競売の場合につき,地上権を設定したものとみなされる」となるはずであるが,地上権を設定したとみなされるのは,抵当権設定者の方ではなく,買受人Cの方でなければならないからである。
民法388条の「抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付キ地上権ヲ設定シタルモノト看做ス」という文言が不適切であることは,その後の法定地上権の立法をみれば明らかである。例えば,民事執行法81条は,土地だけが競売された場合にも,「売却により所有者を異にするに至ったときは,その建物について,地上権が設定されたものとみなす」と規定し,民法388条のような問題が生じていることを回避しているからである。
このように考えると,法定地上権に関しては,民法の唯一の条文である民法旧388条は,そもそも,文言解釈が許されない条文であり,民事執行法81条のように,競売によって,土地とその上の建物が別の所有者に帰属する場合,または,そのことが予想される場合に,建物の保護のために設定されるものであることを認識することができるであろう。
このような理由から,2004年の民法の現代語化においては(現代語化の趣旨を超えることは明らかであるが),土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において,「土地又ハ建物ノミヲ抵当ト為シタルトキハ抵当権設定者ハ競売ノ場合ニ付キ地上権ヲ設定シタルモノト看做ス」という第1類型だけに適用できる不十分な規定から,「土地又は建物につき抵当権が設定され,その実行により所有者を異にするに至ったときは,その建物について,地上権が設定されたものとみなす」へと変更され,2つの類型に適用できる規定へと内容の改正が行われたのである。
法定地上権の成否については,以下において,さまざまな類型ごとの考察を行うが,法定地上権の制度そのものに疑問を持ち,それに代わる方法として,更地にあらかじめ自己借地権を設定しておいて,後に建てる建物の使用権限を確保することができるという「自己借地権」制度を創設し,法定地上権の制度を廃止すべきであるとの以下のような見解が主張されている[内田・民法Ⅲ(2005)419頁]。そこで,法定地上権の類型ごとの考察に先立って,法定地上権の制度を廃止すべきかどうかという問題についても触れておくことにする(以下は,[内田・民法Ⅲ(2005)419頁]の考え方について,筆者が〔〕内に番号を振ったものである)。
〔1〕法定地上権制度を正当化する根拠は,究極的には,建物の保存,つまり土地の抵当権実行に際して建物を収去せざるを得なくなることが,いわゆる「国民経済的」損失であるということしかないように思われる。
〔2〕しかし,土地の価値を低下させない建物であるなら,389条の一括競売制度によって建物の保存を図りうる。他方,一括競売を選択すると土地の価値が下落し,抵当権者が損害を受けるとすれば,建物がその土地の有効利用になっていないのであり,そのような場合に建物を取り壊すことが経済的な損失であるとは当然にはいえない。無論,エコロジーの観点からは別の議論が可能であろうが。
〔3〕このように,立法論としては,複雑な解釈問題を生み出している法定地上権制度を残すよりも,これを廃止して自己賃借権制度を創設する方が望ましいと思われる。
〔1〕に対する批判 法定地上権の制度が,「建物の保存」を図るものであることについては,異論がない。しかし,抵当権の実行によって「建物を収去せざるを得なくなることが,いわゆる『国民経済的』損失である」という意味については,以下のような留保が必要である。すなわち,「建物を収去せざるを得ない」ということは,単に,「有用な建物が取り壊される」ことを意味するだけでなく,「土地は賃貸借では安心できない。土地は所有しなければならない」という土地所有への強迫観念を国民に押し付けることになるのであり,そのことこそが,「国民経済的」損失となるという点に留意すべきである。わが国の借地借家法制は,長い歴史を経て,必ずしも土地を所有せずとも安定的な居住生活が保障されるというように,賃貸借に対する国民の信頼感を徐々に確立させてきた。このことは,現在の循環型経済をめざすエコロジーの観点からも支持できるものである。そして,法解釈学の観点からも,借地借家法は,「売買は賃貸を破る」という地震売買の制度を克服し,「売買は賃貸借を破らず」という原則を樹立してきた[借地借家法10条,31条]。後に詳しく論じるように,本書の目標の1つは,この借地借家法の精神をさらに推し進め,「競売も賃貸借を破らず」,すなわち,「抵当権も賃貸借を破らず」という原則を確立することを通じて,土地所有の神話を打破し,賃貸借(借地または借家)によっても,国民の一人ひとりが,老後を含めた安定的な居住が保障される道を模索することにある。このような観点からは,抵当権の実行によって建物を収去せざるを得ないとすることは,単に建物が物理的に取り壊されるという損失だけでなく,「賃借権では安心できない,所有権こそが老後を含めた保障となる」という,「所有神話」を国民に押し付けることになるのであり,そのことこそが「国民経済的」な損失と考えるべきなのである。
〔2〕に対する批判 〔2〕は,土地所有の神話に基づいて,建物所有を目的とする賃貸借に対して否定的な見解を述べるようなものであり,賛成することができない。建物の有効利用を,土地所有権の価値を高めるという観点だけで見れば,〔2〕のような見解も成り立ちうる。しかし,土地の有効利用は多様な視点から考察すべきであり,土地の有効利用を抵当権者(金銭債権者,特に銀行)の立場からのみ眺めるのは問題であろう。居住目的の建物がある場合には,そこに居住する生活者の視点からも土地の有効利用を考慮すべきである。そのような観点から見れば,民法389条の一括競売には,土地と建物の買受人が同一人になるとは限らないという欠陥があることが明らかであり,民法389条の一括競売を利用すれば,建物の保存が図れるという保障は存在しない。
〔3〕に対する批判 法定地上権の制度は,建物を保護することによって,建物賃借人に対して最低限の居住権を確保するものである。そのような最低限の保護を確保した上で,いわゆる土地の有効活用を図るためのさまざまな方法が考えられるべきである。現在のところ,「自己借地権」は,土地所有者が分譲マンションのために土地使用権を設定し,土地所有者(借地権設定者)がマンションの一部の区分所有者になろうとする場合に限って,借地権設定者が自ら借地権者となることが認められているにすぎない[借地借家法15条1項]。この制度をさらに拡張して,更地にあらかじめ自己借地権を設定しておいて,後に建てる建物の使用権限を確保することができるようにしようというのが「自己借地権」の一般化の構想である。しかし,この構想も,法定地上権が確保された上で,契約自由の精神に従って,利用が可能な限りで,その有効範囲を広げていけばよい問題にすぎない。「自己借地権」が一般化されたからといって,居住権に対する最低限の保護としての法定地上権を廃止すべきだということにはならないない。自己賃借権を義務づけない限り,自己借地権の制度があるだけでは,建物の保存が確保されるわけではないからである。いずれにしても,法定地上権(法定借地権)と自己借地権両立の道が模索されるべきであろう。また,法定地上権が「複雑な問題を生み出している」というのは,金銭債権者の立場に立って,法定地上権を否定する方向で検討するからそのような複雑な問題が生じるのであり,本書のように,「抵当権は,使用・収益権に介入できない」,「抵当権は賃貸借を破らず」,そして,「建物の保護(特に,居住用建物の賃借権)は,金銭債権を目的とする抵当権に優先する」という観点から法定地上権の成否の解釈を行うならば,法定地上権の問題は,単純明快な問題となることがわかるはずである。
このような本書の立場を明らかにするため,以下において,法定地上権が認められるべきことを,さまざまな類型ごとに考察することにする。
法定地上権の成立要件は,民法388条によれば以下の通りであり,その効果は,「その建物について,地上権が設定されたものとみなす」というものである。
これらの要件は,一見したところ,時間的な経過に従って並べられているように見える。特に,抵当権者の利益を優先する考え方では,抵当権の設定当時に抵当目的物の価値を評価するのであるから,抵当権の設定以後に事情が変更され,更地に建物が建てられたり,抵当権の設定時に所有者が異なっていたのが抵当権の実行時に所有者が同一人となったような場合には,もしも,法定地上権を成立させると,抵当権者に損失(設定時に把握していた担保価値が減少する)が生じるために,法定地上権は成立しないと考えてきた。
しかし,法定地上権の目的が,建物の保護であり,それが,抵当権者の利益よりも優先すべきであると考える場合には,(1)と(2)の順序は,逆でもかまわないということになる。
例えば,抵当権の設定当時は,土地とその上の建物が同一の所有者に属しなかったが,(2)その土地または建物の一方につき抵当権が設定され,その後,抵当権の実行までの間に,(1)土地およびその上に存する建物が同一の所有者に属するようになり,(3)その実行により所有者を異にするに至った場合,すなわち,要件が(2),(1),(3)の順序で充足された場合においても,法定地上権の成立が認められるべきことになる。その理由は,以下の通りである。
第1に,民法旧388条とは異なり,法定地上権の目的が,当事者の意思の推測(「抵当権設定者は…地上権を設定したるものと看做す」)にあるのではなく,建物の保護のためである(「その建物について,地上権が設定されたものとみなす」)ということが明確に規定されたことを受けて,従来の解釈とは異なり,法定地上権の要件を,建物を保護するための要件として再構成する必要が生じているからである。この点は非常に重要であり,これまで,当事者の意思の推測を全面に押し出し(たとえば,[我妻・担保物権(1968)352頁],[高木・担保物権(2005)190頁],[内田・民法Ⅲ(2005)423頁],[近江・講義Ⅲ(2007)190頁],[道垣内・担保物権(2008)211頁]など),抵当権者の利益のために,法定地上権の成立を否定してきた学説・判例は,現行民法388条の文言の変更にあわせて,建物の保護の観点から,全面的に見直す必要が生じているといえよう。このことは,民事執行法188条が担保不動産競売に関して,強制競売の規定を全面的に準用しているにもかかわらず,同法81条(法定地上権)についてのみ準用を除外しており,その結果,民法388条の解釈に当たっては,民事執行法81条との整合性を確保することが必要となっていることからも是認されるべきである。
第2に,抵当権者は,抵当目的物の使用・収益権を奪うことはできないのであり,抵当目的物である更地に抵当権設定者が建物を築造しても,それは,土地利用の当然の成り行きであり,抵当権者はそれを覚悟した上で抵当権を設定すべきだからである。したがって,抵当権設定のときに,土地と建物とが同一人に属しているときはもちろん,抵当権の実行の際に,土地と建物が同一人に属するようになり,土地または建物の一方だけに設定された抵当権を実行すれば,建物の利用権が確保されないという場合には,法定地上権を認めても,抵当目的物に対する抵当権設定者の使用・収益権を奪うことができない抵当権者を害することにはならない。
第3に,抵当権の実行によって抵当目的物を取得する買受人にとっては,抵当権の実行当時に,土地と建物の所有権が同一人に帰属している場合には,法定地上権が成立することを予測できるのであり,買受人を害することにもならない。
このように考えると,民法388条における法定地上権の成立要件のうち,(1)と(2)とは,抵当権の実行によって土地と建物の所有権が別人に帰属することになった場合に,建物を保護するに値する要件として,建物に利用権が設定されないことに正当な事由がある場合を例示的に示したにすぎない(例示要件)。すなわち,民法388条の真の要件は,(1)’「建物に利用権が設定されていないことに正当な事由がある」であり,それに(3)の「抵当権の実行により所有者を異にすること」という要件が加わったときに,その建物を保護するために,法定地上権が成立すると再構成することが必要である。
このような解釈は,解釈論の領域を超えているように見えるかもしれない。しかし,このような解釈は,民法612条において「無断譲渡・転貸」が賃貸借解除の要件とされているにもかかわらず,最高裁が,真の要件を信頼関係破壊の法理に従って行った解釈と同様のものに過ぎない。すなわち,この解釈は,最高裁が,「無断譲渡・転貸」という具体的な要件を「背信的行為」という一般要件へと読み替え,たとえ,無断譲渡・転貸があっても,「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事由があるときは,本条に基づく解除権は発生しない」〈最二判昭28・9・25民集7巻9号979頁〉と解釈したのと同じ発想に出るものである。さらに,「抵当権設定者は…地上権を設定したるものと看做す」として当事者の意思を強調していた民法旧388条が,現代語化に際して,「その建物について,地上権が設定されたものとみなす」と改正されたのであるから,このような解釈も,解釈論の枠に収まるものと思われる(民法612条の解釈論の位置づけについては,[加賀山・民法学習法(2007)48頁以下,特に,61-62頁,108-109頁]参照)。
もっとも,このような考え方は,民法388条の要件論としては,全く新しい発想によるものなので,再構成された民法388条の法定地上権の成立要件を条文の形で構造化して示すことが必要であろう。
|
民法388条の要件の構造化←解釈論,かつ,民法388条(改正試案) |
先にも述べたように,2004(平成16)年に民法が現代語化される以前は,民法旧388条は「抵当権設定者ハ…地上権ヲ設定シタルモノト看做ス」と規定しており,法定地上権の成立要件を考察する上で,抵当権設定時の当事者の意思を推測すること,特に,抵当権者が担保価値を評価する上での意思を推測することが重視されてきた。しかし,民法の現代語化に伴う民法388条の修正により,法定地上権の目的が,民事執行法81条にならって,当事者の意思の推測から,「建物について,地上権が設定されたものとみなす」というように,建物保護へと変更されたことが重視されなければならない。さらに,民事執行法81条は,抵当権の実行の際には適用が除外されており[民事執行法188条],抵当権の実行による競売の際に,民事執行法81条と同様の要件で法定地上権の成立を認めることが要請されるに至っていることも,重要な考慮要素となる。
以上のような状況の変更を考慮するならば,当事者の意思の推測を全面に押し出し,抵当権者の利益のために,法定地上権の成立を否定してきた数々の判例は,建物保護の観点から,全面的に見直す必要が生じているといえよう。そこで,以下では,民法旧388条が修正され,法定地上権の目的が,抵当権者の意思の推測から,建物保護の優先へと変更されたことを重視し,そのような新しい観点から,従来の学説および判例の全面的な見直し作業を行うことにする。
(i) 抵当権設定時点
抵当権の設定当時に土地とその上の建物が同一の所有者に属し,土地または建物の一方のみに抵当権が設定された場合,抵当権者は,抵当目的物件が競売された場合に,建物保護のために法定地上権が成立することを予測しうる。
したがって,抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に属する場合には,後に土地と建物が別人に帰属することになったとしても,競売の時点で,建物の存立基盤としての建物利用権が確保されていない場合には,法定地上権が成立すると考えるべきである。
(ii) 抵当権実行時点
従来の通説・判例によれば,法定地上権の成立には,抵当権設定のときに,土地およびその上の建物が同一の所有者に属することが必要であるとされてきた。このため,法定地上権の制度は,以下に述べるように,次のような,3点で複雑な問題を生じると考えられてきた。
第1は,更地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合に,その建物のために法定地上権が成立するかどうかという問題である。第2は,抵当権の設定当時には建物が存在していたが,その後,その建物が取り壊されるなどして滅失したため,建物が再築された場合に,再築された建物のために法定地上権が成立するかどうかという問題である。第3は,先順位抵当権者に関しては法定地上権の要件が満たされていないが,その後設定された後順位抵当権者との関係では,法定地上権の要件が満たされた場合に,法定地上権は成立するのかどうかという問題である。そこで,以下では,これらの問題について検討する。
ここでの問題は,抵当権設定当時更地であった土地に抵当権が設定され,その後に抵当権設定者によって建物が築造され,抵当権者が土地のみを競売した場合に,抵当権設定後に築造された建物のために法定地上権が成立するかどうかである。
従来の要件論によると,土地と建物とが同一所有者に属するという要件は,抵当権設定時が基準となるため,法定地上権は成立しないとされてきた(〈大判大4・7・1民録21輯1313頁〉,〈大判大15・2・5民集5巻82頁〉,〈最二判昭36・2・10民集15巻2号219頁〉)。この場合に,通説が,法定地上権を否定する理由は,更地に抵当権が設定された場合,「抵当権者は,法定地上権成立の予測すらたたないのであり,法定地上権の成立を認めるべきではない」[近江・講義Ⅲ(2007)186頁]というものである。
確かに,最高裁〈最二判昭36・2・10民集15巻2号219頁〉も,民法旧388条の解釈として,「民法388条により法定地上権が成立するためには,抵当権設定当時において地上に建物が存在することを要するものであって,抵当権設定後土地の上に建物を築造した場合は原則として同条の適用がないものと解するを相当とする」という原則論を述べている。しかし,「更地としての評価に基づき抵当権を設定したことが明らかであるときは,たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があっても,民法388条の適用を認むべきではない」とも判示しており,もしも,抵当権者が更地としての評価ではなく,建物の築造を予測して担保価値を把握していた場合には,法定地上権の成立を認める余地を残した判断を行っている。
最二判昭36・2・10民集15巻2号219頁
土地に対する抵当権設定の当時,当該建物は未だ完成しておらず,しかも更地としての評価に基づき抵当権を設定したことが明らかであるときは,たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があっても,民法388条の適用を認むべきではない。
しかし,通説および判例の考え方は,2004年の民法の現代語化によって,民法388条が実質的に改正され,法定地上権の目的が,当事者(特に,抵当権者)の意思の推測から,建物保護のためへと変更されたことが反映されておらず,現行民法の解釈としては,もはや妥当性を有しないというべきである。
現行民法388条は,民事執行法81条に同調(シンクロ)させて改正されたものであり(民事執行法188条が,民事執行法81条の適用を除外しているのは,民法388条によって法定地上権が成立することを前提にしている),抵当権設定の当時にすでに建物が存在することを前提にしているわけではなく,抵当権の実行の当時に建物が存在していれば,その建物の保護のためにも,法定地上権が成立すると考えるべきだからである。
抵当権設定後も,抵当権設定者は,土地の使用・収益,すなわち,建物の建築を自由になしうるのであり,更地に建物を建てることは,むしろ,自然の成り行きである(優良な賃貸マンションが建築された場合には,土地の価格自体も増加するのであって,更地に建物を建築することが抵当権の損失になるわけでもない)。このように考えると,上記の学説のように,抵当権者は,「更地に建物が建つことを予測しえない」というのは詭弁でしかなく([清水(元)・担保物権(2008)]は,杞憂であるとする),抵当権者が,更地を基準にして担保価値を設定するということ自体が,抵当権の効力を過信した,勝手な思い込みに過ぎないというべきである。
抵当権者としては,たとえ,更地に抵当権を設定したとしても,抵当権者がその土地の使用・収益権を奪うことができない以上,土地利用の通常の成り行きとして,建物が建つことを予測して,担保価値を把握すべきある。したがって,更地に抵当権が設定されて,建物が築造された場合に,その後,抵当権が実行され,土地が競売された場合にも,法定地上権が成立することに対して,抵当権者または買受人は,それに異議を唱える権利はない。買受人も,抵当権の実行の際に,すでに建物が存在しており,法定地上権が成立することを予測できるからである。
この点に関して,抵当権者は,この場合,民法389条により,土地・建物を一括して競売することができるのであり,土地のみを競売した場合には,法定地上権が認められるべきであるとする少数説([柚木=高木・担保物権(1973)380頁],松本恒雄「抵当権と利用権との調整についての一考察」民商法雑誌80巻3号31頁以下。)が,現代語化による民法388条の改正によって,以前にも増して説得力を有するに至っている。
強制執行の場合でさえ,土地とその上の建物のうち,一方のみが差し押さえられて一方のみが競売され,強制的に土地と建物が分離される場合には,法定地上権が発生することとされたのであるから[民事執行法81条],更地に抵当権を設定した後,建物が築造された場合に,抵当権者が土地のみを競売した場合にも,法定地上権を認めるべきことは当然である。民事執行法が,不動産担保権の実行としての競売に関して,不動産に対する強制競売に関する規定をほぼ全面的に準用しているにもかかわらず,民事執行法81条(法定地上権)の規定について適用除外としているのは[民事執行法188条],担保権の実行の場合には,民法388条によって法定地上権が確保されており,法定地上権が重複するのを防止するためであるとされている[中野・民事執行概説(2006)306頁]。このことを考慮するならば,法定地上権の成立要件における「土地・建物の所有者の同一人」の要件は,抵当権の設定時のみならず,民事執行法81条の場合と同様,抵当権の実行の時も,基準時点として考慮されるべきである。
したがって,法定地上権の成立要件のうち,「土地とその上の建物が同一所有者に属する」という要件は,必ずしも,抵当権設定時に備わっている必要はなく,抵当権実行時に備わっていればよいと考えるべきである。
抵当権が設定された目的土地が更地であったとしても,抵当権者としては,抵当目的の使用・収益権を奪うことはできないのであり,たとえ,抵当権設定後に更地に建物が築造され,抵当目的物である土地の価値が上下しても,抵当権者は,そのような土地の利用状況の変更に伴う担保価値の変動を覚悟すべきである。したがって,従来の通説とは異なるが,抵当権設定後に更地に建物が築造され,その後に抵当権が実行された場合に,建物を保護するために法定地上権が成立するとしても,抵当権者は,それを甘受すべきであることは,すでに述べた。
そうであるならば,建物が滅失した後に,建物が再築された場合にも,更地に抵当権が設定されていた場合と同様に考えるべきである。すなわち,再築された建物を保護するために,法定地上権の成立を認めるべきである。以下のように,大審院〈大判昭10・8・10民集14巻1549頁〉以来,最高裁〈最三判昭52・10・11民集31巻6号785頁〉もこの法理に則って判決を下してきた。
大判昭10・8・10民集14巻1549頁
土地及び其の上に存する建物が同一の所有者に属する場合に於て,土地のみを抵当と為したるときは,其の建物を取毀ち新たに建築したる場合に於ても仍ほ抵当権設定者は,競売の場合に付,地上権を設定したるものと看做すべきものとす。
最三判昭52・10・11民集31巻6号785頁
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において,抵当権者が,抵当権設定当時,近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは,堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。
ところが,その後,法定地上権を利用した抵当権に対する執行妨害の濫用事例が増加するようになると,たとえ,居住権者の利益を害することがあったとしても,金銭債権者に過ぎない抵当権者の利益を居住権者の利益よりも重視するという考え方が有力となり,法定地上権の成立を大幅に制限する傾向が生じるようになる。特に,東京地裁が1992(平成4)年に公表した執務取扱指針(「東京地裁平成4年6月8日民事第21部執行処分」金法1324号36頁)が,建物が再築された場合に法定地上権の成立を認めないという扱いを採用してからは,それに影響された最高裁が,それ以降,以下の判決〈最三判平9・2・14民集51巻2号375頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第91事件)〉を含めて,さまざまな類型において,法定地上権の成立を認めないという判断を下すようになった。
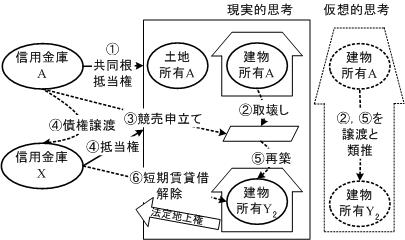 |
所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後,右建物が取り壊され,右土地上に新たに建物が建築された場合には,新建物の所有者が土地の所有者と同一であり,かつ,新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り,新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。 |
| *図112 最三判平9・2・14民集51巻2号375頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第91事件 |
上記の判例の事案の場合,確かに,当初は,土地と建物との双方に抵当権が設定されており,抵当権者は,土地および建物の全体の担保価値を把握していた。しかし,抵当権の実行の当時には,抵当権の目的である建物が取り壊しによって滅失し,建物の抵当権は消滅している。その後,借地人が建物を再築したが,再築建物に抵当権が移行するという法制度は,わが国にはいまだ存在しない(すでに述べたように,フランスでは,増担保請求権の法理を使って,再築後の建物に抵当権の効力が及ぶことを認めている(フランス民法典2420条3項))。このため,再築建物には抵当権の効力が及ばない状態となっていた。したがって,この事案の場合には,①同一の所有者に属する土地および建物(再築)のうち,②一方(土地)だけに抵当権が設定されており,③その実行の結果,所有者を異にするに至ったという,民法388条の要件は完全に満たされている。このように,分析的に考えると,この事案の場合に,法定地上権が成立することは自明のことのように思われる。
それにもかかわらず,この場合に,最高裁があえて法定地上権の成立を否定したのは,上記の東京地裁の執務取扱指針(全体価値考慮説)に影響されたためと思われる。全体価値考慮説は,従来の個別価値考慮説に対立するものであり(現在でも,個別価値考慮説の考え方を維持すべきだとする説としては,[高木・担保物権(2005)211頁],[清水(元)・担保物権(2008)]72頁参照),それぞれの内容の概略は,以下の通りである(なお,両者の区別についての図式化としては,[田髙・物権法(2008)259頁]参照)。
この時代(民法388条が現代語化される前)の最高裁を含めた裁判所の考え方は,法定地上権の成否の判断を,民法旧388条と同様,当事者(特に抵当権者)の意思の推測に求めており,建物の保護よりは,抵当権者が把握する価値こそが重要視されていた。この考え方には,現行民法388条が目的としている建物の保護,特に,建物の居住権を抵当権に優先させるという発想は重視されていない。むしろ,抵当権設定後に築造される建物は,原則として,抵当土地の価値を下げる要因となる邪魔な物とみなされ,抵当権者にとって利益となる特別の場合にのみ,例外的に法定地上権の成立を認めようというものであった。
もっとも,東京地裁の執務取扱指針(全体価値考慮説)が大きな影響力を与えた背景には,抵当権設定者の執行妨害事例(例えば,抵当権設定者が建物を取り壊してバラックを立て,これを法定地上権付きで譲渡するなどの法定地上権の濫用事例)から抵当権者の利益を守ろうとする実務上の要請があり,この指針(全体価値考慮説)がその要請に応えるものだったからである。
しかし,全体価値考慮説に対しては,以下のような問題点があることが指摘されている[田髙・物権法(2008)260-261頁]。
住宅ローンのため住宅と敷地とに共同抵当が設定されたが,ローンの返済が進んでいない段階で火災や震災により住宅が失われた場合,同説によると,建物再築のための新たな融資が受けられなくなってしまう。従来融資をしていた銀行は,新規に何らかの担保が提供されない限り新たなローンの申込みを受け付けないであろうし,かといって別の銀行が法定地上権の成立ないし再築建物を抵当にとって融資に応じるとも考えがたい(野村重信「問題のある法定地上権」金判887号(1992年)2頁等参照)。このように,全体価値考慮説は,災害復興の機会を奪うものと評されかねない一面を内包しているのである。
[山野目・物権(2009)269頁]も,実質論としても問題であると指摘した上で,「判例の解釈は,およそ388条の法文から想定可能な限度を逸している」として平成9年の最高裁判決〈最三判平9・2・14民集51巻2号375頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第91事件)〉を批判する。もしも,裁判所が,民法388条の目的である建物の保護とともに,抵当権者の利益をも確保したいのであれば,抵当権の物上代位[民法372条によって準用される民法304条]の場合と同様,抵当権の目的物である建物が滅失した場合にも,それに代わる再築建物に抵当権の効力が及ぶという新しい解釈(フランスのように増担保請求の法理を使う,または,再築建物に対する物上代位類推適用を行うなど)をすべきであった。そのような努力を抜きにして,建物の保護を目的とする民法388条のすべての要件が満たされているにもかかわらず,民法388条の明文の規定に反して法定地上権の成立を一般的に否定することは,裁判所の権限を逸脱するものといえよう。
上記の平成9年最高裁判決〈最三判平9・2・14民集51巻2号375頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第91事件)〉が例外として法定地上権の成立を認める場合というのは,更地に債権者Aのために抵当権が設定され,その後に建物が築造されたが,その建物にも土地抵当権者のために同順位の抵当権が設定されるという事案である。この場合には,法定地上権を認めても,土地および建物の双方の担保価値を把握している抵当権者の権利を害することがないし,競売による買受人の期待を害するおそれもない。この考え方によると,同じく,共同抵当の場合でも,共同抵当の目的となった土地の上の建物の再築の際に,土地抵当権者に同一順位の建物抵当権が設定されない場合のように,抵当権者の利益を害すると考えられる場合には,法定地上権の成立は否定されることになってしまう。
このような抵当権者の利益を優先する傾向に終止符が打たれ,再度,法定地上権が認められるようになるには,次に述べる最高裁の2007(平成19)年判決〈最二判平19・7・6民集61巻5号1940頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第90事件)〉まで待たなければならなかった。
抵当権者の利益のためには,建物の保護を犠牲にしてもやむをえないという,1992(平成4)年頃から始まる一連の最高裁の判決が,徐々に建物保護を優先するという方向で修正されていく1つの節目となったのは,平成10年の最高裁判決によって,抵当権に基づく賃料債権に対する物上代位が認められるようになったからであろう。
抵当土地に賃貸目的の建物(マンション等)が築造され,まとまった賃料収入が発生すれば,それが,抵当権者の担保目的となるため,建物の築造が,むしろ,抵当権者にとっても歓迎されるべきことが認識されるようになったからである。さらに,抵当権の設定後に,目的不動産に建物が築造された場合に,それが,常に抵当権者にとって損害となるわけではなく,債務者に賃料収入がもたらされる結果,債権の回収が確実になるばかりでなく,抵当土地の地価まで上昇することがわかるようになると,建物を抵当権を妨害するものであるとの認識の下で,法定地上権の成立を否定するという考え方に,必ずしも合理性を見出せないことも次第に明らかとなっていった。
このような経過の中で,法定地上権の成立を否定する傾向を改め,法定地上権の成立を認めた平成19年の最高裁判決〈最二判平19・7・6民集61巻5号1940頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第90事件)〉は,それ以前の判例〈最二判平2・1・22民集44巻1号314頁〉を実質的に変更するものである点からも,高く評価されるべきである。
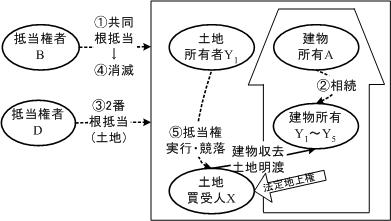 |
土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地上権が成立する。 |
| *図113 最二判平19・7・6民集61巻5号1940頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第90事件 |
この事案は,競売により土地を買い受けたXが,その上に存する建物の共有者であるYらに対して,建物収去明渡を求めたところ,原審が,建物の保護よりも,第1順位の抵当権者の利益を優先した最高裁判例〈最二判平2・1・22民集44巻1号314頁〉に従って法定地上権の成立を否定し,Xの請求を認容したため,Yらが上告したものである。
Yらが上告した背景には,平成2年の最高裁判決は,実は,建物の保護を重視して,法定地上権の成立を肯定するとしていた大審院昭和14年判決以来の判例(〈大判昭14・7・26民集18巻772頁〉およびこれを前提としていた〈最二判昭53・9・29民集32巻6号1210頁〉)の立場を不当に変更したものであり,平成2年の最高裁判決は,2004年の現代語化によって,抵当権者の利益よりも建物保護を優先することが明文上明らかになった民法388条の条文の趣旨に逆行するものであるとの思いがあったものと思われる。平成2年の判決よりも,建物保護を優先してきた従来の判例〈大判昭14・7・26民集18巻772頁〉の立場の方が,現行民法388条の趣旨に合致していることは明らかである。
大判昭14・7・26民集18巻772頁
土地及其の地上の建物が同一所有者に帰属したる際に於て,其の土地又は建物に対し設定せられたる抵当権〔第2順位の抵当権〕の存する限り,当該抵当権実行の為の競売は勿論,右土地及建物が未だ同一所有者に属せざる当時該土地又は建物に対し設定せられたる他の抵当権者〔第1順位の抵当権者〕の申立に因る競売の場合をも包含するものとす。
上記のような建物保護を優先する大審院以来の判例を変更し,抵当権者の利益を優先した最高裁の平成2年判決〈最二判平2・1・22民集44巻1号314頁〉は,しかしながら,当時の学説からは,高い評価を受けていた。
最二判平2・1・22民集44巻1号314頁
土地を目的とする1番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり,法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には,土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても,抵当権の実行により1番抵当権が消滅するときは,法定地上権は成立しない。
その理由は,…土地について一番抵当権が設定された当時土地と地上建物の所有者が異なり,法定地上権成立の要件が充足されていない場合には,一番抵当権者は,法定地上権の負担のないものとして,土地の担保価値を把握するのであるから,後に土地と地上建物が同一人に帰属し,後順位抵当権が設定されたことによって法定地上権が成立するものとすると,一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることになるからである。
最高裁の平成2年判決〈最二判平2・1・22民集44巻1号314頁〉は,それが,上記の大審院昭和14年判決以来の判例と矛盾することになるのではないかとの疑問について,以下のように説明している。
原判決引用の判例(大審院昭和13年(オ)第2187号同14年7月26日判決・民集18巻772頁,最高裁昭和53年(オ)第533号同年9月29日第二小法廷判決・民集32巻1210頁)は,いずれも建物について設定された抵当権が実行された場合に,建物競落人が法定地上権を取得することを認めたものであり,建物についてはこのように解したとしても一番抵当権者が把握した担保価値を損なわせることにはならないから,土地の場合をこれと同視することはできない。
確かに,昭和14年大審院判決は,土地ではなく,建物だけに抵当権が設定された事案であり,最高裁の平成2年判決とは事案が異なっている。しかし,昭和14年大審院判決は,建物に抵当権が設定された場合ばかりでなく,「土地又は建物に対し設定せられたる抵当権の存する」場合と述べて,建物または土地のいずれか一方に抵当権が設定されている場合の双方について,第1抵当権者の利益を犠牲にしても,建物の保護のために,法定地上権の成立を認めたものであり,平成2年判決と両立しえないものである。
したがって,現在の有力説は,以下のように述べて,平成2年の最高裁判決に従って,建物に抵当権が設定された事案である昭和14年判決の考え方そのものを変更すべきであり,いずれの場合も,法定地上権の成立を否定すべきであると主張している[内田・民法Ⅲ(2005)427頁]。
〔最高裁平成2年〕判決には説得力があり,支持できる。しかし,そうであるなら,建物に抵当権が設定された類似の事案で法定地上権を認めるのは一貫しない。抵当権設定後の権利関係は,建物の抵当権であれ土地の抵当権であれ,最優先順位の抵当権を基準に決めるという立場を採用すべきである。したがって,建物の1番抵当権は,その設定当時存在した敷地利用権に及び,たとえ建物所有者が土地所有権を取得しても,もとの利用権は混同の例外として存続する[民法179条1項但書]と考えるべきである。
このような考え方は,現行民法388条が,その成立要件について,建物に抵当権が設定された場合と土地に抵当権が設定された場合とを区別せず,統一的に規定したことに適合的である。しかし,抵当権者の利益ではなく,建物保護をその目的としているという観点からは逆行している。抵当権の実行の結果,土地とその上の建物の所有権者が異なるに至った場合には,建物を保護するために,法定地上権が成立すると考えるべきである[山野目・物権(2009)273頁]。そして,このことは,建物だけに抵当権が設定された場合にも,また,土地のみに抵当権が設定された場合にも,等しく妥当すべきであると考える。
そもそも,法定地上権が成立するかどうかの判断を,先順位抵当権者とか,第2抵当権者とかの意思の推測に求めること自体が誤りであり,法定地上権の成否は,先に示した2つの要件,すなわち,(1)土地または建物に対する抵当権の実行の際に,建物に利用権が設定されていないことに正当な理由があること,および,(2)抵当権の実行により,土地およびその上の建物の所有者を異にするに至ったことを基準に判断されなければならない。本件の場合,第1順位の抵当権の設定当時には,土地と建物の所有権が同一人に帰属していないが,その後,建物所有者が,土地の所有権を相続によって取得することにより,抵当権の実行時には,土地と建物の所有権が同一人に帰属しているのであるから,建物に利用権が設定されていないことに正当な理由がある。したがって,この場合には,第1抵当権者にとっても,また,第2抵当権者にとっても,法定地上権の成立が認められることになる。
このように考えると,最高裁平成19年判決は,第1順位の抵当権が消滅し,第2順位の抵当権者の地位が第1順位へと昇格し,抵当権者が単独となったために,法定地上権の成立が認められたと解するのではなく,たとえ,第1順位の抵当権が消滅しなかった場合にも,法定地上権の成立が認められる事例であると考えることができる。最高裁平成19年判決により,実質的に最高裁平成2年判決が変更され,大審院昭和14年判決の法理が復活しているのであるから,今後は,現行民法388条の目的である建物保護の観点に立って,法定地上権の役割が再評価されるべきである。
法定地上権の成立の類型を,以下のように,基本型,抵当権設定時に同一所有者型,抵当権実行時に同一所有者型,仮登記型,共有型に分類できる。
| (a)基本型 | (i)建物だけに抵当権 | |
| (ii)土地だけに抵当権 | ||
| (b)抵当権設定時に 同一所有者型 |
(i)設定時同一人,競売時別人 | A)抵当物件の譲渡 |
| B)その他の物件の譲渡 | ||
| (ii)登記名義同一人,実質別人 | A)抵当物件の名義同一人 | |
| B)その他の物件の名義同一人 | ||
| (c)抵当権実行時に 同一所有者型 |
(i)設定時別人,競売時同一人 | |
| (ii)登記名義別人,実質同一人 | A)抵当物件の名義前主 | |
| B)その他の物件の名義前主 | ||
| (d)仮登記型 | (i)土地に仮登記,建物に抵当権 | |
| (ii)建物に仮登記,土地に抵当権 | ||
| (e)共有型 | (i)土地共有,建物単独所有 | |
| (ii)建物共有,土地単独所有 | ||
本来なら,これらの類型ごとに考慮すべきであるが,基本形については,すでに詳しく説明したこともあり,紙幅の関係で,詳しい検討は,研究書に譲ることにする(加賀山・担保法(2009)524-543頁参照)。
いずれの類型においても,法定地上権の成立を認めるべきであるというのが,本書の立場である。応用例として,A・C共有の土地(CはAの家族)にAの家族の共有の建物が存在し,土地の双方の持分権に抵当権が設定された場合について,法定地上権を否定した判例〈最三判平6・12・20民集48巻8号1470頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第92事件)〉について言及しておく。
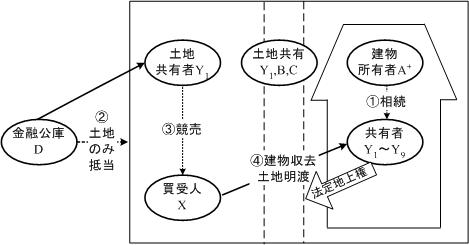 |
地上建物の共有者9人(Y1~Y9)のうちの一人である土地共有者甲(Y1)の債務を担保するため土地共有者(Y1,B,C)の全員が共同して各持分に抵当権を設定し,かつ,甲以外の土地共有者(B,C)らが甲(Y1)の妻子である場合に,右抵当権の実行により甲(Y1)だけについて民法388条本文の事由が生じたとしても,甲(Y1)以外の土地共有者ら(Y2~Y9)が法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができる客観的,外形的事実があるとはいえず,共有土地について法定地上権は成立しない。 |
| *図114 最三判平6・12・20民集48巻8号1470頁 (建物収去土地明渡請求事件) 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第92事件 |
この判例については,この事案の場合,共有者の利益は害されないのであるから,法定地上権を認めるべきであるとの批判がなされている([近江・担保物権(1992)193頁])。本書の立場においても,民法の現代語化に際して,法定地上権の要件は,当事者の意思の推測でないことが明らかとされており,法定地上権の成立要件が満たされている以上,法定地上権を認めるべきであると思われる。
抵当権と用益権との関係においては,借地借家法に基づいて,「売買による所有権の移転は賃貸を破らず」という法理が確立した後においても,抵当権設定後の賃借権は抵当権に対抗できないという法理がまかり通っている。しかし,抵当権はそもそも用益権には干渉できない権利であり,売買による所有権の移転さえ賃貸借を破ることができないのに,抵当権が賃貸借を破るというのは,奇妙である。
ここでは,抵当権と利用権の調和に関する理想を述べた我妻説を理解するとともに,その理想が解釈論としては困難とされた理由,および,その困難性を打開するにはどのような方法が考えられるのかを検討する。
以上の検討を踏まえた上で,2003年の担保法改正によって実現された一連の制度,すなわち,民法387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力),民法389条(抵当地に建物が築造され場合の土地・建物の一括競売),民法395条(短期賃貸借の廃止と「競売建物の明け渡しの猶予」)が,抵当権と利用権の調和を実現しるうものになっておらず,課題が残されていることを理解する。
従来の民法学説をリードしてきた我妻説は,抵当権と用益権との関係について,抵当権が用益権を凌駕している現実に即した解釈論を展開した後に,抵当権と用益権とのあるべき姿(理想)について,以下のような「結語」を述べている[我妻・担保物権(1968)297-298頁]。
根本に遡れば,抵当不動産をみずから用益する者が,競売によって,その用益者としての地位を覆滅されることも批判の余地のある問題である。けだし,現代における不動産所有権は,漸次,客体を物質的に利用する内容を失い,これを他人に物質的に利用させて対価を徴収する機能に転化しようとしているのであり,法律の理想も「所有」に対する「利用」の確保へと向かいつつあるときに,不動産所有権の上の抵当権が終局において不動産の「所有」と「利用」の両者を把握する結果となることは,右の法律理想を裏切るものである。
不動産所有権の上の抵当権もまたその不動産の対価徴収機能の有する交換価値だけを把握するものとなし,目的物の物質的利用権は抵当権によって破壊されないものとすることが,「所有」と「利用」の調和を図ろうとする現代法の理想を貫くものであり,また価値権と利用権との間の真の調和を図るゆえんであろうと思われる。
現行の制度をして直ちにこの理想に達せしめることは不可能であろう。しかしわれわれはここに現行法解釈の目標と理想とをおくべきである。
ところが,このような「所有」と「利用」との理想的な調和点を追求する努力は,現代の通説からは完全に消滅してしまっている。本書では,解釈論としても,このような「所有」と「利用」との調和を実現することが可能であることを示すことにする。
抵当権者と賃借人とは,共通の債務者を挟んで,ともに債権者の立場にある。抵当権者は,通常は,貸金債権者であり,賃借人は,抵当目的物の使用・収益権を有する債権者である。賃借人は,抵当目的物の維持管理に貢献しているが,抵当権者は,目的物に対して,直接的には何の貢献もしていない。したがって,債権の優先弁済権としての立場からすると,抵当権者と不動産保存の先取特権者との関係に対応する。もっとも,賃借人の賃借目的物に対する使用・収益権は,対価としての賃料債務と均衡を保っており,通常の場合は,債権として注目されることは少ない。
しかし,債務者が債務を履行できず,抵当権が実行された場合には,賃借権,特に,借地借家法によって保護される借地借家権は,大きな意味を持つ。借地借家法によって保護される賃借権は,民法605条によって保護される賃借権と同様,すべての第三者に対抗できるものであり,この場合の債務者である賃貸人から賃貸借上の地位を譲り受けるすべての人(目的物の譲受人)に対して対抗できる。このことは,賃貸目的物の売買の場合にも妥当するのであり,さらには,売買の一種である競売にも妥当すると解するのが相当である。
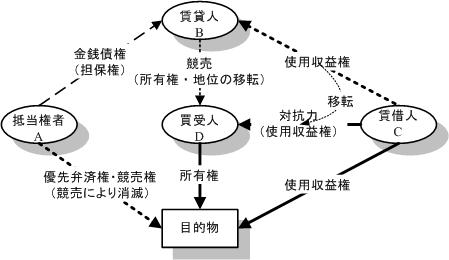 |
| *図115 抵当権と利用権との関係(その1) 対抗力を有する賃借権は,買受人に対抗できる |
確かに,現在の通説は,通常の売買の場合にはこの法理(借地・借家人の保護の法理)の適用を認めるが,競売の場合には,この法理を適用することに消極的である。なぜなら,通説は,抵当権者と賃借人との対抗関係を抵当権の登記と賃借人の対抗要件の発生の前後で判断するという,機械的な方法でしかものごとを考えることができず,先に登記した抵当権は賃借人に対抗できるため,抵当権の実行によって抵当目的物を買い受ける買受人は,利用権の負担のない完全な所有権を取得すると考えているからである。
しかし,これは,余りにも抵当権者にとって都合のよい考え方である。その理由は,競売も売買に過ぎず,買受人は,抵当目的物を原始取得するわけではなく,抵当権設定者(この場合は賃貸人)が有する所有権を承継取得しているに過ぎないという点を無視しているからである。また,抵当目的物が賃借目的物である場合には,抵当権者にとっても,賃借権の存在は当然に予期できるのであり,また,抵当権の実行による不動産競売によって買受人が得る権利は,抵当権設定者(所有者)である賃貸人の権利であり,その権利に対抗力のある賃借権が設定されている場合には,買受人はその負担をも当然に引き受けなければならない。
ところで,不動産競売が行われると,民事執行法59条により,抵当権が消滅するとともに,抵当権に対抗できない権利は,目的物の売却によって消滅するとされており,通説によると,抵当権に遅れて対抗力を得た賃借権は,抵当権に対抗できないと解されている。
しかし,抵当権と競合する他の権利との優先権の順位は,必ずしも,登記の順序によらないことは,民法339条によって明らかであり,抵当目的物の賃借人は,賃借物を善良な管理者の注意をもって保存し,その費用償還請求について留置権をも有する地位に立つ者である。したがって,抵当権者との関係では,賃借人は,民法339条にいう,不動産保存の先取特権者に類する地位を有していると解することができる。そして,民法339条にいう登記をした先取特権者に,建物の登記をした借地人をはじめとして,対抗力を有する賃借人がこれに含まれるとすれば,それらの権利者は,民法339条の類推により,抵当権者に優先する地位を有することになる。たとえ,このような解釈に無理があるとしても,抵当権者は,抵当権設定者の使用・収益権を奪うことができないのであるから,抵当権者は,対抗力を有する使用・収益権に対しては,対抗できないと解することが可能であろう。
このように考えると,もともと,抵当権者は,対抗力を有する賃借権には対抗できないのであり,たとえ,対抗できるとしても,不動産の保存を行っている賃借人には優先権を有しないと解すべきである。その結果,抵当権設定者に対抗できる権利を有する賃借人は,抵当権者にも,また,買受人にも対抗できるのであり,民事執行法59条2項の規定によっても,賃借権は,たとえ,抵当権の設定登記に遅れて対抗力を取得した場合でも,抵当権の実行によっても消滅しないと解することができることになる。
対抗力を有する賃借権は,先に登記をした抵当権にも対抗できるとすると,賃借権が抵当権の執行妨害を助長するのではないのかとの疑問が生じるかもしれない。取得時効の制度が盗人に悪用されたり,消滅時効の制度が借金の踏み倒しに利用されたりするのと同様に,すべての制度が,濫用の危険と隣り合わせに存在しているのであり,濫用の防止を検討しておくことは,これまでにも,抵当権に対抗できる短期賃貸借が抵当権の執行妨害の手段として悪用されてきたことから考えても,重要な課題となる。
抵当権の実行を妨害する目的でなされる詐害的な賃貸借には,一般に次のような特色が見られるとされている[田髙・物権法(2008)240頁]。
2003(平成15)年の担保法・執行法改正により,濫用が目に余るとして短期賃貸借の制度[民法旧395条]が廃止されたのは,正当であった。抵当権の実行によって保護されるべきは,詐害的な短期賃貸借ではなく,借地借家法によって保護される正常な長期賃貸借だったからである(短期賃貸借の制度については,([内田・抵当権と利用権(1983)]21頁以下,吉田克己「民法395条」[広中=星野・百年Ⅱ(1998)691頁以下]参照)。
しかし,短期賃貸借の規定には,その濫用を防止するためのただし書きとして,「其賃貸借〔短期賃貸借〕が抵当権者に損害を及ぼすときは,裁判所は,抵当権者の請求に因り,其解除を命ずることを得」という濫用防止の手段も用意されていた。そして,民法旧395条がただし書きを含めて,すべて削除されたため,抵当権者は,濫用的賃貸借に対して,効果的な手段を失った状態にある。
したがって,本書が提唱するように,対抗力を有するすべての賃借権が抵当権に対抗できるということになると,濫用的賃借権に対しても,抵当権者は,全く無防備な状態にあるということになる。民法を改正するのであれば,本来は,フランス法と同様,抵当権登記後の賃貸借も,買受人が現れるまでになされたものは,原則として買受人に承継され(売買は賃貸借を破らず),例外的に,詐害的な賃貸借を消滅させる(民法旧395条における抵当権者の権利の存続)という戦略をとるべきであった。短期賃貸借の制度を廃止することに気をとられる余り,抵当権者にとって大切な権利(濫用的な賃貸借に対する解除権)まで捨ててしまったのは,「肉を切らせて骨を断つ」つもりで,「角を矯めて牛を殺す」という事態を招いているのであり,皮肉な結果といえよう。
そこで,抵当権者のために,短期賃貸借の場合の濫用を防止することができたのと同様に,対抗力のある賃貸借が濫用された場合にも,それに対抗できる権利を抵当権者に与える必要が生じている。
もっとも,短期賃貸借の弊害であった執行妨害に対しては,民事執行法によっても,以下のように,適切な対応がなされるようになってきている。
しかし,これらの執行法の規定の裏づけとなる実体法上の根拠について,理論的な考察を行うことが重要である。判例は,抵当権に基づく濫用的な賃借権の排除の法理を,債権者代位権によって構成したり〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉,直接に抵当権に基づく物権的請求権として構成している〈最一判平17・3・10民集59巻2号356頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第88事件)〉。しかし,抵当権妨害に対するこれらの実体法上の理論構成は,成功しているとはいえない。なぜなら,第1に,最高裁が抵当権者の被担保債権として構成している「担保価値維持請求権」は物権的請求権であるとされるが,物権的請求権を保全するために債権者代位権を利用するというのは奇妙である。物権的請求権は,相手方に対する直接の請求権でなければならないはずだからである。第2に,抵当権が物権だから,妨害排除請求権や返還請求権という物権的請求権を有するというのも説得的とはいえない。物権であっても,占有権を有しない先取特権に妨害排除請求権,返還請求権を認めることはできないのであって,非占有担保権とされる抵当権についても,同様のことがいえるはずだからである。
平成11年最高裁大法廷判決〈最大判平11・11・24民集53巻8号1899頁〉で提唱された抵当権者の有する担保目的物の維持・保存という概念を違った方向で活用することを考えてみよう。抵当権者Aは,質権とは異なり,抵当権設定者Bから目的物の使用・収益権を奪うことはできない。しかし,Aは,担保権者として,Bに対して,担保目的物を「適切に維持又は保存するよう求める請求権」を有すると考えられる。また,抵当権設定者としての賃貸人Bは,賃借人Cに対して,用法に従った使用・収益をするよう求めることができる。AのBに対する権利(α債権)とBのCに対する権利(β債権)とは,互いに密接な関係にあるため,AはCに対して,債権者代位権の転用として,用法に従った使用・収益を請求することができる。そして,Cが用法に従った使用・収益をしない場合には,Bに代わって損害賠償を請求できるだけでなく,賃貸者の解除をすることもできると解すべきであろう(抵当権者のための詐害的な賃貸借の解除の法理=民法旧395条の抵当権者のための部分的復活)。
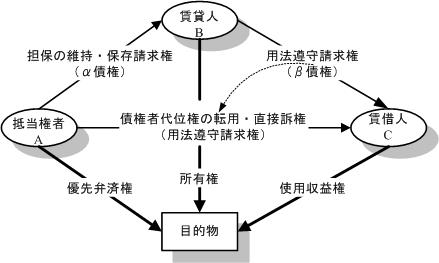 |
| *図116 抵当権と利用権との関係(その2) 抵当権者は賃借人に対して賃貸人の有する同種の権利を転用できる |
また,BC間の賃貸借契約が,借地借家法に基づく賃貸借とは認められない場合,たとえば,一時使用の賃貸借であるとか,賃料が異常に低いなど,使用貸借と同様に扱うのが相当と認められる場合等,借地借家法による対抗力を得るだけの目的で賃貸借契約を締結した場合には,そのような賃貸借は,第三者に対抗できない賃貸借であり,抵当権者および買受人に対しても対抗できないと解することができる([民事執行法83条1項本文]参照)。
抵当権の実行に関して,実体法と手続法との関係を明らかにしているのは,民事執行法188条によって準用される民事執行法59条(売却に伴う権利の消滅等)である。抵当権の消滅の箇所で詳しく論じるが,民事執行法59条1項は,抵当権が実行されると,担保不動産の値下がり等の原因により,たとえ,被担保債権の完全な回収ができない場合であっても,抵当権は消滅することを明らかにしている。それとともに,民事執行法59条2項は,担保権の実行によって「消滅する権利を有する者,差押債権者又は仮差押債権者に対抗することができない不動産に係る権利の取得は,売却によりその効力を失う」と規定している。
たとえ,民法605条による賃借権の登記または借地借家法10条,31条に基づく対抗要件を備えていたとしても,賃借権は,先に登記された抵当権に劣後するのだとしよう。そうだとすると,これは,「地震売買」という悪夢の復活に他ならない。なぜなら,民法の特別法である建物保護に関する法(1909年),借家法(1921年),そして,それらを統合した借地借家法(1991年)によって克服されたはずの「売買は賃貸借を破る(地震売買)」という悪名高い原理が,売買の一つに過ぎない競売を通じて復活することになってしまうからである。つまり,民事執行法59条2項の解釈次第で,賃借人の保護のために民法学者たちの長年の努力の結晶として確立された「売買は賃貸借を破らず(地震売買の回避)」という原則が踏みにじられる危険性がある。
このように考えると,民事執行法59条2項は,実体法と手続法とを架橋する重要な条文であることがわかる。そして,実体法に関する通説・判例に従ってこの民事執行法59条2項を解釈すると,上記のおそれが実現されてしまうことに気づく。なぜなら,抵当権登記に遅れて成立した賃借権は,たとえ,民法および借地借家法によって対抗力を有するものであったとしても,抵当権の実行によって消滅してしまうからである。現に,民事執行の実務においては,そのことを前提として,抵当権の登記に遅れて成立した賃借権は,抵当権の実行によって消滅するとされ,借地上の建物は取り壊され,借家人は,買受人によって借家から追い出されている。
しかし,対抗力を有する賃借権が,先に登記された抵当権の実行によって覆されるという考え方は,対抗力のある権利が衝突した場合に,それぞれの権利の性質や保護の必要性を無視し,単に,「先に対抗要件を備えた方が優先する」という例外の多い原則を安易に適用したことによって生じたものに過ぎない。この考え方は,抵当権の対抗力の理解(典型例は,民法339条の場合であり,先に登記された抵当権でも,後に登記された先取特権に劣後することがあることは,明文上も明らかである)において誤っており,具体的妥当性の点でも,債権の優先弁済権に過ぎない抵当権によって,対抗力のある賃借権を覆滅し,賃借人の居住権を奪うという不条理なものである。したがって,民事執行法59条2項の解釈は根本的な見直しが必要であるというのが,本書の基本的な立場である。
しかし,このような考え方は,通説・判例と真っ向から対立するものであるので,その理由を詳しく述べる必要がある。両者ともに対抗力を有する抵当権と賃借権が衝突した場合に,どちらを優先すべきかという問題について,登記の先後に関係なく,第三者に対して対抗力を有する賃借権が優先するという理由は,以下の通りである。
第1の理由は,一般論としても,対抗力が対立する場合に,対抗要件の取得の時間の先後は,必ずしも対立する権利の優劣を決定する決め手とはならない。特に,「先に登記した抵当権が,後に対抗力を得た権利に優先する」という単純な議論は,民法339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)によっても覆されている。さらには,最高裁の最近の判例〈最一判平14・3・28民集56巻3号689頁〉によっても,抵当権に基づく賃料債権への物上代位の権利は,たとえ抵当権の設定登記が先になされていたとしても,賃借人の有する敷金との相殺権(敷金への充当権)に劣後することが明らかにされている。したがって,「先に登記された抵当権が,後に対抗力を有した賃借権に基づく権利に常に優先する」という考え方は,例外を無視した乱暴な議論であって,必ずしも常に成り立つものではないことを理解しなければならない。
確かに,民事執行法59条2項は,通説によれば,「抵当権等の担保権設定の登記に遅れるものは,売却によって抵当権等が消滅するとともに消滅する」[中野・民事執行概説(2006)149頁]と解されている。なぜなら,登記を有する抵当権と,対抗力を有する賃借権(登記された賃借権[民法605条],建物が登記された借地権[借地借家法10条]または引渡しを受けた借家権[借地借家法31条]とを比較した場合,どちらが優先するかは,通説においては,対抗要件の具備の時間的な先後という単純な基準で優劣が決すると考えられているからである。
しかし,抵当権と他の権利とが衝突する場合に,必ずしも登記の先後だけで優先関係が決まるわけでないことは,すでに述べたように,民法339条を見れば明らかである。民法339条は,抵当権が先に登記されていたとしても,後に登記がなされた不動産保存の先取特権は抵当権に優先する旨を規定している。このように,優先弁済権の優先順位は,必ずしも,登記の先後には依存しない。そして,先に登記した抵当権が,後に登記した不動産保存の先取特権に劣後する理由は,担保目的物の価値の維持または価値の増加に寄与した者は他の債権者よりも優遇されるべきであり,しかも,担保目的物の保存に寄与した者の場合には,直近の保存者(後の保存者)こそが保護されるべきであるという考慮に基づいている。この考え方は,民法330条1項2文ににおいて,「後の保存者が先の保存者に優先する」として明文化されており,民法339条が,後に登記された場合であっても,不動産保存の先取特権を先に登記された抵当権に優先させているのも,もとをたどれば,民法330条1項2文によって具体化された優先順位に関する原則に則ったものと考えることができるのである。
このように考えると,担保不動産を占有し,居住者として,善管注意義務に基づいて不動産の価値の維持に貢献している賃借人の権利は,目的不動産の維持・管理に全く関与せず,担保権を実行して,そこから優先弁済権を得るだけの抵当権よりも優先されてしかるべきである。
そうだからこそ,賃借人の賃料債務に対して抵当権者が物上代位に基づいて請求を行った場合に,賃借人が,敷金返還請求権に基づいて賃料債務との相殺を主張した場合に,最高裁は,賃借人の敷金返還請求権に基づく賃料債務との相殺の権利(充当の権利)が,先に登記をした抵当権者の物上代位に基づく権利に優先することを明らかにしているのである〈最一判平14・3・28民集56巻3号689頁〉。
もっとも,賃料債権に対する抵当権者の物上代位による差押えと当該債権への敷金の相殺とが問題となった事件について,最高裁は,当初は,以下のように判示して,登記を先に得ている抵当権者には,賃借人は対抗できないとしていた〈最三判平13・3・13民集55巻2号363頁〉。
最三判平13・3・13民集55巻2号363頁
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。
しかし,その後,最高裁は,実質的に判例を変更し,以下のように,賃借人の敷金返還請求権に基づく相殺の権利を敷金の充当として再構成することによって,賃借人の権利が,先に登記をした抵当権者の権利に優先することを明らかにするに至ったのである〈最一判平14・3・28民集56巻3号689頁〉。
最一判平14・3・28民集56巻3号689頁
敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。
このように考えると,先に登記した抵当権といえども,常に,賃借人の権利に優先するとはいえないことが明らかである。民法の特別法である借地借家法により,すべての人に建物に関する賃借権(居住権)を対抗できるとして保護されている賃借人に対して,登記を先に得たからという理由だけで,抵当権が賃借人の権利を覆滅できると考えるのは,幻想に過ぎないのであり,借地借家法を無視した議論といわざるを得ない。
第2の理由は,第1の理由と密接に関連するものであるが,抵当権者は,抵当権設定者の使用・収益権を奪うことはできないのであり,抵当不動産の価値を判断する場合に,抵当権設定者が,新たに用益権を設定することを予想すべきだからである。
たとえ,抵当権の設定後に,抵当不動産に用益権が設定されるという事態が発生したとしても,それは,抵当権者が予見すべき想定内の事態であり,そのような事態を含めて,不動産の価値を評価すべきである。つまり,抵当不動産について,抵当権の設定登記の後に賃借権が設定され,そのことによって競売代金が低く見積もられることになったとしても,それは,抵当権設定者の使用・収益権を奪うことができない抵当権者として,当然に甘受しなければならない問題である。なぜなら,この問題は,不況等の理由で不動産価格が下落し,それによって抵当不動産の価値が減少したとしても,それは,抵当権者として予期すべきであって,甘受せざるを得ないのと同じである。このように考えると,抵当権登記に遅れて対抗力を得た賃借権に抵当権が対抗できない結果,抵当権者が不測の損害を被ったとしても,抵当権者はそれを甘受しなければならない。
第3の理由は,抵当権の実行によって買受人が取得できる権利(所有権)は,抵当権者ではなく,抵当権設定者(所有者)に由来するものであり,所有者である抵当権設定者に対抗できる権利を有する賃借人は,買受人に対しても対抗力を有すると考えるべきだからである。
先にも述べたように,抵当権の対抗力は,優先弁済権に過ぎない。抵当権は,抵当権設定者の使用・収益権を奪うことはできないのであり,抵当権を実行しても,その効力は,目的不動産の売却金から他の債権者に先立って債権の弁済を受けることができれば,それで満足すべきものに過ぎず,抵当不動産の利用権に影響を与える力を有しないと解さなければならない。
抵当権者は,債務者が債務不履行に陥った場合には,確かに,抵当不動産を売却する権利を有する。しかし,売却は,抵当権設定者の権利を買受人へと移転させる権限を有するに過ぎない。買受人が譲り受けるのは,抵当権設定者の権利(債務者または物上保証人の有する所有権)であり,したがって,買受人は,抵当権設定者の有する権利以上の権利を取得できるものではない(動産と異なり,実体法上は,不動産の物権変動には公信力は認められていない(民法568条))。したがって,抵当権設定者に対抗できる賃借権を有する賃借人([民法605条]に基づく賃借人ばかりでなく,[借地借家法10条または31条]に基づいて対抗力を有している賃借人)は,抵当目的物の買受人に対しても賃借権を対抗できると解さなければならない。
通説は,先に述べたように,抵当権者は抵当権登記に遅れて対抗要件を得た賃借人に対抗できるのであるから,抵当権の実行によって権利を取得した買受人も賃借人に対抗できるという理論を展開している。しかし,買受人は誰の権利を取得するのか,という観点での考察を怠っており,買受人が賃借人に対抗できるという結論を正当化するには至っていない。
これに対して,上記のような本書の考え方によれば,借地上の建物に抵当権が設定されて,建物が競売された場合には,借地人の交代を歓迎しない借地権者の側から,建物の買受人に対してなされるおそれのある建物収去土地明渡請求から買受人を保護することにもなる。なぜなら,建物所有者は,建物の登記によって借地権の第三者対抗力を獲得する[借地法10条]。したがって,建物の競売によって建物を買い受け,建物の移転登記を取得した買受人は,抵当権設定者の有していた借地権(従たる権利と解されている)を承継し,その借地権をもって,土地の賃貸人に対抗できることになるからである。この結論は,判例〈最三判昭40・5・4民集19巻4号811頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第85事件)〉によっても是認されている。
第4の理由は,第3の理由と密接に関連するが,不動産の買受人は,民事執行法54条による現況調査,62条による物件明細書の備置等によって,不動産の現況を知ることができるのであり,借地権者の存在を前もって知りうる状況にある。したがって,賃借権が買受人に対抗できるとしても,買受人に不測の損害を与えることはないからである。
以上のように考えると,実体法の解釈としては,民法または借地借家法に基づいて第三者に対抗できる賃借権は,抵当権の設定後に成立したものを含めて,抵当権に対抗できると考えるべきであり,民事執行法59条2項の解釈としても,対抗力のある賃借権は,担保権に「対抗することができない権利」には該当しないと解すべきであろう。
上記のような本書の立場に立つまでもなく,実体法の解釈としては,競売によって賃借権が消滅するかどうかの問題は,抵当権者を含む債権者と賃借人との間の優劣の問題として考えるべきではなく,あくまで,所有権を有する債務者(執行債務者)と不動産に係る権利の主体(賃借人等)との間の対抗問題として考えるべきであった。したがって,民事執行法59条2項は,「前項の規定により消滅する権利を有する者,…に対抗することができない不動産に係る権利の取得は売却によりその効力を失う」ではなく,売買の原則に立ち返り,「不動産の所有者または不動産の買受人に対抗することができない不動産に係る権利の取得は,売却によりその効力を失う」と規定すべきであったのである(しかし,それは,立法論であって,解釈論とはいえないので,これ以上は立ち入らない)。
そこで,民事執行法59条2項は,先に述べたように,民法,または借地借家法に基づいて第三者に対抗することのできる賃借権は,担保権に「対抗することができない権利」には該当しないと解し,買受人に対しても賃借権をもって対抗できると解すべきことになる。
以上のような考察を行うことによって,初めて,2003年の民法改正によって新設された民法387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)がいかに無意味な規定であり,無用の長物であるかが明らかとなる。そのことを次に論じることにする。
現行民法387条は,現行民法としては異例の条文である。なぜなら,この条文は,民法における体系上の位置づけが不明なばかりでなく,賃借人の保護という要請とも無関係に規定された,現行民法の中でも最も拙劣で,無益・無意味な条文だからである。
民法の最近の注釈書[我妻,有泉・コンメンタール(2008)606-607頁]によれば,2003年改正は,全体として,抵当不動産の収益価値を重視しており,抵当権の効力を収益価値に及ばせることに力点をおいているが,他方で,不動産用益権の尊重に配慮しているとして,現行民法387条に対して,好意的な評価を下している。その理由は以下の通りである。
抵当権の設定登記に遅れて設定され,これに対抗できない賃借権は,いつ抵当権の実行によりくつがえされるかわからないというのでは,目的不動産の安定した利用収益を図ることができない。一方で,民法旧395条が定めていた短期賃貸借の保護が廃止されたことに対応して,抵当権に対抗できない賃借権に対抗力を備える道を,抵当権者の同意を要件として開いたのが本条である。
本条は,抵当権者の同意がある場合にのみ適用されるので,賃借権者にとってとくに強い手段が認められたわけではない(その点,§378条の代価弁済に類似している)。しかし,このような道が制度化されたことの意義は大きい。たとえば,法定地上権において土地と同一所有者に属していた建物が他者に譲渡され,その者が土地の賃借権を取得した場合についての,388条の拡大解釈を図る努力は,本条によりその建物所有者=賃借権者が土地抵当権に対する対抗力を備えたときは必要のないものとなる。すなわち,本条は,土地とその上の建物が別個の不動産とされることによる矛盾の解決の一助にもなるのである。
しかし,民法387条は,このような楽観的な評価に値しないと思われる。その理由は以下の通りである。
第1は,民法387条の適用範囲が,「登記をした賃貸借」に限定されていることにある。登記をした賃貸借とは民法605条の賃貸借のことであるが,賃貸借の登記は,賃貸人の協力が必要であるため,賃借権自体が登記されることは稀であり,登記された賃貸借は,むしろ,抵当権を妨害する目的(執行妨害)でなされることが多いというのが,従来の考え方であった。そのようなわけで,民法605条による登記をした賃貸借だけを保護していたのでは,通常の賃借人を保護することができない。そうだからこそ,建物保護法に関する法律1条(現行では[借地借家法10条])は,単独では実現不能な賃貸借の登記ではなく,賃借人が単独で登記が可能な賃借人が所有する建物の所有権登記だけで,賃貸借の登記がなされたのと同じ効力を与えたのである。また,建物の引渡しを受けた借家人のために,引渡しがあれば登記は必要ないとして,借家法1条(現行では[借地借家法31条])によって借家人を保護することになったのである。このように考えると,民法387条が,借地借家法を無視して,「登記した賃貸借」だけに保護を与えるとしたことは,時代の流れに逆行するものであり,借地借家法によって保護されている賃借人に対する「嫌がらせ」としか言いようのない愚挙である。
第2は,登記をした賃借権は,たとえ目的物が第三者に譲渡された場合でも,すべての第三者に対抗することができるのであり,このことは,競売による買受人に対しても,当然に対抗できると考えるべきであることは,すでに述べたとおりである。買受人を含めたすべての第三者に対抗できる賃借権について,抵当権者の同意など,とる必要もない。抵当権は,債権を回収するために,債務不履行になった際にはじめて,抵当不動産の競売を申立て,競売代金の中から優先弁済権を得ることができる権利に過ぎないのであって,債務不履行に陥っていない間は,抵当権者は,抵当権設定者の用益には関与できない。したがって,第三者に対抗できる賃借権を有する賃借人は,買受人に対抗する前提として,抵当権者の承諾を得る必要は全くない。それにもかかわらず,2003年の改正によって創設された民法387条は,賃借人が抵当権者に対抗する要件として,賃借人に対して,借地借家法の対抗力[借地借家法10条,31条]ではなく,通常は行われることのない賃借権の登記([民法605条],[不動産登記法3条8号])を必要としている。その上,用益に関して何の権限も有しない抵当権者の承諾を要求し,さらに,抵当権者の1人でも同意しない者があるときは,本条の適用がなく,同意の登記も受理されないとしている。これは,借地法によって第三者に対抗できる権利を有する賃借人(借地・借家人)に対する「嫌がらせ」以外の何ものでもない。
民法387条は,このままであれば,無用の長物として削除されべきであるし,もしも,存続させるのであれば,少なくとも,以下のように改正する必要がある。
第387条 改正試案(抵当権に対する賃貸借の対抗力)
登記をした賃借権または借地借家法10条もしくは31条によって,第三者に対抗できる賃借権は,その対抗要件を備える前に登記をした抵当権および買受人等を含めて,抵当権の実行に伴った権利を有するすべての第三者に対抗することができる。
抵当権の実行に伴う賃借権の保護については,先に述べたように,抵当権設定後に成立した賃借権であっても,第三者対抗要件を有する場合には抵当権にも対抗できるのであり,結果として,抵当権の実行によって出現する買受人に対しても対抗できることが明らかとなった。
さらに,抵当権設定後に生じる賃借人ではなく,抵当権設定後に土地と建物とが別人に帰属する事態が生じた場合には,建物を保護するために,建物のために土地利用権(法定地上権または法定借地権)を発生させる必要がある。これが法定地上権[民法388条]および法定借地権[仮登記担保法10条]の問題であり,法定地上権については,すでに述べたところであり,法定借地権については,後に仮登記担保法の箇所で論じることにする。
ここで論じるのは,通説によって,仮に,法定地上権の成立が否定されると仮定した場合の問題である。
抵当権の実行によって,土地と建物とが別の所有者に帰属する場合には,通常は法定地上権が成立するのであり,本書の立場は,すでに述べたように,あらゆるタイプの場合にも法定地上権が成立することを明らかにしている。
ところが,通説・判例は,土地と所有者とが別人に帰属した場合に,建物を保護するよりも,抵当権および土地買受人を保護する方向に傾斜しており,民法388条の要件が具備されない場合を想定した上で,建物を保護する必要が生じると考えている。特に,土地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合には,通説・判例によると,民法388条の要件が満たされていないとして法定地上権の成立を否定しているため,建物が保護されないことになりかねない。そこで,法定地上権を否定しつつも,抵当権の実行から建物を保護するための何らかの措置が考えられないかが問題となるのである。
民法389条の抵当地の建物の競売(一括競売)は,この問題に関連して,土地について抵当権が設定された後,抵当地に土地所有者自身が築造した場合(2003年改正前の旧389条は,土地所有者自身が抵当権設定後に築造した建物だけが対象とされていた)または第三者が築造した建物であっても,建物のための土地利用権が土地抵当権者に対抗できない場合に,土地抵当権者は,土地だけでなく,建物を土地とともに一括して競売することができると規定している。
抵当土地に築造された建物については,土地だけが競売された場合には,通説・判例によると,建物のために法定地上権が成立することはないとされる。したがって,この規定が,土地抵当権者に,土地だけでなく,その上にある建物まで競売する権限を与えたことは,もしも,土地と建物とが同一人によって買い受けられるならば,建物は保護されることになるという意味で評価されている。
しかし,土地と建物を一括競売したところで,土地と建物が別人によって買い受けられた場合には,民法389条は何の役にも立たない。民法389条は,土地抵当権者の権利ではなく,土地と建物とが別人に帰属することになった際の矛盾を解決するために,土地抵当権者の「一括競売の義務」を定めたものであるとの説も存在するが(松本恒雄「抵当権と利用権の調整についての一考察(1)」民商80巻3号(1979)313-315頁),土地と建物とが別人によって買い受けられた場合には,結局,問題の解決ともならない。
そもそも,民法389条が規定された趣旨は,土地に抵当権が設定された後に,抵当土地に建物が築造されると,その建物が存在するために容易に買受人が現れないという場合に備えて,土地抵当権者に,抵当権の効力の及ばないはずの建物についても,土地とともに競売する特別の権利(一括競売権)を認め,抵当権の実行を容易にすることにあった[民法理由書(1987)379頁]。
このように,抵当権者の利益を優先するという考えを貫くのであれば,抵当権者に一括競売を義務づけることは,抵当権者に大きな負担を課すことになって立法の趣旨にそぐわないばかりでなく,土地と建物とが同一人によって買い受けられるという保障もない以上は,土地とその上の建物が別個の所有者に帰属する場合の建物の保護という機能も果たしえないことになる。
結局のところ,民法389条は,抵当権者の利益だけを考慮して起草された条文であり,建物の保護という観点からは不十分な規定である。問題の解決は,先に論じたように(→*第16章第7節B(b)民法388条の要件の構造化(民法388条の要件の再構成)参照),建物の保護のために,できる限り法定地上権の成立を認める方向で解釈を展開すべきであろう。このようにして,土地について抵当権が設定された後に建物が築造された場合でも,法定地上権の成立を認めるという本書の立場によれば,民法389条2項で明らかにされているように,抵当土地とともに,抵当権の及ばないはずの建物にまで抵当権者に売却させる権限を与える必要はないのであり,一括競売の規定は不要であるということになる。
もしも,民法389条を残すのであれば,抵当権の実行から建物の保護を実現するという観点に徹する規定へと修正すべきであり,したがって,民法389条は,以下のように改正されるべきであろう。
第389条 改正試案(抵当地の上の建物の一括競売)
①抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときにおいて,その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有しない場合は,抵当権者は,土地とともにその建物を競売しなければならならない。その場合には,一括競売された不動産は,同一の買受人に買い受けさせるものとする。
②前項の場合には,土地抵当権者の優先権は,土地の代価についてのみ行使することができる。
2003年の民法担保法の改正以前の民法旧395条は,短期賃貸借を保護するために,以下のように規定していた(カタカナをひらがなに改め,濁点と句読点を補っている)。
旧第395条〔短期賃借権の保護〕
第602条に定めたる期間を超えざる賃貸借は,抵当権の登記後に登記したるものと雖も,之を以て抵当権者に対抗することを得。但,其賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは,裁判所は,抵当権者の請求に因り,其解除を命ずることを得。
借地法や借家法が制定される以前の民法においては,賃貸借が登記されることはほとんどなく,また,賃貸借の登記に代わる対抗要件の制度も存在しなかった。したがって,「売買は賃貸借を破る(地震売買)」という原理が通用していた。このため,抵当権の設定によっても設定者は抵当不動産を他者に賃貸することは自由であるが,抵当権が実行されるとその賃貸借はくつがえされると考えられてきた(現在の通説・判例も同様に解している)。このような時代にあって,賃借人の不安な状況を少しでも改善するため,山林については10年以内,それ以外の土地については5年以内,建物については3年以内に限り(民法602条の短期賃貸借),抵当権の実行によってもくつがえされない,すなわち,抵当権者および競落人(買受人)にも対抗できる賃借権の設定を可能にしたのが,短期賃貸借の制度である[民法旧395条]。
しかし,現実には,この制度がその本来の制度趣旨に沿って利用されることは少なく,むしろ,この制度は濫用され,実際には不動産を利用しないのに,抵当権を害することを目的とした詐害的な短期賃貸借が目立つようになった。
借地法等の特別法によって,正常な賃貸借は,長期型へと移行したのであるから,保護すべきなのは,短期賃貸借ではなく,建物保護法1条や借家法1条によって対抗力を具備された長期の賃貸借(借地借家)であった。それにもかかわらず,民法の抵当権の規定は,このような特別法の趣旨を踏まえた上での適切な修正がなされなかった。そのため,民法は,借地借家法制から見れば,明らかに脱法的な短期賃貸借だけを保護し,保護すべき長期賃貸借の保護を放置するものとなってしまったのである。しかも,通説および判例は,抵当権の設定後に成立した正常な長期賃貸借を保護する解釈方法を探究することを怠っていたため,正常とはいえない短期賃貸借を保護することになり,短期賃貸借は,ますます濫用の方向へと進んでいった。
2003年の民法改正により,短期賃貸借保護の制度は廃止され,これに代わる賃借人の保護制度として,建物の賃貸借についてのみ,抵当権が実行された後の買受人に対する関係で,引渡しの猶予を認める制度が創設された[民法395条]。その結果として,賃借人の保護は,正常な賃貸借の場合も,土地については5年の保護もなくなり,建物については3年の保護がわずか6ヶ月の引渡し猶予へと大きく後退したことになる。
現行民法が,濫用目的に利用されることが多かった短期賃貸借の制度を廃止したことは,正当である。しかし,真に保護すべきは,借地借家法によって第三者に対抗できることが認められている長期賃貸借である。先に述べたように,このような正常な賃貸借については,現行民法395条によっても,その保護がなくなったと考える必要はない。なぜなら,民法395条が認めている引渡し猶予期間は,賃借人の保護というには余りにお粗末なものであり,このような中途半端なものであれば,ほとんどなくても同じである。借地借家法によって保護されている賃借権については,本書の解釈(「抵当権は,後に成立した対抗力を有する賃貸借を破らず」)によれば,さらに大きな保護が約束されることになる。
現行民法395条は,単に,「抵当権者に対抗することができない賃貸借」についてわずかな保護を実現しているに過ぎない。しかし,本書の立場からすれば,すでに述べたように,抵当権の登記に遅れて成立した賃借権であっても,民法605条,借地借家法10条または31条によって第三者に対抗できる賃借権は,抵当権設定者の使用・収益権を害することができない抵当権者に対しても,また,賃貸人の地位を引き継いだに過ぎない買受人に対しても,賃借権をもって抵抗できる(「売買(競売)は賃貸借を破らず」)のであるから,旧395条と同様,現行民法395条も不要である。むしろ,本書で展開した解釈によってのみ,抵当権設定者の使用・収益権を害することなく,目的不動産から優先弁済権を得ることのできる抵当権と,民法および借地借家法によって,居住権として保護され,第三者に対抗できる賃借権との調和が図られるのである。
抵当権の消滅原因を突き詰めていくと,抵当権の性質,すなわち,物権ではなく,債権の掴取力の強化としての優先弁済権に過ぎないことがよく理解できる。なぜなら,物権の消滅原因とされる目的物の滅失によっても,抵当権は消滅せず,物上代位権として存続するからである。抵当権は,混同によって消滅するが,それは,物権だからではなく,債権も,混同によって消滅するからである。
物的担保に共通の消滅原因とされる付従性による消滅は,抵当権が,債権の消滅に従属するものであることを示しており,抵当権の実行による消滅も,競売代金から優先弁済を受けたことによる優先弁済権の満足による消滅であって,債権に従属することを示していることが理解できる。
抵当権に特有の消滅原因とされる代価弁済も,抵当権の消滅請求権の行使による消滅も,抵当権の実行による消滅と同様,抵当目的物の価格に相応する代価の弁済によって消滅するものであり,債権に従属する性質を示している。抵当目的物が時効取得された場合の抵当権の消滅についても,もしも,物権の混同によると理解するならば,債務者や物上保証人による抵当目的物の時効取得の場合にも,抵当権が消滅するはずである。しかし,民法397条の反対解釈によって,その場合には抵当権は消滅しないのであるから,ここでも,抵当権における別個の物権性なるものが否定されることになることを理解することができる。
旧民法(債権担保編)292条は,抵当権の消滅原因として,①債務の消滅,②債権者の抵当の放棄,③時効,④滌除(現行民法における抵当権消滅請求),⑤競落,⑥抵当不動産の滅失(ただし物上代位に転化),⑦公用徴収という,7つの原因を列挙していた。現行民法の立法者は,これらの消滅原因は,「皆当然謂ふを待たざる所」であるとして,この規定を削除した。確かに,立法のあり方としては,現行民法369条~398条のように,抵当権に特有の消滅原因を列挙すれば,それで足るのであろう。しかし,体系的な理解を望むのであれば,以下に述べるように,抵当権の消滅原因を分類・整理して,理解しておく必要がある。
従来の教科書では,抵当権の消滅に関して,担保権の実行を組み込んだ体系的な整理はされていない。この点で,本節は,本書の特色の1つとなっている。
抵当権は,第1に,担保権に共通の消滅原因(2つ),すなわち,①被担保債権の消滅(付従性)によって,または,債務者から使用・収益権を奪わないタイプの②担保権の実行[民事執行法59条1項]によって消滅する。第2に,抵当権に特有の消滅原因(4つ),すなわち,③代価弁済[民法378条],④抵当権消滅請求[民法379~386条],⑤抵当権の消滅時効[民法396条の反対解釈]または⑥抵当不動産の時効取得[民法397条]によって消滅する。
第1の担保権に共通の消滅原因のうち,①被担保債権の消滅(付従性)による消滅については,担保物権の通有性としてすでに説明しているので,ここでは省略する。②担保権の実行の場合,抵当権者は売却代金等から満足を受けることになるが,売却代金が債権額に満たない場合,すなわち,不足分の債権が存続するにもかかわらず,抵当権は消滅する。被担保債権が一部消滅していないのに,抵当権だけが消滅することになり,被担保債権は担保権のない一般債権として存続することになるのであるから,被担保債権の消滅によって担保権もそれに付随して消滅する①の場合とは区別しなければならない。
第2の抵当権に特有の消滅原因のうち,③代価弁済および④抵当権の消滅請求は,第1の消滅原因の中の②担保物権の実行の場合と同様に,被担保債権が完全には満足されないにもかかわらず,抵当権だけが消滅する場合である。つまり,担保権の実行の場合と同様,代価弁済,抵当権の消滅請求によって第三取得者の支払う金額によって被担保債権が満足されない部分の被担保債権は,担保権のない一般債権として存続することになる。
このうち③代価弁済[民法378条]は,債務者の資力が十分でなく(不良債権),第三者に渡った抵当不動産の価格も値下りして,抵当権者が競売しても被担保債権全額の満足が得られないという場合に,抵当権者の方から第三取得者に対して,不動産の売却代金(被担保債権額よりも低額でよい)を請求し,第三取得者がこれに応じてその金額を支払えば,抵当権を消滅させ,第三取得者に負担のない所有権の取得を認めるという制度であり,不動産価格が値下りした場合の不良債権の回収方法として一定の意義を有する。
これに対して,④抵当権消滅請求[民法379~386条]は,上記のような状況であるにもかかわらず,抵当権者が抵当不動産の値上りを期待して,代価弁済を要求しない場合に,抵当不動産の第三取得者の方から,不動産の価額を支払うことによって抵当権を消滅させることを請求できる制度である。
両者は,被担保債権の完全な満足を得ない場合であっても,抵当不動産の価額に相当する金額が弁済されることによって,抵当権を消滅させる制度である点で共通している。両者の違いは,③代価弁済が,抵当権者から第三取得者へと請求するものであるのに対して,④抵当権消滅請求は,反対に,第三取得者から抵当権者へと請求する点にあるに過ぎない。③代価弁済を基本に考えると,④抵当権消滅請求は,対抗・代価弁済ということが可能である。
最後の⑤抵当権の消滅時効または⑥抵当不動産の時効取得は,債権の満足が全く得られないままに抵当権だけが消滅する点で特色を有する。すなわち,この場合には,被担保債権は,それが他の原因で消滅しない限り,一般債権として存続する。
以上の抵当権の消滅原因を表にまとめると以下のようになる。
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ担保物権に 共通の 消滅原因 |
A. 被担保債権の消滅に付従して抵当権が消滅するもの (担保物権の通有性のうちの付従性に基づく効果) |
①被担保債権の消滅 (弁済,相殺,更改,混同, 免除,放棄,消滅時効など) |
|
| B. 被担保債権が一部存続する場合でも抵当権だけが消滅するもの (担保執行手続きによる優先弁済権の満足の効果) |
②抵当権の実行 [民事執行法59条1項] |
||
| Ⅱ抵当権に 特有の 消滅原因 |
C 被担保債権が存続する場合でも, 抵当権だけが消滅するもの |
a) 被担保債権の一部の満足でも 抵当権が消滅するもの (簡易な手続きによる 優先弁済権の満足の効果) |
③代価弁済 [民法378条] |
| ④抵当権消滅請求 [民法379条~386条] |
|||
| b) 被担保債権が満足されないまま 抵当権が消滅するもの (優先弁済権の追及効の制限) |
⑤抵当権の消滅時効 [民法396条の反対解釈] |
||
| ⑥抵当不動産の時効取得 [民法397条] |
|||
通説は,抵当権は物権であるから,上記の第1,第2の消滅原因のほか,第3に,物権に共通の消滅原因(例えば,目的物の滅失・混同)によっても抵当権は消滅すると解している([内田・民法Ⅲ(2005)472頁])。しかし,そのような考え方では,以下に述べるように,抵当権の重要な問題である物上代位を含めて,抵当権の消滅と存続とを整合的に説明することが困難となってしまう。
(i) 目的物の滅失(必ずしも抵当権を消滅させない)
第1に,もしも,通説のように,抵当権が物権に共通の消滅原因である目的物の滅失によって抵当権自体が消滅すると考えるならば,抵当権が存在することを前提として認められている物上代位[民法372条による民法304条の準用]は意味を失ってしまう。そして,目的物の滅失と牽連して生じた債務者の債権(売買代金債権,賃料債権,損害賠償債権等)に対して,抵当権の効力(優先弁済権)が及ぶことを説明することができなくなる。
したがって,物的担保は,目的物の滅失によっても消滅するとは限らないというべきである。本書の立場によれば,物的担保は,物権ではなく,債権の掴取力が質的に強化されたものと考えるため,物的担保は,物権に共通の消滅原因によって消滅するとは限らないということを容易に説明することができる。しかも,このように考えることによってはじめて,①抵当権の目的物の範囲は,本来,不動産および不動産上の権利に限定されている[民法369条]にもかかわらず,目的物である不動産に付加して一体となっている場合には動産にも及ぶこと[民法370条],②債務不履行がある場合には,抵当権はその目的物の果実にも及ぶこと[民法371条],先に述べたように,③目的物が滅失・損傷した場合でも,それに牽連して債務者に生じた債権にも抵当権が及ぶこと[民法372条による民法304条]を,すべて連続的に理解することができるのである。さらには,④抵当権の目的物である建物が滅失し,建替えが行われた場合にも,一定の条件の下に,新建物の上にも抵当権の存続を肯定することが可能となる。最後の点については,本章の*第7節,第8節ですでに述べたので,繰り返さない。
ここでは,建物が滅失しても,抵当権が存続するとされた例として,最高裁平成6年判決〈最三判平6・1・25民集48巻1号18頁〉を挙げるに留める。
最三判平6・1・25民集48巻1号18頁
互いに主従の関係にない甲,乙二棟の建物が,その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても,これをもって,甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく,右抵当権は,丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続すると解するのが相当である。
(ii) 民法179条の混同による消滅(債権者と債務負担者との混同[民法520条]と付従性によって消滅する)
第2に,通説は,物権法総論に規定されている民法179条によって,抵当権の成立している目的物の所有権とその抵当権が同一人に帰して混同を生じた場合には,抵当権は消滅すると考えている。確かに,この結論は正しい。しかし,本書の立場によると,結論を導く理由が異なる。すなわち,この場合は,債権と負担の混同による責任の消滅(付従性)による抵当権の消滅と分類されることになる。
すでに述べたように,物的担保には,物権法総論の規定が適用できないことが多い(留置権も,先取特権も,質権も物権法総論の規定[民法177条,178条]に従っていない)。通説が,物的担保の消滅の場合にのみ物権法の総論[民法179条]を持ち出すのは,ご都合主義のそしりを免れない。この場合には,物権の混同の規定[民法179条]ではなく,債権の混同の規定[民法520条]の類推がなされるべきである。すなわち,上記の例は,債権(の優先弁済権=抵当権)と責任(他人の債務の負担=物上保証)とが同一人に帰属した場合にはその負担は消滅すると考えることになる。債権が消滅すれば,物的担保が付従性によって消滅することは,物的担保の通有性から説明できる。そして,このように考えても,抵当権が第三者の権利の目的となっている場合には抵当権が消滅しないことについても,民法179条が適用されるからではなく,上記と同様に,民法520条が類推適用されるからであるとして,容易に説明できる。
(iii) 抵当権の目的である権利の放棄(権利の消滅が対抗できないために,抵当権を消滅させない)
第3に,民法398条は,地上権・永小作権を抵当権の目的(無体物)とした場合[民法369条2項],その目的である権利が地上権者または永小作人によって放棄されても,抵当権者に対抗できないと規定している。その意味は,抵当権の目的が放棄によって消滅しても,抵当権者は,抵当権は存在するものとして,なお,抵当権に基づいて競売をすることができると解されている。
通説は,権利の放棄は,これによって第三者の権利を害する場合には許されないのであるから,民法398条の規定は当然の規定であると説明している[我妻・担保物権(1968)424頁]。確かに,この結論と理由は正しい。しかし,抵当権の目的が消滅した場合にも抵当権が消滅しないのであれば,当然の規定として説明するのではなく,通説の立場からすれば,少なくとも,抵当権の消滅の例外として,以下のように説明すべき問題であると思われる。
抵当権の目的が消滅すれば,抵当権も消滅するのが原則である(通説)。しかし,権利の放棄は,相対的な効力しか生じないのであり(通説),抵当目的の放棄による抵当権の消滅は,抵当権者に対抗できないのであるから,例外として,抵当権は消滅しない[民法398条]。
抵当権を物権とは考えず,先に述べたように,抵当権の目的の消滅は,必ずしも抵当権の消滅をもたらさない(その典型例は,抵当目的物の滅失の場合の物上代位に基づく抵当権の存続)とする本書の立場からすると,民法398条の規定は,例外ではなく,以下のように,当然の規定ということになる。上記の通説による説明と比べてみると,本書の立場が鮮明になると思われる。
抵当権は,抵当目的(物)が消滅しても,必ずしも消滅しない。しかも,権利の放棄は,相対的な効力しか生じないのであり(通説),抵当目的の放棄による抵当権の消滅は,抵当権者に対抗できないのであるから,抵当権が消滅しないのは当然である[民法398条]。
(iv) 抵当不動産の時効取得(所有権が原始取得されたとしても,必ずしも抵当権を消滅させない)
第4に,民法397条は,「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは,抵当権は,これによって消滅する」と規定しているが,これを反対解釈すると,民法397条は,「債務者又は抵当権設定者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときでも,抵当権は,これによって消滅しない」ということになる。
抵当権が制限物権であるとすると,抵当不動産が取得時効によって原始取得された場合には,制限物権は,例外なしに消滅するというのが物権法の大原則である。民法397条は,その反対解釈により,「抵当不動産が抵当債務者または抵当権設定者によって原始取得された場合でも,抵当権は消滅しない」としているのに等しいのであるから,つまるところ,抵当権は,必ずしも物権の原則には従わないないことを宣言しているのに等しい。
本書の立場によれば,抵当権は債権の優先弁済効に過ぎないのであるが,それが登記された場合には,債権の優先弁済効が第三者にも対抗できるのであり(登記された賃借権が第三者に対抗できる[民法605条]のと同じ現象に過ぎない),このことは,物権の所有者がどのような態様で交代しても変りがない。つまり,抵当権が第三者に譲渡(承継取得)されようが,第三者が時効取得(原始取得)されようが,物権ではなく,物権秩序に従うことのない抵当権は,賃借権の場合と同様,第三者に対抗できるのである。ただし,抵当権といえども,債権の効力に過ぎないから,債権の時効消滅に付従して消滅するほか,第三取得者との関係では,抵当権独自の消滅原因によっても消滅することがある[民法397条の反対解釈]。
なお,民法396条(第三取得者による抵当権の時効消滅の援用)と民法397条(第三取得者による抵当不動産の取得時効に基づく抵当権の消滅)との関係は,本書では,以下の2点で従来の解釈とは異なる。第1に,民法396条は,債務者および抵当権設定者のみに関する規定であると解している。そして,債務者および抵当権設定者との関係では,消滅時効であれ,取得時効であれ,抵当権が独自に時効によって消滅することはないことを明らかにする。すなわち,抵当権が消滅するのは,被担保債権が時効によって消滅する場合など,付従性によって消滅する場合だけであることを規定したものであると解している。第2に,本書では,民法397条は,債務者または抵当権設定者以外の者のみに関する規定であると解している。そして,債務者または抵当権設定者以外の者との関係における抵当権の独自の消滅原因(追及効の消滅)を規定しているものと解している。ただし,第三取得者との関係に限定された抵当権に独自の消滅原因の意味については,本書では,通説とは異なり,物権の取得時効に基づく抵当権の消滅の問題とは考えておらず,民法397条は,抵当権の追及効の限界を示すものであり,第三取得者が抵当不動産を時効で取得した場合に限って,抵当権の追及効が消滅するものと解している。以上の解釈は,通説とは異なる本書独自の説なので,後に詳しく論じることにする。
物的担保は,被担保債権の消滅によって消滅する(付従性)。抵当権も物的担保の1つであるから,被担保債権が,弁済(代物弁済,供託を含む),更改,相殺,混同,免除,放棄,消滅時効によって消滅した場合には,抵当権もそれに付従して消滅する。
債権の消滅による抵当権の消滅は,登記の抹消を待たずに絶対的効力を生じる[我妻・担保物権(1968)421頁]。この点は,抵当権の設定契約を解除したり,抵当権を放棄したりした場合[民法377条]とは異なる。
抵当権の設定された不動産に対して一般債権者が強制競売を申し立てて競売(不動産執行)がなされた場合,または,抵当権者等の担保権者による担保権の実行としての競売(担保不動産競売)が申し立てられて競売がなされた場合には,抵当権は目的物の売却によって消滅する[民事執行法59条1項]。
すなわち,抵当不動産の買受人は,抵当権の負担を引き受けない。占有を伴う不動産上の留置権や最優先の質権で使用・収益権を伴うものの場合には,これらの担保権が買受人に移転し,買受人が被担保債権を弁済しない限りこれらの担保権は存続する[民事執行法59条4項]のと対照的である。
抵当権が消滅し,所有権を取得した買受人が,さらに,競売によって用益権が消滅するため負担のない所有権を取得できるのか,用益権の負担を受けるのかという問題については,すでに第8節(抵当権と用益権の調和)の箇所で論じたので,ここでは触れない。
物的担保は,被担保債権の消滅に付従して消滅する。この点については先に述べた。抵当権の場合には,そのほかに,抵当不動産の所有権を第三者が取得した場合に,その第三取得者との利害を調整するため,被担保債権が完全に消滅しなくても,第三取得者が抵当権者に抵当不動産の価額を支払うことによって,抵当権のみを消滅させる制度が用意されている。抵当権者のイニシアティブで抵当権を消滅させるのが代価弁済の制度であり[民法378条],第三取得者のイニシアティブで抵当権を消滅させるのが抵当権消滅請求権の制度である[民法379条~386条]。
(i) 代価弁済の意義と制度の趣旨
抵当権が設定されても,抵当権の設定者は,抵当権の目的である不動産または地上権を自由に処分することができる。しかし,抵当権には追及効があるため,抵当不動産の所有権又はその上の地上権を買い受けた者(第三取得者)は,抵当権つきのままでその権利を取得することになる。したがって,もしも,その後に抵当権が実行されれば,第三取得者は,取得した権利(所有権,地上権または永小作権)を失うことになる。
このように,抵当不動産上の権利の取得者にとっては,いつ抵当権を実行されてその権利を失うかもしれないという不安がある。また,抵当権者にとっては,抵当目的である不動産が譲渡されるごとに,執行債務者を追及していく必要があり,実行手続きが面倒になる不安がある。そこで,抵当権者と第三取得者の利害を調整するため,抵当不動産の売買に際して,第三取得者が,売主である抵当権設定者ではなく,直接に抵当権者に買受代金を支払うという方法により,抵当権の優先弁済権を簡易な手続きで満足させ,抵当権を消滅させることができる制度が創設された。この制度を代価弁済という[民法378条]。
代価弁済における抵当権者と第三取得者との利害調整の成否は,以下に述べるように,第三取得者が抵当権者に支払う売却代金の額にかかっている。
まず,抵当権者としては,抵当権設定者の資力が乏しく,被担保債権が不良債権となっており,しかも,目的不動産の価格が下落し,上昇が望めない場合には,債権の全額の回収はあきらめざるを得ない。そして,抵当目的物の競売価格よりも高い市場価格に相当する金額を競売手続きによらずに第三取得者から取得することができるのであれば,競売を行うよりも,債権の簡易かつ早期の回収が可能となる。
次に,第三取得者としては,目的不動産または目的地上権が競売になれば,せっかく取得した権利を失う危険がある。競売で目的不動産を買い受ける方法は残されているものの(民法390条),他人に競り負ける可能性もあるし,競り勝つとしても,競売代金を支払わなければ完全な所有権を取得できない。すなわち,抵当権設定者に売買代金を支払って所有権を取得したとしても,抵当権の実行におびえることになるのであるから,抵当権の取得の際に,債権者が提示する代価を債権者に支払って抵当権を消滅させておいた方が,第三取得者にとっても有利となる。
したがって,抵当権者と第三取得者との交渉次第では,両者の利害を一致させることも不可能ではない。例えば,抵当不動産の競売予想価格に相当する金額が提示された場合には,代価弁済が実現する可能性があると思われる。交渉がスムーズに妥結して,債権者が不動産の価値相当額を回収し,抵当権が消滅する場合には,一方で,債権者は,抵当権が実行されたのと同じ満足を得ることができるし,他方で,抵当不動産の第三取得者は,覆されることのない完全な権利を取得できる。そればかりでなく,もしも,一応の満足を得た債権者が,不良債権の処理として債務を免除をすることになれば,債務者にとっても利益がある。
代価弁済および次に述べる抵当権消滅請求は,ともに,抵当不動産の第三取得者と抵当権者の利害を調整する制度であるが,抵当権消滅請求が第三取得者の方から一方的に請求できるのに対し(抵当権者にとって圧迫となる),代価弁済は抵当権者の方から請求があることを必要とする(抵当権者にとって圧迫とならない)点で,両者は,イニシアティブをとる主体が異なっている。
(ii) 代価弁済の要件と効果
抵当権の設定者(A)によって抵当権者(B)のために抵当権が設定されている場合に,抵当不動産の所有権または地上権を買い受けた第三者(第三取得者(C))が,抵当権者Bの請求に応じて,売主Aではなく抵当権者Bに代価を弁済したときに,抵当権は,第三取得者Cのために消滅する。
代価弁済の構造は,第1に,売主Aではなく,売主の債権者である抵当権者Bが買主Cに売買代金を請求している点で,抵当権者が民法423条の債権者代位権を行使しているように見える。しかし,この制度が,抵当権者による債権者代位権の行使だとすると,債務者Aの無資力要件が問題となるはずである。しかし,民法378条は,債務者の無資力を問題としていない点で,債権者代位権の要件を満たしていない。
代価弁済の構造は,第2に,抵当不動産が売却された場合に,抵当権者がその売却代金に対して物上代位権[民法304条]を行使しているようにも見える。しかし,物上代位には債権の差押えが必要とされているが,民法378条は,売買代金債権への差押を要求していない点で,物上代位権の行使とも異なる。
代価弁済の構造は,第3に,動産質権の簡易な実行手続き[民法354条]のように,抵当権の実行手続きとしての抵当権に基づく物上代位権の行使について,簡易な実行手続きを認めた規定であるようにも見える。担保権の実行の開始となる差押えおよび競売による換価手続きを簡略化し,第三取得者が抵当権者に直接代価を支払うことによって抵当権者が満足を受け,抵当権が消滅する制度であると考えることが可能である。確かに,明文の規定で認められている民法354条の動産質権の簡易な実行の場合には,質権設定者に比較して質権者の立場が強く,適切な清算が保障されないことを考慮して,裁判所の選定した鑑定人の評価によることが必要であった[民法354条]。しかし,代価弁済の場合には,第三取得者は代価弁済に対抗する手段として,強力な抵当権消滅請求権を有しており,抵当権者の代価弁済に応じる義務はないのであるから,それ以上に第三債務者を保護する必要がない。したがって,抵当権者に支払うべき売買の代価は,抵当権者が決定したとしても,何らの問題も生じない。そして,第三取得者が抵当権者に代価を支払えば,物上代位権に基づく優先弁済権の簡易な手続きが完結し,抵当権は優先弁済権の満足によって消滅すると考えることができる。
このように,代価弁済を,抵当権者のイニシアティブによる抵当権の簡易な実行手続きとして考えると,代価弁済の効果を,以下のように,整合的に説明することができる。
しかし,代価弁済の制度の運用に当たっては,大きな問題が残されている。抵当権者が1人のときは問題がないが,後順位抵当権者がいる場合には,抵当権が完全には消滅しないため,第三取得者がこの制度を利用するメリットはない。このため,この制度は,実際には余り使われていないとされている。したがって,この制度は,次に述べる抵当権消滅請求の理論上または実務上の橋渡しをするものとして意味を有するということになろう。
なぜなら,抵当権消滅請求の制度は,代価弁済の制度があるために説明が容易な制度であり,代価弁済の制度抜きに抵当権消滅請求の制度を説明することは困難だからである。立法理由書によると,抵当権消滅請求の制度(立法当時は,滌除の制度)がある以上は,代価弁済の制度も認めるべきであるという記述が見られるが[民法理由書(1987)368頁],理論的には,抵当権者の側に代価弁済が認められるから,対抗措置として,第三取得者側に抵当権消滅請求(対抗・代価弁済)が認められるということになるのである。
(i) 抵当権消滅請求の意義
抵当権消滅請求とは,抵当不動産について所有権を取得した第三者が,取得代価又は特に指定した金額を抵当権者に提供して,抵当権の消滅を請求する制度である[民法379条~386条]。抵当権者は,その提供金額に不満があるときは,抵当権を実行して競売を申し立てることができる。抵当権者が競売を申し立てないときは,提供された代価又は金額を承諾したものとみなされ[民法384条],すべての抵当権者の承諾と,第三取得者の提供金額の支払又は供託により,抵当権は消滅する[民法386条]。平成15年の民法改正(法134)により,滌除の制度が見直され,名称と内容が変更されて,抵当権消滅請求の制度として導入された。
(ii) 滌除から抵当権消滅請求への改正の背景と趣旨(滌除制度のデメリットとメリット)
2003(平成15)年民法改正前における,民法旧378条~387条の滌除制度は,抵当権の設定された不動産の所有権,地上権または永小作権を取得した者(第三取得者)が,抵当権者に対して一定の金額を提示し,その金額で抵当権の消滅を求めるものであった。抵当権者がそれを承諾すると,第三取得者は,その金額を支払って抵当権を消滅させ,抵当権の負担のない物件を入手できた。たとえ,抵当権者にとって,第三取得者が提示する金額に不満があって承諾したくないときでも,滌除制度の下では,抵当権者としては,提示された金額より1割高い額で買い受けることを示して競売(増価競売)の申立てをするほかに対抗手段はなく,増価競売の申立てをしなければ,提示された金額を承諾したものみなされることになっていた。
しかも,抵当権者が抵当権を実行しようとすれば,滌除権者に対して抵当権の実行通知をすることが義務づけられており,その上,実行通知をして1ヶ月が経過しないと競売できないということになっていたため[民法旧387条],この1ヶ月の間に抵当権の実行に対する妨害手段が講じられるおそれがあった。
このように,抵当目的の第三取得者から提示された金額の1割増しで買受ける覚悟をしなければならないという増価競売が組み込まれた滌除制度は,抵当権者にとって極めて思い負担となっていた。そして,このような負担があるために,抵当権者は,相当低い額での滌除の申立てにも応ぜざるをえないという不都合が生じていた。
このような弊害があるにもかかわらず,滌除の制度そのものには,以下に述べるように,大きなメリットがある。
第1に,改正後もその効果が変更されていないように,滌除制度の趣旨は,抵当権の負担のついた物件を取得した者が,あたかも物上保証人になったかのように,その物件の価額の限度で,抵当権者に直接に弁済を行い,抵当権の優先弁済権を満足させて抵当権を消滅させる制度である。この制度は,第三取得者の提供する価額が競売代金相当額である場合には,抵当権の正規の実行手続きを行って第三取得者が買受人になった場合と同じ効果を発生させるものである。競売という面倒な手続きを簡略化している点で,通常の抵当権の実行よりも大幅に時間を短縮できる(時は金なり)というメリットを有している(加賀山説:滌除(抵当権消滅請求)=簡易な抵当権実行説)。
第2に,滌除の制度は,例えば,抵当目的物が下落しているにもかかわらず,抵当権者が,値上りを待っていて抵当権を実行しようとせず,「不動産の塩漬け」を行っている場合に,第三取得者の方から,抵当権者に抵当権を実行させることによって,不動産を流動化させるという機能を有している[道垣内・担保物権(2008)167頁]。
そこで,滌除の効果である抵当権の消滅を維持しつつ,上記のような滌除の弊害を除去するため,2003年の改正では,①抵当権の消滅を請求できる者の限定,②抵当権の消滅を請求できる期間の限定,③抵当権者の抵当権実行通知義務の削除,④増価競売制度の廃止による通常の競売申立てへの変更,⑤競売申立て期間を1ヶ月から2ヶ月へと延長することを骨子とし,その上で,滌除という難解な用語を抵当権消滅請求へと変更する改正がなされることになった。
抵当権消滅請求の制度を活用するならば,例えば,抵当権設定者と抵当権者が第三取得者への抵当不動産の任意売却に合意しているにもかかわらず,後順位抵当権者がいわゆる「ごね得」ベースで登記の抹消を拒んでいるため,売却がスムーズに行われないという場合にも,抵当権消滅請求は後順位抵当権者を排除できるため,困難な事態を改善させることが期待できる[小林=山本・担保物権法(2008)114頁]。
なお,滌除の制度と抵当権消滅請求の制度との違いに関する詳細な検討としては,織田博子「抵当権消滅請求制度」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)51頁以下]を参照のこと。
抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,その担保する債権と同時でなければ,時効によって消滅しない[民法396条]。もっとも,被担保債権が消滅時効にかかった場合に,抵当不動産の第三取得者が消滅時効を援用できることについては,判例〈最二判昭48・12・14民集27巻11号1586頁〉および通説([我妻・担保物権(1968)422頁],[高木・担保物権(2005)287頁])もこれを認めている。
それでは,被担保債権とは別に,抵当権自体としては,消滅時効にかからないのであろうか。所有権をはじめ物権は消滅時効にかからないのが原則であることを考えると,抵当権自体も消滅時効には服さないと考えることも可能である。例えば,[道垣内・担保物権(2008)230頁]は,抵当権者が抵当権の消滅時効の進行を中断することが困難であることを理由として,被担保債権の消滅時効とは独立に,抵当権自体が消滅時効によって消滅することはないと解している([内田・民法Ⅲ(2005)473頁]は,これが有力説であるとして賛成する)。
しかし,通説([我妻・担保物権(1968)422頁],[近江・講義Ⅲ(2007)]など)および判例〈大判昭15・11・26民集19巻2100頁〉は,民法396条の反対解釈として,抵当不動産の第三取得者は,被担保債権の消滅時効とは独立に,抵当権の消滅時効([民法167条2項]による20年の消滅時効)を主張できると考えている。
この問題について,旧民法においては,第三取得者との関係では,抵当権は第三取得者の所有権取得から30年の経過によって時効によって消滅すると規定されていた。
旧民法 債権担保編 第296条
抵当不動産の所有者たる債務者が其不動産を譲渡して取得者又は其承継人が之を占有するときは,登記したる抵当は抵当上の訴訟より生ずる妨碍なきに於ては,取得者が其取得を登記したる日より起算し30个年の時効に因りてのみ消滅す。但債権が免責時効に因りて其前に消滅す可き場合を妨げず。
上記のように,旧民法が抵当権の消滅時効の期間を30年としていたのに対して,現行民法の立法者は,一般の時効期間と考えればよいとして抵当権の消滅の規定を起草した。しかし,それが何年となるのかという問題に関しては,現行民法の起草者が抵当権を債権とは考えていなかったことを考慮すると,抵当権は20年の消滅時効に服すると考えていたと思われる〈大判昭15・11・26民集19巻2100頁〉。しかし,抵当権を債権の優先弁済効と性質決定した場合には,債権と同様に10年の消滅時効に服すると考えることも可能であり,そのように考えると,抵当権の消滅時効の実質は,債権の消滅時効とともに付従性によって消滅するというのとほぼ同じ結果となる。
しかし,抵当権が何年間で時効によって消滅するのかという問題は,実は,民法396条の問題ではなく,民法397条によって解決されるべき問題である。なぜなら,民法396条と民法397条とは,以下に述べるように,両者があいまって初めて,時効による抵当権の消滅に関する規定となっているからである。
民法の起草者は,第1に,民法396条において,債務者および抵当権設定者との関係では,抵当権は被担保債権の消滅時効と同時にしか消滅しないことを明らかにしており,第2に,民法397条において,債務者および抵当権設定者以外の者(第三取得者)との関係では,抵当権は,第三取得者が抵当不動産について,取得時効に必要な要件を具備したとき,すなわち,第三取得者が,占有の開始につき善意かつ無過失であれば10年間[民法162条2項],悪意であれば20年間[民法162条1項]の占有の継続によって,抵当権が取得時効の反射的効果によって消滅することを明らかにしているのである。
確かに,通説によれば,民法396条は抵当権の消滅時効を規定し,民法397条は,第三取得者による抵当不動産の取得時効(原始取得)の反射的効果として,抵当権が消滅する場合を規定したものと解している。しかし,民法397条は,債務者および抵当権設定者が所有権を時効取得(原始取得)した場合には,抵当権は消滅しないとしていることから,抵当不動産の原始取得によって,必ずしも抵当権が自動的に消滅するわけではないことが明らかである(民法397条の反対解釈)。そうだとすると,抵当不動産の原始取得によって,抵当権は,自動的に消滅するという説明では,この条文によれば,債務者または抵当権設定者が抵当不動産を時効取得した場合には,自動的に消滅するはずの抵当権が,消滅しないことになるが,それがなぜなのかを説明することはできない。
したがって,抵当権の消滅時効は,第三取得者が抵当不動産を時効取得した場合にのみ発生し,かつ,第三取得者のみが抵当権の消滅時効を援用できることを説明できる理論が必要となるのである。
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは,抵当権は,これによって消滅する[民法397条]。取得時効が完成すると,それは原始取得となるので,抵当権が制限物権だとすると,所有権の負担となっていた抵当権も消滅するはずである。しかし,抵当不動産の取得時効による抵当権の消滅を,自ら義務や責任を負っている抵当債務者や抵当権設定者(物上保証人)にまで及ぼすことは不合理であると考えられ,債務者および物上保証人は,抵当権の消滅の利益を受けないとされたのである。
したがって,民法397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)の意義は,抵当不動産に対する取得時効の完成によって抵当権が消滅することにあるわけではなく,被担保債権の債務者と抵当権設定者は,抵当権の消滅の効果を援用できないとしている点にあることになる[小林=山本・担保物権法(2008)119頁]。
しかし,そうだとすると,以下のような重大な問題が発生する。
第1に,抵当権が所有権を制限する制限物権だとすると,所有権が時効取得(原始取得)された場合には,時効取得者は物権的な負担のない完全な所有権を取得するのであり,制限物権である抵当権は,誰に対しても消滅するはずである。所有権の原始取得の効果は,万人に対して及ぶのであり,債務者および抵当権設定者が原始取得した場合とその他の人が原始取得した場合とで,その効果に差を設けることはできないはずである。
第2に,抵当権設定者はすでに所有権を有しているので,それをさらに時効取得することはないように思えるが,判例は,自己の物について時効取得することを認めている。例えば,判例〈最二判昭42・7・21民集21巻6号1643頁〉(家屋明渡請求事件)は,売主Aから買主Bが不動産を買い受け所有権を取得したが[民法176条],二重譲渡により第2買主Cが先に登記を得た場合に,登記を経ないまま占有を継続したBに所有権の時効取得を認めている。また,〈最一判昭44・12・18民集23巻12号2467頁〉(所有権移転登記手続請求事件)は,前記判例を引用しつつ,売主Aから引渡しを受けた買主Bが登記を経ることなく占有を継続した場合に,買主Bに対して,時効取得を理由とした移転登記請求を認めている。
そうすると,債務者ばかりでなく,抵当権設定者が自己の物について所有権を時効取得することも可能であり,その場合には,抵当権設定者は完全な所有権を原始取得することになり,制限物権である抵当権は消滅するはずである。
実際のところ,抵当権が設定された場合に,取得時効によって所有権を取得できる可能性があるのは,占有をしている抵当権設定者(物上保証人)か,抵当不動産の引渡しを受けた第三取得者にほぼ限定される。そうだとすると,民法397条が,「債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは,抵当権は,これによって消滅する」と規定している意味は,第1に,抵当権設定者については,上記のように,抵当権設定者がたとえ抵当不動産の所有権を時効取得しても抵当権は消滅しないという,物権秩序に関する重大な例外を規定していることになる。第2に,抵当権設定者の場合とは異なり,第三取得者については,10年間占有を継続したとき(抵当権については,悪意または有過失であっても,所有権については,善意・無過失の占有者と判断される〈最三判昭43・12・24民集22巻13号3366頁〉)または20年間占有を継続したときには,民法397条の反対解釈により,抵当権を消滅させることができるということを意味することになる。
つまり,同じ時効取得の場合でも,抵当権設定者の場合には,原始取得しても担保物権が消滅せず,第三取得者の場合には,原始取得によって担保物権が消滅するということになる。このような民法397条の趣旨を,通説のように,抵当権を物権(制限物権)だと考え,第三者が所有権を時効取得した場合には,制限物権である抵当権も消滅するという原理を肯定する立場に立ちつつ,これらを矛盾なく説明することは可能であろうか。
自己の物について取得時効の成立を認める通説・判例の考え方を採用する限り,第1に,抵当権設定者が抵当不動産を時効取得した場合に,抵当権が消滅しないという民法397条の条文を説明することができない。これとは反対に,第2に,通説の考え方によると,第三取得者が抵当不動産を時効取得した場合には,抵当権が消滅することを説明できる。しかし,抵当権の物的負担を負う第三取得者が,自己の物の所有権を時効取得したとして,抵当権の消滅を主張できるかどうかについては,通説は,有力説[近江・講義Ⅲ(2007)258頁]からの厳しい批判にさらされている。第三取得者は,抵当権の存在を登記によって知りうるのであり,抵当権の負担を覚悟すべきことは,信義則上も明らかだからである[槙・担保物権(1981)246頁]。
このように考えると,抵当権を物権と考え,自己の物について所有権の取得時効を認める考え方によっては,民法397条について,抵当債務者および抵当権設定者が抵当権の消滅を主張できず,第三取得者は抵当権の消滅を主張できるという条文の趣旨を説明できないことがわかる。
それでは,抵当権を物権でなく,債権の優先弁済効に過ぎないと考える本書の立場に立った場合には,この問題をどのように説明することができるのであろうか。本書の立場は,抵当権は債権の優先弁済効に過ぎないが,これを登記することによって,その権利を第三者に対抗できると考えている。これは,債権である賃借権の場合にも,賃借権を登記すると,その賃借権が第三者に対抗できる[民法605条]のと同様である。ただし,登記された賃借権は,賃借不動産が第三者に譲渡されても,譲受人に対して賃借権の存続を主張できるというものであるが,登記された抵当権の場合には,抵当目的物が第三者に譲渡されても,その第三者に抵当権の追及効が及ぶという点に相違がある。すなわち,抵当権の第三者効とは,抵当権追及効が第三者にも及ぶという意味である。しかし,抵当権の追及効にも限界が存在する。抵当目的物である山林の樹木が伐採されて,材木となった場合に,抵当権の追及効はどこまで及ぶかという点については,すでに述べたところであるが,抵当権の目的物そのものが第三者によって時効取得された場合に,抵当権の追及効が及ぶかどうかというのが,抵当権と時効との関係に関する問題の本質なのである。
抵当権の追及効に関しては,債務者および抵当権設定者は,債権者との関係では第三者に当たらないから,そもそも,抵当権の追及効の消滅を請求できる立場にない。また,抵当不動産の通常の第三取得者は,抵当権の優先弁済権を対抗される第三者であり,たとえ,所有権を取得したとしても,抵当権者に対抗できない。取得時効は,完全な所有権と矛盾する物権を消滅させることはできても,債権上の権利に影響を与えるものではないからである。
しかし,この抵当権の追及効の効力にも限界がある。確かに,抵当不動産が正規の譲渡によって移転された場合には,抵当権の追及効はどこまでも及ぶ。しかし,抵当不動産が,このルートを外れて,第三者によって時効取得された場合には,例外的に抵当権の追及効も消滅するというのが,民法397条の意味なのである。その場合に,時効取得に要する占有継続の期間と取得者の対応については,議論がある。
判例〈最三判昭43・12・24民集22巻13号3366頁〉は,第三取得者が抵当不動産を10年間占有し続けた場合に,以下のように述べて第三取得者の時効取得を認めている。
最三判昭43・12・24民集22巻13号3366頁
民法162条2項にいう占有者の善意・無過失とは,自己に所有権があるものと信じ,かつ,そのように信ずるにつき過失のないことをいい,占有者において,占有の目的不動産に抵当権が設定されていることを知り,または,不注意により知らなかった場合でも,ここにいう善意・無過失の占有者ということを妨げない。
追及効を制限するに際して,抵当不動産の所有権の取得時効によることを決定した以上,抵当権の追及効の消滅に関して,所有権の取得時効の要件を変える必要はない。判例の見解は,その点で,正鵠を得ているといえよう(なお,抵当権の追及効の限界に関しては,第3節E(b)(抵当権の追及効とその限界)参照)。
民法396条および民法397条に規定された抵当権の消滅原因は,以下の表のようにまとめることができる。
| 民法396条 | 民法397条 | |
|---|---|---|
| 対象となる者 | 債務者および抵当権設定者 | 債務者および抵当権設定者以外の者 |
| 抵当権の消滅原因 | 被担保債権の消滅時効 | 抵当不動産の時効取得 |
| 抵当権の消滅の意味 | 被担保債権の消滅(付従性による消滅) | 追及効の限界と消滅 |
| 留意点 | ①抵当権は消滅時効によっては消滅しない。 ②たとえ上記の者が抵当不動産を時効取得しても,抵当権は消滅しない[民法397条の反対解釈]。 つまり,上記の者に関する限り,抵当権は,消滅時効,取得時効を含め,時効によって消滅することはない。 |
この規定は,抵当権が時効によって消滅することを意味するのではなく,抵当不動産の第三者による取得時効の場合に限って,抵当権の追及効が制限されることを意味している。 つまり,上記の者が抵当不動産を時効によって取得した場合には,抵当権は追及効を失って消滅する。 |
ここで注意しなければならない点は,以下の4点である。
第1は,通説のように,民法396条を安易に反対解釈して,「債務者または抵当権設定者以外の者については,抵当権は消滅時効(20年の消滅時効)にかかる」と解釈することは誤りであることである。なぜなら,「債務者または抵当権設定者以外の者」に関しては,民法397条が規定を行っており,反対解釈を含めて,民法396条の解釈の適用範囲ではないからである。反対解釈するには,すべての場合を尽くした上で行わなければならない。そして,民法396条と民法397条とを総合して,「債務者または抵当権設定者については,抵当権は時効によっては消滅しないし[民法396条の文理解釈],自らの取得時効によっても抵当権は消滅しない[民法397条の反対解釈]」,すなわち,債務者または抵当権設定者については「消滅時効によっても,取得時効によっても抵当権は消滅しない」と解釈しなければならない。
第2は,債務者または抵当権設定者以外の者が抵当目的を時効取得した場合には,民法397条によって,確かに,抵当権が消滅する。しかし,通説のように,その理由を,「抵当目的の取得時効(原始取得)に基づいて,制限物権である抵当権が反射的に消滅するからである」と考えることは誤りであるということである。なぜなら,もしも,抵当権が制限物権であり,抵当目的の時効取得(原始取得)により反射的に消滅するというのであれば,「債務者または抵当権設定者」が抵当目的を時効取得した場合にも,抵当権は消滅するはずである。しかし,この場合には,抵当権は消滅しないのであり[民法397条の反対解釈],通説によるのでは,両者を矛盾なく説明することは不可能だからである。
債務者または抵当権設定者以外の者が抵当目的を時効取得した場合に抵当権が消滅する理由は,抵当権の追及効の限界に求めるべきである。確かに,抵当権の追及効は,通常の譲渡の場合には,登記を理由に,どこまでも及ぶ。しかし,追及効にも限界があることを認めなければならない。抵当不動産について,第三者が,登記にも対抗できる取得時効を成立させた場合には,抵当権の追及効も限界に達して,追及効が消滅し,結果として抵当権が消滅すると考えるべきであろう。
第3は,民法の解釈の基本問題にかかわるものであるが,「反対解釈は,よほど注意して行わないと,間違いを犯すことが多い」ということである。通説が誤った解釈を行っている場合のほとんどが,条文の誤った反対解釈にその原因があるというのが,本書の基本的な立場である。例えば,民法613条前段の反対解釈による誤りについては,*第3章第1節3B(e)で,詳しく解説を行っている。また,民法465条の反対解釈として,連帯債務者は負担部分を超えて弁済していない場合でも,他の連帯債務者に対して求償できる[民法442条]と考えるのは誤りであることについては,*第4章第1 節A(d)で詳しく論じている(なお,複数原因の場合に,事実的因果関係の判断基準である「あれなければ,これなし」という反対解釈が通用しないことについては,[加賀山・契約法講義(2007)318-321頁]を参照するとよい)。
民法396条,397条の解釈においても,一方で,民法396条の反対解釈として,「債務者または抵当権設定者以外の者については,抵当権は消滅時効にかかる」と解釈することは誤りである(この点で,[内田・民法Ⅲ(2005)473頁]が,民法「396条は反対解釈すべきではない」としているのは,正当である)。他方で,上記の表のように,民法397条の反対解釈として,「債務者または抵当権設定者については,抵当権は,取得時効によっても消滅することはない」と解釈することは正しい。なぜ,そのような違いが出てくるのかについては,その理由を,すでに説明しているのであるが,そのことを本当に理解できるかどうかを,読者自身で,もう一度よく確認することが大切である。
第4は,第3点にもかかわる問題であるが,個々の条文を単独で解釈してはならないということである。通説のように,民法396条と民法397条とは,一方は,抵当権の消滅時効の問題であり,他方は,第三者の取得時効による抵当権の消滅の問題であるというように,両者を切り離して解釈してはならない。民法396条と民法397条とは,ともに,抵当権者の満足によらない抵当権の消滅について規定しているのであり,両者を総合して解釈しなければならない。すなわち,民法396条については,「債務者または抵当権設定者」に対しては,抵当権は,消滅時効であれ[民法396条の文理解釈],取得時効であれ[民法397条の反対解釈],被担保債権の消滅時効以外の時効を理由として消滅することはないと解釈すべきであるし,反対に,民法397条については,「債務者または抵当権設定者以外の者以外の者」に対しては,それらの第三者が抵当不動産について取得時効の要件を満たした場合には,(登記によって認められた追及効が,登記に勝る取得時効によって限界に達し),抵当権は消滅すると解すべきなのである。
このように,一般論として,通説・判例が解釈上の誤りを犯している場合を追跡してみると,その多くは,通説・判例が安易な反対解釈を行ったことに起因するというのが筆者の経験則である。このように,反対解釈は,誤りに陥ることが多い。「反対解釈は,『すべての場合が尽くされたかどうか』を慎重に判断した後にのみ行うことができる」ということを肝に銘じておくと,解釈の誤りから免れることが多いであろう。
根抵当権とは,被担保債権について債権枠を設定し,その枠内の個別の債権の発生・消滅にかかわりなく,抵当権の存続を認め,最終的に確定した被担保債権について優先権を与える制度である。債権枠をどのように設定するかが完全に債権者に任せられているものを包括根抵当というが,これは,現行法では禁止されている。そして,現行法においては,債権枠の設定には,債権の性質と債権の限度額(極度額)という2つの面から制限が課せられることになっている。
これを一般先取特権と比較してみよう。一般先取特権の場合,債権の性質(例えば,雇用関係に基づいて生じた債権という性質)のみが特定されており,債権の限度額は制限されていない(例えば,月々に支払われるべき債権は,発生・消滅を繰り返しており,退職金債権を合わせると,債権額は相当な額に達することがありうる)。
このように考えると根抵当権は,債権の付従性から脱却した,もっとも独立性の高い抵当権,すなわち,最も物権らしい抵当権とされているが,実は,最も債権らしい一般先取特権の仕組みと同じであるに過ぎず,根抵当権と通常の抵当権との差は,通説が主張するほどに大きくないことを理解することができる。
普通抵当権が,特定の責任財産(不動産)を公示することを通じて特定の債権に対して優先弁済権を与える制度であることはすでに述べた。これに対して,根抵当権は,債権の流動化を許し,一つの枠として観念できる不特定の債権について,流動中は債権の枠に,確定後は枠内の個々の債権に対して優先弁済権を与えるものである。
「根」という概念は,「枝葉は違っても根は同じ」,「枝葉は枯れても根は残る」との喩えから,一定の継続的な取引関係から生ずる増減変動する多数の債権を全体として対象とする場合に,それらの債権全体を1つのものとして扱うことができるという考え方を表現するものであり,「根質」,「根担保」,「根保証」などの用語法の中で,この概念が用いられている。
根抵当というと,何か複雑なものと思われがちである。しかし,植物の根と枝葉の関係だけでなく,人間も含めて,すべての生物が,その内部では,個々の細胞が常に入れ替わっていること(内部の入れ替わらない生物は存在しない)に思いをいたすと,根抵当が身近に感じられるかもしれない。ただし,担保法において「根」の概念が使われるのは,個々の目的物が変動する場合の「集合」概念とは異なり,被担保債権が変動する場合である点に注意しなければならない。つまり,個々の債権が入れ替わっても,全体としては,1つの債権枠と考え,その債権枠に対して,できる限り普通の抵当と同じような扱いを試みようとしているのが,根抵当なのである。
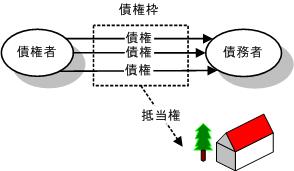 |
| *図117 根抵当の特色=債権の流動性と担保目的物の固定性 |
根抵当を理解するためには,流動化という現象を理解する必要がある。根抵当は,「被担保債権」が流動化すること(一定の範囲で入れ替わること)を許すものである。これに対して,集合物(集合債権)の譲渡担保は,担保の「目的物」が流動化することを許すものである。流動化の対象が,「被担保債権」なのか,「目的物」なのかを区別しなければならない。すなわち,根抵当は,「被担保債権」が入れ替わるのに対して「担保目的物」は特定している。これに対して,集合物(債権)譲渡担保の場合には,「被担保債権」は特定しているが「担保目的物」が入れ替わるのである。このように,根抵当と集合物(集合債権)の譲渡担保とは,明確に区別されなければならない。
担保に関して,被担保債権や目的物が入れ替わるものをどのように考えるべきかについては,すでに述べた一般先取特権[民法306条]を思い起こすと理解が容易となる。例えば,民法306条2号,308条に規定された雇用関係の先取特権の先取特権を例にとってみよう。
第1に,雇用関係,例えば給料債権の先取特権の被担保債権は,給料債権であり,通常は,支払期ごとに発生し,消滅していく。しかし,給料債権という性質による枠に該当する債権が存在する限り,先取特権の効力は継続する点で,被担保債権は流動的でもある。例えば,債務者(使用者)が給料の支払いを遅延している場合には,使用人(被用者)の使用者に対する給料債権はその分だけ増えていく。なぜなら,それらは,すべて,給料債権という性質の枠に当てはまるからである。つまり,給料債権の一般先取特権は,被担保債権が流動的であるという点で,根担保であるということができる。
第2に,給料債権の先取特権の目的物は,使用者の総財産に及ぶ[民法306条]。総財産は,その性質上,常に変化し流動しているのであるから,その点で,一般先取特権は,集合物(集合債権)担保ということもできる。
このように,一般先取特権との対比で考えると,一般先取特権の機能のうち,目的物を特定する一方で,被担保債権の流動化を認めるのが「根」担保であり,被担保債権特定する一方で,目的物の流動化を認めるのが「集合物(集合債権)」担保であるということが理解できる。
一般先取特権については,その性質は,物権ではなく,債権であるというのが最近の有力説の見解であるから,根担保や集合物担保は,他の物的担保に比べて,よりいっそう債権的な性質を有していると考えるべきである。通説は,根抵当権の場合には,後に述べるように,根抵当権が確定するまでは,根抵当には,付従性,随伴性がなく,担保権としての独立性が強く,より物権的であると考えている。しかし,流動性は,物権の固有の性質である「特定性」からは,むしろ乖離する。このことは,目的物の流動性を極端にまで推し進めた「企業担保」が,物権として規定されている[企業担保法1条2項]にもかかわらず,物権の性質が希薄となっていること,すなわち,企業担保は,一般先取特権にも劣後し[企業担保法7条],会社財産に対する一般債権者による強制執行,担保権者による担保権の実行において優先弁済権を有しない[企業担保法2条2項]ことを見てもよくわかる。一定の性質の債権の中で,債権の流動化を認め,担保権の実行の際に初めて債権が特定する根抵当の場合も,被担保債権の流動化を許している時点では特定性を欠いており,物権というよりは,債権的性質の強い,一般先取特権に近い存在であることに留意すべきである。
ところで,根抵当が立法化されたのは,民法制定後70年を経過した1971(昭和46)年のことであり,流動する債権に対しても抵当権を設定したいという社会的要請に答えるためであった。もっとも,民法制定当時から,根抵当権の有効性については争いがあり,現行民法制定から3年後の時点で,明治34年大審院判決〈大判明34・10・25民録7輯9巻137頁〉は,以下のように,根抵当権が有効であることを宣言していた。
大判明34・10・25民録7輯9巻137頁
銀行並に商人間に於て信用を開く為め,従来汎く行はるる所の根抵当と称するもの,即ち抵当が負担す可き最高の金額を定め,債権債務の確定を後日に留保し,交互取引の金円に利息を付け其勘定尻金額を以て実際抵当の負担額と為す可きことを結約したるものの如きは,之れ即ち,将来効力を生ず可き債権債務の為め,予め抵当を設定せるものにして,上文掲ぐる所の抵当と其理由同一に帰着するに付き,其有効たる勿論なり。
根抵当権が必要とされるのは,たとえば,継続的に取引をしている当事者間(銀行と商人,メーカーと卸売・小売商など)において,債権・債務が発生・消滅を繰り返し,その額も常に一定ではない場合である。このような債権を普通の抵当権で担保しようとすれば,抵当権の設定・抹消を頻繁に行わなければならないことになる。
また,後順位の抵当権が存在する場合には,いったんその抵当権が消滅すると,順位昇進の原則によって,後順位抵当権者の順位が上昇するため,再度抵当権を設定する場合には,第1順位を確保することができない。そうすると,金融機関がすんなりとは融資をしてくれないということになりかねない。
このような不便を解消するために,将来にわたって継続的に発生するこれらの債権をあらかじめ一括して担保しうる抵当権の設定が必要とされるようになったのである。根抵当権が設定されてきた典型的な取引契約というのは,以下のような契約である。
根抵当権の立法化に際しては,流動債権について抵当権の設定を認めるとともに,被担保債権の無制限な流動化を制限する(「債権者の債務者に対する一切の債権を担保する」という「包括根抵当」を禁止する)という必要性が生じ,1971年に民法に根抵当の節(21カ条)が追加された。すなわち,被担保債権の流動化については,質的な面(債権の性質,すなわち,「一定の範囲に属する債権」)と量的な面(債権枠としての「極度額」)からチェックされているのである。
この点は,例えば,雇用関係の一般先取特権が,債務者に対するすべての債権について先取特権を有するのではなく,雇用関係に基づいて生じた債権(給料債権,退職金債権,損害賠償債権等)という債権の枠に限定されているのと同様である。
つまり,根抵当とは,民法398条ノ2の文言に即していえば,「一定の範囲に属する」(質的チェックが行われ,包括根抵当は否定される)「不特定の債権」を「極度額」(量的チェックが行われる。これは「枠支配」と呼ばれている)の限度において担保するために設定される抵当権であるということができよう。
債権は特定されていない(設定時に特定した債権を担保するのではなく,債権の入替りは可能である)が,被担保債権を発生原因(既存または将来の取引契約)の面から質的に限定し,かつ,極度額を約定して登記することを有効要件とすることによって量的に制限がなされている。
また,債権の範囲と極度額によって表示される債権枠は最初から特定されており,かつ,抵当権の実行時には債権が確定されて,普通抵当に戻るのであり,債権枠を特定債権と同様に考えれば,根抵当と普通抵当との間に本質的な差異があるわけではない。
従来の説では,根抵当権は被担保債権と切り離されているところにその本質があるとされ,付従性は緩和されていると説明されてきた。
確かに,根抵当権の場合には,個々の被担保債権と根抵当権とは分離されているが,個々の被担保債権を束ねている債権枠と根抵当権とは密接に関連しており,債権の確定という作業を通じて,常に個々の被担保債権と結びつく可能性を有している。
抵当権を合意と登記の対抗力に基づく債権の優先弁済効であるとする本書の立場によれば,根抵当の場合,対象となる債権が,普通抵当権の場合と異なり,特定の債権ではなく,債権枠の範囲内で流動化する債権を扱う点が異なっている過ぎない。物的担保全体から見れば,この現象は,先に述べたように,債権の性質が特定している中で流動化が認められている先取特権(雇用関係の先取特権,不動産賃貸の先取特権など)にも見られる特色であって,根抵当権に特異な減少ではない。
根抵当権の場合,債権枠の範囲内にある流動する債権を対象としているのであるから,個々の債権が発生・消滅しても,流動債権,すなわち,債権枠が消滅するわけではない。したがって,その時点ではいわゆる付従性は問題とならない。これは,一般先取特権について,個々の債権が流動しても,債権の性質という一定の枠の中で効力が認められているのと同じである。
債権の優先弁済効としての抵当権の効力が問題となる時点というのは,常に,根抵当権の確定を通じて特定された個々の債権についてのみ問題となるからである。債権が確定するまでの問題は,債権枠についての問題であって,債権の優先権の問題ではない。
保証人の求償権を担保するために設定される抵当権のように,普通抵当権の場合でも,抵当権設定時に被担保債権の存在を要するという意味での付従性は緩和されている。根抵当の場合,被担保債権が発生・消滅を繰り返し,額も一定限度で変動することが許されているので,成立に関する付従性は一層緩和されているように見える。
しかし,根抵当権は,そもそも債権枠で限定された流動債権を対象にするものであるから,流動中の個々の債権について付従性を問題にすること自体が無意味である。根抵当権の付従性は,流動中は債権の枠自体について,そして,確定した後は個々の債権について考えれば足る問題なのである。
債権が流動中の根抵当の付従性の問題は,枠自体を問題とすべきである。したがって,例えば,根抵当の基礎となっている特定の継続的取引契約が無効の場合は,根抵当権設定契約も無効となるというのが,まさしく付従性の問題なのである。そして,本書の立場に依れば,根抵当権においても,債権枠自体が無効である場合または確定後の債権が無効である場合に,優先弁済権としての抵当権が効力を有しない(根抵当権においても成立に関する付従性が存在する)のは当然であるということになる。
普通抵当では,被担保債権が消滅すると抵当権は消滅するが,根抵当の場合,確定するまでは,被担保債権が存在しなくなっても根抵当権は消滅しない。
このことを根拠に,根抵当権の付従性は緩和されているというのが従来の説であるが,先に述べたように,根抵当権は,債権枠で限定された流動債権に関する抵当権に過ぎないのであり,債権が流動している間は,そもそも付従性は問題とならないし,優先弁済権すら問題とならない。そして,債権が確定作業によって流動を停止したときにはじめて付従性の問題が生じるのであり,この場合は,普通抵当権と同様,根抵当権においても,担保権の通有性としての付従性は保持されている。
普通抵当の場合,債権が譲渡されれば抵当権も随伴して移転するが,根抵当の場合,被担保債権の枠内の個々の債権が譲渡されても根抵当権は随伴しないため,根抵当の場合には随伴性は否定されるとされてきた。
しかし,根抵当は,もともと,流動債権に対して,債権枠の範囲内で優先弁済権を与える制度であり,流動中は個々の債権を問題にしないものであり,枠内の個々の債権が滅失しようが,譲渡されようが,何の効力も生じないのは当然である。このことは,先に述べたように,根抵当権と,一般先取特権とを対比することによって,より理解が深まると思われる。一般先取特権は,保護されるべき一定の債権という枠を想定し,その枠に入る債権について優先弁済権を与えるものである点で,根抵当権と類似している。そして,給料債権が労働者からそれ以外の人に譲渡された場合に,「雇用関係の先取特権は,まさに使用人の保護を目的としたものであり,随伴性がないというべきではないか」[道垣内・担保物権(2008)77頁]とされているが,まさに正当であろう。そして,このことは,根抵当が,独立性が強く,物権としての性質が強いのではなく,反対に,債権の性質が強く,債権の性質という枠から外れた債権については優先弁済権を与えないという,一般先取特権に近い性質を示すものということができよう。
抵当権といわれる債権の優先弁済効は,確定の後に問題となるのであり,根抵当の場合にも,確定の後は,個々の債権の譲渡の場合に,当然に,随伴性を有する。なぜなら,担保物権を優先弁済効を持つ債権に過ぎないとみる本書の立場によれば,そもそも,担保物権の随伴性とは,優先弁済効のある債権が譲渡された場合に,譲渡された債権の優先弁済効も保持されるかという,非常に単純な問題に過ぎないからである。
被担保債権の発生・消滅の影響を受けない,(極度額を限度とした)価値支配権としての性質を独立性といい,個々の債権の発生・消滅によって影響を受けず,付従性のない根抵当は,個々の債権からは一定の独立性を有している。
しかし,債権の発生・消滅に対して独立性を有しているのは,いわゆる物権としての根抵当権ではなく,根抵当権における債権枠なのである。根抵当権の場合においても,包括根抵当が禁止されるなど,債権枠自体に対しても,厳密な意味では独立性を有していない。
根抵当権は,担保物権の通有性である付従性・随伴性が否定された,債権からの独立性の高い物権であるといわれることがある。しかし,根抵当権を,債権から独立した物権であると考えるのは,「根」担保の性質を無視した議論であって,明らかな誤りである。その理由を以下に述べる。
根抵当権においては,目的物は特定するが,被担保債権については流動性を許し,債権枠の中にある債権のみに,かつ,確定後に優先弁済効を与えるというシステムが採用されている。つまり,根抵当権とは,一定の取引関係にある債権者と債務者との間に発生する債権のうち,優先弁済効を有する債権と優先弁済効を有しない債権とを「債権枠」という概念を使って峻別するシステムなのであり,枠からはずれた債権には優先弁済効が付与されないというシステムに過ぎない。
例えば,物品の供給契約という枠が設定されている根抵当権の場合,物の売買代金債権は枠に入るが,物の修理代金債権はその枠には入らず,修理代金債権は優先弁済効を取得しない。このように,根抵当権においては,債権枠からはずれる債権には,そもそも,優先弁済効が与えられない。
したがって,最初は枠に入っていた債権が,極度額を超えるという理由でその一部が枠からはみ出したり,譲渡等の理由で枠から出た場合に優先弁済効が与えられないのも,むしろ当然のことである。
従来の説は,初めから債権枠からはみ出している場合と途中から債権枠をはみ出した場合とを区別し,途中から枠をはみ出した債権に注目し,流動性を許さない普通抵当権との単純な比較から,根抵当権の場合には,付従性が緩和されており,随伴性が否定されるという結論を導いている。
しかし,このような議論は,根抵当権のシステム全体を理解していれば出てくるはずのない議論であって,ここでも,担保物権を物権として捉えることの弊害が表れているように思われる。担保物権を物権として捉えようとする従来の考え方には,本来の物権は,付従性や随伴性という債権への従属性から解放されるべきであると考え方が背景に潜んでおり,根抵当権こそが,まさに,債権から独立した物権本来の姿であるかのような思い入れがあるように思われる。
しかし,債権枠と極度額からはずれる債権には優先弁済効を与えないというのが,まさに,根抵当権の基本的な考え方であって,それは,一般先取特権の場合と同様の,優先弁済効を与える債権の資格に関する基本的なルールなのである。
この基本ルールは,物権とは関係のない「根保証」を含めた,「根」担保に共通するところの被担保「債権」の峻別に関するルールであって,根抵当だけに特別のルールではない。つまり,このルールは,法定担保権および約定の「根」担保に共通の債権の特定に関するルールであって,担保物権の通有性または債権の独立性とは無関係の問題であることを理解する必要がある。
このような「根」担保に共通のルールを理解した上で,根抵当権に関しても,債権枠に収まっている債権については,確定を通じてすべての担保に共通の付従性・随伴性が確保されていることを認識すべきであろう。
根抵当権は,一定の範囲に属する不特定の債権(流動債権)を極度額の限度で担保するために設定するものであり,根抵当権者と根抵当権設定者との根抵当権設定契約によって成立する[民法398条の2第1項]。
根抵当権設定契約においては,債権の範囲,債務者,極度額=「債権の枠」を特定しなければならない。これらの項目は,根抵当権の設定において合意しなければならない必須の項目である。これに反して,確定期日の定めは,任意的である。確定の時期は,設定契約で定めなくても,民法398条の19による確定請求または民法398条の20の確定事由が生じることによっておのずと決まる問題だからである。
根抵当権の設定登記は対抗要件であるが,被担保債権の範囲,債務者の変更,確定期日の変更,相続による根抵当関係の存続,共同根抵当の設定・変更は効力発生要件と解されている。
いわゆる包括的根抵当を排除するため,債権の種類が民法398条ノ2第2項および第3項によって以下のように法定されている。
根抵当権者は,確定した元本並びに利息,その他の定期金および債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,根抵当権を行使することができる[民法398条の3第1項]。つまり,極度額とは,元本・利息・遅延利息を含めた最高限度額のことである。極度額を超えた分については,全く担保されない。
根抵当権は,個々の債権が発生・消滅を繰り返しても,極度額という債権枠に収まる債権についての担保は存続する。したがって,根抵当は,長期間にわたって継続することが予想される。その間に,根抵当に関する要素(債権者,債務者,被担保債権の範囲,極度額等)に変更が生じる可能性があり,根抵当の制度は,そのような変更にも対応できるものであることが要求されている。そこで,根抵当の規定は,このような変更に対して,どのような対応をしているのか,以下で詳しく検討する。
元本が確定する前であれば,根抵当権の担保すべき債権(被担保債権)の範囲を変更することができる[民法398条の4第1項2文]。この変更に関しては,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得る必要はないが[民法398条の4第2項],変更の登記は,効力要件として必要である[民法398条の4第3項]。
元本が確定する前であれば,根抵当権の債務者を変更することができる[民法398条の4第1項第2文]。この変更に関しても,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得る必要はないが[民法398条の4第2項],変更の登記は,効力要件として必要である[民法398条の4第3項]。
なお,債務者の変更とは異なり,債権者の変更は,根抵当権の処分[民法398条の11~15]として構成されている。
根抵当権の極度額を変更するには,利害関係を有する者の承諾を要する[民法398条の5]。
元本が確定する前は,債権が譲渡されて債権者が交代しても,債務引受けによって債務者が交代しても,根抵当権はそれに随伴しない。いわゆる随伴性の否定である。
しかし,根抵当権は,個々の債権ではなく,債権の枠に対して優先弁済権を創設するものである。つまり,「入るものは拒まず,去るものは追わず」という精神のもとに債権の流動性を確保しておき,元本確定の時の債権に従って目的物から優先弁済を受ける権利である。したがって,元本の確定前においては,枠内の個々の債権が滅失しようが譲渡されようが,債権枠の優先弁済権に何の効力も生じないのは,むしろ,当然である。
根抵当の本質が債権枠に対する担保権であることを考えると,債権枠がを移転した場合,すなわち,後に述べる根抵当権の譲渡(債権枠を含めた債権の譲渡)における随伴性を考えるのが,本来の随伴性の意味であると考えるべきであろう。また,根抵当における優先弁済権は,確定の後に問題となるのであり,根抵当の場合にも,確定の後は,当然に個々の債権の移転によって随伴性が問題となり,元本確定後は,当然に,随伴性を有する。
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権につき,根抵当権を行使することができない[民法398条の7第1項1文]。元本の確定前に債務者のために,または,債務者に代って弁済をした者は,弁済による代位により債権が弁済者に移転するが,この場合も,その債権につき,根抵当権を行使することができない[民法398条の7第1項2文]。
元本の確定前に債務引受がなされた場合も,根抵当権者は,引受人の債務につき,その根抵当権を行使することができない[民法398条の7第2項]。債務引受けは,債権が,債務者の責任財産から流出する場合の一つであり,元本確定前の個々の債務の流出に関しては,根抵当権は効力を及ぼさない。
元本の確定前に債権者または債務者の交替による更改があるときは,その当事者は,民法518条の規定(担保の移転)にもかかわらず,根抵当権を新債務に移すことができない[民法398条の7第3項]。
これも,一般には,随伴性の否定と解されている。しかし,繰り返し述べてきたように,根抵当権は,個々の債権ではなく,債権の枠に対して優先弁済権を創設するものである。したがって,元本の確定前においては,枠内の個々の債権が滅失しようが譲渡されようが更改されようが,債権枠の優先弁済権に何の効力も生じないのは,むしろ当然である。
根抵当における優先弁済権は,確定の後に問題となるのであり,根抵当の場合にも,確定の後に,個々の債権者または債務者の交替による更改があるときは,随伴性が問題となり,元本確定後は,更改によって抵当権を移転することができる[民法518条]。
根抵当権の元本が確定する前に根抵当権者が死亡した場合または根抵当権設定者が死亡した場合には,本来ならば,債権枠内の債権または債務は,すべて,相続人へと移転し,債権枠はゼロとなる。しかも,その債権枠の下で,新たに元本が生じることはないので,根抵当権は確定するはずである。
それでは根抵当権を設定した意味がなくなるので,一つの可能性としては,相続の時点で元本を確定させ,その上で,確定した通常の債権および抵当権が相続人へと移転すると構成することが考えられる。もう一つの可能性としては,相続の一般承継性を考慮して,債権枠を含めて,すべての債権および抵当権を相続人へと移転すると構成することもできる。
民法は,原則と例外という形で,以上の二つの可能性を生かすことにしている。まず,民法は,根抵当権の元本確定前に相続が開始した場合には,原則として根抵当権は確定することとした。
民法は,根抵当権の当事者が死亡した場合,例外的に,根抵当権の当事者の一方と他方当事者の相続人との間の合意により,債権枠をも移転し,相続によってすでに相続人へと移転している債権または債務および相続開始後の債権または債務につき根抵当権の効力を及ぼすことができることにしている。
この債権枠の移転に関しては,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得る必要はない[民法398条の8第3項による民法398条の4第2項の準用]が,相続の開始後6ヵ月内に登記をしなければ,債権枠の移転の効果は生じない。すなわち,6ヵ月以内に登記をしない場合は,根抵当権によって担保されるべき元本は相続開始の時に確定したものとみなされる[民法398条の8第4項]。したがって,この場合には,相続の瞬間に根抵当権は通常の抵当権とみなされ,抵当権つきの債権または債務が相続人へと移転する。
元本の確定前に根抵当権者につき相続が開始したときは,原則として,根抵当権は確定し,通常の抵当権つきの債権が相続人へと移転するに過ぎない。
しかし,根抵当権者の相続人と根抵当権設定者との合意によって,根抵当権は,相続開始の時に存在する債権のほか,相続人と根抵当権設定者との合意によって定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保させることができる[民法398条の8第1項]。この場合は,債権とともに債権枠も相続人へと移転すると考えると理解が容易である。
相続の場合に相続人に対して,根抵当権を確定させ,優先権のついた債権の移転を受けるか,それとも,債権枠を含めて債権の移転を受けるかの選択を認めた理由は,相続に単純承認と限定承認の選択を認めたのと同じ考慮によるものと思われる。
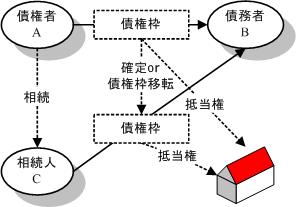 |
| *図118 根抵当権者の相続と元本確定・債権枠移転の選択 |
元本の確定前に根抵当権設定者につき相続が開始したときは,原則として,根抵当権は確定し,通常の抵当権つきの債務が相続人へと移転するに過ぎない。
しかし,根抵当権者と根抵当権設定者の相続人との合意によって,根抵当権は,相続開始の時に存在する債務のほか,抵当権者と根抵当権設定者の相続人との合意によって定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保させることができる[民法398条の10第2項]。この場合は,債務とともに債権枠も相続人へと移転すると考えると理解が容易である。
相続の場合に相続人に対して,根抵当権を確定させ,優先権のついた債務の移転を受けるか,それとも,債権枠を含めて債務の移転を受けるかの選択を認めた理由は,相続に単純承認と限定承認の選択を認めたのと同じ考慮によるものと思われる。
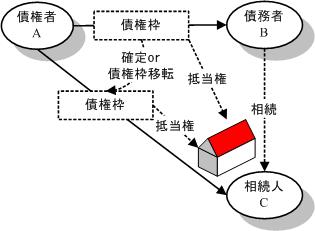 |
| *図119 根抵当権設定者の相続と元本確定・債権枠移転の選択 |
元本の確定前に,根抵当権者である会社が合併したり,根抵当権設定者である会社が合併した場合,一般承継が発生する点では,相続が開始した場合と同様である。
しかし,自然人に一般承継が生じる相続と,法人である会社に一般承継が生じる場合とでは,状況が多少異なる。相続の場合は,被相続人と相続人との人格の違いを認める配慮が求められるが,会社の合併の場合には,通常は,新会社は旧会社のすべての権利・義務を連続的に承継すると考えられており,根抵当の場合も,債権枠を含めてすべての個別債権が移転する取り扱いを原則とするのが適切である。そこで,民法は,会社の合併の場合には,根抵当の債権枠を含めてすべての債権・債務が新会社に移転するのを原則としている[民法398条の9第1項,2項]。
根抵当権者である物上根保証人が元本の確定を請求した場合に,例外的に,確定した抵当権つきの債権・債務の移転を認めることとしている[民法398条の9第3項本文]。ただし,債務者が根抵当権設定者である場合は,確定請求は認められない[民法398条の9第3項ただし書き]。
例外的に認められる確定請求は,根抵当権設定者が合併を知った日から2週間または合併の日から1ヵ月を経過したときは,時効によって消滅する[民法398条の9第5項]。
会社の分割には,以下の2つの形態がある。
会社の分割により,A会社からB会社(分割により設立された会社)又はC会社(営業を継承した会社)への一種の包括承継が生じる。そこで,会社の合併の場合に準じたルールが必要となる。
会社の分割によって,従来A会社が有した根抵当権は,分割時にA会社が有した債権を担保するとともに,新設分割の場合には,その後にA会社及びB会社が取得する債権を担保することになるとし,吸収分割の場合には,C会社が取得する債権を担保することになるとする[民法398条の10第1項]。
これに対して,A会社が根抵当権における債務者である場合には,分割時にA会社が負っていた債務を担保するとともに,新設分割の場合には,その後にA会社及びB会社が負う債務を担保することになるとし,吸収分割の場合には,C会社が負う債務を担保することになるとする[民法398条の10第2項]。
以上の民法398条の10第1項及び第2項は,会社の合併に関する民法398条の9と同様,承継性に重点を置いた解決策を規定している。抵当権設定者である物上根保証人がこの承継性を希望しない場合には,やはり,民法398条の9の場合と同様,設定者に確定請求権を認めるのが相当である。そこで,民法398条の10第3項は,前条第3項~第5項を準用している。
元本の確定前においては,根抵当権者は,転抵当を除いて,第376条1項の抵当権の処分,すなわち,抵当権の譲渡,抵当権の放棄,抵当権の順位の譲渡,抵当権の順位の放棄の4つの処分行為をすることを禁じられる[民法398条の11第1項]。その代わりに,根抵当権の譲渡という別の制度が認められている。
元本の確定前においては,根抵当権者は,第376条1項の抵当権の処分をすることができないが,その根抵当権をもって他の債権の担保すること,すなわち,根抵当権を転抵当とすることは,妨げられない[民法398条の11第1項ただし書き]。
元本の確定前において根抵当を転抵当とする場合,民法377条2項〔転抵当と弁済〕の規定は,原根抵当権者に対する弁済については適用されない。すなわち,元本が確定する前は,原根抵当権者は,転抵当を行った後も,債務者からの弁済を受けることができる。この結果は,元本の確定前には,根抵当を転抵当にすることができないというのと,結果においてほとんど変りがない。
普通抵当で認められている4つの抵当権の処分,すなわち,抵当権の譲渡・放棄,抵当権の順位の譲渡・放棄[民法376条1項2文]は,根抵当では認められていない。その代わりに根抵当権の譲渡という以下の制度が認められている。根抵当権の譲渡に際しては,譲渡人Aと譲受人Dとの間の合意のほか,設定者(BまたはC)の承諾が必要である。
根抵当権者A(極度額1,000万円),債務者B,設定者C,受益者Dとして根抵当権の譲渡の類型を見てみよう。
元本の確定前においては,根抵当権者Aは,根抵当権設定者(BまたはC)の承諾を得て,その根抵当権を受益者Dに譲渡することができる[民法398条の12第1項]。この場合,受益者Dが極度額1,000万円の根抵当権の単独権利者となる。
根抵当権者Aは,その根抵当権を2個の根抵当権に分割して,その1つを,根抵当権設定者(BまたはC)の承諾を得て,受益者Dに譲渡することができる。この場合に,例えば,根抵当権者Aが受益者Dに極度額の6割を譲渡すると,受益者Dは極度額600万円の根抵当権を取得し,根抵当権者Aの極度額は400万円となる。すなわち,その根抵当権を目的とするAの権利は,Dに譲渡した根抵当権について消滅する[民法398条の12第2項]。
根抵当権の分割譲渡をするには,その根抵当権を目的とする権利を有する者(AとDとの合意のほか,設定者(BまたはC),さらに,転抵当権者)の承諾を得なければならない[民法398条の12第3項]。
元本の確定前においては,根抵当権者は,根抵当権設定者の承諾を得て,その根抵当権の一部譲渡をし,抵当権の一部を譲受人と共有(準共有)することができる[民法398条の13]。すなわち,根抵当権者Aと受益者Dが,極度額1,000万円の根抵当権を共有(準共有)する。持分は,当事者の合意がなければ,債権額に比例する[民法398条の14]。
根抵当権の共有者は,各々,その債権額の割合に応じて弁済を受けることができる。ただし,元本の確定前に,これと異なる割合を定めたり,または,ある共有者が他の共有者に先んじて弁済を受けることができる旨を定めたときは,その定めに従う[民法398条の14第1項]。
根抵当権の共有者は,他の共有者の同意を得て,第398条ノ12第1項〔根抵当権の譲渡〕の規定により,その権利を譲渡することができる[民法398条の14第2項]。
根抵当権について民法376条の処分をすることは,転抵当を除いて禁止されているが[民法398条の11],根抵当権者が抵当権の順位の譲渡または放棄を受けることはできる。そして,抵当権の順位の譲渡または放棄を受けた根抵当権者が,その根抵当権の譲渡または一部譲渡を行ったときは,譲受人は,その順位の譲渡または放棄の利益を受けることができる[民法398条の15]。
根抵当権については,転抵当以外の根抵当権の譲渡・放棄,根抵当権の順位の譲渡・放棄を行うことができないが[民法398条の11第1項],根抵当権の順位の変更をすることは可能である。
民法392条,393条が規定する共同抵当は,同一の債権(単数でも複数でもよいが,特定しているもの)を担保する数個の抵当権のことであるため,不特定の債権を担保するものであるから,同一の被担保債権の存在というものを想定することが困難である。しかし,例えば,甲不動産にも乙不動産にも1,000万円の根抵当権を設定して,1,000万円の融資を受けるという共同抵当と同じ形態を当事者が望むこともありうる。
このように,民法392条が適用される共同根抵当を当事者が希望する場合には,その設定(追加的に設定する場合を含む)と同時に,同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨を登記することと,担保すべき「債権の範囲」,「債務者」,「極度額」の3要素について,複数の根抵当権が全く同一である(債権枠の同一性が保持されている)ことを必要とした上で,例外的に認められている[民法398条の16]。
共同根抵当の登記のある根抵当権の担保すべき債権の範囲,債務者もしくは極度額の変更またはその譲渡もしくは一部譲渡は,すべての不動産についてその登記をしなければ,その効力を生じない[民法398条の17第1項]。
共同根抵当の登記がある根抵当権の担保すべき元本は,一つの不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても確定する[民法398条の17第2項]。
数個の不動産の上に根抵当権を有する者は,第398条の16の場合を除くほか,各不動産の代価につき,各極度額に至るまで優先権を行うことができる[民法398条の18]。
例えば,甲不動産に3,000万円,乙不動産に2,000万円の根抵当権を設定し,債権の範囲(債権枠)としての取引の種類を同じにしておくと,その取引から生じる債権が合計額である5,000万円まで担保されることになる。
だだし,それでは,債権枠がその額を超える複数の不動産によって担保されるという危険の分散という利点が生じないため,危険の分散を行うのであれば,実際に生じさせる債権の総額を例えば,3,000万円に抑えるということにしなければならないが,担保設定者からは,合計額の5,000万円に近い額までの融資を要望されることになるため,債権者にとって,危険の分散は確保できなくなるおそれがある。その反面,超過担保となる弊害は減少する。
根抵当権が確定すると,根抵当によって実際に担保される債権が完全に特定され,根抵当としての性質を失い(枠支配の終了,付従性・随伴性の復活),普通抵当に近くなる。例外的に,特定された債権を元本債権とする利息債権は,その後発生するものも,極度額の範囲内で担保される([民法398条の3]参照)。
確定事由と確定の時を列挙すると,以下の通りとなる。
根抵当権者と根抵当権設定者との根抵当権設定契約によって根抵当権の確定期日を定めることができるし,その期日前であれば,当事者は,後順位抵当権者,その他の第三者の承諾を得ることなしに[民法398条の6第2項による,民法398条の4第2項の準用]確定期日を変更することができる[民法398条の6第1項]。ただし,確定期日の変更には,登記が効力要件として必要である[民法398条の6第4項]。
確定期日は,設定の日または変更の日より,5年以内でなければならない[民法398条の6第3項]。
根抵当権設定者は,根抵当権設定の時から3年を経過したときは,担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし,担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは,その期日の到来によって元本が確定する[民法398条の19第1項]。
確定請求がなされたときは,担保すべき元本は,その請求の時から2週間を経過することによって確定する[民法398条の19第2項]。
2003年の民法改正前は,確定事由として,民法398条の20第1項1号において,担保すべき元本の不存在(債権の範囲の変更による特定,取引の終了,その他の事由)が規定されていたが,これが削除された。このため,根抵当権が担保すべき債権が発生する可能性が消滅した場合にも,被担保債権の範囲の変更によってさらにさらに他の取引から生じる債権を担保するものとすることが可能となった。一方で,確定期日の定めのある根抵当権については,5年以内という制限があるものの,客観的に元本発生の可能性がなくなっても元本確定を生じさせることができなくなるという問題が生じている。
根抵当権者が抵当不動産について,競売,担保不動産収益執行,または第372条で準用する第304条の規定による物上代位に基づく差押を申し立てたときには,この競売手続の開始もしくは担保不動産収益執行の開始または差押えが実際になされることを条件に,競売または物上代位の差押えの申立てをしたときに遡って根抵当権が確定する[民法398条の20第1項1号]。
根抵当権者が抵当不動産に対して,滞納処分による差押えをしたときは,その時に根抵当権が確定する[民法398条の20第1項第2号]。
根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあることを知った時から2週間を経過したときに,根抵当権は確定する[民法398条の20第1項第3号]。
この場合において,競売手続の開始または差押えの効力が消滅したときは,担保すべき元本は確定しなかったものとみなされる。ただし,元本が確定したものとして,その根抵当権またはこれを目的とする権利を取得した者の権利を害することはできない[民法398条の20第2項]。
債務者または根抵当権設定者に破産開始の決定があったときは,その時に根抵当権が確定する[民法398条の20第1項第4号]。
この場合において,破産宣告の効力が消滅したときは,担保すべき元本は確定しなかったものとみなされる。ただし,元本が確定したものとして,その根抵当権またはこれを目的とする権利を取得した者の権利を害することはできない[民法398条の20第2項]。
元本の確定後においては,根抵当権設定者は,その根抵当権の極度額につき,普通抵当権において被担保債権に制限があるのと同様,現に存する債務の額とそれ以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額へと減じるよう請求することができる[民法398条の21第1項]。
民法398条の16の共同根抵当の登記がなされた根抵当権の極度額の減額請求については,極度額の減額請求は,1つの不動産ついてすればよい[民法398条の21第2項]。
元本の確定後において,現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者(物上保証人)または抵当不動産につき,所有権,地上権,永小作権もしくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者(第三取得者)は,その極度額に相当する金額を払い渡し,または,これを供託して,その根抵当権の消滅を請求することができる。この場合においては,その払渡し,または,供託は,弁済の効力を有する[民法398条の22第1項]。
民法398条の16の共同根抵当の登記がなされた根抵当権の消滅請求については,1つの不動産についてすればよい[民法398条の22第2項]。また,第380条及び第381条〔抵当権消滅請求権を行使できない者〕の規定は,根抵当消滅請求に準用される[民法398条の22第3項]。
仮登記担保とは,弁済期前の契約を利用して,債務を弁済できない場合には目的物から優先弁済を受ける権利を仮登記によって保全するものである。従来は,仮登記担保について,(1)債務者の債務不履行に備えての債権者による「債権額での売買予約(または停止条件つき売買契約)」,(2)債務者による「時価での買戻・再売買の予約」,(3)債務者による「超過金の清算」又は特約がある場合の「貸金債権と代金債権との相殺予約」[仮登記担保法9条]の組み合わせと考えられてきた。しかし,目的物の所有権を債権者に移転するという点で,担保という性質を逸脱しており,次に述べる譲渡担保の場合と同様,一種の通謀虚偽表示(信託的行為)と見なければならない。すなわち,仮登記担保の目的は,債権回収の方法として,目的不動産の換価・処分権を取得し,目的不動産の価値から優先的に債権を回収し,残りの価値を清算するというものであり,所有権を債権者に帰属させるというのは,譲渡担保の場合と同様,見せかけに過ぎないことを理解する。
仮登記担保法は,当事者の合意が債務不履行の場合には,その時点で,目的不動産の所有権が債権者に移転するとしているにもかかわらず,債権者が清算金の見積もりを利害関係者に通知してから2ヶ月間(清算期間)を経過しなければ所有権は移転しないとして,当事者の合意が見せかけであることを一部見抜いている。しかし,清算期間を経過すると,清算金の支払前に,債権者に所有権が移転すると解したことは,立法者が,当事者の嘘を完全には見抜いていないことを示すものであり,立法の失敗であったことを示している。なぜなら,債権者に目的不動産の所有権の帰属まで認める必要は全くなく,目的不動産の換価・処分権を取得させることで十分であり,処分清算を行った後,清算金を支払った時点で,はじめて所有権を買受人(債権者も含まれる)に移転することで十分だったからである。
ここでは,担保目的での不動産の代物弁済予約に関する判例法理を集大成し,民法学会の叡智を結集して制定された仮登記担保法が,その後ほとんど利用されなくなっている現実を直視し,なぜ,仮登記担保法が実務から敬遠されるに至っているのかを検討する。そして,目的不動産の所有権を債権者に移転することを前提にして,換価処分の方法を帰属清算方式に限定したことが,仮登記担保が利用されなくなる最大の原因であったことを理解する。清算金の支払いがないままに,目的物の所有権を債権者に帰属させることは,一方で,担保設定者の権利を害しており,他方で,市場での処分に先行して,債権者に清算金の支払を義務づけることは,債権者に対する不当な要求であり,両当事者ともに納得のいかない結果が生じているからである。
不動産の担保制度に関しては,動産とは異なり,目的不動産に対する使用・収益権を奪わずに目的不動産を担保に供することができる抵当権という制度が民法によって認められている。しかし,不動産に抵当権を設定した場合には,その実行方法が,競売手続きに限定されている。競売手続きによる場合は,現状では,目的物の市場価格を正確に反映できず,それよりも低い価格でしか売却できないという弱点がある。そこで,実務では,目的物を市場価格で売却するさまざまな方法(仮登記担保,譲渡担保がその典型例)が考案されることになった。仮登記担保は,債務者が債務を任意に履行しない場合に,担保目的である不動産を代物弁済として債権者に目的物の所有権を帰属させ,債権者が目的物を市場で売却することを通じて,結果的に,債権の回収を図るという目的に奉仕するものである。
しかし,停止条件付代物弁済または代物弁済予約の問題点は,債権者が債権額以上に値打ちのある不動産を担保目的物としながら,担保不動産を丸取りし,清算を行わないという行き過ぎた商慣習を生み出した点にある。
これに対しては,まず,学説によって厳しい批判が行われ(米倉明「抵当不動産における代物弁済の予約」ジュリ281号(1963)68頁,椿寿夫『代物弁済予約の研究』有斐閣(1975)がその代表。学説の展開については,井熊長幸「仮登記担保」[星野・講座3(1984)241頁以下]参照),これを受けた判例によって,債権者に清算が義務づけられ,優先弁済権の範囲が,清算によって被担保債権の範囲に限定されることになった(〈最一判昭42・11・16民集21巻9号2430頁〉,〈最大判昭49・10・23民集28巻7号1473頁〉)。
このような学説・判例の動向を踏まえて,1978(昭和53)年に,仮登記担保契約に関する法律(仮登記担保法)が制定され,代物弁済として債権者に所有権の移転が認められる前提として,清算額を適正にするたけの利害関係者への通知の義務づけ[仮登記担保法2条,5条],清算金に対する後順位担保権者の物上代位権の付与[仮登記担保法4条],清算金が支払われるまでの債務者の受戻権の確保[仮登記担保法11条],清算金が適正でない場合の抵当権への移行[仮登記担保法12条]等を骨子とする仮登記担保制度が確立した。
仮登記担保の債権者は,仮登記担保を実行しようと思えば,目的不動産の価値を評価し,債権額との差額である清算額を見積もって債務者および利害関係人に通知しなければならず,その清算金を支払うまでは,目的物の所有権を取得することができない[仮登記担保法2条1項]。適正な清算をするためのやむをえない措置とはいえ,目的物を処分する前に精算金を支払わなければならないことは,債権者にとって大きな負担となる。このため,仮登記担保は,債権者にとって旨味がなくなっただけでなく,むしろ,利用しにくいものとなってしまった。その結果として,仮登記担保法の施行以後,停止条件付代物弁済または代物弁済予約の利用が激減し,ほとんど使われない状態となっている。
学説・判例を集大成する形で成立した仮登記担保法の出現によって,仮登記担保自体が余り利用されなくなってしまったことは皮肉な結果である。このような結果となった原因としては,仮登記担保法が,代物弁済の方形式を尊重して,清算について「帰属清算」方式のみを認め,市場で処分して,売却代金から清算するという方法「処分清算方式」を否定した点にあると思われる。
仮登記担保は,もともとは,「担保ための代物弁済予約」,「停止条件つき代物弁済契約」などと呼ばれていたが,どちらも本質は同じであり,債務者が借金を支払えないときには,不動産で代物弁済することを,債権者が予約または停止条件つきで契約し,その債権者の地位を仮登記によって保全するものである。
1978(昭和53)年に制定された仮登記担保法では,仮登記担保契約とは,「金銭債務を担保するため,その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約,停止条件付代物弁済契約その他の契約で,その契約による権利について仮登記又は仮登録のできるもの」とされている[仮登記担保法1条]。
本来,「担保のための代物弁済予約」は,債務者が債務を返済しない場合に備えて,もしも,債務者が期限内に弁済をしない場合には,おカネの代わりに,モノで弁済してもらうという予約をしておくことである。つまり,通常の代物弁済[民法482条]が債務を決済する一方法であるのに対して,担保のための代物弁済予約は,債権の回収を事前に確保する物的担保として位置づけられている。
したがって,仮登記担保は,通常の代物弁済とは異なり,債権者は,債務者が借金を支払えない場合に直ちに目的不動産の所有権を取得できるのではなく,2ヵ月の清算期間を経なければ所有権は債権者に移転しないし,目的不動産の評価額が債権額よりも大きいときは,清算金を支払わなければ,仮登記を本登記に代えることはできず,不動産の引渡を受けることもできない[仮登記担保法2条]。
また,清算期間が満了して,債権者が本登記請求権および引渡請求権に基づき本登記や目的物の引渡を請求してきた場合に,債務者は,清算金請求権を根拠に同時履行の抗弁権を主張して,債権者の引渡請求および本登記請求を拒絶できる[仮登記担保法3条2項]。
さらに,後順位債権者(後順位仮登記担保権者を除く)が債権者の示した清算金の見積額(それに対して後順位債権者は物上代位できる)に不満であり,清算期間内に競売を請求した場合には,仮登記担保権は抵当権とみなされてしまい,仮登記担保権者は,当然には,目的物の所有権を取得できなくなる[仮登記担保法13条1項]。
抵当権という不動産に適した典型担保が用意されているのに,予約と仮登記を転用して非典型担保を創設しようとする意図はどこにあるのだろうか。かつては,担保としての代物弁済予約を利用する意図としては,以下のものが挙げられていた。
このうち,a(清算の不要)は,昭和49年の最高裁判決〈最一判昭42・11・16民集21巻9号2430頁〉によって清算義務が課せられ,かつ,d(第三者異議の訴え)も否定された。このため,代物弁済予約の旨みは,(b)と(c)とにあるとされることになった。
最一判昭42・11・16民集21巻9号2430頁
貸金債権担保のため,不動産に抵当権を設定するとともに,右不動産につき停止条件付代物弁済契約または代物弁済の予約を締結した形式がとられている場合において,契約時におけるその不動産の価額と弁済期までの元利金額とが合理的均衡を失するようなときは,特別な事情のないかぎり,右契約は,債務者が弁済期に債務の弁済をしないとき,債権者において,目的不動産を換価処分してこれによって得た金員から債権の優先弁済を受け,残額はこれを債務者に返還する趣旨であると解するのが相当である。
債権者に清算義務があると解される場合には,右債権者が,目的不動産を債務者の所有物として差し押えた他の債権者に対して行使しうる権利は,自己の債権についての優先弁済権を主張してその満足をはかる範囲に限られ,たとえ差押前に所有権移転請求権保全の仮登記を経由していても,差押債権者に対して右仮登記の本登記手続をするについての承諾を求め,その執行を全面的に排除することは許されない。
上記のように,(a)と(d)のうまみは判例によって否定されたため,(c)の競売手続の回避が重要な意味をもっていたが,仮登記担保法は,後順位担保権者による競売請求を認めたため[仮登記担保法12条],この点でも債権者のメリットを失わせている。なぜなら,競売手続に持ち込まれると,仮登記担保は,仮登記担保は,担保仮登記のされた時にその抵当権の設定の登記がされたものとみなされ[仮登記担保法13条],抵当権の優先弁済権を有するだけとなり,仮登記担保のメリットはなくなってしまうからである。このように考えると,仮登記担保は,競売手続を免れた場合にのみ,かろうじて,(b)の抵当権の良いとこ取り(抵当権消滅請求の排除,被担保債権の範囲の限定の排除)が仮登記担保のメリットとなっているに過ぎない。
仮登記担保は,もともと,金融機関による利用率は低く,貸金業者,商社,メーカー等がよく利用していたが,上記のように,後順位者による競売請求が認められたこと,根仮登記担保が冷遇された[仮登記担保法14条]こともあって,その利用度は著しく落ち込んでいる。
仮登記担保法が,仮登記担保を抵当権に接近する方向で,しかも,抵当権とは異なる新しい工夫を取り入れて立法したことは,理念的には,利害関係者の調整という点で,一定の調和を達成している。特に,物的担保の本質である清算法理が,流担保効果を本質とする代物弁済予約に対しても整合的に実現された意義は大きい。仮登記担保法は,物的担保に関する清算法理,利害関係者の調整原理を最高度に発展させたものであり,仮登記担保法の規定は,その他の非典型担保(特に譲渡担保)に可能な限り類推適用されるべきであるとの見解が主張されている([鈴木・物権法(1994)297頁],[鈴木・物権法(1994)263頁])ことには,十分な理由がある。仮登記担保法の規定は,抵当権の規定が不十分な場合(例えば,物上代位に関する抵当権と質権との優先順位[仮登記担保法4条1項])には,類推適用されるべきであろう。
それにもかかわらず,仮登記担保の利用が落ち込んでいる真の理由は,不動産譲渡担保の利用頻度が増加していることとの比較によって見えてくる。譲渡担保と仮登記担保とを単純に表面的に比較すると,明らかに仮登記担保の方が優れている。なぜなら,譲渡担保は,債務不履行が生じる前に,最初から債権者が所有権を取得することになっているのに対して(大きな嘘),仮登記担保の場合は,債務不履行があった場合に初めて所有権が債権者に移転することにしており(小さな嘘),法律構成がより抵当権に近づいているからである。しかし,譲渡担保は,その実体と法律構成とが,余りにもかけ離れているために,「大きな嘘」が見破られ,後に述べるように,学説・判例の努力によって,所有権が移転しない方向での理論が積み重ねられ,清算方式に処分清算が認められている点が強みである。この点,仮登記担保は,所有権の移転を契約時ではなく,債務不履行の後としているため,そのような小さな嘘が見破られることなく,債権者への所有権移転という構成が受け入れられてしまった。その結果,仮登記担保は,譲渡担保の場合と異なり,清算方式が,帰属清算しか認められていない。所有権の移転の時期を債務不履行の時点とするという小さな嘘によって,債権者への所有権の移転が受け入れられたために,市場での処分による簡易で妥当な清算をすることが困難となってしまったのである。債権者側の自業自得の感があるものの,所有権が債権者に帰属している以上,帰属清算を義務づけられ,市場での処分の後に清算するとう通常の清算方法が使えないことによって,仮登記担保は,利用率の低迷という結果に陥っているのである。
本来の代物弁済予約は,物の所有権を移転することによって弁済の代わりとするものであり,清算を必要としないはずである。仮登記担保の場合に清算が必要とされるのは,譲渡担保による清算法理の影響を受けたものである。
したがって,仮登記担保契約とは,債権者側による,債務が弁済できない場合に備えての債権額による目的不動産の売買予約(停止条件つき売買契約)と,債務者側による,売買予約に対する清算までの間の時価による買戻特約の追加および売買が実行された場合には,超過金の清算又は貸金債権と売買代金債権を対当額で相殺するという予約とが組み合わされた契約と考えるべきである。また,清算期間の満了によって所有権が債権者に移転した場合でも,清算金を支払うまでは債務相当額を支払って目的物の受戻しをすることができると規定している[仮登記担保法11条]ことは,清算期間が満了して売買が成立し,所有権が買主である債権者Aに移転した後も,清算金支払いまでの間は,債務者である売主Aに,売買の対当額で買い戻す権利を与えるものであると考えることができる。
もっとも,清算期間が終了すると債権者に自動的に所有権が移転するとしていることについては,契約文言にこだわらずに仮登記担保のあるべき姿に即して再構成するならば,以下のように,上記の解釈をさらに一歩進めることができる。
確かに,仮登記担保法は,目的物の所有権は,清算期間の終了によって債権者に移転すると規定している[仮登記担保法2条1項]。この条文の規定にもかかわらず,次のような解釈が可能である。第1に,所有権が自動的に移転するというのは,代物弁済そのものが見せかけに過ぎないのと同様,実は,見せかけ(虚偽表示)に過ぎず,債務者が実際に清算金を受け取るまで,または,処分清算がなされるまでは,受戻しができるとされていること[仮登記担保法11条]の意味を,受戻期間までは,清算期間が続いているのであり,それまで,所有権も債権者に移転しないと解することが可能である。
すなわち,仮登記担保において,目的物の所有権が移転する時期は,仮登記担保法2条にいう清算期間の終了の時ではなく,仮登記担保法11条にいう受戻可能期間の終了のときであり,だからこそ,債務者は,それまで,債務を弁済して所有権の移転を阻止する(いったん移った所有権を受け戻すのではない)ことができるのであり,清算金の支払いと所有権移転との同時履行関係の承認,または,清算金の支払を理由に留置権を行使することができる〈最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁〉という公平性を確保することができるのである。
このように考えると,第2に,債権者は,清算期間満了後も所有権を取得するのではなく,受戻可能の間は,目的物の換価・処分権のみを取得していると解することができる。そうすると,債権者は,目的物を市場で処分し,その売却代金から債権額を控除し,後順位権者(物上代位権者)がいる場合には,残額を供託するか[仮登記担保法7条],後順位権者がいない場合は,残額を債務者に支払うこと,すなわち,処分清算を通じて,清算義務を果たすことが可能となる。もっとも,市場での目的物の売却に際しては,債権者は事情を説明し,目的物の所有権に関する登記は,いったん,債権者に移るが,その後,買受人に移転することを約することになろう。
このように解することによって,債務者が,清算期間の終了後も,処分が完全に終了するまで,いわゆる買戻しができるという規定[仮登記担保法11条]も,特別の規定ではなく,処分清算のプロセスにおける当然の規定(清算期間後であっても,債務者が清算金の支払いを受けるまでは同時履行の関係を認める)として理解することができるようになるばかりでなく,受戻しが5年の消滅時効に服することの不当性も明らかとなる。
このような解釈は,仮登記担保法が予定していた趣旨とは異なる。しかし,仮登記担保法の利用率の激減を通じて,立法の不都合が明らかとなった現在,可能な限りの解釈技術を駆使して,仮登記担保法の運用を,帰属清算から処分清算への転換を行うことが求められているといえよう。そのような努力なしに現状を放置すれば,仮登記担保法の利用は,今後,ますます衰退の一途をたどることになるであろう。
仮登記担保は,当事者の合意によって成立し,その効力は,仮登記によって公示される。仮登記担保の設定は,第三者(物上保証人)によってもなしうる。債権は,金銭債務に限定され[仮登記担保法1条],目的物も,土地または建物が一般的であるが,仮登記をなし得るものであれば,土地・建物以外でもよい[仮登記担保法20条]。この仮登記は,通例,「所有権移転請求権保全の仮登記」[不動産登記法2条2項]である。この登記は,所有権に関する登記として登記簿の甲区欄に記載される。仮登記担保は,単独で用いられることもあるが,実際には,同じ債権を担保するために,抵当権・根抵当権と併用して設定されることが多い。
仮登記担保は,特定額の債権のためだけでなく,根担保として設定される場合も少なくない。判例は,特別の事情がない限り,根仮登記担保権者は物件の適正評価額全部を把握できると解していたが,仮登記担保法は,強制競売等においては,その効力を有しない[仮登記担保法14条]としている。仮登記担保においては,債権額を登記する方法が存在せず,包括根抵当と同様,他の債権者を害するというのがその理由とされている。
仮登記担保の実行プロセスを優れた図解である[近江・講義Ⅲ(2007)265頁]に倣って作成した図96に従って仮登記担保の実行を説明する。ただし,〔イタリック〕の部分は,本書で述べた仮登記担保のあるべき姿に即して解釈した筆者の独自の見解である。
仮登記担保法は,清算期間を清算金の支払いとは無関係に,機械的に2ヶ月と定めている。これに対して,本書の立場は,清算金の支払いまでが真の清算期間であり,債権者は,いわゆる清算期間(第1期)の2ヶ月が過ぎれば処分清算をすることが可能となるとともに,債務者も,清算金の支払いがある(第2期)までは,受戻ではなく弁済によって債務と仮登記担保を消滅させることができるというものである。
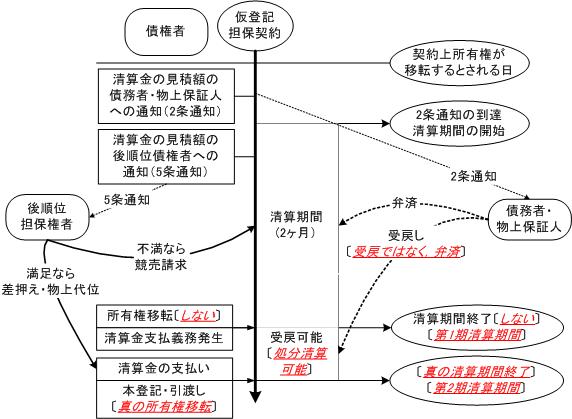 |
| *図120 仮登記担保の実行の流れ 注:[近江・講義Ⅲ(2007)280頁]に依拠して作成したもの 〔イタリック〕は,筆者の独自の解釈 |
いわゆる代物弁済の予約(買戻付款つきの売買予約)の場合は,債務者が期限に弁済をしない場合に,債権者が仮登記担保の設定者に対して予約完結の意思表示をする。いわゆる停止条件つき代物弁済契約(停止条件つき・買戻付款つきの売買契約)の場合は,債務者の債務不履行によって条件が成就するので,特別の意思表示は不要である。もっとも,仮登記担保は抵当権の設定と併用されることが多いので,いずれにせよ,抵当権の実行を選ぶか仮登記担保を選ぶかの意思表示が必要となる。
仮登記担保の効力としての所有権移転を実現するためには,債権者は,さらに,仮登記担保法2条1項に基づく通知をする必要がある。
仮登記担保契約が目的物の所有権の移転を目的とするものである場合には,予約を完結する意思を表示した日,停止条件が成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に,債権者が「清算金の見積額(清算金がないと認めるときは,その旨)」をその契約の相手方である債務者又は第三者(物上保証人)に通知し,かつ,その通知が債務者等に到達した日から2ヵ月(清算期間)を経過しなければ,その所有権の移転の効力は生じない[仮登記担保法2条1項]。
本書の立場では,2条通知は,清算手続きを透明にするための手続きであり,2条通知の到達からの2ヶ月間を,清算金の見積額が公正に決定されるための利害関係人による監視期間と位置づけている(第1期清算期間)。つまり,この期間が終了しても,条文の文言とは異なるが,所有権は債権者には移転しない。しかし,この期間の終了によって,債権者は,競売ではなく,処分清算,すなわち,市場での換価・処分を行うことができるようになる(第2期清算期間)。これが,仮登記担保法の下における処分清算の実現という,立法論に近い解釈論である。そして,換価・処分により買受人が目的物を買い受け,清算金額が支払われたときにはじめて,所有権が買受人に移転する。これは,競売の場合に,買受人の代金支払いによって物件の所有権が移転する[民事執行法79条]のと同じ原理である。このような解釈論は,一見,無謀のように思われるかもしれないが,不動産譲渡担保をコントロールするためには,極めて有効な解釈であると考えている。
この通知は,以下の2点を明らかにしてしなければならない[仮登記担保法2条2項]。
債務者・物上保証人に対する清算金の見積額の通知(2条通知)が到達してから2ヵ月間は清算期間とされており,その間は,所有権は債権者に移転せず,後順位債権者との利益調整が行われるが,この期間は,債務者にとっては,弁済の猶予期間としての意味をもっている。
本書の立場では,この期間を清算期間(第1期)と考えている。この期間が債務者にとって弁済の猶予期間となることは当然であるが,この期間が終了した場合でも,その後に清算金が支払われるまでは,債務者は物件の引渡を拒絶することも(同時履行の抗弁権),弁済によって担保権を消滅させることもできるのであるから,債務者にとっては,決定的な期間ではない。この期間は,むしろ,債権者が提示した清算金の見積額が公正なものかどうかを後順位担保権者が吟味し,実行手続きを通常の処分清算にするか,それとも,例外的な競売手続にするかを決定するための期間として位置づけるべきである。
さらに,債務者・物上保証人は,清算期間経過後であっても,清算金支払債務の弁済を受けるまでは,債権等の額に相当する金銭を債権者に提供して,土地等の所有権の受戻しを請求することができる[仮登記担保法11条本文]。ただし,清算期間が経過した時から5年が経過したとき,又は第三者が所有権を取得したときは,この限りでない[仮登記担保法11条ただし書き]。
本書の立場では,この期間を受戻期間ではなく,第2期清算期間と考えている。この期間中に,一方で,債権者は,帰属清算ではなく,物件の換価・処分権に基づいて,市場での換価・処分を行うことができる。他方で,債務者は,清算期間(第1期)の場合と同様,受戻しではなく弁済によって担保権を消滅させることができる。これに対して,5条通知を受けた後順位担保権者は,もはや,競売を請求することはできない。
(i) 後順位債権者への通知(5条通知)
清算金の見積額の通知が債務者等に到達した時において,担保仮登記後に登記・仮登記がされている先取特権,質権若しくは抵当権を有する者又は後順位の担保仮登記の権利者があるときは,債権者は,遅滞なく,これらの者に対し,(1)「2条通知をした旨」,(2)「2条通知が債務者等に到達した日」および(3)「2条通知によって債務者等に通知した事項」を通知しなければならない[仮登記担保法5条1項]。この5条通知を受けなかった後順位債権者は,清算期間経過後も競売を請求できると解されている〈最二判昭61・4・11民集40巻3号584頁〉。
最二判昭61・4・11民集40巻3号584頁
仮登記担保権者は,仮登記担保契約に関する法律2条1項所定の債務者又は第三者に対する通知をし,その到達の日から2月の清算期間を経過したのちであっても,同法5条1項所定の通知をしていない後順位担保権者に対しては,仮登記に基づく本登記の承諾請求をすることはできない。
仮登記担保の目的不動産の競売による売却代金で共益費用たる執行費用,仮登記担保権者の被担保債権及び後順位担保権者の被担保債権に優先する債権を弁済すれば剰余を生ずる見込みのない場合であっても,右後順位担保権者に対する仮登記担保契約に関する法律5条1項所定の通知は不要とはならない。
(ii) 後順位債権者の立場の選択
これらの通知(5条通知)を受けた後順位債権者は,債権者が提示した清算金の見積額で満足する場合(例えば,自己の債権額が清算金によって弁済を受けうる場合)は,その清算金の上に物上代位を行うことによって優先弁済権を確保することができるし,債権者が提示した清算金の見積額に不満の場合には,清算期間内に限り競売請求をすることができる。
仮登記担保権者から清算額の見積額の通知(5条通知)を受けた先取特権,質権又は抵当権を有する者(後順位の担保仮登記権利者を除く)は,清算期間内は,これらの権利によって担保される債権の弁済期の到来前であっても,土地等の競売を請求することができる[仮登記担保法12条]。
競売手続が開始されると,仮登記担保は抵当権とみなされる。すなわち,仮登記担保は,担保仮登記のされた時にその抵当権の設定の登記がされたものとみなされ[仮登記担保法13条1項],もはや目的物をまるごと把握することはできなくなり[仮登記担保法15条1項],優先弁済権を取得するに過ぎなくなる。最高裁49年判決では,仮登記担保権者が先に私的実行を始めれば後順位抵当権者の競売を排除できるとしていたので〈最大判昭49・10・23民集28巻7号1473頁〉,この点でも,仮登記担保の旨みは小さくなったといわれている[内田・民法Ⅲ(2005)553頁]。
もっとも,強制競売の開始決定が,清算金の支払の債務の弁済後(清算金がないときは,清算期間の経過後)にされた申立てに基づくときは,担保仮登記の権利者は,不動産の所有権を取得しており,したがって,その土地等の所有権の取得をもって差押債権者に対抗することができる[仮登記担保法15条2項]。
(i) 物上代位と差押え
債権者から5条通知を受けた後順位債権者(仮登記後に登記がされた先取特権,質権又は抵当権を有する者)は,その順位により,債務者等が支払を受けるべき清算金(同項の規定による通知に係る清算金の見積額を限度とする。)に対しても,物上代位の手続により,その権利を行うことができる。この場合には,清算金の払渡し前に差押えをしなければならない[仮登記担保法4条1項]。
物上代位の目的物は,債務者が支払を受けるべき清算金払渡請求権であり,上記のように,清算金の見積額がその限度とされている[仮登記担保法8条2項]。
(ii) 清算金の支払に関する処分の禁止
清算金の支払を目的とする債権については,清算期間が経過するまでは,譲渡その他の処分をすることができない[仮登記担保法6条1項]。
清算期間が経過する前に清算金支払債務が弁済された場合には,その弁済をもって後順位債権者に対抗することができない。後順位債権者への通知(5条通知)がされないで清算金支払債務が弁済された場合も,同様とする[仮登記担保法6条2項]。
(iii) 清算金の供託
債権者は,清算金の支払を目的とする債権につき差押え又は仮差押えの執行があったときは,清算期間が経過した後,清算金を債務履行地の供託所に供託して,その限度において債務を免れることができる[仮登記担保法7条1項]。
供託がされたときは,債務者等の「清算金払渡請求権」に代えて,債務者等の「供託金の還付請求権」につき,同項の差押え又は仮差押えの執行がされたものとみなされる[仮登記担保法7条2項]。
債権者は,仮登記担保法15条1項の場合(競売開始決定によって仮登記担保権者が本登記を請求できない場合)を除き,供託金を取り戻すことができない[仮登記担保法7条3項]。
債権者は,債務者等のほか,差押債権者又は仮差押債権者に対しても,遅滞なく,供託の通知をしなければならない[仮登記担保法7条4項]。
(i) 清算金の額の決定
債権者は,清算期間が経過した時の土地等の価額がその時の債権等の額を超えるときは,その超える額に相当する金銭(清算金)を債務者等に支払わなければならない[仮登記担保法3条1項]。ここにいう土地等の価額とは,債務者に通知した見積額ではなく,清算期間経過時の客観的な価額である。もっとも,債務者・物上保証人が争わないときは,清算金はその見積額によって定まる。
(ii) 清算金の見積金額の通知の拘束力
債権者は,清算金の額が通知した清算金の見積額に満たないことを主張することができないし,後順位債権者も,清算金の額が見積額を超えることを主張することができない[仮登記担保法8条]。
(iii) 土地等の価額が債権等の額を超えないときの債権の一部消滅
通常の場合とは反対に,清算期間が経過した時の土地等の価額がその時の債権等の額に満たないときは,債権は,反対の特約がない限り,その価額の限度において消滅する[仮登記担保法9条]。つまり,債務者としては,相殺予約の完結権を行使しなければ,それで債務をすべてまぬかれることができる。
この清算金の支払債務と土地等の所有権移転の登記及び引渡しの債務の履行については,同時履行の抗弁権の規定が準用される[仮登記担保法3条2項]。
本来,清算の方法には,債権者が目的不動産を第三者に処分し,その売却代金の中から優先弁済を受けるという「処分清算」と,債権者が不動産を取得し,それを自ら評価してその超過額を債務者に返還するという「帰属清算」がある。しかし,仮登記担保の場合には,同時履行の抗弁権が認められていることから,帰属清算方式が原則とされることになった。
もっとも,仮登記担保権者が清算金を支払わないまま不動産を第三者に譲渡したときは,債務者・物上保証人は,留置権をもって不動産の譲受人に対抗できる〈最一判昭58・3・31民集37巻2号152頁〉。したがって,処分清算方式をとったとしても,債務者・物上保証人は保護されることに変わりはない。
これらの規定に反する特約で,債務者等に不利なものは,清算期間が経過した後になされたものを除き無効である[仮登記担保法3条3項]。清算期間経過後の債務者に不利な特約を許すのは,流質契約の場合と同様の趣旨に出るものである。ただし,債権者が,あらかじめ本登記に必要な書類を設定者から預かり,清算金を支払わずに本登記をした場合については,清算期間経過後に本登記を行った場合でも,債務者・物上保証人は,同時履行の抗弁権を奪われており,登記抹消請求権を有すると解されている。
債務者・物上保証人が清算金の見積額に満足しており,後順位債権者がない場合には,債権者は,清算期間経過後に清算金を支払って,債務者または物上保証人に対して,仮登記を本登記にするから手続に協力するよう要求することができる。
(i) 清算金の供託から1ヵ月を経過する前の場合
債権者が仮登記をした後に目的不動産を担保にとった後順位債権者に対しては,清算金を供託してから1ヵ月を経過する前は,仮登記担保権者は,不動産登記法の原則に則り,その登記を抹消する手続に協力するよう要求できる。これを本登記承諾請求という。
この場合,仮登記担保権者が仮登記を本登記に改めるには,まず,2条通知が債務者等に到達した時において,担保仮登記に基づく本登記につき登記上利害関係を有する第三者があるときは,債権者は,遅滞なく,その第三者に対し,2条通知をした旨,および2条通知により債務者等に通知した債権等の額を通知しなければならない[仮登記担保法5条2項]。
次に,仮登記担保権者は,不動産登記法の規定に従い,後順位債権者の承諾書または後順位債権者に対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない[不動産登記法105条による146条1項の準用]。
(ii) 清算金の供託から1ヵ月を経過した後の場合
担保仮登記の権利者は,清算金を供託した日から1ヵ月を経過した後にその担保仮登記に基づき不動産登記法105条1項に規定する本登記を申請する場合には,同項において準用する同法第146条1項の規定にかかわらず,後順位債権者(後順位仮登記担保権者を除く)が第4条1項の差押えをしたことおよび清算金を供託したことを証する書面をもってこれらの者の承諾書に代えることができる[仮登記担保法18条本文]。
いずれにせよ,後順位債権者が清算金の見積額に満足せず,競売を請求した場合,すなわち,本登記の申請に係る土地等につきこれらの者のために担保権の実行としての競売の申立ての登記がされているときは,本登記請求はできない[仮登記担保法18条ただし書き]。競売手続においては,仮登記担保権者は抵当権者とみなされるに過ぎないからである[仮登記担保法13条1項]。
担保仮登記がされている土地等に対する強制競売,担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行手続(以下「強制競売等」という。)においては,その担保仮登記の権利者は,他の債権者に先立って,その債権の弁済を受けることができる。この場合における順位に関しては,その担保仮登記に係る権利を抵当権とみなし,その担保仮登記のされた時にその抵当権の設定の登記がされたものとみなされる[仮登記担保法13条1項]。
所有権の移転に関する仮登記がされている土地等に対する強制競売又は担保権の実行としての競売において配当要求の終期が定められたときは,裁判所書記官は,仮登記の権利者に対し,その仮登記が担保仮登記であるときはその旨並びに債権(利息その他の附帯の債権を含む。)の存否,原因及び額を,担保仮登記でないときはその旨を配当要求の終期までに執行裁判所に届け出るよう催告しなければならない[仮登記担保法17条1項]。
差押えの登記前にされた担保仮登記に係る権利で売却により消滅するものを有する債権者は,前項の規定による債権の届出をしたときに限り,売却代金の配当又は弁済金の交付を受けることができる[仮登記担保法17条2項]。
担保仮登記の権利者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは,その満期となった最後の2年分についてのみ,同項の規定による権利を行うことができる[仮登記担保法13条2項]。
担保仮登記の権利者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において,その最後の2年分についても,これを適用する。ただし,利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない[仮登記担保法13条3項]。
仮登記担保契約で,消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は,強制競売等においてはその効力を有しない[仮登記担保法14条]。
土地及びその上にある建物が同一の所有者に属する場合において,その土地につき担保仮登記がされたときは(建物のみに担保仮登記がなされた場合を除く),その仮登記に基づく本登記がされる場合につき,その建物の所有を目的として,地上権ではなく,土地の賃貸借がされたものとみなされる[仮登記担保法10条1文]。この場合において,その存続期間及び借賃は,当事者の請求により,裁判所が定める[仮登記担保法10条2文]。建物のみに担保仮登記をする場合について規定がなされていないのは,当事者間で条件つきで土地利用権を設定するのが通常であるとの理由によるものとされている。
民法の不備から必然的に生じた動産譲渡担保を取り上げ,譲渡担保を担保物権と考えると,それは,物権法定主義に反しないのか,質権における占有改定の禁止との関係で,譲渡担保が第三者に対抗できるとする理由は何なのか,実質が担保であるにもかかわらず,所有権を移転するという譲渡担保の意思表示は,通謀虚偽表示として無効となるのではないのか等の問題を検討し,譲渡担保に関する基本的な考え方を明らかにする。
そして,動産譲渡担保,不動産譲渡担保,債権譲渡担保のそれぞれについて,判例法理の展開過程を理解する。その上で,民法における動産質権の簡易の実行方法[民法354条],仮登記担保法の諸規定,債権集合譲渡担保に関する判例法理〈最一判平13・11・22民集55巻6号1056頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第99事件)〉等を参照しながら,譲渡担保に関する法律を制定するとしたら,どのような点に留意すべきかを検討する。そのことを通じて,譲渡担保の要件と効果のあるべき姿を追求する。
譲渡担保は,抵当権の不備を埋めるために作り出された実務慣行を判例が追認するという歴史的な経過をたどっている。したがって,譲渡担保を理解するためには,「抵当権(広い意味では,現行民法の担保物権の制度全体)にいかなる不備があるのか」という観点から眺めてみるとよい。そうすると,難解とされる譲渡担保を比較的容易に理解することができる。そこで本章では,まず,譲渡担保の発展を抵当権の不備という観点から概観する。その後,動産譲渡担保,不動産譲渡担保,債権譲渡担保の順で,それぞれの譲渡担保の特色について考察することにしよう。
債務者が物の占有を債権者に移転せず,自ら使用・収益をしながら,それを担保に供して融資を得ようとするならば,民法上は,その物の上に抵当権を設定するしかない。質権の場合には,債務者は債権者に目的物を引渡さなければならないため[民法344,345条],債務者が使用・収益をしながら融資を受けるということができないからである。ところが,債務者が目的物の使用・収益をすることを認める抵当権は,不動産または不動産物権に限定されており[民法369条],動産に抵当権を設定することは,民法上は認められていない。
しかし,これでは,企業用の動産を担保化しようという実務の要請に応えることができなくなってしまう[民法の立法上の不備)。そこで実務家は,動産に対する抵当を実現するため,法の裏をかく戦略をとることになる。すなわち,当事者間で,「担保の目的で物の所有権を移転する」という契約を結ぶことによって,動産に対する抵当を実現しようとする。つまり,簡易な動産抵当を実現するために,実務では,目的(当事者の真意)は担保であるにもかかわらず,手段(表示による外観)は担保の目的を超えて,所有権の移転をする(信託的行為)という方法が利用されるようになる。したがって,譲渡担保の合意には,広い意味での通謀虚偽表示[民法94条]が存在することになる。
通謀虚偽表示というと,譲渡担保契約という法律行為自体が無効となるのではないかと考える人がいる。しかし,結果はそうではない。通謀虚偽表示は,当事者間においては,当事者の真意(意思)を優先して,外形(表示)を無効とする制度であり[民法94条1項],ただし,その無効な外形(表示)である所有権の移転を善意(・無過失)で信じた第三者が出現した場合には,当事者は,その表示(所有権移転)の無効を善意(・無過失)の第三者に対抗できなくなる[民法94条2項]。すなわち,善意(・無過失)の第三者が債権者から担保目的物を譲り受けた場合には,債務者は,自らの所有権を第三者に主張できなくなるのである。
ここで問題としている譲渡担保の場合,当事者の共通の意思を探求すると,それは,「譲渡は見せかけであり,本来の意図は,目的物を使いながらそれを担保にする」というものである。通謀虚偽表示の考え方に即して言い換えると,譲渡担保における表示(外形)は,財産権の移転だがその意思(真意)は,担保権の設定であるというものである。この問題に関して,通謀虚偽表示について浅い理解しかできず,「通謀虚偽は無効である」とだけ覚えている人にとっては,そのまま「譲渡担保は無効である」と考えるか,反対に,それを有効と考える場合には,「譲渡担保は通謀虚偽表示ではない」といわざるを得ない。
判例も,譲渡担保は通謀虚偽表示ではないから,無効ではなく,信託的行為として有効であるとしている(〈大判大3・11・2民録20輯865頁〉,〈大判大8・7・9民録25輯1373頁〉)。しかし,通謀虚偽表示について深い理解をしている人にとっては,「譲渡担保は,通謀虚偽表示だからこそ,担保として有効である」という,別の答えを出すことができる。つまり,通謀虚偽表示について深い理解をしている人にとっては,譲渡担保は通謀虚偽表示であると考えても,何の支障もないのである。
その理由は,民法94条1項により,通謀虚偽表示が無効であるとされる理由は,有効と見せている外見(表示)よりも,無効とする当事者の内心の共通意思が尊重される結果だからである。したがって,譲渡担保の場合においても,当事者間では,表示(目的物の譲渡)よりも真意(目的物に対する担保権の設定)が優先される。すなわち,一方で表示(財産権の譲渡)が無効となり,他方で真意(担保権の設定)が有効となるので,有効な担保権の設定が認められることになるのである。
もっとも,善意(・無過失)の第三者が出現した場合には,取引の安全を確保するため,当事者間の真意よりも,表示が優先される。すなわち,善意(・無過失)の第三者が出現した場合には,譲渡担保は,担保権の設定ではなく,財産権が移転しているとみなされても仕方がない。したがって,譲渡担保を第三者に対抗するためには何らかの公示手段(明認方法など)を講じる必要があるという適切な結論を導き出すことができるのである。このことは,以下の表のようにまとめることができる。
| 表示と意思 | 効果 | 善意の第三者との関係 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通常の通謀虚偽表示 | 例えば,所有権の移転の表示 | 法律行為の無効 | 表示は無効 | 表示の無効を対抗できない |
| 真意は,所有権の移転を無効とする | 真意が尊重される | 真意が否認される | ||
| 信託的行為 (例えば譲渡担保) |
例えば,所有権の移転の表示 | 有効な信託的行為 (有効な担保権の設定) |
表示は無効 | 表示の無効を対抗できない |
| 真意は,信託的行為(担保権の設定) | 真意が尊重される | 真意が否認されうる | ||
先に述べたように,ある物を譲渡担保にする場合というのは,目的物の所有権を移転したいわけではなくて,抵当権を設定しようとして,他によい方法がないので,売買契約をしてしまうというものである。
例えば,ピアノ教室の先生が融資を得るためにピアノを質に入れる場合を想定してみよう。質権を設定する場合には,目的物を債権者に引き渡さなければならない[民法344条]。しかも,占有改定は許されない[民法345条]。しかし,これではピアノ教室を継続することはできない。そうではなく,ピアノ教室の先生としては,ピアノを使いながら融資をうけ,返せない場合にはピアノを持っていってくださいという契約にしたい。ところが,こういう制度は日本にはない。自動車のようにピアノにも動産抵当という制度があれば,ピアノを使いながら融資を受け,ピアノで稼いだお金で借金を返すことができる。しかし,わが国には,特別法で認められている場合にしか,動産抵当は利用できないのである。それでは,どうしたらよいのだろうか。
ピアノの先生としては,まず,目的物を債権者に売ったことにする。そして,売買代金を受け取る。しかし,この名目上の代金こそが,実は融資金(借金)なのである(第1の通謀虚偽表示)。次に,ピアノを売ってしまうと,自分が使えない。そこで,売買によってピアノの現在の所有者ということになっているお金の貸主から,ピアノを借りたことにして,賃料を払わなければならない。しかし,この名目上の賃料こそが,実は借りたお金の利子なのである(第2の通謀虚偽表示)。さらに,ピアノ教室が順調に行って,借りたお金を返済しきった場合には,買い戻し(厳密には,再売買の予約)が付いているので,ピアノは無事帰ってくる(第3の通謀虚偽表示)。不幸にも,お金を返せなくなったら,買戻しはできないため,ピアノをあきらめて,債権者に持っていってもらうということになる。もっとも,債権者は,ピアノが欲しいわけではないので,それを売り払って債権の回収に当てるというわけである。
譲渡担保については,担保のための所有権移転が通謀虚偽表示なのかどうか,通謀虚偽表示だとするならば,その効力は無効となるのか,当事者の間では,担保としての効力が認められ,所有権は移転しないが,第三者との関係では,やはり,所有権は移転するのかをめぐって,論争が繰り広げられてきた。
しかし,譲渡担保は,真意(担保権(設定者に使用・収益権を残す担保権)の設定)と表示(所有権の移転)とが食い違っている点,すなわち,当事者が所有権移転という外形を取りつつ,目的物に担保を設定することを合意しているという点で,通謀虚偽表示(信託的行為)であり,外形としての所有権の移転は無効であり(所有権的構成の否定),譲渡担保は,質権とは異なり,抵当権と同様,設定者から使用・収益権を奪わない担保権であり,かつ,その実行は,仮登記担保とは異なり,市場での売却を行うという処分清算型の物的担保として構成すべきであるというのが,本稿の結論である。
通説は,譲渡担保には,債権者が設定者の使用・収益権を奪うものと,設定者に使用・収益権を継続させるものとの2種類があるとする。しかし,債権者が設定者の使用・収益権を奪うのであれば,本来の売買であるか,質権の設定であるかであろう。そうだとすると,それを譲渡担保として考察する必要はないので,本書では取り上げない。担保のために所有権を取得するという譲渡担保の特質から考える限り,設定者は当然に使用・収益権を継続することができることを原則に考えるべきである[山野目・物権(2009)315頁]。
譲渡担保は,すでに述べたように,質権とは異なり,債務者に目的物の使用・収益を認めるという担保を設定するために,所有権を移転するという外形をとるものである。譲渡担保は,真意と外形が異なる合意に他ならず,その性質は,通謀虚偽表示[民法94条]であるから,当事者間では外形(表示)よりも真意(意思)が優先する(表示・外形の無効,その結果としての真意の無効)。したがって,真意としての担保権の設定(債務者に目的物の使用・収益を許すが,債務者が債務を履行しない場合には,債権者は,目的物を処分することができ,その売得金の中から,他の債権者に先立って優先弁済を受けることができるという権利の設定)が有効となり,外形としての所有権の移転は無効となる。
もっとも,当事者間でも,買戻特約付きの真正の売買か,譲渡担保かで争いが生じる場合がありうる。そのようなに,目的不動産の占有の移転が伴わない場合には,判例は,売買ではなく,譲渡担保であると推定している〈最三判平18・2・7民集60巻2号480頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第95事件)〉。
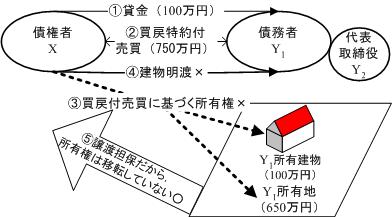 |
買戻特約付売買契約の形式が採られていても,目的不動産の占有の移転を伴わない契約は,特段の事情のない限り,債権担保の目的で締結されたものと推認され,その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である。 |
| *図121 最三判平18・2・7民集60巻2号480頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)第95事件 |
譲渡担保は,目的物に処分清算を伴う動産抵当を設定するものであり,所有権は,債務者に残されたままであり,内部的にも対外的にも移転しない。もっとも,譲渡担保は,通謀虚偽表示であるから,外形(所有権移転)を善意(・無過失)で信頼した第三者には,所有権移転が無効であることを対抗できない。したがって,一方で,担保権者が目的物を処分し,第三者が善意・無過失である場合には,担保設定者は,所有権を失う危険性がある。他方で,担保設定者は,占有を継続しているので,目的物が動産の場合,担保設定者を所有者だと善意・無過失で信じた第三者に対しては,担保権者は追及できず,担保権を失う危険性がある。つまり,譲渡担保の効力を第三者に対抗するためには,目的物に明認方法を講じるなど,対抗要件を備える必要が生じることになる。しかし,このことは,譲渡担保によって目的物の所有権が譲渡担保の設定の時点から,確定的に,債権者に移転することを意味するものではない。目的物の所有権は,債務者に帰属したままであり,善意(無過失)の第三者が現れたときに,所有権移転が無効であることを主張できなくなるに過ぎない。目的物に明認方法等が施されている等の事情により,第三者が譲渡担保の存在を知りうる場合には,所有権は,依然として,債務者が保持する。
債務者が債務を履行しない場合には,債権者は,譲渡担保を実行して,他の債権者に先立って優先弁済を受けることができる。これは,譲渡担保が,動産抵当としての効力を有するからである。もっとも,動産抵当といっても,それは特別法上の制度であり,民法では動産抵当は認められていないために,その実行手続きは,通常の抵当権のように競売によることはできない。したがって,どのような手続きによって譲渡担保を実現するかは,解釈学の課題となる。
その場合に参考にされるべき条文は,1つは,動産について,競売によらずに担保権の簡易な実行を認めている民法354条(動産質権の簡易な実行)であり,もう1つは,不動産について,帰属清算を認めている仮登記担保法の一連の規定[仮登記担保法2条以下],債権について,直接取立てを認めている民法366条の規定,最後に,抵当権の簡易な実行を定めている代価弁済[民法378条]および抵当権消滅請求[民法379-386条]の規定である。これらの問題については,動産譲渡担保,不動産譲渡担保,債権譲渡担保の箇所において,詳しく論じるので,ここでは,その概略を述べておくことにする。
譲渡担保の実行手続き[民法354条]においては,目的物の所有権は債務者にあること,債権者は,担保権者として目的物を処分して,その売買代金の中から他の債権者に先立って優先弁済を受ける権利を有するにとどまるという点が確認されなければならない。質権の簡易な実行手続きについては,流質[民法349条]の場合とは異なり,所有権が債務者に帰属したまま,債権者に目的物の処分権を与えたものと解すべきであることはすでに述べた。譲渡担保の実行手続きも,同様にして,所有権は債務者に帰属することを前提にして検討されるべきである。
確かに,譲渡担保における所有権の帰属については,所有権的構成と担保的構成とで争われている。原則として所有権的構成をとりながら,設定者の下に所有権マイナス担保権という物権的権利(設定者留保権)が残るとする折衷説[道垣内・担保物権(2008)299頁]がある。また,担保的構成をとる学説の中にも,抵当権説[米倉・譲渡担保(1976)43頁以下],抵当権とは異なる一種の制限物権が帰属するという説[高木・担保物権(2005)334頁]がある。
しかし,譲渡担保における所有権の移転は,すでに述べたように,見せ掛けに過ぎない。第1に,所有権を取得する譲渡担保権者には,目的物を所有したいとの真意はなく,譲渡担保の設定後も,譲渡担保設定者のみが目的物の使用・収益権を有する。第2に,売買代金名目で譲渡担保権者から交付される金銭は,当事者の意図からすれば,明らかに貸金であり,所有権の移転の対価とは考えられていない。第3に,目的物の使用・収益の対価(賃料)の名目で支払われる金銭は,実は,貸金の利息であり,当事者間には,所有権が譲渡担保権者に移っているとの前提に基づいて賃料を支払っているという意識は存在しない。第4に,貸金の期限が到来した場合には,もしも,譲渡担保設定者は貸金を返済して被担保債権を消滅させることができれば,名目上移転していた所有権の返還を受けること(いわゆる受戻し)ができると考えており,反対に,もしも,貸金の返済ができなければ,譲渡担保権者は,目的物を処分して,売却代金の中から優先的に債権を回収することができ,残額があれば,それを譲渡担保設定者に返還しなければならない(清算義務)と考えている。このような一連の手続き全体を見れば,譲渡担保権者には,譲渡担保設定者に債務不履行がある場合に限って,目的物を処分する権限(担保権)があるだけだということが明らかとなる。しかも,担保権の目的物の処分は,通常は,他人への売却処分となるのであって,自ら担保目的物を買い取るという例外的な場合を除いて,譲渡担保権者は,最初から最後まで,決して,担保目的物の所有権を取得することはないというべきである。反対に,目的物の所有権は,担保権の実行によって売却処分が行われるまで,使用・収益権を含めて,譲渡担保設定者に帰属すると考えなければならない。本書が,所有権的構成を否定し,担保的構成を採用するのは,以上の理由に基づく(「譲渡担保=通謀虚偽表示(信託的行為)」説)。
このことは,譲渡担保が担保であることの必然的な帰結である。そもそも,担保とは,第1に,少なくとも担保権の実行までは債務者(担保権設定者)から所有権を剥奪しないものをいうのであり(設定者から使用・収益権を奪う質権でさえ,所有権は奪わない),第2に,担保権の実行の目的は,債権の確実な回収(事実上または法律上の優先弁済権)を認めるものであり,第3に,債権者に清算を義務づける〈最一判昭46・3・25民集25巻2号208頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第96事件)〉ものでなければならないからである。すなわち,第1に,債権者にはじめから所有権を移転するのであれば,それは,贈与か売買か交換であって,担保権の設定とはいえない。また,第2に,債権者に事実上の優先弁済権または法律上の優先弁済権が確保されないものは,物的担保とはいえない。さらに,第3に,債権者に清算義務を課さないものは,純粋な代物弁済であって,担保とはいえない。
最後の清算手続きについては,典型担保のためには,国家機関が関与する競売等の手続きが用意されているが,非典型担保の場合には,市場における処分によらざるを得ない。市場での処分には,仮登記担保法が採用している「帰属清算型」と,「処分清算型」とがあるが,帰属清算型は,仮登記担保法等の特別法の規制に基づき,後順位担保権者等の監視の下での厳格な手続きを踏まないと,十分な清算がなされないおそれがある。さらに,一定の事由を要件にするとしても,担保権者に自動的に所有権を帰属させる帰属清算型においては,担保権者は,すでに所有権を取得しているため,清算額をなるべく低く見積もろうとするモラルハザードが発生する。このような弊害を避けるためにも,非典型担保における清算手続きは,市場での売却という第三者が介在するため,公平さを保つことができる処分清算型が原則とされるべきである(なお,〈最一判昭46・3・25民集25巻2号208頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第96事件)〉は,処分清算と帰属清算の両方を認めている)。
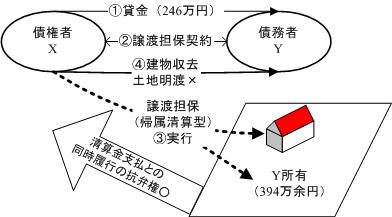 |
貸金債権担保のため債務者所有の不動産につき譲渡担保契約を締結し,債務者が弁済期に債務を弁済すれば,右不動産を債務者に返還するが,弁済をしないときは,右不動産を債務の弁済に代えて確定的に債権者の所有に帰せしめるとの合意のもとに所有権移転登記が経由されている場合において,債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは,債権者は,目的不動産を換価処分するかまたはこれを適正に評価することによって具体化する価額から債権額を差し引き,残額を清算金として債務者に支払うことを要する。 債権者が,この担保目的実現の手段として,債務者に対し右不動産の引渡ないし明渡を請求する訴えを提起した場合に,債務者が清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは,特段の事情のある場合を除き,債権者の右請求は,債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきものと解するのが相当である。 |
| *図122 最一判昭46・3・25民集25巻2号208頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第96事件 |
したがって,譲渡担保の実行手続きは,目的物の債権者に帰属させないのを原則とし,債権者のイニシアティブで目的物を第三者に処分するという,処分清算型を原則とすべきことになる。つまり,譲渡担保とは,設定者から所有権および使用・収益権を奪うことなく,債務不履行の際には,担保権者に目的物の処分清算を認める担保権であるということになる(「譲渡担保=所有権・使用・収益権を奪うことなく処分清算を許す担保権」説)。
判例は,先に述べたように,譲渡担保の実行方法として,処分清算とは異なり,代物弁済予約型の清算方法である帰属清算型(所有権を債権者に帰属させた後に清算を行う方式)を認めている(〈最一判昭46・3・25民集25巻2号208頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第96事件)〉,〈最一判昭62・2・12民集41巻1号67頁〉)。しかし,所有権をいったん債権者に帰属させた上で清算を行うという代物弁済予約型の清算方法は,先に述べたように,特別法の厳格なルールがないとモラルハザードを発生させるばかりでなく,あくまで所有権の移転は生じないとすべき譲渡担保には適合しない。譲渡担保の合意は,あくまで,債務者に目的物の使用・収益を許し,債務者が債務を履行しない場合には,債権者は,目的物を処分する権限を取得し,処分した売買代金の中から,他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するに過ぎないと解すべきだからである。
仮登記担保法が採用する帰属清算型の実行方法は,実定法による明確な手続きが確保している場合にのみ,債権者の過酷な回収方法をコントロールできるのであり,そのような方法が取れない,動産譲渡担保,債権譲渡担保については,特別の事情がある場合(流質,流抵当を認めてもよいような事情が認められる場合)を除いて採用されるべきではない。この点が,仮登記担保と譲渡担保との決定的な違いとなる。
なお,譲渡担保について,処分清算型を原則とする本稿の立場からは,債務者のいわゆる受戻権とは,実質的には移転していないが,形式的に移転している所有権の外形を抹消し,元の状態に戻すことを意味する(受戻し=名目上の所有権移転の抹消)。受戻しという用語法は,一見,実際に移転した担保目的物の所有権を買い戻すというニュアンスが含まれるので,用語としては適切ではない。しかし,仮登記担保法の制定後,広く一般に利用されている用語法なので,本書でも利用することにする。ただし,必要に応じて「いわゆる受戻権」というような表現によって,「移転した所有権の買戻しではない」という点に注意を喚起しようと思う。
このいわゆる受戻しは,本書の立場では,債権を弁済することによって実現するが,その時期は,債権者が目的物を第三者に処分するまでに限定されることになる。この考え方によれば,平成6年最高裁判決〈最三判平6・2・22民集48巻2号414頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第97事件)〉が譲渡担保について,「債権者〔譲渡担保権者〕が…目的物を第三者に譲渡したときは,原則として,譲受人は目的物の所有権を確定的に取得し,債務者は,清算金がある場合に債権者に対してその支払を求めることができるにとどまり,残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできなくなるものと解するのが相当である」と判示していることについて,仮登記担保法11条ただし書きの規定(受戻権とその制限)を援用することなしに,譲渡担保の理論から説明することが可能となる。
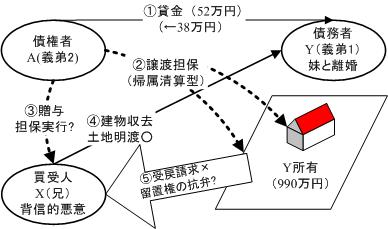 |
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を譲渡した場合には,譲渡担保を設定した債務者は,譲受人がいわゆる背信的悪意者に当たるときであると否とにかかわらず,債務を弁済して目的不動産を受け戻すことができない。 |
| *図123 最三判平6・2・22民集48巻2号414頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第97事件 |
もっとも,上記の平成6年最高裁判決は,肝心の「譲渡担保権の実行」としての「第三者への譲渡」につき,親族間の無償譲渡(贈与)でもよいとしているが,贈与では優先弁済権は実現されないばかりでなく,そもそも,清算もありえないのであって,事案の具体的妥当性を欠く不当な判決となっているのが惜しまれる。
譲渡担保が担保権であり,理論的には,所有権的構成が破綻していることが明らかであるにもかかわらず,最高裁が譲渡担保に関して,基本的に所有権的構成を採用していることを考慮し,判例実務との乖離を小さくできるという点から,所有権的構成を基本にした理論構成に賛意を表する学説が存在する。しかし,以下に見るように,最高裁のいわゆる譲渡担保の所有権的構成は,すでに破綻しており,歴史的な経緯を知る上では尊重に値するが,理論的な面では重要な役割を終えたと考えるべきである。
譲渡担保権に関する判例法理とされる「譲渡担保の所有権的構成」が理論的なほころびを見せ始めたのは,第1に,会社更生手続きにおいて,譲渡担保者を所有権者とは扱わず,更生担保権者に準じて優先弁済権のみを主張しうるとした昭和41年最高裁判決〈最一判昭41・4・28民集20巻4号900頁〉に始まる。
最一判昭41・4・28民集20巻4号900頁
会社更生手続の開始当時において,更生会社と債権者間の譲渡担保契約に基づいて債権者に取得された物件の所有権の帰属が確定的でなく両者間になお債権関係が存続している場合には,当該譲渡担保権者は,物件の所有権を主張して,その取戻を請求することはできない。
前項の場合において,譲渡担保権者は,更生担保権者に準じて,その権利の届出をし,更生手続によってのみ権利行使をすべきである。
第2に,昭和57年最高裁判決が,所有権的構成を取りつつも,その所有権の移転は,債権担保の目的の範囲内に制限されるとして,譲渡担保設定者に不法行為者に対する明渡請求を認めるに至る〈最三判昭57・9・28判時1062号81頁,判タ485号83頁〉。
最三判昭57・9・28判時1062号81頁,判タ485号83頁
譲渡担保は,債権担保のために目的物件の所有権を移転するものであるが,右所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ認められるのであって,担保権者は,債務者が被担保債務の履行を遅滞したときに目的物件を処分する権能を取得し,この権能に基づいて目的物件を適正に評価された価額で確定的に自己の所有に帰せしめ又は第三者に売却等することによって換価処分し,優先的に被担保債務の弁済に充てることができるにとどまり,他方,設定者は,担保権者が右の換価処分を完結するまでは,被担保債務を弁済して目的物件についての完全な所有権を回復することができるのであるから(最高裁昭和39年(オ)第440号同41年4月28日第一小法廷判決・民集20巻4号900頁,同昭和42年(オ)第1279号同46年3月25日第一小法廷判決・民集25巻2号208頁,同昭和55年(オ)第153号同57年1月22日第二小法廷判決・民集36巻1号92頁参照),正当な権原なく目的物件を占有する者がある場合には,特段の事情のない限り,設定者は,前記のような譲渡担保の趣旨及び効力に鑑み,右占有者に対してその返還を請求することができるものと解するのが相当である。
第3に,平成7年最高裁判決が,譲渡担保権者は第三取得者に当たらないとして,目的物に対する所有権の取得を否定したこと〈最二判平7・11・10民集49巻9号2953頁〉を通じて,譲渡担保の所有権的構成の理論的破綻が徐々に明らかになっていく。
最二判平7・11・10民集49巻9号2953頁
譲渡担保権者は,担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り,民法378条所定の滌除権者たる第三取得者に当たらない。
第4に,平成18年最高裁判決〈最二判平18・10・20民集60巻8号3098頁〉は,被担保債権の弁済後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ,その旨の登記がされたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができないとしつつ,以下のように判示して,弁済期前においては,たとえ譲渡担保権者が目的物を譲渡した場合でも,譲渡担保権者は,目的不動産を処分する権能を有しないことから,受戻権を行使しうることを明らかにしている。このことは,譲渡担保権が設定されても,その時点では,所有権が譲渡担保権者に移っていないことを認める結果となっている。少なくとも,この判決が単純な所有権的構成に立つものでないのは明らかである[田髙・物権法(2008)291頁]。
最二判平18・10・20民集60巻8号3098頁
被担保債権の弁済期前に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえた場合は,少なくとも,設定者が弁済期までに債務の全額を弁済して目的不動産を受け戻したときは,設定者は,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができると解するのが相当である。なぜなら,弁済期前においては,譲渡担保権者は,債権担保の目的を達するのに必要な範囲内で目的不動産の所有権を有するにすぎず,目的不動産を処分する権能を有しないから,このような差押えによって設定者による受戻権の行使が制限されると解すべき理由はないからである。
このように,判例における譲渡担保に関する所有権的構成は,整合性の維持が困難になっていくのであり,以下に述べる抵当権法理の準用を通じて,理論的に破綻するに至る。
譲渡担保権に関する所有権的構成の理論的破綻が決定的となるのは,譲渡担保に担保物権の通有性である物上代位を認めた平成11年の最高裁決定(最二決平11・5・17民集53巻5号863頁)によってであろう。所有権者が物上代位権を行使できないことは当然にもかかわらず,譲渡担保権者に物上代位の権利を認めたからである。
最二決平11・5・17民集53巻5号863頁
銀行甲が,輸入業者乙のする商品の輸入について信用状を発行し,約束手形の振出しを受ける方法により乙に輸入代金決済資金相当額を貸し付けるとともに,乙から右約束手形金債権の担保として輸入商品に譲渡担保権の設定を受けた上,乙に右商品の貸渡しを行ってその処分権限を与えたところ,乙が,右商品を第三者に転売した後,破産の申立てをしたことにより右約束手形金債務につき期限の利益を失ったという事実関係の下においては,甲は,右商品に対する譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として,転売された右商品の売買代金債権を差し押さえることができる。
動産譲渡担保権に基づく物上代位権の行使は,右譲渡担保権の設定者が破産宣告を受けた後においても妨げられない。
譲渡担保は,条文には規定がないのであるから,物上代位の制度を譲渡担保に適用する場合に,譲渡担保を動産抵当に類似するととして民法372条で準用される民法304条を類推するのか,それとも,動産売買の先取特権に類似するとして,民法304条を類推するのかが問題となる。本件の場合,譲渡担保権者(甲)は,譲渡担保設定者(乙)の目的動産(輸入商品)の代金を融資し,その融資金の返済を受けていないのであるから,甲の地位は,代金の支払いを受けていない動産売主の立場に類似しているということができる。そこで,甲に対して動産売主の先取特権者に類似する立場で,民法304条の類推適用をすることが可能となる。
動産先取特権が優先弁済権を有するのは,すでに,動産売主の先取特権の箇所(*第11章)で学んだように,目的物の価値の導入・維持・増加に寄与したからである。本件の場合,譲渡担保権者甲は,目的物の代金を貸し付けることによって目的物の導入に寄与しており,動産売主と同様に,第三順位の先取特権を有する者と同等に扱うことができる。動産先取特権の場合,買主が目的物を売却して第三者に所有権が移転した場合には,追及効がない代わりに,売買代金の上に,物上代位権を及ぼすことができる[民法304条]。本件の場合,譲渡担保権者甲は,譲渡担保設定者乙に商品の処分権限を与えており,追及効を有しない。したがって,甲は,民法304条を類推して,商品の売買代金債権に対して物上代位権を有するということができるということになる。
平成11年の最高裁決定(最二決平11・5・17民集53巻5号863頁)を正当化するためには,譲渡担保における所有権的構成をあきらめ,かつ,譲渡担保の場合に,事案によっては,動産売買の先取特権の規定の類推を認める必要がある。このようにして,譲渡担保の問題が複雑な展開を示せば示すほど,典型担保に関する知識,特に,優先弁済権に関する先取特権に関する知識が必要となるのである。
平成18年の最高裁判決〈最一判平18・7・20民集60巻6号2499頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第98事件)〉は,集合物譲渡担保が複数設定された場合について,先順位譲渡担保と後順位譲渡担保との存在を認めている。
最一判平18・7・20民集60巻6号2499頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第98事件
動産譲渡担保が同一の目的物に重複して設定されている場合,後順位譲渡担保権者は私的実行をすることができない。
譲渡担保について所有権的構成をとる場合に,後順位譲渡担保権者を観念することは,不可能である。後順位抵当権者の存在を認める以上,最高裁は,少なくとも集合物譲渡担保について,所有権的構成を捨てて,担保的構成に移行したといわざるをえないであろう。
また,最高裁の平成8年判決は,表面的には,「譲渡担保権設定者は,譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず,清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても,譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない」〈最二判平8・11・22民集50巻10号2702頁〉とし判示している。
最二判平8・11・22民集50巻10号2702頁
譲渡担保権設定者は,譲渡担保権者が清算金の支払又は提供をせず,清算金がない旨の通知もしない間に譲渡担保の目的物の受戻権を放棄しても,譲渡担保権者に対して清算金の支払を請求することはできない。
譲渡担保権設定者の清算金支払請求権は,譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を自己に帰属させ又は換価処分する場合において,その価額から被担保債権額を控除した残額の支払を請求する権利であり,他方,譲渡担保権設定者の受戻権は,譲渡担保権者において譲渡担保権の実行を完結するまでの間に,弁済等によって被担保債務を消滅させることにより譲渡担保の目的物の所有権等を回復する権利であって,両者はその発生原因を異にする別個の権利であるから,譲渡担保権設定者において受戻権を放棄したとしても,その効果は受戻権が放棄されたという状況を現出するにとどまり,右受戻権の放棄により譲渡担保権設定者が清算金支払請求権を取得することとなると解することはできないからである。また,このように解さないと,譲渡担保権設定者が,受戻権を放棄することにより,本来譲渡担保権者が有している譲渡担保権の実行の時期を自ら決定する自由を制約し得ることとなり,相当でないことは明らかである。
しかし,この事案は,不動産の譲渡担保設定者が事業に失敗して自殺し,その相続財産法人の財産管理人が,譲渡担保の実行を求めるため,譲渡担保権者に対して,受戻権を放棄する旨を通知して清算金の支払いを請求した事案であった。このため,この事件を契機として,譲渡担保権者のイニシアティブで担保権の実行を促す必要性が生じていることが一般に理解されるようになり,抵当権における簡易な実行手続きとしての「対抗・代価弁済(抵当権消滅請求)」の類推が図られるべきかどうかが問題とされるに至っている。このように見てくると,譲渡担保は,ますます,典型担保である抵当権に近づいてきていることがわかる。
さらに,譲渡担保目的物の受戻権に関しては,目的物の処分後は,判例(〈最三判平6・2・22民集48巻2号414頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第97事件)〉,〈最二判平11・2・26判時1671号67頁,判タ999号215頁〉)によって,譲渡担保設定者には受戻権が認められないとされる代わりに,譲渡担保設定者が清算金を受け取るまでは,目的物に対して留置権を主張する余地が認められている点が重要である。
最二判平11・2・26判時1671号67頁,判タ999号215頁←上記の差戻後上告審判決
譲渡担保権者から目的物を譲り受けた第三者は,譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張して明渡しを拒む譲渡担保権設定者に対し,右請求権の消滅時効を援用することができる。
もっとも,平成6年最高裁判決〈最三判平6・2・22民集48巻2号414頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第97事件)〉については,すでに,事案の解決としての具体的な妥当性に問題があることを指摘したが,親族間で40年にわたる裁判闘争が展開された複雑な事案であり,さまざまな解釈を取りうる点に留意が必要である[田髙・物権法(2008)281頁以下参照])。
上記の一連の判決により,以下のことが明らかにされたと思われる。一方で,譲渡担保権者には,目的物に対する所有権は認められず,債務者の債務不履行がある場合に限って目的物を換価・処分する権限を有するだけであり,かつ,処分した後は,担保設定者に清算金を支払う義務が生じること。他方で,譲渡担保設定者は,目的物の処分後は,受戻しができない代わりに,清算金を受け取るまで,目的物を留置する権利が認められることである。
いずれにせよ,民法に不備があるために,不動産以外の目的物に担保の王である抵当権を設定することができず,国民が苦し紛れに譲渡担保という通謀虚偽表示をせざるを得なくなっている現状は放置されるべきではない。国家法の不備によって国民を「嘘つき」にしている現状は早急に改善されるべきである。そのためには,譲渡担保を私的実行を許す典型担保の一つとして民法に組み込み,すべての財産(動産,不動産,財産権)に対して,設定者の使用・収益権を奪うことなく担保権が設定できるようにするとともに,その担保権が正常な賃借権を害することがないよう,かつ,清算が公平かつスムーズに行えるよう,私的実行について必要最小限のコントロールを行うことができるように,民法の担保法の改正が必要であると考える。
以上の議論で明らかになったように,動産に関する譲渡担保は,その実質は,民法に不備があって欠けている,動産について抵当権(処分清算を伴う動産抵当)を創設するものである。
動産譲渡担保は,表示上は,債務者が所有する目的物を債権者に譲渡する契約となっているが,その真意(契約の目的)は,目的物を債務者が使用・収益することを許しつつ担保目的物とすること,すなわち,私的実行を許す動産抵当を実現しようとするものである。
したがって,動産譲渡担保は,抵当権の効力と同様,目的物の所有権は債務者に保持され,債務者が使用・収益することを認めつつ,債権者が,「他の債権者に先立って弁済を受ける権利」として構成されることになる。
問題は,債権の弁済期が到来しても債務者(譲渡担保設定者)が弁済をしない場合,債権者(譲渡担保権者)は,担保権を実行することができるになるが,そのときに,債権者はどのような権利を取得できるかである。債権者は,当然に,清算なしに目的物の所有権を取得できるのか(流抵当型),債権額と目的物の価額とを清算をした後に所有権を取得できるのか(帰属清算型),債権者は所有権を取得できるわけではなく,目的物を処分する権限のみを有し,処分して得た売得金の中から優先的に弁済を受けることができるだけであるのか(処分清算型)が問題となる。
この点については,すでに,譲渡担保は処分清算型を原則とすることに意味があることを述べたので,ここでは繰り返さない。
動産譲渡担保を認める必要性は,先に述べたように,第1に,債務者に目的物の使用・収益を許さない質権ばかりでなく,債務者者が目的物の使用・収益を継続しつつ目的物を債権の担保に供する制度を認める必要性が認められる。すなわち,債務者が債権者に対して動産譲渡担保を設定したときは,債務者が期限内に債務を弁済できなった場合には,債権者が目的物を適切に処分し,その売得金から優先弁済を受けることを認めるという,処分清算を許す動産抵当を認める必要性がある。
しかし,動産譲渡担保を認める必要性は,それに限定されない。第2に,目的物が特定物ではなく,倉庫内の在庫品のように,物品に出入りがあって特定しない集合物に対して担保を設定する必要性があるからである。この場合の特色は,債務者が単に目的物を使用・収益することが認められるだけでなく,弁済期までは目的物の処分も自由にできるという点にある。質権が,目的物の使用・収益だけでなく目的物の処分を禁止しているのと比較すると,その特色がよく理解できると思われる。
このような集合物に対する譲渡担保は,一部は,工場抵当や企業担保という特別法で認められている。しかし,そのような特別法によることなく,在庫品に対する担保権の設定を認め,弁済期間内は,債務者に目的物の自由な処分を認めつつ,弁済期になっても債務者が債務の弁済ができない場合に限って,倉庫等にある目的物(流動する目的物は,この時点で流動をやめ,確定する)を処分する権限を債務者から奪って債権者に与え,それを適切に処分した売得金の中から,債権額について,他の債権者に先立って弁済を受ける権利を認める点に,集合物譲渡担保の特色がある(詳しくは,千葉恵美子「集合動産担保の効力(1)~(4完)」判タ756~766号(1991)参照)。
判例も,流動する債権の種類,量的範囲,所在場所が明確に特定されているという要件の下に,構成部分の変動する集合動産の譲渡担保を有効としている(〈最一判昭54・2・15民集33巻1号51頁〉,〈最三判昭62・11・10民集41巻8号1559頁〉,〈最一判平18・7・20民集60巻6号2499頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第98事件)〉)。
上記の判例については,先取特権の箇所で,動産売買の先取特権と譲渡担保との競合問題として,検討した。以下の判例は,その後の集合物譲渡担保に関する平成18年最高裁判例である。
|
|
構成部分の変動する集合動産(特定の漁場のいけす内に存する養殖魚(ブリ,ハマチ等))を目的とする対抗要件を備えた譲渡担保が複数設定されている場合において,譲渡担保の設定者が,その目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合,当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り,当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。 |
| *図124 最一判平18・7・20民集60巻6号2499頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第98事件 |
このような厳密な意味で目的物が特定しない場合というのは,一般先取特権の目的物が特定しない場合と非常によく似ている。この意味でも,物的担保を物権として構成することなく,債権の掴取力に優先弁済権が付加されたに過ぎないと考える本書の立場の優位性が明らかとなる。債権の場合,強制執行の対象となる目的物が刻々と変化することは,むしろ当然であり,強制執行の開始によって初めて特定するからである。一般先取特権が物権でないのと同様,集合物譲渡担保も物権でないと考えるならば,その理論的解明は,一般先取特権との対比を通じて,飛躍的に進展するものと思われる。
なお,目的物が確定してからの集合物譲渡担保の効力は,先に述べた,通常の動産譲渡担保の場合と同様である。
法律に不備があるため,その有用性が肯定されるべき動産の譲渡担保の場合とは異なり,不動産の譲渡担保については,その有用性に疑いがある。なぜならば,担保制度としては,不動産担保の雄としての抵当権があり,債務者は,目的物の使用・収益を継続しながら,目的物を担保に供する道が開かれている。また,非典型担保としても,目的物の使用・収益を継続しながら,目的物を担保に供することができる仮登記担保制度までもが認められているため,不動産譲渡担保を認めるためには,その実益を明らかにしなければならない。
抵当権と仮登記担保の制度が認められているにもかかわらず,実務上,不動産の譲渡担保が利用されている唯一の理由は,担保の目的物である不動産を市場で処分して債権を回収したいという債権者の要請に応える制度(処分清算方式)が用意されていないことによる。
抵当権の場合には,抵当直流れの合意がない限り,債権者は競売によって債権を回収するほかない。また,抵当直流れを制度化したともいえる仮登記担保の場合には,先に述べたように,帰属清算という方式が採用されいるため,まず債権者の資金で清算を行うことが必要であり,その清算が終了してからでなければ,目的物を市場で処分して換価することができない。債権者が示した清算額に後順位債権者等が不満を抱けば,結局,抵当権と同じく,競売によって債権を回収するほかなくなる。
処分清算方式を実現できるのは,現在のところ不動産譲渡担保だけであるため,抵当権や仮登記担保という優れた不動産担保制度があるにもかかわらず,不動産の譲渡担保が利用されているのである。
述べた処分清算方式を認めるという解釈を採用するのが妥当であるということになる。
動産の担保方法として,民法が,債務者の使用・収益を認めない質権しか用意しなかったことは,法の不備というべきであり,債務者が目的物の使用・収益を継続しつつ目的物を担保に供することができる動産譲渡担保を新しい物的担保として認めることは,社会の進展に伴う実務の要請に応えるものとして是認すべきであることはすでに述べた。しかし,債権の場合には,債権を担保する方法として,必ずしも債権者が目的物の占有を取り上げる必要のない権利質が用意されており,債権について譲渡担保を認めなければならないという強い理由は存在しない。
債権譲渡担保が必要となるのは,集合動産譲渡担保と同じく,集合債権譲渡の場合である。動産の集合物譲渡担保の場合にも,譲渡担保を認める理由は,弁済期まで債務者に使用・収益だけでなく,目的物の処分権を許す制度が必要だからであった。集合債権譲渡の場合に,譲渡担保が必要な理由は,質権では,債務者の処分権を認めることができないからである。
債権譲渡担保においても,債務者に債権の処分を許すことはできない。処分を許したのでは,債務者の債務不履行の場合に,その債権から弁済を受けることができないからである。したがって,通常の債権譲渡担保は,債権に質権を設定したのと同じである。債権質の設定の対抗要件は,債権譲渡の対抗要件と同一であり,この点でも,債権質と債権譲渡担保とを区別する理由は存在しない。
もっとも,担保提供者が将来取得するであろう債権を包括的に譲渡担保とすることができるかどうかについては,ここで検討しておく。判例は,医師が将来において社会保険診療報酬支払基金から支払いを受けるであろう8年3ヶ月分の診療報酬債権を包括的に譲渡する契約を,一定の条件を示しながら有効としているので〈最三判平11・1・29民集53巻1号151頁〉,そのような将来債権に関する譲渡担保も,同様に,認められるものと思われる。
最三判平11・1・29民集53巻1号151頁
医師が社会保険診療報酬支払基金から将来八年三箇月の間に支払を受けるべき各月の診療報酬債権の一部を目的として債権譲渡契約を締結した場合において,右医師が債務の弁済のために右契約を締結したとの一事をもって,契約締結後六年八箇月目から一年の間に発生すべき目的債権につき契約締結時においてこれが安定して発生することが確実に期待されたとはいえないとし,他の事情を考慮することなく,右契約のうち右期間に関する部分の効力を否定した原審の判断には,違法がある。
さらに,判例は,債務者が取引先に対して取得するであろう売掛代金について包括的に譲渡予約する契約を,目的債権の特定性,識別可能性を要件として,有効としている〈最二判平12・4・21民集54巻4号1562頁〉。
最二判平12・4・21民集54巻4号1562頁
甲が乙との間の特定の商品の売買取引に基づき乙に対して現に有し又は将来有することのある売掛代金債権を目的として丙との間で譲渡の予約をした場合,譲渡の目的となるべき債権は,甲の有する他の債権から識別ができる程度に特定されているということができる。
債権に関して譲渡担保を認める必要性が大きいのは,集合債権に関する譲渡担保である(これまでの学説・判例の積み重ねについては,堀龍兒「集合債権論」[伊藤古稀記念・担保制度の現代的展開(2006)254頁以下]参照)。集合債権譲渡担保に関する法理は,平成13年の最高裁判決〈最一判平13・11・22民集55巻6号1056頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第99事件)〉によって完成された。ここでは,この判決を理解するうえで必要な知識を確認し,その法理を明らかにすることにする。
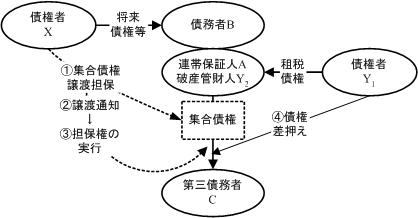 |
| *図125 集合債権譲渡担保の対抗要件 最一判平13・11・22民集55巻6号1056頁 民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第99事件 |
原審の確定した前記事実関係によれば,本件契約は,ベストフーズ(A)が,イヤマフーズ(B)の上告人(X)に対する債務の担保として,上告人(X)に対し,ダイエーと(C)の間の継続的取引契約に基づく本件目的債権を一括して確定的に譲渡する旨の契約であり,譲渡の対象となる債権の特定に欠けるところはない。そして,本件通知中の「ベストフーズ(A)は,同社がダイエー(C)に対して有する本件目的債権につき,上告人(X)を権利者とする譲渡担保権を設定したので,民法467条に基づいて通知する。」旨の記載は,ベストフーズ(A)がダイエー(C)に対し,担保として本件目的債権を上告人(X)に譲渡したことをいうものであることが明らかであり,本件目的債権譲渡の第三者対抗要件としての通知の記載として欠けるところはないというべきである。
本件通知には,上記記載に加えて,「上告人(X)からダイエー(C)に対して譲渡担保権実行通知(書面又は口頭による。)がされた場合には,この債権に対する弁済を上告人(X)にされたい。」旨の記載があるが,この記載は,上告人(X)が,自己に属する債権についてベストフーズ(A)に取立権限を付与したことから,ダイエー(C)に対し,別途の通知がされるまではベストフーズ(A)に支払うよう依頼するとの趣旨を包含するものと解すべきであって,この記載があることによって,債権が上告人(X)に移転した旨の通知と認めることができないとすることは失当である。
そうすると,本件通知に債権譲渡の第三者対抗要件としての通知の効力を否定して上告人(X)の請求を棄却すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点をいう論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。
(i) 集合債権,集合債権譲渡担保について
集合債権とは,一定の識別基準で範囲を確定される既発生,未発生の指名債権群をいう。金融実務においては,取引活動の過程において取得する集合債権を一括して,債権譲渡の法形式を用いて担保化する必要性が生じている。
集合債権譲渡担保契約は,担保設定者が正常な経営を続けている限りは,担保設定者が目的債権を自由に取り立てて満足することが許され,担保設定者の下で目的債権が順次消滅していくことが当初から予定されており,一定の信用上の問題が発生してはじめて,担保設定者の取立権が消滅し,担保権者が現実に存する未決済の債権を取り立てて自己の債権に充当するという形態をとるのが通例となっている。
集合債権譲渡担保契約においては,債権譲渡という法形式(債権質の法形式も同じ)を利用しながら,債務者が正常な間は目的債権の流動化を許容するという点で,債権譲渡そのものとも債権質の設定とも異なる実態(債権の上の抵当権または浮動担保ともいうべき実態)に特色がある。
(ii) 債権に関する譲渡担保の必要性
民法で定められている債権担保の方法が債権質に限定されているため,担保権設定者にとって以下のような不便が生じることとなり,その克服が,譲渡担保という形式で行われることになる。この点は,動産の担保の場合とまったく同様である。
動産質権の場合,占有改定による質権の設定が禁止されているため,担保権の設定者は,動産を利用しながら担保を設定することができない。そこで,動産を占有し利用しながらそれを担保に入れることができる方法として,動産の譲渡担保契約(売買と賃貸と買戻しを結合させた契約)が判例法を通じて発展することになった。
債権質の場合,質権の設定によって債務者は第三債務者に対する債権の弁済受領権を失ってしまう[民法366条]。そこで,債権質とは異なり,実行のときまでは第三債務者に対する債権の取立てが債務者に認められるような債権担保の方法,すなわち,債権譲渡を行いつつ一定の時期まで債務者に第三債務者に対する弁済受領権を与える方法または債権譲渡の予約契約という方法が,債権の譲渡担保として発展することになった。
質権設定によって債務者が蒙る不便については,立法によって克服されている場合がある。たとえば,特許法95条は,特許権に質権を設定した場合,以下のように,質権が実行されるまでは,質権設定者のみが特許権を行使することができ,質権者は,特許権を行使することができないとしている。この規定は,[実用新案法25条],[意匠法35条],[商標法34条]においても準用されているが,[著作権法66条]は,この法理をさらに徹底させている。
(iii) 債権に関する譲渡担保の対抗要件
債権譲渡の対抗要件は,民法467条以下に規定されている。これに対して,債権に対する担保権の設定は,法律上は債権質に限定されており,その対抗要件は民法364条に規定されているが,民法364条は,その対抗要件は民法467条従ってなされるべきことを規定している。したがって債権に関しては,その譲渡の対抗要件も,担保権の設定の対抗要件も,等しく,債務者に対する通知か債務者の承諾であるということになる。
(iv) 典型担保と非典型担保としての譲渡担保との融合
集合債権に関する担保は,本来の債権譲渡とも債権質とも異なり,担保の実行までは債務者に権限を残すことが重要なのである。その精神は,まさに抵当権の考え方によって実現されているのであり,動産の譲渡担保,債権の譲渡担保は,不動産にしか許されないとされてきた抵当権を,動産においても,さらには債権においても,その精神を実現するための試みであったと評価することが可能であろう。
譲渡担保の歴史は,動産に始まって不動産,債権へと拡大し,財産権すべてを覆うに至っている。このことは,財産権のすべてについて,質権とは異なる統一的な抵当権的な担保の必要性を暗示していると考えることが可能である。すべての財産権に対して,質権的な担保方法と並行して,抵当権的な担保方法をも実現することが,担保法に関する立法上の緊急の課題となっている。
なお,本件については,さらに,続きがある。最高裁判決でいったん敗訴した国が,以下のような新たな論拠をもって,訴えを提起したからである。すなわち,本件は,将来債権の譲渡担保契約がなされ,その旨の対抗要件である通知も完了したが,その後に譲渡担保設定者が滞納した国税の法定納期限が到来し,その後,目的債権が発生したという事案であったため,国としては,法定納期限の後に債権が発生し,そのときに譲渡担保の対抗要件も具備されるのであるから,国税徴収が譲渡担保に優先すると主張したのである。これに対して,平成19年最高裁判決〈最一判平19・2・15民集61巻1号243頁〉は,以下のように判示して,譲渡担保権者が優先するとした。
最一判平19・2・15民集61巻1号243頁
国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として,債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する。
所有権留保は,割賦販売等の信用販売でよく使われる制度である。従来は,文字通り,買主が売買残代金を完済するまで,売主が所有権を留保し,したがって,買主は,それまで,条件付の権利(期待権)を有するに過ぎないと考えられてきた。
しかし,近年は,所有権留保を譲渡担保として構成する立場が有力となってきている。すなわち,割賦販売の場合にも所有権は,契約時に所有権を取得するが,残代金の支払いを担保するために,売買目的物に譲渡担保を設定すると構成するのである。この構成が理論的な整合性を持つためには,割賦販売を従来のように特殊の売買と見るのではなく,本来の売買と準消費貸借との結合として構成する必要があることを明らかにする。
ここでは,このような新しい立場に立った場合,所有権留保と譲渡担保との関係を連続的に理解するできること,および,所有権留保においても,担保的構成のメリットが大きいことを明らかにする。
所有権留保とは,売買代金債権を担保するために,売買代金が完済されるまで,売買の目的物の所有権を買主に移転せず,売主に留保するとする特約のことをいう。所有権留保の特約が行われた売買契約を所有権留保売買といい,その売主は所有権留保売主又は留保売主と呼ばれており,その買主は所有権留保買主又は留保買主と呼ばれている。
所有権留保売買の場合,債権者(売主)が,担保のために新たに所有権を取得するのではなく,担保のためにもともと売主に帰属していた所有権を留保する点で譲渡担保と異なるように見える。
しかし,動産の売買契約においては,売買代金の全額が売主に支払われなくとも,売買目的物の占有を買主に移転すると,所有権も買主に移転すると解されている。したがって,所有権留保は,見かけ上は,代金が完済されるまで目的物の所有権を買主へと移転させない特約として表れるが,実質的には,引渡しと同時に目的物の所有権が売主から買主へと移転することを前提とした上で,残代金を担保するために,買主が売主のために売買目的物に譲渡担保を設定したものと考える方が取引の実態に即している(売主の所有権留保=買主による譲渡担保設定)。
このように考えると,所有権留保のメカニズは,売買目的物の所有権が引渡しによって売主から買主へと移転し,その後,残代金を担保するために,買主が売主のために設定する譲渡担保によって,売買目的物の所有権が,見かけ上,買主から売主へと移転するように見えるだけである。つまり,実際の所有権は,目的物の引渡しによって買主に移転したままであり,売主は,売買残代金の支払いを受けるまでの間,所有権ではなく,債権担保としての譲渡担保権を有しているに過ぎない。
所有権留保は,譲渡担保の場合と同様,判例によって認められた担保物権であると考えられている。ただし,判例は,譲渡担保と同じく,所有権構成を採用してきた〈最一判昭49・7・18民集28巻5号743頁〉。
最一判昭49・7・18民集28巻5号743頁(第三者異議事件)
代金完済に至るまで目的物の所有権を売主に留保し買主に対する所有権の移転は代金完済を停止条件とする旨の合意がされている動産の割賦払約款付売買契約において,代金完済に至るまでの間に買主の債権者が目的物に対し強制執行したときは,売主又は売主から目的物を買い受けた第三者は,所有権を主張し,第三者異議の訴えによって右執行を排除することができる。
被担保債権である代金債権が全部履行されるまでは,留保売主は,留保買主の他の債権者に対して,売買目的物の所有権を主張することができるとされている。しかし,所有権を主張できるという正確な意味は,本来の所有権に基づく返還請求を無償で実現できるわけではない。
すなわち,売買目的物が動産である場合は,留保買主からの譲受人は即時取得する可能性がある[民法192条]。そして,留保買主に代金債権の不履行があると,留保売主は,確かに,債務不履行に基づいて売買契約を解除し,留保買主に対して売買目的物の引渡しを求めることができるように見える。しかし,これは実質的には所有権留保(譲渡担保)という担保権の私的実行であるから,留保売主は,留保買主に対して,目的物の価額と被担保債権の額との差額を清算金として支払わなければならない。
すなわち,留保売主は,残代金債権を確保するために,売買目的物を売却処分し,その売却代金から他の債権者に先立って被担保債権の弁済を受けるか(処分清算)または被担保債権から目的物の現存価格を差し引いた額を買主に支払って,目的物の所有権を取得するか(帰属清算),いずれかの方法をとることができるに過ぎない。このように,所有権留保と譲渡担保とは,その実行方法についても同一である。
売主の所有権留保と売買目的物につき,買主から譲渡担保の設定を受けた者との間の関係は,いわゆる黙示の質権として第1順位の先取特権[民法330条1項1号]とみなされる動産譲渡担保と,第3順位の動産売主の先取特権との競合問題として,民法330条1項および2項によって解決されることになる。この点につき,以下の判例〈最二判昭58・3・18判時1095号104頁〉は,所有権留保とその後に設定された譲渡担保との競合問題を扱っており,所有権留保と譲渡担保との優劣関係を考察する上で参考になる。
最二判昭58・3・18判時1095号104頁,判タ512号112頁,金法1042号127頁,金商684号3頁
所有権留保売買の目的動産につき,買主から譲渡担保権の設定を受けた者が,売主に対し,買主の未払残代金を支払う旨申し入れ,その額の調査に要する期間右の動産の処分を猶予するよう要請し,売主がこれに応じるかのような態度を示していたときでも,売主が猶予する旨約したのでない限り,売主が右動産を他に処分しても右譲渡担保権の侵害にはあたらず,売主は,右譲渡担保権者に対しその担保権の喪失による損害を賠償する責を負わない。
割賦販売において所有権留保が広く行われていることを背景に,割賦販売法は,当事者間に明示の特約がなくても所有権留保がなされたことを推定する規定を置いている[割賦販売法7条]。
自社割賦販売においては,留保所有権は,原則どおり,売主に帰属する。しかし,ローン提携販売の場合には,もともと売主に帰属する所有権留保は,金融機関による売主への融資としての債権の買取りにより,提携先の金融機関に帰属する。もっとも,買主が金融機関への分割弁済を怠った場合に,売主が保証人としての責任を果たした場合には,民法500条以下の弁済代位に基づき,いったん金融機関に帰属した所有権留保が,担保権の随伴性に基づき,売主に復帰することになる。また,個別信用購入あっせん(立替払い契約)の場合には,売主は保証責任を負わないため,担保としての所有権留保は,クレジット会社に帰属する。
ただし,宅地建物取引業法は,宅地または建物を割賦販売する場合に,売主に先取特権の登記または抵当権の設定・登記を認める一方で,売主が所有権留保を行うこと,または,譲渡担保を設定することを原則的に禁止している[宅地建物取引業法43条]。不動産買主の保護と,買主のマイホーム取得の夢を壊さない配慮である。
動産の所有権留保および譲渡担保については,その公示方法が十分でないため,売主に所有権があることを信じた動産の買主は,民法192条の即時取得の規定によって,担保権のない完全な所有権を取得することができた。しかし,自動車等の登録制を採用している動産については民法192条の適用はないとされているため,ディーラーが所有権留保をしている自動車をサブディーラーから購入した買主(ユーザー)が,売買代金をサブディーラーに支払ったにもかかわらず,サブディーラーがディーラーに代金を完済していないという場合に,ディーラーがサブディーラーとの売買契約を解除し,留保所有権に基づいて,ユーザーに対し,売買目的物である車の返還を請求するという事態が生じた。
最高裁は,以下のように,昭和50年~57年の一連の判決(〈最二判昭50・2・28民集29巻2号193頁(民法判例百選Ⅰ〔第6版〕第100事件)〉,〈最一判昭52・3・31金法835号33頁,金商535号42頁〉,〈最三判昭56・7・14判時1018号77頁〉,〈最二判昭57・12・17判時1070号26頁〉)を通じて,サブディーラーとディーラーとの間に自動車売買契約の履行に協力関係がある場合,所有権留保に基づいてユーザーに対して自動車の返還を請求することは,権利の濫用として許されないとの法理を確立している。
自動車の販売につき,サブディーラー(国際自動車整備工場)が,まずディーラー(尼崎日産自動車)所有の自動車をユーザーに売却し,その後右売買を完成するためディーラーからその自動車を買い受けるという方法がとられていた場合において,ディーラーが,サブディーラーとユーザーとの自動車売買契約の履行に協力しておきながら,その後サブディーラーにその自動車を売却するにあたって所有権留保特約を付し,サブディーラーの代金不払を理由に同人との売買契約を解除したうえ,留保された所有権に基づき,既にサブディーラーに代金を完済して自動車の引渡を受けているユーザーにその返還を請求することは,権利の濫用として許されない。 *図126 最二判昭50・2・28民集29巻2号193頁
民法判例百選Ⅰ〔第6版〕(2009)第100事件
自動車販売の場合,ユーザーは,使用名義にかかわらず,使用名義に基づいて自動車の購入をしている実態を踏まえるならば,自動車売買における所有権留保は,公示の実体を備えておらず,譲渡担保の場合と同様,善意・無過失の第三者には対抗できないと解すべきであろう。
さらに,消費者保護を考慮するならば,登記できる不動産について,宅地建物業法が登記できる不動産である宅地・建物の割賦販売に関して,所有権留保または譲渡担保を設定することを原則的に禁止しているのと同様,登記できる自動車の売主であるディーラーは,割賦販売の方法によって自動車を売買するに際しては,たとえ所有権留保または譲渡担保を設定したとしても,その効力はユーザーには対抗できないと解すべきである。ディーラーは,そのほかに,動産売主として,登記を要しない先取特権という担保権をも有するのであるが,動産先取特権は,サブディーラーが自動車を第三者であるユーザーに引渡した場合には追及効を失う[民法333条]。このように考えると,ディーラーは,第三者であるユーザーに対しては,いかなる担保権をも行使することができないと解すべきことになろう。
自由な議論が許されるために民法学から権威主義を払拭したい,厳格な判断基準を有する社会科学としての民法学を作り上げたいというのが,民法学者としての筆者の長年の夢であった。
民法学には,未だに権威主義が根強く残っている。権威のある学説を攻撃すると,たとえ,その学説が論理的に破綻している場合であっても,学会から無視されかねないし,通説に従って議論している人に対して違った観点から批判すると,人格攻撃と誤解されかねない。そのような弊害を取り去り,学者同士が権威に囚われず,自由な議論ができるようにするためには,議論の前提となる共通のよりどころ(共通の基盤)が必要である。それを前提に議論ができれば,議論をめぐる感情的な対立等のさまざまな弊害が取り除かれるからである。
もちろん,通説・判例がそのような共通の基盤となっているならそれでよい。しかし,通説・判例も,権威主義に陥っていることがあり,無条件では議論の前提としての共通の基盤とすることができない。通説・判例ではなく,民法の条文を議論の前提にするというのも,無条件というわけにはいかない。その理由は以下の3点に要約できる。第1に,条文は簡略すぎるため,問題解決のためには必ず解釈を必要とするが,その解釈が権威主義を脱していない通説・判例によって支配されているからである。第2に,民法の条文自体が,立法の過誤に陥っている場合もあるからである。確かに,憲法76条3項によって,裁判官は法律に拘束されるかもしれないが,学問の自由を謳歌する学者にとっては,条文自体も批判の対象となりうる。第3に,民法の債権法が改正されることが規定事実化されている現状においては,現行民法の条文自体も共通の基盤とはなりえないからである。現行民法の条文を金科玉条とする議論は,債権法が改正されるであろう数年後には,通用しないものとなってしまう。
このように考えると,民法学において自由な議論を促進するためには,誰もが疑わない公理(または,議論の前提としての仮定的な公理)に基づいて,誰もが疑わない変形規則(推論規則)を使って定理を導き出し,その定理にしたがって,民法の条文を正当化したり,誤りを指摘したりすることできるという公理的体系(公理系)を作り出すというのが最も確実な方法であろう。
もちろん,前提となる公理を変更すれば,違った結論が導き出される可能性はある(例えば,「ユークリッド幾何学」の公理である「平行線は交わらない」だけを変更し,それ以外の公理系を利用することによって,「非ユークリッド幾何学」が誕生したのが,その典型例である)。しかし,別の公理を利用したときにも,あるルールを導き出すためには,その公理と推論規則から導かれる定理のみを使うことが許されるのであるから,議論がかみ合い,自由な議論が保障されことになる。
このように考えると,民法に関する自由な議論を保障するための共通基盤を用意するためには,現行民法において顕在化しているルールのほぼすべてを論理的に導きくことができるような,民法の公理的体系を構築することが不可欠となる。しかも,そのような民法の公理的体系を構築しておけば,たとえ,債権法改正が行われて,条文が全く新しいものとなったとしても,新しい民法の条文のほぼすべてのルールを上記と同一の公理,または,全く新しい1つの公理から出発し,誰もが認める変形規則(推論規則)のみを使って,新しい民法条文に対応できる公理的体系を構築することも可能となる。
そのような公理的体系を議論の共通基盤に据えることができれば,学者の仕事(通説に対する批判と新しい学説の提唱,新しい判例に対する判例評釈,立法に対する批判と立法論等)も,論理的整合性を失わない範囲で,具体的な妥当性を極限まで追及することができることになる。
このような共通基盤が存在すれば,ある人の議論に反論するには,具体的な妥当性を考慮に入れて公理自体を変更すべきあると迫るとか,公理または定理からルールが導き出される過程における推論規則の適用に誤りがあるとか,ほぼ2つの方向の議論だけに集中できる。そうすると,議論は常にかみ合い,建設的な議論が期待できる。また,議論の方向が,上記のように,政策的な判断を含む公理に対する議論と推論規則の適用の誤りに関する議論との2つに明確に2分されるため,人格攻撃との区別も明確となり,人間関係が険悪となることを避けることもできよう。
本書は,筆者が創設した担保法の新しい体系にに基づいて執筆されたわが国で最初の教科書である。ここでいう体系とは,担保法が1つの概念から始まり,整合的な分岐を経て,すべてのルールが出発点の概念によって説明されているという意味である。
具体的にいえば,本書における担保法の出発点は,「債権担保」という概念であり,その概念は,「債権の掴取力の強化である」として定義される。そして,その概念は,第1段階として,債権の固有の効力の中で,「債権の掴取力の対世効」として拡張され,次の展開過程への準備がなされる。第2段階では,債権の掴取力が,量的強化(人的担保)と質的強化(物的担保)という2つの方面で展開される。
第1段階では,債権の掴取力が対世効を獲得する過程が,第1に,第三債務者に対する直接取立権の獲得,第2に,責任財産の逸失に対する追及効の獲得,第3に,目的債権に対する優先弁済権の獲得の過程として示される。
第1に,直接取立権を可能にするのは,債務者の無資力,または,被保全債権(α債権)と目的債権(β債権)との牽連性であることが示される。
債務者の無資力を要件として,債務者に対する債務名義なしに第三債務者に対して直接取立てを実現する制度が債権者代位権である[民法423条]。そして,その制度は,無資力を要件とせず,被保全債権と目的債権との間の密接な関係(牽連性)を要件として,債務名義なしに第三債務者に対して直接取立てを実現する制度(直接訴権)へと進化する([民法613条],[自賠法15条,16条])。そして,これらの制度は,債権質の直接取立権[民法366条]へとつながっていく。
第2に,債務者の責任財産が逸失した場合に,第三者(受益者,転得者)への追及効を可能にするのは,詐害行為取消権[民法424条~426条]の制度であり,債権者が追及効を獲得するための要件は,債務者の害意と第三者(受益者・転得者)の「悪意」であることが示される。
第三者への追及効を実現する詐害行為取消権は,「登記」によって追及効を実現している抵当権とつながっていく。なぜなら,登記は,第三者を悪意とみなす効力を有することから,債務者の害意と第三者(受益者・転得者)を要件として逸失した責任財産に対して追及効を有する先取特権と抵当権との間には,要件(悪意と登記)の上でも,また,効果(追及効)の上でも重なり合う点が存在するからである。
第3に,事実上の優先弁済権,または,法律上の優先弁済権を可能にするのは,被担保債権(α債権)と目的債権(β債権)との牽連性であることが示される。
被担保債権と目的債権との間の牽連性によって優先権が生み出される理由は,牽連性のある2つの債権は,あたかも運命共同体のように,同時に履行されるべきであり,目的債権(β債権)だけを実現することは,当事者の合理的な期待を裏切るものだからである。そこで,被担保債権(α債権)との同時実現を確保するため,被担保債権(α債権)の債権者に,目的債権の履行を拒絶する抗弁権(履行拒絶の抗弁権)が与えられることになる。そして,目的債権(β債権)の実現を望む相手方による被担保債権(α債権)の同時履行が,事実上,他の債権者に先立って実現されることになる(同時履行の抗弁権))。さらに,第三者が途中で介入してきても,同時履行の関係が害されることはないという考え方を介して,被担保債権(α債権)と目的債権(β債権)との同時履行・同時消滅を通じて,被担保債権(α債権)が他の債権者に先立って実現されるに至る(相殺の抗弁)。
具体的には,牽連する2つの債権のうち,一方の債権(β債権)が譲渡され場合に,β債権の債務者であるα債権の債権者は,相殺の抗弁をもって,債権の譲受人に対抗することができる[民法468条2項]。また,β債権が第三者によって差押えられても,α債権の債権者は,相殺をもって差押債権者に対抗することができる[民法511条]。これが,法律上の優先弁済権である先取特権へとつながっていく。
第2段階では,債権の掴取力の強化が,責任財産の個数の拡大(人的担保)と責任財産からの優先弁済権(物的担保)の2つの方面で展開される。
第1に,掴取力の量的拡大としての人的担保には,保証と連帯債務とが含まれるが,連帯債務は,本来の債務(負担部分)と保証(保証部分)の結合として定義されるため,保証の法理(債務のない責任としての付従性,求償権の発生)のみによって,保証と連帯債務に関するすべてのルールを導き出せることが明らかとなる。
第2に,掴取力の質的拡大としての物的担保には,事実上の優先弁済権を有する留置権と,法律上の優先弁済権を有する先取特権,質権,抵当権とが含まれる。
事実上の優先弁済権を実現する留置権は,債務者または所有者からの目的物の引渡請求権(β債権)に対して,①目的物の占有が適法に取得されたものであること,②被担保債権(α債権)が目的物の取得原因を介して,β債権と牽連していることの2つを要件とし成立する。そして,③占有権の継続という要件を満たすと,それが,第三者に対する対抗要件として機能し,β債権の履行を拒絶することを通じて,α債権の事実上の優先弁済権を実現している。
法律上の優先弁済権とは,先取特権のことであり,質権は,それに留置効力が付加されたものであり,抵当権は,それに追及効が付加されたものである。
すべての物的担保は,債権の掴取力が強化されたものに過ぎないため,すべて,付従性と不可分性を有する。そして,物的担保に関するすべての条文は,物的担保の優先弁済権,付従性,不可分性と,それぞれの担保権に特有の性質(留置的効力,追及効)から導き出すことができる。
本書では,人的担保である保証と連帯債務について,公理から定理を導き出し,そこから保証と連帯債務の重要な条文を説明するという試みを行った。物的担保においても,そのような推論を重ねて本書の執筆を行っている。
債権法改正が実現されたとしても,このような公理的体系が完成していれば,それに基づいて,立法の不備を指摘することも可能であるし,新しい債権法に基づいて,その条文をすべて説明できる新しい公理的体系を作成することも容易となる。その結果としての公理に多くの人が納得した場合にのみ,立法が成功したことが証明されると思われる。逆からいえば,立法者は,改正すべき債権法の公理と定理とを明らかにし,その上で,具体的なルールを作成すべきであるということになる。
本書の試みが,現行民法の解釈学の1つの基準となるばかりでなく,過去,現在,未来の立法に対する評価基準になることがあれば,幸いである。
(本文中に掲載したものを学習の便宜を図るためにまとめたもの)
[民法目次]へ